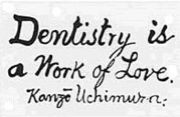昨日,メンバーからのご質問に曖昧に回答してしまいましたので,
本日,改めてトピを立てました.
詳細は,以下をご確認願います.
http://
昨日,唾液をたくさん出すと言う下りから,食事ではなくサプリメントがあると書きましたが,ここに引っかかり,本日,調べてみました.興味深い知見がありましたので,ご紹介します.
「プロフィリン」(モリムラ)という製品があります.
これに関しての論文を以下に記載します.
ちなみにこれは,モリムラの「クリニカル・M・リポート新聞第7号」を抜粋しました.
『う蝕予防のためのプロフィー・ハブ・コンセプト』:Dr.Sune Wikner
≪要約≫
⒈ハイリスクグループではフッ化物によるう蝕予防には限界がある
⒉フッ化物については,pHが低い時は高濃度のフッ化物だけが歯質の脱灰を防ぐことができる
⒊糖質を摂取後,プラークのpHは低下するが,これは唾液中に含まれる重炭酸塩やリン酸塩のような緩衝作用のある成分により中和される
⒋唾液中の緩衝成分の濃度が非常に低い人々もいる.このような人々では糖質の摂取により容易に脱灰が起こる
⒌唾液中の緩衝成分の濃度が高ければ,う蝕誘発因子に関係なく,う蝕のリスクは無視してよいレベルまで減少する
⒍咀嚼により唾液分泌が促進され,唾液中の緩衝成分の濃度は一般に上昇するが,40%の人では上昇は見られない.それゆえガムを噛むことが全ての人においてう蝕を減少させるわけではない
⒎プロフィリンは,重炭酸塩とリン酸塩を配合している
⒏プロフィリンは,全ての人において唾液の緩衝能を上げる
⒐プロフィリンは,プラークのpHを臨界pHよりも高く引き上げる
≪詳細≫
重炭酸塩とリン酸塩のイオンは,唾液に通常含まれている成分であり,低下したpHを引き上げ,唾液の緩衝能のかなりの部分を占めている.これらの唾液中のイオン濃度が低くなればなるほど,唾液の緩衝能は低くなり,う蝕リスクは高くなる.
プロフィリンは,食品です.口腔内の渇きを癒すドロップと書いてありますが,甘味成分は,キシリトールとソルビトールです.
・義歯を装着している人でお口の渇きを感じているひと
・様々な薬剤で口腔が乾燥している人
・唾液緩衝能が低い人
にオススメしますと書いてありました.
ここから,neneの見解です.
英語訳が何となくしっくり来ない箇所もありますが^^;
よく言う臨界pHって,唾液のpHを測定しますよね.
この先生は,プラークのpHを測定しているようです.
また「本当?」って思える箇所も見受けられました.
エビデンスの程は,如何でしょう.定かではありません.
うちの歯科診療所には以前からこのプロフィリンがありまして,使ったことはないですが,この情報がneneの頭の隅にインプットされ,先日の発言に至ったのだと思います.
唾液は大量に出てもあまり意味がないのかと疑問に思いますが,量より質なのだと解釈しました.
うちにあったプロフィリンは,6年前のものでした^^;
早速,注文したので,効果を試してみますね.
本日,改めてトピを立てました.
詳細は,以下をご確認願います.
http://
昨日,唾液をたくさん出すと言う下りから,食事ではなくサプリメントがあると書きましたが,ここに引っかかり,本日,調べてみました.興味深い知見がありましたので,ご紹介します.
「プロフィリン」(モリムラ)という製品があります.
これに関しての論文を以下に記載します.
ちなみにこれは,モリムラの「クリニカル・M・リポート新聞第7号」を抜粋しました.
『う蝕予防のためのプロフィー・ハブ・コンセプト』:Dr.Sune Wikner
≪要約≫
⒈ハイリスクグループではフッ化物によるう蝕予防には限界がある
⒉フッ化物については,pHが低い時は高濃度のフッ化物だけが歯質の脱灰を防ぐことができる
⒊糖質を摂取後,プラークのpHは低下するが,これは唾液中に含まれる重炭酸塩やリン酸塩のような緩衝作用のある成分により中和される
⒋唾液中の緩衝成分の濃度が非常に低い人々もいる.このような人々では糖質の摂取により容易に脱灰が起こる
⒌唾液中の緩衝成分の濃度が高ければ,う蝕誘発因子に関係なく,う蝕のリスクは無視してよいレベルまで減少する
⒍咀嚼により唾液分泌が促進され,唾液中の緩衝成分の濃度は一般に上昇するが,40%の人では上昇は見られない.それゆえガムを噛むことが全ての人においてう蝕を減少させるわけではない
⒎プロフィリンは,重炭酸塩とリン酸塩を配合している
⒏プロフィリンは,全ての人において唾液の緩衝能を上げる
⒐プロフィリンは,プラークのpHを臨界pHよりも高く引き上げる
≪詳細≫
重炭酸塩とリン酸塩のイオンは,唾液に通常含まれている成分であり,低下したpHを引き上げ,唾液の緩衝能のかなりの部分を占めている.これらの唾液中のイオン濃度が低くなればなるほど,唾液の緩衝能は低くなり,う蝕リスクは高くなる.
プロフィリンは,食品です.口腔内の渇きを癒すドロップと書いてありますが,甘味成分は,キシリトールとソルビトールです.
・義歯を装着している人でお口の渇きを感じているひと
・様々な薬剤で口腔が乾燥している人
・唾液緩衝能が低い人
にオススメしますと書いてありました.
ここから,neneの見解です.
英語訳が何となくしっくり来ない箇所もありますが^^;
よく言う臨界pHって,唾液のpHを測定しますよね.
この先生は,プラークのpHを測定しているようです.
また「本当?」って思える箇所も見受けられました.
エビデンスの程は,如何でしょう.定かではありません.
うちの歯科診療所には以前からこのプロフィリンがありまして,使ったことはないですが,この情報がneneの頭の隅にインプットされ,先日の発言に至ったのだと思います.
唾液は大量に出てもあまり意味がないのかと疑問に思いますが,量より質なのだと解釈しました.
うちにあったプロフィリンは,6年前のものでした^^;
早速,注文したので,効果を試してみますね.
|
|
|
|
コメント(20)
>naomiさま
いろいろありがとうございました m(_ _)m
今回のトピは,『う蝕予防のためのプロフィー・ハブ・コンセプト』:Dr.Sune Wiknerで,
原題は「The Profy-Buff Concept」となっています.スウェーデンの歯科医師ですね.
PubMedで調べてみましたが,簡単に見つからず・・・.
他にもう蝕に関する論文は,以前から多数書かれていたようです.
確かにこの論文を全部信じることはできませんでしたが,
フッ化物に関しては,ヨーロッパの現状でものを言っているようです.
そして,このプロフィリンは,キシリトールガムより効果があると言っているのですね.
勉強不足なので良く分からないのですが,
この製品は「唾液の緩衝能」がもともと低い人を適正値まで上げるのか,
適正以上に上げることが可能なのか,
そもそも唾液の緩衝能が低いとは,pHだけの問題なのか,
頭が混乱してきました^^;
ちなみに,諸外国のフッ化物濃度は,ホームケア製品でも,
5000ppmF程度は一般的なようです.
これよりも効果があるか,あるいは同等の効果があると言っているのでしょうか?
当歯科診療所では,たぶん2000年以前にこの製品を入手したようですが,
やっとモリムラで並行輸入できるようになったのでしょう.
う蝕のハイリスク者には,試してみたい気がします.
と言うより,EBD的に定かでないにしても,
歯科衛生士として「唾液の緩衝能を上げる可能性」を,
知識として持っていれば良いと思いました.
nene的には,gelを使ってみたいです.
>日本は、いいとこどりのような気が^^;せっかくなら、日本独自の歯の予防方法とか発見したら、すごいのにねー日本の衛生士冥利につきるってもんだ^^
日本独自のう蝕予防製品,ここだけの話ですが^^;
水面下で研究され,製品化が期待されています.
しかし,日本は,薬事がバリアーが高くて困りますね.
いろいろありがとうございました m(_ _)m
今回のトピは,『う蝕予防のためのプロフィー・ハブ・コンセプト』:Dr.Sune Wiknerで,
原題は「The Profy-Buff Concept」となっています.スウェーデンの歯科医師ですね.
PubMedで調べてみましたが,簡単に見つからず・・・.
他にもう蝕に関する論文は,以前から多数書かれていたようです.
確かにこの論文を全部信じることはできませんでしたが,
フッ化物に関しては,ヨーロッパの現状でものを言っているようです.
そして,このプロフィリンは,キシリトールガムより効果があると言っているのですね.
勉強不足なので良く分からないのですが,
この製品は「唾液の緩衝能」がもともと低い人を適正値まで上げるのか,
適正以上に上げることが可能なのか,
そもそも唾液の緩衝能が低いとは,pHだけの問題なのか,
頭が混乱してきました^^;
ちなみに,諸外国のフッ化物濃度は,ホームケア製品でも,
5000ppmF程度は一般的なようです.
これよりも効果があるか,あるいは同等の効果があると言っているのでしょうか?
当歯科診療所では,たぶん2000年以前にこの製品を入手したようですが,
やっとモリムラで並行輸入できるようになったのでしょう.
う蝕のハイリスク者には,試してみたい気がします.
と言うより,EBD的に定かでないにしても,
歯科衛生士として「唾液の緩衝能を上げる可能性」を,
知識として持っていれば良いと思いました.
nene的には,gelを使ってみたいです.
>日本は、いいとこどりのような気が^^;せっかくなら、日本独自の歯の予防方法とか発見したら、すごいのにねー日本の衛生士冥利につきるってもんだ^^
日本独自のう蝕予防製品,ここだけの話ですが^^;
水面下で研究され,製品化が期待されています.
しかし,日本は,薬事がバリアーが高くて困りますね.
お邪魔致します。。。
某老人施設・歯科訪問介護に便乗致しました。
高齢者に対しての口腔ケアーのあり方に、かなり疑問を抱いて帰ってまいりました。
予防という視点で捕らえ、DHの役割を専門的に導入するには非常に難しい現場であると痛感致しました。
現場の声によるとやはり保険システムに縛られ、医療人の志より、数をこなす?見たいな風潮があり、グレーゾーンなども考慮せざるえない環境にあるのでしょう。。。
介護に携わる方により異なると感じておりますが、口腔内管理を知らない介護福祉士・ホームヘルパーの方々が対処していました。
高齢者の方々の約半数以上は、誤嚥性肺炎とある本で読みましたが、事実上、nene様がおっしゃるように、誤嚥性肺炎を助長するような状況でした。食に始まり、シモの世話に追われ、日々の生活の中で口腔ケアーは二の次と言ったところなのでしょう。
実際、専門職の歯科スタッフの口腔ケアーもDR・DHが対処していましたが、さまざまな状況によりケアーも形だけのような対処でした。身体的・肉体的・経済的さまざまな視点からみると、何を優先し提供すべきなのか?
難しいですね。
某老人施設・歯科訪問介護に便乗致しました。
高齢者に対しての口腔ケアーのあり方に、かなり疑問を抱いて帰ってまいりました。
予防という視点で捕らえ、DHの役割を専門的に導入するには非常に難しい現場であると痛感致しました。
現場の声によるとやはり保険システムに縛られ、医療人の志より、数をこなす?見たいな風潮があり、グレーゾーンなども考慮せざるえない環境にあるのでしょう。。。
介護に携わる方により異なると感じておりますが、口腔内管理を知らない介護福祉士・ホームヘルパーの方々が対処していました。
高齢者の方々の約半数以上は、誤嚥性肺炎とある本で読みましたが、事実上、nene様がおっしゃるように、誤嚥性肺炎を助長するような状況でした。食に始まり、シモの世話に追われ、日々の生活の中で口腔ケアーは二の次と言ったところなのでしょう。
実際、専門職の歯科スタッフの口腔ケアーもDR・DHが対処していましたが、さまざまな状況によりケアーも形だけのような対処でした。身体的・肉体的・経済的さまざまな視点からみると、何を優先し提供すべきなのか?
難しいですね。
>えなかさま
コメントありがとうございました.
介護の現場介入は大変難しいと聞いております.
neneは,全く経験が無いことですが,このコミュのメンバーで,実際に携わっておられる方やヘルパーの資格を持っていられる方がいますが,大変だったと聞いたことがあります.
ブラッシングどろこじゃないのよって感じですかね?
施設の責任者ですら,口腔保健のことを知らないのは当たり前のようです.
しかし,現在,歯科衛生士業界で活発な動きを見せているのは,介護とインプラントです.
どれも口と全身の関わりからQOLの向上に関連しています.
昨今,流行のキーワード「生活医療」にフォーカスすることが重要なようです.
介護の現場では「歯科医療従事者のマンパワーが足りない」,
という括りだけでは済まされないのでしょうか?
コメントありがとうございました.
介護の現場介入は大変難しいと聞いております.
neneは,全く経験が無いことですが,このコミュのメンバーで,実際に携わっておられる方やヘルパーの資格を持っていられる方がいますが,大変だったと聞いたことがあります.
ブラッシングどろこじゃないのよって感じですかね?
施設の責任者ですら,口腔保健のことを知らないのは当たり前のようです.
しかし,現在,歯科衛生士業界で活発な動きを見せているのは,介護とインプラントです.
どれも口と全身の関わりからQOLの向上に関連しています.
昨今,流行のキーワード「生活医療」にフォーカスすることが重要なようです.
介護の現場では「歯科医療従事者のマンパワーが足りない」,
という括りだけでは済まされないのでしょうか?
naomiさん!
厳しくないと感じます。
当然のことと感じます。
また、広範囲になればなるほど職域を越えていくのは当然のことで、やはり全身を見ることも食を見ることも出来ない衛生士は、知識も無ければ、プロ意識もないと感じます。
(詳細にこだわり追求し、知識を得れば得るほど理想は高く、ゴールも無く、「一生勉強だなー」まだまだ、「何もできないなー」と
感じております。(反省。。。)
だからこそ、勇気を持ち、コメントを出してよかったです。
とても勉強になります。
また、同じ歯科衛生士でもこんなに職業意識(プロ意識)を持った方々がたくさんいることを理解でき安心と共に刺激を受けます。
もしよろしければ、是非口腔リハビリの方法を教えていただきたいと感じます。(以前、米山先生とはスタディーグループで活動していたことがございます。このときは介護に携わらない一面でのお付き合いでした。しかしながら、人として、本当に素晴らしい方で尊敬しています。)
私は、介護とは無縁の診療室に勤務しておりました。
目指すべきコンセプトは、「健康で快適な生活サポート」を心掛けておりましたので、介護を受けなくて良い環境作り(口腔内管理・全身管理)また、歯科医院在中の栄養士と共に食の管理をしておりました。
残念ながら、通院が不可になる方が数名おりまして、院長・担当衛生士は訪問ケアーに伺っておりました。
そして今回、チャンスがあり訪問の同行を致しましたが、
正直な気持ちで現場を見たときのショックは忘れられません。。。
あまりにもケアーの対処方法が違いすぎました。
もちろん、ケアーする相手が違うことや環境により大きく異なるとは思いますが・・・
個人的には祖母が特養に入所しています。
ここの特養施設は、全身管理はもちろんのこと、食後の口腔内管理・清掃用具の管理・デンチャーの名前入りの管理も全て行われています。そして管理栄養士・介護士・ヘルパー・意思・看護士の方とも情報を交換をしてくださいます。家族共々感謝の気持ちでいっぱいです。そして出来る範囲で、交代で毎日介護に行っています。
もちろん私の最大の役割は、祖母と会話をし、笑顔で笑い、生活サポートである、食事のフォロー・口腔内リハビリ・口腔衛生管理をお願いしてさせていただいております。
(しかし、リハビリの実践は無く本で学び何ちゃってになっているかもしれません。)もっと、快適に!もっと、全身を理解しなければとあせるばかりです。
上記コメントを下さっているnaomi・chiraさんのような方が多くいる職場は、きっと患者様が一番喜んでいらっしゃると感じます。そして、同じ衛生士でも着目する視点・職場の環境でまったく異なる状況かと思いますが、今後の高齢者社会を考えると、
衛生士という職業問わず、人として介護のサポートが出来るような状況は作らなければならないと強く感じます。
口腔内管理を出来ても、介護が出来ない。食べるサポートが出来ないでは、患者様どころか、自分の両親・配偶者すらもサポートすることは出来ないと感じております。
QOLの必要性を感じ、口腔内の域を超える全身サポートの出来る衛生士及び人を目指し今後も努力したいと思います。
厳しくないと感じます。
当然のことと感じます。
また、広範囲になればなるほど職域を越えていくのは当然のことで、やはり全身を見ることも食を見ることも出来ない衛生士は、知識も無ければ、プロ意識もないと感じます。
(詳細にこだわり追求し、知識を得れば得るほど理想は高く、ゴールも無く、「一生勉強だなー」まだまだ、「何もできないなー」と
感じております。(反省。。。)
だからこそ、勇気を持ち、コメントを出してよかったです。
とても勉強になります。
また、同じ歯科衛生士でもこんなに職業意識(プロ意識)を持った方々がたくさんいることを理解でき安心と共に刺激を受けます。
もしよろしければ、是非口腔リハビリの方法を教えていただきたいと感じます。(以前、米山先生とはスタディーグループで活動していたことがございます。このときは介護に携わらない一面でのお付き合いでした。しかしながら、人として、本当に素晴らしい方で尊敬しています。)
私は、介護とは無縁の診療室に勤務しておりました。
目指すべきコンセプトは、「健康で快適な生活サポート」を心掛けておりましたので、介護を受けなくて良い環境作り(口腔内管理・全身管理)また、歯科医院在中の栄養士と共に食の管理をしておりました。
残念ながら、通院が不可になる方が数名おりまして、院長・担当衛生士は訪問ケアーに伺っておりました。
そして今回、チャンスがあり訪問の同行を致しましたが、
正直な気持ちで現場を見たときのショックは忘れられません。。。
あまりにもケアーの対処方法が違いすぎました。
もちろん、ケアーする相手が違うことや環境により大きく異なるとは思いますが・・・
個人的には祖母が特養に入所しています。
ここの特養施設は、全身管理はもちろんのこと、食後の口腔内管理・清掃用具の管理・デンチャーの名前入りの管理も全て行われています。そして管理栄養士・介護士・ヘルパー・意思・看護士の方とも情報を交換をしてくださいます。家族共々感謝の気持ちでいっぱいです。そして出来る範囲で、交代で毎日介護に行っています。
もちろん私の最大の役割は、祖母と会話をし、笑顔で笑い、生活サポートである、食事のフォロー・口腔内リハビリ・口腔衛生管理をお願いしてさせていただいております。
(しかし、リハビリの実践は無く本で学び何ちゃってになっているかもしれません。)もっと、快適に!もっと、全身を理解しなければとあせるばかりです。
上記コメントを下さっているnaomi・chiraさんのような方が多くいる職場は、きっと患者様が一番喜んでいらっしゃると感じます。そして、同じ衛生士でも着目する視点・職場の環境でまったく異なる状況かと思いますが、今後の高齢者社会を考えると、
衛生士という職業問わず、人として介護のサポートが出来るような状況は作らなければならないと強く感じます。
口腔内管理を出来ても、介護が出来ない。食べるサポートが出来ないでは、患者様どころか、自分の両親・配偶者すらもサポートすることは出来ないと感じております。
QOLの必要性を感じ、口腔内の域を超える全身サポートの出来る衛生士及び人を目指し今後も努力したいと思います。
「唾液とその役割」に関して記述します.
(東京医科歯科大学,小林賢一歯科医師より)
◆唾液の役割
「デンプンを分解する消化作用,酸を口腔内から除去する浄化作用,再石灰化作用,酸を中和する緩衝作用,細菌の発育を抑制する抗菌作用,口腔内を保湿,滑らかにする湿潤・潤滑作用などがあり,口腔内環境の最大決定因子です.
このように唾液は,健康な口腔組織を維持する上で非常に重要であり,唾液分泌量が減少すると,う蝕,酸蝕に大きな影響を与えるだけでなく,義歯の予後や摂食,嚥下,会話などにも大きな影響を与え,QOLを低下させることにもなります.」
◆酸蝕修飾因子としての唾液
「唾液には,pHの変化に対して抵抗するph緩衝作用があります.正常な唾液分泌が行われている場合には,1%のクエン酸を飲むと1分後にpHは2〜3に低下しますが,上顎中切歯の口蓋面とその隣接面では,2分以内,上顎第一大臼歯で4〜5分以内でpH5.5に復帰することが報告されています.
しかし,唾液分泌能が低い場合には,酸性飲料の摂取後,pHがもとの値に戻るのに30分を必要とします.
この緩衝作用は,主として唾液中の重炭酸塩による緩衝システムによるもので,唾液の分泌量に依存しています.
そのため唾液の分泌量が減少し,緩衝能が低下すると,う蝕だけでなく酸蝕にも罹患しやくなります.
特に口腔乾燥症の場合は,それだけで酸蝕の原因となってしまいます.
また,安静時唾液量が毎分0.1mLに低下した場合には,酸蝕のリスクが5倍となります.」
上記のことから,このトピの懸案事項であった「唾液の緩衝能を上げる」とは,
やはり唾液の分泌量を促進することでありましたね^^
(東京医科歯科大学,小林賢一歯科医師より)
◆唾液の役割
「デンプンを分解する消化作用,酸を口腔内から除去する浄化作用,再石灰化作用,酸を中和する緩衝作用,細菌の発育を抑制する抗菌作用,口腔内を保湿,滑らかにする湿潤・潤滑作用などがあり,口腔内環境の最大決定因子です.
このように唾液は,健康な口腔組織を維持する上で非常に重要であり,唾液分泌量が減少すると,う蝕,酸蝕に大きな影響を与えるだけでなく,義歯の予後や摂食,嚥下,会話などにも大きな影響を与え,QOLを低下させることにもなります.」
◆酸蝕修飾因子としての唾液
「唾液には,pHの変化に対して抵抗するph緩衝作用があります.正常な唾液分泌が行われている場合には,1%のクエン酸を飲むと1分後にpHは2〜3に低下しますが,上顎中切歯の口蓋面とその隣接面では,2分以内,上顎第一大臼歯で4〜5分以内でpH5.5に復帰することが報告されています.
しかし,唾液分泌能が低い場合には,酸性飲料の摂取後,pHがもとの値に戻るのに30分を必要とします.
この緩衝作用は,主として唾液中の重炭酸塩による緩衝システムによるもので,唾液の分泌量に依存しています.
そのため唾液の分泌量が減少し,緩衝能が低下すると,う蝕だけでなく酸蝕にも罹患しやくなります.
特に口腔乾燥症の場合は,それだけで酸蝕の原因となってしまいます.
また,安静時唾液量が毎分0.1mLに低下した場合には,酸蝕のリスクが5倍となります.」
上記のことから,このトピの懸案事項であった「唾液の緩衝能を上げる」とは,
やはり唾液の分泌量を促進することでありましたね^^
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ベテラン歯科衛生士への道 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ベテラン歯科衛生士への道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人