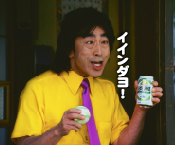コミュ開設のお祝いとして、前に書いたエッセイを
載せさせていただきます。
かなり長いので、邪魔でしたら消してくださいw
題して「映画を読む・・2001年編」です^^
生物の進化とは何であろうか。何億年か前に生まれたアメーバのような単細胞生物が長い年月を経て海を征服した。その中のあるものは住み慣れた海を離れ地上で生活を始めた・・そして地上をも征服したのだ。強い生物・・言い換えれば「生き残れる生物」の条件とは何であろうか。それは「何物をも砕ける牙」であったり、「相手を殺せる爪」であったりしたことであろう。また、弱い生物も「生き残れる繁殖力」で対抗したことであろう。では、「人間」には何があったのか・・なぜ「生き残れた」のであろうか。
猿たちのなかから、住み慣れた森を離れ地上で暮らすものたちが現れた・・彼らは「牙」も「爪」も、いわゆる武器となるものを持ち合わせていない・・そして硬い皮膚や甲羅といった身を守るものも持ち合わせていない・・。唯一の財産である、二足歩行によって得た「大きな脳」もまだ役立ってはいないのだ。そんな種族がなぜ「生き残れた」のであろうか・・。不思議に思わないであろうか・・オーストラルピテクスとクロマニヨン人はなぜにあのように「違う」のか・・とても同じ種族とは思えない。そこには何らかの「力」が働いていた・・と考えるほうが自然ではなかろうかと・・。
「2001年宇宙の旅」を読む、あるいは見るたびに私はそんなことを考える。アフリカのどこかにモノリスが立っている姿を、である。この映画の主題は・・いろいろな説があるにしろ・・「神」の姿であろうと思う。知恵に目覚めた生物が「神」あるいはそれに近いものになるまでの、長い時間をかけた壮大な「実験」であろうと・・。
スタンリー・キューブリックはアーサー・C・クラークが1950年に発表した短編「前哨」からヒントを得て制作に乗り出した。キューブリックは既に「博士の異常な愛情」でアカデミー賞を受賞しており、この壮大なSF作品を手がけるための名声と資金援助を得ていたのだ。映画は5年の時間をかけて制作された・・キューブリックはクラークに何度も脚本の手直しをさせたそうである。そして1968年に映画が完成し、公開と同時にセンセーションを巻き起こした。それはそうだ・・映画はほとんどストーリーを語らないのであるから・・そして謎に満ちたラストシーンは論争を巻き起こし、「正しい解釈」がいくつも出来上がるほどであった。詳しくは不明だが、映画の後を追って、SF小説「2001年宇宙の旅」(原題:2001;A space oddyssey)が発売され、ベストセラーとなった。論評で「映画を見てから読む原作・・これが当てはまるのは本書しかない」と言われたそうである。本当にそうなのであろうか・・。
私は小説を先に読んだ・・たしか高校生のころであり、既に映画は終了していた。それから何度かの再上映にも行けず、やっと映画を見たのは25歳くらいの頃である。「今世紀最後の公開!」というキャッチフレーズで、今はなきテアトル東京のシネラマ(知ってるかなぁ)で見たのである。それもオールナイト上映で、たしか秋川リサ(これも知ってるかなぁ)が来ていた。当然ながら、2001年フリークの総会みたいなものであるから、オープニングのツァラトウストラから異常な熱気である。キューブリックのクレジットが出ると拍手が沸き起こる・・良い時代だった・・のかもしれない。
小説は、「最初」の人間となる「月を見るもの」の群れから始まる。ちなみに映画のクレジットでも「Moon watcher」の名前が出ている。彼らは絶滅寸前である・・当然のことである・・武器も防具も持たない「か弱い」草食動物などは肉食動物の「餌」でしかないのだ。そのうえ、彼らは「繁殖力」も持っていない、子供はなかなか独り立ちせず、一度に一人しか生まれないのである。よくもまぁ、こんな生物が今まで生き残ったもんだ・・と思わせるオープニングである。彼らは気まぐれな「豹」のような生物が、たまたまほろ穴に入ってこなかった・・というだけで生きているのであり、いつかは自分の番がくることを察している・・どちらにしても30年も生きられないのであるが。そこに「モノリス」が現れる・・。
私が2001年を好きなのは、映画と小説が「別物」だからである。多くの映画は原作の周りをウロウロしているだけであり、原作の持つ「緻密性」や「組み立て」といったものを無視している。それはそうだ・・映画には「時間」と「費用」の制約があり、なおかつ商業的に成功しなければならない。原作をそのまま映画化したら、5時間以上もある退屈な作品になってしまうであろうから。ところが、2001年は違うのである。クラークの描いた小説は、非常に緻密な論理を組み立て、「意志」の存在を正面から見据えている・・彼の考える「神」の姿であろうが。それに対しキューブリックは「視覚」と「聴覚」という限られた手段で、見ている人間に「解釈」をせまるのである。キューブリックにかかれば、クラークの原作さえも「解釈」の一つであり、それが正しいのかさえも明らかにしないのだ。映画を見た人間は、大抵は「悩む」であろう・・多くの人は「解釈」をあきらめ、「何だかよく分からない・・」となり、また他の人は原作に「解釈」をゆだねるであろう。しかし、本当にこの映画を楽しむためには、「自分なりの解釈」をする必要がある・・少なくとも私はそう思うのだが。
話しをモノリスに戻そう・・2001年では3個のモノリスが現れる。最初のモノリスは教育機械、少なくとも知恵の可能性を高めるための機械である。たまたま近くにいた「月を見るもの」たちに教育をほどこす・・「道具」を使うことを・・。彼らはその資格を持っている数少ない生物なのであった。「手」が自由なのだから。原作では最初のモノリスは地球全体にばらまかれている・・可能性を高めるには当然のことである。「月を見るもの」は、ふと、ころがっている骨を持ち上げる・・それは「手」の延長であり、「手」よりも硬く破壊力を持っていた。そして彼らは、恐怖を知らない「仲間」の草食動物を倒し、「雑食」に目覚めるのである・・なにより「肉」は栄養があり、かれらの体格を向上させた・・そして、「敵」に対しても武器となるのである。「月を見るもの」はこうして世界最初の「殺人者」となる・・そして「力」の象徴である骨を空高くほうりなげる・・。
「骨」が「人工衛星」に変わるシーンは、いつ見ても感動的である・・人間は幾多の「絶滅」の機会を逃れ、宇宙に進出するまでに成長した。ヨハン・シュトラウスのワルツをバックに「PanAm」の宇宙機が宇宙ステーションを目指す・・誰が「PanAm」が倒産するなどと考えたであろうか・・強いアメリカの象徴であるのに・・。宇宙機はステーションの港である中心の回転と同期を取って回転する・・良いなぁ、好きだなぁ、このシーン。原作では中心はステーションと逆に回転することによって「静止」しているのだが、やはり「港」に接岸する儀式としては映画のシーンのほうが意味深い・・ステーション側からの映像で、管制塔(と呼ぶのか?)が小さく見えているのがいかにも人間らしくて良いのだ。映画のコンピュータについては、かのダイクストラが協力している、もちろんIBMのバックアップもあったであろうが。まだ「コンピュータ」などというものと縁のない生活をしていた私には「夢の国」に見えたものである。この宇宙機や月船、宇宙船ディスカバリー号のコンピュータ・ディスプレイは・・たとえ無意味なものであっても・・当時の人々に「宇宙旅行」という夢を具体化したのではあるまいか・・。本当に2001年には宇宙へ行けるのだ、と。
映画にはセリフのあるシーンはわずか40分しかない・・数少ないセリフのシーンは主に宇宙ステーションと月のクラビウス基地、TMA1までが一つの説明となる。あとはディスカバリー号のボーマンとブール、HALのやりとりくらいである。セリフは聞けば分かる・・あたりまえだが・・驚くのは宇宙ステーションから地球へのビジフォン代くらいか・・わずか$1.70・・うーん、安い!。月船では「無重力トイレ」のシーンが好きだ・・変な私であるが・・あの壁にかかっている注意書きが市販されていて、友達からもらった・・引越しのドサクサでなくしてしまったが・・残念。これがまた、これでもか!というくらい丁寧な注意書きなのだ。ひまな人はシーンを止めてじっくり見てほしい(読めないとは思うが・・)。
クラビウス基地からティコ・クレーターに向かうシーンでサンドイッチを食べる・・あれを食べてみたいと思ったのは私くらいか・・合成ハムはどんな味なのだろうか、と。TMA1(ティコ・マグネティック・アノマリィ1号)はその名のとおりティコ・クレーターの地磁気異常現象であるが、ここに二つ目のモノリス・・当然ながら両方を見た人間はいない・・があった。モノリスは300万年の眠りから覚め、自分に与えられた任務である「通信」を行う・・後で分かるが、この「通信」は単なる連絡では無く、多くの情報を含んでいたのだ。映画で刺激的な音がするのは、この「通信」の音だけである・・キーンという耳をふさぎたくなるような音・・DDにしたのはこのためだけか、というくらいであるが。
原作では通信は土星に向けて送られる、映画では木星であるが・・どちらが良いかは好き好きであるが、原作の土星のほうが面白い。それには、「土星の輪」の謎とか、土星の衛星の一つであるヤペタスの謎が付いてくるからであるが。映画で木星を選んでしまったため、2010年では木星が主人公になってしまった・・蛇足であるが。
映画の見せ場であるディスカバリー号である。ディビット・ボーマンとフランク・ブール、HAL9000との宇宙飛行が始まる・・HALを一文字ずらすとIBMになる・・有名な話しであるが、真偽は分からない・・。他の3人の乗組員は人工冬眠で眠らされている。彼らは結局、出演しない・・クレジットに出ているんだろうか?・・見てみようっと。
ちょっと不思議に感じるのはデスカバリー号の大きさと回転部分である。ポッドの大きさに比べて本船が小さいと感じないか?ポッドの出口と回転部分の関係も悩むところであるが・・。HAL9000は、メモリーの奥底にある秘密指令で論理回路に異常をきたす・・ボーマンとブールは秘密指令の存在を知らないのだから、HALの悩みに応えることができない。そして秘密であるがゆえにHALも相談できない・・人工知能の精神病である・・未来には起こりうるのであろうか・・ありそうなことではあるが。
ポッドが明かりを点けて進んでくるシーンはコントラストがむちゃくちゃ高く、どんなPJでもつらいシーンである。音の無い世界での恐怖というのは恐ろしいもんだ、と変な感心をしてしまうが。原作でのHALの反乱はブールを土星(映画では木星)に送りこんでからは、映画と変化している。原作では単純にハッチを開いて船内を真空にしてしまう・・空気を必要とする生物は死んでしまう・・ボーマンはやっとの思いで非常用の部屋に移り、非常用酸素で生き残る。映画ではボーマンがブールを救助しにポッドで船外に出て(ヘルメットを忘れて)、HALの拒絶により非常用ハッチを開け、ポッドを爆破してなんとか船内に入る・・このほうが迫力はあると思う。ボーマンはHALの思考回路をはずして船の制御部分のみを生かす・・そこで制御の切れた秘密指令が現れるのだ。
土星(映画では木星)に到着したボーマンを待っていたのは、最後のモノリスである。大きさは映画ではよく分からないが、1マイルもの大きさである。ボーマンは危険を覚悟でポッドによる調査に出かける・・ポッドが近づいた時にゲートが開くのである・・最後のモノリスはスターゲートだったのだ・・。ここからの移動シーンは意味不明であり、素直に見ておいた方が無難だと思う、一部はマウイ島のハレアカラ火山の火口で撮影されたそうだ・・マウイでそんな話しを聞いた。ポッドはおそらく数万光年の旅を一気に駆け抜け・・終点の部屋に到着した。お分かりであろうか・・月のモノリスが送った通信には地球のテレビ電波が含まれていたのだ・・その中に出てくる部屋(おそらくはホテル)を作ってボーマンを入れたのである。食器やナイフ、スプーンなども・・そしてガウンなども。ここからは解釈の分かれるところであるが、最終的にスターチャイルドとなる過程で不要な肉体を滅ぼす必要がある・・純粋な意識のみが必要だからである。そのため、ゆっくりと時間をかけてボーマンの肉体を滅ぼす・・無理のないように・・と、私は考えている。映画はその時間を省略するために、ボーマンが振り返るたびに時間を変化させるのだ。自分が人間であった最後の証しであるポッドを見つめながらボーマンの肉体は滅び、後には生まれたばかりのスターチャイルドが残る。彼(?)は自分の能力を試しに、ほんの数万光年をヨチヨチ歩きして故郷の地球へ戻る・・何をしたいのか自分でも分からずに。
原作で描かれた「意志」とはどういった存在なのであろうか。まだ人間が猿との境目を行ったり来たりしているころ、それは地球に「種」をまいている。地球だけ?答えはNOであろう・・それが何を求めているのか。この点が「解釈」の分かれ目であろう。そして、永遠の疑問が残される・・あれは本当に「神」だったのであろうか、と。
終わり
載せさせていただきます。
かなり長いので、邪魔でしたら消してくださいw
題して「映画を読む・・2001年編」です^^
生物の進化とは何であろうか。何億年か前に生まれたアメーバのような単細胞生物が長い年月を経て海を征服した。その中のあるものは住み慣れた海を離れ地上で生活を始めた・・そして地上をも征服したのだ。強い生物・・言い換えれば「生き残れる生物」の条件とは何であろうか。それは「何物をも砕ける牙」であったり、「相手を殺せる爪」であったりしたことであろう。また、弱い生物も「生き残れる繁殖力」で対抗したことであろう。では、「人間」には何があったのか・・なぜ「生き残れた」のであろうか。
猿たちのなかから、住み慣れた森を離れ地上で暮らすものたちが現れた・・彼らは「牙」も「爪」も、いわゆる武器となるものを持ち合わせていない・・そして硬い皮膚や甲羅といった身を守るものも持ち合わせていない・・。唯一の財産である、二足歩行によって得た「大きな脳」もまだ役立ってはいないのだ。そんな種族がなぜ「生き残れた」のであろうか・・。不思議に思わないであろうか・・オーストラルピテクスとクロマニヨン人はなぜにあのように「違う」のか・・とても同じ種族とは思えない。そこには何らかの「力」が働いていた・・と考えるほうが自然ではなかろうかと・・。
「2001年宇宙の旅」を読む、あるいは見るたびに私はそんなことを考える。アフリカのどこかにモノリスが立っている姿を、である。この映画の主題は・・いろいろな説があるにしろ・・「神」の姿であろうと思う。知恵に目覚めた生物が「神」あるいはそれに近いものになるまでの、長い時間をかけた壮大な「実験」であろうと・・。
スタンリー・キューブリックはアーサー・C・クラークが1950年に発表した短編「前哨」からヒントを得て制作に乗り出した。キューブリックは既に「博士の異常な愛情」でアカデミー賞を受賞しており、この壮大なSF作品を手がけるための名声と資金援助を得ていたのだ。映画は5年の時間をかけて制作された・・キューブリックはクラークに何度も脚本の手直しをさせたそうである。そして1968年に映画が完成し、公開と同時にセンセーションを巻き起こした。それはそうだ・・映画はほとんどストーリーを語らないのであるから・・そして謎に満ちたラストシーンは論争を巻き起こし、「正しい解釈」がいくつも出来上がるほどであった。詳しくは不明だが、映画の後を追って、SF小説「2001年宇宙の旅」(原題:2001;A space oddyssey)が発売され、ベストセラーとなった。論評で「映画を見てから読む原作・・これが当てはまるのは本書しかない」と言われたそうである。本当にそうなのであろうか・・。
私は小説を先に読んだ・・たしか高校生のころであり、既に映画は終了していた。それから何度かの再上映にも行けず、やっと映画を見たのは25歳くらいの頃である。「今世紀最後の公開!」というキャッチフレーズで、今はなきテアトル東京のシネラマ(知ってるかなぁ)で見たのである。それもオールナイト上映で、たしか秋川リサ(これも知ってるかなぁ)が来ていた。当然ながら、2001年フリークの総会みたいなものであるから、オープニングのツァラトウストラから異常な熱気である。キューブリックのクレジットが出ると拍手が沸き起こる・・良い時代だった・・のかもしれない。
小説は、「最初」の人間となる「月を見るもの」の群れから始まる。ちなみに映画のクレジットでも「Moon watcher」の名前が出ている。彼らは絶滅寸前である・・当然のことである・・武器も防具も持たない「か弱い」草食動物などは肉食動物の「餌」でしかないのだ。そのうえ、彼らは「繁殖力」も持っていない、子供はなかなか独り立ちせず、一度に一人しか生まれないのである。よくもまぁ、こんな生物が今まで生き残ったもんだ・・と思わせるオープニングである。彼らは気まぐれな「豹」のような生物が、たまたまほろ穴に入ってこなかった・・というだけで生きているのであり、いつかは自分の番がくることを察している・・どちらにしても30年も生きられないのであるが。そこに「モノリス」が現れる・・。
私が2001年を好きなのは、映画と小説が「別物」だからである。多くの映画は原作の周りをウロウロしているだけであり、原作の持つ「緻密性」や「組み立て」といったものを無視している。それはそうだ・・映画には「時間」と「費用」の制約があり、なおかつ商業的に成功しなければならない。原作をそのまま映画化したら、5時間以上もある退屈な作品になってしまうであろうから。ところが、2001年は違うのである。クラークの描いた小説は、非常に緻密な論理を組み立て、「意志」の存在を正面から見据えている・・彼の考える「神」の姿であろうが。それに対しキューブリックは「視覚」と「聴覚」という限られた手段で、見ている人間に「解釈」をせまるのである。キューブリックにかかれば、クラークの原作さえも「解釈」の一つであり、それが正しいのかさえも明らかにしないのだ。映画を見た人間は、大抵は「悩む」であろう・・多くの人は「解釈」をあきらめ、「何だかよく分からない・・」となり、また他の人は原作に「解釈」をゆだねるであろう。しかし、本当にこの映画を楽しむためには、「自分なりの解釈」をする必要がある・・少なくとも私はそう思うのだが。
話しをモノリスに戻そう・・2001年では3個のモノリスが現れる。最初のモノリスは教育機械、少なくとも知恵の可能性を高めるための機械である。たまたま近くにいた「月を見るもの」たちに教育をほどこす・・「道具」を使うことを・・。彼らはその資格を持っている数少ない生物なのであった。「手」が自由なのだから。原作では最初のモノリスは地球全体にばらまかれている・・可能性を高めるには当然のことである。「月を見るもの」は、ふと、ころがっている骨を持ち上げる・・それは「手」の延長であり、「手」よりも硬く破壊力を持っていた。そして彼らは、恐怖を知らない「仲間」の草食動物を倒し、「雑食」に目覚めるのである・・なにより「肉」は栄養があり、かれらの体格を向上させた・・そして、「敵」に対しても武器となるのである。「月を見るもの」はこうして世界最初の「殺人者」となる・・そして「力」の象徴である骨を空高くほうりなげる・・。
「骨」が「人工衛星」に変わるシーンは、いつ見ても感動的である・・人間は幾多の「絶滅」の機会を逃れ、宇宙に進出するまでに成長した。ヨハン・シュトラウスのワルツをバックに「PanAm」の宇宙機が宇宙ステーションを目指す・・誰が「PanAm」が倒産するなどと考えたであろうか・・強いアメリカの象徴であるのに・・。宇宙機はステーションの港である中心の回転と同期を取って回転する・・良いなぁ、好きだなぁ、このシーン。原作では中心はステーションと逆に回転することによって「静止」しているのだが、やはり「港」に接岸する儀式としては映画のシーンのほうが意味深い・・ステーション側からの映像で、管制塔(と呼ぶのか?)が小さく見えているのがいかにも人間らしくて良いのだ。映画のコンピュータについては、かのダイクストラが協力している、もちろんIBMのバックアップもあったであろうが。まだ「コンピュータ」などというものと縁のない生活をしていた私には「夢の国」に見えたものである。この宇宙機や月船、宇宙船ディスカバリー号のコンピュータ・ディスプレイは・・たとえ無意味なものであっても・・当時の人々に「宇宙旅行」という夢を具体化したのではあるまいか・・。本当に2001年には宇宙へ行けるのだ、と。
映画にはセリフのあるシーンはわずか40分しかない・・数少ないセリフのシーンは主に宇宙ステーションと月のクラビウス基地、TMA1までが一つの説明となる。あとはディスカバリー号のボーマンとブール、HALのやりとりくらいである。セリフは聞けば分かる・・あたりまえだが・・驚くのは宇宙ステーションから地球へのビジフォン代くらいか・・わずか$1.70・・うーん、安い!。月船では「無重力トイレ」のシーンが好きだ・・変な私であるが・・あの壁にかかっている注意書きが市販されていて、友達からもらった・・引越しのドサクサでなくしてしまったが・・残念。これがまた、これでもか!というくらい丁寧な注意書きなのだ。ひまな人はシーンを止めてじっくり見てほしい(読めないとは思うが・・)。
クラビウス基地からティコ・クレーターに向かうシーンでサンドイッチを食べる・・あれを食べてみたいと思ったのは私くらいか・・合成ハムはどんな味なのだろうか、と。TMA1(ティコ・マグネティック・アノマリィ1号)はその名のとおりティコ・クレーターの地磁気異常現象であるが、ここに二つ目のモノリス・・当然ながら両方を見た人間はいない・・があった。モノリスは300万年の眠りから覚め、自分に与えられた任務である「通信」を行う・・後で分かるが、この「通信」は単なる連絡では無く、多くの情報を含んでいたのだ。映画で刺激的な音がするのは、この「通信」の音だけである・・キーンという耳をふさぎたくなるような音・・DDにしたのはこのためだけか、というくらいであるが。
原作では通信は土星に向けて送られる、映画では木星であるが・・どちらが良いかは好き好きであるが、原作の土星のほうが面白い。それには、「土星の輪」の謎とか、土星の衛星の一つであるヤペタスの謎が付いてくるからであるが。映画で木星を選んでしまったため、2010年では木星が主人公になってしまった・・蛇足であるが。
映画の見せ場であるディスカバリー号である。ディビット・ボーマンとフランク・ブール、HAL9000との宇宙飛行が始まる・・HALを一文字ずらすとIBMになる・・有名な話しであるが、真偽は分からない・・。他の3人の乗組員は人工冬眠で眠らされている。彼らは結局、出演しない・・クレジットに出ているんだろうか?・・見てみようっと。
ちょっと不思議に感じるのはデスカバリー号の大きさと回転部分である。ポッドの大きさに比べて本船が小さいと感じないか?ポッドの出口と回転部分の関係も悩むところであるが・・。HAL9000は、メモリーの奥底にある秘密指令で論理回路に異常をきたす・・ボーマンとブールは秘密指令の存在を知らないのだから、HALの悩みに応えることができない。そして秘密であるがゆえにHALも相談できない・・人工知能の精神病である・・未来には起こりうるのであろうか・・ありそうなことではあるが。
ポッドが明かりを点けて進んでくるシーンはコントラストがむちゃくちゃ高く、どんなPJでもつらいシーンである。音の無い世界での恐怖というのは恐ろしいもんだ、と変な感心をしてしまうが。原作でのHALの反乱はブールを土星(映画では木星)に送りこんでからは、映画と変化している。原作では単純にハッチを開いて船内を真空にしてしまう・・空気を必要とする生物は死んでしまう・・ボーマンはやっとの思いで非常用の部屋に移り、非常用酸素で生き残る。映画ではボーマンがブールを救助しにポッドで船外に出て(ヘルメットを忘れて)、HALの拒絶により非常用ハッチを開け、ポッドを爆破してなんとか船内に入る・・このほうが迫力はあると思う。ボーマンはHALの思考回路をはずして船の制御部分のみを生かす・・そこで制御の切れた秘密指令が現れるのだ。
土星(映画では木星)に到着したボーマンを待っていたのは、最後のモノリスである。大きさは映画ではよく分からないが、1マイルもの大きさである。ボーマンは危険を覚悟でポッドによる調査に出かける・・ポッドが近づいた時にゲートが開くのである・・最後のモノリスはスターゲートだったのだ・・。ここからの移動シーンは意味不明であり、素直に見ておいた方が無難だと思う、一部はマウイ島のハレアカラ火山の火口で撮影されたそうだ・・マウイでそんな話しを聞いた。ポッドはおそらく数万光年の旅を一気に駆け抜け・・終点の部屋に到着した。お分かりであろうか・・月のモノリスが送った通信には地球のテレビ電波が含まれていたのだ・・その中に出てくる部屋(おそらくはホテル)を作ってボーマンを入れたのである。食器やナイフ、スプーンなども・・そしてガウンなども。ここからは解釈の分かれるところであるが、最終的にスターチャイルドとなる過程で不要な肉体を滅ぼす必要がある・・純粋な意識のみが必要だからである。そのため、ゆっくりと時間をかけてボーマンの肉体を滅ぼす・・無理のないように・・と、私は考えている。映画はその時間を省略するために、ボーマンが振り返るたびに時間を変化させるのだ。自分が人間であった最後の証しであるポッドを見つめながらボーマンの肉体は滅び、後には生まれたばかりのスターチャイルドが残る。彼(?)は自分の能力を試しに、ほんの数万光年をヨチヨチ歩きして故郷の地球へ戻る・・何をしたいのか自分でも分からずに。
原作で描かれた「意志」とはどういった存在なのであろうか。まだ人間が猿との境目を行ったり来たりしているころ、それは地球に「種」をまいている。地球だけ?答えはNOであろう・・それが何を求めているのか。この点が「解釈」の分かれ目であろう。そして、永遠の疑問が残される・・あれは本当に「神」だったのであろうか、と。
終わり
|
|
|
|
|
|
|
|
欲ばりでイインダヨ〜☆ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
欲ばりでイインダヨ〜☆のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90047人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6428人
- 3位
- 独り言
- 9045人