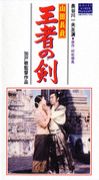あれから20年…、
この記事がなければ、研究はもっと進んでいたかもしれません。それにもまして、静岡の郷土史家が歴史を捏造したかのような物言いが憎い!
記事はこちら、「メコンプラザ」
http://
からコピペしています。
山田長政は実在したか
― 日タイ修好百周年に寄せて ―
矢野 暢
やの・とおる 京都大教授(国際政治学、外交史)
1936年、熊本県生まれ。京都大学法学部卒。法学博士。東南アジアの地域研究に優れた業績を残し「タイ・ビルマ現代政治史研究」「日本の南洋史観」「劇場国家・日本」など著書多数。「冷戦と東南アジア」で昭和61年度吉野作造賞受賞。
一次資料も明治期の写本
ことしは、日タイ修好百周年記念の年にあたる。官民あげて記念の行事や事業の準備が進められているときくが、この年にあたって気になることがある。それは、ほかならぬ山田長政のことである。
日本人は、タイというとすぐ山田長政の名前を口にする。それは、ほとんど条件反射的ですらある。しかし、山田長政は、ほんとうに日タイ友好の象徴といわれるにふさわしい存在なのかどうか、この際、学問的に再検討を加える必要がありはしないかと思う。ことと次第では、山田長政の歴史的実在すらを疑わねばならない可能性すらあるのだ。
過去に山田長政を実在の人物として描きあげてきた日本側の資料は、必ずしも好もしいものばかりではない。もっとも初期の資料として知られるのは南禅寺金地院の僧崇伝の『異国日記』であって、「山田仁左衛門長正」という名前が記されている。長政についての確かな資料が元和7年(1621)のこの日記だけだという事実は、もっと注目されていい。ついで、智原五郎八の『暹羅国山田氏興亡記』は、山田長政伝説の種をまいた作品である。五郎八自身が聞き書きによると断っているのに、一次資料として、ごく最近まで頻繁に引用されてきた重大な存在でもある。
これは寛永期の作といわれるが明治14年の政府修史局写本しか残っていない。ところがこの『興亡記』は、文化5年(1808)の近藤重蔵『外蕃通書』によって、根も葉もない虚説と斥けられている。
宝永4年(1707)の『天竺徳兵衛物語』も有名だが、およそ90歳になっての追想禄である。その他いくつかあるが、いずれも伝聞を越える具体的な記述は乏しく、また山田の出身地についても伊勢あるいは尾張としていて、静岡出身とはしていない。そして共通して、山田の晩年、すなわち南タイに渡って業死を遂げたといわれる局面については記述していない。
ところが、文化10年(1813)に出た平田篤胤の『気吹飈(いぶきおろし)』は、智原の『興亡記』などを素材に、まさに荒唐無けいな山田長政論を展開している。見てきたようなウソでかたまっており、武勇の人物としての山田像がこの講釈本で決定的になってしまう。ただ、話の展開は、後代の山田長政論とは細目がかなりちがっている。
このような江戸期の山田長政像がより鮮明な容姿を与えられるようになるのは、明治維新以降である。主として静岡の郷土史家の仕事を通じて、かなり具体性をもった山田長政像がつくりあげられていくことになる。とくに関口隆正や間宮武などという人物のことは、この際洗い直してみる必要があろう。
南進論風潮強まったとき
明治20年代という明治期南進論の風潮に導かれたものであろう、明治25年の関口の『山田長政事蹟考』と『山田長政本伝』は、山田が駿府の生まれであったかのように実証してみせた作品である。静岡の郷土史家たちは、山田の子孫の存在と過去帳の存在まではっきり調べ出してくる。
山田長政の存在が公的に認知されたのは、大正4年11月、宮内大臣波多野敬直によって従四位を贈られたときであった。折しも、大正期南進論の最盛期であった。皮肉なことに、山田長政がシャムで活躍したかどうかについての実証的な検証は、むしろその後に行われるのである。
岩生成一氏の『南洋日本町の研究』の刊行は大正15年のことであった。これによって、アユタヤーの一角に所在した日本人町の様相が明らかになった。そして、その岩生氏が、山田長政の実在を実証する決定的な資料として、アユタヤーに住まったオランダの商館員ファン・フリートの「シャム国革命史話」というオランダ語文献を発見することになる。昭和5年のことであった。
シャムに長年住まった三木栄氏の一連の山田長政論が、昭和の初めごろから「史学雑誌」等の論文で世に問われることになる。三木栄氏の代表著『山田仁左衛門長政』が刊行されるのは昭和11年秋、まさに日本が国策としての南進政策を打ち出した直後のことであった。三木氏は、岩生氏を補佐するかのように、戦後にかけて独自の山田長政論を展開しつづけることになる。
問題は、そのファン・フリートの作品に登場する日本人である。「オークヤーセーナーピムック」という人物である。シャムでは官吏になると欽賜名(ラーチャティナナーム)に名前が変わるしきたりであったから、山田長政が山田長政として活躍しえたわけではない。岩生氏はじめ多くの日本人学者は、この「オークヤーセーナーピムック」こそが山田であると比定している。
問われる歴史学の破綻
私が気にするのは、まさにこの点である。江戸期にはじまる山田長政像の形成過程の吟味をいい加減に放置しながら、それを受けて長政探しを行った昭和期の精神性、そしてファン・フリートの描く、あたかもヨーロッパの宮廷物語のような劇的な描写に歴史の現実を読みとろうとした性急で浅薄な知性の質に、私はこだわりたいのである。むろん、タイ語の信頼できる文献には、どこにも「山田長政」もなければ「オークヤーセーナーピムック」も出てこない。アユタヤーが滅亡したときに史料が消えたからだ、と、みな解釈しているが、そうだろうか。
密航してシャムに渡った二流の商人「山田長正」は、あるいは実在したかもしれない。それ以上の存在ではなかったことは確かであろう。だが、山田長政はつねに武断的英雄として描かれてきた。そのこと自体、望ましい歴史学的認識の破綻を意味しよう。それよりも、日本人は江戸から今日にかけて、なぜ東南アジアとの関わりにおいて「山田長政」を必要としたのか、それこそが問題であろう。アジア事情にうとい日本の政治的知性の、むしろ知識社会学的問題として、その点は問われねばなるまい。私たちは、南進論的思考をこの際きっぱりと超克すべきであろう。ことしは、まさにそのための年なのである。
毎日新聞(夕刊) 昭和62年(1987年)3月4日 水曜日 (4)
−−−−−−−−−−
17世紀シャム国王の武官として活躍したとされる「山田長政」が、日タイ修好百年のことし、ブームだ。タイ政府の観光キャンペーンも功を奏してか、長政ゆかりのアユタヤに行く日本人は例年になく多く、テレビ番組や旅行記などにも長政ものが目立つ。日本政府も修好百年事業の目玉商品として現地に「アユタヤ歴史資料館」を無償援助でつくることを決め、経団連なども日本人町跡整備のための募金活動を始めている。こんなおり、東南アジアにくわしい国際政治学者の矢野暢京大教授(50)が「長政は国策的に作られた人物。実在は疑わしく、盲目的な英雄扱いは外交上もマイナス」と発言、各界に波紋を呼んでいる。外務省も長政の扱いは「十分、配慮する」と慎重だ。長政のどこまでが「虚」で、どこまでが「実」なのか −こんな関心の高まりもやはりブームである。(宇佐美 雄策記者)
日タイ修好100年でブームだが 実在したのか 英雄・山田長政
矢野京大教授の架空説に波紋
戦前の国策が生む 出生年月・日本の身分など不明 タイ・オランダ資料に名前がない
史実としての長政は存在」の反論も
「戦中派の日本人の頭には、ゾウに乗って活躍したシャムの日本武将のイメージがこびりついているが、ラッキョウの皮をむくように調べれば調べるほどに、なにも確実なものは残らない」と矢野教授。
その「英雄長政の不在論」は単純明快だ。?江戸時代の長政伝は創作で、歴史研究に最も大切な長政の出生の場所・年月、日本での身分、シャム渡航の日時、方法、シャムでの生活、死亡原因などが解明されていない ?タイ・オランダ資料に「山田長政」の名が一切ない ?オランダ資料にある日本人傭兵名と江戸幕府資料の長政は一致するとされているが、オランダ人自体の記述は伝聞で、そのまま信用できない −というもの。
矢野教授によれば、山田長政の名が一般に知られだしたのは、宝永4年(1707)の「天竺徳兵衛物語」の出版後から。このあとさまざまな長政伝が出回るが、「無断引用、盗作の繰り返し」で次々に話に尾ヒレがついた。
幕末の英国人外交官アーネスト・サトウが、オランダ文献にあるシャム時代の日本人傭兵のリーダー「オークヤ・セナピムク」と「山田長政」は同一人物だ、との新説を唱えた。このあと昭和5年、岩生成一・元東大教授(86)がオランダ・ハーグの国立公文書館で調べたアユタヤのオランダ商館長、ファン・フリートの「シャム国王位継承革命戦記」(1640年)などの記録と元和7年(1621年)、徳川幕府に長政が送ったとされる手紙などを照合、同一人物と結論付けた。現在、学会では、この説に落ち着いている。
しかし、矢野教授は「長政研究が最も盛んだった昭和初期の日本の政治的影響も検証し、常識とされたことを冷静に疑ってみる必要がある」と強調する。
こういった矢野教授の”挑戦”に対して、戦前から南洋日本人町や朱印船貿易研究の第一人者とされる岩生・元東大教授は「矢野さんがどのくらいオランダ文献を吟味されたかしらないが、観念的に長政が実在しなかった、といっても説得力はない」という。「確かに江戸の本の中には、おもしろおかしく書いた作り話も多いが、長政が幕府に送ってきた書簡類などと、細かいことまで正確に記述したオランダ文献とは矛盾しない。戦争中、軍の威光を傘に、ずいぶんインチキな長政論をぶった連中もいたが、史実としての長政まで否定することはできない」と反論する。
矢野教授は「江戸幕府の外交文書をまとめた『異国日記』には『長正』のサインの書簡があるが、これで長政の全容や武将としての活躍がわかるものではない」としたうえ、「私は、日本人の頭にある長政は実在しない、と言いたいのです。過去の長政についての誇張、わい曲の歴史は戦後、放置されたまま。いまこそ、虚飾と史実とを区別できるチャンスです」と語る。
矢野教授は、昭和6年の満州事変以降の日本の南進政策が、長政を英雄に仕立てたとし、その国策化の歴史をあげる。
昭和15年当時、長政は「南進の先覚者」と新聞にも扱われ、長政の映画も「国策映画」と呼ばれた。太平洋戦争突入の翌年の昭和17年、国定修身教科書に長政が登場した。
矢野教授は、江戸時代の国学者、平田篤胤の「講本気吹於呂志」(文化10年、1813)の記述に注目する。まるで修身教科書のモデルだというのだ。
「従わぬ国々を長政が討ちたいらげ、戦うごとに勝て、実に天竺中(東南アジアやインド)を震いわななかせ、日本軍といえば、小児もなきをやめ、天竺の国々をおぢ畏れさせたほどのことでござる。実に御国の武勇を天竺中に輝かしつけたでござる。大日本魂の人の外国に渡りたる時の手本ともすべきこと」
国粋主義を強調した篤胤の長政礼賛が、そのまま「大東亜戦争」当時の教育にも用いられたのは、必然的でもあった、と矢野教授は分析する。
朝日新聞(夕刊) 昭和62年(1987年)3月10日 水曜日 (4)
この記事がなければ、研究はもっと進んでいたかもしれません。それにもまして、静岡の郷土史家が歴史を捏造したかのような物言いが憎い!
記事はこちら、「メコンプラザ」
http://
からコピペしています。
山田長政は実在したか
― 日タイ修好百周年に寄せて ―
矢野 暢
やの・とおる 京都大教授(国際政治学、外交史)
1936年、熊本県生まれ。京都大学法学部卒。法学博士。東南アジアの地域研究に優れた業績を残し「タイ・ビルマ現代政治史研究」「日本の南洋史観」「劇場国家・日本」など著書多数。「冷戦と東南アジア」で昭和61年度吉野作造賞受賞。
一次資料も明治期の写本
ことしは、日タイ修好百周年記念の年にあたる。官民あげて記念の行事や事業の準備が進められているときくが、この年にあたって気になることがある。それは、ほかならぬ山田長政のことである。
日本人は、タイというとすぐ山田長政の名前を口にする。それは、ほとんど条件反射的ですらある。しかし、山田長政は、ほんとうに日タイ友好の象徴といわれるにふさわしい存在なのかどうか、この際、学問的に再検討を加える必要がありはしないかと思う。ことと次第では、山田長政の歴史的実在すらを疑わねばならない可能性すらあるのだ。
過去に山田長政を実在の人物として描きあげてきた日本側の資料は、必ずしも好もしいものばかりではない。もっとも初期の資料として知られるのは南禅寺金地院の僧崇伝の『異国日記』であって、「山田仁左衛門長正」という名前が記されている。長政についての確かな資料が元和7年(1621)のこの日記だけだという事実は、もっと注目されていい。ついで、智原五郎八の『暹羅国山田氏興亡記』は、山田長政伝説の種をまいた作品である。五郎八自身が聞き書きによると断っているのに、一次資料として、ごく最近まで頻繁に引用されてきた重大な存在でもある。
これは寛永期の作といわれるが明治14年の政府修史局写本しか残っていない。ところがこの『興亡記』は、文化5年(1808)の近藤重蔵『外蕃通書』によって、根も葉もない虚説と斥けられている。
宝永4年(1707)の『天竺徳兵衛物語』も有名だが、およそ90歳になっての追想禄である。その他いくつかあるが、いずれも伝聞を越える具体的な記述は乏しく、また山田の出身地についても伊勢あるいは尾張としていて、静岡出身とはしていない。そして共通して、山田の晩年、すなわち南タイに渡って業死を遂げたといわれる局面については記述していない。
ところが、文化10年(1813)に出た平田篤胤の『気吹飈(いぶきおろし)』は、智原の『興亡記』などを素材に、まさに荒唐無けいな山田長政論を展開している。見てきたようなウソでかたまっており、武勇の人物としての山田像がこの講釈本で決定的になってしまう。ただ、話の展開は、後代の山田長政論とは細目がかなりちがっている。
このような江戸期の山田長政像がより鮮明な容姿を与えられるようになるのは、明治維新以降である。主として静岡の郷土史家の仕事を通じて、かなり具体性をもった山田長政像がつくりあげられていくことになる。とくに関口隆正や間宮武などという人物のことは、この際洗い直してみる必要があろう。
南進論風潮強まったとき
明治20年代という明治期南進論の風潮に導かれたものであろう、明治25年の関口の『山田長政事蹟考』と『山田長政本伝』は、山田が駿府の生まれであったかのように実証してみせた作品である。静岡の郷土史家たちは、山田の子孫の存在と過去帳の存在まではっきり調べ出してくる。
山田長政の存在が公的に認知されたのは、大正4年11月、宮内大臣波多野敬直によって従四位を贈られたときであった。折しも、大正期南進論の最盛期であった。皮肉なことに、山田長政がシャムで活躍したかどうかについての実証的な検証は、むしろその後に行われるのである。
岩生成一氏の『南洋日本町の研究』の刊行は大正15年のことであった。これによって、アユタヤーの一角に所在した日本人町の様相が明らかになった。そして、その岩生氏が、山田長政の実在を実証する決定的な資料として、アユタヤーに住まったオランダの商館員ファン・フリートの「シャム国革命史話」というオランダ語文献を発見することになる。昭和5年のことであった。
シャムに長年住まった三木栄氏の一連の山田長政論が、昭和の初めごろから「史学雑誌」等の論文で世に問われることになる。三木栄氏の代表著『山田仁左衛門長政』が刊行されるのは昭和11年秋、まさに日本が国策としての南進政策を打ち出した直後のことであった。三木氏は、岩生氏を補佐するかのように、戦後にかけて独自の山田長政論を展開しつづけることになる。
問題は、そのファン・フリートの作品に登場する日本人である。「オークヤーセーナーピムック」という人物である。シャムでは官吏になると欽賜名(ラーチャティナナーム)に名前が変わるしきたりであったから、山田長政が山田長政として活躍しえたわけではない。岩生氏はじめ多くの日本人学者は、この「オークヤーセーナーピムック」こそが山田であると比定している。
問われる歴史学の破綻
私が気にするのは、まさにこの点である。江戸期にはじまる山田長政像の形成過程の吟味をいい加減に放置しながら、それを受けて長政探しを行った昭和期の精神性、そしてファン・フリートの描く、あたかもヨーロッパの宮廷物語のような劇的な描写に歴史の現実を読みとろうとした性急で浅薄な知性の質に、私はこだわりたいのである。むろん、タイ語の信頼できる文献には、どこにも「山田長政」もなければ「オークヤーセーナーピムック」も出てこない。アユタヤーが滅亡したときに史料が消えたからだ、と、みな解釈しているが、そうだろうか。
密航してシャムに渡った二流の商人「山田長正」は、あるいは実在したかもしれない。それ以上の存在ではなかったことは確かであろう。だが、山田長政はつねに武断的英雄として描かれてきた。そのこと自体、望ましい歴史学的認識の破綻を意味しよう。それよりも、日本人は江戸から今日にかけて、なぜ東南アジアとの関わりにおいて「山田長政」を必要としたのか、それこそが問題であろう。アジア事情にうとい日本の政治的知性の、むしろ知識社会学的問題として、その点は問われねばなるまい。私たちは、南進論的思考をこの際きっぱりと超克すべきであろう。ことしは、まさにそのための年なのである。
毎日新聞(夕刊) 昭和62年(1987年)3月4日 水曜日 (4)
−−−−−−−−−−
17世紀シャム国王の武官として活躍したとされる「山田長政」が、日タイ修好百年のことし、ブームだ。タイ政府の観光キャンペーンも功を奏してか、長政ゆかりのアユタヤに行く日本人は例年になく多く、テレビ番組や旅行記などにも長政ものが目立つ。日本政府も修好百年事業の目玉商品として現地に「アユタヤ歴史資料館」を無償援助でつくることを決め、経団連なども日本人町跡整備のための募金活動を始めている。こんなおり、東南アジアにくわしい国際政治学者の矢野暢京大教授(50)が「長政は国策的に作られた人物。実在は疑わしく、盲目的な英雄扱いは外交上もマイナス」と発言、各界に波紋を呼んでいる。外務省も長政の扱いは「十分、配慮する」と慎重だ。長政のどこまでが「虚」で、どこまでが「実」なのか −こんな関心の高まりもやはりブームである。(宇佐美 雄策記者)
日タイ修好100年でブームだが 実在したのか 英雄・山田長政
矢野京大教授の架空説に波紋
戦前の国策が生む 出生年月・日本の身分など不明 タイ・オランダ資料に名前がない
史実としての長政は存在」の反論も
「戦中派の日本人の頭には、ゾウに乗って活躍したシャムの日本武将のイメージがこびりついているが、ラッキョウの皮をむくように調べれば調べるほどに、なにも確実なものは残らない」と矢野教授。
その「英雄長政の不在論」は単純明快だ。?江戸時代の長政伝は創作で、歴史研究に最も大切な長政の出生の場所・年月、日本での身分、シャム渡航の日時、方法、シャムでの生活、死亡原因などが解明されていない ?タイ・オランダ資料に「山田長政」の名が一切ない ?オランダ資料にある日本人傭兵名と江戸幕府資料の長政は一致するとされているが、オランダ人自体の記述は伝聞で、そのまま信用できない −というもの。
矢野教授によれば、山田長政の名が一般に知られだしたのは、宝永4年(1707)の「天竺徳兵衛物語」の出版後から。このあとさまざまな長政伝が出回るが、「無断引用、盗作の繰り返し」で次々に話に尾ヒレがついた。
幕末の英国人外交官アーネスト・サトウが、オランダ文献にあるシャム時代の日本人傭兵のリーダー「オークヤ・セナピムク」と「山田長政」は同一人物だ、との新説を唱えた。このあと昭和5年、岩生成一・元東大教授(86)がオランダ・ハーグの国立公文書館で調べたアユタヤのオランダ商館長、ファン・フリートの「シャム国王位継承革命戦記」(1640年)などの記録と元和7年(1621年)、徳川幕府に長政が送ったとされる手紙などを照合、同一人物と結論付けた。現在、学会では、この説に落ち着いている。
しかし、矢野教授は「長政研究が最も盛んだった昭和初期の日本の政治的影響も検証し、常識とされたことを冷静に疑ってみる必要がある」と強調する。
こういった矢野教授の”挑戦”に対して、戦前から南洋日本人町や朱印船貿易研究の第一人者とされる岩生・元東大教授は「矢野さんがどのくらいオランダ文献を吟味されたかしらないが、観念的に長政が実在しなかった、といっても説得力はない」という。「確かに江戸の本の中には、おもしろおかしく書いた作り話も多いが、長政が幕府に送ってきた書簡類などと、細かいことまで正確に記述したオランダ文献とは矛盾しない。戦争中、軍の威光を傘に、ずいぶんインチキな長政論をぶった連中もいたが、史実としての長政まで否定することはできない」と反論する。
矢野教授は「江戸幕府の外交文書をまとめた『異国日記』には『長正』のサインの書簡があるが、これで長政の全容や武将としての活躍がわかるものではない」としたうえ、「私は、日本人の頭にある長政は実在しない、と言いたいのです。過去の長政についての誇張、わい曲の歴史は戦後、放置されたまま。いまこそ、虚飾と史実とを区別できるチャンスです」と語る。
矢野教授は、昭和6年の満州事変以降の日本の南進政策が、長政を英雄に仕立てたとし、その国策化の歴史をあげる。
昭和15年当時、長政は「南進の先覚者」と新聞にも扱われ、長政の映画も「国策映画」と呼ばれた。太平洋戦争突入の翌年の昭和17年、国定修身教科書に長政が登場した。
矢野教授は、江戸時代の国学者、平田篤胤の「講本気吹於呂志」(文化10年、1813)の記述に注目する。まるで修身教科書のモデルだというのだ。
「従わぬ国々を長政が討ちたいらげ、戦うごとに勝て、実に天竺中(東南アジアやインド)を震いわななかせ、日本軍といえば、小児もなきをやめ、天竺の国々をおぢ畏れさせたほどのことでござる。実に御国の武勇を天竺中に輝かしつけたでござる。大日本魂の人の外国に渡りたる時の手本ともすべきこと」
国粋主義を強調した篤胤の長政礼賛が、そのまま「大東亜戦争」当時の教育にも用いられたのは、必然的でもあった、と矢野教授は分析する。
朝日新聞(夕刊) 昭和62年(1987年)3月10日 水曜日 (4)
|
|
|
|
|
|
|
|
山田仁左衛門長政 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
山田仁左衛門長政のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90051人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人