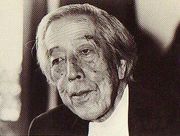https:/
羽仁五郎bot
@gorohani
我々は、またもやだまされるのであろうか。我々が一たびだまされた、その責任は彼らにある。しかし、我々が再びだまされるならば、その責任は今度は我々にあるだろう。我々は、もっと賢くならなければならない。
11:23 - 2018年10月6日
アステローペ・リーフ
@reef100
返信先: @gorohaniさん
【1】「お金という資源」の解放、「論理という資源」の解放
「お金という資源」の解放、「論理という資源」の解放、この二つは必須。羽仁五郎は独占資本からの解放を示唆し論理という資源の解放を示唆してきた。いろんな言葉やたとえで。しかしまだまだ入り口であった。漠然としているレベル。総論は正しくても脳みそに焼き付けるまで人民にヒットしてない。
「お金という資源」の解放、「論理という資源」の解放、この二つは必須。
「お金という資源」の解放はベンジャミン氏山口薫氏のご指摘【日銀の国有化】。
(必読読書:『公共貨幣』
山口 薫 著
東洋経済新報社
https:/
論理という資源からの解放は大きくは二つ。
一つはここを蹴飛ばせばあそこが飛び出るという【羽仁五郎の言う社会科学としての論理】。(注:これは成果物)
もう一つの論理は【羽仁五郎の言う「アリストテレスの論理学」=三段論法からの脱出】。(注:これは成果物を生むための思考回路であり、ファシズムに騙されないための思考回路)
【2】【羽仁五郎の言う社会科学としての論理】
【羽仁五郎の言う社会科学としての論理】は、小難しいことは問題ではない。最低限、日常会話言語に言えば「人民の視点」があるかないかで判別できる。論理的に言うなら、人民主権の確立にあたる。
【3】羽仁五郎の言う「アリストテレスの論理学(=三段論法)からの解放】
【羽仁五郎の言う「アリストテレスの論理学(=三段論法)からの解放】はもっとも日本人民の不得手なわかりにくいものだ。
何とかしてこれを日本人民に分からせようとして羽仁五郎は苦心惨憺している。
その苦心惨憺のひとつが量子力学をヒントにした説明。
観測されている時と観測されてない時とでは量子の動きが違う。
観測されてない時は全く予測外動きをしているという事を例に、事実として新しい論理学の存在を示唆している。
(注:まぁ、人間の思考回路も定説とか、教科書とか、メディアとか、こうなっているんだから仕方ないとかいうあきらめ、もう絶体絶命だなどというあきらめ、そんなことにとらわれてはいけないという事を言いたいのだろうね、羽仁五郎は。そして、もっともっと斬新な発見を、論理の発見をしていけという、実践の論理なんだろうと思う)
日常会話言語的に言えば、「歴史には間違い(予想外)が起こる。」という言葉を羽仁五郎は使っている。
(注:歴史そのものが生きののように、非線形な歴史を生み出すという発見をしたのでしょうね。)
科学者の言葉でこれ(量子力学の世界)を読み解くと、湯川秀樹はこういっている。 ニュートン力学というのはドグマ。湯川秀樹が言っているように理論のほころびがわからなくなってしまっているもの。 (物理法則:http://
*−−−−−引用開始−−−−−−−−*
湯川秀樹は、ニュートン力学は適用範囲が広かったことに言及しつつ、だからドグマになっても不思議ではなかったのだ、と述べている[4]。つまり、適用範囲が広くて、かつそれ自体で閉じているような理論体系を学習・習得すると、学習者は思考がその理論体系に沿ってしか動かなくなり、世界を見ても世界自体を見ることなく、自己完結した理論体系や用語へと変換するだけなので、理論のほころびがわからなくなり、あたかも世界が理論に沿って全てが動いているようにしか感じられなくなってしまう、ということである。
[4]^ a b 湯川秀樹 『物理講義』 講談社〈講談社学術文庫〉、1977年、21-22頁。
ISBN 4-06-158195-3。
*−−−−−引用終了−−−−−−−−*
基本的に科学といってもこういうものです。
こういう科学者もいる。
【電子のレベルでは、因果律の働く余地が全くない。「量子力学のパラドックス(ジレンマ、真と偽の混在)について。」】
※【参考情報】
(出典:「理性のゆらぎ」 青山圭秀著 P.180〜P.182 )
*−−−引用開始−−−*
たとえば、物質を構成する原子は、中心に原子核があり、その周りを電子が回っているものと考えられた時期があった。今でも、中学や高校の教科書には、そうか書いてある。とすれば、ある時点における電子の位置(q)という運動量(p、質量×速度)は、古典力学、すなわち因果律にしたがって一意に定まることになる。
しかし、そのような電子の“軌道”というものは、実際には存在しないのである。量子力学の教えるところによれば、ある時、ある電子がどこにいるのかは、測定した瞬間に確定するのであるが、その結果は純粋に確率的に決まる。多回数の観測を行った場合の傾向は分かっても、一度の観測でどういう結果が得られるかは、全くの偶然による。その結果に対応する原因は、「分からない」のではなく、「ない」のである。ある時、ある電子がどういう運動量を持つのかも同様に、純粋に確率的に、偶然決まる。そこには、因果律の働く余地が全くないと考えられているのである。
この思想を推し進めていくと、われわれが物理的に「実在」していると思っているものも、実は全て、本質的にあやふやな存在であることになる。この世界には、およそ知りうる本質的に確定したものは、何一つない。何事も、どこまでも、確率的事象であり、確率的存在であることとなる。
量子論のこの思想は、われわれの直観からは到底受け入れ難いものである。しかし今日、科学者たちがこれを認めざるを得ないのはなぜか。それは、これによって、自然の現象をより単純に、整合的に説明できるからである。もともと、因果律も、われわれの経験を説明するための産物である。経験の質と量が増せば、常識もまた、変更される。しかし、ここまで来ればだれにも明らかなように、これで本当に正しい常識が得られたのかどうかなど、実はどこまで行っても分からないのである。
覆る常識は、因果律に限らない。われわれの科学を支えるもう一つの柱、「観測」もそうである。
われわれは、ものごとをありのまま観測し、そこから客観的データを得ていると、何世紀にもわたって思い続けてきた。まさにそれこそが科学の基盤であり、科学を科学たらしめるもののはずであった。ところが、やはり今世紀に入ってから、われわれの観測はつねにある「ゆらぎ」がつきまとうことがはっきりと認識される。
現在成功を収めている量子力学の基本方程式は、対象にある観測を行ったときに、その対象の状態が変わり、それを含んだある観測値が得られる、という形をしている。つまり、われわれが何かを観測しようと思ったとき、観測されたものはすでに状態を変えている、ということである。
ある粒子の位置を確かめようとすれば、運動量が決まらない。運動量を測定しようとすれば、今度は位置が決まらなくなる。Δq・Δp≧h/4πという一遍の不等式で表されるこのゆらぎは、人間の物理的認識において根本的に避けがたい要素と考えられている(不確定性原理:Uncertainty principle)。
さらに、その観測を行う装置や、当の観測者自身はどういう法則に従うのかという問題も生じる。観測対象が不確定性に従うことはいいとして(よくはないが、仕方がないとして)、ではそれを観測する装置や観測者自身は、確定した何かなのだろうか。しかし、観測装置は明らかに量子力学に従うだろうし、観測者である人間も、これを物体と考えるなら、その個々の構成粒子は量子力学に従い、不確定なもののはずである。そうすると、それらの間で行われている観測という行為が、何かしら意味のあるものだという保証は、どこにあるのだろうか。
この問題を解決するために、たとえばノイマンという天才数学者(アメリカ)は、量子力学から独立した、つまり、物理法則によらない、観測者の「自意識」というものを想定した。あらゆる観測を行う主体は、結局、この自意識だというのである。(J.von Neumann 『 Mathematische Grundlangen der Quantenmechanik 邦訳:量子力学の数学的基礎 みすず書房』)。
なるほど、そう考えればことは収まるし、また、そのように考えざるを得ないようにも見える。ところが、この想定は、一つの大きな犠牲をわれわれに強いることとなる。なぜなら、もともと物理学には、この世界の実在を、全て物質とその相互作用とに帰着させようという大前提があったはずだからである。その物質をとことんつきつめていくと量子力学という理論につき当たり、その挙げ句われわれは、この巨大な思想を完結させるために、非物理的実体を想定せざるを得ないというパラドックスに陥る。
実は、量子力学にはこのような根本的なパラドックスがいくつかあり、それらの解決はついていない。量子力学が本当に「完結」するのか、さらに一般相対性理論というもう一方の大理論と折り合いがつくのかどうかも、大いに疑わしい。
そもそも、この世界を記述する際に、それを物理的側面からのみで完結させることができるなどという保証は、どこにもないのである。
以上のような人間理性の本質とも関連して、イギリスの天才物理学者ホーキングは、次のように語る。
「もし、完全な統一理論が本当に存在するとすれば、それはわれわれの行為をも決定しているだろう。これはつまり、この理論をわれわれが探究することによって得るであろう結果も、この理論自身によって決定されているということだ。しかし、われわれが証拠から出発して正しい結論を引出すことをこの理論が決定づけていると、どうして言えるのか?われわれが誤った結論を引出すと結論づけられていても、不思議ではないのではなかろうか?ひょっとして、そもそも結論になどたどりつきさえしないようになっているのではないのか?」(S.W.ホーキング 『A BRIEF HISTORY OF TIME 邦訳:ホーキング宇宙を語る 早川書房』)
*−−−引用終了−−−*
リーフ注:パラドックス:「パラドックス(paradox)とは、ギリシャ語で「矛盾」「逆説」「ジレンマ」を意味する言葉。 数学・哲学の分野では「一見間違っていそうだが正しい説」もしくは「一見正しく見えるが正しいと認められない説」等を指して用いられる。」
(出典:パラドックスとは (パラドックスとは) [単語記事] - ニコニコ大百科 http://
量子力学、不確定性原理、ヴェーダの世界までいくと形而上学的な世界の話と科学的な物理学の話の境界線があたかもなくなるような・・・。
ただ、ここで注目しておきたいのは、青山さんの「 しかし、そのような電子の“軌道”というものは、実際には存在しないのである。量子力学の教えるところによれば、ある時、ある電子がどこにいるのかは、測定した瞬間に確定するのであるが、その結果は純粋に確率的に決まる。多回数の観測を行った場合の傾向は分かっても、一度の観測でどういう結果が得られるかは、全くの偶然による。その結果に対応する原因は、「分からない」のではなく、「ない」のである。ある時、ある電子がどういう運動量を持つのかも同様に、純粋に確率的に、偶然決まる。そこには、因果律の働く余地が全くないと考えられているのである。 」
の部分である。おそらく、羽仁五郎のいいたいこともここにある。
この決まってないのではなくって「ない」のであるというのは、価値の世界と似ていはしないか。情緒的価値判断から情緒的価値判断の演繹を現代のわれわれ日本人は日常会話言語においても、政治家の答弁や裁判官の判決文においても嫌というほどきかされる。あたかもそれが論理的推論で正しいかのように。
【4】「決まってない」のではなくて「ない」のは、価値の世界もまた似ている。
(注:これは、ファシズムに騙されない思考回路と直結している脳みその武器である。理論武装である。)
【事実と価値の二元論】について
学校教育は無論の事、例の教育勅語も情緒的価値判断の塊だ。
しかし、本来、情緒的価値判断は、情緒的価値判断から無限にどんな方向にも演繹できるものなのだ。
言葉の意味の本質的意味定義もそうだ。
どんな目的で、どういう視点を選択したかでどうにでもいえるのだ。それが価値。
我々の脳みそは、この情緒的価値判断から情緒的価値判断を無限にチェーンできる。
学問的には、価値二元論が、戦後英米倫理学会において、どうしてナチスのようなファシズムに人々が騙されていったのかを研究した結果としてクローズアップされた。
【注:価値二元論そのものは自然主義ファラシー(ファラシー:誤謬)という形で二十世紀初頭に一大革新をもたらしている。遡れば18世紀のヒュームやカントも論じている。二十世紀初頭にイギリスのG・E・ムーアとドイツのマックス・ヴェーバーが自然主義(価値一元論)批判(自然主義ファラシー)。】
その真髄は、「価値」と「事実」は二元であるということだ。
「事実」からいかなる「価値」も論理的推論で演繹できず、
「価値」から「事実」も論理的推論で演繹できない。
言い換えれば、いかなる「価値」も「事実」に還元できず、
いかなる「事実」も「価値」に還元できない。
価値の演繹を、「道徳教科書」も、「修身教科書」も、「教育勅語」もくりかえすが、これでもかこれでもかと繰り返し洗脳するが、しかし、価値から価値はどんなに論理をならべても、アリストテレスの三段論法では無限にバリエーションをもって無限につながり、しかし、どんなに時間とエネルギーを費やし
ても、国家権力で強制的に洗脳して、学問の真理として絶対に、「事実」からいかなる「価値」も演繹できず、いかなる「価値」からもいかなる「事実」も演繹できない。例えばこれは、天皇が天孫降臨の子孫だという虚構を事実として敷衍するがわにとっても、象徴天皇の権威という「価値」を何らかの「事実」に還元しようとしたり、虚構の事実(ウソ、神話)に還元しようとする天皇制にとってはこれほど不都合なものはないのではないだろうか。
天皇制ばかりではない、あらゆる権威にとって、あるいはあらゆる権力にとって、価値二元論の存在は、脅威である。
(注:権力を持つものは全て脅威だ。親でも、学校の教師でも、裁判官でも、国家でも。)
日本人民の脳みそが価値二元論を当たり前のこととして認識するようになれば、
再び三度ファシズムの洗脳におかされる危険は極めて低くなるのではないだろうか。
その意味でナチスに迫害された学者による価値二元論への到達は極めて価値のあるものではないだろうか。
この価値二元論に即した本で
「思考と行動における言語」 S.I.ハヤカワ著がある。https:/
もし学問的に読みたいなら碧海純一の「法哲学概説」の中の「自然主義ファラシー」が学問的解説だと思います。この本は全訂第二版補正版が出てますがこれではなて全訂第一版の方がはるかに優れている。全訂第一版は碧海純一が(師弟関係の師からの圧力と思うが)取っ払った「社会統制論」がある。
いずれにせよ、我が国人民は「価値」と「事実」が分かってない。
(注;そのために脳において足枷がつけられているに等しい。「論理という資源」が解放されない大きな要因である。
社会契約というような約束定義というものも、ピンとこない大きな原因である。
例えば、国家が人民が作った、という約束定義を聞いても、それが約束定義だと断っても、ほんとかどうか知らないが中学校の元教師という人さえ、ネットで、国家は弱肉強食でできたものだと言ってくる。
頭に約束定義の意味がからっきし、ヒットしない。その様な親や教師に教育されてればなおさら子供の頭にはヒットしないだろう。)
【5】約束定義の威力
これは、我が国人民が「価値」と「事実」の実相が分かってないということは、
約束定義というものを血肉化できない大きな原因の一つだと思うのです。
「国家は人民が作った」という約束定義を根幹とすることに(対して)、国家は弱肉強食で強いものが作ったのだという主張を多くに日本人民は信じている。(そして、首をひねる。)
「『国家は人民が作った』という事にしよう、これを根幹に置かなければ、人民の自然権(価値)を守れない。人民の自然権を守る社会科学を構築できない」ということが頭にヒットしないようだ。
なぜ、近代社会契約の国家の約束定義を作ったかが理解しづらいようだ。
*−−−−−−注;開始−−−−−−*
もう少し詳しく言えば、近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。人民の自然権を守る為に人民が国家を作った」を詳しく言えば、
(1)一人一人の個人の自然権を個人では守れない。しかし、強大な国家権力を持つ国家なら個人の自然権を守ることができる。そのために人民が、国家を作った。そして、強大な国家権力を国家を信じて託した。
(2)しかし、国家が強大な国家権力を濫用して人民の自然権を棄損したら目も当てられれない。防ぐ方法がない。だから、人民は、近代憲法を作って、国家に「絶対にこの憲法を守って信じて託された国家権力を使わせていただきます」という誓約(立憲主義)をして、国家権力を信託された。国家権力の信託と、立憲主義という誓約は、一体のもの。
(3)ゆえにもし、国家権力が安倍晋三の様に立憲主義を破棄したり、国家の目的である人民の自然権を棄損したら、もはやそのような国家権力は国家権力の資格がない。リセットしなければならないものであるということだ。ここに抵抗権も革命権もある。初めから人民にある。
(4)人民主権というのは、国家を作った人民に、政治を最終的に決定する権利があるということ。人民 vs 国家 という構図において、国家に主権はない。
主権は100%人民にある。
(5)近代democracyのdemocracyの語源は、デーモス(民衆)によるクラトス(支配:権力)であり、これは、近代社会契約の国家の約束定義に合致しており、
また、人民主権と同義のものだ。
多数決=近代democracyではない。多数決は、democracyを実現する可能性のある一つのツール(道具)に過ぎない。ファシズム(=三権の癒着)でも多数決を使う。
今の日本がそうだ。間接民主制(議会制民主主義と命名しようが)これは、多数決の一種でありそれがdemocracyのことではない。
*−−−−−−注;終了−−−−−−*
約束定義をしたこと、約束定義を受け入れたことで、すなわち社会契約したことで、根幹に置くことで、近代democracyはなりたっている。近代憲法も、近代立憲主義も、人民主権もなりたっている。導出され、連関している。
【6】天賦人権について
片山さつきらが国民に主権なんかあるわけないじゃないかとか、天賦人権なんかあるわけないじゃないか、人権なんか国家が法律(憲法も大きくは法律)に書いて初めて与えられるものだとか、いうのに対して、一般国民は、天賦人権はあるという。
(※天賦人権が実在するというのは論理的推論において正しいか間違っているかという正誤の問題になってしまっている点に注意すべきだ。)
これは自然権なんかあるわけないじゃないかという主張に対して、自然権は事実としてあるという論争に似ている。
しかし、事実と価値の二元論に即していえば、自然権も、基本的人権も、価値なのだ。
事実から演繹できない価値なのだ。事実に還元できない価値なのだ。
しかし、自然権という価値を、あるいは人権という価値を、人間には、あるものと認めましょう、という約束定義という立場で根幹に置いたならどうか。
この約束定義として、自然権というものが人間にはあるものと認めましょうというのが、近代社会契約の国家の約束定義でもあるのだ。
(そういう約束定義なしで)
事実として自然権が人間には先験的にア・プリオリにこの世の出現以前からあるというような主張をするならこれは価値一元論(=自然主義)だ。
王権神授説など典型的な自然主義だ。
原点としての価値を置きそこから論理的推論で演繹する。
あるいは原点としての事実を置きその事実から価値を演繹してく。
天孫降臨族の天皇制、天皇主権も典型的な価値一元論であり自然主義だ。
では、自然法を説く法哲学者は皆自然主義者か?ちがう。ラートブルフは、私は自然法に帰依するといった。
帰依=正しいと信じる=価値としてみとめて、その価値を正しいものとして受け入れる。
事実であるかないかではなく。帰依し、その価値を根源に置くことで、そこから社会科学を発展させていく手法は価値二元論と矛盾しない。
(※ラートブルフは正誤問題として自然法の実在を問うという事はあっさりパスして帰依するという約束定義で、そこから自然法に基づく社会科学の構築をしているということだ)
(続く:http://
羽仁五郎bot
@gorohani
我々は、またもやだまされるのであろうか。我々が一たびだまされた、その責任は彼らにある。しかし、我々が再びだまされるならば、その責任は今度は我々にあるだろう。我々は、もっと賢くならなければならない。
11:23 - 2018年10月6日
アステローペ・リーフ
@reef100
返信先: @gorohaniさん
【1】「お金という資源」の解放、「論理という資源」の解放
「お金という資源」の解放、「論理という資源」の解放、この二つは必須。羽仁五郎は独占資本からの解放を示唆し論理という資源の解放を示唆してきた。いろんな言葉やたとえで。しかしまだまだ入り口であった。漠然としているレベル。総論は正しくても脳みそに焼き付けるまで人民にヒットしてない。
「お金という資源」の解放、「論理という資源」の解放、この二つは必須。
「お金という資源」の解放はベンジャミン氏山口薫氏のご指摘【日銀の国有化】。
(必読読書:『公共貨幣』
山口 薫 著
東洋経済新報社
https:/
論理という資源からの解放は大きくは二つ。
一つはここを蹴飛ばせばあそこが飛び出るという【羽仁五郎の言う社会科学としての論理】。(注:これは成果物)
もう一つの論理は【羽仁五郎の言う「アリストテレスの論理学」=三段論法からの脱出】。(注:これは成果物を生むための思考回路であり、ファシズムに騙されないための思考回路)
【2】【羽仁五郎の言う社会科学としての論理】
【羽仁五郎の言う社会科学としての論理】は、小難しいことは問題ではない。最低限、日常会話言語に言えば「人民の視点」があるかないかで判別できる。論理的に言うなら、人民主権の確立にあたる。
【3】羽仁五郎の言う「アリストテレスの論理学(=三段論法)からの解放】
【羽仁五郎の言う「アリストテレスの論理学(=三段論法)からの解放】はもっとも日本人民の不得手なわかりにくいものだ。
何とかしてこれを日本人民に分からせようとして羽仁五郎は苦心惨憺している。
その苦心惨憺のひとつが量子力学をヒントにした説明。
観測されている時と観測されてない時とでは量子の動きが違う。
観測されてない時は全く予測外動きをしているという事を例に、事実として新しい論理学の存在を示唆している。
(注:まぁ、人間の思考回路も定説とか、教科書とか、メディアとか、こうなっているんだから仕方ないとかいうあきらめ、もう絶体絶命だなどというあきらめ、そんなことにとらわれてはいけないという事を言いたいのだろうね、羽仁五郎は。そして、もっともっと斬新な発見を、論理の発見をしていけという、実践の論理なんだろうと思う)
日常会話言語的に言えば、「歴史には間違い(予想外)が起こる。」という言葉を羽仁五郎は使っている。
(注:歴史そのものが生きののように、非線形な歴史を生み出すという発見をしたのでしょうね。)
科学者の言葉でこれ(量子力学の世界)を読み解くと、湯川秀樹はこういっている。 ニュートン力学というのはドグマ。湯川秀樹が言っているように理論のほころびがわからなくなってしまっているもの。 (物理法則:http://
*−−−−−引用開始−−−−−−−−*
湯川秀樹は、ニュートン力学は適用範囲が広かったことに言及しつつ、だからドグマになっても不思議ではなかったのだ、と述べている[4]。つまり、適用範囲が広くて、かつそれ自体で閉じているような理論体系を学習・習得すると、学習者は思考がその理論体系に沿ってしか動かなくなり、世界を見ても世界自体を見ることなく、自己完結した理論体系や用語へと変換するだけなので、理論のほころびがわからなくなり、あたかも世界が理論に沿って全てが動いているようにしか感じられなくなってしまう、ということである。
[4]^ a b 湯川秀樹 『物理講義』 講談社〈講談社学術文庫〉、1977年、21-22頁。
ISBN 4-06-158195-3。
*−−−−−引用終了−−−−−−−−*
基本的に科学といってもこういうものです。
こういう科学者もいる。
【電子のレベルでは、因果律の働く余地が全くない。「量子力学のパラドックス(ジレンマ、真と偽の混在)について。」】
※【参考情報】
(出典:「理性のゆらぎ」 青山圭秀著 P.180〜P.182 )
*−−−引用開始−−−*
たとえば、物質を構成する原子は、中心に原子核があり、その周りを電子が回っているものと考えられた時期があった。今でも、中学や高校の教科書には、そうか書いてある。とすれば、ある時点における電子の位置(q)という運動量(p、質量×速度)は、古典力学、すなわち因果律にしたがって一意に定まることになる。
しかし、そのような電子の“軌道”というものは、実際には存在しないのである。量子力学の教えるところによれば、ある時、ある電子がどこにいるのかは、測定した瞬間に確定するのであるが、その結果は純粋に確率的に決まる。多回数の観測を行った場合の傾向は分かっても、一度の観測でどういう結果が得られるかは、全くの偶然による。その結果に対応する原因は、「分からない」のではなく、「ない」のである。ある時、ある電子がどういう運動量を持つのかも同様に、純粋に確率的に、偶然決まる。そこには、因果律の働く余地が全くないと考えられているのである。
この思想を推し進めていくと、われわれが物理的に「実在」していると思っているものも、実は全て、本質的にあやふやな存在であることになる。この世界には、およそ知りうる本質的に確定したものは、何一つない。何事も、どこまでも、確率的事象であり、確率的存在であることとなる。
量子論のこの思想は、われわれの直観からは到底受け入れ難いものである。しかし今日、科学者たちがこれを認めざるを得ないのはなぜか。それは、これによって、自然の現象をより単純に、整合的に説明できるからである。もともと、因果律も、われわれの経験を説明するための産物である。経験の質と量が増せば、常識もまた、変更される。しかし、ここまで来ればだれにも明らかなように、これで本当に正しい常識が得られたのかどうかなど、実はどこまで行っても分からないのである。
覆る常識は、因果律に限らない。われわれの科学を支えるもう一つの柱、「観測」もそうである。
われわれは、ものごとをありのまま観測し、そこから客観的データを得ていると、何世紀にもわたって思い続けてきた。まさにそれこそが科学の基盤であり、科学を科学たらしめるもののはずであった。ところが、やはり今世紀に入ってから、われわれの観測はつねにある「ゆらぎ」がつきまとうことがはっきりと認識される。
現在成功を収めている量子力学の基本方程式は、対象にある観測を行ったときに、その対象の状態が変わり、それを含んだある観測値が得られる、という形をしている。つまり、われわれが何かを観測しようと思ったとき、観測されたものはすでに状態を変えている、ということである。
ある粒子の位置を確かめようとすれば、運動量が決まらない。運動量を測定しようとすれば、今度は位置が決まらなくなる。Δq・Δp≧h/4πという一遍の不等式で表されるこのゆらぎは、人間の物理的認識において根本的に避けがたい要素と考えられている(不確定性原理:Uncertainty principle)。
さらに、その観測を行う装置や、当の観測者自身はどういう法則に従うのかという問題も生じる。観測対象が不確定性に従うことはいいとして(よくはないが、仕方がないとして)、ではそれを観測する装置や観測者自身は、確定した何かなのだろうか。しかし、観測装置は明らかに量子力学に従うだろうし、観測者である人間も、これを物体と考えるなら、その個々の構成粒子は量子力学に従い、不確定なもののはずである。そうすると、それらの間で行われている観測という行為が、何かしら意味のあるものだという保証は、どこにあるのだろうか。
この問題を解決するために、たとえばノイマンという天才数学者(アメリカ)は、量子力学から独立した、つまり、物理法則によらない、観測者の「自意識」というものを想定した。あらゆる観測を行う主体は、結局、この自意識だというのである。(J.von Neumann 『 Mathematische Grundlangen der Quantenmechanik 邦訳:量子力学の数学的基礎 みすず書房』)。
なるほど、そう考えればことは収まるし、また、そのように考えざるを得ないようにも見える。ところが、この想定は、一つの大きな犠牲をわれわれに強いることとなる。なぜなら、もともと物理学には、この世界の実在を、全て物質とその相互作用とに帰着させようという大前提があったはずだからである。その物質をとことんつきつめていくと量子力学という理論につき当たり、その挙げ句われわれは、この巨大な思想を完結させるために、非物理的実体を想定せざるを得ないというパラドックスに陥る。
実は、量子力学にはこのような根本的なパラドックスがいくつかあり、それらの解決はついていない。量子力学が本当に「完結」するのか、さらに一般相対性理論というもう一方の大理論と折り合いがつくのかどうかも、大いに疑わしい。
そもそも、この世界を記述する際に、それを物理的側面からのみで完結させることができるなどという保証は、どこにもないのである。
以上のような人間理性の本質とも関連して、イギリスの天才物理学者ホーキングは、次のように語る。
「もし、完全な統一理論が本当に存在するとすれば、それはわれわれの行為をも決定しているだろう。これはつまり、この理論をわれわれが探究することによって得るであろう結果も、この理論自身によって決定されているということだ。しかし、われわれが証拠から出発して正しい結論を引出すことをこの理論が決定づけていると、どうして言えるのか?われわれが誤った結論を引出すと結論づけられていても、不思議ではないのではなかろうか?ひょっとして、そもそも結論になどたどりつきさえしないようになっているのではないのか?」(S.W.ホーキング 『A BRIEF HISTORY OF TIME 邦訳:ホーキング宇宙を語る 早川書房』)
*−−−引用終了−−−*
リーフ注:パラドックス:「パラドックス(paradox)とは、ギリシャ語で「矛盾」「逆説」「ジレンマ」を意味する言葉。 数学・哲学の分野では「一見間違っていそうだが正しい説」もしくは「一見正しく見えるが正しいと認められない説」等を指して用いられる。」
(出典:パラドックスとは (パラドックスとは) [単語記事] - ニコニコ大百科 http://
量子力学、不確定性原理、ヴェーダの世界までいくと形而上学的な世界の話と科学的な物理学の話の境界線があたかもなくなるような・・・。
ただ、ここで注目しておきたいのは、青山さんの「 しかし、そのような電子の“軌道”というものは、実際には存在しないのである。量子力学の教えるところによれば、ある時、ある電子がどこにいるのかは、測定した瞬間に確定するのであるが、その結果は純粋に確率的に決まる。多回数の観測を行った場合の傾向は分かっても、一度の観測でどういう結果が得られるかは、全くの偶然による。その結果に対応する原因は、「分からない」のではなく、「ない」のである。ある時、ある電子がどういう運動量を持つのかも同様に、純粋に確率的に、偶然決まる。そこには、因果律の働く余地が全くないと考えられているのである。 」
の部分である。おそらく、羽仁五郎のいいたいこともここにある。
この決まってないのではなくって「ない」のであるというのは、価値の世界と似ていはしないか。情緒的価値判断から情緒的価値判断の演繹を現代のわれわれ日本人は日常会話言語においても、政治家の答弁や裁判官の判決文においても嫌というほどきかされる。あたかもそれが論理的推論で正しいかのように。
【4】「決まってない」のではなくて「ない」のは、価値の世界もまた似ている。
(注:これは、ファシズムに騙されない思考回路と直結している脳みその武器である。理論武装である。)
【事実と価値の二元論】について
学校教育は無論の事、例の教育勅語も情緒的価値判断の塊だ。
しかし、本来、情緒的価値判断は、情緒的価値判断から無限にどんな方向にも演繹できるものなのだ。
言葉の意味の本質的意味定義もそうだ。
どんな目的で、どういう視点を選択したかでどうにでもいえるのだ。それが価値。
我々の脳みそは、この情緒的価値判断から情緒的価値判断を無限にチェーンできる。
学問的には、価値二元論が、戦後英米倫理学会において、どうしてナチスのようなファシズムに人々が騙されていったのかを研究した結果としてクローズアップされた。
【注:価値二元論そのものは自然主義ファラシー(ファラシー:誤謬)という形で二十世紀初頭に一大革新をもたらしている。遡れば18世紀のヒュームやカントも論じている。二十世紀初頭にイギリスのG・E・ムーアとドイツのマックス・ヴェーバーが自然主義(価値一元論)批判(自然主義ファラシー)。】
その真髄は、「価値」と「事実」は二元であるということだ。
「事実」からいかなる「価値」も論理的推論で演繹できず、
「価値」から「事実」も論理的推論で演繹できない。
言い換えれば、いかなる「価値」も「事実」に還元できず、
いかなる「事実」も「価値」に還元できない。
価値の演繹を、「道徳教科書」も、「修身教科書」も、「教育勅語」もくりかえすが、これでもかこれでもかと繰り返し洗脳するが、しかし、価値から価値はどんなに論理をならべても、アリストテレスの三段論法では無限にバリエーションをもって無限につながり、しかし、どんなに時間とエネルギーを費やし
ても、国家権力で強制的に洗脳して、学問の真理として絶対に、「事実」からいかなる「価値」も演繹できず、いかなる「価値」からもいかなる「事実」も演繹できない。例えばこれは、天皇が天孫降臨の子孫だという虚構を事実として敷衍するがわにとっても、象徴天皇の権威という「価値」を何らかの「事実」に還元しようとしたり、虚構の事実(ウソ、神話)に還元しようとする天皇制にとってはこれほど不都合なものはないのではないだろうか。
天皇制ばかりではない、あらゆる権威にとって、あるいはあらゆる権力にとって、価値二元論の存在は、脅威である。
(注:権力を持つものは全て脅威だ。親でも、学校の教師でも、裁判官でも、国家でも。)
日本人民の脳みそが価値二元論を当たり前のこととして認識するようになれば、
再び三度ファシズムの洗脳におかされる危険は極めて低くなるのではないだろうか。
その意味でナチスに迫害された学者による価値二元論への到達は極めて価値のあるものではないだろうか。
この価値二元論に即した本で
「思考と行動における言語」 S.I.ハヤカワ著がある。https:/
もし学問的に読みたいなら碧海純一の「法哲学概説」の中の「自然主義ファラシー」が学問的解説だと思います。この本は全訂第二版補正版が出てますがこれではなて全訂第一版の方がはるかに優れている。全訂第一版は碧海純一が(師弟関係の師からの圧力と思うが)取っ払った「社会統制論」がある。
いずれにせよ、我が国人民は「価値」と「事実」が分かってない。
(注;そのために脳において足枷がつけられているに等しい。「論理という資源」が解放されない大きな要因である。
社会契約というような約束定義というものも、ピンとこない大きな原因である。
例えば、国家が人民が作った、という約束定義を聞いても、それが約束定義だと断っても、ほんとかどうか知らないが中学校の元教師という人さえ、ネットで、国家は弱肉強食でできたものだと言ってくる。
頭に約束定義の意味がからっきし、ヒットしない。その様な親や教師に教育されてればなおさら子供の頭にはヒットしないだろう。)
【5】約束定義の威力
これは、我が国人民が「価値」と「事実」の実相が分かってないということは、
約束定義というものを血肉化できない大きな原因の一つだと思うのです。
「国家は人民が作った」という約束定義を根幹とすることに(対して)、国家は弱肉強食で強いものが作ったのだという主張を多くに日本人民は信じている。(そして、首をひねる。)
「『国家は人民が作った』という事にしよう、これを根幹に置かなければ、人民の自然権(価値)を守れない。人民の自然権を守る社会科学を構築できない」ということが頭にヒットしないようだ。
なぜ、近代社会契約の国家の約束定義を作ったかが理解しづらいようだ。
*−−−−−−注;開始−−−−−−*
もう少し詳しく言えば、近代社会契約の国家の約束定義「国家は人民が作った。人民の自然権を守る為に人民が国家を作った」を詳しく言えば、
(1)一人一人の個人の自然権を個人では守れない。しかし、強大な国家権力を持つ国家なら個人の自然権を守ることができる。そのために人民が、国家を作った。そして、強大な国家権力を国家を信じて託した。
(2)しかし、国家が強大な国家権力を濫用して人民の自然権を棄損したら目も当てられれない。防ぐ方法がない。だから、人民は、近代憲法を作って、国家に「絶対にこの憲法を守って信じて託された国家権力を使わせていただきます」という誓約(立憲主義)をして、国家権力を信託された。国家権力の信託と、立憲主義という誓約は、一体のもの。
(3)ゆえにもし、国家権力が安倍晋三の様に立憲主義を破棄したり、国家の目的である人民の自然権を棄損したら、もはやそのような国家権力は国家権力の資格がない。リセットしなければならないものであるということだ。ここに抵抗権も革命権もある。初めから人民にある。
(4)人民主権というのは、国家を作った人民に、政治を最終的に決定する権利があるということ。人民 vs 国家 という構図において、国家に主権はない。
主権は100%人民にある。
(5)近代democracyのdemocracyの語源は、デーモス(民衆)によるクラトス(支配:権力)であり、これは、近代社会契約の国家の約束定義に合致しており、
また、人民主権と同義のものだ。
多数決=近代democracyではない。多数決は、democracyを実現する可能性のある一つのツール(道具)に過ぎない。ファシズム(=三権の癒着)でも多数決を使う。
今の日本がそうだ。間接民主制(議会制民主主義と命名しようが)これは、多数決の一種でありそれがdemocracyのことではない。
*−−−−−−注;終了−−−−−−*
約束定義をしたこと、約束定義を受け入れたことで、すなわち社会契約したことで、根幹に置くことで、近代democracyはなりたっている。近代憲法も、近代立憲主義も、人民主権もなりたっている。導出され、連関している。
【6】天賦人権について
片山さつきらが国民に主権なんかあるわけないじゃないかとか、天賦人権なんかあるわけないじゃないか、人権なんか国家が法律(憲法も大きくは法律)に書いて初めて与えられるものだとか、いうのに対して、一般国民は、天賦人権はあるという。
(※天賦人権が実在するというのは論理的推論において正しいか間違っているかという正誤の問題になってしまっている点に注意すべきだ。)
これは自然権なんかあるわけないじゃないかという主張に対して、自然権は事実としてあるという論争に似ている。
しかし、事実と価値の二元論に即していえば、自然権も、基本的人権も、価値なのだ。
事実から演繹できない価値なのだ。事実に還元できない価値なのだ。
しかし、自然権という価値を、あるいは人権という価値を、人間には、あるものと認めましょう、という約束定義という立場で根幹に置いたならどうか。
この約束定義として、自然権というものが人間にはあるものと認めましょうというのが、近代社会契約の国家の約束定義でもあるのだ。
(そういう約束定義なしで)
事実として自然権が人間には先験的にア・プリオリにこの世の出現以前からあるというような主張をするならこれは価値一元論(=自然主義)だ。
王権神授説など典型的な自然主義だ。
原点としての価値を置きそこから論理的推論で演繹する。
あるいは原点としての事実を置きその事実から価値を演繹してく。
天孫降臨族の天皇制、天皇主権も典型的な価値一元論であり自然主義だ。
では、自然法を説く法哲学者は皆自然主義者か?ちがう。ラートブルフは、私は自然法に帰依するといった。
帰依=正しいと信じる=価値としてみとめて、その価値を正しいものとして受け入れる。
事実であるかないかではなく。帰依し、その価値を根源に置くことで、そこから社会科学を発展させていく手法は価値二元論と矛盾しない。
(※ラートブルフは正誤問題として自然法の実在を問うという事はあっさりパスして帰依するという約束定義で、そこから自然法に基づく社会科学の構築をしているということだ)
(続く:http://
|
|
|
|
|
|
|
|
羽仁五郎 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
羽仁五郎のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人