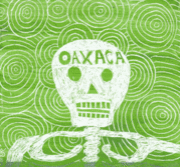開催終了メキシコ文化研究会 2007年連続講演会@メキシコシティ
詳細
2007年09月15日 15:02 更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
メキシコ文化研究会 2007年連続講演会
「メキシコ文化とは何かを考える 〜二つの文化的ルーツと風土〜」 のお知らせ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
この度、下記の要領で連続講演会をさせて頂くことになりました。
興味のある方は是非ご参加下さい。
このお知らせメール以外に、下記インターネットサイト
http://
にて、随時講演会についての情報や、詳細、お知らせなどを更新しています。
また、このインターネットサイトから、内容が更新されるとメールで自動的に更
新内容をメールで受け取ることができる「メール配信」サービスへの登録もで
きます。特に講演会期間中、メキシコ文化研究会からの臨時のお知らせなど
もこちらから配信させていただく予定にしております。登録、解除の方法も簡単
ですので、是非あわせてご利用下さい。
それでは、皆様の多数の参加をお待ちしております。
メキシコ文化研究会
-------------------------------------------------------------------
メキシコ文化研究会 2007年連続講演会
「メキシコ文化とは何かを考える 〜二つの文化的ルーツと風土〜」
【会場】
在メキシコ日本大使館 別館 (領事部 文化広報センター)
Reforma No.295, Piso 3, Col. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
【日程】
■朝の部 10:30分 開始
講演 約1時間 + ミニパネルディスカッション&質問タイム 約30分
■夜の部 19:00分 開始
講演 約1時間 + 質問タイム 10分程度
■講演は輪番制で、異なった日程の夜の部と朝の部に、同じ内容が話されます。講演日にご注意下さい。
■残念ながら、夜の部は時間の都合上、ミニパネルや質問タイムに十分な時間が取れません。予めご了承下さい。
【持ち物】
■必要な方は筆記具。
■建物入館の際に必要となる場合があるかもしれませんので、心配な方は念のために身分証明証をご持参下さい。(入り口で「A la conferencia」というと、身分証明証を提出せずに通しても
らえる場合があります。)
【参加料】
参加無料です。お気軽にご来場下さい。
【プログラム】
■ 開会式 朝の部 9月25日(火) 10:30
1.開会の挨拶
2.各講演紹介
3.「メキシコ文化とは何かを考える 〜二つの文化的ルーツと風土〜」 (イントロダクション)
楠原生雄 (メキシコ国立自治大学大学院 建築学専攻 博士課程)
今年の講演会では、各講演者の講演テーマに重ねて、講演会全体を通じて「メキシコ文化とは何かを考える〜二つの文化的ルーツと風土〜」というテーマに目を向けてみたいと考えています。開会式に際してイントロとして、どのような考えでこのテーマを設定したのかお話しし、またその問題意識を持つようになった背景にはどのようなメキシコ文化の事象があるのかについて、二つのルーツの文化的折衷あるいは文化的混血とでも呼べる例や、古代・植民地時代・現代を通じて継承されてきたと考えられる土着文化の例などを羅列的に紹介してみたいと思います。様々な分野からメキシコの様々な時代・地域を扱う各講演を聴いていただく前に、一つの視点を提供するガイドのようなものとして聴いていただきたいと思います。
■ 第1回
夜の部 9月25日(火) 19:00、 朝の部 10月9日(火) 10:30
「国際都市テオティワカン 〜庶民の生活と都市を支えるインフラ〜」
福原弘識 (愛知県立大学大学院 国際文化研究科 博士後期過程)
テオティワカンは、南北に走る「死者の大通り」に沿ってピラミッドなどが整然と並び、きちんと計画性を持って築かれた都市です。大型のピラミッドは初期段階から作られ始めましたが、庶民の住居は西暦四百年頃になって次々に作られていきました。彼らの住居は、他の地域ではあまり見られない集合型住宅で、整然と整備された区画とインフラの網の目の上に建設されています。また、テオティワカンにはメソアメリカ各地からやってきた「他民族」たちもテオティワカン人とともに暮らしており、まさにメキシコ・シティのような国際都市でもありました。この講演会では、意外に知られていない住居地区と、国際色あふれる庶民の生活を中心にご紹介したいと思います。
■ 第2回
夜の部 10月9日(火) 19:00、朝の部 10月23日(火) 10:30
「テオティワカンの住居−居住空間から見える住人の生活」
古賀優子(愛知県立大学大学院 国際文化研究科 博士後期課程)
テオティワカンは都市内外に10万人〜15万人を抱える大都市でした。住民の生活の場、活動の場は、社会階級により、都市中心部の宮殿、「アパートメント住居」と呼ばれる60mx60mの平屋建ての複合住居、周縁部に存在した、土を固めた床の住居と形態が異なりました。テオティワカンの住居とはどのような空間だったのか、そこではどのような活動が行なわれていたのか、何を食べていたのか、建築・壁画・考古学データから見える、当時の住人の営みをご紹介します。
■ 第3回
夜の部 10月23日(火) 19:00、朝の部 11月6日(火) 10:30
「サアチラ王朝史 〜モンテ・アルバン衰退後のサポテカ文化〜」
池田和歌子 (メキシコ国立自治大学大学院 哲文学部 メソアメリカ学専攻 修士課程)
多くの黄金製品が出土したことでも有名なオアハカ州のモンテ・アルバン遺跡は、紀元前500年頃から約1300年間の長きにわたり、サポテカ人のサポテカ文化の中心地として機能していました。しかし、モンテ・アルバン衰退後のサポテカ文化については、まだまだわかっていないことが多くあります。一般に、多くの書籍では「モンテ・アルバンの衰退後、オアハカ地域の西側にいたミステカ人の侵入を受けた」と説明されています。それでは、その後のサポテカ人たちは一体どうなってしまったのでしょうか?モンテ・アルバン衰退後に力を持ったサポテカの都市、サアチラの王朝史とその政治的活動について、絵文書や古文書を用いながら皆さんに御紹介したいと思います。
■ 第4回
夜の部 11月6日(火) 19:00、朝の部 11月20日(火) 10:30
「土器を拾って歩こう 〜発掘調査とは別の考古学調査方法から〜」
黒崎充 (メキシコ国立自治大学 哲文学部 人類学調査研究所 博士課程)
発掘を中心とする考古学研究法以外に、メソアメリカの考古学研究では、まずその前提となる遺跡の把握と測量調査、そして組織化された表面採集資料の調査があります。この発表では、いろいろな制約によって発掘調査の実施が難しい中で、いかにして研究をすすめていくかということに触れてみたいと思います。
これによって外に出て、遺跡を探しに出てみようという気持ちになっていただければうれしいなあと思っています。
■ 第5回
夜の部 11月20日(火) 19:00、朝の部 12月4日(火) 10:30
「ミステカ・アルタ 〜文明形成期の日常生活風景〜」
松原信之 (メキシコ国立人類学歴史学大学 考古学部)
メキシコの古代文明!!と聞くとマヤやアステカ、テオティワカン遺跡などを思い浮かべる方は少なくないと思います。また、これらの遺跡を実際に訪れ古代への妄想にふけった事がある方も少なくはないのではないでしょうか。しかしながらメキシコを代表するこれらの文明は突如として現れたのではありません。メキシコにおいて農耕を中心とする定住生活がようやく安定してゆくのは紀元前1500年頃。これ以降、メキシコ湾岸のオルメカ文化やモンテ・アルバンのサポテカ文化等の発展した社会形態が進んでゆき、メソアメリカという一つの大きな流れが少しずつ形成されてゆく時代になります。
しかしながらその当時の大部分の人々はまだまだ小村落に小さな住居を作り、家族を一つの単位とするさほど社会格差のない生活をしていました。今回の発表ではこれらの普段はあまり表舞台に立たない人達の、小さな小さな日常生活を実際の発掘の話と共に皆さんと垣間見て行ければと思います。当時の人々はどんな暮らしをしていたのでしょうか? どんな家に住み、どういう習慣を持ち、どんな食生活をしていたのでしょうか? 文明は一日にして成らず、です。
■ 第6回
夜の部 12月4日(火)19:00、朝の部 1月15日(火) 10:30
「雨季と乾季の気象学、そして気候はどのように建築の形成に影響するのか」
楠原生雄 (メキシコ国立自治大学大学院 建築学専攻 博士課程)
伝統文化の形成には土地の気候風土が大きな要因となりますが、では気候とは一体何かと考えた時、メキシコになぜ雨季と乾季があるのかさえ知らない人は多いと思います。そこでまず私たちが知っているメキシコの気候がどのように形成されているのかを気象学的に説明し、それがメキシコ文化の形成にどう影響してきたのかを簡単に考察します。その上で、では気候の違いはいったい民家や伝統建築の形成にどのような形で表れるのかについて、メキシコを支配する熱帯・乾燥帯・温帯という3つの典型的な条件下で住居建築がどの様に快適性を確保しようとしてきたのかを例にとって説明したいと思います。
■ 第7回
夜の部 1月15日(火) 19:00、朝の部 1月29日(火) 10:30
「タラウマラの先住民集落 〜現代に生きる先住民文化〜」
上西和美 (メキシコ国立人類学歴史学大学 民族学部)
メキシコ北部チワワ太平洋鉄道が走るシエラ・マドレ山脈に住むタラウマラ族たち。彼らはソノラ州のジャキ族と並んで、北部メキシコを代表する先住民族です。厳しい風土条件によって外界から隔離されてきた彼らは、近代化の進む現代社会の影響を受けつつも、太古からの風習を守り続けているといわれています。しかしその風習も、先スペイン期文化がそのまま現代まで残ってきているわけではなく、植民地時代にはカトリック宣教師達によってスペイン文化の影響を受け、元来の農業形態、宗教儀式、生活習慣などが複雑に変化したりスペイン文化と結合されてきたものなのです。
今回は、そんなタラウマラ族とは一体どんな人たちなのか、人類学者の調査方法とはどんなものなのかを、誇り高き彼らの生活や世界観が覗けるビデオ映像と共にご紹介したいと思います。
■ 第8回
夜の部 1月29日(火) 19:00、朝の部 2月12日(火) 10:30
「16世紀修道院の建築計画における古代文化の影響」
喜多裕子 (筑波大学大学院 人間総合科学研究科 世界文化遺産学専攻 博士課程。2007年4月〜2008年3月:メキシコ国立保存修復博物館学大学大学院 建築学研究科 不動産文化遺産保存修復専攻 研究滞
在)
メキシコの植民地期(1521〜1821年)の建築は、スペイン文化と先住民文化との融合の歴史を担っています。植民地期建築における先住民文化の影響に関して、建築彫刻や壁画などに見られる図像、建造物の配置などの建築計画といった視点から、60年代半ばから70年代にわたって、欧米・ラテンアメリカを中心に、さまざまな論争が繰り広げられました。
植民地化直後の16世紀の建造物には、異文化の融合が何かしらの「形」として表出されています。その中でも特に、先住民の改宗を目的として建てられた数多くの修道院には、修道院建築というスペイン文化の器の中に、意図的に先住民文化の要素がとりこまれています。
16世紀の修道院の建築要素をとりあげ、その空間的特徴と機能から、二つの文化がどのように混合されていったのかをお話したいと思います。
■ 第9回
夜の部 2月12日(火) 19:00、朝の部 2月26日(火) 10:30
「16世紀テキキ美術における先スペイン期図像の残存」
柳澤佐永子 (メキシコ国立自治大学大学院 哲文学部 美術史専攻 博士課程)
メキシコ各地でみられる教会。ヨーロッパで見る教会とどこか少し違うと感じる人が多いと思います。これらメキシコの教会の魅力は、やはりそこにみられるメソアメリカ美術の影響ではないでしょうか。特に、スペイン人による征服直後の16世紀に建てられた教会には、先スペイン期に使われていたモチーフがそのまま使われているものも多く、それはテキキ美術と呼ばれています。では、そのテキキ美術のモチーフとは一体どのようなものなのでしょうか。今回の発表ではその具体例をお見せしようと思います。
■ 第10回
夜の部 2月26日(火) 19:00、朝の部 3月11日(火) 10:30
「教会の聖人像を『読む』」
渡辺裕木 (メキシコ文化財保存修復士)
カトリック教会には、多くの聖人像や絵画が飾られています。一見どれも同じように見える聖人も、それぞれが所属していた修道会の服を身に付け、生き様を象徴する物を携えています。そこを読み解けば、聖人の名前を『見分ける』ことができ、また、何千といるカトリック聖人の中で、メキシコの教会で見る聖人はある程度限られていることも見えてきます。宗教美術に馴染みの薄い方なら誰もが疑問に思う幾つかの宗教的なモチーフの説明と合わせて、教会の聖人をいかに見分けるかというお話をします。名前や逸話を知る聖人の像を探すことが、メキシコ文化に触れるみなさんのもう一つの楽しみになれば幸いです。
■ 閉会式
夜の部 3月11日(火) 19:00
パネル・ディスカッション
皆様の多数のご参加をお待ちしております!!!
メキシコ文化研究会
メキシコ文化研究会 2007年連続講演会
「メキシコ文化とは何かを考える 〜二つの文化的ルーツと風土〜」 のお知らせ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
この度、下記の要領で連続講演会をさせて頂くことになりました。
興味のある方は是非ご参加下さい。
このお知らせメール以外に、下記インターネットサイト
http://
にて、随時講演会についての情報や、詳細、お知らせなどを更新しています。
また、このインターネットサイトから、内容が更新されるとメールで自動的に更
新内容をメールで受け取ることができる「メール配信」サービスへの登録もで
きます。特に講演会期間中、メキシコ文化研究会からの臨時のお知らせなど
もこちらから配信させていただく予定にしております。登録、解除の方法も簡単
ですので、是非あわせてご利用下さい。
それでは、皆様の多数の参加をお待ちしております。
メキシコ文化研究会
-------------------------------------------------------------------
メキシコ文化研究会 2007年連続講演会
「メキシコ文化とは何かを考える 〜二つの文化的ルーツと風土〜」
【会場】
在メキシコ日本大使館 別館 (領事部 文化広報センター)
Reforma No.295, Piso 3, Col. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
【日程】
■朝の部 10:30分 開始
講演 約1時間 + ミニパネルディスカッション&質問タイム 約30分
■夜の部 19:00分 開始
講演 約1時間 + 質問タイム 10分程度
■講演は輪番制で、異なった日程の夜の部と朝の部に、同じ内容が話されます。講演日にご注意下さい。
■残念ながら、夜の部は時間の都合上、ミニパネルや質問タイムに十分な時間が取れません。予めご了承下さい。
【持ち物】
■必要な方は筆記具。
■建物入館の際に必要となる場合があるかもしれませんので、心配な方は念のために身分証明証をご持参下さい。(入り口で「A la conferencia」というと、身分証明証を提出せずに通しても
らえる場合があります。)
【参加料】
参加無料です。お気軽にご来場下さい。
【プログラム】
■ 開会式 朝の部 9月25日(火) 10:30
1.開会の挨拶
2.各講演紹介
3.「メキシコ文化とは何かを考える 〜二つの文化的ルーツと風土〜」 (イントロダクション)
楠原生雄 (メキシコ国立自治大学大学院 建築学専攻 博士課程)
今年の講演会では、各講演者の講演テーマに重ねて、講演会全体を通じて「メキシコ文化とは何かを考える〜二つの文化的ルーツと風土〜」というテーマに目を向けてみたいと考えています。開会式に際してイントロとして、どのような考えでこのテーマを設定したのかお話しし、またその問題意識を持つようになった背景にはどのようなメキシコ文化の事象があるのかについて、二つのルーツの文化的折衷あるいは文化的混血とでも呼べる例や、古代・植民地時代・現代を通じて継承されてきたと考えられる土着文化の例などを羅列的に紹介してみたいと思います。様々な分野からメキシコの様々な時代・地域を扱う各講演を聴いていただく前に、一つの視点を提供するガイドのようなものとして聴いていただきたいと思います。
■ 第1回
夜の部 9月25日(火) 19:00、 朝の部 10月9日(火) 10:30
「国際都市テオティワカン 〜庶民の生活と都市を支えるインフラ〜」
福原弘識 (愛知県立大学大学院 国際文化研究科 博士後期過程)
テオティワカンは、南北に走る「死者の大通り」に沿ってピラミッドなどが整然と並び、きちんと計画性を持って築かれた都市です。大型のピラミッドは初期段階から作られ始めましたが、庶民の住居は西暦四百年頃になって次々に作られていきました。彼らの住居は、他の地域ではあまり見られない集合型住宅で、整然と整備された区画とインフラの網の目の上に建設されています。また、テオティワカンにはメソアメリカ各地からやってきた「他民族」たちもテオティワカン人とともに暮らしており、まさにメキシコ・シティのような国際都市でもありました。この講演会では、意外に知られていない住居地区と、国際色あふれる庶民の生活を中心にご紹介したいと思います。
■ 第2回
夜の部 10月9日(火) 19:00、朝の部 10月23日(火) 10:30
「テオティワカンの住居−居住空間から見える住人の生活」
古賀優子(愛知県立大学大学院 国際文化研究科 博士後期課程)
テオティワカンは都市内外に10万人〜15万人を抱える大都市でした。住民の生活の場、活動の場は、社会階級により、都市中心部の宮殿、「アパートメント住居」と呼ばれる60mx60mの平屋建ての複合住居、周縁部に存在した、土を固めた床の住居と形態が異なりました。テオティワカンの住居とはどのような空間だったのか、そこではどのような活動が行なわれていたのか、何を食べていたのか、建築・壁画・考古学データから見える、当時の住人の営みをご紹介します。
■ 第3回
夜の部 10月23日(火) 19:00、朝の部 11月6日(火) 10:30
「サアチラ王朝史 〜モンテ・アルバン衰退後のサポテカ文化〜」
池田和歌子 (メキシコ国立自治大学大学院 哲文学部 メソアメリカ学専攻 修士課程)
多くの黄金製品が出土したことでも有名なオアハカ州のモンテ・アルバン遺跡は、紀元前500年頃から約1300年間の長きにわたり、サポテカ人のサポテカ文化の中心地として機能していました。しかし、モンテ・アルバン衰退後のサポテカ文化については、まだまだわかっていないことが多くあります。一般に、多くの書籍では「モンテ・アルバンの衰退後、オアハカ地域の西側にいたミステカ人の侵入を受けた」と説明されています。それでは、その後のサポテカ人たちは一体どうなってしまったのでしょうか?モンテ・アルバン衰退後に力を持ったサポテカの都市、サアチラの王朝史とその政治的活動について、絵文書や古文書を用いながら皆さんに御紹介したいと思います。
■ 第4回
夜の部 11月6日(火) 19:00、朝の部 11月20日(火) 10:30
「土器を拾って歩こう 〜発掘調査とは別の考古学調査方法から〜」
黒崎充 (メキシコ国立自治大学 哲文学部 人類学調査研究所 博士課程)
発掘を中心とする考古学研究法以外に、メソアメリカの考古学研究では、まずその前提となる遺跡の把握と測量調査、そして組織化された表面採集資料の調査があります。この発表では、いろいろな制約によって発掘調査の実施が難しい中で、いかにして研究をすすめていくかということに触れてみたいと思います。
これによって外に出て、遺跡を探しに出てみようという気持ちになっていただければうれしいなあと思っています。
■ 第5回
夜の部 11月20日(火) 19:00、朝の部 12月4日(火) 10:30
「ミステカ・アルタ 〜文明形成期の日常生活風景〜」
松原信之 (メキシコ国立人類学歴史学大学 考古学部)
メキシコの古代文明!!と聞くとマヤやアステカ、テオティワカン遺跡などを思い浮かべる方は少なくないと思います。また、これらの遺跡を実際に訪れ古代への妄想にふけった事がある方も少なくはないのではないでしょうか。しかしながらメキシコを代表するこれらの文明は突如として現れたのではありません。メキシコにおいて農耕を中心とする定住生活がようやく安定してゆくのは紀元前1500年頃。これ以降、メキシコ湾岸のオルメカ文化やモンテ・アルバンのサポテカ文化等の発展した社会形態が進んでゆき、メソアメリカという一つの大きな流れが少しずつ形成されてゆく時代になります。
しかしながらその当時の大部分の人々はまだまだ小村落に小さな住居を作り、家族を一つの単位とするさほど社会格差のない生活をしていました。今回の発表ではこれらの普段はあまり表舞台に立たない人達の、小さな小さな日常生活を実際の発掘の話と共に皆さんと垣間見て行ければと思います。当時の人々はどんな暮らしをしていたのでしょうか? どんな家に住み、どういう習慣を持ち、どんな食生活をしていたのでしょうか? 文明は一日にして成らず、です。
■ 第6回
夜の部 12月4日(火)19:00、朝の部 1月15日(火) 10:30
「雨季と乾季の気象学、そして気候はどのように建築の形成に影響するのか」
楠原生雄 (メキシコ国立自治大学大学院 建築学専攻 博士課程)
伝統文化の形成には土地の気候風土が大きな要因となりますが、では気候とは一体何かと考えた時、メキシコになぜ雨季と乾季があるのかさえ知らない人は多いと思います。そこでまず私たちが知っているメキシコの気候がどのように形成されているのかを気象学的に説明し、それがメキシコ文化の形成にどう影響してきたのかを簡単に考察します。その上で、では気候の違いはいったい民家や伝統建築の形成にどのような形で表れるのかについて、メキシコを支配する熱帯・乾燥帯・温帯という3つの典型的な条件下で住居建築がどの様に快適性を確保しようとしてきたのかを例にとって説明したいと思います。
■ 第7回
夜の部 1月15日(火) 19:00、朝の部 1月29日(火) 10:30
「タラウマラの先住民集落 〜現代に生きる先住民文化〜」
上西和美 (メキシコ国立人類学歴史学大学 民族学部)
メキシコ北部チワワ太平洋鉄道が走るシエラ・マドレ山脈に住むタラウマラ族たち。彼らはソノラ州のジャキ族と並んで、北部メキシコを代表する先住民族です。厳しい風土条件によって外界から隔離されてきた彼らは、近代化の進む現代社会の影響を受けつつも、太古からの風習を守り続けているといわれています。しかしその風習も、先スペイン期文化がそのまま現代まで残ってきているわけではなく、植民地時代にはカトリック宣教師達によってスペイン文化の影響を受け、元来の農業形態、宗教儀式、生活習慣などが複雑に変化したりスペイン文化と結合されてきたものなのです。
今回は、そんなタラウマラ族とは一体どんな人たちなのか、人類学者の調査方法とはどんなものなのかを、誇り高き彼らの生活や世界観が覗けるビデオ映像と共にご紹介したいと思います。
■ 第8回
夜の部 1月29日(火) 19:00、朝の部 2月12日(火) 10:30
「16世紀修道院の建築計画における古代文化の影響」
喜多裕子 (筑波大学大学院 人間総合科学研究科 世界文化遺産学専攻 博士課程。2007年4月〜2008年3月:メキシコ国立保存修復博物館学大学大学院 建築学研究科 不動産文化遺産保存修復専攻 研究滞
在)
メキシコの植民地期(1521〜1821年)の建築は、スペイン文化と先住民文化との融合の歴史を担っています。植民地期建築における先住民文化の影響に関して、建築彫刻や壁画などに見られる図像、建造物の配置などの建築計画といった視点から、60年代半ばから70年代にわたって、欧米・ラテンアメリカを中心に、さまざまな論争が繰り広げられました。
植民地化直後の16世紀の建造物には、異文化の融合が何かしらの「形」として表出されています。その中でも特に、先住民の改宗を目的として建てられた数多くの修道院には、修道院建築というスペイン文化の器の中に、意図的に先住民文化の要素がとりこまれています。
16世紀の修道院の建築要素をとりあげ、その空間的特徴と機能から、二つの文化がどのように混合されていったのかをお話したいと思います。
■ 第9回
夜の部 2月12日(火) 19:00、朝の部 2月26日(火) 10:30
「16世紀テキキ美術における先スペイン期図像の残存」
柳澤佐永子 (メキシコ国立自治大学大学院 哲文学部 美術史専攻 博士課程)
メキシコ各地でみられる教会。ヨーロッパで見る教会とどこか少し違うと感じる人が多いと思います。これらメキシコの教会の魅力は、やはりそこにみられるメソアメリカ美術の影響ではないでしょうか。特に、スペイン人による征服直後の16世紀に建てられた教会には、先スペイン期に使われていたモチーフがそのまま使われているものも多く、それはテキキ美術と呼ばれています。では、そのテキキ美術のモチーフとは一体どのようなものなのでしょうか。今回の発表ではその具体例をお見せしようと思います。
■ 第10回
夜の部 2月26日(火) 19:00、朝の部 3月11日(火) 10:30
「教会の聖人像を『読む』」
渡辺裕木 (メキシコ文化財保存修復士)
カトリック教会には、多くの聖人像や絵画が飾られています。一見どれも同じように見える聖人も、それぞれが所属していた修道会の服を身に付け、生き様を象徴する物を携えています。そこを読み解けば、聖人の名前を『見分ける』ことができ、また、何千といるカトリック聖人の中で、メキシコの教会で見る聖人はある程度限られていることも見えてきます。宗教美術に馴染みの薄い方なら誰もが疑問に思う幾つかの宗教的なモチーフの説明と合わせて、教会の聖人をいかに見分けるかというお話をします。名前や逸話を知る聖人の像を探すことが、メキシコ文化に触れるみなさんのもう一つの楽しみになれば幸いです。
■ 閉会式
夜の部 3月11日(火) 19:00
パネル・ディスカッション
皆様の多数のご参加をお待ちしております!!!
メキシコ文化研究会
困ったときには