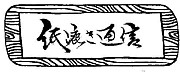開催終了エジプトで紙漉き
詳細
2010年01月13日 04:38 更新
「文化庁文化交流使事業」は,芸術家,文化人等,文化に携わる人々を「文化交流使」に指名し,世界の人々の日本文化への理解の深化につながる活動や,日本と外国の文化人とのネットワークづくりにつながる活動を展開するものです。
この考えは故河合隼雄氏が文化庁長官の時に提案して進められた制度です。
残念なことに事業仕分けで制度は無くなる運命です。
平成21年度の指定は昨年7月7日に決定しました。
氏名 伊部 京子
プロフィール 和紙造形家
派遣国 米国、エジプト
内容 米国では、イリノイ大学に寄贈した器材一式を借り受け、
各地の大学において実演指導を行う。
エジプトではアレクサンドリア大学を中心として、
指導者の養成コースを開設し、本格的な指導を行う。
http://
この考えは故河合隼雄氏が文化庁長官の時に提案して進められた制度です。
残念なことに事業仕分けで制度は無くなる運命です。
平成21年度の指定は昨年7月7日に決定しました。
氏名 伊部 京子
プロフィール 和紙造形家
派遣国 米国、エジプト
内容 米国では、イリノイ大学に寄贈した器材一式を借り受け、
各地の大学において実演指導を行う。
エジプトではアレクサンドリア大学を中心として、
指導者の養成コースを開設し、本格的な指導を行う。
http://
コメント(4)
2010年01月13日 04:43
文化庁に提出した申請書類の一部です。
伊部京子さんは書類作りのプロです。
私も参考にしていますが簡単にまねできるものではありません。
====================
今回和紙づくりのあらゆるノーハウを保持する阿波和紙の伝統工芸士上田貞子と和紙の普及と海外での指導に定評ある田村正の精鋭2人を伴いプロジェクトを力強くスタートさせ、軌道にのせることを目指します。
上田は私の阿波和紙伝統産業会館での現地制作の補佐を長らく続けていて、私の制作には精通しています。田村はチリ、アメリカでの大学の授業に同行し、指導と手わざで評価されています。
展覧会場であるDARB1718は紙工房とは至近距離にあり、展覧会とワークショップを同時に開催、公開し、実験的な制作と並行して、和紙のデモンストレーションも行います。オープニングの当日は紙漉きデモンストレーションを行いその場で希望者をつのり、後日工房でのハンズ・オン・ワークショップへの誘導します。
展覧会の開催中はウェークエンドにギャラリー・トークと伊部の作品づくりを公開いたします。
和紙の伝統と創生の両面を作品と技で披露するとともに、そのパワーを異国でのものづくりにも役立てることを目的にプロジェクトを推進いたします。
2010年03月05日 12:09
NHKラジオ深夜便
2月25日放送
〜〜〜〜〜〜〜〜
今日最初の話題は、エジプトにできた新しい大学についてです。
ーーーーーーーーー
大学の紹介がありました。詳しく知りたい方は
私の日記へ
ここは和紙のコミュと言うことで割愛しました。
ーーーーーーーーー
さて、日本が誇れる技術は新しいものばかりではありません。
古くからも驚くような知恵と技術があるんですね。
今カイロでは伊部京子(いべきょうこ)さんとエジプト人のモハメット・アブエルナガさんお二人の作品展「Paper Tales」(紙の伝説)が今月6日から明日27日まで開催されています。
伊部京子さんは京都工芸繊維大学で教鞭をとられていますが、今回は文化庁文化交流使の和紙造形家としてエジプトにおいでになっています。
伊部さんの作品は既存の和紙そのものを利用するというよりは、和紙になる前の段階の原料を素材にしたダイナミックな作品群です。屏風や壁掛け、天井からつるしたオブジェなど紙となる素材がもつ可能性をとことん追求した作品ともいえます。
伊部さんによりますと作品は最近製作したものばかりを持っていらしたということで、日本の伝統ともいえる和紙を扱いながら常に新しい技術や作風を模索し続けていらっしゃいます。さらに後に続く学生達には製作過程も方法も全て伝えています。どんなに真似されても原料の調達それ自体が難しいこともありますし、そこには伊部さんが編み出した手法はご自身のオリジナルであるという誇りがうかがえます。
モハメット・アブエルナガさんはカイロ大学芸術科の教授で、和紙に魅せられ10年前に京都へ6カ月留学し紙漉きの技術まで学んだ方です。キャンバスに描かれた絵にごく薄い透けるような和紙をヴェールをかけるように用いているのが特徴です。
ところで「紙」といえば英語で「paper」このペーパーの語源になっているのが古代エジプトで使われていた「パピルス」だというのはご存知でしょうか。
古代エジプトのパピルスの原料は水辺に生えるカヤツリグサ科の植物です。
ローマ時代に入る頃までこのパピルスに記述された文書が知的遺産として流通していました。その後パピルスは紙や羊皮紙に取って代わられ次第に廃れていったのですが、20世紀半ばに復活し今ではエジプトの代表的なおみやげ物のひとつになっています。
エジプト人にとって手作りの紙といえば頭に浮かぶのはパピルスです。
今回、伊部さんはこの作品展の開会式に紙漉きの実演も用意して下さいました。実際に紙漉きをされたのは日本から同行された手漉き和紙の匠・田村正(たむらただし)さんと伝統工芸士の上田貞子(うえたさだこ)さんです。
白濁している水から漉きあげた紙はごく薄いけれどとても丈夫です。紙漉きを知らない人々にとってこの薄さと丈夫さは驚異の技に映るようですね。乾かして板から外した紙を手にして、オーッという声が上がるのが何より嬉しい、とおっしゃっていました。
そんな中、手漉きの紙を3年前から作っているという小さな工房を訪ねてみました。
原料は稲藁です。ここでは植物の繊維を薬品で全部溶かしてしまうので、和紙のような繊細な紙には仕上がらず、ザラリとした風合いの厚手の紙として出来上がります。
伊部さん田村さんによりますと、バナナの幹の植物繊維を利用してこの稲藁と混ぜていけばかなり質の良い紙ができる可能性があるということでした。
紙は土の中から生まれた植物の生命を生成して出来上がります。常に紙に問いかけ紙と向き合う、紙は変幻自在です。と伊部さんがおっしゃっていましたが、ナイルの岸辺に生まれたパピルスも稲藁もバナナの幹もやはり植物です。問い続けていれば良いものが生まれてくると思います。
余談ですが今回伊部京子さんの一部の壁掛けの作品がカイロの乾燥した気候の影響で歪みが出てきてしまいました。日頃は歪まないようにボードで裏面を補強するそうですが、今回移送の重量制限があったので外してきたものが歪んでいます。それに引き換え古来からの手法で製作した屏風は内部に(表裏合わせて3重なので)6重に古い良く乾燥した和紙を下貼りしてあるということで、全く歪みが出ていないんですね。昔からの智慧と技術の確かさが確認された一件でした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには