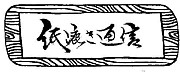開催終了第16回 和紙文化講演会
詳細
2008年09月24日 00:49 更新
第16回 和紙文化講演会
『生活をうるおす和紙』
−手漉き和紙の多彩な展開−
<和紙文化研究会 創立20周年記念大会>
和紙の特長のひとつには、文字を記すだけではなくさまざまに加工され、
生活の広い用途に活用されてきたことが挙げられる。
生活をうるおす和紙を展望すると、巧みな技やその豊かな広がりが残されている。
和紙と生活の伝統を広い視野で検証し、
和紙を現代に活かす可能性やそのすぐれた価値を探りたい。
[日時] 平成20年11月30日(日)
午前10:00〜午後5:00
閉会後、校内にて講演者を交え懇親会を催します。会費別途
[会場] 昭和女子大学グリーンホール
・東急新玉川線三軒茶屋駅下車 南出口より徒歩5分
・JR渋谷バスターミナルより
三軒茶屋方面行 昭和女子大学前下車
[参加費] 一般 3500円
(機関紙「和紙文化研究」第16号及び講演要旨集を含む)
[定員]
250名
[参加申し込み方法]
参加費の事前申し込みによる受付です。郵便振替用紙に
住所、氏名、電話、FAX番号、専門分野もしくは所属を
ご記入の上、参加費を払い込みください。準備の都合上、
お早めにお申し込み下さい。締め切り11月20日(木)
[振込先]
郵便振替口座:00170−8−402506
「和紙文化講演会」
[事務局]
〒110-8714 東京都台東区上野公園12−8
東京藝術大学 大学院美術研究科 保存化学気付
和紙文化講演会事務局 稲葉政満
東京藝大内 FAX 050−5525−2505
特設 携帯電話 080−6730−8581
(この特設電話は会期までの平日、午後1時〜6時)
*会場の昭和女子大学へのお問い合わせはご遠慮ください。
主催 和紙文化研究会
後援 文化財保存修復学会
『生活をうるおす和紙』
−手漉き和紙の多彩な展開−
<和紙文化研究会 創立20周年記念大会>
和紙の特長のひとつには、文字を記すだけではなくさまざまに加工され、
生活の広い用途に活用されてきたことが挙げられる。
生活をうるおす和紙を展望すると、巧みな技やその豊かな広がりが残されている。
和紙と生活の伝統を広い視野で検証し、
和紙を現代に活かす可能性やそのすぐれた価値を探りたい。
[日時] 平成20年11月30日(日)
午前10:00〜午後5:00
閉会後、校内にて講演者を交え懇親会を催します。会費別途
[会場] 昭和女子大学グリーンホール
・東急新玉川線三軒茶屋駅下車 南出口より徒歩5分
・JR渋谷バスターミナルより
三軒茶屋方面行 昭和女子大学前下車
[参加費] 一般 3500円
(機関紙「和紙文化研究」第16号及び講演要旨集を含む)
[定員]
250名
[参加申し込み方法]
参加費の事前申し込みによる受付です。郵便振替用紙に
住所、氏名、電話、FAX番号、専門分野もしくは所属を
ご記入の上、参加費を払い込みください。準備の都合上、
お早めにお申し込み下さい。締め切り11月20日(木)
[振込先]
郵便振替口座:00170−8−402506
「和紙文化講演会」
[事務局]
〒110-8714 東京都台東区上野公園12−8
東京藝術大学 大学院美術研究科 保存化学気付
和紙文化講演会事務局 稲葉政満
東京藝大内 FAX 050−5525−2505
特設 携帯電話 080−6730−8581
(この特設電話は会期までの平日、午後1時〜6時)
*会場の昭和女子大学へのお問い合わせはご遠慮ください。
主催 和紙文化研究会
後援 文化財保存修復学会
コメント(1)
2008年09月24日 00:56
講演プログラム
9:40 開場
10:00〜10:10 開会挨拶 大江礼三郎
(東京農工大学名誉教授)
10:10〜11:00 講演(1)北村 春香
(浜田市金城歴史民俗資料館学芸員)
「日常の紙布、非日常の紙布」
日本の紙布は江戸時代から各地で作られてきた。
各地に残る紙布の伝承から、日常の紙布、
非日常の紙布を紐解いてみたい。
最近では紙糸を用いた様々な商品も登場しているが、
これら紙布の伝承から過去、現在、未来を考察する。
11:00〜11:50 講演(2)奥窪 聖美
(漆芸作家、日本工芸会正会員)
「漆芸と和紙」
漆芸の表面は硬い塗りで覆われる為、軟らかな和紙とは縁遠そうだが、
実は漆濾しには欠かせないし、素地や下地にしたり、
紙肌塗りをすることもあり、和紙とは親密なのだ。
制作の実際を通して和紙の使われ方を紹介する。
1:20〜 2:10 講演(3)石川 満夫
(越前和紙を愛する会会長)
「越前美術紙−多彩な漉き模様の技巧」
漉き模様紙は、越前和紙を特長づける代表的存在である。
その技法は平安時代から続く打雲、飛雲に遡る。
江戸時代には漉き込み、透かし入れ、昭和に入ると水切り、
ひっかけなど多種多様な技巧が編み出された、
それを可能にしたのは“用”に応える越前紙漉きの柔軟性であろう。
2:10〜 3:00 講演(4)近藤 恭子
(和紙文化研究会会員)
「「千代紙」の変遷」
千代紙は木版による印刷技術が大衆文化を彩ったことにより生まれ発展した。
浮世絵、錦絵の影響を受けて独自に発達した江戸千代紙と、
染色の世界に影響を受け与えた京千代紙との違いを中心に、
その歴史と現在の姿を紹介する。
3:30〜 4:20 講演(5)久米 康生
(和紙文化研究会代表)
「生活を多彩にデザインした和紙」
来航した海外の知識人は、
和紙の特長は日常生活の広い用途に活用されていることであると評価している。
それらを反映して西洋の博物館に保管されている
コレクションからインテリア材としてのいくつかのデザインを考える。
4:20〜 4:50 総合討議 座長:稲葉 政満
(東京藝術大学大学院教授)
4:50〜 5:00 閉会挨拶 半田 正博
(東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター教授)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには