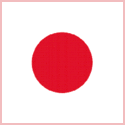開催終了2/11【大阪】☆皇統の未来を守るオフ@阿部野☆
詳細
2009年01月21日 21:13 更新
☆皇統の未来を守るオフ@阿部野☆
●日時:平成21年2月11日(水曜日・建国記念の日)午後3時集合厳守
●雨天:断行(内容は一部変更の場合あり)。
●集合場所:南海電鉄南海線・高野線「岸里玉出」駅「岸里口」改札前
※岸里玉出駅には、岸里口(北口)と玉出口(南口)がありますが、お間違いなく【岸里口】にお進み下さい。
※岸里玉出駅は、南海線・高野線ともに普通電車のみ停車。
地図:http://
路線図:http://
●順路:南海「岸里玉出」駅岸里口〜阿部野神社〜北畠顕家公御墓〜阪堺電軌にて天王寺方面。
●趣旨:大阪市阿倍野区北畠三丁目御鎮座の別格官幣社阿部野神社は、吉野朝の功臣北畠親房公ならびに北畠顕家公を御祭神として、顕家公が散華された阿部野古戦場の地に御創建された神社です。
贈正一位北畠准后親房公は後醍醐天皇の御信任頗る厚く、天皇の吉野遷幸ののち大命を奉戴して東国に下られ王事に御奔走、後醍醐天皇崩御ののち皇位を践まれた義良親王(後村上天皇)の御為に、常陸国小田城の陣中に『神皇正統記』を著して国の真姿を説かれました。のち吉野に戻られ、正平九年四月十七日(一説九月十五日)六十二歳にて薨去されるまで吉野朝の柱石として、後村上天皇を助け奉られました。
贈従一位鎮守府大将軍北畠顕家公は親房公の御嫡長子。十六歳で陸奥守に任じられると、義良親王を奉じて奥州へ下向されてかの地を御平定、足利高氏が朝廷に叛くや直ちに奥羽の騎馬兵団を率いて御上洛、高氏を西海道に敗走せしめました。延元三年賊軍御討伐のため再び奥州より長駆西上されるも、同年五月二十二日、御奮戦空しく御歳二十一歳にて御殉節されました。
己が何者であるかを知ろうともせず即物的利己主義に奔る凶徒蔓延る乱世に、不屈の確信をもって歴史を見据え、皇統の正理を唱えられた親房公と、皇統の未来に殉ずるべく賊の群れに体をぶつけられた顕家公。
今また獣にも似た凶徒の横行する世となったこの国で、邦家の来し方行く末に想いを致すべき建国の日に、阿部野のみ社に参じ親房公顕家公の大前に額づくことは、大いに意義あることでありましょう。
又の年戊寅の春二月、鎭守大將軍顯家卿又親王をさきだて申、かさねてうちのぼる。海道の國々ことごとくたひらぎぬ。伊勢伊賀をへて大和に入、奈良の京になむつきにける。それより所々の合戰あまたゝびに勝負侍りしに、同五月和泉國にてのたゝかひに、時いたらざりけむ、忠孝の道こゝにきはまりはべりにき。苔の下にうづもれぬ、たゞいたづらに名をのみぞとゞめてし、心うき世にもはべるかな。(北畠親房公『神皇正統記』人巻・後醍醐天皇延元三年条)
●費用:交通費適宜(阪堺電軌運賃は200円)。
●当日連絡先:090-9273-5667(14:30以降繋がります)
http://
http://
●日時:平成21年2月11日(水曜日・建国記念の日)午後3時集合厳守
●雨天:断行(内容は一部変更の場合あり)。
●集合場所:南海電鉄南海線・高野線「岸里玉出」駅「岸里口」改札前
※岸里玉出駅には、岸里口(北口)と玉出口(南口)がありますが、お間違いなく【岸里口】にお進み下さい。
※岸里玉出駅は、南海線・高野線ともに普通電車のみ停車。
地図:http://
路線図:http://
●順路:南海「岸里玉出」駅岸里口〜阿部野神社〜北畠顕家公御墓〜阪堺電軌にて天王寺方面。
●趣旨:大阪市阿倍野区北畠三丁目御鎮座の別格官幣社阿部野神社は、吉野朝の功臣北畠親房公ならびに北畠顕家公を御祭神として、顕家公が散華された阿部野古戦場の地に御創建された神社です。
贈正一位北畠准后親房公は後醍醐天皇の御信任頗る厚く、天皇の吉野遷幸ののち大命を奉戴して東国に下られ王事に御奔走、後醍醐天皇崩御ののち皇位を践まれた義良親王(後村上天皇)の御為に、常陸国小田城の陣中に『神皇正統記』を著して国の真姿を説かれました。のち吉野に戻られ、正平九年四月十七日(一説九月十五日)六十二歳にて薨去されるまで吉野朝の柱石として、後村上天皇を助け奉られました。
贈従一位鎮守府大将軍北畠顕家公は親房公の御嫡長子。十六歳で陸奥守に任じられると、義良親王を奉じて奥州へ下向されてかの地を御平定、足利高氏が朝廷に叛くや直ちに奥羽の騎馬兵団を率いて御上洛、高氏を西海道に敗走せしめました。延元三年賊軍御討伐のため再び奥州より長駆西上されるも、同年五月二十二日、御奮戦空しく御歳二十一歳にて御殉節されました。
己が何者であるかを知ろうともせず即物的利己主義に奔る凶徒蔓延る乱世に、不屈の確信をもって歴史を見据え、皇統の正理を唱えられた親房公と、皇統の未来に殉ずるべく賊の群れに体をぶつけられた顕家公。
今また獣にも似た凶徒の横行する世となったこの国で、邦家の来し方行く末に想いを致すべき建国の日に、阿部野のみ社に参じ親房公顕家公の大前に額づくことは、大いに意義あることでありましょう。
又の年戊寅の春二月、鎭守大將軍顯家卿又親王をさきだて申、かさねてうちのぼる。海道の國々ことごとくたひらぎぬ。伊勢伊賀をへて大和に入、奈良の京になむつきにける。それより所々の合戰あまたゝびに勝負侍りしに、同五月和泉國にてのたゝかひに、時いたらざりけむ、忠孝の道こゝにきはまりはべりにき。苔の下にうづもれぬ、たゞいたづらに名をのみぞとゞめてし、心うき世にもはべるかな。(北畠親房公『神皇正統記』人巻・後醍醐天皇延元三年条)
●費用:交通費適宜(阪堺電軌運賃は200円)。
●当日連絡先:090-9273-5667(14:30以降繋がります)
http://
http://
コメント(17)
2009年02月14日 18:46
>智ちゃんさん
また宜しくお願いします。
>ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
参加者は、初参加の方2名を含む14名でした。
天気予報とは正反対の日本晴れで気温も高く、絶好の紀元節日和となった当日、午後3時に南海「岸里玉出」駅岸里口に集合し、徒歩数分の阿部野神社に向かいました。阿部野神社では、まずは「神は人の敬によって威を増し 人は神の徳によって運を添う」という『御成敗式目』の文言が掲げられた拝殿社頭にて一同御祭神北畠親房公北畠顕家公に対し奉り皇室の弥栄と国家の安泰を熱祷致しました。その後、拝殿横手から続く「御魂振之道」と名付けられた細い参道に入り、御本殿の真後ろに鎮座する奥宮・御魂振之宮の広前に進みます。この御魂振之宮は、大東亜戦争の戦災で焼失した御社殿の復興事業開始時に、天照大御神・三輪大神・少彦名大神・菅原道真公を御祭神として復興成就祈願のために御造営されたもので、昭和四十三年遂に御社殿復興の成った後は、「一願一遂の宮」と称されています。皆それぞれ祈願した後は、各自境内の散策・学習や授与所での御朱印・御守の拝受等に時を過ごしました。
阿部野神社を辞したのちは、北畠三丁目から同二丁目の住宅地を十数分歩き、北畠顕家公御墓のある北畠公園に向かいます。流石に大阪市内随一の高級住宅街であるだけに、国旗を掲揚している住宅も道々見られます。
北畠公園はあべの筋に面した小さな公園ですが、楠の巨木が何本も聳え立ち、その木蔭によって日中でも薄暗く、あべの筋の喧騒も遮断されています。一同北畠顕家公御墓に拝礼して公の忠勇を偲び、暫く園内で各自散策・学習を行ったあと、御墓前を辞します。
北畠公園近くから熊野街道(熊野古道)に入り、空襲を免れた蒼古たる旧家が建ち並ぶ古街道をそぞろ歩き、阿倍王子神社に至りました。阿倍王子神社は社伝によるともと仁徳天皇の御創建に成るといい、この近辺に拠った名族阿倍氏(安倍氏)の氏神を経て、熊野詣での盛行とともに熊野街道沿いに勧請された九十九王子のひとつ「阿倍野王子」となり、時流によって衰微する王子社の多いなか、大阪府下で唯一現存する王子社として現在に至っています。御祭神は、熊野王子神(伊邪那岐命、伊邪那美命、速素盞鳴命)、八幡大神(品陀別命)です。境内には紀元二千六百年紀念碑もあります。一同御祭神に皇室の弥栄と国家の安泰を祈願しました。
阿倍王子神社でも参拝後授与所を訪れたあと、すぐ近くの安倍晴明神社に向かいました。安倍晴明神社は阿倍王子神社の飛地境内末社で、「陰陽師」ブームで一般にも知られるようになった安倍晴明公の御生誕地とされています。御祭神は安倍晴明大神(安倍晴明公)。周辺の旧地名は晴明公の伝説上の父君・安倍保名公に由来する「保名」であり、いまも近くの保名郵便局にその名を残しています(晴明公の父君は歴史上は安倍益材公とされています)。同社でも一同御祭神に皇室の弥栄と国家の安泰を祈願し、これにて紀元節オフの全行程を終了致しました。
オフ終了後は、近くの阪堺「東天下茶屋」電停から路面電車であべの筋を北上して天王寺駅前に向かい、料理店にて紀元節奉祝懇話会を開催致しました。
※「あべの」の漢字表記について、「阿部野」とするのは現在、阿部野神社と近鉄・大阪阿部野橋駅くらいで、区名をはじめ多くは「阿倍野」が用いられています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには