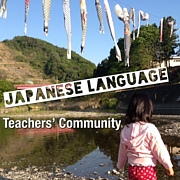|
|
|
|
コメント(14)
mixi@sasakiworld? さんのおっしゃるとおり、
> 格助詞「に」が場所や範囲を示す時には、
>
> で (する)
> に (いる・ある)
ですが、こういう言い方もできます。
A.駐車場<で>車を停める
B.駐車場<に>車を停める
Aは車を停める行為をする場所、つまり人(行為者)がいる場所が駐車場であることを示します。
例えばタクシーが目的地に着いたときは「ここで停めてください。」ですね。人の場所が重要だからです。
Bは車を運ぶ最終地点、つまり車がある場所が駐車場である事を示します。
そのタクシーに暫く待ってもらう待機場所を示すときは「ここに停めてください。」です。車の場所が重要だからです。
この例の場合、人と車が移動しながら、常に同じ場所に在るので、混乱が起きるのだと思います。
ですから、わたしは次の例文を使って説明しています。
C.公園<で>ゴミを捨てる。
D.公園<に>ゴミを捨てる。
ボードに公園(実際には楕円)を書いて、
Cは公園の中にいる人がゴミを捨てるところ
Dは公園の外にいる人が公園の中にゴミを投げ入れるところ
を書き加えます。
これでだいたい理解してもらえます。
次に駄目押しとして、
E.ここ<で>書いてください。
F.ここ<に>書いてください。
「入管で書類を書きます。入管の人が言います」と前置きして、
Eを言いながら机の表面を示して、「ここで書きます。」
Fを言いながら紙を持って指差して、「ここに書きます。」
最後に、かねて準備しておいた練習問題をさせれば一件落着です。(^^)
> 格助詞「に」が場所や範囲を示す時には、
>
> で (する)
> に (いる・ある)
ですが、こういう言い方もできます。
A.駐車場<で>車を停める
B.駐車場<に>車を停める
Aは車を停める行為をする場所、つまり人(行為者)がいる場所が駐車場であることを示します。
例えばタクシーが目的地に着いたときは「ここで停めてください。」ですね。人の場所が重要だからです。
Bは車を運ぶ最終地点、つまり車がある場所が駐車場である事を示します。
そのタクシーに暫く待ってもらう待機場所を示すときは「ここに停めてください。」です。車の場所が重要だからです。
この例の場合、人と車が移動しながら、常に同じ場所に在るので、混乱が起きるのだと思います。
ですから、わたしは次の例文を使って説明しています。
C.公園<で>ゴミを捨てる。
D.公園<に>ゴミを捨てる。
ボードに公園(実際には楕円)を書いて、
Cは公園の中にいる人がゴミを捨てるところ
Dは公園の外にいる人が公園の中にゴミを投げ入れるところ
を書き加えます。
これでだいたい理解してもらえます。
次に駄目押しとして、
E.ここ<で>書いてください。
F.ここ<に>書いてください。
「入管で書類を書きます。入管の人が言います」と前置きして、
Eを言いながら机の表面を示して、「ここで書きます。」
Fを言いながら紙を持って指差して、「ここに書きます。」
最後に、かねて準備しておいた練習問題をさせれば一件落着です。(^^)
「にて」という文語調の格助詞がありますね。
これは、口語文法の格助詞「で」にあたりますね。
文語調の「にて」ですが、結構日常会話でも改まった場などでよく使用されています。
例:
まもなく、校庭にて朝礼を行います。
詳しくは、銀行の窓口にてお問い合わせください。
同じような文脈で「において」「におきまして」も使用されます。
「にて」「において」「におきまして」は、当然、書き言葉でも用いられますが、アナウンスや案内など、きちんとメッセージを伝えなければならないような役割を担った人が話し言葉で使用することも多いようです。
というのも、格助詞「に」「で」にはいろいろな機能がそなわっており、場合によっては誤解を招くおそれがあるからです。
帰着点を表す「に」の代わりに、「〜のほうに(へ)」とわざわざ言ったりします(例:こちらのほうにご記入願います)
教室では、こういったバリエーションにも触れて、実用的な日本語を教えるのが望ましいと思います。
これは、口語文法の格助詞「で」にあたりますね。
文語調の「にて」ですが、結構日常会話でも改まった場などでよく使用されています。
例:
まもなく、校庭にて朝礼を行います。
詳しくは、銀行の窓口にてお問い合わせください。
同じような文脈で「において」「におきまして」も使用されます。
「にて」「において」「におきまして」は、当然、書き言葉でも用いられますが、アナウンスや案内など、きちんとメッセージを伝えなければならないような役割を担った人が話し言葉で使用することも多いようです。
というのも、格助詞「に」「で」にはいろいろな機能がそなわっており、場合によっては誤解を招くおそれがあるからです。
帰着点を表す「に」の代わりに、「〜のほうに(へ)」とわざわざ言ったりします(例:こちらのほうにご記入願います)
教室では、こういったバリエーションにも触れて、実用的な日本語を教えるのが望ましいと思います。
私は一応まがりなりにもロシア語のプロパーではありますが、通時言語学の専門ではありませんし、今後どうなっていくのかまではわかりません。通時言語学者にもネイティブにもわからないのではないでしょうか。
昔どうだったかは、昔の人に聞くしかないですかね(冗談)。
私は、恥ずかしながら知りません。
トルストイの肉声を蓄音機に録音したものが記録として残っているらしいですよ。вокзалという単語をトルストイがその録音で発話しているとは思えませんが、聞いてみたいですよね。
まあ、それを聞くまでもなく、トルストイの時代は子音の有声化については今と同じだったはずです。
もし仮にвокзалが「vokzal」と発音されていたような時代があったとすれば、それは、教会スラブ語の時代あたりにさかのぼらなければならないでしょうね。
昔どうだったかは、昔の人に聞くしかないですかね(冗談)。
私は、恥ずかしながら知りません。
トルストイの肉声を蓄音機に録音したものが記録として残っているらしいですよ。вокзалという単語をトルストイがその録音で発話しているとは思えませんが、聞いてみたいですよね。
まあ、それを聞くまでもなく、トルストイの時代は子音の有声化については今と同じだったはずです。
もし仮にвокзалが「vokzal」と発音されていたような時代があったとすれば、それは、教会スラブ語の時代あたりにさかのぼらなければならないでしょうね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
☆日本語教師☆ 更新情報
-
最新のアンケート