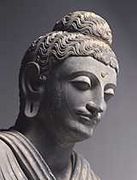相応部経典>因縁篇>第七羅睺羅相応
「 [一八] 第七 羅睺羅相応[ラーフラ・サムユッタ]
第一品
第一 眼
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼をも嫌悪し、耳をも嫌悪し、鼻をも嫌悪し、舌をも嫌悪し、身をも嫌悪し、意をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第二 色
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
色は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 声は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 香は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 味は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 法は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は色をも嫌悪し、声をも嫌悪し、香をも嫌悪し、味をも嫌悪し、触をも嫌悪し、法をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第三 識
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼識をも嫌悪し、耳識をも嫌悪し、鼻識をも嫌悪し、舌識をも嫌悪し、身識をも嫌悪し、意識をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第四 触
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼触をも嫌悪し、耳触をも嫌悪し、鼻触をも嫌悪し、舌触をも嫌悪し、身触をも嫌悪し、意触をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第五 受
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼触によって生じる受をも嫌悪し、耳触によって生じる受をも嫌悪し、鼻触によって生じる受をも嫌悪し、舌触によって生じる受をも嫌悪し、身触によって生じる受をも嫌悪し、意触によって生じる受をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る」
『南伝大蔵経13 相応部経典2』大蔵出版 P361–366
六根 眼耳鼻舌身意
六境 色声香味触法
六識 眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識
六触 眼触・耳触・鼻触・舌触・身触・意触
六受 眼触所生受・耳触所生受・鼻触所生受・舌触所生受・身触所生受・意触所生受
無常・苦・無我を観じて厭患・離貪・解脱する
離貪せずに解脱はなく、厭患がなければ離貪もありません。厭患するためには必ず執着している対象の欠点を事実の通りに見る必要があります。覆すことのできない一切の欠点とは、即ちその無常性・苦性・無我性です。この欠点を知らずに執着の対象を嫌悪するという道理はありません。無常を認めなければ、恒常を認めることになり、恒常ならば楽にして有我という結論になるからです。逆に言えば、無常想・無常における苦想・苦における無我想を繰り返すだけで必ず厭患が結果され、続いて離貪・解脱があります。この問答を一人で延々繰り返す瞑想をゴータマはラーフラに教えているのです。それならば、それを自分に適応してこの問答を一人でずっと考え続ければ自分も解脱するだろうと見るのが正見です。即ち道諦における智です。以後、同形式の文が続きます。
「 [一八] 第七 羅睺羅相応[ラーフラ・サムユッタ]
第一品
第一 眼
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼をも嫌悪し、耳をも嫌悪し、鼻をも嫌悪し、舌をも嫌悪し、身をも嫌悪し、意をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第二 色
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
色は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 声は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 香は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 味は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 法は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は色をも嫌悪し、声をも嫌悪し、香をも嫌悪し、味をも嫌悪し、触をも嫌悪し、法をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第三 識
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意識は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼識をも嫌悪し、耳識をも嫌悪し、鼻識をも嫌悪し、舌識をも嫌悪し、身識をも嫌悪し、意識をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第四 触
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意触は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼触をも嫌悪し、耳触をも嫌悪し、鼻触をも嫌悪し、舌触をも嫌悪し、身触をも嫌悪し、意触をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る。
第五 受
一 このように私は聞いた。あるとき、世尊はサーヴァッティのジェータ林、アナータピンディカ園に住していた。
二 そのとき、具寿ラーフラは世尊のところに詣った。詣って世尊に問訊し、一方に座った。
三 一方に座った具寿ラーフラは世尊にこう言った。
善いかな、大徳。世尊は私のために法を説いてください。私は聞いて一処に退き、不放逸に、熱心に、専念して住そうと思います。
四 ラーフラ、これをどう思うか。
眼触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
五 耳触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
六 鼻触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
七 舌触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
八 身触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
九 意触によって生じる受は常なのか、無常なのか。
大徳、無常です。
無常であるものは苦なのか、楽なのか。
大徳、苦です。
無常であり、苦であり、変化する法を「これは私のものである。これは私である。これは私の本質である」と認めるのは正しいだろうか。
大徳、そうではありません。
一〇 ラーフラ、このように見て有聞の聖弟子は眼触によって生じる受をも嫌悪し、耳触によって生じる受をも嫌悪し、鼻触によって生じる受をも嫌悪し、舌触によって生じる受をも嫌悪し、身触によって生じる受をも嫌悪し、意触によって生じる受をも嫌悪する。
一一 嫌悪して離貪する。離貪して解脱する。解脱して「私は解脱した」という智がある。「生は尽きた。梵行には住した。作すべきことを作した。さらにこの状態にならず」と知る」
『南伝大蔵経13 相応部経典2』大蔵出版 P361–366
六根 眼耳鼻舌身意
六境 色声香味触法
六識 眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識
六触 眼触・耳触・鼻触・舌触・身触・意触
六受 眼触所生受・耳触所生受・鼻触所生受・舌触所生受・身触所生受・意触所生受
無常・苦・無我を観じて厭患・離貪・解脱する
離貪せずに解脱はなく、厭患がなければ離貪もありません。厭患するためには必ず執着している対象の欠点を事実の通りに見る必要があります。覆すことのできない一切の欠点とは、即ちその無常性・苦性・無我性です。この欠点を知らずに執着の対象を嫌悪するという道理はありません。無常を認めなければ、恒常を認めることになり、恒常ならば楽にして有我という結論になるからです。逆に言えば、無常想・無常における苦想・苦における無我想を繰り返すだけで必ず厭患が結果され、続いて離貪・解脱があります。この問答を一人で延々繰り返す瞑想をゴータマはラーフラに教えているのです。それならば、それを自分に適応してこの問答を一人でずっと考え続ければ自分も解脱するだろうと見るのが正見です。即ち道諦における智です。以後、同形式の文が続きます。
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏典 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏典のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人