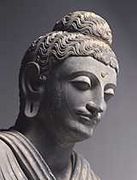(『南伝大蔵経16下 相応部経典6』大蔵出版 P153から)
「 第七 尋覓品
[六七] 第一 尋覓
(第一 勝智)
二 比丘たちよ、三つの尋求(esanā)がある。何を三となすのか。欲尋求(kāmesanā)、有尋求(bhavesanā)、梵行尋求(brahmacariyesanā)である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を勝智(abhiññā)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を勝智するために四神足を修習するべきである。
(第二 遍知)
四 比丘たちよ、三つの尋求がある。何を三となすのか。欲尋求、有尋求、梵行尋求である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を遍知(pariññā)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
五 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を遍知するために四神足を修習するべきである。
(第三 遍尽)
六 比丘たちよ、三つの尋求がある。何を三となすのか。欲尋求、有尋求、梵行尋求である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を遍尽(parikkaya、遍く尽きる、完全に尽きる)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
七 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を遍尽するために四神足を修習するべきである。
(第四 断)
八 比丘たちよ、三つの尋求がある。何を三となすのか。欲尋求、有尋求、梵行尋求である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を断じる(pahāna)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
九 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を断じるために四神足を修習するべきである。
[六八] 第二 次第
二 比丘たちよ、三次第(vidhā、種、種類、次第;慢、慢類)がある。何を三となすのか。「私は優れている」という次第と、「私は等しい」という次第と、「私は劣っている」という次第である。比丘たちよ、これを三次第となす。
三 比丘たちよ、この三次第を勝智するために・・・・・・遍知するために・・・・・・遍尽するために・・・・・・断じるために四神足を修習すべきである。何を四神足となすのか。
四 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三次第を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習するべきである。
[六九] 第三 漏
二 比丘たちよ、三漏がある。何を三となすのか。欲漏(kāmāsava)、有漏(bhavāsava)、無明漏(avijjāsava)である。比丘たちよ、これを三漏となす。
三 比丘たちよ、この三漏を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである。何を四神足をなすのか。
四 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲・・・勤・・・心・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三漏を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習するべきである。
[七〇] 第四 有
二 比丘たちよ、三有がある。何を三となすのか。欲有(kāmabhava)、色有(rūpabhava)、無色有(arūpabhava)である。比丘たちよ、これを三有となす。
三 比丘たちよ、この三有を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七一] 第五 苦
二 比丘たちよ、三苦がある。何を三となすのか。苦苦(dukkhadukkhatā)、行苦(saṅkhāradukkhatā)、壊苦(vipariṇāmadukkhatā、変易、変化、変壊の苦)である。比丘たちよ、これを三苦となす。
三 比丘たちよ、この三苦をを勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七二] 第六 礙
二 比丘たちよ、三碍(khila、碍、頑固、荒地、蕪心)がある。何を三となすのか。貪碍、瞋碍、癡碍である。比丘たちよ、これを三碍となす。
三 比丘たちよ、この三碍を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七三] 第七 垢
二 比丘たちよ、三垢(mala、垢、垢穢)がある。何を三となすのか。貪垢、瞋垢、癡垢である。比丘たちよ、これを三垢となす。
三 比丘たちよ、この三垢を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七四] 第八 揺
二 比丘たちよ、三破壊(nīgha、悩乱、激情;殺、破壊)がある。何を三となすのか。貪破壊、瞋破壊、癡破壊である。比丘たちよ、これを三破壊となす。
三 比丘たちよ、この三破壊を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七五] 第九 受
二 比丘たちよ、三受がある。何を三となすのか。楽受・苦受・不苦不楽受である。比丘たちよ、これを三受となす。
三 比丘たちよ、この三受を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七六] 第一〇 渇愛
二 比丘たちよ、三愛がある。何を三となすのか。欲愛(kāmataṇhā)、有愛(bhavataṇhā)、無有愛(vibhavataṇhā)である。比丘たちよ、これを三愛となす。
三 比丘たちよ、この三愛を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
第七 尋覓品
[摂頌]
(一)尋覓と、(二)次第と、(三)漏と、
(四)有と、(五)三苦と、
(六)礙と、(七)垢と、(八)揺と、
(九)受と、(一〇)渇愛と。
第八 暴流品
[七七] 第一 暴流
二 比丘たちよ、四暴流(ogha、暴流、流、洪水)がある。何を四となすのか。欲暴流(kāmogha)、有暴流(bhavogha)、見暴流(diṭṭhogha)、無明暴流(avijjogha)である。比丘たちよ、これを四暴流となす。
三 比丘たちよ、この四暴流を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七八] 第二 軛
二 比丘たちよ、四軛(yoga、軛、束縛、繋縛;結合、関係;瑜伽、瞑想、観行、修行、努力)がある。何を四となすのか。欲軛(kāmayoga)、有軛(bhavayoga)、見軛(diṭṭhiyoga)、無明軛(avijjāyoga)である。比丘たちよ、これを四軛となす。
三 比丘たちよ、この四軛を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七九] 第三 取
二 比丘たちよ、四取(upādāna、取、取著、執着)がある。何を四となすのか。欲取(kāmupādāna)、見取(diṭṭhupādāna)、戒禁取(sīlabbatupādāna)、我語取(attavādupādāna)である。比丘たちよ、これを四取となす。
三 比丘たちよ、この四取を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八〇] 第四 繋
二 比丘たちよ、四繋(gantha、縛、繋、繋縛[ganthati、縛る、結ぶ、調合する、編集する])がある。何を四となすのか。貪求という身繋(abhijjhā kāyagantha)、瞋という身繋(byāpādo kāyagantha)、戒禁取という身繋(sīlabbataparāmāso kāyagantha)、この実執という身繋(idaṃsaccābhiniveso kāyagantha、idaṃこのsacca真実、諦abhinivesa執持、現貪、執着[nivesa、住居、住著])である。比丘たちよ、これを四繋となす。
三 比丘たちよ、この四繋を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八一] 第五 随眠
二 比丘たちよ、七随眠(anusaya、随眠、煩悩、使[anuseti、随眠する、随増する、潜在する])がある。何を七となすのか。欲貪随眠(kāmarāgānusaya)、瞋随眠(paṭighānusaya、対碍随眠)、見随眠(diṭṭhānusaya)、疑随眠(vicikicchānusaya)、慢随眠(mānānusaya)、有貪随眠(bhavarāgānusaya)、無明随眠(avijjānusaya)である。これを七随眠となす。
三 比丘たちよ、この七随眠を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八二] 第六 妙欲
二 比丘たちよ、五妙欲(pañca kāmaguṇā)がある。何を五となすのか。眼で識られるべき色(cakkhuviññeyyā rūpa)の可楽(iṭṭha)、可愛(kanta)、可意(manāpa)、愛色(piyarūpa)、欲を伴い(kāmūpasaṃhita)、染められるべきもの(rajanīya)、耳で識られるべき声(sotaviññeyyā sadda)・・・・・・鼻で識られるべき香(ghānaviññeyyā gandha)・・・・・・舌で識られるべき味(jivhāviññeyyā rasa)・・・・・・身で識られるべき触れられるべきもの(kāyaviññeyyā phoṭṭhabba)の可楽、可愛、可意、愛色、欲を伴い、染められるべきものである。
三 比丘たちよ、この五妙欲を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八三] 第七 蓋
二 比丘たちよ、五蓋(nīvaraṇa)がある。何を五となすのか。欲意欲蓋(kāmacchandanīvaraṇa)、瞋恚蓋(byāpādanīvaraṇa)、惛眠蓋(thinamiddhanīvaraṇa)、掉悔蓋(uddhaccakukkuccanīvaraṇa)、疑蓋(vicikicchānīvaraṇa)である。
三 比丘たちよ、この五蓋を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八四] 第八 蘊
二 比丘たちよ、五取蘊がある。何を五となすのか。色取蘊(rūpupādānakkhandha)、受取蘊(vedanupādānakkhandha)、想取蘊(saññupādānakkhandha)、行取蘊(saṅkhārupādānakkhandha)、識取蘊(viññāṇupādānakkhandha)である。比丘たちよ、これを五取蘊となす。
三 比丘たちよ、この五取蘊を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八五] 第九 下分
二 比丘たちよ、五の下分結がある。何を五となすのか。有身見(sakkāyadiṭṭhi)、疑(vicikicchā)、戒禁取(sīlabbataparāmāsa)、欲への意欲(kāmacchanda)、瞋恚(byāpāda)である。比丘たちよ、これを五下分結となす。
三 比丘たちよ、この五下分結を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八六] 第一〇 上分
(第一 証知)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色への貪り(rūparāga)、無色への貪り(arūparāga)、慢(māna)、掉挙(uddhacca)、無明(avijjā)である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を勝智するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を勝智するために四神足を修習するべきである。
(第二 遍知)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色貪、無色貪、慢、掉挙、無明である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を遍知するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を遍知するために四神足を修習するべきである。
(第三 遍尽)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色貪、無色貪、慢、掉挙、無明である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
ある。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を遍尽するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を遍尽するために四神足を修習するべきである。
(第四 断)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色貪、無色貪、慢、掉挙、無明である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
ある。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を断つために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を断つために四神足を修習するべきである。
[摂頌]
(一)暴流と、(二)軛と、(三)取と、
(四)繋と、(五)随眠と、
(六)妙欲と、(七)蓋と、
(八)蘊と、(九、一〇)上下分と。
第七 神足相応[畢]」
『南伝大蔵経16下 相応部経典6』大蔵出版 P153–155
「神足相応」 完
「 第七 尋覓品
[六七] 第一 尋覓
(第一 勝智)
二 比丘たちよ、三つの尋求(esanā)がある。何を三となすのか。欲尋求(kāmesanā)、有尋求(bhavesanā)、梵行尋求(brahmacariyesanā)である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を勝智(abhiññā)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を勝智するために四神足を修習するべきである。
(第二 遍知)
四 比丘たちよ、三つの尋求がある。何を三となすのか。欲尋求、有尋求、梵行尋求である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を遍知(pariññā)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
五 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を遍知するために四神足を修習するべきである。
(第三 遍尽)
六 比丘たちよ、三つの尋求がある。何を三となすのか。欲尋求、有尋求、梵行尋求である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を遍尽(parikkaya、遍く尽きる、完全に尽きる)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
七 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を遍尽するために四神足を修習するべきである。
(第四 断)
八 比丘たちよ、三つの尋求がある。何を三となすのか。欲尋求、有尋求、梵行尋求である。比丘たちよ、これを三つの尋求となす。
比丘たちよ、この三つの尋求を断じる(pahāna)するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
九 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三つの尋求を断じるために四神足を修習するべきである。
[六八] 第二 次第
二 比丘たちよ、三次第(vidhā、種、種類、次第;慢、慢類)がある。何を三となすのか。「私は優れている」という次第と、「私は等しい」という次第と、「私は劣っている」という次第である。比丘たちよ、これを三次第となす。
三 比丘たちよ、この三次第を勝智するために・・・・・・遍知するために・・・・・・遍尽するために・・・・・・断じるために四神足を修習すべきである。何を四神足となすのか。
四 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三次第を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習するべきである。
[六九] 第三 漏
二 比丘たちよ、三漏がある。何を三となすのか。欲漏(kāmāsava)、有漏(bhavāsava)、無明漏(avijjāsava)である。比丘たちよ、これを三漏となす。
三 比丘たちよ、この三漏を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである。何を四神足をなすのか。
四 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲・・・勤・・・心・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この三漏を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習するべきである。
[七〇] 第四 有
二 比丘たちよ、三有がある。何を三となすのか。欲有(kāmabhava)、色有(rūpabhava)、無色有(arūpabhava)である。比丘たちよ、これを三有となす。
三 比丘たちよ、この三有を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七一] 第五 苦
二 比丘たちよ、三苦がある。何を三となすのか。苦苦(dukkhadukkhatā)、行苦(saṅkhāradukkhatā)、壊苦(vipariṇāmadukkhatā、変易、変化、変壊の苦)である。比丘たちよ、これを三苦となす。
三 比丘たちよ、この三苦をを勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七二] 第六 礙
二 比丘たちよ、三碍(khila、碍、頑固、荒地、蕪心)がある。何を三となすのか。貪碍、瞋碍、癡碍である。比丘たちよ、これを三碍となす。
三 比丘たちよ、この三碍を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七三] 第七 垢
二 比丘たちよ、三垢(mala、垢、垢穢)がある。何を三となすのか。貪垢、瞋垢、癡垢である。比丘たちよ、これを三垢となす。
三 比丘たちよ、この三垢を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七四] 第八 揺
二 比丘たちよ、三破壊(nīgha、悩乱、激情;殺、破壊)がある。何を三となすのか。貪破壊、瞋破壊、癡破壊である。比丘たちよ、これを三破壊となす。
三 比丘たちよ、この三破壊を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七五] 第九 受
二 比丘たちよ、三受がある。何を三となすのか。楽受・苦受・不苦不楽受である。比丘たちよ、これを三受となす。
三 比丘たちよ、この三受を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七六] 第一〇 渇愛
二 比丘たちよ、三愛がある。何を三となすのか。欲愛(kāmataṇhā)、有愛(bhavataṇhā)、無有愛(vibhavataṇhā)である。比丘たちよ、これを三愛となす。
三 比丘たちよ、この三愛を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
第七 尋覓品
[摂頌]
(一)尋覓と、(二)次第と、(三)漏と、
(四)有と、(五)三苦と、
(六)礙と、(七)垢と、(八)揺と、
(九)受と、(一〇)渇愛と。
第八 暴流品
[七七] 第一 暴流
二 比丘たちよ、四暴流(ogha、暴流、流、洪水)がある。何を四となすのか。欲暴流(kāmogha)、有暴流(bhavogha)、見暴流(diṭṭhogha)、無明暴流(avijjogha)である。比丘たちよ、これを四暴流となす。
三 比丘たちよ、この四暴流を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七八] 第二 軛
二 比丘たちよ、四軛(yoga、軛、束縛、繋縛;結合、関係;瑜伽、瞑想、観行、修行、努力)がある。何を四となすのか。欲軛(kāmayoga)、有軛(bhavayoga)、見軛(diṭṭhiyoga)、無明軛(avijjāyoga)である。比丘たちよ、これを四軛となす。
三 比丘たちよ、この四軛を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[七九] 第三 取
二 比丘たちよ、四取(upādāna、取、取著、執着)がある。何を四となすのか。欲取(kāmupādāna)、見取(diṭṭhupādāna)、戒禁取(sīlabbatupādāna)、我語取(attavādupādāna)である。比丘たちよ、これを四取となす。
三 比丘たちよ、この四取を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八〇] 第四 繋
二 比丘たちよ、四繋(gantha、縛、繋、繋縛[ganthati、縛る、結ぶ、調合する、編集する])がある。何を四となすのか。貪求という身繋(abhijjhā kāyagantha)、瞋という身繋(byāpādo kāyagantha)、戒禁取という身繋(sīlabbataparāmāso kāyagantha)、この実執という身繋(idaṃsaccābhiniveso kāyagantha、idaṃこのsacca真実、諦abhinivesa執持、現貪、執着[nivesa、住居、住著])である。比丘たちよ、これを四繋となす。
三 比丘たちよ、この四繋を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八一] 第五 随眠
二 比丘たちよ、七随眠(anusaya、随眠、煩悩、使[anuseti、随眠する、随増する、潜在する])がある。何を七となすのか。欲貪随眠(kāmarāgānusaya)、瞋随眠(paṭighānusaya、対碍随眠)、見随眠(diṭṭhānusaya)、疑随眠(vicikicchānusaya)、慢随眠(mānānusaya)、有貪随眠(bhavarāgānusaya)、無明随眠(avijjānusaya)である。これを七随眠となす。
三 比丘たちよ、この七随眠を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八二] 第六 妙欲
二 比丘たちよ、五妙欲(pañca kāmaguṇā)がある。何を五となすのか。眼で識られるべき色(cakkhuviññeyyā rūpa)の可楽(iṭṭha)、可愛(kanta)、可意(manāpa)、愛色(piyarūpa)、欲を伴い(kāmūpasaṃhita)、染められるべきもの(rajanīya)、耳で識られるべき声(sotaviññeyyā sadda)・・・・・・鼻で識られるべき香(ghānaviññeyyā gandha)・・・・・・舌で識られるべき味(jivhāviññeyyā rasa)・・・・・・身で識られるべき触れられるべきもの(kāyaviññeyyā phoṭṭhabba)の可楽、可愛、可意、愛色、欲を伴い、染められるべきものである。
三 比丘たちよ、この五妙欲を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八三] 第七 蓋
二 比丘たちよ、五蓋(nīvaraṇa)がある。何を五となすのか。欲意欲蓋(kāmacchandanīvaraṇa)、瞋恚蓋(byāpādanīvaraṇa)、惛眠蓋(thinamiddhanīvaraṇa)、掉悔蓋(uddhaccakukkuccanīvaraṇa)、疑蓋(vicikicchānīvaraṇa)である。
三 比丘たちよ、この五蓋を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八四] 第八 蘊
二 比丘たちよ、五取蘊がある。何を五となすのか。色取蘊(rūpupādānakkhandha)、受取蘊(vedanupādānakkhandha)、想取蘊(saññupādānakkhandha)、行取蘊(saṅkhārupādānakkhandha)、識取蘊(viññāṇupādānakkhandha)である。比丘たちよ、これを五取蘊となす。
三 比丘たちよ、この五取蘊を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八五] 第九 下分
二 比丘たちよ、五の下分結がある。何を五となすのか。有身見(sakkāyadiṭṭhi)、疑(vicikicchā)、戒禁取(sīlabbataparāmāsa)、欲への意欲(kāmacchanda)、瞋恚(byāpāda)である。比丘たちよ、これを五下分結となす。
三 比丘たちよ、この五下分結を勝智・・・遍知・・・遍尽・・・断じるために四神足を修習すべきである・・・・・・
[八六] 第一〇 上分
(第一 証知)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色への貪り(rūparāga)、無色への貪り(arūparāga)、慢(māna)、掉挙(uddhacca)、無明(avijjā)である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を勝智するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を勝智するために四神足を修習するべきである。
(第二 遍知)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色貪、無色貪、慢、掉挙、無明である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を遍知するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を遍知するために四神足を修習するべきである。
(第三 遍尽)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色貪、無色貪、慢、掉挙、無明である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
ある。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を遍尽するために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を遍尽するために四神足を修習するべきである。
(第四 断)
二 比丘たちよ、五の上分結がある。何を五となすのか。色貪、無色貪、慢、掉挙、無明である。比丘たちよ、これを五上分結となす。
ある。比丘たちよ、これを五上分結となす。
比丘たちよ、この五上分結を断つために四神足を修習するべきである。何を四神足となすのか。
三 比丘たちよ、ここに比丘がいて欲三摩地勤行成就の神足を修習し、勤三摩地・・・・・・心三摩地・・・・・・観三摩地勤行成就の神足を修習する。比丘たちよ、この五上分結を断つために四神足を修習するべきである。
[摂頌]
(一)暴流と、(二)軛と、(三)取と、
(四)繋と、(五)随眠と、
(六)妙欲と、(七)蓋と、
(八)蘊と、(九、一〇)上下分と。
第七 神足相応[畢]」
『南伝大蔵経16下 相応部経典6』大蔵出版 P153–155
「神足相応」 完
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏典 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏典のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90029人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6414人
- 3位
- 独り言
- 9044人