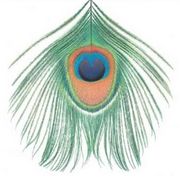XTCは、「Apple Venus Vol.1」をリリースしたのが1999年、
前作「ノンサッチ」から実に7年の歳月が経過しております。
ご承知のように、ヴァージン・レコードとの対立とストライキ、新レーベル立ち上げ、レコーディングなどの様々な出来事があったのですが、
一口に7年と言っても、これがXTCのキャリアにおいてどれだけ異常な事態であったか、次のディスコグラフィーをご覧ください。
私自身は、「オレンジズ&レモンズ」からのリスナーなので、
新作「ノンサッチ」が発売されることを、
約3年間、首を長くして待っていたのを思い出します。
<1> 「ホワイト・ミュージック」 … 1978年
<2> 「Go 2」 … 1978年
<3> 「ドラムズ・アンド・ワイアーズ」… 1979年
<4> 「ブラック・シー」 … 1980年
<5> 「イングリッシュ・セツルメント」 … 1982年
<6> 「ママー」 … 1983年
<7> 「ザ・ビッグ・エキスプレス」 … 1984年
<8> 「スカイラーキング」 … 1986年
<9> 「オレンジズ&レモンズ」 … 1989年
<10> 「ノンサッチ」 … 1992年
<11> 「アップル・ヴィーナス Vol.1」 … 1999年
<12> 「ワスプ・スター」 … 2000年
次からは、
<10 ノンサッチ>リリース後から、
アンディ、コリンの動きを中心に、「アップル・ヴィーナスシリーズ」をレコーディングするまでの長い道のりについて書いていきます。
前作「ノンサッチ」から実に7年の歳月が経過しております。
ご承知のように、ヴァージン・レコードとの対立とストライキ、新レーベル立ち上げ、レコーディングなどの様々な出来事があったのですが、
一口に7年と言っても、これがXTCのキャリアにおいてどれだけ異常な事態であったか、次のディスコグラフィーをご覧ください。
私自身は、「オレンジズ&レモンズ」からのリスナーなので、
新作「ノンサッチ」が発売されることを、
約3年間、首を長くして待っていたのを思い出します。
<1> 「ホワイト・ミュージック」 … 1978年
<2> 「Go 2」 … 1978年
<3> 「ドラムズ・アンド・ワイアーズ」… 1979年
<4> 「ブラック・シー」 … 1980年
<5> 「イングリッシュ・セツルメント」 … 1982年
<6> 「ママー」 … 1983年
<7> 「ザ・ビッグ・エキスプレス」 … 1984年
<8> 「スカイラーキング」 … 1986年
<9> 「オレンジズ&レモンズ」 … 1989年
<10> 「ノンサッチ」 … 1992年
<11> 「アップル・ヴィーナス Vol.1」 … 1999年
<12> 「ワスプ・スター」 … 2000年
次からは、
<10 ノンサッチ>リリース後から、
アンディ、コリンの動きを中心に、「アップル・ヴィーナスシリーズ」をレコーディングするまでの長い道のりについて書いていきます。
|
|
|
|
コメント(29)
(2)「ノンサッチ」と「Apple Venus Vol.1」の関連性について
XTCは、アルバムをレコーディングする際に、それぞれ仮のタイトルをつけております。
詳しくは、「ソング・ストーリーズ」を参照いただければ分かりますが、
アンディは、1991年までに新しいアルバムを書き上げており、
その時点では『ザ・ラスト・バルーン』と名付けておりました。
後に、「ノンサッチ」に変更されました。(ソング・ストーリーズ:P379)
アルバム・ジャケットについて、ジュール・ヴェルヌを思わせる、
50年代の架空のミュージカル・ジャケットを思わせるようにしたかったのですが、
CDジャケットでは見栄えがせず、中止となり、
あの「宮殿」ジャケットになりました。(ソング・ストーリーズ:P 390)
「ラスト…」と名前をつけると、「バンドとして最後の…」と連想されるので却下されましたが、
この時点で「Vol.1」のエンディングを飾る、あの名曲のタイトルが登場してます!
(参照:「Apple Venus Vol.1」は『ヒストリー・オヴ・ミドル・エイジ』と仮タイトルがついておりました。(ソング・ストーリーズ:P 425)
XTCは、アルバムをレコーディングする際に、それぞれ仮のタイトルをつけております。
詳しくは、「ソング・ストーリーズ」を参照いただければ分かりますが、
アンディは、1991年までに新しいアルバムを書き上げており、
その時点では『ザ・ラスト・バルーン』と名付けておりました。
後に、「ノンサッチ」に変更されました。(ソング・ストーリーズ:P379)
アルバム・ジャケットについて、ジュール・ヴェルヌを思わせる、
50年代の架空のミュージカル・ジャケットを思わせるようにしたかったのですが、
CDジャケットでは見栄えがせず、中止となり、
あの「宮殿」ジャケットになりました。(ソング・ストーリーズ:P 390)
「ラスト…」と名前をつけると、「バンドとして最後の…」と連想されるので却下されましたが、
この時点で「Vol.1」のエンディングを飾る、あの名曲のタイトルが登場してます!
(参照:「Apple Venus Vol.1」は『ヒストリー・オヴ・ミドル・エイジ』と仮タイトルがついておりました。(ソング・ストーリーズ:P 425)
(3)「ノンサッチ」から「Apple Venus Vol.1」への流れについて
アンディは「ノンサッチ」について、2001年のインタビューでこう振り返っています。
「今の僕なら、もう少し違った作品にしてみたと思う。
いろんなスタイルを盛り込みすぎたかな。
タイプのはっきり異なる2枚のアルバムが作られていたかも知れない。」
これは、「ラップド・イン・グレイ」「ルック」と、
「ザ・バラッド・オブ・ピーター・パンプキンヘッド」「クロコダイル」と対比して述べてます。(ロッキング・オン:2001.5)
アンディは前2曲の方に傾倒しており、
アレンジにおいては、それぞれ、
デイヴ・グレゴリーが重要な働きをしております。
「ラップド・イン・グレイ」では、デイヴが弦楽器をアレンジし、
「ルック」で、デイヴが自らピアノ、シンセを弾き、オーケストラの指揮、
アレンジメント、弦楽四重奏を担当しました。(ソング・ストーリーズ:P400-405)
また、「ノンサッチ」リリース後、次のような発言がありました。
「僕の父はドラマーで、僕もドラマーになりたかった。
最初に考えるのはリズムで、その後にメロディなんだ。
エスニックな要素を含めて、ずっとリズムやパーカッションの実験に魅力を感じてきた。けれども、今の音楽においてはドラムスという楽器は支配的過ぎるから、
今度はドラム抜きのレコードを作ってみたいと考えている。」(クロスビート:1992.11)
まさに、次のアルバムとのミッシングリンクとも受け取れます。
リズムを最初に考えて作曲する人が、
あえてドラムを抜きで作曲するというところに、
「Apple Venus Vol.1」の特異性があらわれていると思います。
そしてもうひとつの到達点として、「ワスプ・スター」に至るのだ、ということです。
アンディは「ノンサッチ」について、2001年のインタビューでこう振り返っています。
「今の僕なら、もう少し違った作品にしてみたと思う。
いろんなスタイルを盛り込みすぎたかな。
タイプのはっきり異なる2枚のアルバムが作られていたかも知れない。」
これは、「ラップド・イン・グレイ」「ルック」と、
「ザ・バラッド・オブ・ピーター・パンプキンヘッド」「クロコダイル」と対比して述べてます。(ロッキング・オン:2001.5)
アンディは前2曲の方に傾倒しており、
アレンジにおいては、それぞれ、
デイヴ・グレゴリーが重要な働きをしております。
「ラップド・イン・グレイ」では、デイヴが弦楽器をアレンジし、
「ルック」で、デイヴが自らピアノ、シンセを弾き、オーケストラの指揮、
アレンジメント、弦楽四重奏を担当しました。(ソング・ストーリーズ:P400-405)
また、「ノンサッチ」リリース後、次のような発言がありました。
「僕の父はドラマーで、僕もドラマーになりたかった。
最初に考えるのはリズムで、その後にメロディなんだ。
エスニックな要素を含めて、ずっとリズムやパーカッションの実験に魅力を感じてきた。けれども、今の音楽においてはドラムスという楽器は支配的過ぎるから、
今度はドラム抜きのレコードを作ってみたいと考えている。」(クロスビート:1992.11)
まさに、次のアルバムとのミッシングリンクとも受け取れます。
リズムを最初に考えて作曲する人が、
あえてドラムを抜きで作曲するというところに、
「Apple Venus Vol.1」の特異性があらわれていると思います。
そしてもうひとつの到達点として、「ワスプ・スター」に至るのだ、ということです。
(4)「Apple Venus」が「シリーズ」になった理由
「Apple Venus」が「シリーズ」になった理由として、
「持っている曲が40曲あり、93年にはオーケストラ・アルバム、
95年にはギター・アルバムが出る予定だった。
まさに『二つの頭を持つ怪物』だ。(「ソング・ストーリーズ」)」とあり、
当初から2枚ばらばらにリリースする予定だったようです。
しかし、「Apple Venus」はアコースティックとエレクトリックで、
『表と裏で1枚のコイン』であるため、
2枚組みのリリースも検討されておりましたが、
様々な事情から、断念します。
資金面のことについて、こちらで触れております。
http://4xtc.blog8.fc2.com/blog-entry-59.html
また、バンド内でも意見が分かれました。
「新マネージャーであるポール・ベイリーは
クッキング・ヴァイナルと新しい契約を結ぶまでに、
アンディは2枚のアルバムを一緒にして、
2枚組みとして出すと考えていたが、コリンとデイヴは反対だった。
結果として分割して発表することになった。」
(ソング・ストーリーズP417)とあります。
そして、「Apple Venus Vol.1」は1999年2月にリリースされました。
「Apple Venus」が「シリーズ」になった理由として、
「持っている曲が40曲あり、93年にはオーケストラ・アルバム、
95年にはギター・アルバムが出る予定だった。
まさに『二つの頭を持つ怪物』だ。(「ソング・ストーリーズ」)」とあり、
当初から2枚ばらばらにリリースする予定だったようです。
しかし、「Apple Venus」はアコースティックとエレクトリックで、
『表と裏で1枚のコイン』であるため、
2枚組みのリリースも検討されておりましたが、
様々な事情から、断念します。
資金面のことについて、こちらで触れております。
http://4xtc.blog8.fc2.com/blog-entry-59.html
また、バンド内でも意見が分かれました。
「新マネージャーであるポール・ベイリーは
クッキング・ヴァイナルと新しい契約を結ぶまでに、
アンディは2枚のアルバムを一緒にして、
2枚組みとして出すと考えていたが、コリンとデイヴは反対だった。
結果として分割して発表することになった。」
(ソング・ストーリーズP417)とあります。
そして、「Apple Venus Vol.1」は1999年2月にリリースされました。
(5)「Apple Venus」が「シリーズ」になった効果
アコースティック編(Vol.1)を先に出すことになった理由として、
アンディは「久しぶりにアルバムを出すので、
最初は目新しいものがいいかと思った。
今までとは少し違ったものをだしてみたかった。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
とあります。
そして、立て続けに「Vol.2」を発表しよういう計画がありました。
「2000年になる前にいろんながらくたが出てくるだろうから、
それに紛れるのもイヤなので、2000年頭には出そうと思っている。
西暦2000年にかこつけたクズが山ほど出てくるに決まってる。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
とアンディは言っておりましたが、
結局、発売されたのは2000年5月です。
このことについて、アンディは、
「今から考えれば、1つにして大きく出すよりも、
2つにしてちょこちょこと出したほうが正解だったかな、と思う。」
(ストレンジ・デイズ2000年7月号)と答えております。
確かに、分割することでプロモーションも2倍になりますから、
宣伝にもお金がかかるのでしょうが、
その分、インタビューなどの機会が増えるので、
私としては嬉しい限りです。
アコースティック編(Vol.1)を先に出すことになった理由として、
アンディは「久しぶりにアルバムを出すので、
最初は目新しいものがいいかと思った。
今までとは少し違ったものをだしてみたかった。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
とあります。
そして、立て続けに「Vol.2」を発表しよういう計画がありました。
「2000年になる前にいろんながらくたが出てくるだろうから、
それに紛れるのもイヤなので、2000年頭には出そうと思っている。
西暦2000年にかこつけたクズが山ほど出てくるに決まってる。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
とアンディは言っておりましたが、
結局、発売されたのは2000年5月です。
このことについて、アンディは、
「今から考えれば、1つにして大きく出すよりも、
2つにしてちょこちょこと出したほうが正解だったかな、と思う。」
(ストレンジ・デイズ2000年7月号)と答えております。
確かに、分割することでプロモーションも2倍になりますから、
宣伝にもお金がかかるのでしょうが、
その分、インタビューなどの機会が増えるので、
私としては嬉しい限りです。
あんー・・・>12:自己レス
インスト盤ですね。聴きました・・・
この日本語の紙があるから良いような・・・
でもわたくし専門家でもないので意味がわからなかったりしますけどね。
最初の文章で誰が書いたのか?と思いましたら
A・パートリッジ本人なのですね。
普通でもややこしい表現なので訳すの大変ですね。
なんとなく分かるのはデイブがどーのこーのというとこですね〜
>13:tetsuさんのバトンの同列の方も覗きに行かしてもらいました!
招待されたので・・・!違?^^;
このバトン、人の読むとすごい発見ありますね〜・・・!
思っても見なかった意外!とか気が付かなかった点とか・・・
ほんの一部ですが総合的な印象、そうでない印象とか・・・
面白い面白い。する人みんなのバトン見に行きたいです。
足跡下さい!
面白いです。
「ワスプ〜」あまり聴いてなかったり・・・
2枚組の1枚ですね。「アップル〜」では気にならなかったけど
「ワスプ〜」ではデイブ居ないってことですよね〜
コレも人のバトンで気が付いたのですが・・・
インスト盤ですね。聴きました・・・
この日本語の紙があるから良いような・・・
でもわたくし専門家でもないので意味がわからなかったりしますけどね。
最初の文章で誰が書いたのか?と思いましたら
A・パートリッジ本人なのですね。
普通でもややこしい表現なので訳すの大変ですね。
なんとなく分かるのはデイブがどーのこーのというとこですね〜
>13:tetsuさんのバトンの同列の方も覗きに行かしてもらいました!
招待されたので・・・!違?^^;
このバトン、人の読むとすごい発見ありますね〜・・・!
思っても見なかった意外!とか気が付かなかった点とか・・・
ほんの一部ですが総合的な印象、そうでない印象とか・・・
面白い面白い。する人みんなのバトン見に行きたいです。
足跡下さい!
面白いです。
「ワスプ〜」あまり聴いてなかったり・・・
2枚組の1枚ですね。「アップル〜」では気にならなかったけど
「ワスプ〜」ではデイブ居ないってことですよね〜
コレも人のバトンで気が付いたのですが・・・
(6)インストゥルメンタル・ヴァージョンについて
せっかくですから、インストゥルメンタル・ヴァージョンについて。
「Apple Venus Vol.1」のインストゥルメンタル・ヴァージョンとして、
”Instruvenus” が製作されました。
イギリスと日本のみのリリースです。
「チョークヒルズ」サイトでは、「カラオケ・ヴァージョン」と紹介されておりますが、
解説を見ると、インストゥルメンタル用にミックスしており、
単に「ヴォーカル抜き」というわけではないようです。
そもそも、このアルバムを製作することについて、アンディはこう述べております。
「『アップル・ヴィーナス』をレコーディングしたときに、
全曲インストゥルメンタル・ミックスを作っていた。
その時点ではアルバムとしてリリースするつもりはなかったが、
『出さないのか』と聞いてくる人が結構いて、興味がわいた。」
(ロッキング・オン2001年3月号)
そして、続けて「Wasp Star」のインストゥルメンタル・ヴァージョンとして、
” Waspstrumental” がリリースされます。
「『アップル・ヴィーナス』シリーズはこれで
(注:インストアルバムを出したことで)完結したと考えたい。
もう一度過去に戻るということをしたくなかった。
今後は「アップル・ヴィーナス」から離れて、新しいものを作りたいと思っている。」
(ストレンジ・デイズ2002年11月号)
過去にこだわらない、アンディの決意が感じられます。
それは、「Fuzzy Warbles」シリーズにも通じるものがあります。
参考:
“Instruvenus”
http://chalkhills.org/reelbyreal/a_AppleVenusV1.html#instru
“Waspstrumental”
http://chalkhills.org/reelbyreal/a_WaspStar.html#mental
せっかくですから、インストゥルメンタル・ヴァージョンについて。
「Apple Venus Vol.1」のインストゥルメンタル・ヴァージョンとして、
”Instruvenus” が製作されました。
イギリスと日本のみのリリースです。
「チョークヒルズ」サイトでは、「カラオケ・ヴァージョン」と紹介されておりますが、
解説を見ると、インストゥルメンタル用にミックスしており、
単に「ヴォーカル抜き」というわけではないようです。
そもそも、このアルバムを製作することについて、アンディはこう述べております。
「『アップル・ヴィーナス』をレコーディングしたときに、
全曲インストゥルメンタル・ミックスを作っていた。
その時点ではアルバムとしてリリースするつもりはなかったが、
『出さないのか』と聞いてくる人が結構いて、興味がわいた。」
(ロッキング・オン2001年3月号)
そして、続けて「Wasp Star」のインストゥルメンタル・ヴァージョンとして、
” Waspstrumental” がリリースされます。
「『アップル・ヴィーナス』シリーズはこれで
(注:インストアルバムを出したことで)完結したと考えたい。
もう一度過去に戻るということをしたくなかった。
今後は「アップル・ヴィーナス」から離れて、新しいものを作りたいと思っている。」
(ストレンジ・デイズ2002年11月号)
過去にこだわらない、アンディの決意が感じられます。
それは、「Fuzzy Warbles」シリーズにも通じるものがあります。
参考:
“Instruvenus”
http://chalkhills.org/reelbyreal/a_AppleVenusV1.html#instru
“Waspstrumental”
http://chalkhills.org/reelbyreal/a_WaspStar.html#mental
(7)デモについて(アンディの場合)
ご存知のように、XTCはレコーディング前にデモを製作しております。
これは「Apple Venus」シリーズに限ることではなく、過去のアルバム製作について、
概ね次のようなスタイルをとっております。
? 作曲
? ホーム・デモ製作
? ?について、プロデューサーと協議、もしくはスタジオで投票
? スタジオ録音
デモを作る理由の一つに、『スタジオレンタル期間の短縮による経費節減』があげられます。
つまり、作詞・作曲した状態でスタジオに持ち込み、そこから曲を組み立てるよりも、
ある程度形にした上で、スタジオでレコーディングした方が早く済むというものです。
しかし、それらの努力にもかかわらず、予算オーバーに追い込まれることもたびたび。
これらについては、「ソング・ストーリーズ」等で触れております。
アンディは「じっくりと」デモを製作する傾向があります。
「詳細はほぼデモ段階で計画が立てられ、決定が下され、準備がなされる。
即興はごくわずかで、95%近くは、各パーツの準備と組み合わせの作業だ。
各パーツが役割を果たし、互いに機能してこそ、動きがうまれる。
時計・タンスを作るのと似ている。」(クロスビート 1999年3月号)
「僕たちの作業は時計作りみたいなものだ。
時計職人はインプロバイズしない。
それぞれの歯車がしっかりかみ合うように、
決まった工程で綿密に組み立てているだろう?
スタジオでの作業が事前に把握できていれば、
スタジオでの貴重な時間の節約、ひいては予算の節約にもなる。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
また、XTCのレコーディングは『職人芸』と評されますが、
これについてアンディはこう言っております。
「今はそれが正しくなりつつある。
自分がそれを職業として選んだとき、すっかりのめり込んで、
そのディティールに役割を果たすことに歓びを感じるというものだ。
椅子やテーブルを作るのに似て、
役割を果たし、美しく、きちんと細部まで精巧でなければならない。」
(プレイヤー1999年4月号)
ご存知のように、XTCはレコーディング前にデモを製作しております。
これは「Apple Venus」シリーズに限ることではなく、過去のアルバム製作について、
概ね次のようなスタイルをとっております。
? 作曲
? ホーム・デモ製作
? ?について、プロデューサーと協議、もしくはスタジオで投票
? スタジオ録音
デモを作る理由の一つに、『スタジオレンタル期間の短縮による経費節減』があげられます。
つまり、作詞・作曲した状態でスタジオに持ち込み、そこから曲を組み立てるよりも、
ある程度形にした上で、スタジオでレコーディングした方が早く済むというものです。
しかし、それらの努力にもかかわらず、予算オーバーに追い込まれることもたびたび。
これらについては、「ソング・ストーリーズ」等で触れております。
アンディは「じっくりと」デモを製作する傾向があります。
「詳細はほぼデモ段階で計画が立てられ、決定が下され、準備がなされる。
即興はごくわずかで、95%近くは、各パーツの準備と組み合わせの作業だ。
各パーツが役割を果たし、互いに機能してこそ、動きがうまれる。
時計・タンスを作るのと似ている。」(クロスビート 1999年3月号)
「僕たちの作業は時計作りみたいなものだ。
時計職人はインプロバイズしない。
それぞれの歯車がしっかりかみ合うように、
決まった工程で綿密に組み立てているだろう?
スタジオでの作業が事前に把握できていれば、
スタジオでの貴重な時間の節約、ひいては予算の節約にもなる。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
また、XTCのレコーディングは『職人芸』と評されますが、
これについてアンディはこう言っております。
「今はそれが正しくなりつつある。
自分がそれを職業として選んだとき、すっかりのめり込んで、
そのディティールに役割を果たすことに歓びを感じるというものだ。
椅子やテーブルを作るのに似て、
役割を果たし、美しく、きちんと細部まで精巧でなければならない。」
(プレイヤー1999年4月号)
(8)デモについて(コリンの場合)
コリンの場合、アンディとは少し異なります。
コリンの発言から。
「僕はデモを念入りにやるのは好きなほうじゃない。
スタジオ入りしたとき、もし細部まで考えてしまっていると、
これから曲を仕上げようっていう肝心なときに逆に出来が悪かったりする。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1992年6月号)
アンディは、コリンのことをこう見ております。
1曲につき複数のヴァージョンを作る傾向があるか、という質問に対して、
「僕よりコリンのほうがその傾向が強い。
あいつはいつも1曲につきガラリと違うヴァージョンを3〜4個用意する。
僕は自宅で8トラック・デモを作り始めるころは曲のキャラクターが頭の中でほぼ完全にイメージできている。
でもコリンは最後の最後まで確信が持てない。
もっと意外な発見があるんじゃないかと、
いろんな方向に突っつきまわしてみたがるタチなんだ。」
(ロッキング・オン2001年3月号)
確かに、こうしたことを踏まえて過去のデモ音源を聴くと、
アンディの作品には「本番さながらのデモが多い」という感じがあるのに対して、
一方、コリンのデモは「たたき台」の印象を受けます。
結果として「良質なレコーディング」に至るのですから、
これらは二人のアプローチの違いといえるのでしょう。
私個人としては、(作曲数の差で)コリンのデモが少ないことは残念ですし、
上記の「違うヴァージョン」というのを聴いてみたいと切に願います。
また、古い話で恐縮ですが、
15年ほど前に出回ったカセットテープの「スカイラーキング・デモ」は、
(元々音質は悪いのですが)アンディの曲に対してコリン
の方が更に音質が悪かったなあということを思い出しました。
※なお、この「デモ」の話をすると、
将来的には「ホームスパン」や、「ファジー・ウォーブルズ」の
事まで言及しなければいけないのですが、また別の機会にふれようと思います。
コリンの場合、アンディとは少し異なります。
コリンの発言から。
「僕はデモを念入りにやるのは好きなほうじゃない。
スタジオ入りしたとき、もし細部まで考えてしまっていると、
これから曲を仕上げようっていう肝心なときに逆に出来が悪かったりする。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1992年6月号)
アンディは、コリンのことをこう見ております。
1曲につき複数のヴァージョンを作る傾向があるか、という質問に対して、
「僕よりコリンのほうがその傾向が強い。
あいつはいつも1曲につきガラリと違うヴァージョンを3〜4個用意する。
僕は自宅で8トラック・デモを作り始めるころは曲のキャラクターが頭の中でほぼ完全にイメージできている。
でもコリンは最後の最後まで確信が持てない。
もっと意外な発見があるんじゃないかと、
いろんな方向に突っつきまわしてみたがるタチなんだ。」
(ロッキング・オン2001年3月号)
確かに、こうしたことを踏まえて過去のデモ音源を聴くと、
アンディの作品には「本番さながらのデモが多い」という感じがあるのに対して、
一方、コリンのデモは「たたき台」の印象を受けます。
結果として「良質なレコーディング」に至るのですから、
これらは二人のアプローチの違いといえるのでしょう。
私個人としては、(作曲数の差で)コリンのデモが少ないことは残念ですし、
上記の「違うヴァージョン」というのを聴いてみたいと切に願います。
また、古い話で恐縮ですが、
15年ほど前に出回ったカセットテープの「スカイラーキング・デモ」は、
(元々音質は悪いのですが)アンディの曲に対してコリン
の方が更に音質が悪かったなあということを思い出しました。
※なお、この「デモ」の話をすると、
将来的には「ホームスパン」や、「ファジー・ウォーブルズ」の
事まで言及しなければいけないのですが、また別の機会にふれようと思います。
(9)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その1)
「Apple Venus Vol.1」の特徴として、オーケストラの導入があげられます。
私は、1曲目の「リヴァー・オヴ・オーキッズ」の出だしでガツンとやられました。
オーケストラを活用したレコーディングというのは、
決して新しいアイディアというわけではありません。
この時期、一部のレビューでは、
「エルヴィス・コステロに先を越された」という指摘がありました。
同じ時期に、エルヴィス・コステロは、
弦楽四重奏ブロドスキー・クァルテットと協演したアルバム
「ジュリエット・レターズ」を発表しているので、
(XTCとエルヴィス・コステロって、デビューの時期も近いし)
お互いに全く意識していない、というわけではないと思いますが。
ただし、XTCが安易な模倣をするわけも無く、
以前から暖めていたアイデアを実行することにした、
と考えるのが自然だと思います。
「最初のうちはオーケストラを使う曲を作っていた。
ずっとそんなのをやりたいと思っていたから。
でも1年くらいしたらまた飽きてきて、
もっとやかましいエレクトリックな曲を作り始めた。」
(ザ・ディグ1997年5/6月号)
「Apple Venus Vol.1」の特徴として、オーケストラの導入があげられます。
私は、1曲目の「リヴァー・オヴ・オーキッズ」の出だしでガツンとやられました。
オーケストラを活用したレコーディングというのは、
決して新しいアイディアというわけではありません。
この時期、一部のレビューでは、
「エルヴィス・コステロに先を越された」という指摘がありました。
同じ時期に、エルヴィス・コステロは、
弦楽四重奏ブロドスキー・クァルテットと協演したアルバム
「ジュリエット・レターズ」を発表しているので、
(XTCとエルヴィス・コステロって、デビューの時期も近いし)
お互いに全く意識していない、というわけではないと思いますが。
ただし、XTCが安易な模倣をするわけも無く、
以前から暖めていたアイデアを実行することにした、
と考えるのが自然だと思います。
「最初のうちはオーケストラを使う曲を作っていた。
ずっとそんなのをやりたいと思っていたから。
でも1年くらいしたらまた飽きてきて、
もっとやかましいエレクトリックな曲を作り始めた。」
(ザ・ディグ1997年5/6月号)
(10)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その2)
オーケストラのスコアの準備のためマイク・バットが雇われました。
「『グリーンマン』と『アイ・キャント・オウン・ハー』のオーケストラ・アレンジは、
マイク・バットに頼んだ。
『グリーンマン』はできるだけ僕のデモに沿って、
『アイ・キャント・オウン・ハー』はマイクの自由にやってもらった。
1回だけロンドンのスタジオで作業したが、
電話口で彼がピアノを弾き、
僕はそれでいいか、それはちょっと、
などといって短期間で仕上げた。短期間の割にはすばらしいアレンジだ。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
このマイク・バットという人、シンガー・ソングライターであり、
映画や舞台の音楽を担当している人です。
女性4人のストリング・カルテット“ボンド”のファースト・アルバム(の一部)や、
イギリスの子ども番組「ウォンブルズ」のサントラを担当しております。
余談ですが、この「ウォンブルズ・コレクション」(CD2枚組み)、
子ども番組のサントラですが、大人が聴いていて楽しくなるアルバムです。
オーケストラのスコアの準備のためマイク・バットが雇われました。
「『グリーンマン』と『アイ・キャント・オウン・ハー』のオーケストラ・アレンジは、
マイク・バットに頼んだ。
『グリーンマン』はできるだけ僕のデモに沿って、
『アイ・キャント・オウン・ハー』はマイクの自由にやってもらった。
1回だけロンドンのスタジオで作業したが、
電話口で彼がピアノを弾き、
僕はそれでいいか、それはちょっと、
などといって短期間で仕上げた。短期間の割にはすばらしいアレンジだ。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
このマイク・バットという人、シンガー・ソングライターであり、
映画や舞台の音楽を担当している人です。
女性4人のストリング・カルテット“ボンド”のファースト・アルバム(の一部)や、
イギリスの子ども番組「ウォンブルズ」のサントラを担当しております。
余談ですが、この「ウォンブルズ・コレクション」(CD2枚組み)、
子ども番組のサントラですが、大人が聴いていて楽しくなるアルバムです。
>エンジさん
…NHK第一放送ってことは、ラジオですよね。
どんな状況で曲がかかったのでしょうか…
『リスナーからの結婚に関するお悩み相談』の最中とか…
リアルすぎる。
(11)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その3)
オーケストラを導入したアルバムについて、アンディはこう述べております。
「アルバムのシークエンスについて、演劇的なシーンを思い浮かべる。
舞台衣装を着た役者が居て、舞台装置があって。
まぁたしかにヴィジュアルだけど。僕はフェイクが好きなんだ。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
「聞き手がびっくりして『うわー、こんなのモダンすぎてたまらないよー』
なんて右往左往するようなものは作るつもりはない。
とてもオールド・ファッションで曲によっては中世の音楽みたいだったり、
ビクトリア調のクラシック交響楽みたいだったり、
民族音楽みたいだったり、ロックン・ロールみたいだったり、
ミュージカルみたいだったりする。
一貫した音楽形態っていうのはないんだけど、
確かなのはとてもフレンドリーなレコードだっていうことさ。」
(プレイヤー1999年4月号)
『オーケストラを導入』というと、先入観として敷居が高く感じますが、
アルバムを実際に聴くと、すっと耳に入ってきます。
アルバムを製作した結果、とっつきやすい音楽が出来たのではなく、
最初から計算されていたもの、と言えます。
…NHK第一放送ってことは、ラジオですよね。
どんな状況で曲がかかったのでしょうか…
『リスナーからの結婚に関するお悩み相談』の最中とか…
リアルすぎる。
(11)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その3)
オーケストラを導入したアルバムについて、アンディはこう述べております。
「アルバムのシークエンスについて、演劇的なシーンを思い浮かべる。
舞台衣装を着た役者が居て、舞台装置があって。
まぁたしかにヴィジュアルだけど。僕はフェイクが好きなんだ。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
「聞き手がびっくりして『うわー、こんなのモダンすぎてたまらないよー』
なんて右往左往するようなものは作るつもりはない。
とてもオールド・ファッションで曲によっては中世の音楽みたいだったり、
ビクトリア調のクラシック交響楽みたいだったり、
民族音楽みたいだったり、ロックン・ロールみたいだったり、
ミュージカルみたいだったりする。
一貫した音楽形態っていうのはないんだけど、
確かなのはとてもフレンドリーなレコードだっていうことさ。」
(プレイヤー1999年4月号)
『オーケストラを導入』というと、先入観として敷居が高く感じますが、
アルバムを実際に聴くと、すっと耳に入ってきます。
アルバムを製作した結果、とっつきやすい音楽が出来たのではなく、
最初から計算されていたもの、と言えます。
(12)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その4)
XTCはプロデューサーとしてヘイデン・ベンダルを、
エンジニアとしてニック・デイヴスを迎えます。
ヘイデン・ベンダルは、「ソング・ストーリーズ(P418)」によれば、
「1977年に『3D-EP』をレコーディングした。」とありますが、
別なインタビューでは、アンディはこう述べております。
「オーケストラルなレコードを作れる人が条件だった。
彼には『Go2』のときに少しエンジニアリングを頼んだことがあって、
技術的に卓越しているだけでなく、人間的にもやりやすい相手で、
リラックスして作業できた。」と述べております。
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
ヘイデン・ベンダルに対する、アンディの評価は高いです。
「ヘイデンはレコーディングが得意、
エンジニアで参加したニック・デイヴスはミキシングが得意。
ヘイデンは特に本物の楽器のレコーディングがうまい。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
また、コリンも、
「ヘイドン・ベンダルはいい仕事をした。舵取りがうまい」
(ソング・ストーリーズ P424)
とほめております。
XTCはプロデューサーとしてヘイデン・ベンダルを、
エンジニアとしてニック・デイヴスを迎えます。
ヘイデン・ベンダルは、「ソング・ストーリーズ(P418)」によれば、
「1977年に『3D-EP』をレコーディングした。」とありますが、
別なインタビューでは、アンディはこう述べております。
「オーケストラルなレコードを作れる人が条件だった。
彼には『Go2』のときに少しエンジニアリングを頼んだことがあって、
技術的に卓越しているだけでなく、人間的にもやりやすい相手で、
リラックスして作業できた。」と述べております。
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
ヘイデン・ベンダルに対する、アンディの評価は高いです。
「ヘイデンはレコーディングが得意、
エンジニアで参加したニック・デイヴスはミキシングが得意。
ヘイデンは特に本物の楽器のレコーディングがうまい。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
また、コリンも、
「ヘイドン・ベンダルはいい仕事をした。舵取りがうまい」
(ソング・ストーリーズ P424)
とほめております。
(13)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その5)
いよいよレコーディングですが、『お約束』のトラブルがありました。
「レコーディングがスタートしたのは97年後半、
ケントにあるスクィーズのクリス・ディフォードのスタジオ。
テクニック的にひどいスタジオで、何ひとつうまくいかない。
当惑したディフォードは『使用料はタダ』と言ってきたので、
もうちょっとがんばったところ、
彼は突然考えを変えて使用料をよこせといってきた。
断ると、彼は僕たちが作ったテープを全部盗んでしまった。
だから年明けて最初からやり直さなきゃならなかった。」
(プレイヤー1999年4月号)
「ソング・ストーリーズ(P418)」にも、次のような記述があります。
「ヘイドン・ベンダルの(ケントにある)プログラミング用の部屋で、
1、 2週間プリプロダクションを行い、
クリス・ディフォード(スクィーズ)のスタジオに移ったが、
スタジオの準備が出来ておらず、
ほとんどレコーディングが進まないまま、
3週間がたち、スタジオを出た。使用料を要求され、
払うまではテープを渡さないと言われたので、
最初からやり直すことにした。」
しかしXTCはその逆境を乗り越えます。
「大変だったことは、スタートすること(笑)。
しかし、難問を切り抜けるのは結構得意でねえ。
問題というのはいつも何かを教えてくれるものなんだと思っているから、
いろんなことがうまくいかないことによって
自分自身がより良くなっているような気がしている。
プロデューサーが時間切れでも、
デイヴが辞めても不快じゃない。」
(プレイヤー1999年4月号)
「悪かった点はレコーディングを始めるときの恐怖感かな。
とても長い間でも・テープのままで、
どの曲もデモの音にすっかりなれてしまっていたからね。
そしてその慣れてしまった音をレコーディング作業で
どのようにして良くしていくかを考えたわけだ。」
(ストレンジ・デイズ2001年5月号)
これまで、レコーディングの際には様々なトラブルに遭遇したXTCですが、
今回も例に漏れず、それらを乗り越えていきます。
いよいよレコーディングですが、『お約束』のトラブルがありました。
「レコーディングがスタートしたのは97年後半、
ケントにあるスクィーズのクリス・ディフォードのスタジオ。
テクニック的にひどいスタジオで、何ひとつうまくいかない。
当惑したディフォードは『使用料はタダ』と言ってきたので、
もうちょっとがんばったところ、
彼は突然考えを変えて使用料をよこせといってきた。
断ると、彼は僕たちが作ったテープを全部盗んでしまった。
だから年明けて最初からやり直さなきゃならなかった。」
(プレイヤー1999年4月号)
「ソング・ストーリーズ(P418)」にも、次のような記述があります。
「ヘイドン・ベンダルの(ケントにある)プログラミング用の部屋で、
1、 2週間プリプロダクションを行い、
クリス・ディフォード(スクィーズ)のスタジオに移ったが、
スタジオの準備が出来ておらず、
ほとんどレコーディングが進まないまま、
3週間がたち、スタジオを出た。使用料を要求され、
払うまではテープを渡さないと言われたので、
最初からやり直すことにした。」
しかしXTCはその逆境を乗り越えます。
「大変だったことは、スタートすること(笑)。
しかし、難問を切り抜けるのは結構得意でねえ。
問題というのはいつも何かを教えてくれるものなんだと思っているから、
いろんなことがうまくいかないことによって
自分自身がより良くなっているような気がしている。
プロデューサーが時間切れでも、
デイヴが辞めても不快じゃない。」
(プレイヤー1999年4月号)
「悪かった点はレコーディングを始めるときの恐怖感かな。
とても長い間でも・テープのままで、
どの曲もデモの音にすっかりなれてしまっていたからね。
そしてその慣れてしまった音をレコーディング作業で
どのようにして良くしていくかを考えたわけだ。」
(ストレンジ・デイズ2001年5月号)
これまで、レコーディングの際には様々なトラブルに遭遇したXTCですが、
今回も例に漏れず、それらを乗り越えていきます。
(14)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その6)
ヘイデン・ベンダルの本領発揮です。
「ヘイデンはものすごいサンプルのライブラリーを持っていて、
6台ほどのサンプラーを使ってそれらを鳴らしていた。
ただしオーケストラらしく聞こえるサウンドは、
すべて本物のストリングスだ。やっぱり本物は違う。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
と、高く評価する一方、こんな面もあります。
「だけどうんざりするぐらい、仕事が遅いのがタマに傷でさ。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
「こちらも準備に時間をかけなきゃいけなかったけど。
とにかくその遅さたるや、バリウムが胃に流れ込むようなんだ。
とってもいい人だったけど。
最初、2枚組みを作ろうとしていて、
彼も『その時間はある』と言っていたが、
彼は自分の仕事の遅さを過小評価していた。
結局、アルバム半分作ったところで時間切れになってしまったので、
場所を変えてニック・デイヴィスと一緒にやることになった。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
結果、「ヘイデン・ベンダルは別の仕事が入っていて完成まで付き合えなかった
(プレイヤー 1999年4月号)」として、中途で終了となります。
ヘイデン・ベンダルの本領発揮です。
「ヘイデンはものすごいサンプルのライブラリーを持っていて、
6台ほどのサンプラーを使ってそれらを鳴らしていた。
ただしオーケストラらしく聞こえるサウンドは、
すべて本物のストリングスだ。やっぱり本物は違う。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
と、高く評価する一方、こんな面もあります。
「だけどうんざりするぐらい、仕事が遅いのがタマに傷でさ。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
「こちらも準備に時間をかけなきゃいけなかったけど。
とにかくその遅さたるや、バリウムが胃に流れ込むようなんだ。
とってもいい人だったけど。
最初、2枚組みを作ろうとしていて、
彼も『その時間はある』と言っていたが、
彼は自分の仕事の遅さを過小評価していた。
結局、アルバム半分作ったところで時間切れになってしまったので、
場所を変えてニック・デイヴィスと一緒にやることになった。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
結果、「ヘイデン・ベンダルは別の仕事が入っていて完成まで付き合えなかった
(プレイヤー 1999年4月号)」として、中途で終了となります。
(15)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その7)
「プレイリー・プリンス(ドラマー)のスケジュールを年明けまでおさえて、
チッピング・ノートンスタジオを予約したが、
予算を使いすぎ、アビー・ロードスタジオの使用は危ぶまれた。」
(ソング・ストーリーズ P419)
という危機を乗り切り、バンドはオーケストラによるレコーディングの際に、
「伝説の」アビー・ロードスタジオを使用します。
レコーディングの際に、
アビーロードスタジオのスタジオ1(一番大きいところ)を借りました。
1日で7曲と「ザ・ラスト・バルーン」のフリューゲルホーンを録音します。
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
アンディは、
「オーケストラとの共演について、首の後ろの毛が逆立った。
40人のプレイヤーがそれぞれに小さな楽器を持って
それに一心に心を傾けて演奏するのだから高揚する。
まるで嵐のすぐ横、ツナミのすぐそばにいるみたいな。」
(プレイヤー 1999年4月号)
『アイ・キャント・オウン・ハー』の盛り上がっていくところは特に、
思わず涙が出るくらいだった。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
と、振り返っております。
「プレイリー・プリンス(ドラマー)のスケジュールを年明けまでおさえて、
チッピング・ノートンスタジオを予約したが、
予算を使いすぎ、アビー・ロードスタジオの使用は危ぶまれた。」
(ソング・ストーリーズ P419)
という危機を乗り切り、バンドはオーケストラによるレコーディングの際に、
「伝説の」アビー・ロードスタジオを使用します。
レコーディングの際に、
アビーロードスタジオのスタジオ1(一番大きいところ)を借りました。
1日で7曲と「ザ・ラスト・バルーン」のフリューゲルホーンを録音します。
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
アンディは、
「オーケストラとの共演について、首の後ろの毛が逆立った。
40人のプレイヤーがそれぞれに小さな楽器を持って
それに一心に心を傾けて演奏するのだから高揚する。
まるで嵐のすぐ横、ツナミのすぐそばにいるみたいな。」
(プレイヤー 1999年4月号)
『アイ・キャント・オウン・ハー』の盛り上がっていくところは特に、
思わず涙が出るくらいだった。」
(ミュージック・マガジン1999年5月号)
と、振り返っております。
(16)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その8)
こぼれ話をいくつか。
アンディは、「本物のオーケストラは素晴らしいが、例外もある。」としております。
「『イースター・シアター』のバースの木管楽器はサンプルのほうが
ずっとくっきりしていた。
本物だと何だかパクパクしてるだけでぼやけちゃって。
でも同じ曲のほかの部分は本物のレガートや、息づかいがよかった。
これはサンプルでは表現できない。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
コリンは、いつもベースを一番最後にレコーディングしております。
「だからその曲にベースが必要か否かは後になってから決定することができた。
例えば『リヴァー・オブ・オーキッズ』にはベースが入っていない。
オーケストラによるベースだけでよかったんだ。」
(ベース・マガジン1999年3月号)
ただ、むやみに「穴を埋めていくように」オーケストラを使うのではなく、
きちんと曲に応じて、取捨選択をしていることが伺えます。
こぼれ話をいくつか。
アンディは、「本物のオーケストラは素晴らしいが、例外もある。」としております。
「『イースター・シアター』のバースの木管楽器はサンプルのほうが
ずっとくっきりしていた。
本物だと何だかパクパクしてるだけでぼやけちゃって。
でも同じ曲のほかの部分は本物のレガートや、息づかいがよかった。
これはサンプルでは表現できない。」
(サウンド&レコーディング・マガジン1999年3月号)
コリンは、いつもベースを一番最後にレコーディングしております。
「だからその曲にベースが必要か否かは後になってから決定することができた。
例えば『リヴァー・オブ・オーキッズ』にはベースが入っていない。
オーケストラによるベースだけでよかったんだ。」
(ベース・マガジン1999年3月号)
ただ、むやみに「穴を埋めていくように」オーケストラを使うのではなく、
きちんと曲に応じて、取捨選択をしていることが伺えます。
(17)「Apple Venus Vol.1」とオーケストラ(その9)
残ったミキシングは、アンディとニックで実施します。
ミックスのスタジオはロックフィールドで行われました。
理由は、「『ノンサッチ』〜『Vol.2』まで、よい成果が出たから。
ここは静かでよく寝られるし。これは大事なことだよ。」
(サウンド&レコーディング・マガジン2000年7月号)
とあります。
「自分でやらないと、どうも違和感がある。
自分の子どもを他人が育てる、
それどころか代わりに産んでくれちゃったみたいな感じで。
レコーディングは材料の買い物で、
買ってきたものをテーブルに並べる。
ほんの少しの材料でもレピシ通りのものを規定量だけ入れなかったら、
必ず味に影響する。」
(サウンド&レコーディング・マガジン 1999年3月号)
ここにも、アンディの「ディティールに対する配慮」が読み取れます。
時期がずれますが、ミックスがうまくいかなかった話として、
『ノンサッチ』の際の、ニック・デイヴィス、
そしてガス・ダッジョンとのやりとりを紹介します。
「ニック・デイヴィスとミックスするとき、
まず彼(ニック)にガス(・ダッジョン)を解雇した理由を説明し、
ミックス・ダウンは僕が彼の横に座って一緒にやることになると話した。
ニックがまず2時間ほどスタジオにこもり、
それから僕が入って彼にいろんなアイディアをぶつける。
2人で時間をかけて、それらを順番に試していって、うまく使えればOK!
使えなければ捨てていく。
それから彼がもう2時間ばかり僕の未熟なアイディアを形にしていき、
最後の数時間は一緒に細かい部分をつめていき、
という感じで行われた。
彼はガスの手によってだらっとした音になってしまったミックスに
エネルギーを吹き込んでくれた。」
(サウンド&レコーディング・マガジン 1992年6月号)
アンディが、それだけニックを信頼しているということです。
残ったミキシングは、アンディとニックで実施します。
ミックスのスタジオはロックフィールドで行われました。
理由は、「『ノンサッチ』〜『Vol.2』まで、よい成果が出たから。
ここは静かでよく寝られるし。これは大事なことだよ。」
(サウンド&レコーディング・マガジン2000年7月号)
とあります。
「自分でやらないと、どうも違和感がある。
自分の子どもを他人が育てる、
それどころか代わりに産んでくれちゃったみたいな感じで。
レコーディングは材料の買い物で、
買ってきたものをテーブルに並べる。
ほんの少しの材料でもレピシ通りのものを規定量だけ入れなかったら、
必ず味に影響する。」
(サウンド&レコーディング・マガジン 1999年3月号)
ここにも、アンディの「ディティールに対する配慮」が読み取れます。
時期がずれますが、ミックスがうまくいかなかった話として、
『ノンサッチ』の際の、ニック・デイヴィス、
そしてガス・ダッジョンとのやりとりを紹介します。
「ニック・デイヴィスとミックスするとき、
まず彼(ニック)にガス(・ダッジョン)を解雇した理由を説明し、
ミックス・ダウンは僕が彼の横に座って一緒にやることになると話した。
ニックがまず2時間ほどスタジオにこもり、
それから僕が入って彼にいろんなアイディアをぶつける。
2人で時間をかけて、それらを順番に試していって、うまく使えればOK!
使えなければ捨てていく。
それから彼がもう2時間ばかり僕の未熟なアイディアを形にしていき、
最後の数時間は一緒に細かい部分をつめていき、
という感じで行われた。
彼はガスの手によってだらっとした音になってしまったミックスに
エネルギーを吹き込んでくれた。」
(サウンド&レコーディング・マガジン 1992年6月号)
アンディが、それだけニックを信頼しているということです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
Apple Venus Vol.1 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
Apple Venus Vol.1のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 38429人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37145人
- 3位
- 広島東洋カープ
- 55240人