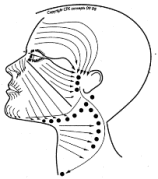|
|
|
|
コメント(29)
子宮筋腫
月経異常、不正子宮出血、貧血、頻尿、便秘、圧迫症状などがありますが、自覚症状がない場合も多いようです。
30代女性の4人に1人、40代では3人に1人が子宮筋腫を持つとも言われていますが、20代の方にも見られるようになって来ています。
分類として
粘膜下筋腫
子宮内膜直下(子宮の内側)に発生し子宮内腔に向かって発育します。発生頻度は少ないですが、筋腫自体が小さくても過多月経や月経痛などの症状が強いことが多いのが特徴になります。
筋層内筋腫(壁内筋腫)
子宮壁筋層内(子宮壁の真ん中)に発生し、筋層内に発育します。子宮筋腫中もっとも多いといわれています(約70%ほど)。
漿膜下筋腫
子宮漿膜直下(子宮の外側)に発生した筋腫で、子宮の表面(漿膜面)に向かって発育します。この種類は筋腫が大きくても筋腫特有の症状は無いか、あるいはあったとしても軽い場合がほとんどといわれています。
子宮頸部筋腫
左の丸い筋腫は子宮頸部に発生している子宮頸部筋腫ですが、このような例は少数(約5%ほど)です。
月経異常、不正子宮出血、貧血、頻尿、便秘、圧迫症状などがありますが、自覚症状がない場合も多いようです。
30代女性の4人に1人、40代では3人に1人が子宮筋腫を持つとも言われていますが、20代の方にも見られるようになって来ています。
分類として
粘膜下筋腫
子宮内膜直下(子宮の内側)に発生し子宮内腔に向かって発育します。発生頻度は少ないですが、筋腫自体が小さくても過多月経や月経痛などの症状が強いことが多いのが特徴になります。
筋層内筋腫(壁内筋腫)
子宮壁筋層内(子宮壁の真ん中)に発生し、筋層内に発育します。子宮筋腫中もっとも多いといわれています(約70%ほど)。
漿膜下筋腫
子宮漿膜直下(子宮の外側)に発生した筋腫で、子宮の表面(漿膜面)に向かって発育します。この種類は筋腫が大きくても筋腫特有の症状は無いか、あるいはあったとしても軽い場合がほとんどといわれています。
子宮頸部筋腫
左の丸い筋腫は子宮頸部に発生している子宮頸部筋腫ですが、このような例は少数(約5%ほど)です。
機能性月経困難症
生理は、子宮の内側の膜(子宮内膜)が剥がれ落ちる現象をいいます。
この子宮内膜が剥がれ落ちる時に、プロスタグランジンというホルモン様物質が分泌されて子宮をギュッと収縮させ、経血を押し出します。
そのホルモンの量が多いと、子宮が必要以上に収縮することにより生理痛が起こるのです。
また、子宮の発達の程度が遅く子宮口が狭い場合、経血が出にくいので、排出を促すために子宮が強く収縮するので生理痛が起きます。
※プロスタグランジン:
必須脂肪酸であるリノール酸とリノレン酸から、体内で作られるホルモンの様な働きをする物質。
炎症、痛み、腫れの調整、血圧、心機能、胃腸機能と消化酵素の分泌調整、腎機能と流動調節、血液凝固と血小板凝集、アレルギー反応、神経伝達、各種ホルモンの産生に関与。
生理は、子宮の内側の膜(子宮内膜)が剥がれ落ちる現象をいいます。
この子宮内膜が剥がれ落ちる時に、プロスタグランジンというホルモン様物質が分泌されて子宮をギュッと収縮させ、経血を押し出します。
そのホルモンの量が多いと、子宮が必要以上に収縮することにより生理痛が起こるのです。
また、子宮の発達の程度が遅く子宮口が狭い場合、経血が出にくいので、排出を促すために子宮が強く収縮するので生理痛が起きます。
※プロスタグランジン:
必須脂肪酸であるリノール酸とリノレン酸から、体内で作られるホルモンの様な働きをする物質。
炎症、痛み、腫れの調整、血圧、心機能、胃腸機能と消化酵素の分泌調整、腎機能と流動調節、血液凝固と血小板凝集、アレルギー反応、神経伝達、各種ホルモンの産生に関与。
子宮内膜症とは
子宮内膜症とは「通常なら子宮の内側をおおっている粘膜が通常とは異なる場所にも子宮内膜が生育している病気」になります。
子宮内膜症は卵管や卵巣、ダグラス窩、膀胱子宮窩などの子宮周囲の組織に最も良く見られますが、その場所でも子宮内腔で起こるのと同様に、毎月内膜が増殖と剥離出血を繰り返すことになります。
月経期になると子宮内膜とは異なる場所にできた子宮内膜でも剥離・出血があるということは、その場所では、内出血を起こしたような状態になりますから痛みが現れることになります。
子宮内膜のできた場所により現れる症状に差があります。
・子宮周辺あるいは子宮筋層内
:激痛を伴うような月経痛(生理痛)
・腹膜 :下腹部の痛み
・ダグラス窩:肛門の方への痛み
・膀胱子宮窩:尿意を催した時の下腹部痛
また、子宮内膜症の症状が続くことにより継続的炎症による組織間の癒着や月経時以外での月経時に似た下腹部痛や腰痛を感じたり、性交時痛・排卵痛などの症状が現れることもあります。
子宮内膜症とは「通常なら子宮の内側をおおっている粘膜が通常とは異なる場所にも子宮内膜が生育している病気」になります。
子宮内膜症は卵管や卵巣、ダグラス窩、膀胱子宮窩などの子宮周囲の組織に最も良く見られますが、その場所でも子宮内腔で起こるのと同様に、毎月内膜が増殖と剥離出血を繰り返すことになります。
月経期になると子宮内膜とは異なる場所にできた子宮内膜でも剥離・出血があるということは、その場所では、内出血を起こしたような状態になりますから痛みが現れることになります。
子宮内膜のできた場所により現れる症状に差があります。
・子宮周辺あるいは子宮筋層内
:激痛を伴うような月経痛(生理痛)
・腹膜 :下腹部の痛み
・ダグラス窩:肛門の方への痛み
・膀胱子宮窩:尿意を催した時の下腹部痛
また、子宮内膜症の症状が続くことにより継続的炎症による組織間の癒着や月経時以外での月経時に似た下腹部痛や腰痛を感じたり、性交時痛・排卵痛などの症状が現れることもあります。
ESHREguideline for the diagnosis and treatment of endometriosis (欧州生殖発生学会)による子宮内膜症の診断・治療ガイドライン
このESHREのガイドラインは世界子宮内膜症学会(WES)も推奨しています。
このガイドラインはは欧州子宮内膜症連合(EEA)のサイトhttp://www.endometriosis.org/にて見ることができます。
翻訳サイトはこちらに記載しておきます。
http://honyaku.yahoo.co.jp/
また、日本子宮内膜症協会(JEMA)大まかな和訳も載っています。http://www.jemanet.org/13_guideline/index.html
このESHREのガイドラインは世界子宮内膜症学会(WES)も推奨しています。
このガイドラインはは欧州子宮内膜症連合(EEA)のサイトhttp://www.endometriosis.org/にて見ることができます。
翻訳サイトはこちらに記載しておきます。
http://honyaku.yahoo.co.jp/
また、日本子宮内膜症協会(JEMA)大まかな和訳も載っています。http://www.jemanet.org/13_guideline/index.html
低用量ピル(OC : Oral Contraceptive)とは
低容量ピルは当時の厚生省が1999年6月17日にホルモン量の少ない経口避妊薬(低用量ピル)として承認したもので、1999年9月2日より発売が始まっています。
低用量ピルには卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲストロン)が含まれており、これらのホルモンを一定量を飲むことにより妊娠や生理に伴うさまざまなトラブルを減らすことを目的としています。
定義としてエチニルエストラジオールの1錠中のホルモン含有量が50μg未満のものをいいます。このホルモン量を減らすことで今までのピルに比べ副作用が「軽減」されることになりました。
もちろん副作用が軽減されるといっても、気分が悪くなる、頭痛、体重増加、不正出血、精神症状(うつ症状など)が現れることがあります。
また、血栓症や乳ガン、子宮頚ガンなどの可能性が指摘されています(子宮体ガンと卵巣ガンは予防作用があるといわれています)。
低容量ピルは当時の厚生省が1999年6月17日にホルモン量の少ない経口避妊薬(低用量ピル)として承認したもので、1999年9月2日より発売が始まっています。
低用量ピルには卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲストロン)が含まれており、これらのホルモンを一定量を飲むことにより妊娠や生理に伴うさまざまなトラブルを減らすことを目的としています。
定義としてエチニルエストラジオールの1錠中のホルモン含有量が50μg未満のものをいいます。このホルモン量を減らすことで今までのピルに比べ副作用が「軽減」されることになりました。
もちろん副作用が軽減されるといっても、気分が悪くなる、頭痛、体重増加、不正出血、精神症状(うつ症状など)が現れることがあります。
また、血栓症や乳ガン、子宮頚ガンなどの可能性が指摘されています(子宮体ガンと卵巣ガンは予防作用があるといわれています)。
女性ホルモンの働き
女性の生理に対して働いているのが2つの女性ホルモンです。
この2つの女性ホルモンは初経から閉経までの約35年間、妊娠の準備のために働いているのかというと、実際は、女性の心身の健康を総合的に保つという、もう一つの働きもあります。
この2つの女性ホルモンのうちエストロゲンは、骨量の減少や血中のコレステロール量の調節、皮膚や骨を強くする働きなどもあります。
特にコレステロールの調整作用は、生活習慣病のリスクを下げることの有益な働きとなっています。
もう一つの女性ホルモンであるプロゲステロンは、受精卵の着床のための準備をするだけではなく、エストロゲンの働きを抑え、血糖値の正常化や体脂肪の代謝に関与しています。
女性の生理に対して働いているのが2つの女性ホルモンです。
この2つの女性ホルモンは初経から閉経までの約35年間、妊娠の準備のために働いているのかというと、実際は、女性の心身の健康を総合的に保つという、もう一つの働きもあります。
この2つの女性ホルモンのうちエストロゲンは、骨量の減少や血中のコレステロール量の調節、皮膚や骨を強くする働きなどもあります。
特にコレステロールの調整作用は、生活習慣病のリスクを下げることの有益な働きとなっています。
もう一つの女性ホルモンであるプロゲステロンは、受精卵の着床のための準備をするだけではなく、エストロゲンの働きを抑え、血糖値の正常化や体脂肪の代謝に関与しています。
PMSとその症状
PMSとは Premenstrual Syndromeの略で、「通常、月経の2週間ないし1週間位前からおこり、月経開始とともに消失する、周期性のある一連の身体的、および精神的症状を示す症候群」と定義されています。
通常、月経が始まると症状が消えますが、始まっても2〜3日続く場合もあります。
症状として大きく分けると、身体的症状と精神的症状に分けることができます。
精神的な症状として
・怒りやすくなる
・ゆううつになる
・うまく集中できない
・判断力、集中力の低下
・イライラする
・無気力になる
・自信が持てなくなる
・不安になる
・涙もろい
・孤独感に苛まれる など
身体的症状として
・頭痛
・肩こり
・めまい
・下腹部が張る
・下腹部が痛む
・腰痛
・悪心、動悸
・脚や顔のむくみ
・食欲が増える(減る)
・眠くなる
・乳房が張り、痛む
・肌あれがする
・疲労
以上の症状から生活上のトラブルが生じることがあります。
・他人との口論
・ひきこもり
・仕事を休む
・不意に家族や友人を傷つける(肉体的・精神的)
・物損
・万引き など
PMSとは Premenstrual Syndromeの略で、「通常、月経の2週間ないし1週間位前からおこり、月経開始とともに消失する、周期性のある一連の身体的、および精神的症状を示す症候群」と定義されています。
通常、月経が始まると症状が消えますが、始まっても2〜3日続く場合もあります。
症状として大きく分けると、身体的症状と精神的症状に分けることができます。
精神的な症状として
・怒りやすくなる
・ゆううつになる
・うまく集中できない
・判断力、集中力の低下
・イライラする
・無気力になる
・自信が持てなくなる
・不安になる
・涙もろい
・孤独感に苛まれる など
身体的症状として
・頭痛
・肩こり
・めまい
・下腹部が張る
・下腹部が痛む
・腰痛
・悪心、動悸
・脚や顔のむくみ
・食欲が増える(減る)
・眠くなる
・乳房が張り、痛む
・肌あれがする
・疲労
以上の症状から生活上のトラブルが生じることがあります。
・他人との口論
・ひきこもり
・仕事を休む
・不意に家族や友人を傷つける(肉体的・精神的)
・物損
・万引き など
擬閉経療法とは
擬閉経療法は、生理が止まると子宮内膜症が良くなることを利用し、薬剤投与により閉経の時期と同じようなホルモン状態にすることをいいます。
擬妊娠療法と異なる点として挙げられるものは、治療中のエストロゲン量が非常に少ないレベルに抑えられるということになります。
擬閉経療法によってエストロゲンを低下させると子宮内膜の増殖は抑えられますから子宮内膜症も軽快することになります。
しかし、人工的にエストロゲンを低下させた状態を長期間に渡って行っていると、閉経後と同様に骨粗鬆症になる可能性がありますから、「子宮内膜症に対してある程度の治療効果が期待でき、かつ、骨粗鬆症が発生する心配が少ない」期間の中で治療を行うことを目標とされます。
擬閉経療法は、生理が止まると子宮内膜症が良くなることを利用し、薬剤投与により閉経の時期と同じようなホルモン状態にすることをいいます。
擬妊娠療法と異なる点として挙げられるものは、治療中のエストロゲン量が非常に少ないレベルに抑えられるということになります。
擬閉経療法によってエストロゲンを低下させると子宮内膜の増殖は抑えられますから子宮内膜症も軽快することになります。
しかし、人工的にエストロゲンを低下させた状態を長期間に渡って行っていると、閉経後と同様に骨粗鬆症になる可能性がありますから、「子宮内膜症に対してある程度の治療効果が期待でき、かつ、骨粗鬆症が発生する心配が少ない」期間の中で治療を行うことを目標とされます。
子宮内膜症の診断方法
子宮内膜症の診断方法は、大まかにこの方法があります。
・内診
・血液検査
・画像診断(超音波、MRI、CTなど)
・腹腔鏡
このうち、腹腔鏡をのぞく方法は一般的に行われていますが、腹腔鏡はあまり行われていません。また、この中でも、通常は内診と超音波による方法だけで子宮内膜症と診断されている場合が多いようです。
その理由として、内診だけでも75%の高率で診断することができるということと、患者さんにとって負担・苦痛の少ない検査法だからです。
ただ、
・何らかの症状がある方で子宮内膜症ではないと診断された人を腹腔鏡で再検査を行うと約15%の人に子宮内膜症が発見された。
・原因不明の不妊症の方を腹腔鏡検査すると40〜50%の確率で子宮内膜症が見つかる。
というデータがあります。
このようなことから腹腔鏡検査は有用なものなのが分かりますが、患者さんにとって腹腔鏡検査はとても負担のかかる検査です。
この検査を行う場合には有用さと負担を考えや上で主治医とよく話し合いましょう。
子宮内膜症の診断方法は、大まかにこの方法があります。
・内診
・血液検査
・画像診断(超音波、MRI、CTなど)
・腹腔鏡
このうち、腹腔鏡をのぞく方法は一般的に行われていますが、腹腔鏡はあまり行われていません。また、この中でも、通常は内診と超音波による方法だけで子宮内膜症と診断されている場合が多いようです。
その理由として、内診だけでも75%の高率で診断することができるということと、患者さんにとって負担・苦痛の少ない検査法だからです。
ただ、
・何らかの症状がある方で子宮内膜症ではないと診断された人を腹腔鏡で再検査を行うと約15%の人に子宮内膜症が発見された。
・原因不明の不妊症の方を腹腔鏡検査すると40〜50%の確率で子宮内膜症が見つかる。
というデータがあります。
このようなことから腹腔鏡検査は有用なものなのが分かりますが、患者さんにとって腹腔鏡検査はとても負担のかかる検査です。
この検査を行う場合には有用さと負担を考えや上で主治医とよく話し合いましょう。
子宮腺筋症とは。
子宮腺筋症とは子宮筋腫と症状も他覚的所見も非常に似通っているのですが、子宮内膜症によって起こる疾患ですので子宮筋腫とは異なる疾患になります。
子宮内膜症というのは、子宮内膜が本来の場所以外で増殖することにより起こる疾患ですが、このうち、内膜の増殖が子宮筋層に限局したものをいいます。
子宮腺筋症では、内膜が子宮筋層内で増殖するので、生理の時期になると子宮筋層内で増殖した内膜がはがれ落ちることで生理痛の原因にもなります。
また、内膜が筋層で増殖することから子宮自体のの肥大化を起こします。そのため子宮全体の大きさも大きくなるので、子宮筋腫との鑑別が難しくなっています。
子宮腺筋症とは子宮筋腫と症状も他覚的所見も非常に似通っているのですが、子宮内膜症によって起こる疾患ですので子宮筋腫とは異なる疾患になります。
子宮内膜症というのは、子宮内膜が本来の場所以外で増殖することにより起こる疾患ですが、このうち、内膜の増殖が子宮筋層に限局したものをいいます。
子宮腺筋症では、内膜が子宮筋層内で増殖するので、生理の時期になると子宮筋層内で増殖した内膜がはがれ落ちることで生理痛の原因にもなります。
また、内膜が筋層で増殖することから子宮自体のの肥大化を起こします。そのため子宮全体の大きさも大きくなるので、子宮筋腫との鑑別が難しくなっています。
ピルの副作用について
・肝機能障害;
ピルの代謝は肝臓で行われます。なのでピルを常時飲み続けることによって肝機能の障害を起こす可能性があるといわれています。ピルを常用する場合などは肝臓の定期検診も行うようにしましょう。
・心臓・血管系に対する影響;
多い副作用ではないといわれていますが、血栓症を起こしやすくなるという副作用があります。狭心症や心筋梗塞、高血圧、高脂血症・高コレステロール血症の方、脳血管障害の既往のある方は注意が必要といえます。
・喫煙;
喫煙者では非喫煙者よりも心臓・血管系への障害が発生しやすいといわれています。ピルを服用する時は、健康への被害を考えて禁煙をしてみましょう。
・浮腫・体重増加;
女性ホルモンには、水分を貯め置く働きがあるのでむくみがでやすくなります。また、低量用ピルの使用でも体重の増加が出ることがあるそうです。
・乳腺の肥大;
乳腺の肥大化はバストが大きくなることにつながります。急にバストが大きくなることがありましたら、バストに白線(妊娠線とおなじもの)がバストにできることがありますので、白線予防のためにバスとのマッサージが必要になることが、まれにあります。
・性欲減退;
妊娠中に性欲が減退することはよく知られていますが、ピル服用中は偽妊娠状態と同じ状態になっていますので性欲が減退してきます。
・子宮筋腫への影響;
子宮筋腫は、エストロゲンの働きにより増大します。このことから、ピルを内服することにより筋腫が大きくなる可能性があります。
・カンジダ症への影響;
ピル内服により、膣内の弱酸性の状態が変化をすることがあります。この状態は、最近の増殖を抑える力は弱くなるのでカンジダ膣炎を起こしやすくなります。
・その他;
糖尿病の悪化、皮膚の色素沈着、うつ感、高血圧など
・肝機能障害;
ピルの代謝は肝臓で行われます。なのでピルを常時飲み続けることによって肝機能の障害を起こす可能性があるといわれています。ピルを常用する場合などは肝臓の定期検診も行うようにしましょう。
・心臓・血管系に対する影響;
多い副作用ではないといわれていますが、血栓症を起こしやすくなるという副作用があります。狭心症や心筋梗塞、高血圧、高脂血症・高コレステロール血症の方、脳血管障害の既往のある方は注意が必要といえます。
・喫煙;
喫煙者では非喫煙者よりも心臓・血管系への障害が発生しやすいといわれています。ピルを服用する時は、健康への被害を考えて禁煙をしてみましょう。
・浮腫・体重増加;
女性ホルモンには、水分を貯め置く働きがあるのでむくみがでやすくなります。また、低量用ピルの使用でも体重の増加が出ることがあるそうです。
・乳腺の肥大;
乳腺の肥大化はバストが大きくなることにつながります。急にバストが大きくなることがありましたら、バストに白線(妊娠線とおなじもの)がバストにできることがありますので、白線予防のためにバスとのマッサージが必要になることが、まれにあります。
・性欲減退;
妊娠中に性欲が減退することはよく知られていますが、ピル服用中は偽妊娠状態と同じ状態になっていますので性欲が減退してきます。
・子宮筋腫への影響;
子宮筋腫は、エストロゲンの働きにより増大します。このことから、ピルを内服することにより筋腫が大きくなる可能性があります。
・カンジダ症への影響;
ピル内服により、膣内の弱酸性の状態が変化をすることがあります。この状態は、最近の増殖を抑える力は弱くなるのでカンジダ膣炎を起こしやすくなります。
・その他;
糖尿病の悪化、皮膚の色素沈着、うつ感、高血圧など
尿意が起きると下腹部痛
尿意で下腹部痛が起きる場合、最初に考えるのは膀胱炎だと思います。
膀胱炎は、トイレを我慢したり下腹部を冷やす環境、疲労の蓄積、不衛生などが誘引となり、尿道から細菌が膀胱に入り込んだときに炎症を起こします。
このとき尿意で下腹部痛が起きるだけではなく、頻尿、排尿痛、残尿感、血尿などの症状が現れます。
膀胱炎以外に尿意によって起こる下腹部痛で考えられるのは、子宮内膜症でしょう。
膀胱のすぐ後ろには子宮がありますが、膀胱と子宮との間にあるスペース(膀胱子宮窩)は子宮内膜症の好発部位でもあるので、この場所に子宮内膜症が発生すると膀胱が尿が溜まり膨らんだ時に、この内膜症が起こった部位を刺激しますので、尿意を感じると下腹部が痛くなるのです。
特に生理中から生理後に尿意によって下腹部痛が出やすくなっている方は子宮内膜症の可能性があるといえます。
また、子宮筋腫が大きくなりすぎると、尿が膀胱にたまって膨らむことを妨害しますので、このことにより痛みを出すことも考えられます。
いずれにしろ、継続的に尿意で下腹部痛があるようなときには専門医に相談することをお勧めいたします。
尿意で下腹部痛が起きる場合、最初に考えるのは膀胱炎だと思います。
膀胱炎は、トイレを我慢したり下腹部を冷やす環境、疲労の蓄積、不衛生などが誘引となり、尿道から細菌が膀胱に入り込んだときに炎症を起こします。
このとき尿意で下腹部痛が起きるだけではなく、頻尿、排尿痛、残尿感、血尿などの症状が現れます。
膀胱炎以外に尿意によって起こる下腹部痛で考えられるのは、子宮内膜症でしょう。
膀胱のすぐ後ろには子宮がありますが、膀胱と子宮との間にあるスペース(膀胱子宮窩)は子宮内膜症の好発部位でもあるので、この場所に子宮内膜症が発生すると膀胱が尿が溜まり膨らんだ時に、この内膜症が起こった部位を刺激しますので、尿意を感じると下腹部が痛くなるのです。
特に生理中から生理後に尿意によって下腹部痛が出やすくなっている方は子宮内膜症の可能性があるといえます。
また、子宮筋腫が大きくなりすぎると、尿が膀胱にたまって膨らむことを妨害しますので、このことにより痛みを出すことも考えられます。
いずれにしろ、継続的に尿意で下腹部痛があるようなときには専門医に相談することをお勧めいたします。
排卵痛について
排卵の時期に痛みがあると排卵痛だといいますが、排卵痛とは何でしょう?
排卵は、成熟し卵子が、卵巣の表面を破り卵巣外に放出される現象をいい、このときに起こる痛みを排卵痛といっています。
また、この排卵の時期に一時的に減少するエストロゲンにより引き起こされることもあるようです。
いずれにせよ、これらのものは病的なものとは言いにくいのですが、この排卵の時期に起こる痛みは病的な場合によっても起こる事があります(骨盤内の炎症や子宮筋腫や内膜症、卵巣嚢腫、卵巣がんなど)。
排卵時に起こる痛みがある場合、病的なものかそうでないものかを一度、専門医に相談するようお勧めいたします。
排卵の時期に痛みがあると排卵痛だといいますが、排卵痛とは何でしょう?
排卵は、成熟し卵子が、卵巣の表面を破り卵巣外に放出される現象をいい、このときに起こる痛みを排卵痛といっています。
また、この排卵の時期に一時的に減少するエストロゲンにより引き起こされることもあるようです。
いずれにせよ、これらのものは病的なものとは言いにくいのですが、この排卵の時期に起こる痛みは病的な場合によっても起こる事があります(骨盤内の炎症や子宮筋腫や内膜症、卵巣嚢腫、卵巣がんなど)。
排卵時に起こる痛みがある場合、病的なものかそうでないものかを一度、専門医に相談するようお勧めいたします。
性行為中の痛みや、性行為の後の腹痛
ここでいう性交痛は、挿入時に膣の入り口付近が痛む場合を除いています。
男性器を挿入時したときに膣の奥の方を突かれたときに痛みや、激痛が走るなどの場合、子宮形成不全などを除けば、まず子宮内膜症の存在が疑われます。
膣の一番奥には子宮と直腸で作られる窪みがあり、ここをダグラス窩といい子宮内膜症の好発部位となっています。
この部位に内膜症が起こると、性交時にはこの場所が刺激されることにより痛みを感じることになるのです。
また、子宮筋腫が子宮の後面にできた場合も、性交時痛が起きることがあります。
性行痛が続くような事があるときは専門医に相談するようにしましょう。
ここでいう性交痛は、挿入時に膣の入り口付近が痛む場合を除いています。
男性器を挿入時したときに膣の奥の方を突かれたときに痛みや、激痛が走るなどの場合、子宮形成不全などを除けば、まず子宮内膜症の存在が疑われます。
膣の一番奥には子宮と直腸で作られる窪みがあり、ここをダグラス窩といい子宮内膜症の好発部位となっています。
この部位に内膜症が起こると、性交時にはこの場所が刺激されることにより痛みを感じることになるのです。
また、子宮筋腫が子宮の後面にできた場合も、性交時痛が起きることがあります。
性行痛が続くような事があるときは専門医に相談するようにしましょう。
タンポンと子宮内膜症
月経血が逆流することは子宮内膜症のリスクになるといわれています。
そのプロセスとして
生理の時期に月経血が膣から体外に流れ出ずに、子宮から卵管の方へ逆流し腹腔内へ流れ出ることで、月経血と共に子宮内膜が腹腔内へ運ばれ、そこに子宮内膜が付着し、増殖することで子宮内膜症が起こるといわれています。
この現象はしばしば見られることができるそうで、様々の研究でも、このようなプロセスを経て子宮内膜が腹腔内に生育することを裏付けています。
では、タンポンによって逆流することはあるのでしょうか?
現在の所、その様なことは確認されておらず、今の所は問題が無いといえそうです。
このようなことから、タンポンが起因しての子宮内膜症は、今の所無いといえるかと思います。
月経血が逆流することは子宮内膜症のリスクになるといわれています。
そのプロセスとして
生理の時期に月経血が膣から体外に流れ出ずに、子宮から卵管の方へ逆流し腹腔内へ流れ出ることで、月経血と共に子宮内膜が腹腔内へ運ばれ、そこに子宮内膜が付着し、増殖することで子宮内膜症が起こるといわれています。
この現象はしばしば見られることができるそうで、様々の研究でも、このようなプロセスを経て子宮内膜が腹腔内に生育することを裏付けています。
では、タンポンによって逆流することはあるのでしょうか?
現在の所、その様なことは確認されておらず、今の所は問題が無いといえそうです。
このようなことから、タンポンが起因しての子宮内膜症は、今の所無いといえるかと思います。
低量用ピルの服用に際しての注意事項
1. 正しい服用方法と飲み忘れへの対応
a. 毎日一定時間に服用しましょう
b. 消退出血が2ヵ月以上こない時には受診しましょう
c. 飲み忘れが24時間以内の時は、気付いた時点で服用する
d. 飲み忘れが24時間以上たっている場合には、そのシートの服用はやめて次の月経まで待って新しいシートの服用を始める
e. ピルの避妊効果が確実になるには7日間必要とするので、避妊に注意しましょう
f. 下痢や嘔吐の時には、ピルの効果が減弱する恐れがありますので、下痢や嘔吐が続くようであったりするなら、避妊方法の併用をお勧めします
g. ピルを服用している人の中には、コンタクトレンズを装着している時に違和感を訴えることがあります
h. 他の低用量ピルに切り替えることもできます
2. 併用薬
胃薬、風邪薬、頭痛の薬など、ほとんどの薬は大丈夫ですが、注意の必要な薬もあります。
副腎皮質ホルモン剤(ステロイド剤)の作用が増強することがあります。
抗うつ薬の作用が増強することがあります。
てんかんの薬(抗けいれん薬)、抗アレルギー薬によってピルの効果を減弱させるものがあります。
抗生物質の中にはピルの効果を減弱させるものがあります。
糖尿病の人は要注意、インスリンや糖尿病の治療薬の作用が増強することがあります。
疾病の治療中の方は、主治医と相談してピルの服用をしましょう。
3. 服用を中止すべき症状
血栓症や乳ガン、子宮頚ガンが増悪する可能性があります。その他、体に不調がありましたら主治医に相談しましょう。
4. 妊娠への注意
不適切な飲み方により、すり抜け排卵があります。
5. 飲みはじめの副作用
不性器出血がみられることがあります、吐き気や乳房痛、乳房の緊満感などが比較的多くみられますが、しだいに消失することが多いです。また、体重が微増することが多いようです。
6. 定期検査
飲み始めて1・3・6ヵ月、1年毎に受診、検査を受けることが望ましいですが、体に変化があるときにも受診、検査をしましょう。
7. 処方の間隔
最高3ヵ月分まで処方できるそうです。
8. 血液検査、臨床検査値への影響
・総コルチゾールの増加
・甲状腺機能検査
ご不明な点がありましたら主治医にご相談ください。
1. 正しい服用方法と飲み忘れへの対応
a. 毎日一定時間に服用しましょう
b. 消退出血が2ヵ月以上こない時には受診しましょう
c. 飲み忘れが24時間以内の時は、気付いた時点で服用する
d. 飲み忘れが24時間以上たっている場合には、そのシートの服用はやめて次の月経まで待って新しいシートの服用を始める
e. ピルの避妊効果が確実になるには7日間必要とするので、避妊に注意しましょう
f. 下痢や嘔吐の時には、ピルの効果が減弱する恐れがありますので、下痢や嘔吐が続くようであったりするなら、避妊方法の併用をお勧めします
g. ピルを服用している人の中には、コンタクトレンズを装着している時に違和感を訴えることがあります
h. 他の低用量ピルに切り替えることもできます
2. 併用薬
胃薬、風邪薬、頭痛の薬など、ほとんどの薬は大丈夫ですが、注意の必要な薬もあります。
副腎皮質ホルモン剤(ステロイド剤)の作用が増強することがあります。
抗うつ薬の作用が増強することがあります。
てんかんの薬(抗けいれん薬)、抗アレルギー薬によってピルの効果を減弱させるものがあります。
抗生物質の中にはピルの効果を減弱させるものがあります。
糖尿病の人は要注意、インスリンや糖尿病の治療薬の作用が増強することがあります。
疾病の治療中の方は、主治医と相談してピルの服用をしましょう。
3. 服用を中止すべき症状
血栓症や乳ガン、子宮頚ガンが増悪する可能性があります。その他、体に不調がありましたら主治医に相談しましょう。
4. 妊娠への注意
不適切な飲み方により、すり抜け排卵があります。
5. 飲みはじめの副作用
不性器出血がみられることがあります、吐き気や乳房痛、乳房の緊満感などが比較的多くみられますが、しだいに消失することが多いです。また、体重が微増することが多いようです。
6. 定期検査
飲み始めて1・3・6ヵ月、1年毎に受診、検査を受けることが望ましいですが、体に変化があるときにも受診、検査をしましょう。
7. 処方の間隔
最高3ヵ月分まで処方できるそうです。
8. 血液検査、臨床検査値への影響
・総コルチゾールの増加
・甲状腺機能検査
ご不明な点がありましたら主治医にご相談ください。
<生活習慣病>糖尿病防ぐたんぱく質、子宮内膜症も予防?
糖尿病や動脈硬化を防ぐ働きのあるたんぱく質「アディポネクチン」が、子宮内膜症や子宮体がんを予防している可能性のあることが、東京大の研究で分かった。9日に大阪市で開かれた日本生殖医学会で発表した。
研究チームは、77人分の健康な状態の子宮内膜を調べた。その結果、アディポネクチンが働くのに必要な受容体2種が、子宮内膜に存在していることを突き止めた。
受容体は常に存在し、特に受精卵が着床する時期に増えることが分かった。また、子宮内膜の細胞にアディポネクチンを加えると、炎症の原因となる物質の産生が抑えられ、24時間後には半減した。
一方、子宮内膜症の患者は、そうでない人に比べて血中のアディポネクチン濃度が約2割低下していた。肥満や偏食、運動不足などで生活習慣が乱れると、アディポネクチンの分泌が減り、糖尿病や動脈硬化の症状を悪化させることが知られている。
国内の生殖期の女性の約10%(100万〜200万人)が子宮内膜症の患者とされるが、発症の原因は分かっていない。
研究チームの東大大学院3年、竹村由里さん(29)は「アディポネクチンの分泌が十分なことが、子宮内膜にとっていい状態だということが分かった。生活習慣が子宮内膜症に関与している可能性を示している」と話している。
(毎日新聞) - 11月10日
糖尿病や動脈硬化を防ぐ働きのあるたんぱく質「アディポネクチン」が、子宮内膜症や子宮体がんを予防している可能性のあることが、東京大の研究で分かった。9日に大阪市で開かれた日本生殖医学会で発表した。
研究チームは、77人分の健康な状態の子宮内膜を調べた。その結果、アディポネクチンが働くのに必要な受容体2種が、子宮内膜に存在していることを突き止めた。
受容体は常に存在し、特に受精卵が着床する時期に増えることが分かった。また、子宮内膜の細胞にアディポネクチンを加えると、炎症の原因となる物質の産生が抑えられ、24時間後には半減した。
一方、子宮内膜症の患者は、そうでない人に比べて血中のアディポネクチン濃度が約2割低下していた。肥満や偏食、運動不足などで生活習慣が乱れると、アディポネクチンの分泌が減り、糖尿病や動脈硬化の症状を悪化させることが知られている。
国内の生殖期の女性の約10%(100万〜200万人)が子宮内膜症の患者とされるが、発症の原因は分かっていない。
研究チームの東大大学院3年、竹村由里さん(29)は「アディポネクチンの分泌が十分なことが、子宮内膜にとっていい状態だということが分かった。生活習慣が子宮内膜症に関与している可能性を示している」と話している。
(毎日新聞) - 11月10日
25:ももこさん>辛そうですね。。。何か症状を和らげる為のヒントになれば良いのですが。しかし、私は医学的に素人なので、経験談として書き込みをします。
私のPMSの症状は、風邪をひいた時のような関節の痛みと腰痛です。それと、下腹部の痛みと張り。その時々で強弱の違いはありますが、年々辛くなるいっぽうでした。ですが、久々に整体に行き骨盤矯正を受けたところ、今までの痛みは何だったの?という位、症状が軽くなりとても楽になりました。
26:山さん>補正下着は使用していませんが。私もなんらかの効果があったのではと思います。体の歪みが下着によって矯正されたのかな?!なんて感想を持ちました。体の歪みと月経異常・月経痛に何かの因果関係があるような気がします。
私のPMSの症状は、風邪をひいた時のような関節の痛みと腰痛です。それと、下腹部の痛みと張り。その時々で強弱の違いはありますが、年々辛くなるいっぽうでした。ですが、久々に整体に行き骨盤矯正を受けたところ、今までの痛みは何だったの?という位、症状が軽くなりとても楽になりました。
26:山さん>補正下着は使用していませんが。私もなんらかの効果があったのではと思います。体の歪みが下着によって矯正されたのかな?!なんて感想を持ちました。体の歪みと月経異常・月経痛に何かの因果関係があるような気がします。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
美容・健康情報 更新情報
-
最新のアンケート
美容・健康情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89995人
- 3位
- 酒好き
- 170659人