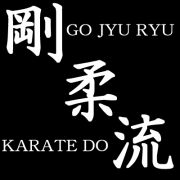|
|
|
|
コメント(40)
>J3さん。
あ、なるほど、そういうスタンスなんですねー。
その見方は俺も同意です。もともとサイファの上段からの槌拳〜掴み〜底突きは連続動作であって、競技用みたいに止めたりしませんもんね。沖縄の形もそうですし、本来の意味のものは危なくて使えません(^^;)
でも、競技組手の中でも形の中にある技を使って、流派の特色を出したいというのが私の願望なんですよね。今の大会って4つの流派が集まってるのに、動きが同じってのがなんか寂しくもあり。ただ、競技で勝つための最もムダが少ない方法を突き詰めたのが今の形ってのもわかるし。これはどうにもならないジレンマですけど、まあ自分がするぐらいはあがいてみるかな、と(笑)
・・・そういう意味では20年前ぐらいのビデオにある猫足対前屈立ちの組手の時代とか、憧れです(笑)
あ、なるほど、そういうスタンスなんですねー。
その見方は俺も同意です。もともとサイファの上段からの槌拳〜掴み〜底突きは連続動作であって、競技用みたいに止めたりしませんもんね。沖縄の形もそうですし、本来の意味のものは危なくて使えません(^^;)
でも、競技組手の中でも形の中にある技を使って、流派の特色を出したいというのが私の願望なんですよね。今の大会って4つの流派が集まってるのに、動きが同じってのがなんか寂しくもあり。ただ、競技で勝つための最もムダが少ない方法を突き詰めたのが今の形ってのもわかるし。これはどうにもならないジレンマですけど、まあ自分がするぐらいはあがいてみるかな、と(笑)
・・・そういう意味では20年前ぐらいのビデオにある猫足対前屈立ちの組手の時代とか、憧れです(笑)
>えがわちょうさんへ
>指定形では鉄槌、底突きのあと、その手のままで右足を1歩だし中段突きですよね。
指定形ではそのとおりです。
沖縄の剛柔流でも、私が持っている書籍では何れも、右足を一歩踏み出して右サンチン立ち、右手掛け受け(捕り手受け)、すぐに左中段突き
(すなわち、指定型は右掛け受けの動作を省略している)
という形です。
えがわ ちょうさんの道場の動作は、この、沖縄剛柔流の動作をさらにもう一度受けが入る、ということになりますでしょうか?
指定形、沖縄剛柔流、えがわちょうさんの道場、それぞれ解釈が変わってくるかと思われます。
よろしければ、他にも指定形との違う部分がありましたらお教え願えないでしょうか?
>指定形では鉄槌、底突きのあと、その手のままで右足を1歩だし中段突きですよね。
指定形ではそのとおりです。
沖縄の剛柔流でも、私が持っている書籍では何れも、右足を一歩踏み出して右サンチン立ち、右手掛け受け(捕り手受け)、すぐに左中段突き
(すなわち、指定型は右掛け受けの動作を省略している)
という形です。
えがわ ちょうさんの道場の動作は、この、沖縄剛柔流の動作をさらにもう一度受けが入る、ということになりますでしょうか?
指定形、沖縄剛柔流、えがわちょうさんの道場、それぞれ解釈が変わってくるかと思われます。
よろしければ、他にも指定形との違う部分がありましたらお教え願えないでしょうか?
>小次郎さんへ
師範の不幸により道場が散会したので、教本と、私の体に入っている形と、その当時、師範がいっていた解釈でよろしくれば、文章につづらせて頂きます。
サイファの出だしですが、右拳を腰にとり左開掌を右手の拳に添え、(教本はたて拳だったが、ふつうの引き手だったと思います)
から
右足から右45度前方向に出て、右横エンピ、左足を後ろに引き四股立ちとなりながら、左掌で押さえ受け、右エンピ、右裏拳。
(教本は水月の高さになっているのですが、私の記憶だと、エンピ(肘)は、かたいので相手のどこに当たってもダメージが大きい。女性などがヒジテツを出すのは、鍛えなくてもかたい部分なんだよ。顔をねらっても有効だよと、いわれた気がします。)
あと右横エンピの時は右手の拳で、掌が上から下へ一気に回しながらエンピを突き出す感じに、と習った感じがします。
尚、顔の向き(目の方向は)進行方向の相手から目を離さない。との指導を受け、中学生にも当時そのような指導をしていたと思います。
ですから、最初に前進する3歩の手業がちょっと違うところと、中段の二段かけてのところでしょうか。
師範の不幸により道場が散会したので、教本と、私の体に入っている形と、その当時、師範がいっていた解釈でよろしくれば、文章につづらせて頂きます。
サイファの出だしですが、右拳を腰にとり左開掌を右手の拳に添え、(教本はたて拳だったが、ふつうの引き手だったと思います)
から
右足から右45度前方向に出て、右横エンピ、左足を後ろに引き四股立ちとなりながら、左掌で押さえ受け、右エンピ、右裏拳。
(教本は水月の高さになっているのですが、私の記憶だと、エンピ(肘)は、かたいので相手のどこに当たってもダメージが大きい。女性などがヒジテツを出すのは、鍛えなくてもかたい部分なんだよ。顔をねらっても有効だよと、いわれた気がします。)
あと右横エンピの時は右手の拳で、掌が上から下へ一気に回しながらエンピを突き出す感じに、と習った感じがします。
尚、顔の向き(目の方向は)進行方向の相手から目を離さない。との指導を受け、中学生にも当時そのような指導をしていたと思います。
ですから、最初に前進する3歩の手業がちょっと違うところと、中段の二段かけてのところでしょうか。
>旅人Takaさんへ
話題作りありがとうございます。
1番目の指定形については、可もなく不可もなく、というところでしょうか。
自分の個人的意見としては、演武者の方の動きにバネがなく、「剛剛流」という感じになっているのが多少気になりますが....
(最近の形競技者全体に言えることではありますが)
3番目は、形は妙ですが分解はなかなか面白いですね。
第一動作をセイパイと同じ「腕ひしぎ」とした解釈は初見です。
2〜4番目の外国人の方の全ての演武について言えますが、沖縄剛柔流の古い動きと、後から付け足したと思われる動作がごちゃ混ぜになっている様です。
本土の剛柔会系の動きではないので、恐らくは、
1:熱心な外国人空手家が、沖縄剛柔流を学びに渡沖し、これを学んだ。
2:帰国後、道場を開いて剛柔流を広めた
3:しかし、弟子、孫弟子、ひ孫弟子と伝わるうちに、どんどんと動作が変質した。
という演武ではないかと推察します。
話題作りありがとうございます。
1番目の指定形については、可もなく不可もなく、というところでしょうか。
自分の個人的意見としては、演武者の方の動きにバネがなく、「剛剛流」という感じになっているのが多少気になりますが....
(最近の形競技者全体に言えることではありますが)
3番目は、形は妙ですが分解はなかなか面白いですね。
第一動作をセイパイと同じ「腕ひしぎ」とした解釈は初見です。
2〜4番目の外国人の方の全ての演武について言えますが、沖縄剛柔流の古い動きと、後から付け足したと思われる動作がごちゃ混ぜになっている様です。
本土の剛柔会系の動きではないので、恐らくは、
1:熱心な外国人空手家が、沖縄剛柔流を学びに渡沖し、これを学んだ。
2:帰国後、道場を開いて剛柔流を広めた
3:しかし、弟子、孫弟子、ひ孫弟子と伝わるうちに、どんどんと動作が変質した。
という演武ではないかと推察します。
>小次郎 さん
どういたしまして。
1は指導用マニュアル的なビデオなので逆に競技に使う時に味付けしやすいのかと思います。
サイファ→セイエンチン→シソウチン→クルルンファでの系譜で見ると堅さだけが目立ってしまってますね。。。ってか、世界チャンプに対して失礼な言い方ですが。
3は鷺足立ちで正面を向いているので糸東流かと思います。
分解は、巴投げ・腕ひしぎはデフォルメしすぎの感じがしますね、ヨーロッパは派手な分解を好むようです。
2・4は沖縄剛柔の先生のクセが段々と大げさになってしまった感じがしますね。分解を正しく伝えているのかが心配になります。
ここで、皆さんに質問があります。
諸手突きの後の鉄槌掌底打ちの解釈は教本では足取りに対してだったと思いますが、他の解釈はあるのでしょうか?
自分としては足取りならば、膝を動かせばそのまま顔面への攻撃になるし、取られた後に鉄槌掌底打ち→頭部を挟んでねじるのは難しいと思います。
どういたしまして。
1は指導用マニュアル的なビデオなので逆に競技に使う時に味付けしやすいのかと思います。
サイファ→セイエンチン→シソウチン→クルルンファでの系譜で見ると堅さだけが目立ってしまってますね。。。ってか、世界チャンプに対して失礼な言い方ですが。
3は鷺足立ちで正面を向いているので糸東流かと思います。
分解は、巴投げ・腕ひしぎはデフォルメしすぎの感じがしますね、ヨーロッパは派手な分解を好むようです。
2・4は沖縄剛柔の先生のクセが段々と大げさになってしまった感じがしますね。分解を正しく伝えているのかが心配になります。
ここで、皆さんに質問があります。
諸手突きの後の鉄槌掌底打ちの解釈は教本では足取りに対してだったと思いますが、他の解釈はあるのでしょうか?
自分としては足取りならば、膝を動かせばそのまま顔面への攻撃になるし、取られた後に鉄槌掌底打ち→頭部を挟んでねじるのは難しいと思います。
ご教授いただきありがとうございます。
教本を確認したところ、相手の前襟を交差した手で掴み引く、と共に胸部又は脇腹に諸手突き、足取りにきたところを鉄槌掌底打ち・・・となっていました。
>えがわ ちょう さん
>相手の肋骨に諸手突きをし、相手が前に倒れる時、 あたまを挟む
そうですね、『前に倒れた時に』が自然ですよね
>ra-ga さん
>沖縄では基本の分解 応用分解とあります。
はい、分解は1つではなく複数(隠されている)と教わりました。
>諸手は突くんですが最終的に・・・・
引き込むということですか? そのまま鉄槌につながりますね。
なんとなく自分なりの解釈ができてきました。
ありがとうございます。
教本を確認したところ、相手の前襟を交差した手で掴み引く、と共に胸部又は脇腹に諸手突き、足取りにきたところを鉄槌掌底打ち・・・となっていました。
>えがわ ちょう さん
>相手の肋骨に諸手突きをし、相手が前に倒れる時、 あたまを挟む
そうですね、『前に倒れた時に』が自然ですよね
>ra-ga さん
>沖縄では基本の分解 応用分解とあります。
はい、分解は1つではなく複数(隠されている)と教わりました。
>諸手は突くんですが最終的に・・・・
引き込むということですか? そのまま鉄槌につながりますね。
なんとなく自分なりの解釈ができてきました。
ありがとうございます。
>諸手突きの後の鉄槌掌底打ちの解釈は教本では足取りに対してだったと思いますが、他の解釈はあるのでしょうか?
>>相手の肋骨に諸手突きをし、相手が前に倒れる時、あたまを挟む、(とどめを刺す)と習っています。
自分の聞いた解釈ではその他に、「諸手突きは、相手の鎖骨部分の急所押し痛めであり、それを喰らって思わずしゃがみ込んだ相手へのトドメ」
というのがありました。
>自分としては足取りならば、膝を動かせばそのまま顔面への攻撃になるし、取られた後に鉄槌掌底打ち→頭部を挟んでねじるのは難しいと思います。
上記についての自分の解釈ですが、
1:平拳による上段突きで相手のノドを狙う
(正拳ではアゴに当たってしまうが、平拳ならばノドに入る)
(型では諸手突きですが、これは片手でも構わないと思います)
2:相手がその上段突きをかわしてしゃがみ込み、膝取りの投げを狙う。
3:相手が膝を取りにきた瞬間、相手の頭部を押さえて鉄槌掌底打ち。
(正拳突きでは、頭部には滑ってしまう可能性が高いし、硬い頭骨には硬い拳よりも浸透力のある鉄槌の方が有効なため)
>>相手の肋骨に諸手突きをし、相手が前に倒れる時、あたまを挟む、(とどめを刺す)と習っています。
自分の聞いた解釈ではその他に、「諸手突きは、相手の鎖骨部分の急所押し痛めであり、それを喰らって思わずしゃがみ込んだ相手へのトドメ」
というのがありました。
>自分としては足取りならば、膝を動かせばそのまま顔面への攻撃になるし、取られた後に鉄槌掌底打ち→頭部を挟んでねじるのは難しいと思います。
上記についての自分の解釈ですが、
1:平拳による上段突きで相手のノドを狙う
(正拳ではアゴに当たってしまうが、平拳ならばノドに入る)
(型では諸手突きですが、これは片手でも構わないと思います)
2:相手がその上段突きをかわしてしゃがみ込み、膝取りの投げを狙う。
3:相手が膝を取りにきた瞬間、相手の頭部を押さえて鉄槌掌底打ち。
(正拳突きでは、頭部には滑ってしまう可能性が高いし、硬い頭骨には硬い拳よりも浸透力のある鉄槌の方が有効なため)
>小次郎 さん
興味深い解釈ですね。
私なりにまとめてみると
教本及び道場の教えからの疑問
1.諸手突きの肩-鎖骨の急所は狙って打つにはあまりにもピンポイントすぎるし、道衣の上からでは位置が判りづらい
2.1からの流れでの足取りは不自然すぎる
3.鉄槌掌底では極めにはならないのでないか
当初の私の解釈
1.相手が襟を両手で掴んで引き込み又は振り回しにきたところを、肋骨への右手平拳突き
2.同時に右足を半前屈に引き崩し
3.左手で相手の右手を掴み投げ(右手は添手)
4.投げの時左足を弧を描きながら引く(体を左に開く)
・・・簡単に言うと襟を掴んできた相手に小手返し
というものでした。
しかしここにも矛盾が・・・
・襟を掴まれた位置により体捌きが変わる
・腕力に頼った投げになり(襟上部の場合)型にするには不十分
・左足を引く動作が型には無い
(付け加えるなら、左足引きでの四股立ち下段払い)
まだまだ研究・稽古不足でこの仮説を実証するにはいたっていませんが、皆様の研究材料の種になればいいかと思います。
興味深い解釈ですね。
私なりにまとめてみると
教本及び道場の教えからの疑問
1.諸手突きの肩-鎖骨の急所は狙って打つにはあまりにもピンポイントすぎるし、道衣の上からでは位置が判りづらい
2.1からの流れでの足取りは不自然すぎる
3.鉄槌掌底では極めにはならないのでないか
当初の私の解釈
1.相手が襟を両手で掴んで引き込み又は振り回しにきたところを、肋骨への右手平拳突き
2.同時に右足を半前屈に引き崩し
3.左手で相手の右手を掴み投げ(右手は添手)
4.投げの時左足を弧を描きながら引く(体を左に開く)
・・・簡単に言うと襟を掴んできた相手に小手返し
というものでした。
しかしここにも矛盾が・・・
・襟を掴まれた位置により体捌きが変わる
・腕力に頼った投げになり(襟上部の場合)型にするには不十分
・左足を引く動作が型には無い
(付け加えるなら、左足引きでの四股立ち下段払い)
まだまだ研究・稽古不足でこの仮説を実証するにはいたっていませんが、皆様の研究材料の種になればいいかと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
剛柔流(空手) 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
剛柔流(空手)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人