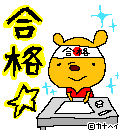|
|
|
|
コメント(26)
ペナルティーは課していませんが、カンニングするのですよ。宿題って言ってもやってこないし、「できる」っていうからやらせたら、全然できないし。勉強に対して誠実じゃないということは、他の面でも、不誠実になると思います。
だから、カンニングが、いけないことということを解らせるために、ペナルティーを今回は課しました。泣いて、悔しい、だから次はやってやる!という思いに繋がる可能性があるはずですから、これは大切だと私は思います。
単語の習得の開発している暇は、学生なので、はっきり言ってありませんよ。具体案を教えてほしいです。
私は、単語なんて、皆苦しんでしか覚えられないと思います。よほど、英語が好きな子どもならいいかもしてませんが・・・日本のように日本語で毎日を不自由なく暮らせる民族は、外国語を毎日使いませんし、定着なんてはっきりいって不可能ですよ。・・そうしたら、もう、無理に詰め込んで、授業で使って定着を図るしかないのですから・・・
確かに、すべて没収というのはいいアイディアだと思うのですが、信頼関係を崩したくないというのもあります。
だから、カンニングが、いけないことということを解らせるために、ペナルティーを今回は課しました。泣いて、悔しい、だから次はやってやる!という思いに繋がる可能性があるはずですから、これは大切だと私は思います。
単語の習得の開発している暇は、学生なので、はっきり言ってありませんよ。具体案を教えてほしいです。
私は、単語なんて、皆苦しんでしか覚えられないと思います。よほど、英語が好きな子どもならいいかもしてませんが・・・日本のように日本語で毎日を不自由なく暮らせる民族は、外国語を毎日使いませんし、定着なんてはっきりいって不可能ですよ。・・そうしたら、もう、無理に詰め込んで、授業で使って定着を図るしかないのですから・・・
確かに、すべて没収というのはいいアイディアだと思うのですが、信頼関係を崩したくないというのもあります。
ぴのこさんの言われている事は、自分なりにわかってはいますし、子どもがどうしたら、意欲的に勉強に取り組むように、意味づけをするかが大きな課題であることはわかります。
しかし塾は、学校ではありませんから、ただ「勉強を教えること」が目的です。よって生徒もそれを前提として入ってくることが、当たり前のこととして要求されるべきではないでしょうか?
しかし、最近は、親が子どもを保育所として送ってきている場合が多く、塾の本来のあり方と、現実があっていないのは現状です。
学問的な話になりますが、アメリカで1966年に「コールマン報告」というものが発表されたのをご存知でしょうか?
概要は、人間は、生まれ育った、家庭環境、地域によって、もう、その子の人生は大半決まってくるというものです。文化的に下位層の家庭に生まれた子どもは、社会的上昇移動が困難であり、上昇移動ができる下位文化層の子どもは、本当に一握りです。これは科学的にも証明されていますし、疑いの余地がありません。
彼らが勉強嫌いになるのは、生まれたときから決まっていたといっても、過言ではないのです。そのような子どもを塾に入れるようなこと事態、反教育(ここでは、学習者の望まない教育を大人が押し付け、学習意欲さえもなくさせてしまう教育)であり、彼らが虚無感を感じ、バーンアウト(燃え尽き症候群)を起こす可能性もあります。これこそが、人間としての豊かさの喪失にもつながります。これを、塾が解決できるでしょうか?
学校に任せるしか、(学校さえも頼りありませんが・・・)今の日本のシステムでは道はありません。
だから、塾は、教科としての勉強を教える場所でしかないのです。
生徒が勉強が嫌いなのは、承知ですが、それに向かわせるように、時には強制して教えていくしかないのだと私は考えます。あくまで、塾の仕事として、学校教育なら、話はべつですが・・・
しかし塾は、学校ではありませんから、ただ「勉強を教えること」が目的です。よって生徒もそれを前提として入ってくることが、当たり前のこととして要求されるべきではないでしょうか?
しかし、最近は、親が子どもを保育所として送ってきている場合が多く、塾の本来のあり方と、現実があっていないのは現状です。
学問的な話になりますが、アメリカで1966年に「コールマン報告」というものが発表されたのをご存知でしょうか?
概要は、人間は、生まれ育った、家庭環境、地域によって、もう、その子の人生は大半決まってくるというものです。文化的に下位層の家庭に生まれた子どもは、社会的上昇移動が困難であり、上昇移動ができる下位文化層の子どもは、本当に一握りです。これは科学的にも証明されていますし、疑いの余地がありません。
彼らが勉強嫌いになるのは、生まれたときから決まっていたといっても、過言ではないのです。そのような子どもを塾に入れるようなこと事態、反教育(ここでは、学習者の望まない教育を大人が押し付け、学習意欲さえもなくさせてしまう教育)であり、彼らが虚無感を感じ、バーンアウト(燃え尽き症候群)を起こす可能性もあります。これこそが、人間としての豊かさの喪失にもつながります。これを、塾が解決できるでしょうか?
学校に任せるしか、(学校さえも頼りありませんが・・・)今の日本のシステムでは道はありません。
だから、塾は、教科としての勉強を教える場所でしかないのです。
生徒が勉強が嫌いなのは、承知ですが、それに向かわせるように、時には強制して教えていくしかないのだと私は考えます。あくまで、塾の仕事として、学校教育なら、話はべつですが・・・
>アルさん
結構違和感あり。
塾は、ただ『勉強を教えること』が目的なのですか?
僕は専門家ではないので、教育論とかは分かりませんが、その、『コールマン報告』というのはそんなに権威のある報告なのですか?40年も前の報告なのに。
僕には、『(ほぼ)生まれつきのようなものだから、どうしようもない、手遅れだ』と思考停止しているようにしか思えません。
悪い環境に育っていたとしても、勉強に向かう姿勢を育ててあげることは出来ないのですか?
それとも、それに割く時間すらありませんか?
少なくとも僕は、塾は勉強を教えるだけの場とは思っていないし、勉強嫌いも治せると思ってやっています。
そうでなければ、僕らの存在価値はありますか?
結構違和感あり。
塾は、ただ『勉強を教えること』が目的なのですか?
僕は専門家ではないので、教育論とかは分かりませんが、その、『コールマン報告』というのはそんなに権威のある報告なのですか?40年も前の報告なのに。
僕には、『(ほぼ)生まれつきのようなものだから、どうしようもない、手遅れだ』と思考停止しているようにしか思えません。
悪い環境に育っていたとしても、勉強に向かう姿勢を育ててあげることは出来ないのですか?
それとも、それに割く時間すらありませんか?
少なくとも僕は、塾は勉強を教えるだけの場とは思っていないし、勉強嫌いも治せると思ってやっています。
そうでなければ、僕らの存在価値はありますか?
横から失礼します。
勿論生まれつきというのも否定はしませんが、肯定はしません。塾のあり方としてはそういうのも有りなのでしょう。「教科としての勉強を教える場所でしかない」ですか。私はそんな塾ならやりたくありません。また、強制して教えることは目的があるのではないですか?それは、親に喜ばれるためですか?私は、子供がそれで点数がとれ、面白いと感じてもらうために、敢えてつまらなくても強制的にさせるだけです。「やらせる→できた→面白い→やる」という好循環が目的です。
勉強が面白いものなどと言うつもりもないです。ただ、子供達に達成感を教え、社会で生き抜くための強い人間にしたいと思うだけです。勉強はその武器の1つでしかありません。あなたの定義されている塾がその域にしか居ないだけであって、私が目指す塾の形とは違います。それをひとくくりに言うのはどうかと思いますよ。
私はあなたの考え方もあって良いと思います。ただ、私は塾の守備範囲をもっと広く捕らえていますし、勉強だけを望まれ、社会性はどうでもいいという家ならうちからお断りします。学校ではなく、私企業だからこそ出来ることと言うのは存在するのだと思います。
ちょっと結論を急ぎすぎていませんか?結論が出たと思ったらまだ結論ではない。これが学問の基本ではないでしょうか。
勿論生まれつきというのも否定はしませんが、肯定はしません。塾のあり方としてはそういうのも有りなのでしょう。「教科としての勉強を教える場所でしかない」ですか。私はそんな塾ならやりたくありません。また、強制して教えることは目的があるのではないですか?それは、親に喜ばれるためですか?私は、子供がそれで点数がとれ、面白いと感じてもらうために、敢えてつまらなくても強制的にさせるだけです。「やらせる→できた→面白い→やる」という好循環が目的です。
勉強が面白いものなどと言うつもりもないです。ただ、子供達に達成感を教え、社会で生き抜くための強い人間にしたいと思うだけです。勉強はその武器の1つでしかありません。あなたの定義されている塾がその域にしか居ないだけであって、私が目指す塾の形とは違います。それをひとくくりに言うのはどうかと思いますよ。
私はあなたの考え方もあって良いと思います。ただ、私は塾の守備範囲をもっと広く捕らえていますし、勉強だけを望まれ、社会性はどうでもいいという家ならうちからお断りします。学校ではなく、私企業だからこそ出来ることと言うのは存在するのだと思います。
ちょっと結論を急ぎすぎていませんか?結論が出たと思ったらまだ結論ではない。これが学問の基本ではないでしょうか。
このコミュでは始めて書き込みさせていただきます。
人間が環境に左右されることには異論はありませんが、勉強だけ教えてもねぇ。仕事としておもしろくないですよ。
毎年同じような授業したって、年ごとに成績が変わりますからね。教えることだって大して重要じゃないと思っています。
ある程度経験のある人が教えれば、大差はないと思ってますし。
どんな生徒でも成績を大幅にアップできますというのであれば、勉強だけ教えていてもなんとかなると思いますけど。
あと、上位生だけ相手にしてるところも入りますかね。
あくまで、小学生・中学生を教えている立場で話しますが、
授業をする立場として大事なのは、塾という環境を提供してあげることだと考えています。
小学生には小学生の、中学生には中学生の過ごしやすい環境・状況があります。
そういう環境を授業において構築できる人が優れた講師だと私は考えています。
勉強を教えるということを使って、環境を整えていく。
変な言い方ですが、子供を適切な子供扱いしてあげるということです。
環境を整えてあげられれば、塾にいる間は生徒は間違った方向にはいきませんから。
カンニングにしろ宿題忘れにしろ対策はたくさんありますが、クラスの雰囲気がカンニングを許さない、宿題忘れを許さないというふうにもっていくのが長期的なビジョンだと思っていますし、それがベテラン講師の役目だとも考えています。
それが環境づくりだと思いますし。
あくまで私の場合ですが、仕事としてやっていて面白いのは、勉強を教えることが面白いわけではなく、生徒が自分の影響を受けて成長していくのが面白いんです。
いろんな生徒がいるのを、自分の生徒として一体感を持たせるのが楽しい。
人間は生まれたときの環境で人生が決まるみたいですが、生徒の人生をどうこうしようとして、この職業を私はやってるわけではありません。
反感を買うかもしれませんが、私は人として付き合ったときに気持ちよく付き合える人間を多く育てたいと思ってますので、あくまでその方法が勉強を教えるということだったということです。
文化的・社会的に低い地位の人でも、人間としていい人は多くいます。
そんな人を育てたいだけなんですけどねぇ。
話が長く、まとまってない部分も多くありますが、社会不適格者のたわごとと聞き流してくださるとありがたいです。
人間が環境に左右されることには異論はありませんが、勉強だけ教えてもねぇ。仕事としておもしろくないですよ。
毎年同じような授業したって、年ごとに成績が変わりますからね。教えることだって大して重要じゃないと思っています。
ある程度経験のある人が教えれば、大差はないと思ってますし。
どんな生徒でも成績を大幅にアップできますというのであれば、勉強だけ教えていてもなんとかなると思いますけど。
あと、上位生だけ相手にしてるところも入りますかね。
あくまで、小学生・中学生を教えている立場で話しますが、
授業をする立場として大事なのは、塾という環境を提供してあげることだと考えています。
小学生には小学生の、中学生には中学生の過ごしやすい環境・状況があります。
そういう環境を授業において構築できる人が優れた講師だと私は考えています。
勉強を教えるということを使って、環境を整えていく。
変な言い方ですが、子供を適切な子供扱いしてあげるということです。
環境を整えてあげられれば、塾にいる間は生徒は間違った方向にはいきませんから。
カンニングにしろ宿題忘れにしろ対策はたくさんありますが、クラスの雰囲気がカンニングを許さない、宿題忘れを許さないというふうにもっていくのが長期的なビジョンだと思っていますし、それがベテラン講師の役目だとも考えています。
それが環境づくりだと思いますし。
あくまで私の場合ですが、仕事としてやっていて面白いのは、勉強を教えることが面白いわけではなく、生徒が自分の影響を受けて成長していくのが面白いんです。
いろんな生徒がいるのを、自分の生徒として一体感を持たせるのが楽しい。
人間は生まれたときの環境で人生が決まるみたいですが、生徒の人生をどうこうしようとして、この職業を私はやってるわけではありません。
反感を買うかもしれませんが、私は人として付き合ったときに気持ちよく付き合える人間を多く育てたいと思ってますので、あくまでその方法が勉強を教えるということだったということです。
文化的・社会的に低い地位の人でも、人間としていい人は多くいます。
そんな人を育てたいだけなんですけどねぇ。
話が長く、まとまってない部分も多くありますが、社会不適格者のたわごとと聞き流してくださるとありがたいです。
否定されたとは感じていませんよ。別にそれはそれでありな考え方だとは思っていますから。そして、その上での行動を考え取るようにしています。
アルさんの書き方で問題なのは押し付けに走っているように読める点です。(そんなつもりは無いのかもしれませんが)あなたより考えた上で行動している人も居るかもしれませんよ。
確かに、コールマン報告はアメリカ史上最大の教育調査です。そして参考にすべき部分があるのは事実です。ただ、1965年という時代や、教育背景は全く変わっているのが実情です。当然国民性も違いますしね。それらを踏まえれば、それに傾倒していても話にならないとも考えることが出来るのではないでしょうか。
別にコールマン報告を否定するのが仕事ではありませんので、それを報告したいというのはありませんよ。事実参考になる点も多いですから。私自身は今、目の前に居る生徒の成長に如何にして関わるべきなのかを悩むだけです。そのときに、「塾」が「勉強だけを教えておけばいい」とは考えていないというだけです。
アルさんの書き方で問題なのは押し付けに走っているように読める点です。(そんなつもりは無いのかもしれませんが)あなたより考えた上で行動している人も居るかもしれませんよ。
確かに、コールマン報告はアメリカ史上最大の教育調査です。そして参考にすべき部分があるのは事実です。ただ、1965年という時代や、教育背景は全く変わっているのが実情です。当然国民性も違いますしね。それらを踏まえれば、それに傾倒していても話にならないとも考えることが出来るのではないでしょうか。
別にコールマン報告を否定するのが仕事ではありませんので、それを報告したいというのはありませんよ。事実参考になる点も多いですから。私自身は今、目の前に居る生徒の成長に如何にして関わるべきなのかを悩むだけです。そのときに、「塾」が「勉強だけを教えておけばいい」とは考えていないというだけです。
文化的・社会的に地位の低い人が、「悪い人」というように受け取られたのなら、誤解ですよ。
教育すること、よりよい人間関係を築くことが、人間にっとて豊かな人格を育むというスタンスを私自身も大切だと思っています。
しかし、塾では、人格的な教育までには発展しない、限界があると私は考えます。
体系的に、その子の特徴を生かした教科学習をし、夏休みには、体験学習をする塾、そして、アルバイトではなく、教員免許を持っ他人材を責任者がしっかりと、教師教育している・・・ならば、それは教育効果もありでしょうし、理想ですけどね。
コールマンの報告を知らない方も多かったですし・・・そういう現実を教育者として知っておくことは大切なことだと思います。
教育すること、よりよい人間関係を築くことが、人間にっとて豊かな人格を育むというスタンスを私自身も大切だと思っています。
しかし、塾では、人格的な教育までには発展しない、限界があると私は考えます。
体系的に、その子の特徴を生かした教科学習をし、夏休みには、体験学習をする塾、そして、アルバイトではなく、教員免許を持っ他人材を責任者がしっかりと、教師教育している・・・ならば、それは教育効果もありでしょうし、理想ですけどね。
コールマンの報告を知らない方も多かったですし・・・そういう現実を教育者として知っておくことは大切なことだと思います。
ども。書き込みさせていただきます。
ちなみに、教員免許は持ってません。
教育論も体系づいた学問としては大して詳しくない、法学部卒です。
塾の生徒だった頃の自分と周辺の友人たちのことを振り返るに、塾というのは多くの子供たちにとって「勉強を教えてもらう場所」ではなく、「勉強の仕方を学ぶ場所」であったような気がします。
もちろん、思春期真っ盛りのその時期に本気で勉強をしたいと思うような殊勝な輩は、いつの時代でも少数派です。だから、生徒にとって塾に対する一番の位置付けは、結局のところ「塾の友達と会うためのクラブ活動」みたいなものでしょう。たいがい。
でも、塾の授業中は遊んだりおしゃべりをしたりすることはできません。勉強をします。それも、学校のように第二の我が家と思えるくらい緊張感の薄いアットホームな空気ではなく、(一応でも)「勉強するぞ」という気合が満ちている環境の下で友達と勉強をいっしょにする。そういうことをする中で、子供は子供なりの競争心を刺激され、また自分の勉強の到達度を痛感し、「どうしたら成績が伸びるのか」というテーマに一生懸命に悩み、もがいて苦しんで試行錯誤をする。
勉強するだけなら、おんなじことを学校で教わっているのだからそっちで学べば良いことなのです。タダなんだし、学校で勉強しておしまいにできれば、塾に行くのに使う時間で思いっきり遊べる訳だし。
でも、塾に来る生徒たちはそれができない。学校の授業を受けているだけでは勉強が分からない、あるいはそれだけでは物足りない。だから、勉強と向き合うに際して足りない何かを補いたいがために塾に来る。そういう心理が働いているのではないかと私は思います。
(昔を思い出してシミュレーションしたとき、ただ「勉強を詰め込む」だけの空間に自ら足を運んだ、あるいは親に指示されたからといって素直にそれに従ったと思いますか?たとえ子供でも1歳半を過ぎれば自我が出ますから、本気でイヤなもんはイヤだと主張するもんです。
子供にだってちっちゃいながらもプライドがあります。自分の抱えている(学力に対する)劣等感を克服したいとか、目の前にある(成績の)壁を乗り越えてやりたいとか、そういう情熱は、実は当の本人の内側では他人には馬鹿にできないくらいの強い燃え方をしていたりするもんです)
学力を意識されるようになる年頃の子供を持つ親も、塾に対して求めているものは似たようなものであると思います。
機械的に知識を詰め込んで、頭でっかちの「知ったかぶり」のロボットみたいな子供に育ててやりたいと、どこの親が思うでしょうか。人の親たるもの、我が子には立派に自律した人間になって欲しいと願うものです。成績上昇は確かに目先の目標ではあるけれども、最終的な、特に学力の乏しい子供を持つ親が抱く到達点は
「自分から悩み、自ら答えを考え出せる力を持った人になる」
ということの一点であるのではなかろうか、と私は考えます。
塾が直接接するお客様は勉強を教わりに来る生徒ですが、商売の基本に立ち返るならば、本当のお客様というのは塾にお金を払ってくださるご両親(片親でもいいや)です。そう考えたとき、生徒に「テストで問われる知識」をたくさん詰め込み、表面的にテストの点数を上昇させ、以って生徒のご両親に「子供の学力が上がった」と思わせるというのは、これは立派な詐欺です。お客様の本当の希望を果たしていない。
塾講師たるもの、生徒にはどんな手段によってであれ「勉強の楽しさ、面白さ」を教えることで学習に対する本人の意欲を引き出すことをしなければなりません。塾に通ったことで考えることが楽しくなった、授業を受けているうちに脳みその歯車の滑りが良くなってきた、そういう風に感じさせることができなければ、私は塾講師としては失格であると思います。
……長くなったので、一回切ります。
本当は「単語テストの有効な行い方」を書きたいのだった……。
ちなみに、教員免許は持ってません。
教育論も体系づいた学問としては大して詳しくない、法学部卒です。
塾の生徒だった頃の自分と周辺の友人たちのことを振り返るに、塾というのは多くの子供たちにとって「勉強を教えてもらう場所」ではなく、「勉強の仕方を学ぶ場所」であったような気がします。
もちろん、思春期真っ盛りのその時期に本気で勉強をしたいと思うような殊勝な輩は、いつの時代でも少数派です。だから、生徒にとって塾に対する一番の位置付けは、結局のところ「塾の友達と会うためのクラブ活動」みたいなものでしょう。たいがい。
でも、塾の授業中は遊んだりおしゃべりをしたりすることはできません。勉強をします。それも、学校のように第二の我が家と思えるくらい緊張感の薄いアットホームな空気ではなく、(一応でも)「勉強するぞ」という気合が満ちている環境の下で友達と勉強をいっしょにする。そういうことをする中で、子供は子供なりの競争心を刺激され、また自分の勉強の到達度を痛感し、「どうしたら成績が伸びるのか」というテーマに一生懸命に悩み、もがいて苦しんで試行錯誤をする。
勉強するだけなら、おんなじことを学校で教わっているのだからそっちで学べば良いことなのです。タダなんだし、学校で勉強しておしまいにできれば、塾に行くのに使う時間で思いっきり遊べる訳だし。
でも、塾に来る生徒たちはそれができない。学校の授業を受けているだけでは勉強が分からない、あるいはそれだけでは物足りない。だから、勉強と向き合うに際して足りない何かを補いたいがために塾に来る。そういう心理が働いているのではないかと私は思います。
(昔を思い出してシミュレーションしたとき、ただ「勉強を詰め込む」だけの空間に自ら足を運んだ、あるいは親に指示されたからといって素直にそれに従ったと思いますか?たとえ子供でも1歳半を過ぎれば自我が出ますから、本気でイヤなもんはイヤだと主張するもんです。
子供にだってちっちゃいながらもプライドがあります。自分の抱えている(学力に対する)劣等感を克服したいとか、目の前にある(成績の)壁を乗り越えてやりたいとか、そういう情熱は、実は当の本人の内側では他人には馬鹿にできないくらいの強い燃え方をしていたりするもんです)
学力を意識されるようになる年頃の子供を持つ親も、塾に対して求めているものは似たようなものであると思います。
機械的に知識を詰め込んで、頭でっかちの「知ったかぶり」のロボットみたいな子供に育ててやりたいと、どこの親が思うでしょうか。人の親たるもの、我が子には立派に自律した人間になって欲しいと願うものです。成績上昇は確かに目先の目標ではあるけれども、最終的な、特に学力の乏しい子供を持つ親が抱く到達点は
「自分から悩み、自ら答えを考え出せる力を持った人になる」
ということの一点であるのではなかろうか、と私は考えます。
塾が直接接するお客様は勉強を教わりに来る生徒ですが、商売の基本に立ち返るならば、本当のお客様というのは塾にお金を払ってくださるご両親(片親でもいいや)です。そう考えたとき、生徒に「テストで問われる知識」をたくさん詰め込み、表面的にテストの点数を上昇させ、以って生徒のご両親に「子供の学力が上がった」と思わせるというのは、これは立派な詐欺です。お客様の本当の希望を果たしていない。
塾講師たるもの、生徒にはどんな手段によってであれ「勉強の楽しさ、面白さ」を教えることで学習に対する本人の意欲を引き出すことをしなければなりません。塾に通ったことで考えることが楽しくなった、授業を受けているうちに脳みその歯車の滑りが良くなってきた、そういう風に感じさせることができなければ、私は塾講師としては失格であると思います。
……長くなったので、一回切ります。
本当は「単語テストの有効な行い方」を書きたいのだった……。
トピック立てた本人の
>皆さん色々、思想?があるようですので、それを活用して、新しいトッピクにトライしてみてください。
という一言にえらくムカついてます。
っていうか、所詮学生なんて暇だろ?忙しいことに何の積極的理由があるんだ?
生徒に教えるための効率的な単語の勉強方法なんて、お前みたいな非生産的な「考える葦」が自分で考えろ。自分が携わる他人に影響を与える有効な手段を自ら考案できないで、一体何のために「学生」って身分でいるんだい?
なーんて言ってドロップアウトしても良いのですが、他にトピックをご覧になっている方々にも問題提起したいので、話を続けます。
で、「英単語の有効な学習方法」ですが。
我々大人でも日本語で新しく知った言葉をしばらく使わずにいると忘れてしまうように、子供も所詮は忘却の生き物であると思います。私。
なので、基本的にはやはり「繰り返し」の作業をさせるしかないのではないでしょうか。
もちろん、通常の学習に支障のない限度の単語量を持っている生徒については
・長文読解を繰り返すことで頻出単語に馴染ませる
・「でる順」などで単語やイディオムを効率的に記憶させる
というのが、生徒の興味を刺激しやすいという点からも有効であると思います。
しかし、問題はいわゆる「できない」生徒です。
こいつら、どうしたら良いでしょうかねー。カンニングしたりしますから。笑
現在、私が採っている方法は「日本語(カタカナ語)」に溶け込んでいる単語から覚えさせる、というものです。
例えば体について云えば、
・ロングヘア、ショートヘア
・アイコンタクト
・チーク(化粧用語)
・リップクリーム
・マウスピース
・ネックレス、タートルネック
・チェストパス(バスケ用語)
・ハンド(サッカー用語)
・ネイルアート
・ニードロップ(プロレス用語)
・ヒールキック(サッカー用語)
・トゥシューズ(バレエ用語)
などなど、生徒の知っている言葉から、
「この言葉はな、英語でこう綴るねんで」
という具合に教えます。で、書き取り10回とか。
そんな風にして少しずつ英語のスペルに慣れさせるのが、子供たちの英語の習得に興味を持たせるきっかけになればなー、といつも思っています。
皆さん、右も左も分からないのに突然「今日から成人のみなさんは必須科目になったから、全員サンスクリット語を覚えろ」とか云われてもイヤでしょ?笑
こうしてやると、結構子供たちは「自力で書く」っていうのをしてくれています。少なくともうちの教室では。
みなさんのところはいかがなものでしょうか。
>皆さん色々、思想?があるようですので、それを活用して、新しいトッピクにトライしてみてください。
という一言にえらくムカついてます。
っていうか、所詮学生なんて暇だろ?忙しいことに何の積極的理由があるんだ?
生徒に教えるための効率的な単語の勉強方法なんて、お前みたいな非生産的な「考える葦」が自分で考えろ。自分が携わる他人に影響を与える有効な手段を自ら考案できないで、一体何のために「学生」って身分でいるんだい?
なーんて言ってドロップアウトしても良いのですが、他にトピックをご覧になっている方々にも問題提起したいので、話を続けます。
で、「英単語の有効な学習方法」ですが。
我々大人でも日本語で新しく知った言葉をしばらく使わずにいると忘れてしまうように、子供も所詮は忘却の生き物であると思います。私。
なので、基本的にはやはり「繰り返し」の作業をさせるしかないのではないでしょうか。
もちろん、通常の学習に支障のない限度の単語量を持っている生徒については
・長文読解を繰り返すことで頻出単語に馴染ませる
・「でる順」などで単語やイディオムを効率的に記憶させる
というのが、生徒の興味を刺激しやすいという点からも有効であると思います。
しかし、問題はいわゆる「できない」生徒です。
こいつら、どうしたら良いでしょうかねー。カンニングしたりしますから。笑
現在、私が採っている方法は「日本語(カタカナ語)」に溶け込んでいる単語から覚えさせる、というものです。
例えば体について云えば、
・ロングヘア、ショートヘア
・アイコンタクト
・チーク(化粧用語)
・リップクリーム
・マウスピース
・ネックレス、タートルネック
・チェストパス(バスケ用語)
・ハンド(サッカー用語)
・ネイルアート
・ニードロップ(プロレス用語)
・ヒールキック(サッカー用語)
・トゥシューズ(バレエ用語)
などなど、生徒の知っている言葉から、
「この言葉はな、英語でこう綴るねんで」
という具合に教えます。で、書き取り10回とか。
そんな風にして少しずつ英語のスペルに慣れさせるのが、子供たちの英語の習得に興味を持たせるきっかけになればなー、といつも思っています。
皆さん、右も左も分からないのに突然「今日から成人のみなさんは必須科目になったから、全員サンスクリット語を覚えろ」とか云われてもイヤでしょ?笑
こうしてやると、結構子供たちは「自力で書く」っていうのをしてくれています。少なくともうちの教室では。
みなさんのところはいかがなものでしょうか。
皆さん、感情論になりすぎてますので、私は、もうここトッピクでは、書き込みしませんが、もう少し、冷静になってから考えてみてくさい。
学生は暇ですか・・・私は、そういった学生と一緒にされたくないですね。確かに学生はそうだと世間一般考えてますし、実際多いですけど、私に夏休みなどありませんよ、中学校の先生にはなしを聞いたり、実際に小学校などに行ってボランティアもしてます。塾でアルバイトしているのも、実際に今の子どもがどうであるのか知りたいからです。
理論や科学的なものの見方も勉強していますし、塾について書かれた文献も読んでいます。
「教育とは何か」「人間とは何か」自分なりに考え、文献も読み、現場からの声も聞けるように、自分で行動していますよ。
たぶん、皆さんが考えている、人格教育と私が考えている人格教育では、相違点があるのでしょう。
経験だけでは補えないものって教育には多いのですよ。ベテラン教員の学級崩壊はいい例です。子どもは変わり行く存在です。時代が変わり行くとき、大人の経験則だけを頼りにしては、真に教育をすることはできません。
自分の立場を否定されたからといって、感情的になるのではなく、そういう考え方もあるのかと考え、じゃあ、この人はなぜそう考えるのか、と建設的にならなければ、話し合いの意味はなくなって合いますと思いますよ。
途中で、私も感情的になったと感じた人もいるかもしれませんが、それは誤解ですよ。
あと、私が学生だから、女だから、年下だから的な発言は、教育者として疑問です。
学生は暇ですか・・・私は、そういった学生と一緒にされたくないですね。確かに学生はそうだと世間一般考えてますし、実際多いですけど、私に夏休みなどありませんよ、中学校の先生にはなしを聞いたり、実際に小学校などに行ってボランティアもしてます。塾でアルバイトしているのも、実際に今の子どもがどうであるのか知りたいからです。
理論や科学的なものの見方も勉強していますし、塾について書かれた文献も読んでいます。
「教育とは何か」「人間とは何か」自分なりに考え、文献も読み、現場からの声も聞けるように、自分で行動していますよ。
たぶん、皆さんが考えている、人格教育と私が考えている人格教育では、相違点があるのでしょう。
経験だけでは補えないものって教育には多いのですよ。ベテラン教員の学級崩壊はいい例です。子どもは変わり行く存在です。時代が変わり行くとき、大人の経験則だけを頼りにしては、真に教育をすることはできません。
自分の立場を否定されたからといって、感情的になるのではなく、そういう考え方もあるのかと考え、じゃあ、この人はなぜそう考えるのか、と建設的にならなければ、話し合いの意味はなくなって合いますと思いますよ。
途中で、私も感情的になったと感じた人もいるかもしれませんが、それは誤解ですよ。
あと、私が学生だから、女だから、年下だから的な発言は、教育者として疑問です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
塾の先生 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
塾の先生のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89525人