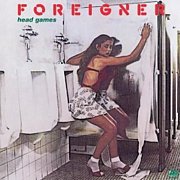Coldplay「Parachutes」2000年UK
コールドプレイ「パラシューツ」
1.Don't Panic
2.Shiver
3.Spies
4.Sparks
5.Yellow
6.Trouble
7.Parachutes
8.High Speed
9.We Never Change
10.Everything's Not Lost〜Life Is For Living(secret track)
11.Careful Where You Stand
12.For You
Will Champion(Dr)
Guy Berryman(B)
Chris Martin(Vo,G,Piano)
Jonny Buckland(G)
出したアルバムの4枚全てが1000万枚を超えるような世界規模のメガヒットを連発し、今やモンスターバンドになってしまった彼ら。
しかし私がこの1stアルバムを聴いたのは、このデビュー作の日本盤が出て、すこし話題になっていたくらいの頃だ。このときは、正直、全く何て情緒的で弱々しく力無い音なんだろう、と感じ、私の中に留まることはなかった。ちょうどその頃か少し前にはやったアメリカの超叙情派カントリーテイストのカウンティングクロウズとか、その辺りの流れに響いた向きか、とくくってしまった。
そんなわけで2ndはパスしてしまった。
そして2006年の3rdアルバム、X&Yがでた。街中から流れてきたその歌声を聴いたとき、私は完全にU2の新譜だと思ってしまった。うたいあげる時に伸ばされる声の響きはボノに酷似していた。しかし最近のボノと比べると、やけに丁寧で繊細だな、と。それがあの暗い暗いコールドプレイだとわかって驚いた。そんなバンドだったっけ?!
元の印象が相当暗かったせいで、X&Yはかなりポジティブになった印象を受けた。
つまり弱々しくて、後ろ向きで、ネガティヴな連中が、力強さと前向きさをつかみ取ったんだな、知らない間に、色々な葛藤を乗り越えて、勝ち取ったんだな、そんな風に私は受け止めた。
1stでは聴かれなかったようなテクノ的ビート感、まるでZooropa〜Pop期のU2のような、あるいは後期のピンクフロイドやDepesh mode、最近ではMuseのようなスペイシーで大きな空間の使い方、その方法論自体に、彼らが前向きさとパワーと自信を勝ち得たことを感じた。
基本的に、ロックというものは、精神の闇や、挫折や葛藤、弱さや苦しみ、そんなものから始まるし、そこをどれだけ踏まえた音が鳴らされているかどうか、ということはかなり重要な要素になっている、と私は思う。それがどんな類いの苦しみなのか、どんな希望を抱くのか、そこに時代による違いや共通点が宿るものだ。
そんな意味で、Coldplayのアルバムごとの遍歴には、私には好意的な精神的音楽遍歴が感じられた。X&Yを聴いて、ちょっとあらためて彼らのアルバムを聞き直してみよう、と思ったのだ。
そして、あらためて聴いた、この「パラシューツ」。
申し訳ない、というか情けない。
こんなに良いアルバムだったのか。
先入観というか、あやうく見過ごしてしまうところだった。
2ndの「A Rush of Blood to the Head(静寂の世界)」も良いが、今の私には1stの方が、断然響く。
と言うわけで、Parachutes、やっぱり暗いことは暗い。
しかし、X&Yを通過した耳で聞くと、全く違う表情を見せてくれた。
消え入りそうなファルセットの裏声、9割の悲観と自虐の中に、確かに1割ほどの、希望と願いをこめた、弱々しくも美しい光のようなものが横たわっている。
この1stアルバムの魅力のひとつは、その悲観の”率直さ”だろう。
等身大の、生々しい絶望や悲しみが、自分の言葉でつづられていて、とてもパーソナルな感触をあたえる。これだけ個人的な内面的な感情、それも陰の側面をさらけ出すこと、それを伝えられることは、なかなか力量がいることだ。音楽的にも人間力的にも。
たいがいは、ありきたりな音楽的プロトタイプ、ありがちな形にあてはめて、自分の本当の感情をそのまんまはすくい取れない、音楽として表現しきれないものだ。
というわけで、彼らの魅力のもうひとつは、細かな感情のひだを、うつくしいメロディーに変えてしまうソングライティングの能力だ。
かれらのメロディーの魅力を語るときに、その時代的普遍性を言われることがある。しかし、彼らの音からは、U2やDepeshに代表される英国ニューウェーブ勢の成熟と、REMやレディオヘッドなどのグランジ以降のギターロックからの影響が感じられる。その意味では、きわめて現代的なサウンドなのだ。普遍的に感じさせるほど、ナチュラルにメロディがこなれているということだろう。そして、それだけ広く視野を広げた感受性のキャパシティが、かれらを英国というワクにはまらないスケールの大きな同時代性を勝ち得たのだろう。
この点では、アルバムを重ねるごとに、彼らは大いに大英帝国の先輩達の遺産を引き継いでいく。しかし、この1stアルバムでは、まだまだ弱々しく悲愴な、スタートしたばかりの繊細な楽曲に、オリジナリティが感じられる。
9割の悲観と1割の希望、そんな気分が、今の私にはとてもしっくりくる。
彼らの歩みは、その逆。
ありのままの自分たちを歌った1st、自分達の姿を突き詰めて、そぎ落としてゆく過程がソリッドな音になった2nd、そして全部かかえて力強く歩み始めた3rd、まるで今までの3作が遠い過去の話であるかのような普遍的なメロディーを奏で始めた最新作。きわめて個人的な歌の昇華が、メロディーの力を借りて普遍性をもつことを、メガヒットを連発することで証明してしまった彼ら。
一作ずつ成長してゆく姿を、ありのままみせてくれている彼ら。
一貫してすばらしいソングライティング力ゆえに、豊かな表現力で、雄弁に伝わるメロディーをかける彼ら。ふとした瞬間に、偉大な先輩を彷彿とさせる側面は、我々の耳を引きつける。
次はどんな一歩を踏み出してゆくのか、ずっと、その真摯な歩みを、我々に見せて欲しい。
もしも最近の彼らのポップな魅力だけをみている方は、ぜひこの1stアルバムを聴いてみて欲しい。彼らの本質は、ここにあるのだと思う。すばらしいメロディーや、アレンジで、逆に見えにくくなってしまっているかもしれない。
ひりひりするくらい、ぎりぎりの、繊細な、暗い魂のさまよい、そこから始まる旅路。
名盤です。
コールドプレイ「パラシューツ」
1.Don't Panic
2.Shiver
3.Spies
4.Sparks
5.Yellow
6.Trouble
7.Parachutes
8.High Speed
9.We Never Change
10.Everything's Not Lost〜Life Is For Living(secret track)
11.Careful Where You Stand
12.For You
Will Champion(Dr)
Guy Berryman(B)
Chris Martin(Vo,G,Piano)
Jonny Buckland(G)
出したアルバムの4枚全てが1000万枚を超えるような世界規模のメガヒットを連発し、今やモンスターバンドになってしまった彼ら。
しかし私がこの1stアルバムを聴いたのは、このデビュー作の日本盤が出て、すこし話題になっていたくらいの頃だ。このときは、正直、全く何て情緒的で弱々しく力無い音なんだろう、と感じ、私の中に留まることはなかった。ちょうどその頃か少し前にはやったアメリカの超叙情派カントリーテイストのカウンティングクロウズとか、その辺りの流れに響いた向きか、とくくってしまった。
そんなわけで2ndはパスしてしまった。
そして2006年の3rdアルバム、X&Yがでた。街中から流れてきたその歌声を聴いたとき、私は完全にU2の新譜だと思ってしまった。うたいあげる時に伸ばされる声の響きはボノに酷似していた。しかし最近のボノと比べると、やけに丁寧で繊細だな、と。それがあの暗い暗いコールドプレイだとわかって驚いた。そんなバンドだったっけ?!
元の印象が相当暗かったせいで、X&Yはかなりポジティブになった印象を受けた。
つまり弱々しくて、後ろ向きで、ネガティヴな連中が、力強さと前向きさをつかみ取ったんだな、知らない間に、色々な葛藤を乗り越えて、勝ち取ったんだな、そんな風に私は受け止めた。
1stでは聴かれなかったようなテクノ的ビート感、まるでZooropa〜Pop期のU2のような、あるいは後期のピンクフロイドやDepesh mode、最近ではMuseのようなスペイシーで大きな空間の使い方、その方法論自体に、彼らが前向きさとパワーと自信を勝ち得たことを感じた。
基本的に、ロックというものは、精神の闇や、挫折や葛藤、弱さや苦しみ、そんなものから始まるし、そこをどれだけ踏まえた音が鳴らされているかどうか、ということはかなり重要な要素になっている、と私は思う。それがどんな類いの苦しみなのか、どんな希望を抱くのか、そこに時代による違いや共通点が宿るものだ。
そんな意味で、Coldplayのアルバムごとの遍歴には、私には好意的な精神的音楽遍歴が感じられた。X&Yを聴いて、ちょっとあらためて彼らのアルバムを聞き直してみよう、と思ったのだ。
そして、あらためて聴いた、この「パラシューツ」。
申し訳ない、というか情けない。
こんなに良いアルバムだったのか。
先入観というか、あやうく見過ごしてしまうところだった。
2ndの「A Rush of Blood to the Head(静寂の世界)」も良いが、今の私には1stの方が、断然響く。
と言うわけで、Parachutes、やっぱり暗いことは暗い。
しかし、X&Yを通過した耳で聞くと、全く違う表情を見せてくれた。
消え入りそうなファルセットの裏声、9割の悲観と自虐の中に、確かに1割ほどの、希望と願いをこめた、弱々しくも美しい光のようなものが横たわっている。
この1stアルバムの魅力のひとつは、その悲観の”率直さ”だろう。
等身大の、生々しい絶望や悲しみが、自分の言葉でつづられていて、とてもパーソナルな感触をあたえる。これだけ個人的な内面的な感情、それも陰の側面をさらけ出すこと、それを伝えられることは、なかなか力量がいることだ。音楽的にも人間力的にも。
たいがいは、ありきたりな音楽的プロトタイプ、ありがちな形にあてはめて、自分の本当の感情をそのまんまはすくい取れない、音楽として表現しきれないものだ。
というわけで、彼らの魅力のもうひとつは、細かな感情のひだを、うつくしいメロディーに変えてしまうソングライティングの能力だ。
かれらのメロディーの魅力を語るときに、その時代的普遍性を言われることがある。しかし、彼らの音からは、U2やDepeshに代表される英国ニューウェーブ勢の成熟と、REMやレディオヘッドなどのグランジ以降のギターロックからの影響が感じられる。その意味では、きわめて現代的なサウンドなのだ。普遍的に感じさせるほど、ナチュラルにメロディがこなれているということだろう。そして、それだけ広く視野を広げた感受性のキャパシティが、かれらを英国というワクにはまらないスケールの大きな同時代性を勝ち得たのだろう。
この点では、アルバムを重ねるごとに、彼らは大いに大英帝国の先輩達の遺産を引き継いでいく。しかし、この1stアルバムでは、まだまだ弱々しく悲愴な、スタートしたばかりの繊細な楽曲に、オリジナリティが感じられる。
9割の悲観と1割の希望、そんな気分が、今の私にはとてもしっくりくる。
彼らの歩みは、その逆。
ありのままの自分たちを歌った1st、自分達の姿を突き詰めて、そぎ落としてゆく過程がソリッドな音になった2nd、そして全部かかえて力強く歩み始めた3rd、まるで今までの3作が遠い過去の話であるかのような普遍的なメロディーを奏で始めた最新作。きわめて個人的な歌の昇華が、メロディーの力を借りて普遍性をもつことを、メガヒットを連発することで証明してしまった彼ら。
一作ずつ成長してゆく姿を、ありのままみせてくれている彼ら。
一貫してすばらしいソングライティング力ゆえに、豊かな表現力で、雄弁に伝わるメロディーをかける彼ら。ふとした瞬間に、偉大な先輩を彷彿とさせる側面は、我々の耳を引きつける。
次はどんな一歩を踏み出してゆくのか、ずっと、その真摯な歩みを、我々に見せて欲しい。
もしも最近の彼らのポップな魅力だけをみている方は、ぜひこの1stアルバムを聴いてみて欲しい。彼らの本質は、ここにあるのだと思う。すばらしいメロディーや、アレンジで、逆に見えにくくなってしまっているかもしれない。
ひりひりするくらい、ぎりぎりの、繊細な、暗い魂のさまよい、そこから始まる旅路。
名盤です。
|
|
|
|
コメント(1)
僕とこのアーティストとの出会いはガールフレンドの勧めだった。
既にアメリカでブレイクした後で、RADIOHEADやデイヴ・マシューズバンドに凝っていたので割とすんなり入り込めた。
確かに線の細い印象はあったが、トラヴィス、ミューズ、ヴァーヴも聴いていたからUKバンドはこんなものかとそれほど気にはならなかった。
このアーティストを語るうえで欠かせないのは、アルバムごとに楽曲、アレンジ等のスケールアップしていることもさることながら、ライヴ・パフォーマンスの成長ぶりだと思う。
2ndがリリースされる前にインターネットで公開されたライブを観たときは正直がっかりした。演奏は下手ではないが、ロックバンドとは思えない積極性に欠けるパフォーマンスだった。
それが3rdの頃には別のバンドとも思えるダイナミックなクリスのフロントマンのとしての見事な成長ぶりに驚かされた。会場との一体感は、彼らの作品がファンに認知された証だろう。他のメンバーは地味だが、彼らとの信頼関係がクリスを支えていることは言うまでもない。
既にアメリカでブレイクした後で、RADIOHEADやデイヴ・マシューズバンドに凝っていたので割とすんなり入り込めた。
確かに線の細い印象はあったが、トラヴィス、ミューズ、ヴァーヴも聴いていたからUKバンドはこんなものかとそれほど気にはならなかった。
このアーティストを語るうえで欠かせないのは、アルバムごとに楽曲、アレンジ等のスケールアップしていることもさることながら、ライヴ・パフォーマンスの成長ぶりだと思う。
2ndがリリースされる前にインターネットで公開されたライブを観たときは正直がっかりした。演奏は下手ではないが、ロックバンドとは思えない積極性に欠けるパフォーマンスだった。
それが3rdの頃には別のバンドとも思えるダイナミックなクリスのフロントマンのとしての見事な成長ぶりに驚かされた。会場との一体感は、彼らの作品がファンに認知された証だろう。他のメンバーは地味だが、彼らとの信頼関係がクリスを支えていることは言うまでもない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
洋楽名盤・新譜 レビュー 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
洋楽名盤・新譜 レビューのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90050人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人