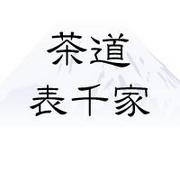お茶にまつわる言葉でしりとりお勉強をしましょう。
ルール:普通にしりとりをする(お茶に関連する用語)
コメントとして、その用語の説明をしながら勉強する。
「ん」で終わったら1つ前の文字から続ける。
■■あくまで真面目に!が秘訣です。■■
しりとり既出ワードリストはこちら
http://
ルール:普通にしりとりをする(お茶に関連する用語)
コメントとして、その用語の説明をしながら勉強する。
「ん」で終わったら1つ前の文字から続ける。
■■あくまで真面目に!が秘訣です。■■
しりとり既出ワードリストはこちら
http://
|
|
|
|
コメント(769)
まっちゃん
関戸家旧蔵の蜜柑の水指、その話は他の方からも伺いました。
名品中の名品だそうですね。
地元ですから関戸さまのご当主にも以前はよくお茶会でお目にかかりました。
自分ちの旧蔵品によそのお茶会で再会するって、どんな気分なんでしょう。
庶民には想像がつきません。
ミロクさん
ジーポせんせご多用中のご様子にて、及ばずながらあたくしめが画像をいくつかアップします。
左は写ですがまっちゃんのお話にあった「蓋裏のぶらんこ唐子」
右は湯木美術館所蔵品です。こちらの蓋裏はもちろん「ぶらんこ唐子」なのでしょうね。
いろいろ検索してましたら、祥瑞について面白いエッセイを見つけましたのでご一読ください。
http://china168.web.infoseek.co.jp/sennsei3.htm
祥瑞って謎めいた面白いものなのですね。
しりとりは「い」のままです。
関戸家旧蔵の蜜柑の水指、その話は他の方からも伺いました。
名品中の名品だそうですね。
地元ですから関戸さまのご当主にも以前はよくお茶会でお目にかかりました。
自分ちの旧蔵品によそのお茶会で再会するって、どんな気分なんでしょう。
庶民には想像がつきません。
ミロクさん
ジーポせんせご多用中のご様子にて、及ばずながらあたくしめが画像をいくつかアップします。
左は写ですがまっちゃんのお話にあった「蓋裏のぶらんこ唐子」
右は湯木美術館所蔵品です。こちらの蓋裏はもちろん「ぶらんこ唐子」なのでしょうね。
いろいろ検索してましたら、祥瑞について面白いエッセイを見つけましたのでご一読ください。
http://china168.web.infoseek.co.jp/sennsei3.htm
祥瑞って謎めいた面白いものなのですね。
しりとりは「い」のままです。
ak@netさん
あの水指は今出来かと重いぐらい綺麗でしたよ
思わす「お作は?」って聞きたいぐらいww
祥瑞五郎太夫についてですが
このような文献がありましたのご紹介します
これは「定本九谷」と言う本の中で紹介されていた一説です
【祥瑞五郎太夫】
伊勢松坂在大口村の庄屋、代々伊藤を姓とし五郎太夫を名とする、永正年間遺明使京都東福寺の桂悟和尚に伴い入明し、同十年に帰朝せし伊藤五郎太夫は、祥瑞五郎太夫の素祖父にして陶磁に関係ない別人を、同一人に混同する説普く流布し、正史もこれに紛れるものも多い。
世に祥瑞と称する伊藤五郎太夫は、天正五年の生まれにして、文禄三年豊臣侍従少将利長(後に前田に復姓す加賀藩二代)の内命に因って、支那の製磁法研究の為渡明し、寧波の陶工に扮し、景徳鎮御器廠の陶工たること二十三箇年、書く其奥義を極め良品を作り、「呉祥瑞五郎太甫造」と銘する、これが祥瑞の称の起れる所以なり、品種は専ら日本への輸出抹茶器類にして、形式文様は小堀遠州の指示に因るもの多いという、藍色極めて鮮麗にして染付の最上位たり、元和二年帰朝して築後の朝妻に開窯し、また肥前有田に本邦最初の磁器を創成す、萬治三年製磁探究に苦心を重ねる後藤才次郎に出会い、其狐忠を哀れみ相携へて九谷に来る、業を授けて所謂古九谷を大成させる、寛文三年五月一六日郷里に歿す、年八十七
どこまでが真実なのかは私にはわかりませんが
参考になれば…
あの水指は今出来かと重いぐらい綺麗でしたよ
思わす「お作は?」って聞きたいぐらいww
祥瑞五郎太夫についてですが
このような文献がありましたのご紹介します
これは「定本九谷」と言う本の中で紹介されていた一説です
【祥瑞五郎太夫】
伊勢松坂在大口村の庄屋、代々伊藤を姓とし五郎太夫を名とする、永正年間遺明使京都東福寺の桂悟和尚に伴い入明し、同十年に帰朝せし伊藤五郎太夫は、祥瑞五郎太夫の素祖父にして陶磁に関係ない別人を、同一人に混同する説普く流布し、正史もこれに紛れるものも多い。
世に祥瑞と称する伊藤五郎太夫は、天正五年の生まれにして、文禄三年豊臣侍従少将利長(後に前田に復姓す加賀藩二代)の内命に因って、支那の製磁法研究の為渡明し、寧波の陶工に扮し、景徳鎮御器廠の陶工たること二十三箇年、書く其奥義を極め良品を作り、「呉祥瑞五郎太甫造」と銘する、これが祥瑞の称の起れる所以なり、品種は専ら日本への輸出抹茶器類にして、形式文様は小堀遠州の指示に因るもの多いという、藍色極めて鮮麗にして染付の最上位たり、元和二年帰朝して築後の朝妻に開窯し、また肥前有田に本邦最初の磁器を創成す、萬治三年製磁探究に苦心を重ねる後藤才次郎に出会い、其狐忠を哀れみ相携へて九谷に来る、業を授けて所謂古九谷を大成させる、寛文三年五月一六日郷里に歿す、年八十七
どこまでが真実なのかは私にはわかりませんが
参考になれば…
祥瑞・・・色んな説があってミステリアスなんですね。
しりとりが無ければ気が付かずにいたでしょう。
しりとりに感謝。
で、
続けましょう。
「い」伊羅保茶碗(いらぼちゃわん)
高麗茶碗の一種で、多くは江戸時代初期に日本からの注文で作られたと考えられています。
伊羅保の名前は、砂まじりの肌の手触りがいらいら(ざらざら)しているところに由来するとされています。
作行は、やや薄めで、形は深め、胴はあまり張らず、腰から口まで真直ぐに延び、口が大きく開いています。
素地は、鉄分が多い褐色の砂まじりの土で、轆轤目が筋立ち、石灰の多い伊羅保釉(土灰釉)を高台まで薄く総掛けしてあり、土見ずになっています。
伊羅保茶碗には、「古伊羅保(こいらぼ)」、「黄伊羅保(きいらぼ)」、「釘彫伊羅保(くぎぼりいらぼ)」、「片身替(かたみがわり)」などがあります。
「古伊羅保」は、大振りで、口縁には形成のとき土が不足して別の土を付け足した「べべら」があり、口縁の切り回しがあり、高台は竹の節、時には小石も混じって「石はぜ」が出たものもあります。見込みに白刷毛目(内刷毛)が一回りあり「伊羅保の内ばけ」といって約束になっています。
「黄伊羅保」は、黄釉の掛かったものをいい、やや端反で口縁は切り回し樋口(といくち)になっていて、べべら、見込みの砂目、竹の節高台が約束事になっています。
「釘彫伊羅保」は、高台内に釘で彫ったような巴状の彫があり、口縁は切り廻しないが山道になりべべらがあり、高台は竹の節でなく兜巾もありません。
「片身替」は、失透の井戸釉と伊羅保釉が掛け分けになったもので、高台は竹の節、兜巾は丸く大きく、たいてい「べべら」や「石はぜ」があり、見込みは刷毛目が半回りして(井刷毛)必ず刷毛先を見るのが約束になっています。
伊羅保は渋すぎてあまり好みではないのですが、勉強する良い機会だと思いまして。
画像左、伊羅保 中、黄伊羅保 右、釘彫伊羅保
しりとりのお次は「ぼ」か「ほ」「ぽ」でも可ですよね。
しりとりが無ければ気が付かずにいたでしょう。
しりとりに感謝。
で、
続けましょう。
「い」伊羅保茶碗(いらぼちゃわん)
高麗茶碗の一種で、多くは江戸時代初期に日本からの注文で作られたと考えられています。
伊羅保の名前は、砂まじりの肌の手触りがいらいら(ざらざら)しているところに由来するとされています。
作行は、やや薄めで、形は深め、胴はあまり張らず、腰から口まで真直ぐに延び、口が大きく開いています。
素地は、鉄分が多い褐色の砂まじりの土で、轆轤目が筋立ち、石灰の多い伊羅保釉(土灰釉)を高台まで薄く総掛けしてあり、土見ずになっています。
伊羅保茶碗には、「古伊羅保(こいらぼ)」、「黄伊羅保(きいらぼ)」、「釘彫伊羅保(くぎぼりいらぼ)」、「片身替(かたみがわり)」などがあります。
「古伊羅保」は、大振りで、口縁には形成のとき土が不足して別の土を付け足した「べべら」があり、口縁の切り回しがあり、高台は竹の節、時には小石も混じって「石はぜ」が出たものもあります。見込みに白刷毛目(内刷毛)が一回りあり「伊羅保の内ばけ」といって約束になっています。
「黄伊羅保」は、黄釉の掛かったものをいい、やや端反で口縁は切り回し樋口(といくち)になっていて、べべら、見込みの砂目、竹の節高台が約束事になっています。
「釘彫伊羅保」は、高台内に釘で彫ったような巴状の彫があり、口縁は切り廻しないが山道になりべべらがあり、高台は竹の節でなく兜巾もありません。
「片身替」は、失透の井戸釉と伊羅保釉が掛け分けになったもので、高台は竹の節、兜巾は丸く大きく、たいてい「べべら」や「石はぜ」があり、見込みは刷毛目が半回りして(井刷毛)必ず刷毛先を見るのが約束になっています。
伊羅保は渋すぎてあまり好みではないのですが、勉強する良い機会だと思いまして。
画像左、伊羅保 中、黄伊羅保 右、釘彫伊羅保
しりとりのお次は「ぼ」か「ほ」「ぽ」でも可ですよね。
ak@netさん同様、伊羅保はあまり好きではなく詳しくは知らなかったのですが、
いい勉強になりました。何か伊羅保について思い出せそうで、思い出せない(笑)
永楽さんの「伊羅保写し片身替」でお茶を頂きました。とても綺麗でした。
あまりしりとりが動いてないので・・・
「火屋」〜ほや
火屋香炉、火屋蓋置がありますが、先日火屋(火舎)付火入を購入したので・・・
他にも色々火屋系で何かお話や写真がありましたら、ご紹介下さいませ。
☆火屋(穂屋)香炉〜天子が四方拝の時に用いる香炉という。蓋置に用いる時は殊更に賞玩する。袋棚以上の茶事に用いる。
☆火屋蓋置〜七種蓋置の一つ。もと香炉を仮に蓋置に用いたところから、この名が生じた。台子・長板などの茶事に使う。質は胡銅、鉄。稽古用としては陶磁などでこの形を写した物を使っている。
〜茶道辞典より〜簡単ですが・・・
写真は火入。本歌があって、確か青磁で上の部分は唐銅だったと記憶しています。それを多少デザインは違いますが高取焼で写したもので、気に入って購入したものです。
火屋蓋置・香炉の写真が探せなかったのでもしあればどなたかお願い致します。
次は「や」でお願い致します。
いい勉強になりました。何か伊羅保について思い出せそうで、思い出せない(笑)
永楽さんの「伊羅保写し片身替」でお茶を頂きました。とても綺麗でした。
あまりしりとりが動いてないので・・・
「火屋」〜ほや
火屋香炉、火屋蓋置がありますが、先日火屋(火舎)付火入を購入したので・・・
他にも色々火屋系で何かお話や写真がありましたら、ご紹介下さいませ。
☆火屋(穂屋)香炉〜天子が四方拝の時に用いる香炉という。蓋置に用いる時は殊更に賞玩する。袋棚以上の茶事に用いる。
☆火屋蓋置〜七種蓋置の一つ。もと香炉を仮に蓋置に用いたところから、この名が生じた。台子・長板などの茶事に使う。質は胡銅、鉄。稽古用としては陶磁などでこの形を写した物を使っている。
〜茶道辞典より〜簡単ですが・・・
写真は火入。本歌があって、確か青磁で上の部分は唐銅だったと記憶しています。それを多少デザインは違いますが高取焼で写したもので、気に入って購入したものです。
火屋蓋置・香炉の写真が探せなかったのでもしあればどなたかお願い致します。
次は「や」でお願い致します。
しりとりご無沙汰してました^^;
季節も炉になりましたので形物香合で
「辻堂」
西の最高位にあって、東の交趾大亀と対峙するだけに、その威容と雅趣を誇示しているのである。『茶道荃蹄』には「角四方おろし屋根の上に松葉と木葉との模様あり」とあり、題は「辻堂」となっている。『茶道宝鑑』の香合図会には「宗甫書付には、ワラ屋とあり、閑事庵書付には落葉香合とあり」とあるところから、「辻堂」と決まるまでに色々な名称があったことがわかる。(「葛屋ともいった」)いずれにしても四方箱形の上に四角錐が乗り、いかにも辻堂の名にふさわしく、しかもこれに松葉と木の葉の二種の落葉紋が散らされている意匠は、わびを尊重する茶の湯の道具としてこれ程意に叶うものはないということが出来よう。また『香合真図』に「至ってすくなし」とあるごとく、今日伝えられているのも稀で、東京に一点(現在五島美術館蔵)、名古屋に一点(関戸家伝来)、関西に二点(平瀬家旧蔵、他一点)が知られている。
(形物香合より)
自分も本歌は一度しか拝見したことありませんが
どうどうとした香合でしたよ
次は「う」でお願いします
季節も炉になりましたので形物香合で
「辻堂」
西の最高位にあって、東の交趾大亀と対峙するだけに、その威容と雅趣を誇示しているのである。『茶道荃蹄』には「角四方おろし屋根の上に松葉と木葉との模様あり」とあり、題は「辻堂」となっている。『茶道宝鑑』の香合図会には「宗甫書付には、ワラ屋とあり、閑事庵書付には落葉香合とあり」とあるところから、「辻堂」と決まるまでに色々な名称があったことがわかる。(「葛屋ともいった」)いずれにしても四方箱形の上に四角錐が乗り、いかにも辻堂の名にふさわしく、しかもこれに松葉と木の葉の二種の落葉紋が散らされている意匠は、わびを尊重する茶の湯の道具としてこれ程意に叶うものはないということが出来よう。また『香合真図』に「至ってすくなし」とあるごとく、今日伝えられているのも稀で、東京に一点(現在五島美術館蔵)、名古屋に一点(関戸家伝来)、関西に二点(平瀬家旧蔵、他一点)が知られている。
(形物香合より)
自分も本歌は一度しか拝見したことありませんが
どうどうとした香合でしたよ
次は「う」でお願いします
「と」青井戸「土岐」で〜す
この茶碗は東博にて本年四月から七月に常設展示されたようですが
自分は2005年愛知万博協賛「桃山陶の華麗な世界展」の際に愛知陶磁資料館で観ました。
〈画像とともに、高麗茶碗 林屋晴三 中央公論新社より〉
外箱に記された戸田露吟の箱書きによれば土岐丹後守所持により「土岐井戸」と呼ばれる。
この茶碗のみどころは釉のやわらかさとそれに似合ったおだやかな姿であろう。腰をまるく胴にわずかに轆轤目を立てながらふっくらと丸く立ち上がっている。さほど厚手でないために見込みも外側に向かってたっぷりと丸みがあり、中央には一方に寄って茶溜りがつけられ、目跡が四つ残っている。濃い枇杷色の釉が薄くかけられ、高台部はさらに薄く暗褐色の土を見せ、胴裾一ヶ所に白く釉が流れて高台に至り梅華皮風になっている。高台脇は斜めに削れまわされ、高台は畳付きに向かってすぼまるように削りだされて、高台脇から高台内にかけてかせたように梅華皮が生じている。いつの頃に納められたか明らかではないが、秋草と扇面の蒔絵を施し、蓋裏に桔梗の家紋をつけた内箱に入っている。
東京国立博物館所蔵 広田コレクション
伝来 土岐丹後守…広田不孤斎…東京国立博物館
次は「き」でお願いします
この茶碗は東博にて本年四月から七月に常設展示されたようですが
自分は2005年愛知万博協賛「桃山陶の華麗な世界展」の際に愛知陶磁資料館で観ました。
〈画像とともに、高麗茶碗 林屋晴三 中央公論新社より〉
外箱に記された戸田露吟の箱書きによれば土岐丹後守所持により「土岐井戸」と呼ばれる。
この茶碗のみどころは釉のやわらかさとそれに似合ったおだやかな姿であろう。腰をまるく胴にわずかに轆轤目を立てながらふっくらと丸く立ち上がっている。さほど厚手でないために見込みも外側に向かってたっぷりと丸みがあり、中央には一方に寄って茶溜りがつけられ、目跡が四つ残っている。濃い枇杷色の釉が薄くかけられ、高台部はさらに薄く暗褐色の土を見せ、胴裾一ヶ所に白く釉が流れて高台に至り梅華皮風になっている。高台脇は斜めに削れまわされ、高台は畳付きに向かってすぼまるように削りだされて、高台脇から高台内にかけてかせたように梅華皮が生じている。いつの頃に納められたか明らかではないが、秋草と扇面の蒔絵を施し、蓋裏に桔梗の家紋をつけた内箱に入っている。
東京国立博物館所蔵 広田コレクション
伝来 土岐丹後守…広田不孤斎…東京国立博物館
次は「き」でお願いします
今年お初となりますね^^;
久隅守景(くすみもりかげ) 生没年不詳(十七世紀)
江戸時代初頭の狩野派が生んだ異色の画家といわれ、
伝記については確実に知る事の出来る資料が無く謎の画家の一人。
活躍時期はほぼ十七世紀前半から末期に及ぶとみられ、
狩野探幽門下の四天王の筆頭とされた俊才であったが、
のちに破門されたと伝えられる。守景は通称を半兵衛といい、
無下斎、無礙斎さらに、一陳翁、棒印と号した。
若くして狩野探幽の門下に入り、師の「守信」の一字を拝領して守景の画名が
許された。守景は晩年、加賀に赴き、六年間滞在したといい、
名品が数多く描かれた。作風は狩野派の技法だけにとどまらず、
雪舟・雪村などの室町代の水墨画も漢画的な作品も多い。
お次は「げ」か「け」でお願いします
久隅守景(くすみもりかげ) 生没年不詳(十七世紀)
江戸時代初頭の狩野派が生んだ異色の画家といわれ、
伝記については確実に知る事の出来る資料が無く謎の画家の一人。
活躍時期はほぼ十七世紀前半から末期に及ぶとみられ、
狩野探幽門下の四天王の筆頭とされた俊才であったが、
のちに破門されたと伝えられる。守景は通称を半兵衛といい、
無下斎、無礙斎さらに、一陳翁、棒印と号した。
若くして狩野探幽の門下に入り、師の「守信」の一字を拝領して守景の画名が
許された。守景は晩年、加賀に赴き、六年間滞在したといい、
名品が数多く描かれた。作風は狩野派の技法だけにとどまらず、
雪舟・雪村などの室町代の水墨画も漢画的な作品も多い。
お次は「げ」か「け」でお願いします
「ゆ」 かってファンクラブ会員だった(その後解散)こともあり今でも大好きな斉藤由貴にちなんで
高麗茶碗の御所丸 銘「由貴」で、ひとつよろしく。
吉兆主人であった湯木貞一が後述の売立により入手して以来、長らく門外不出と
なっておりましたが一度里帰りした模様です。銘「由貴」は茶友である松永耳庵が
湯木氏にちなんで贈った銘ではと想像してます。
文献解説を抜粋
「古田高麗」と似た白刷毛と称される白い御所丸のなかでも、この種の姿のものは
この茶碗と「古田高麗」の二碗を見るのみである。
かって福山の藤井家に伝来したが、昭和8年の同家の売立まではほとんど知られてなかった。
売立の際には「古田高麗」と同手のものとして大変な評判を呼んだといわれ、その様子
を高原杓庵が記した書状が添っている。
後に内箱として造られた桐木地の箱に、松永耳庵が「由貴」の追銘を書き付けている。
高麗茶碗 第三巻より
お次は「き」で
高麗茶碗の御所丸 銘「由貴」で、ひとつよろしく。
吉兆主人であった湯木貞一が後述の売立により入手して以来、長らく門外不出と
なっておりましたが一度里帰りした模様です。銘「由貴」は茶友である松永耳庵が
湯木氏にちなんで贈った銘ではと想像してます。
文献解説を抜粋
「古田高麗」と似た白刷毛と称される白い御所丸のなかでも、この種の姿のものは
この茶碗と「古田高麗」の二碗を見るのみである。
かって福山の藤井家に伝来したが、昭和8年の同家の売立まではほとんど知られてなかった。
売立の際には「古田高麗」と同手のものとして大変な評判を呼んだといわれ、その様子
を高原杓庵が記した書状が添っている。
後に内箱として造られた桐木地の箱に、松永耳庵が「由貴」の追銘を書き付けている。
高麗茶碗 第三巻より
お次は「き」で
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
表千家 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
表千家のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170672人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人