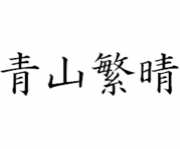■文化伝統から語る国家の自立
・利他主義と集団帰属意識に基づく文化伝統
(ぬりさんの本編トピックから一部抜粋)
近年日本の自立をうたう人々の中でよく見受けられるのが、「日本の文化や伝統と誇りを取り戻せ」的な主張である(例えば、JCの「真の自立国家シナリオ」周辺などhttp://
制度的な民主国家にどっぷりはまってしまうと、その国は群集心理に右往左往する国家ということになってしまう。必ずしも国民の群集心理が良い結果をもたらすとは限らない。特に混乱時には、群集心理こそ危険の種になる。そのためにも、混乱の前に、冷静に国民を導き、冷静な国家決断を下せる人物を見極められる国民にならなければならないのではないか。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ぬりさんが立てた「日本という国家が自立するには」トピックから、文化伝統を専門にピックアップして『自立した民主国家日本』を語り合うトピです。
アプローチとしては、美しい国・伝統・固有の文化・ナショナルアイデンティティー・パトリオティズム・ナショナリズム・反日の裏側、などでしょうか。
・利他主義と集団帰属意識に基づく文化伝統
(ぬりさんの本編トピックから一部抜粋)
近年日本の自立をうたう人々の中でよく見受けられるのが、「日本の文化や伝統と誇りを取り戻せ」的な主張である(例えば、JCの「真の自立国家シナリオ」周辺などhttp://
制度的な民主国家にどっぷりはまってしまうと、その国は群集心理に右往左往する国家ということになってしまう。必ずしも国民の群集心理が良い結果をもたらすとは限らない。特に混乱時には、群集心理こそ危険の種になる。そのためにも、混乱の前に、冷静に国民を導き、冷静な国家決断を下せる人物を見極められる国民にならなければならないのではないか。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ぬりさんが立てた「日本という国家が自立するには」トピックから、文化伝統を専門にピックアップして『自立した民主国家日本』を語り合うトピです。
アプローチとしては、美しい国・伝統・固有の文化・ナショナルアイデンティティー・パトリオティズム・ナショナリズム・反日の裏側、などでしょうか。
|
|
|
|
コメント(40)
私が個人的に経験している狭い範囲の体験から書かせていただければ、自国の伝統に誇りをもっている国の人々は、他国の文化にも強い興味を示し、知性に基づいて自国の文化を体系的また経験的に語れる人に対しては、同じく尊敬の念を持って接してくることがとても多いものです。
例えばそれはフランスであったり、イギリスであったりといった国の人々なのですが、彼らはの中では、自己のアイデンティティーなり、文化的な帰属意識なりが非常に明確であることが多いため、他国の文化理解にも寛容であり深い興味を示してくれます。
互いの国の文化の異差を認識し、相互理解という興味を繋ぎ、文化を知的コミュニケーションのためのツールとして活用する。この精神世界のカタルシスの様なものが文化の一つの醍醐味かなと自分では思っています。
しかし、現実問題としてこのツールが使えない国が、極東アジアに存在しますね。
その原因はどの辺に由来するかと書けば、大方の予想が浮かび上がってきます。その辺の不幸なからくりも、このトピで少しづつ掘り下げて行ければと思っています。
例えばそれはフランスであったり、イギリスであったりといった国の人々なのですが、彼らはの中では、自己のアイデンティティーなり、文化的な帰属意識なりが非常に明確であることが多いため、他国の文化理解にも寛容であり深い興味を示してくれます。
互いの国の文化の異差を認識し、相互理解という興味を繋ぎ、文化を知的コミュニケーションのためのツールとして活用する。この精神世界のカタルシスの様なものが文化の一つの醍醐味かなと自分では思っています。
しかし、現実問題としてこのツールが使えない国が、極東アジアに存在しますね。
その原因はどの辺に由来するかと書けば、大方の予想が浮かび上がってきます。その辺の不幸なからくりも、このトピで少しづつ掘り下げて行ければと思っています。
>戦後GHQによって失われた旧仮名遣いも取り戻さなければ・・・。日本の自立を考える上で、この様な根拠の無い民族主義・復古主義を唱えることは結構危険だ。文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうとする試みは、必ず歪んだ感情を生み出す。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
敗戦によって他国(戦勝国)によって壊されたもの(例えば旧仮名遣い?)を取り戻したい…という想いが何故に「歪んだ感情」に繋がるのかが理解できません(旧仮名遣いは、ある時代表現をしようとする場合、欠かせないものでは…)。
また、「文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうと」する事を否定して、どこにどうやってわが国の『自立の根拠』を求めるのかも理解できません。
まるで「鯨を食うのは野蛮だ」と牛を食う奴に言われているような気分になります。
ハワイも米国統治直後は言葉もフラも総て禁止されました。
ハワイアン達はそれらを根気強く復活させ、今日のハワイ文化と云われるものを確立させています。
ナショナリズムは家族・友人・故郷・国土・歴史・文化に愛着を感じるものとして…なぜ、それがいけない事なのですか。
一部の政治的な思惑を持つ団体・結社の下品な振る舞いによって、こうした否定的なコンセンサスが形成されているとしたら、彼の団体の成果を認めざるを得ません。
ちなみに私は評判の芳しくない「団塊世代」です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
敗戦によって他国(戦勝国)によって壊されたもの(例えば旧仮名遣い?)を取り戻したい…という想いが何故に「歪んだ感情」に繋がるのかが理解できません(旧仮名遣いは、ある時代表現をしようとする場合、欠かせないものでは…)。
また、「文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうと」する事を否定して、どこにどうやってわが国の『自立の根拠』を求めるのかも理解できません。
まるで「鯨を食うのは野蛮だ」と牛を食う奴に言われているような気分になります。
ハワイも米国統治直後は言葉もフラも総て禁止されました。
ハワイアン達はそれらを根気強く復活させ、今日のハワイ文化と云われるものを確立させています。
ナショナリズムは家族・友人・故郷・国土・歴史・文化に愛着を感じるものとして…なぜ、それがいけない事なのですか。
一部の政治的な思惑を持つ団体・結社の下品な振る舞いによって、こうした否定的なコンセンサスが形成されているとしたら、彼の団体の成果を認めざるを得ません。
ちなみに私は評判の芳しくない「団塊世代」です。
ルンルリーさん、誤解はしておりません。
むしろ貴方のご意見は心地良く拝見しています。
最近では、昭和天皇(陛下)のご行為に対する評価についても、双方にとても心打たれるものを感じ、日本人って良いな、と考えさせていただきました。
こちらこそ、少し拗ねて見せるなど、大人気ない書き方をしてしまい申し訳ありませんでした。
ただ「団塊世代」は政治的にからきしだらしないのも事実であり、私の周囲もノンポリのビジネスオヤジばかりです。
そんな自戒も多少含まれていたとご了解いただければ幸いです。
この国の民主的な方向については、決して後戻りする事は無いと信じています。むしろ行き過ぎた人権主義へのゆり戻しが多少起こっているのではないでしょうか。
いずれにしても、感じておられる「違和感」の部分については了解いたしました。
むしろ貴方のご意見は心地良く拝見しています。
最近では、昭和天皇(陛下)のご行為に対する評価についても、双方にとても心打たれるものを感じ、日本人って良いな、と考えさせていただきました。
こちらこそ、少し拗ねて見せるなど、大人気ない書き方をしてしまい申し訳ありませんでした。
ただ「団塊世代」は政治的にからきしだらしないのも事実であり、私の周囲もノンポリのビジネスオヤジばかりです。
そんな自戒も多少含まれていたとご了解いただければ幸いです。
この国の民主的な方向については、決して後戻りする事は無いと信じています。むしろ行き過ぎた人権主義へのゆり戻しが多少起こっているのではないでしょうか。
いずれにしても、感じておられる「違和感」の部分については了解いたしました。
物事を成す時、どのジャンルでもおそらく繰り返し言われるだろう事の一つに、『基本に帰れ、基本を大事に。』という言葉がある。伝統。古きもの。これらの概念は、時に忌むべき進歩の無い悪いもので、克服すべきものとして認識されることがある。例えば、愛国心の概念をを教育基本法に盛り込もうとした内閣府は、床の間の復活を口にして批判を浴びていた。
しかしだ。古臭い事柄に少し光をあてて自分達を省みることは、時に自分というもの存在のありかを教えてくれる。果たして私たち日本人の文化は、どの文化圏に属しているのだろうか。
アングロサクソンを中心とした西洋にはキリスト教文化圏が、中東にはイスラム文明があり、インドを中心にした東南アジアにはヒンズー文明が、そしてアジア圏には中華文明がある。では、私たちが属する世界は『中華圏』だろうか。
否だ。わたし達の根本精神は、決して中華思想などではない。むしろ私たちは、一国で一つの文化を表現出来うる要としての存在を、おそらく国としての形を整えた段階から継続して保持している。その特殊性ゆえに、一国で一文化圏を築くという特殊な精神性をもっているといえないだろうか。私たちの国家とは、すなわちそのような文化であると私は認識している。
それらをふまえ、国家の自立を伝統文化から語るとき、最も大切なことは『日本的な精神』であり『日本人の心根』というような言葉でくくられるものではないだろうか。清廉潔白・誠実・努力・ふたごころの無い清さ・謙遜な心、などの美徳を自分自身の中に再認識する所から、私たちは自らの壊れかけてしまったアイデンティティーを確立する必要があるように思う。それらは決して古臭くダサい物ではない。美しい国とは、そのような精神の集合体であろう。
どうして壊れかけてしまったのか、それを探ることもまた私たちが私たちであることを取り戻す鍵となるだろうと思う。国家とは文化であり、薫り高き文化は、私たちの誇りだ。そこには戦いも無く、排他性も無い。融和と協調と清潔と美を尊ぶ、共存の精神がある。
しかしだ。古臭い事柄に少し光をあてて自分達を省みることは、時に自分というもの存在のありかを教えてくれる。果たして私たち日本人の文化は、どの文化圏に属しているのだろうか。
アングロサクソンを中心とした西洋にはキリスト教文化圏が、中東にはイスラム文明があり、インドを中心にした東南アジアにはヒンズー文明が、そしてアジア圏には中華文明がある。では、私たちが属する世界は『中華圏』だろうか。
否だ。わたし達の根本精神は、決して中華思想などではない。むしろ私たちは、一国で一つの文化を表現出来うる要としての存在を、おそらく国としての形を整えた段階から継続して保持している。その特殊性ゆえに、一国で一文化圏を築くという特殊な精神性をもっているといえないだろうか。私たちの国家とは、すなわちそのような文化であると私は認識している。
それらをふまえ、国家の自立を伝統文化から語るとき、最も大切なことは『日本的な精神』であり『日本人の心根』というような言葉でくくられるものではないだろうか。清廉潔白・誠実・努力・ふたごころの無い清さ・謙遜な心、などの美徳を自分自身の中に再認識する所から、私たちは自らの壊れかけてしまったアイデンティティーを確立する必要があるように思う。それらは決して古臭くダサい物ではない。美しい国とは、そのような精神の集合体であろう。
どうして壊れかけてしまったのか、それを探ることもまた私たちが私たちであることを取り戻す鍵となるだろうと思う。国家とは文化であり、薫り高き文化は、私たちの誇りだ。そこには戦いも無く、排他性も無い。融和と協調と清潔と美を尊ぶ、共存の精神がある。
昨日、象徴としての天皇制トピにてコメントを入れた際
母校の校歌並びに建学の精神を思い出し、皆様にご紹介したいと思いました。
なぜなら、今回のトピを考えるにあたって深く関係がありそうな
歌詞であり、精神(基礎となる考え方)があるからです。
一読され、参考となれば幸いです。
----------------------------------------
國學院大學校歌
芳賀 矢一 作詞
本居 長世 作曲
1. 見はるかすもの みな清らなる
澁谷の岡に 大學たてり
いにし ふみ
古へ今の 書明らめて
もとい
國の基を 究むるところ
建学の精神
【明治】
明治維新の際、わが国の急務は、まず、世界の先進国に追いつくことであった。
そのため、欧米列強の思想、文化、体制の導入が急がれ、
その余り、欧化万能の風潮がわが国をおおう有様となった。
しかし、わが国が独立を全うし、国家の発展を将来に期するためには、
思想も文化も体制も、単に欧風の模倣でなく、
わが国の歴史・民族性に基づくものでなければならない。
國學院大學の母体である皇典講究所は、
このような反省の気運を背景として、 明治15年に創立された。
11月4日の開校式当日、有栖川宮幟仁親王は、
初代総裁として教職員・生徒に対して、次のような告諭を述べられた。
「凡学問ノ道ハ本ヲ立ツルヨリ大ナルハ莫シ、
故ニ国体ヲ講明シテ以テ立国 ノ基礎ヲ鞏クシ、徳性ヲ涵養シテ以テ
人生ノ本分ヲ尽スハ百世易フベカラザル 典則ナリ、而シテ世或ハ
此ニ暗シ、是レ本黌ノ設立ヲ要スル所以ナリ」
國學院大學建学の精神はこの告諭の「本ヲ立ツル」ことを基底としている。
元学長芳賀矢一博士作詞の校歌は、この精神を正しくうたいあげている。
この建学の精神こそ、本学の学問研究・人間教育を特色づけるものである。
===============================================
【平成】
冷戦構造の終焉以降、世界はグローバル化の波に飲み込まれつつあります。グローバル化とは、世界各地の多様な民族が育んできたさまざまな価値観を同一化することにほかなりません。現在の世界を見渡せば、汎アメリカ主義的な考え方がことさら目立つようになってきました。しかし遥か昔に誕生した柱となる文明・文化はいくつもあり、それらがひとつになるということは、到底あり得ない話なのです。
言葉を換えれば、多様な文化があるからこそ、人間は幸福になれるのだとも言えるでしょう。アメリカの文化には民主主義・自由主義・資本主義など、さまざまな美点があることは確かです。しかしながら、これらを取り入れたからといって、すべての民族が幸福になるというわけではありません。ましてや、暴力による価値の押し付けなど論外でしょう。
では、世界のグローバル化において、日本人はどのような態度で臨むべきなのでしょうか。最も大切なことは、私たち自身が日本人であることを常に意識しながら文化の有り様を考える必要がある、ということです。ここでいう文化とは、日本人の生き方のスタイルや考え方の傾向を意味しています。
真の意味でのグローバル化とは、やみくもに外国の文化を受けいれるということではありません。「日本人とは何か?」「日本文化とは何か?」という問題意識を常に持ちながら、私たち日本人は外国の文化を受けいれていく必要があるのです。
明治15(1882) 年に設立された皇典講究所を母体とする國學院大學は、もともと国史・国文・国法を攻究する学校として構想されました。それらの研究を基に日本文化を明らかにし、さらには諸外国に向かって日本文化を発信することこそが、本学の建学の精神なのです。西洋の文化を学ぼうとするとき、あるいはグローバル化を考えるとき、私たちは日本人の生き方のスタイルを見つめながら研究・教育を行う必要があると考えます。
今までの日本人は、「自分たちが何者であるか」を世界の人々に対してあまり説明してきませんでした。しかし、グローバル化がますます進みつつある現代において、このような一方通行の情報発信は通用しません。
まず、「自分たちが何者であるか、自分たちが築き上げてきた文化がどのようなものであるのか」をよく理解したうえで、私たちは私たち自身の文化を世界に向かって発信していかなければならないのです。
國學院大學学長
安蘇谷正彦氏(あそや まさひこ)の言葉より引用しました。
母校の校歌並びに建学の精神を思い出し、皆様にご紹介したいと思いました。
なぜなら、今回のトピを考えるにあたって深く関係がありそうな
歌詞であり、精神(基礎となる考え方)があるからです。
一読され、参考となれば幸いです。
----------------------------------------
國學院大學校歌
芳賀 矢一 作詞
本居 長世 作曲
1. 見はるかすもの みな清らなる
澁谷の岡に 大學たてり
いにし ふみ
古へ今の 書明らめて
もとい
國の基を 究むるところ
建学の精神
【明治】
明治維新の際、わが国の急務は、まず、世界の先進国に追いつくことであった。
そのため、欧米列強の思想、文化、体制の導入が急がれ、
その余り、欧化万能の風潮がわが国をおおう有様となった。
しかし、わが国が独立を全うし、国家の発展を将来に期するためには、
思想も文化も体制も、単に欧風の模倣でなく、
わが国の歴史・民族性に基づくものでなければならない。
國學院大學の母体である皇典講究所は、
このような反省の気運を背景として、 明治15年に創立された。
11月4日の開校式当日、有栖川宮幟仁親王は、
初代総裁として教職員・生徒に対して、次のような告諭を述べられた。
「凡学問ノ道ハ本ヲ立ツルヨリ大ナルハ莫シ、
故ニ国体ヲ講明シテ以テ立国 ノ基礎ヲ鞏クシ、徳性ヲ涵養シテ以テ
人生ノ本分ヲ尽スハ百世易フベカラザル 典則ナリ、而シテ世或ハ
此ニ暗シ、是レ本黌ノ設立ヲ要スル所以ナリ」
國學院大學建学の精神はこの告諭の「本ヲ立ツル」ことを基底としている。
元学長芳賀矢一博士作詞の校歌は、この精神を正しくうたいあげている。
この建学の精神こそ、本学の学問研究・人間教育を特色づけるものである。
===============================================
【平成】
冷戦構造の終焉以降、世界はグローバル化の波に飲み込まれつつあります。グローバル化とは、世界各地の多様な民族が育んできたさまざまな価値観を同一化することにほかなりません。現在の世界を見渡せば、汎アメリカ主義的な考え方がことさら目立つようになってきました。しかし遥か昔に誕生した柱となる文明・文化はいくつもあり、それらがひとつになるということは、到底あり得ない話なのです。
言葉を換えれば、多様な文化があるからこそ、人間は幸福になれるのだとも言えるでしょう。アメリカの文化には民主主義・自由主義・資本主義など、さまざまな美点があることは確かです。しかしながら、これらを取り入れたからといって、すべての民族が幸福になるというわけではありません。ましてや、暴力による価値の押し付けなど論外でしょう。
では、世界のグローバル化において、日本人はどのような態度で臨むべきなのでしょうか。最も大切なことは、私たち自身が日本人であることを常に意識しながら文化の有り様を考える必要がある、ということです。ここでいう文化とは、日本人の生き方のスタイルや考え方の傾向を意味しています。
真の意味でのグローバル化とは、やみくもに外国の文化を受けいれるということではありません。「日本人とは何か?」「日本文化とは何か?」という問題意識を常に持ちながら、私たち日本人は外国の文化を受けいれていく必要があるのです。
明治15(1882) 年に設立された皇典講究所を母体とする國學院大學は、もともと国史・国文・国法を攻究する学校として構想されました。それらの研究を基に日本文化を明らかにし、さらには諸外国に向かって日本文化を発信することこそが、本学の建学の精神なのです。西洋の文化を学ぼうとするとき、あるいはグローバル化を考えるとき、私たちは日本人の生き方のスタイルを見つめながら研究・教育を行う必要があると考えます。
今までの日本人は、「自分たちが何者であるか」を世界の人々に対してあまり説明してきませんでした。しかし、グローバル化がますます進みつつある現代において、このような一方通行の情報発信は通用しません。
まず、「自分たちが何者であるか、自分たちが築き上げてきた文化がどのようなものであるのか」をよく理解したうえで、私たちは私たち自身の文化を世界に向かって発信していかなければならないのです。
國學院大學学長
安蘇谷正彦氏(あそや まさひこ)の言葉より引用しました。
明治維新後、大学創世記の頃は何れの学府も崇高なる理念を掲げ「日本をより良い国にしよう!」という機運と決意と志のもと建立されて来たと拝察しています。2006年12月現在、100年以上前に書かれた文面を目にしても何ら違和感を感じられないかと存じます。今も変わらずこの理念は生きているからではないでしょうか?「國の基(もとい)を究むるところ」として機能していると信じたいです。
伝統文化を語る時、どうしても教育と切り離して語れないとも思いました。これまで累々時間を掛けて研究してきた成果を正しく伝える場としても大学はあるからです。そこには偏った
見方、未熟な考え方があってはならない。平衡がとれたスタンスが要求されるのは言うまでもありません。
ただし、受け手としての学生・または聴衆の側の成熟度がどうか...これです。この点がやはり気懸かりでもあります。基礎的な学力と知識が準備されてなければとせっかくの機会(講義)も「猫に小判」となりかねませんw
国力の衰退は学力低下と比例するという危惧を感ずるから
今、見直しが急務であるわけで、そういう意味では個々の家庭
生活の中で日常的に行われてきている「教育」の質も当然、問われているのですよね。
「国家」を構成するのは、まさしく「国民」です。その国民、個々の成熟度合い(知的にも精神的にも)が「国家が自立できる」方向へと歩める鍵を握っていそうです。
先人からの遺産である「伝統文化」の現在の継承者は私たちです。私たちは次世代へ正しくこの遺産を伝える義務があります。この自覚を持っているかどうかも併せて問いたいです。
伝統文化を語る時、どうしても教育と切り離して語れないとも思いました。これまで累々時間を掛けて研究してきた成果を正しく伝える場としても大学はあるからです。そこには偏った
見方、未熟な考え方があってはならない。平衡がとれたスタンスが要求されるのは言うまでもありません。
ただし、受け手としての学生・または聴衆の側の成熟度がどうか...これです。この点がやはり気懸かりでもあります。基礎的な学力と知識が準備されてなければとせっかくの機会(講義)も「猫に小判」となりかねませんw
国力の衰退は学力低下と比例するという危惧を感ずるから
今、見直しが急務であるわけで、そういう意味では個々の家庭
生活の中で日常的に行われてきている「教育」の質も当然、問われているのですよね。
「国家」を構成するのは、まさしく「国民」です。その国民、個々の成熟度合い(知的にも精神的にも)が「国家が自立できる」方向へと歩める鍵を握っていそうです。
先人からの遺産である「伝統文化」の現在の継承者は私たちです。私たちは次世代へ正しくこの遺産を伝える義務があります。この自覚を持っているかどうかも併せて問いたいです。
ぬりです
ちょっと前になりますが・・・。
>5:こーちゃんさん
[私の文]
『戦後GHQによって失われた旧仮名遣いも取り戻さなければ・・・。日本の自立を考える上で、この様な根拠の無い民族主義・復古主義を唱えることは結構危険だ。文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうとする試みは、必ず歪んだ感情を生み出す。』
[こーちゃんさんのコメント:5]
『敗戦によって他国(戦勝国)によって壊されたもの(例えば旧仮名遣い?)を取り戻したい…という想いが何故に「歪んだ感情」に繋がるのかが理解できません(旧仮名遣いは、ある時代表現をしようとする場合、欠かせないものでは…)。
また、「文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうと」する事を否定して、どこにどうやってわが国の『自立の根拠』を求めるのかも理解できません。
まるで「鯨を食うのは野蛮だ」と牛を食う奴に言われているような気分になります。』
ある程度推敲したつもりだったのですが、バーバル(言語的)コミュニケーションとは難しいものですね。色々と誤解が(ショボン
旧仮名遣い(本来は歴史的仮名遣と書くべきですけど)を取り戻さなければと書いたのは、復古主義に対する皮肉です。実際あまりそうした活動をしている人に出会ったことはありませんし。文化とは、その伝統性に価値があるのではない気がします。ルーブル美術館等に行くと、博物的価値と美術的価値の境目がわからなくなります。「もし伝統的な日本精神の一つとして武士道精神が美しいなら、切腹の文化を取り戻そうという動きがもっと出てきてもいいだろ」、に近い皮肉です。古く続いているから価値があるのではなくて、古く続いてきたものの中に、共感できる部分があるからこそ、価値を見出せるのではないでしょうか。
歪んだ感情につながるの原因となるのは、自分の文化の誇りのラディカルな根拠に文化の独自性・一貫性を持ち出す傾向の事です。うーん、うまく言えない。
「今はだめだめだけど、俺たちホントは昔から凄いんダゼ」→「わーい俺たちすげー」みたいな理屈とでも言いましょうか。その辺りから、自らの文化や歴史に対する過剰な正当化・賛美と、排他的な思想が生まれるような気がしています。
誇りって色んなものがあると思うんですけど、極論を言えば自分(たち)の現在とこれからの生き様にこそ、誇りをもったほうがよいと思うんです。
文化認識についてこんな事を書くと、文化軽視と言われそうですが、言いたいことは伝統的価値と、文化そのものの価値って、通常一緒くたにしてるよなという私の個人的思いです。長く伝統的に鯨を食べていたことは、単なる歴史的事実であって、期間の長さは食鯨文化を主張する大した根拠にはならんような気がします。私は食鯨には賛成ですが、どんな文化も時代が変われば消えてしまう運命のものがあります。例え10年前から食べていても、主張の文言が変わるだけで、他国からの文化干渉との衝突という点では似たようなものかと。
そのあたりが、元々の「偏狭」なナショナリティと「健全」なナショナリティの違いに対する私の主張でした。るるーさんや、エルゼさんとも、少し認識は違うのかもしれませんし、自分でも本当にそこがネックなのか、正直あまり自信がありません。
ただ、変な方向にいく危険があるなという懸念を持っていることだけは確かです。
本当は教育や歴史的仮名遣とかについても語りたいのですが、それはまた次の機会にして、今回は過去の自分へのフォロー止まりみたいですね。やっぱり自分が一番可愛いようです。
ちょっと前になりますが・・・。
>5:こーちゃんさん
[私の文]
『戦後GHQによって失われた旧仮名遣いも取り戻さなければ・・・。日本の自立を考える上で、この様な根拠の無い民族主義・復古主義を唱えることは結構危険だ。文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうとする試みは、必ず歪んだ感情を生み出す。』
[こーちゃんさんのコメント:5]
『敗戦によって他国(戦勝国)によって壊されたもの(例えば旧仮名遣い?)を取り戻したい…という想いが何故に「歪んだ感情」に繋がるのかが理解できません(旧仮名遣いは、ある時代表現をしようとする場合、欠かせないものでは…)。
また、「文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうと」する事を否定して、どこにどうやってわが国の『自立の根拠』を求めるのかも理解できません。
まるで「鯨を食うのは野蛮だ」と牛を食う奴に言われているような気分になります。』
ある程度推敲したつもりだったのですが、バーバル(言語的)コミュニケーションとは難しいものですね。色々と誤解が(ショボン
旧仮名遣い(本来は歴史的仮名遣と書くべきですけど)を取り戻さなければと書いたのは、復古主義に対する皮肉です。実際あまりそうした活動をしている人に出会ったことはありませんし。文化とは、その伝統性に価値があるのではない気がします。ルーブル美術館等に行くと、博物的価値と美術的価値の境目がわからなくなります。「もし伝統的な日本精神の一つとして武士道精神が美しいなら、切腹の文化を取り戻そうという動きがもっと出てきてもいいだろ」、に近い皮肉です。古く続いているから価値があるのではなくて、古く続いてきたものの中に、共感できる部分があるからこそ、価値を見出せるのではないでしょうか。
歪んだ感情につながるの原因となるのは、自分の文化の誇りのラディカルな根拠に文化の独自性・一貫性を持ち出す傾向の事です。うーん、うまく言えない。
「今はだめだめだけど、俺たちホントは昔から凄いんダゼ」→「わーい俺たちすげー」みたいな理屈とでも言いましょうか。その辺りから、自らの文化や歴史に対する過剰な正当化・賛美と、排他的な思想が生まれるような気がしています。
誇りって色んなものがあると思うんですけど、極論を言えば自分(たち)の現在とこれからの生き様にこそ、誇りをもったほうがよいと思うんです。
文化認識についてこんな事を書くと、文化軽視と言われそうですが、言いたいことは伝統的価値と、文化そのものの価値って、通常一緒くたにしてるよなという私の個人的思いです。長く伝統的に鯨を食べていたことは、単なる歴史的事実であって、期間の長さは食鯨文化を主張する大した根拠にはならんような気がします。私は食鯨には賛成ですが、どんな文化も時代が変われば消えてしまう運命のものがあります。例え10年前から食べていても、主張の文言が変わるだけで、他国からの文化干渉との衝突という点では似たようなものかと。
そのあたりが、元々の「偏狭」なナショナリティと「健全」なナショナリティの違いに対する私の主張でした。るるーさんや、エルゼさんとも、少し認識は違うのかもしれませんし、自分でも本当にそこがネックなのか、正直あまり自信がありません。
ただ、変な方向にいく危険があるなという懸念を持っていることだけは確かです。
本当は教育や歴史的仮名遣とかについても語りたいのですが、それはまた次の機会にして、今回は過去の自分へのフォロー止まりみたいですね。やっぱり自分が一番可愛いようです。
>ぬりさん
お久しぶりです。
>ある程度推敲したつもりだったのですが、バーバル(言語的)コミュニケーションとは難しいものですね。色々と誤解が(ショボン
今日は忘年会があまして、今帰ってきました…。
酒が入った勢いで、正直に書きます。
僕のような単純な人間から見ると、ぬりさんのように真面目で頭の良い人は、どうしても戦後史観から抜け出せていないように感じます。
大変失礼な物言いをしていると思いますが、そもそものスタートが間違っている?ように感じてしまうのです。
ソ連崩壊と共に、世界は民族主義的価値観で再編されつつあると思いますが、如何でしょうか…?
その現状で、日本人だけが何時までも(ある意味)贖罪意識やナショナリズムに対する後ろめたい気持ちで過ごす必要は無いと思うのです。
戦後61年、日本がそういう気持ちで過ごしてきた事は皆(特定アジアを除いて)分かっていると思います。
そろそろ、自己主張しましょうよ!(多分「ねじれ」も解消します)
今月のWillに渡部昇一氏の「戦後史公開講座−2」で次のような事が書かれています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
「アメリカに騎士道精神なし」
東京裁判で日本政府は、天皇が裁かれるかどうかということを非常に心配していました。
戦勝国が国際法に基づいて裁判を行っているのであれば、裁かれる心配など全くする必要はなかったのですが、そうではなかったため心配だった。
−−−−−−−−−−
戦時国際法は交戦規定を定めています。
決闘のプロセスの中での、開戦手続きや捕虜を虐待してはいけないなどについての規則です。
だから戦争をしている国家の主体には、法は及ばない。
−−−−−−−−−−
ただ、日本は真珠湾攻撃を国交断絶以前に行ったということが問題だった。
しかし、日本は天皇陛下も東條首相も参謀総長も軍令部総長も連合艦隊司令長官も、無通告攻撃する意思はなかったのです。
−−−−−−−−−−
日本が無通告攻撃をしてしまったのは、そもそも外務省のミスであるため、(いわゆるA級戦犯の)東郷茂徳外務大臣はそれを気にしたのでした。
…結局、東京裁判では(それは)問題にならなかった。
−−−−−−−−−−
しかしこれを問題にするならば、アメリカは何度も戦争をしていますが、戦闘の前に宣戦布告をした例はないことも指摘されています。
テキサス占領でもハワイ占領でもグアム島やフィリッピンを手に入れた米西戦争でもそうです。
==========
あまり長々と引用は止めますが、戦争は国際法上も認められたものであり、日本の戦争指導者はそれに準じて戦争を行い、負けてしまった…という事です。
無論、戦争ですから双方に被害者が出る事は当たり前であり、被害が大きくならない内に停戦する知恵も必要であったでしょうし、その前に、戦争せずに済む方策も必要でしたでしょう。
ただ、いずれも当事者ではない後知恵の意見でしかありません。
今度は負けない戦争、その前に戦争しないで済む方策を考えなきゃいけませんね。上手く纏まりません、おやすみなさい…。
お久しぶりです。
>ある程度推敲したつもりだったのですが、バーバル(言語的)コミュニケーションとは難しいものですね。色々と誤解が(ショボン
今日は忘年会があまして、今帰ってきました…。
酒が入った勢いで、正直に書きます。
僕のような単純な人間から見ると、ぬりさんのように真面目で頭の良い人は、どうしても戦後史観から抜け出せていないように感じます。
大変失礼な物言いをしていると思いますが、そもそものスタートが間違っている?ように感じてしまうのです。
ソ連崩壊と共に、世界は民族主義的価値観で再編されつつあると思いますが、如何でしょうか…?
その現状で、日本人だけが何時までも(ある意味)贖罪意識やナショナリズムに対する後ろめたい気持ちで過ごす必要は無いと思うのです。
戦後61年、日本がそういう気持ちで過ごしてきた事は皆(特定アジアを除いて)分かっていると思います。
そろそろ、自己主張しましょうよ!(多分「ねじれ」も解消します)
今月のWillに渡部昇一氏の「戦後史公開講座−2」で次のような事が書かれています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
「アメリカに騎士道精神なし」
東京裁判で日本政府は、天皇が裁かれるかどうかということを非常に心配していました。
戦勝国が国際法に基づいて裁判を行っているのであれば、裁かれる心配など全くする必要はなかったのですが、そうではなかったため心配だった。
−−−−−−−−−−
戦時国際法は交戦規定を定めています。
決闘のプロセスの中での、開戦手続きや捕虜を虐待してはいけないなどについての規則です。
だから戦争をしている国家の主体には、法は及ばない。
−−−−−−−−−−
ただ、日本は真珠湾攻撃を国交断絶以前に行ったということが問題だった。
しかし、日本は天皇陛下も東條首相も参謀総長も軍令部総長も連合艦隊司令長官も、無通告攻撃する意思はなかったのです。
−−−−−−−−−−
日本が無通告攻撃をしてしまったのは、そもそも外務省のミスであるため、(いわゆるA級戦犯の)東郷茂徳外務大臣はそれを気にしたのでした。
…結局、東京裁判では(それは)問題にならなかった。
−−−−−−−−−−
しかしこれを問題にするならば、アメリカは何度も戦争をしていますが、戦闘の前に宣戦布告をした例はないことも指摘されています。
テキサス占領でもハワイ占領でもグアム島やフィリッピンを手に入れた米西戦争でもそうです。
==========
あまり長々と引用は止めますが、戦争は国際法上も認められたものであり、日本の戦争指導者はそれに準じて戦争を行い、負けてしまった…という事です。
無論、戦争ですから双方に被害者が出る事は当たり前であり、被害が大きくならない内に停戦する知恵も必要であったでしょうし、その前に、戦争せずに済む方策も必要でしたでしょう。
ただ、いずれも当事者ではない後知恵の意見でしかありません。
今度は負けない戦争、その前に戦争しないで済む方策を考えなきゃいけませんね。上手く纏まりません、おやすみなさい…。
>ぬりさん
13のぬりさんのご意見について、14であまり関係の無い事ばかりを書いてしまったようです。
そこで、
>歪んだ感情につながるの原因となるのは、自分の文化の誇りのラディカルな根拠に文化の独自性・一貫性を持ち出す傾向の事です。うーん、うまく言えない。
「今はだめだめだけど、俺たちホントは昔から凄いんダゼ」→「わーい俺たちすげー」みたいな理屈とでも言いましょうか。その辺りから、自らの文化や歴史に対する過剰な正当化・賛美と、排他的な思想が生まれるような気がしています。
僕は反対の考えを持っています。
自らの歴史や文化に対する深い理解と誇りは、「排他的な思想」どころか、他文化に対する好奇心と理解とに繋がると思っています。
この辺りの違いは、いくら話し合っても平行線でしょう。
核武装が抑止力になるかならないかの話と同じです。
こんどこそ、おやすみなさい。
13のぬりさんのご意見について、14であまり関係の無い事ばかりを書いてしまったようです。
そこで、
>歪んだ感情につながるの原因となるのは、自分の文化の誇りのラディカルな根拠に文化の独自性・一貫性を持ち出す傾向の事です。うーん、うまく言えない。
「今はだめだめだけど、俺たちホントは昔から凄いんダゼ」→「わーい俺たちすげー」みたいな理屈とでも言いましょうか。その辺りから、自らの文化や歴史に対する過剰な正当化・賛美と、排他的な思想が生まれるような気がしています。
僕は反対の考えを持っています。
自らの歴史や文化に対する深い理解と誇りは、「排他的な思想」どころか、他文化に対する好奇心と理解とに繋がると思っています。
この辺りの違いは、いくら話し合っても平行線でしょう。
核武装が抑止力になるかならないかの話と同じです。
こんどこそ、おやすみなさい。
私も時間がないので少しだけ。
なんか平行線ではなくてただ伝わってないだけな気がします…。核武装の時とは全然違う感じ。
こーちゃんさんのおっしゃっている事は、私はとても素直に同意できます。私が日本が悪かったとうしろめたい気持ちを持ってるわけでなくて、そういう人がまだいるという事が問題なのだと思っています。そもそも私はいわゆる戦後史観は客観視してますのでそこはスタートではないです。私のスタートは…科学…でしょうか(笑)。歴史はからっきしです。
文化についても同意見です。深い理解と誇りはとても大切で、排他的なものは「そこ」からは生まれないと思っています。
危惧しているのは全く別の事です。
それを説明する方法は難しいです。「日本は素晴らしい」と「日本が素晴らしい」との壁にも近いかもしれません。
逆に、何が問題だと思いますか?
なんか平行線ではなくてただ伝わってないだけな気がします…。核武装の時とは全然違う感じ。
こーちゃんさんのおっしゃっている事は、私はとても素直に同意できます。私が日本が悪かったとうしろめたい気持ちを持ってるわけでなくて、そういう人がまだいるという事が問題なのだと思っています。そもそも私はいわゆる戦後史観は客観視してますのでそこはスタートではないです。私のスタートは…科学…でしょうか(笑)。歴史はからっきしです。
文化についても同意見です。深い理解と誇りはとても大切で、排他的なものは「そこ」からは生まれないと思っています。
危惧しているのは全く別の事です。
それを説明する方法は難しいです。「日本は素晴らしい」と「日本が素晴らしい」との壁にも近いかもしれません。
逆に、何が問題だと思いますか?
すみません、一度寝たのですが、眠れなくなって…
それで、思うのですが…例えば
ぬりさんは核武装が抑止力を持ち得ないと「思う」から、核武装をすべきでは無いと考えます。
僕は核武装が抑止力にならない「かも」しれないとしても、抑止力としての可能性がゼロでない限り、核武装しておくべきであると考えます。
ぬりさんは、自国の歴史・文化に対する過度の誇りや自信は排他的な思想に繋がると考えます。
僕は自国の歴史・文化を理解すれば、他国の歴史・文化をも理解するこころに繋がると考えます。
これは、ぬりさんが正しいのか僕が正しいのか、という問題では無く………個々の世界感の違いかもしれません。
ぬりさんも僕もお互いの考えは理解できますし、自分の中にも若干あるものだと思います。
ただ…何というか…大変僭越な物言いになってしまいますが…自己及び周囲に対する自信?の持ちよう…というような事ではなかろうか・と思います。
正直に申し上げて、僕は決して立派な人間ではありません。
ただ、僕自身がつまらない人間でも、日本の歴史・文化には誇りを持っていますし、(歴史的)結果の如何に関らず、先人への敬意は自然に沸いてきます…(何故かな?)
普段、この国の多くの人たちは戦争指導者を責めようとは思わず、敵国だった米国への恨みつらみを持とうとしません。
多分それが日本人の自信と誇りなのではないでしょうか。
それで、思うのですが…例えば
ぬりさんは核武装が抑止力を持ち得ないと「思う」から、核武装をすべきでは無いと考えます。
僕は核武装が抑止力にならない「かも」しれないとしても、抑止力としての可能性がゼロでない限り、核武装しておくべきであると考えます。
ぬりさんは、自国の歴史・文化に対する過度の誇りや自信は排他的な思想に繋がると考えます。
僕は自国の歴史・文化を理解すれば、他国の歴史・文化をも理解するこころに繋がると考えます。
これは、ぬりさんが正しいのか僕が正しいのか、という問題では無く………個々の世界感の違いかもしれません。
ぬりさんも僕もお互いの考えは理解できますし、自分の中にも若干あるものだと思います。
ただ…何というか…大変僭越な物言いになってしまいますが…自己及び周囲に対する自信?の持ちよう…というような事ではなかろうか・と思います。
正直に申し上げて、僕は決して立派な人間ではありません。
ただ、僕自身がつまらない人間でも、日本の歴史・文化には誇りを持っていますし、(歴史的)結果の如何に関らず、先人への敬意は自然に沸いてきます…(何故かな?)
普段、この国の多くの人たちは戦争指導者を責めようとは思わず、敵国だった米国への恨みつらみを持とうとしません。
多分それが日本人の自信と誇りなのではないでしょうか。
るるーさん
私が言いたかったことを、かなり代弁して頂いた気がします。
ただ、いくつかの国の文化や人にこれまで触れてきて、また触れてきた人と会って、異文化の相互理解とはとても難しいなとも感じています。相互尊重、異文化コミュニケーションが成立するのは、部分的なケースに限られてしまうのだろうなというのが、私のこれまでの少ない経験上の思いでもあります。
ある程度、お互い無干渉を貫く為の方法を考えた方が賢いのかなと。
人間の可能性は信じますが。
こーちゃんさんへ
トピ違いですが、
>ぬりさんは核武装が抑止力を持ち得ないと「思う」から、核武装をすべきでは無いと考えます。
>僕は核武装が抑止力にならない「かも」しれないとしても、抑止力としての可能性がゼロでない限り、核武装しておくべきであると考えます。
それも勘違いだと思います。私は単純に核に反対したいわけではなくて、核武装が抑止力を持つ為には様々な条件が必要で、今後の日本の仮想的との間にそのような条件がそろう可能性は低いと「思い」、また、核武装を仮にしたとして、しない場合よりも危機の可能性が高まり、色んな意味でも日本人のためにならないと考えているから、反対なのです。抑止力としての可能性はゼロではありません。というか、どのような戦略にも絶対はありませんよね。結局は、そのときに何を考え、何を大切にし、何を選ぶかだけだと思います。
>個々の世界感の違いかもしれません。
もちろんそうだと思っていますよ(^^)。違いがあるからこそ、青山さんは語り合う事を大切に考えているんでしょうね。私は、自分の世界観の中だけに関しては自分の考えは絶対に正しいと考えていますが、かといって自分の世界観を他人に押し付けたいとは思いませんから。でも、それって普通のことだと思います。
>自己及び周囲に対する自信?の持ちよう…というような事ではなかろうか・と思います。
うーむ。わかるようなわからないような。私が自信を持っているから、世界観が異なるって事なんでしょうか・・・。自信って単純じゃないですよね・・・。
誇りって一体何なんだろう。
今の日本人が誰も責めないのは、自立してないから?
責めれば自立しているわけでは決してありませんが。
21でおっしゃりたかったことは、なんだったんだろう。
でも、とてもすなおな想いなのかなと感じました。
私が言いたかったことを、かなり代弁して頂いた気がします。
ただ、いくつかの国の文化や人にこれまで触れてきて、また触れてきた人と会って、異文化の相互理解とはとても難しいなとも感じています。相互尊重、異文化コミュニケーションが成立するのは、部分的なケースに限られてしまうのだろうなというのが、私のこれまでの少ない経験上の思いでもあります。
ある程度、お互い無干渉を貫く為の方法を考えた方が賢いのかなと。
人間の可能性は信じますが。
こーちゃんさんへ
トピ違いですが、
>ぬりさんは核武装が抑止力を持ち得ないと「思う」から、核武装をすべきでは無いと考えます。
>僕は核武装が抑止力にならない「かも」しれないとしても、抑止力としての可能性がゼロでない限り、核武装しておくべきであると考えます。
それも勘違いだと思います。私は単純に核に反対したいわけではなくて、核武装が抑止力を持つ為には様々な条件が必要で、今後の日本の仮想的との間にそのような条件がそろう可能性は低いと「思い」、また、核武装を仮にしたとして、しない場合よりも危機の可能性が高まり、色んな意味でも日本人のためにならないと考えているから、反対なのです。抑止力としての可能性はゼロではありません。というか、どのような戦略にも絶対はありませんよね。結局は、そのときに何を考え、何を大切にし、何を選ぶかだけだと思います。
>個々の世界感の違いかもしれません。
もちろんそうだと思っていますよ(^^)。違いがあるからこそ、青山さんは語り合う事を大切に考えているんでしょうね。私は、自分の世界観の中だけに関しては自分の考えは絶対に正しいと考えていますが、かといって自分の世界観を他人に押し付けたいとは思いませんから。でも、それって普通のことだと思います。
>自己及び周囲に対する自信?の持ちよう…というような事ではなかろうか・と思います。
うーむ。わかるようなわからないような。私が自信を持っているから、世界観が異なるって事なんでしょうか・・・。自信って単純じゃないですよね・・・。
誇りって一体何なんだろう。
今の日本人が誰も責めないのは、自立してないから?
責めれば自立しているわけでは決してありませんが。
21でおっしゃりたかったことは、なんだったんだろう。
でも、とてもすなおな想いなのかなと感じました。
>この様な根拠の無い民族主義・復古主義を唱えることは結構危険だ。文化の独自性や一貫性に、自身の誇りを見出そうとする試みは、必ず歪んだ感情を生み出す。
親トピの問題提起を解きほぐす意味で、私達が属している文化は、いったい世界標準で見た場合、どのような認識をされているかを主に『文明の衝突』から少しづつご紹介しようかなと思います。
【孤立する立場の、しかも単独で中核国を形成する日本という特殊な我が国】
シドニー・ミンツによれば「どんな国も独特だ」という事になるようですが、文明の見地から区分すれば、基本的に冷戦後の国家は下の様な分類に大別されます。
?中核国・・・その文明の発生地であり、文化の中心である国
?構成国・・・文化の面でその文明と完全に同一視できる立場の国
?孤立国・・・他の社会と文化を共有しない国
?分裂国・・・二つ以上の民族や人種や宗教を持つ国
?の例として、欧米の中核国は「アメリカ」「ドイツ・フランス」であり、その間で揺れている「イギリス」がさらにもう一つの力の中心を構成しているという具合。
?の構成国の例として、ヨーロッパ・欧米文明に一致する「イタリア」がそれにあたります。
?エチオピア・ハイチ・日本などがこれに該当します。
文明の衝突では、最も重要な孤立国は日本であると定義しています。
?分裂国の例は枚挙に暇がありません。例えばそれは冷戦時代、無理に国としてまとめられ、マルクス・レーニン主義のイデオロギーによって正当化された、独裁的な共産主義体制の国々です。
これらの分類から日本の特殊性を客観的にみると以下の様な像が浮かび上がってきます。
日本の独特な文化を共有する国は何処にもなく、移住した先の日系人はその国を動かすほどの多人数を構成しておらず、かといって移住先の文化に混じることもありません。
日本の孤立度がさらに高まるのは、日本文化は高度に排他的であり、他国に広く支持される可能性のある宗教やイデオロギーを伴わないという事実によります。結果的にそれら宗教やイデオロギーをツールとして他国を構成国として獲得しえないという事になります。
よって、日本は事実上、日本一国で中核国となりうる孤立国です。
これらを踏まえて私は、この日本という唯一特殊な文明は、他国に例えば『靖国』『死者の魂のありか』『天皇』『神道』などの理解を求める場合の難しさを思うのです。
どの文明にも属さないというこの客観的事実は、言うなれば暗黙の共通理解のもと支持・共感してくれる真の同盟国を持たないということです。私たちの国が抱える靖国問題などの苦悩は、この単独で文明を構築している事に端を発しているものと思います。
歪んだ感情を呼び込まないためにも、私たちは私たちの独自性を客観的に知っておく必要があると私は思っています。
親トピの問題提起を解きほぐす意味で、私達が属している文化は、いったい世界標準で見た場合、どのような認識をされているかを主に『文明の衝突』から少しづつご紹介しようかなと思います。
【孤立する立場の、しかも単独で中核国を形成する日本という特殊な我が国】
シドニー・ミンツによれば「どんな国も独特だ」という事になるようですが、文明の見地から区分すれば、基本的に冷戦後の国家は下の様な分類に大別されます。
?中核国・・・その文明の発生地であり、文化の中心である国
?構成国・・・文化の面でその文明と完全に同一視できる立場の国
?孤立国・・・他の社会と文化を共有しない国
?分裂国・・・二つ以上の民族や人種や宗教を持つ国
?の例として、欧米の中核国は「アメリカ」「ドイツ・フランス」であり、その間で揺れている「イギリス」がさらにもう一つの力の中心を構成しているという具合。
?の構成国の例として、ヨーロッパ・欧米文明に一致する「イタリア」がそれにあたります。
?エチオピア・ハイチ・日本などがこれに該当します。
文明の衝突では、最も重要な孤立国は日本であると定義しています。
?分裂国の例は枚挙に暇がありません。例えばそれは冷戦時代、無理に国としてまとめられ、マルクス・レーニン主義のイデオロギーによって正当化された、独裁的な共産主義体制の国々です。
これらの分類から日本の特殊性を客観的にみると以下の様な像が浮かび上がってきます。
日本の独特な文化を共有する国は何処にもなく、移住した先の日系人はその国を動かすほどの多人数を構成しておらず、かといって移住先の文化に混じることもありません。
日本の孤立度がさらに高まるのは、日本文化は高度に排他的であり、他国に広く支持される可能性のある宗教やイデオロギーを伴わないという事実によります。結果的にそれら宗教やイデオロギーをツールとして他国を構成国として獲得しえないという事になります。
よって、日本は事実上、日本一国で中核国となりうる孤立国です。
これらを踏まえて私は、この日本という唯一特殊な文明は、他国に例えば『靖国』『死者の魂のありか』『天皇』『神道』などの理解を求める場合の難しさを思うのです。
どの文明にも属さないというこの客観的事実は、言うなれば暗黙の共通理解のもと支持・共感してくれる真の同盟国を持たないということです。私たちの国が抱える靖国問題などの苦悩は、この単独で文明を構築している事に端を発しているものと思います。
歪んだ感情を呼び込まないためにも、私たちは私たちの独自性を客観的に知っておく必要があると私は思っています。
学者たちは、文明の種類と数について、おおむね一致した見解を持っているようです。無理なく意見が一致するところでは、歴史的には少なくとも12の文明が存在し、現存する文明は5つという事です。
消滅した文明は、メソポタミア、エジプト、クレタ、古代ギリシア・ローマ、ビザンティン、中央アメリカ、アンデスの七つ。現存する文明は、中国、日本、インド、イスラム、西欧、この五つ。
【中華文明】・・・遡ること少なくとも紀元前1500年に、そしておそらくはさらにその1000年前から一つの明確な文明が存在していたか、あるいは二つの文明があってそのどちらかがどちらかを継承したと見られています。儒教を基本理念にもつ文明です。
【日本文明】・・・一部の学者は、極東文明という名で日本と中国をひとつの文明だと定義している向きもありますが、ほとんどの学者は日本を固有の文明と位置付けています。中国文明から派生して、西暦100年ないし400年の時期にあらわれたと見る見方が一般的です。
【ヒンドゥー文明】・・・インド亜大陸には、少なくとも紀元前1500年ごろから、ひとつまたはそれ以上の文明が存在していたと認識されています。紀元前2000年以降、ヒンドゥー教は亜大陸の文化の中心でした。
【イスラム文明】・・・西暦7世紀にアラビア半島に端を発して、イスラム教は急速に北アフリカやイベリア半島に、更には中央大陸、インド亜大陸東南アジアへと広がっていきました。
【西欧文明】・・・西暦700年ないし800年に表れたとされています。そこには主に、ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカの、三つの主要な構成要素があります。
私たちの文化を私達が正確に知ることは、近年失ってしまった私たちのアイデンティテーを取り戻すためにも、とても有効だと私は思います。上記紹介の文明の分類は、日本人だけが信仰している類の学説ではなく、定説として定着している世界観です。
自らの文化のみを特別で優位なものであると認識する危険は、ナショナリズムを間違った方向に誘導するものです。私たちはむしろ、ナショナリズムというよりパトリオティズム(愛国主義)に立ち返る必要があると私は感じています。
消滅した文明は、メソポタミア、エジプト、クレタ、古代ギリシア・ローマ、ビザンティン、中央アメリカ、アンデスの七つ。現存する文明は、中国、日本、インド、イスラム、西欧、この五つ。
【中華文明】・・・遡ること少なくとも紀元前1500年に、そしておそらくはさらにその1000年前から一つの明確な文明が存在していたか、あるいは二つの文明があってそのどちらかがどちらかを継承したと見られています。儒教を基本理念にもつ文明です。
【日本文明】・・・一部の学者は、極東文明という名で日本と中国をひとつの文明だと定義している向きもありますが、ほとんどの学者は日本を固有の文明と位置付けています。中国文明から派生して、西暦100年ないし400年の時期にあらわれたと見る見方が一般的です。
【ヒンドゥー文明】・・・インド亜大陸には、少なくとも紀元前1500年ごろから、ひとつまたはそれ以上の文明が存在していたと認識されています。紀元前2000年以降、ヒンドゥー教は亜大陸の文化の中心でした。
【イスラム文明】・・・西暦7世紀にアラビア半島に端を発して、イスラム教は急速に北アフリカやイベリア半島に、更には中央大陸、インド亜大陸東南アジアへと広がっていきました。
【西欧文明】・・・西暦700年ないし800年に表れたとされています。そこには主に、ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカの、三つの主要な構成要素があります。
私たちの文化を私達が正確に知ることは、近年失ってしまった私たちのアイデンティテーを取り戻すためにも、とても有効だと私は思います。上記紹介の文明の分類は、日本人だけが信仰している類の学説ではなく、定説として定着している世界観です。
自らの文化のみを特別で優位なものであると認識する危険は、ナショナリズムを間違った方向に誘導するものです。私たちはむしろ、ナショナリズムというよりパトリオティズム(愛国主義)に立ち返る必要があると私は感じています。
るるーさん
まずは、危ないか均整が取れているかという有益性の前に、歴史研究のレベルで日本の国家アイデンティティは反中国をきっかけに立ち上がったというのは事実であろうと思います。もちろん、日本のナショナルアイデンティティの端緒が反中国であったからといって現在においてアンチ中国である必要はありません。
アイデンティティというのは自己の中でのみ完結せず、他者との相関の中で生まれ出るものです。
最近の言葉で「反xx」というと国家間での幼稚な反駁や仮想敵国を作る卑劣な国家戦略を連想させますが、あの文章で言う「反」とは、巨大なものに飲み込まれずに自立を志向する志としての「反」であると解釈してます。
ちなみに現在の日本で自立に相応しいナショナルアイデンティティを強固にする上で、どういう「反」が必要だと思われますか?それは「反」米ではないでしょうか?
まずは、危ないか均整が取れているかという有益性の前に、歴史研究のレベルで日本の国家アイデンティティは反中国をきっかけに立ち上がったというのは事実であろうと思います。もちろん、日本のナショナルアイデンティティの端緒が反中国であったからといって現在においてアンチ中国である必要はありません。
アイデンティティというのは自己の中でのみ完結せず、他者との相関の中で生まれ出るものです。
最近の言葉で「反xx」というと国家間での幼稚な反駁や仮想敵国を作る卑劣な国家戦略を連想させますが、あの文章で言う「反」とは、巨大なものに飲み込まれずに自立を志向する志としての「反」であると解釈してます。
ちなみに現在の日本で自立に相応しいナショナルアイデンティティを強固にする上で、どういう「反」が必要だと思われますか?それは「反」米ではないでしょうか?
私は生き残るキーポイントは『反』ではなく、『中立』だと思っています。
戦いに巻き込まれることなく中立を保った国だけが、(例えば戦火で)荒廃した文明にかわって、イニシアチブをとるだろうという予想です。
文明間の争いに巻き込まれないインテリジェンスが、日本生き残りの鍵であろうという感じでしょうか。
>歴史研究のレベルで日本の国家アイデンティティは反中国をきっかけに立ち上がったというのは事実であろうと
というご指摘のリサーチを出来ないうちに書き込むのはあまりに乱暴ですが、どの国の誰の研究が反日をベースにしているのか、わたしの検証している書籍にはそのような見解はあまり無くそれは一つには、日本人の文献から参照していないからだと思います。バイアスのかかりやすい同胞の情報より、我々の感情から遠いところの書籍をとりあえず参照したいと、基本的には思っています。
戦いに巻き込まれることなく中立を保った国だけが、(例えば戦火で)荒廃した文明にかわって、イニシアチブをとるだろうという予想です。
文明間の争いに巻き込まれないインテリジェンスが、日本生き残りの鍵であろうという感じでしょうか。
>歴史研究のレベルで日本の国家アイデンティティは反中国をきっかけに立ち上がったというのは事実であろうと
というご指摘のリサーチを出来ないうちに書き込むのはあまりに乱暴ですが、どの国の誰の研究が反日をベースにしているのか、わたしの検証している書籍にはそのような見解はあまり無くそれは一つには、日本人の文献から参照していないからだと思います。バイアスのかかりやすい同胞の情報より、我々の感情から遠いところの書籍をとりあえず参照したいと、基本的には思っています。
歴史を良く知れば知るほど、腹の立つ事が多い。
今の日本の状況を知れば知るほど、情けないやら、腹立たしいやら。
その様なネガティブな「感情」が自立のベースになるのでしょうか。
北方領土を返せ!、竹島は日本の領土だ!、反日教育をやめろ!、アメリカにだまされるな!、そっちが脅すならこっちも核もつぞ!・・・。日本の自立を強く主張する声の中には、こんな声も聞こえてきます。で、多分全部正しい。でも、これをただ強く主張し、こちらの言う通りにさせる事が、自立なのでしょうか。もし毎日そんなことを叫んでいたら、結局誰にも相手にされなくなるだけですよね。なんか違う。あ、主張が間違っているいう意味ではありません。私も腹立っています。
多分こういったのは、人間が本能的に持つ、異質な物に対する嫌悪感です。世界が日本しかなかったら発生しない感情。
反発できる事と、自立していることを混同することもよくしますが、私は別のものだと思っています。実際よくある。で、後で気が付いて少し恥ずかしくなったりする。
眠いので、よくわからなくなってきましたが、私が言いたいのはそんなような事です。ではまた。おやすみなさい。
今の日本の状況を知れば知るほど、情けないやら、腹立たしいやら。
その様なネガティブな「感情」が自立のベースになるのでしょうか。
北方領土を返せ!、竹島は日本の領土だ!、反日教育をやめろ!、アメリカにだまされるな!、そっちが脅すならこっちも核もつぞ!・・・。日本の自立を強く主張する声の中には、こんな声も聞こえてきます。で、多分全部正しい。でも、これをただ強く主張し、こちらの言う通りにさせる事が、自立なのでしょうか。もし毎日そんなことを叫んでいたら、結局誰にも相手にされなくなるだけですよね。なんか違う。あ、主張が間違っているいう意味ではありません。私も腹立っています。
多分こういったのは、人間が本能的に持つ、異質な物に対する嫌悪感です。世界が日本しかなかったら発生しない感情。
反発できる事と、自立していることを混同することもよくしますが、私は別のものだと思っています。実際よくある。で、後で気が付いて少し恥ずかしくなったりする。
眠いので、よくわからなくなってきましたが、私が言いたいのはそんなような事です。ではまた。おやすみなさい。
>そういう自制心の利いた国が、自立した国の理想だと考えています。
日本に今、一番欠けてしまっている部分でもありまして、
これは本当に危機的状況かと感ずる次第です。
自制心、教育の究極の目的はここに集約されて行くように思えます。
成熟した、円熟した思考を備えた国民へと成長してゆかねば
「自制心」まで到達する前に、自然淘汰されてしまいそうです。
教育を一番に掲げておられる安倍首相の目は澄んでおられてていいですね。
有言実行を強く望んでいます。
先ほど、安倍内閣メールマガジン号外−教育再生特集(2007/01/27) が届きました。
皆様もご購読されておられるかもしれませんが、参考までに…ご高覧くださいませ。
-----------------------------------------------ここから↓
[安倍総理のメッセージ]
「美しい国、日本」の実現のためには、その基本は次代を担う子供や若者
の育成にあります。教育再生は、安倍内閣の最重要課題です。昨年末、60
年ぶりに教育基本法が改正され、教育再生の理念と原則が確立しました。今
回いただいた報告をもとに、すぐできることは直ちに実行するとともに、必
要な法案をこの通常国会に提出してまいります。
教育再生には、文字どおり国民一人ひとりに、社会総がかりで一緒に取り
組んでいただくことが必要不可欠です。今後とも国民的な議論を深め、叡智
を結集して教育再生に取り組んでまいります。
〜ライブ・トーク官邸第15回「ホット対談・教育再生」より〜
参照 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/kettei/070124houkoku.html
日本に今、一番欠けてしまっている部分でもありまして、
これは本当に危機的状況かと感ずる次第です。
自制心、教育の究極の目的はここに集約されて行くように思えます。
成熟した、円熟した思考を備えた国民へと成長してゆかねば
「自制心」まで到達する前に、自然淘汰されてしまいそうです。
教育を一番に掲げておられる安倍首相の目は澄んでおられてていいですね。
有言実行を強く望んでいます。
先ほど、安倍内閣メールマガジン号外−教育再生特集(2007/01/27) が届きました。
皆様もご購読されておられるかもしれませんが、参考までに…ご高覧くださいませ。
-----------------------------------------------ここから↓
[安倍総理のメッセージ]
「美しい国、日本」の実現のためには、その基本は次代を担う子供や若者
の育成にあります。教育再生は、安倍内閣の最重要課題です。昨年末、60
年ぶりに教育基本法が改正され、教育再生の理念と原則が確立しました。今
回いただいた報告をもとに、すぐできることは直ちに実行するとともに、必
要な法案をこの通常国会に提出してまいります。
教育再生には、文字どおり国民一人ひとりに、社会総がかりで一緒に取り
組んでいただくことが必要不可欠です。今後とも国民的な議論を深め、叡智
を結集して教育再生に取り組んでまいります。
〜ライブ・トーク官邸第15回「ホット対談・教育再生」より〜
参照 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/kettei/070124houkoku.html
るるーさん、例えば「中立」ということでいうと日米軍事同盟の解消ということでしょうか?軍事同盟がある限り、同盟国が相対する軍事的衝突に大なり小なりコミットせざるを得ないでしょう。米中が台湾海峡で衝突する事態になったとき、日本は中立を保てるでしょうか?また、そこまで日本人が思い切れるものでしょうか?
それがるるーさんの言う「中立」であれば、非常にアグレッシブでかつラディカルであり、反とか中立とか単語の語感や言葉のあやを越えて私の感覚と一致します。
ぬりさん
>その様なネガティブな「感情」が自立のベースになるのでしょうか。
私自身、特にネットに良く観られる反韓国・反中国の感情的な罵詈雑言には辟易し、自分のブログでは「反日・反中・反韓と戦うブログ」とキャプションを入れていたこともあります。
「反xx」という単語への反応ではなく、根幹の部分が伝わらないものかなぁ。私の表現に問題があるのでしょうが、もうすこし粘ってみます。
ここであの文章を紹介したのは戦争で大敗し大国の脅威にさらされた日本が自らを鍛え上げ、その時代において支配的な帝国と対等の国であろうとしたその気構えを良しとしたからです。そこに国家国民としての日本人の始まりがあったというのは事実はどうか知りませんが、良い話ではないかと。
いや、別に反米で行こうぜ、というわけではないのですが、今の日本のアメリカに対する骨がらみの依存や自己欺瞞を見るにつけ、お行儀良く「良識」の上に鎮座していて何かが変わるのだろうか?という疑問があるのです。
それがるるーさんの言う「中立」であれば、非常にアグレッシブでかつラディカルであり、反とか中立とか単語の語感や言葉のあやを越えて私の感覚と一致します。
ぬりさん
>その様なネガティブな「感情」が自立のベースになるのでしょうか。
私自身、特にネットに良く観られる反韓国・反中国の感情的な罵詈雑言には辟易し、自分のブログでは「反日・反中・反韓と戦うブログ」とキャプションを入れていたこともあります。
「反xx」という単語への反応ではなく、根幹の部分が伝わらないものかなぁ。私の表現に問題があるのでしょうが、もうすこし粘ってみます。
ここであの文章を紹介したのは戦争で大敗し大国の脅威にさらされた日本が自らを鍛え上げ、その時代において支配的な帝国と対等の国であろうとしたその気構えを良しとしたからです。そこに国家国民としての日本人の始まりがあったというのは事実はどうか知りませんが、良い話ではないかと。
いや、別に反米で行こうぜ、というわけではないのですが、今の日本のアメリカに対する骨がらみの依存や自己欺瞞を見るにつけ、お行儀良く「良識」の上に鎮座していて何かが変わるのだろうか?という疑問があるのです。
TATSU さんの問いかけが「『反××』ならあなたは「反何か」という事でしたので、あえて反ではない『中立』としたのであって、日米軍事同盟国を否定する話しではそもそも無いと思います。
実際中共をみても「反××」精神から生まれるものは憎しみと無理解の何物でもない。我々は、むしろ相互理解なり相互認識を進める必要があり、反××から物事をスタートさせる所に、善とか親とか信の概念は無い。こんな不毛な感情から生まれるものは争いだけです。
日米間の同盟に話しを移せば、何らかの同盟関係は戦略上やはり必要です。それが対米であるべきか、対中であるべきか、対EUであるべきか、もしくは複合的な同盟関係かということは、ここでは長くなりますので一応割愛しますが、基本的に日本はEU、更にはロシア・インドとも、もっと親密になる必要があると思っています。
これは予想される米中の経済・エネルギー・軍事等の覇権争いに巻き込まれることなく、自国のプレゼンスを確保するためにも、必須だと思っています。
日本がアメリカの属国化している現状は、どう考えても自立した国家のありようとは程遠い。外交的な日本のプレゼンスは無きに等しいですから。
例えば今、久間防衛大臣がブッシュ政権下の大量破壊兵器疑惑に関して、アメリカ批判を繰り返していますが、立場はどうあれ、同盟国の間違った政策に対しては、はっきり国家の方針として『大切な同盟国の皆さん、私たちの国はあなた方の真の同盟国として、あえて苦言を呈します』という、自国の正義を伝えるべきであり、真の対等なパートナーシップとはそうあるべきだと思います。
これは決して『反米』ではありません。
むしろ真の友好国としての当然の責務だろうと思います。
米中が台湾海峡で衝突する事態においても同様です。日本を初めとするアジア諸国は、おそらくうろたえるばかりです。しかしそのとき日本のとるべき態度は、国連を巻き込んだ両国の説得以外にはないでしょう。両国の覇権主義に乗って戦火に巻き込まれるような愚かな道に引きずり込まれる事だけは避けなければと思います。
かような事態を未然に避ける為に、中核国である欧米(アメリカ)・中国・インド・イスラム・日本は、他国(他の文明内の争い)への介入を慎むことが肝要です。現代の多極的な世界において、この原則が平和を維持する第一条件であると思っています。
第二に必要なのは、共同した調停のためのルールです。
覇権争いの最期の防波堤となるものは、このかなり難しい調停のための苦悩の努力でしょう。それは、とみに無力化している国連や、敢えて不平等なスタートだと知りつつもNPTに加盟することで表現されている、ルールを尊重しようとする国際社会の智なのではないでしょうか。
実際中共をみても「反××」精神から生まれるものは憎しみと無理解の何物でもない。我々は、むしろ相互理解なり相互認識を進める必要があり、反××から物事をスタートさせる所に、善とか親とか信の概念は無い。こんな不毛な感情から生まれるものは争いだけです。
日米間の同盟に話しを移せば、何らかの同盟関係は戦略上やはり必要です。それが対米であるべきか、対中であるべきか、対EUであるべきか、もしくは複合的な同盟関係かということは、ここでは長くなりますので一応割愛しますが、基本的に日本はEU、更にはロシア・インドとも、もっと親密になる必要があると思っています。
これは予想される米中の経済・エネルギー・軍事等の覇権争いに巻き込まれることなく、自国のプレゼンスを確保するためにも、必須だと思っています。
日本がアメリカの属国化している現状は、どう考えても自立した国家のありようとは程遠い。外交的な日本のプレゼンスは無きに等しいですから。
例えば今、久間防衛大臣がブッシュ政権下の大量破壊兵器疑惑に関して、アメリカ批判を繰り返していますが、立場はどうあれ、同盟国の間違った政策に対しては、はっきり国家の方針として『大切な同盟国の皆さん、私たちの国はあなた方の真の同盟国として、あえて苦言を呈します』という、自国の正義を伝えるべきであり、真の対等なパートナーシップとはそうあるべきだと思います。
これは決して『反米』ではありません。
むしろ真の友好国としての当然の責務だろうと思います。
米中が台湾海峡で衝突する事態においても同様です。日本を初めとするアジア諸国は、おそらくうろたえるばかりです。しかしそのとき日本のとるべき態度は、国連を巻き込んだ両国の説得以外にはないでしょう。両国の覇権主義に乗って戦火に巻き込まれるような愚かな道に引きずり込まれる事だけは避けなければと思います。
かような事態を未然に避ける為に、中核国である欧米(アメリカ)・中国・インド・イスラム・日本は、他国(他の文明内の争い)への介入を慎むことが肝要です。現代の多極的な世界において、この原則が平和を維持する第一条件であると思っています。
第二に必要なのは、共同した調停のためのルールです。
覇権争いの最期の防波堤となるものは、このかなり難しい調停のための苦悩の努力でしょう。それは、とみに無力化している国連や、敢えて不平等なスタートだと知りつつもNPTに加盟することで表現されている、ルールを尊重しようとする国際社会の智なのではないでしょうか。
るるーさん、私の言う「反」とはアンチxxや排外主義でも偏狭な国粋主義でもなく「「反」とは、巨大なものに飲み込まれずに自立を志向する志としての「反」である」と29で定義しているのですが、なかなか会話が噛み合いませんね。このまま排外主義者君として説教され続けると、なおもって平行線かな(笑)
同盟関係をどうするか国際関係をどう制御するかという方法論以前にもっと根幹の部分でアメリカ依存の植民地マインドを再検討する必要があると思ってます。アメリカ的価値観や、現代のリバイアサンとまで呼ばれる巨大国家に対する畏れへの「抵抗」が無ければ、イランへの侵略が進行しつつある昨今『あえて苦言を呈する』ことなど叶わないでしょう。
そうした「反」「抵抗」と、国家間での相互理解・認識を深める交流というのは必ずしも矛盾しません。当時の巨大国家である唐への「反」で国家体制を強化しナショナリズムを確立した日本ですが、中国皇帝に対し大王でなく天皇であると対等の立場で名乗るも遣唐使を継続的に遣わして交流を続けたのです。
同盟関係をどうするか国際関係をどう制御するかという方法論以前にもっと根幹の部分でアメリカ依存の植民地マインドを再検討する必要があると思ってます。アメリカ的価値観や、現代のリバイアサンとまで呼ばれる巨大国家に対する畏れへの「抵抗」が無ければ、イランへの侵略が進行しつつある昨今『あえて苦言を呈する』ことなど叶わないでしょう。
そうした「反」「抵抗」と、国家間での相互理解・認識を深める交流というのは必ずしも矛盾しません。当時の巨大国家である唐への「反」で国家体制を強化しナショナリズムを確立した日本ですが、中国皇帝に対し大王でなく天皇であると対等の立場で名乗るも遣唐使を継続的に遣わして交流を続けたのです。
TATSUさんとは基本的におそらく思いは同じでしょう。
ただ違うとすれば私が、「反」が必要だというところからスタートしない、というかしたくないと思っているだけだろうと思います。現実的には行動を起こす上で、反という感情は強烈なエネルギーになり得ますし、ライバル設定もしかりだと思います。ただ私的にははそうありたくないというような所でしょうか。それが『お行儀良く「良識」の上に鎮座』という感じに写るのかもですね。
しかし北東アジアに蔓延している「反××」感情には、本当にうんざりです。自国が一番すぐれているという奢りの感情にも辟易してしまいます。諸悪の根源はその辺の優越感情ではないでしょうか。
説教しましたか(笑
自分の意思なり思いを一方的に書くと説教調になるようです。
表現がへたなだけで、TATSUさん、他意はありませんので、ひとつよろしくということで(笑
ただ違うとすれば私が、「反」が必要だというところからスタートしない、というかしたくないと思っているだけだろうと思います。現実的には行動を起こす上で、反という感情は強烈なエネルギーになり得ますし、ライバル設定もしかりだと思います。ただ私的にははそうありたくないというような所でしょうか。それが『お行儀良く「良識」の上に鎮座』という感じに写るのかもですね。
しかし北東アジアに蔓延している「反××」感情には、本当にうんざりです。自国が一番すぐれているという奢りの感情にも辟易してしまいます。諸悪の根源はその辺の優越感情ではないでしょうか。
説教しましたか(笑
自分の意思なり思いを一方的に書くと説教調になるようです。
表現がへたなだけで、TATSUさん、他意はありませんので、ひとつよろしくということで(笑
るるーさん
>自国が一番すぐれているという奢りは、排除したいのです。
>しかし、日本の文明が世界の中で唯一特殊だという事実は、
>やはり自分たちの事実として認識したいと思うのですよ。
ハンチントン氏の説の概要は知ってますが詳しくは勉強してませんので、自信を持って断言することは今の私には適いませんが、直感的に言っておそらく事実でしょう。その点はまったく同意です。「中国文明から派生して、西暦100年ないし400年の時期にあらわれた」日本文明は、西暦600年代についに国際政治のレベルでも中国圏からの独立と対等な国家としての自意識確立に至ったという風に解釈すると、私が引用した話と矛盾するとも思えません。ハンチントン氏の説の詳細は存じませんので、具体論では矛盾するのかも知れませんが。
>「反」って相手を想定している気がしませんか?
>相手の存在が前提の自立って、本当の自立ではないような、
>なんかそんな気がするんですけどどうでしょうか。
そうです。想定してます。
反という言葉の語感はアレルギーが強いので、ことさらそれを掲げようとは思いません。このトピックの対話でその想いを強くしました(笑)
ただ、アメリカへの反感や憎悪を掻き立てようという意図はまったくありませんが、今の日本でアメリカを想定しない自立はありえないと思うし、意識的にも想定しなければ駄目だというのが私の考えです。心理学者の岸田秀氏は「日本はアメリカに二度(黒船・WW2)レイプされ、アメリカに対してアンビバレンスを背負った」と言ってます。日米同盟とか渡された憲法とかそういう政治的・機能的な問題ではなく、もっと根幹の部分で日本人が自らを直視しなければならないと思うのです。歴史的にそのような呪いをかけられたのが現代の日本であるが故に自立には常にアメリカの影が付きまとうのではないかと。
例えが非常に良くないのですが、父親と子供のころから仲良しで反抗期もなくエディプス的葛藤もなく何でもいう事を聞く良い子が本当にしっかりと自立できるだろうか、というとニュアンスは伝わるでしょうか?
>自国が一番すぐれているという奢りは、排除したいのです。
>しかし、日本の文明が世界の中で唯一特殊だという事実は、
>やはり自分たちの事実として認識したいと思うのですよ。
ハンチントン氏の説の概要は知ってますが詳しくは勉強してませんので、自信を持って断言することは今の私には適いませんが、直感的に言っておそらく事実でしょう。その点はまったく同意です。「中国文明から派生して、西暦100年ないし400年の時期にあらわれた」日本文明は、西暦600年代についに国際政治のレベルでも中国圏からの独立と対等な国家としての自意識確立に至ったという風に解釈すると、私が引用した話と矛盾するとも思えません。ハンチントン氏の説の詳細は存じませんので、具体論では矛盾するのかも知れませんが。
>「反」って相手を想定している気がしませんか?
>相手の存在が前提の自立って、本当の自立ではないような、
>なんかそんな気がするんですけどどうでしょうか。
そうです。想定してます。
反という言葉の語感はアレルギーが強いので、ことさらそれを掲げようとは思いません。このトピックの対話でその想いを強くしました(笑)
ただ、アメリカへの反感や憎悪を掻き立てようという意図はまったくありませんが、今の日本でアメリカを想定しない自立はありえないと思うし、意識的にも想定しなければ駄目だというのが私の考えです。心理学者の岸田秀氏は「日本はアメリカに二度(黒船・WW2)レイプされ、アメリカに対してアンビバレンスを背負った」と言ってます。日米同盟とか渡された憲法とかそういう政治的・機能的な問題ではなく、もっと根幹の部分で日本人が自らを直視しなければならないと思うのです。歴史的にそのような呪いをかけられたのが現代の日本であるが故に自立には常にアメリカの影が付きまとうのではないかと。
例えが非常に良くないのですが、父親と子供のころから仲良しで反抗期もなくエディプス的葛藤もなく何でもいう事を聞く良い子が本当にしっかりと自立できるだろうか、というとニュアンスは伝わるでしょうか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|