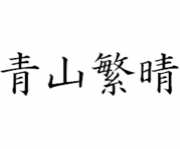「国家の自立とはなんだろう
なんて、おもわない?
もし思うことあったら、新トピたてて遊ぼうよ^^」
去る11月16日、るるーさんにこんなとっても危険なキラーパスを頂きましたw。
とても興味ある主題であると同時に、非常に深く、迂闊に動けないなというのが正直な所。核武装論の場でも、頑なにこの問題を避けて通ってきました。知識なしに語っていた核武装論の時とは異なり、根が深すぎて、普通に理屈だけで説明しても何も伝わらないような気がしたからです。しかし、それと同時にこのコミュニティの皆さんに問いかけてみたいという気持ちも強かった。これは私の一つの試みであり、自分へのささやかな挑戦です。
トピックを立てる以上、ある程度の道筋を立てた問いかけがしたい。私のような門外漢の若者にそんな大それた事は不可能だということも、トピック主としてこのコミュニティにもっと適任の方がいらっしゃることも百も承知です。それでも、私にふって下さったるるーさんの直感に甘えて、私が考えたことが少しでも踏み台になればと思い、考える時間を少し頂きました。ある問題に対峙する時、その質を決めるのは情報量や経験の多寡ではないと信じて。
国家の自立とは何か。おそらくそんなあいまいなものに答えなどないでしょう。しかし、日本は自立した国家か?との問いかけには、素直にYesと答えられない何かがそこにある。それを少しでもあぶり出したい。現在の地球上の人間にとって、この国家の自立という奇妙な概念は一体何なのだろう・・・。
私は何を問いたいのだろう。
プラトンは「メノン」の中で、「問題の解決を求めることは不条理だ」と言ったという。もし何を捜し求めているのか分かっているのなら問題は存在しないし、逆にもし何を捜し求めているのかも分かっていないのなら、何かを発見できるはずもない。それでも私がこうして問いを立てるのは、自分の中に答えがあることは分かっていながら、どうやってそこにたどり着けばよいのかが皆目分からないからだ。だから、皆さんに問いたい。この場という力をお借りして。
以下、私が今日まで思って来たことを書かせて頂きます。残念な事に、非力な私では自分の力だけで本質に迫る事が出来ず、思索のヒントを多くの書籍に頼り、引用や説明の多い長文になってしまいました。これを読む前に、自身の思いを語るもよし、とりあえず拾い読みしてコメントするもよし、だと思います。相変わらず長い・・・しかしこれが最低限だと信じる。
■「ねじれ」の認識
いまさらまだ戦後かよと思いたくなるほど、戦争と直接は無関係なはずの私達にも歴史の問題は突きつけられる。人間の過去に対するこだわりというものは驚愕に値する。おそらくこのような、自分や他人の過去の行動をつい顧(省)みてしまうという人間の社会的性質が、自らの行為を膨大な記録と記憶によって残させてきて、またそれを元に文化や文明をブラッシュアップさせてきたのだろう。しかし、「戦後」という言葉が今もこれ程大きな意味を持っているという現実は、そんな人間の性質だけではないそれ以上の何かがそこにあることを私達に感じさせる。自分の過去の行いが正しかったのか、間違っていたのか。相手はどうだったのか。それをどのように認識するかということは、人間が生きていく上で驚くほど重要な位置を占めているということなのだろう。日常の経験でもそうだ。人は気がつかないうちに過去に縛られて生きている。そしてそれを乗り越えようとする。
終戦後の日本人のこころの変遷を大きく考えていると、奇妙な当惑に突き当たる。それは、かつての自らの理を翻し、敵だったアメリカを含む連合国をあたかも疑いも無いかの如く受け入れ、それらの事が現在の平和と経済発展をもたらしたと平気で賞賛する。そんなきりもみ飛行をしながら無理やり着地するようなアクロバティックな離れ業をやってのけている。すごい。そしてなにより、そんなねじれた現状に対する感覚の鈍さだ^1。それを象徴する例が、「敗戦」ではなく「終戦」という言葉であり^3、「占領軍」ではなく「進駐軍」、「日本軍」を「自衛隊」、「駆逐艦」を「護衛艦」etc.・・・。自分達で勝ち取った平和憲法が日本を守ってきたなどという文字通り平和な鈍さすら存在する。こうした嘘をちりばめる事によって、見て見ないふりをし、自分を欺き正当化してきた(後述するが、かといって改憲派も然りなのである)。
この様な欺瞞は、それでも前に進まねばならなかった戦後当時の日本人のある種の必要だった人間的弱さからきているとも言えるし、そのような精神的弱体化が連合軍側の意図でもあった事も事実である。
「勝者こそ正義」というレベルの現実は受け止められても、敗けたのにもかかわらず、それを素直に敗けと認めることは許されなかった。いわば敗け切っていない。勝者によってそんな矛盾に満ちた答えのない状況に強制的追い込まれ、ナショナリティや主体を破壊されながらも、それを肯定して(おそらくどこかでは否定して)今日まで生きてきた。
我々は国家として生きる上での眼に見えない重い十字架を背負わされ、汚れた過去とねじれた現実、そして「国」という枠組みから目をそらし、振り返らず前を向き豊かさを追いかける事で、背中にあるその存在を忘れようとしてきたのだ。そして、これまではそれほど気にならなかったし、完全に忘れてしまうにはまだまだ時間が足りていない。たぶん。
世界が今まで通りなら、日本もこのままでいいのかもしれない。しかし時代は変わった。冷戦は終わり、日本は新たな国際的な混乱と脅威に巻き込まれようとしている。今こそ国家の自立が問われるときなのではないか。その為には、憲法改正などの具体的方法の前に、この問題の根っこにそびえている自己認識の「ねじれ」を真正面から直視するところから始めなければならないのではないかと、私は考えている。そこに日本が表面上いくら取り繕っても、なかなか自立しそうにない元凶があるのではないか。
以下、その「ねじれ」を直視するという事が、具体的にどのような形で現れ、克服される可能性があるのかを考えてみたいと思う。
■憲法について
・渡され方
象徴的な出来事はやはり憲法の「渡され方」だろう。連合軍当局が憲法草案を日本側に突きつけたとき、日本側に検討の為に与えられた時間はわずか15分だった。1946年2月13日、連合軍総司令部民政局局長コートニー・ホイットニーは、日本側に草案を手渡し、一旦隣のベランダに退いた。そして検討時間が過ぎ、一同が会した時、ホイットニーが話したとされている有名なくだりがある。
「いやあ、原子力的な日光(atomic sunshine)の中でひなたぼっこしてましたよ。」
後にホイットニーはこの発言を(この日彼は体調が悪かった為)冷静さを欠いた冗談だったと証言しているが、だからこそ本音を現しているともいえる。つまり、原子爆弾という権力によって裏付けられた草案だという事を、日本人に飲み込ませようとしたのである(「ニッポン日記」マーク・ゲイン)。
私達はこうして、軍事力を放棄することをうたっているはずの憲法を、ある意味「原子力的」に(軍事力によって)「押し付けられ」、その後この矛盾した強制と不条理な価値観をどこか否定できないと自分で感じるようになった。そして後に、「憲法勝ち取り説」(押し付けられたが望んでいたものだった)、「憲法形見説」(犠牲者によって与えられた贈り物だ)、「押し付け消化説」(強制の事実は時間によって消化された)、「9条世界遺産説」(太田光+中沢新一)、などの奇妙な護憲派を生んでしまった。一方、主に交戦権の回復を目指し、戦前日本を全肯定もせず否定もしないといったような立場にたつ、改憲論も根強く存在してきた。しかし、彼らもまた「ねじれ」感覚に鈍く、自分の原点が汚れていて、自立した統治などしてきていない事を直視しないようにしているという点で、護憲派と共通しているとも言えるのではないだろうか。この護憲派と改憲派という二つの対照的な立場は、この意味において「ねじれ」が生んだ双生児なのである^1。新憲法成立過程で唯一反対を貫いた美濃部達吉は、後に改憲案として「第一条 日本帝国ハ連合国ノ指揮ヲ受ケテ 天皇之ヲ統治ス」とすべきであると主張した。負けた人間が、負けたという事実を自分に隠蔽したらおしまいだという、汚れた自分をシンプルに受け入れた、簡潔な態度である。現状に素直に反映させるのであれば、現代の改憲派は「アメリカの庇護の下成立している偽独立国日本は、今後真の独立・自立を目指す」という条文を入れなければならない。
私達はまず、このようなねじれた現状を正面から認識するところから始め、その上で憲法をもう一度選び直す、または作り変える必要があるのではないだろうか。
・第九条について
交戦権についてここで議論を始めてしまうと、トピックがいくつあっても足りない。ただここで私が最低限問いたいのは、自衛隊についての現状を正しく憲法で再規定する必要はあるということ。そうでないと、「憲法は憲法で、重要なのは解釈だ」などという、憲法を尊重しない不思議な立憲国国民であり続けなければいけない。他の条文も然りだ。それとも、いつまでもホンネとタテマエを使い分け続けるのが日本的だなどとでも言うのだろうか。それはそれとして一つの日本的文化なのかもしれないが、その欺瞞が国民の精神の根にもたらす弊害に目をつぶってはいやしないだろうか。
そもそも、ここの話は、人々が憲法や法律を大切にするという事が大前提になっている。国にとっての憲法の重要性を感じる人間の気持ちを見つめるところから考えなければならない。
もう一つ、将来自衛隊が戦闘活動を行う事になった場合、軍法会議が今の日本に存在しない事が致命的になるという事も付け加えさせて頂く^2。
・第六五条について
「行政権は、内閣に属する」とある。これは国の最高責任が曖昧に散らされているとも言える。このことは、日本国民が責任がはっきりしない行政やそれを規定するはずの選挙になかなか関心を持てない元凶の一つになっているのではないか。この条項を「行政権は、内閣総理大臣に属する」と改正できるかどうかということも、注目に値する日本に課せられた重大な課題ではないだろうか^2。
■天皇について
・戦争責任
天皇に関する戦後のねじれは、宣戦の詔勅に捺印し発布した責任と、その名のもとに死んだ自国の兵士たちに対する責任が、(GHQの策略と日本側の望みとして)戦争裁判で免責され、戦犯が代わりに絞首刑にされたこと、また併せてその後天皇も自身の責任を明らかにしなかったこと、さらに天皇に向けられるべき責任の問いかけが社会的に抑圧されてきたことからくるものである。死者の声を代弁すべき日本遺族会が、天皇を責めるのではなく慰霊を懇願するという、これまた離れ業的な主張の反転をさせてしまい、死者たちの遺言執行人がどこにもいなくなってしまった。その抑圧が、1966年、三島由紀夫に「英霊の声」を書かせた^1。日本の保守派は、天皇に道義的責任はないという戦後的な詭弁を捏造することで、致命的な弱点を抱えることになってしまった。大岡昇平は天皇の生涯に触れ、心からの敬愛に立ち、死者への責任を追及した信奉者を、一人として持たずに逝った「裕仁氏はやはり運が悪いおいたわしい天皇だと言わざるをえない」と言った(「二極対立の時代を生き続けたいたわしさ」大岡昇平)。私達はせめて、「責めはしないが正しくはないこと」と断言し、この過去のねじれを直視する必要があるのではないだろうか。
・日本と天皇
かといって、日本にとっての天皇の存在意義が損なわれたわけではない。トインビー、バグビー、ハンチントンといった20世紀を代表する歴史学者、文明論者たちはいずれも、日本という国は「一つの国で一つの文明をなす」世界でも独特な存在である、と語っているらしい^3。日本は様々な文化を取り込んで来たので、それが一つであることをはっきり証明することは不可能だが、彼らが指摘したように、どこかに統一された精神世界があるような気もする。もしそれがあるとすれば、天皇制であり、神道であり、併せてあいまいではあるが日本の文化、伝統、精神なのだろう。おそらくは、四方を海に囲まれ、季節がはっきりしていて、山がちで平野が少ないというこの風土を生き抜く上で、過去の日本人が自然に選択した生き方の知恵の結晶としての指針であり、長きにわたって大切にしてきた合理的なシステムだったのだろう。神道のその宗教としての特殊性は、教祖や宗教指導者、まともな経典すらないということではないだろうか。すなわち、基本的には自然な生活に根ざしたものしか残っていないという意味で、人間の宗教的側面を最小限にそぎ落としたものなのかもしれない。それって凄い。私自身が頻繁に使っている、「美学」とか「汚れ」などという概念も、言われてみれば、そうしたものに根ざしているのかなと思う。先日ある海外の友人に、「オオバ(私)は日本人の中で最も日本人的で、かつ最も興味深い男だ」と言われた。おそらく後者は別の意味だろうが(笑)。
青山さんがその著書で、「何とも情けない政治、後手後手の安全保障政策、荒廃しきった教育のなかで、これほど社会が安定を保っているのは、世界の常識からして信じられないような奇跡です。(中略)深い理由の一つとして天皇の存在があることを指摘しようと思います。」^2と語っておられるように、現在の日本においてもなお天皇の存在、日常に根ざしている神道の働きは大きいのではないだろうか。その事にも目を向け、日本にとっての天皇の扱いを、厳かに、真摯に考えなおす必要があるということを、皆さんに問いたい。
■戦死者の弔いについて
・正解は無い?
細木数子がTVの人生相談番組で、相談者にゆかりのある故人のお墓参りを薦めているシーンをよく観る。私はこの占い師が好きという訳ではないが、このアドバイスによって心の問題を多く解決してきたという事実は、人間の精神にとって死者への態度というものが、目に見えない深いレベルで重要な位置を占めているということだろう。実際、他人の人格を判断するとき、その人の死者に対する態度というものは、意外と重要なウェイトを占めている。靖国参拝に対する日本や隣国の過激な反応も、単なる政治問題では無く、"それなり"に人間のそうした心情に立脚しているのだと思う。
火事場で自分を押し倒した上に、覆い被さって焼け死んだ人の灰に守られて生き延びた人が、生きて最初に命ぜられた(理不尽な)仕事が「自分を守って死んだその人を否定せよ」だった^1。それが戦後の日本の姿だ。生き残った私は「私の為に死んだこの死者を否定できない」と言うべきなのか、それとも「私の為に死んだにせよ、死者の悪業は糾弾されなければならない」と言うべきなのか。これが敗戦後の私達に突きつけたれた問いなのだろう。
そこにはおそらく万人が受け入れやすい正解はない。そこには悲しい事実があるだけだからだ。正解がないままに、ある人々は「死者を礼讃する」道を選び、ある人々は「死者を糾弾する」道を選んだ。しかし、その主張のどちらもが、私達の「敗戦国問題」を解決に導いてくれなかった事実は認めなければならない。いや、近年は礼讃を是とし、それこそ答えだとする人々が増えて来た気もする。しかし、そのような戦死者礼讃の傾向が、再び国家を新たな戦争や武力行使に向かわせるのではないかという懸念は間違いなく成立する。では我々はどうしたらよいのか。尊い犠牲の上に今日の平和があると礼讃するでもなし、過去の汚点として他者としての戦死者を糾弾し諸外国に永久に謝罪し続けるでもない。それらは両者とも自らの汚点に目をつぶっている。その意味では平和記念公園と靖国神社も同じ問題を抱えている。誤解を恐れず言えば、ただ、ありのままの汚れた死としての戦死者を受け入れなければならないのではないか。そのようなまっすぐな認識を持って始めて、諸外国に与えた多くの犠牲者に対しての立ち位置を確保することが出来るのではないだろうか。
◇以上の3つの議論は、具体的行動というよりは、その前段階における再認識の薦めである。メンタルには根源的であると思われる一方、どこか遠く、実際は日々の生活のなかでその問題意識を実感しにくいことも事実。しかし、これらの問いに直面した時、当惑することも確かなのである。そして、これらの問いは、国民一人一人というよりも、直接には政治家や、あーだこーだ言う評論家にこそ突きつけられるべきで、我々一般国民はそれらの人々の言動の裏にあるこの心理的な問題を、冷静に理解し、受け止め、判断するために、上記の事に気がつくことが必要ではないだろうか。
もちろん、こんな小難しいことを自己分析などせずとも、「今までは幼稚だった」と一言で切り捨て、とにかく自立するということは、既に可能な時代に突入しつつあるのだなとも感じる。青山さんは、自立した国民であろうとすることは、「幼年国家としての自覚を、国民合意に基づく思想としてもつことでもある。」と述べている^2。
■真の民主国家について
日本が民主国家とは笑わせる話で、低い投票率と低い政治への関心。今の日本国民に、国民が国を決めて動かしているという自覚がある人がどれだけいるだろうか。
・利他主義と集団帰属意識
ヒトを含むあらゆる社会性動物は、様々なレベルの集団を形成するが、社会生物学ではいわゆる「利他行動」と呼ばれる行為の結果として集団(集団帰属意識)が生じるていると説明される。もっとも身近な例は家族や親族に対する利他行動である。
ヒトの凄いところは、明らかに血縁関係は遠いのに、自分となんらかの些細な共通項を見つけるだけで、仲間意識を作り出してしまうという意識の延長技をやってのける驚異的な行動の幅の広さを持ち合わせていることだ。それは空間的・時間的距離さえ簡単に超えられる。はっきりとは証明されていないが、おそらくこの驚愕の事実を説明出来る唯一の手段は、身体的特徴に限らず、文化や習慣の一番元となっている、実在はするが少し抽象的な概念(身体的特徴や性質を発現する遺伝子セットとしてのジーン、または文化伝播の単位ミーム)の淘汰に注目することである。つまり、相手とのなんらかの共通の特徴を発見した場合、その特徴を出来るだけ広める、またはもしその特徴の存続が脅威にさらされているのであれば守ろうとする行動が、進化遺伝学的に安定に存在しうるということである。もし、一個体の利益よりも、同じ特徴をもつ個体全体の為に行動をしたほうが、その特徴の存続にとって有利な状況に置かれた場合、単独では考えられないような利他的な行動を起こすことが理論上可能である。
ここで、注意して欲しいのは、生物学が理解出来るのは、人間の行動の幅の限界のみであって、行動のレパートリーの限界を規定することは出来ないということである。我々が、この苦難に満ちた状況で自立して生きるという、かつてない選択をするということは、この行動レパートリーの限界へのあくなき挑戦なのである。
・社会生物学からみた国とナショナリズム
「国」の概念は、おそらく人間の社会性動物としてのこの側面が過去最大規模に近い形で発現した例だろう(おそらく宇宙人が侵略してきたら、世界規模になるだろう)。しかし、その共通の特徴というものは、個々の国で様々で、民族としての血統であったり、言語や宗教、生活習慣といった文化であったり、単に定められた地域に住んでいることだけだったりもする。日本の場合はどうだろうか。狭い国土で長い年月あまり多くの外国人を受け入れてこなかった日本は、上に挙げたすべての項目において共通項を見出すことが出来る、数少ない国なのではないだろうか。それがもしかしたら、トインビーらが指摘した日本の特異性を生み出した根源だったのかもしれない。外的な脅威なく安定した閉じた空間のなかで長期間生きていると、国内での多様化が進み(その意味で文化は華開くのだが)、国内の共通項への関心は低下し、個人主義に徐々に移行していく。しかし、国単位での脅威が存在するということを潜在意識が認識すると、俄然国レベルの文化の共通項などを意識しはじめ、様々な形のナショナリズムが台頭してくる。幕末に様々なレベル・形で現れた尊王攘夷論の多形化現象が良い例だろう。それは別の側面では、危険な変化の始まりでもあり、人類は決まって同様の変化に併せて軍備を増強させ、戦争に走ってきた。
ここまでで私が言いたかったことは、現在の日本国民の国に対する主体性の無さは、精神的に主体を破壊されてきたのに加えて、脅威の存在から長期間目をそむけて来たことによる当然の帰結だということである。自立する必然性が存在していない。一方で、今また日本の人々がそのような脅威を感じつつあるということだ。
・現代において
冷戦時代のアメリカの庇護による安定の時代は過ぎた。北朝鮮によるテロ攻撃や核の脅威、今まで安全を保障してくれていたはずのアメリカにとっても、冷戦時代の時ほど日本を守るメリットはなくなってきてしまった。持論を併せさせて頂けば、石油供給能力の懸念と中国の台頭、アメリカの覇権主義との世界の対立などから、21世紀の世界構造は大きく変わっていくだろう→ピークオイルコミュ参照(オイ。
日本の自立を語る上で、アメリカの存在をはずすわけにはいかない。例えばこういう意見が存在する。日米安保を破棄し、在日米軍を追い出し、米ドルの下での円を脱却してこそ、真の日本の自立が成り立つ、云々。これはこれで一つの真実だろう。あとは食料とエネルギーなどの資源をちゃんと確保できれば、理想的な自立国家が誕生する。しかし、これらの意見に対して私の立場は明確だ。現在も(ある程度限定的な)将来も、日米の現体制は日本にとって非常に重要だという事である。我々に必要なのは、そういう状況を主体的に選び直すことなのではないか。それが、真に現実に即した自立ではないか。
また、近年日本の自立をうたう人々の中でよく見受けられるのが、「日本の文化や伝統と誇りを取り戻せ」的な主張である(例えば、JCの「真の自立国家シナリオ」周辺などhttp://
もう一つ。制度的な民主国家にどっぷりはまってしまうと、その国は群集心理に右往左往する国家ということになってしまう。必ずしも国民の群集心理が良い結果をもたらすとは限らない。特に混乱時には、群集心理こそ危険の種になる。そのためにも、混乱の前に、冷静に国民を導き、冷静な国家決断を下せる人物を見極められる国民にならなければならないのではないか。
故意に弱体化されたメンタリティの中で、国家としての主体性を失い、これから激動の世界に翻弄されていくのを黙ってみているよりは、危険(軍国化を望むナショナリズムや差別的民族主義の発生等)を伴うとしても、それを取り除きながらも、国民からボトムアップ的に主体性を獲得し、自らの頭で考え、自らの手で国民と祖国の運命を決するという困難な道のりへの覚悟を今決めることが、「私」たちを守り、そうした生き方が日本人の誇りや美意識に適っているのだと信じる。青山さんの言葉を借りれば、「自ら引き受けて、おのれ自身で生きる。自分でものを考え、行動する国民になる」という事である^2。
まとめると、世界の現実と未来、日本の直視しがたい歴史と現在のメンタリティの弱さを正面から見つめ、憲法改正、天皇の扱い、戦死者の扱いなどを通じて、日本人一人一人がこの国を自ら主体的に作っているという意識で、国に関与するようになったとき、日本は真の意味で自立したと言えるのではないか。
ありがとうございました。みなさんの考えるきっかけとなれれば幸いです。
主に参考にさせて頂いた書籍
1:「敗戦後論」加藤典洋 「群像」95年1月号
2:「日本国民が決断する日」青山繁晴 扶桑社 2004年
3:「日本人としてこれだけは知っておきたいこと」中西輝政
PHP
新書 2006年
特に、「ねじれ」のアイディアは1に多くを負っている。3はたまたま最近読んだ。
なんて、おもわない?
もし思うことあったら、新トピたてて遊ぼうよ^^」
去る11月16日、るるーさんにこんなとっても危険なキラーパスを頂きましたw。
とても興味ある主題であると同時に、非常に深く、迂闊に動けないなというのが正直な所。核武装論の場でも、頑なにこの問題を避けて通ってきました。知識なしに語っていた核武装論の時とは異なり、根が深すぎて、普通に理屈だけで説明しても何も伝わらないような気がしたからです。しかし、それと同時にこのコミュニティの皆さんに問いかけてみたいという気持ちも強かった。これは私の一つの試みであり、自分へのささやかな挑戦です。
トピックを立てる以上、ある程度の道筋を立てた問いかけがしたい。私のような門外漢の若者にそんな大それた事は不可能だということも、トピック主としてこのコミュニティにもっと適任の方がいらっしゃることも百も承知です。それでも、私にふって下さったるるーさんの直感に甘えて、私が考えたことが少しでも踏み台になればと思い、考える時間を少し頂きました。ある問題に対峙する時、その質を決めるのは情報量や経験の多寡ではないと信じて。
国家の自立とは何か。おそらくそんなあいまいなものに答えなどないでしょう。しかし、日本は自立した国家か?との問いかけには、素直にYesと答えられない何かがそこにある。それを少しでもあぶり出したい。現在の地球上の人間にとって、この国家の自立という奇妙な概念は一体何なのだろう・・・。
私は何を問いたいのだろう。
プラトンは「メノン」の中で、「問題の解決を求めることは不条理だ」と言ったという。もし何を捜し求めているのか分かっているのなら問題は存在しないし、逆にもし何を捜し求めているのかも分かっていないのなら、何かを発見できるはずもない。それでも私がこうして問いを立てるのは、自分の中に答えがあることは分かっていながら、どうやってそこにたどり着けばよいのかが皆目分からないからだ。だから、皆さんに問いたい。この場という力をお借りして。
以下、私が今日まで思って来たことを書かせて頂きます。残念な事に、非力な私では自分の力だけで本質に迫る事が出来ず、思索のヒントを多くの書籍に頼り、引用や説明の多い長文になってしまいました。これを読む前に、自身の思いを語るもよし、とりあえず拾い読みしてコメントするもよし、だと思います。相変わらず長い・・・しかしこれが最低限だと信じる。
■「ねじれ」の認識
いまさらまだ戦後かよと思いたくなるほど、戦争と直接は無関係なはずの私達にも歴史の問題は突きつけられる。人間の過去に対するこだわりというものは驚愕に値する。おそらくこのような、自分や他人の過去の行動をつい顧(省)みてしまうという人間の社会的性質が、自らの行為を膨大な記録と記憶によって残させてきて、またそれを元に文化や文明をブラッシュアップさせてきたのだろう。しかし、「戦後」という言葉が今もこれ程大きな意味を持っているという現実は、そんな人間の性質だけではないそれ以上の何かがそこにあることを私達に感じさせる。自分の過去の行いが正しかったのか、間違っていたのか。相手はどうだったのか。それをどのように認識するかということは、人間が生きていく上で驚くほど重要な位置を占めているということなのだろう。日常の経験でもそうだ。人は気がつかないうちに過去に縛られて生きている。そしてそれを乗り越えようとする。
終戦後の日本人のこころの変遷を大きく考えていると、奇妙な当惑に突き当たる。それは、かつての自らの理を翻し、敵だったアメリカを含む連合国をあたかも疑いも無いかの如く受け入れ、それらの事が現在の平和と経済発展をもたらしたと平気で賞賛する。そんなきりもみ飛行をしながら無理やり着地するようなアクロバティックな離れ業をやってのけている。すごい。そしてなにより、そんなねじれた現状に対する感覚の鈍さだ^1。それを象徴する例が、「敗戦」ではなく「終戦」という言葉であり^3、「占領軍」ではなく「進駐軍」、「日本軍」を「自衛隊」、「駆逐艦」を「護衛艦」etc.・・・。自分達で勝ち取った平和憲法が日本を守ってきたなどという文字通り平和な鈍さすら存在する。こうした嘘をちりばめる事によって、見て見ないふりをし、自分を欺き正当化してきた(後述するが、かといって改憲派も然りなのである)。
この様な欺瞞は、それでも前に進まねばならなかった戦後当時の日本人のある種の必要だった人間的弱さからきているとも言えるし、そのような精神的弱体化が連合軍側の意図でもあった事も事実である。
「勝者こそ正義」というレベルの現実は受け止められても、敗けたのにもかかわらず、それを素直に敗けと認めることは許されなかった。いわば敗け切っていない。勝者によってそんな矛盾に満ちた答えのない状況に強制的追い込まれ、ナショナリティや主体を破壊されながらも、それを肯定して(おそらくどこかでは否定して)今日まで生きてきた。
我々は国家として生きる上での眼に見えない重い十字架を背負わされ、汚れた過去とねじれた現実、そして「国」という枠組みから目をそらし、振り返らず前を向き豊かさを追いかける事で、背中にあるその存在を忘れようとしてきたのだ。そして、これまではそれほど気にならなかったし、完全に忘れてしまうにはまだまだ時間が足りていない。たぶん。
世界が今まで通りなら、日本もこのままでいいのかもしれない。しかし時代は変わった。冷戦は終わり、日本は新たな国際的な混乱と脅威に巻き込まれようとしている。今こそ国家の自立が問われるときなのではないか。その為には、憲法改正などの具体的方法の前に、この問題の根っこにそびえている自己認識の「ねじれ」を真正面から直視するところから始めなければならないのではないかと、私は考えている。そこに日本が表面上いくら取り繕っても、なかなか自立しそうにない元凶があるのではないか。
以下、その「ねじれ」を直視するという事が、具体的にどのような形で現れ、克服される可能性があるのかを考えてみたいと思う。
■憲法について
・渡され方
象徴的な出来事はやはり憲法の「渡され方」だろう。連合軍当局が憲法草案を日本側に突きつけたとき、日本側に検討の為に与えられた時間はわずか15分だった。1946年2月13日、連合軍総司令部民政局局長コートニー・ホイットニーは、日本側に草案を手渡し、一旦隣のベランダに退いた。そして検討時間が過ぎ、一同が会した時、ホイットニーが話したとされている有名なくだりがある。
「いやあ、原子力的な日光(atomic sunshine)の中でひなたぼっこしてましたよ。」
後にホイットニーはこの発言を(この日彼は体調が悪かった為)冷静さを欠いた冗談だったと証言しているが、だからこそ本音を現しているともいえる。つまり、原子爆弾という権力によって裏付けられた草案だという事を、日本人に飲み込ませようとしたのである(「ニッポン日記」マーク・ゲイン)。
私達はこうして、軍事力を放棄することをうたっているはずの憲法を、ある意味「原子力的」に(軍事力によって)「押し付けられ」、その後この矛盾した強制と不条理な価値観をどこか否定できないと自分で感じるようになった。そして後に、「憲法勝ち取り説」(押し付けられたが望んでいたものだった)、「憲法形見説」(犠牲者によって与えられた贈り物だ)、「押し付け消化説」(強制の事実は時間によって消化された)、「9条世界遺産説」(太田光+中沢新一)、などの奇妙な護憲派を生んでしまった。一方、主に交戦権の回復を目指し、戦前日本を全肯定もせず否定もしないといったような立場にたつ、改憲論も根強く存在してきた。しかし、彼らもまた「ねじれ」感覚に鈍く、自分の原点が汚れていて、自立した統治などしてきていない事を直視しないようにしているという点で、護憲派と共通しているとも言えるのではないだろうか。この護憲派と改憲派という二つの対照的な立場は、この意味において「ねじれ」が生んだ双生児なのである^1。新憲法成立過程で唯一反対を貫いた美濃部達吉は、後に改憲案として「第一条 日本帝国ハ連合国ノ指揮ヲ受ケテ 天皇之ヲ統治ス」とすべきであると主張した。負けた人間が、負けたという事実を自分に隠蔽したらおしまいだという、汚れた自分をシンプルに受け入れた、簡潔な態度である。現状に素直に反映させるのであれば、現代の改憲派は「アメリカの庇護の下成立している偽独立国日本は、今後真の独立・自立を目指す」という条文を入れなければならない。
私達はまず、このようなねじれた現状を正面から認識するところから始め、その上で憲法をもう一度選び直す、または作り変える必要があるのではないだろうか。
・第九条について
交戦権についてここで議論を始めてしまうと、トピックがいくつあっても足りない。ただここで私が最低限問いたいのは、自衛隊についての現状を正しく憲法で再規定する必要はあるということ。そうでないと、「憲法は憲法で、重要なのは解釈だ」などという、憲法を尊重しない不思議な立憲国国民であり続けなければいけない。他の条文も然りだ。それとも、いつまでもホンネとタテマエを使い分け続けるのが日本的だなどとでも言うのだろうか。それはそれとして一つの日本的文化なのかもしれないが、その欺瞞が国民の精神の根にもたらす弊害に目をつぶってはいやしないだろうか。
そもそも、ここの話は、人々が憲法や法律を大切にするという事が大前提になっている。国にとっての憲法の重要性を感じる人間の気持ちを見つめるところから考えなければならない。
もう一つ、将来自衛隊が戦闘活動を行う事になった場合、軍法会議が今の日本に存在しない事が致命的になるという事も付け加えさせて頂く^2。
・第六五条について
「行政権は、内閣に属する」とある。これは国の最高責任が曖昧に散らされているとも言える。このことは、日本国民が責任がはっきりしない行政やそれを規定するはずの選挙になかなか関心を持てない元凶の一つになっているのではないか。この条項を「行政権は、内閣総理大臣に属する」と改正できるかどうかということも、注目に値する日本に課せられた重大な課題ではないだろうか^2。
■天皇について
・戦争責任
天皇に関する戦後のねじれは、宣戦の詔勅に捺印し発布した責任と、その名のもとに死んだ自国の兵士たちに対する責任が、(GHQの策略と日本側の望みとして)戦争裁判で免責され、戦犯が代わりに絞首刑にされたこと、また併せてその後天皇も自身の責任を明らかにしなかったこと、さらに天皇に向けられるべき責任の問いかけが社会的に抑圧されてきたことからくるものである。死者の声を代弁すべき日本遺族会が、天皇を責めるのではなく慰霊を懇願するという、これまた離れ業的な主張の反転をさせてしまい、死者たちの遺言執行人がどこにもいなくなってしまった。その抑圧が、1966年、三島由紀夫に「英霊の声」を書かせた^1。日本の保守派は、天皇に道義的責任はないという戦後的な詭弁を捏造することで、致命的な弱点を抱えることになってしまった。大岡昇平は天皇の生涯に触れ、心からの敬愛に立ち、死者への責任を追及した信奉者を、一人として持たずに逝った「裕仁氏はやはり運が悪いおいたわしい天皇だと言わざるをえない」と言った(「二極対立の時代を生き続けたいたわしさ」大岡昇平)。私達はせめて、「責めはしないが正しくはないこと」と断言し、この過去のねじれを直視する必要があるのではないだろうか。
・日本と天皇
かといって、日本にとっての天皇の存在意義が損なわれたわけではない。トインビー、バグビー、ハンチントンといった20世紀を代表する歴史学者、文明論者たちはいずれも、日本という国は「一つの国で一つの文明をなす」世界でも独特な存在である、と語っているらしい^3。日本は様々な文化を取り込んで来たので、それが一つであることをはっきり証明することは不可能だが、彼らが指摘したように、どこかに統一された精神世界があるような気もする。もしそれがあるとすれば、天皇制であり、神道であり、併せてあいまいではあるが日本の文化、伝統、精神なのだろう。おそらくは、四方を海に囲まれ、季節がはっきりしていて、山がちで平野が少ないというこの風土を生き抜く上で、過去の日本人が自然に選択した生き方の知恵の結晶としての指針であり、長きにわたって大切にしてきた合理的なシステムだったのだろう。神道のその宗教としての特殊性は、教祖や宗教指導者、まともな経典すらないということではないだろうか。すなわち、基本的には自然な生活に根ざしたものしか残っていないという意味で、人間の宗教的側面を最小限にそぎ落としたものなのかもしれない。それって凄い。私自身が頻繁に使っている、「美学」とか「汚れ」などという概念も、言われてみれば、そうしたものに根ざしているのかなと思う。先日ある海外の友人に、「オオバ(私)は日本人の中で最も日本人的で、かつ最も興味深い男だ」と言われた。おそらく後者は別の意味だろうが(笑)。
青山さんがその著書で、「何とも情けない政治、後手後手の安全保障政策、荒廃しきった教育のなかで、これほど社会が安定を保っているのは、世界の常識からして信じられないような奇跡です。(中略)深い理由の一つとして天皇の存在があることを指摘しようと思います。」^2と語っておられるように、現在の日本においてもなお天皇の存在、日常に根ざしている神道の働きは大きいのではないだろうか。その事にも目を向け、日本にとっての天皇の扱いを、厳かに、真摯に考えなおす必要があるということを、皆さんに問いたい。
■戦死者の弔いについて
・正解は無い?
細木数子がTVの人生相談番組で、相談者にゆかりのある故人のお墓参りを薦めているシーンをよく観る。私はこの占い師が好きという訳ではないが、このアドバイスによって心の問題を多く解決してきたという事実は、人間の精神にとって死者への態度というものが、目に見えない深いレベルで重要な位置を占めているということだろう。実際、他人の人格を判断するとき、その人の死者に対する態度というものは、意外と重要なウェイトを占めている。靖国参拝に対する日本や隣国の過激な反応も、単なる政治問題では無く、"それなり"に人間のそうした心情に立脚しているのだと思う。
火事場で自分を押し倒した上に、覆い被さって焼け死んだ人の灰に守られて生き延びた人が、生きて最初に命ぜられた(理不尽な)仕事が「自分を守って死んだその人を否定せよ」だった^1。それが戦後の日本の姿だ。生き残った私は「私の為に死んだこの死者を否定できない」と言うべきなのか、それとも「私の為に死んだにせよ、死者の悪業は糾弾されなければならない」と言うべきなのか。これが敗戦後の私達に突きつけたれた問いなのだろう。
そこにはおそらく万人が受け入れやすい正解はない。そこには悲しい事実があるだけだからだ。正解がないままに、ある人々は「死者を礼讃する」道を選び、ある人々は「死者を糾弾する」道を選んだ。しかし、その主張のどちらもが、私達の「敗戦国問題」を解決に導いてくれなかった事実は認めなければならない。いや、近年は礼讃を是とし、それこそ答えだとする人々が増えて来た気もする。しかし、そのような戦死者礼讃の傾向が、再び国家を新たな戦争や武力行使に向かわせるのではないかという懸念は間違いなく成立する。では我々はどうしたらよいのか。尊い犠牲の上に今日の平和があると礼讃するでもなし、過去の汚点として他者としての戦死者を糾弾し諸外国に永久に謝罪し続けるでもない。それらは両者とも自らの汚点に目をつぶっている。その意味では平和記念公園と靖国神社も同じ問題を抱えている。誤解を恐れず言えば、ただ、ありのままの汚れた死としての戦死者を受け入れなければならないのではないか。そのようなまっすぐな認識を持って始めて、諸外国に与えた多くの犠牲者に対しての立ち位置を確保することが出来るのではないだろうか。
◇以上の3つの議論は、具体的行動というよりは、その前段階における再認識の薦めである。メンタルには根源的であると思われる一方、どこか遠く、実際は日々の生活のなかでその問題意識を実感しにくいことも事実。しかし、これらの問いに直面した時、当惑することも確かなのである。そして、これらの問いは、国民一人一人というよりも、直接には政治家や、あーだこーだ言う評論家にこそ突きつけられるべきで、我々一般国民はそれらの人々の言動の裏にあるこの心理的な問題を、冷静に理解し、受け止め、判断するために、上記の事に気がつくことが必要ではないだろうか。
もちろん、こんな小難しいことを自己分析などせずとも、「今までは幼稚だった」と一言で切り捨て、とにかく自立するということは、既に可能な時代に突入しつつあるのだなとも感じる。青山さんは、自立した国民であろうとすることは、「幼年国家としての自覚を、国民合意に基づく思想としてもつことでもある。」と述べている^2。
■真の民主国家について
日本が民主国家とは笑わせる話で、低い投票率と低い政治への関心。今の日本国民に、国民が国を決めて動かしているという自覚がある人がどれだけいるだろうか。
・利他主義と集団帰属意識
ヒトを含むあらゆる社会性動物は、様々なレベルの集団を形成するが、社会生物学ではいわゆる「利他行動」と呼ばれる行為の結果として集団(集団帰属意識)が生じるていると説明される。もっとも身近な例は家族や親族に対する利他行動である。
ヒトの凄いところは、明らかに血縁関係は遠いのに、自分となんらかの些細な共通項を見つけるだけで、仲間意識を作り出してしまうという意識の延長技をやってのける驚異的な行動の幅の広さを持ち合わせていることだ。それは空間的・時間的距離さえ簡単に超えられる。はっきりとは証明されていないが、おそらくこの驚愕の事実を説明出来る唯一の手段は、身体的特徴に限らず、文化や習慣の一番元となっている、実在はするが少し抽象的な概念(身体的特徴や性質を発現する遺伝子セットとしてのジーン、または文化伝播の単位ミーム)の淘汰に注目することである。つまり、相手とのなんらかの共通の特徴を発見した場合、その特徴を出来るだけ広める、またはもしその特徴の存続が脅威にさらされているのであれば守ろうとする行動が、進化遺伝学的に安定に存在しうるということである。もし、一個体の利益よりも、同じ特徴をもつ個体全体の為に行動をしたほうが、その特徴の存続にとって有利な状況に置かれた場合、単独では考えられないような利他的な行動を起こすことが理論上可能である。
ここで、注意して欲しいのは、生物学が理解出来るのは、人間の行動の幅の限界のみであって、行動のレパートリーの限界を規定することは出来ないということである。我々が、この苦難に満ちた状況で自立して生きるという、かつてない選択をするということは、この行動レパートリーの限界へのあくなき挑戦なのである。
・社会生物学からみた国とナショナリズム
「国」の概念は、おそらく人間の社会性動物としてのこの側面が過去最大規模に近い形で発現した例だろう(おそらく宇宙人が侵略してきたら、世界規模になるだろう)。しかし、その共通の特徴というものは、個々の国で様々で、民族としての血統であったり、言語や宗教、生活習慣といった文化であったり、単に定められた地域に住んでいることだけだったりもする。日本の場合はどうだろうか。狭い国土で長い年月あまり多くの外国人を受け入れてこなかった日本は、上に挙げたすべての項目において共通項を見出すことが出来る、数少ない国なのではないだろうか。それがもしかしたら、トインビーらが指摘した日本の特異性を生み出した根源だったのかもしれない。外的な脅威なく安定した閉じた空間のなかで長期間生きていると、国内での多様化が進み(その意味で文化は華開くのだが)、国内の共通項への関心は低下し、個人主義に徐々に移行していく。しかし、国単位での脅威が存在するということを潜在意識が認識すると、俄然国レベルの文化の共通項などを意識しはじめ、様々な形のナショナリズムが台頭してくる。幕末に様々なレベル・形で現れた尊王攘夷論の多形化現象が良い例だろう。それは別の側面では、危険な変化の始まりでもあり、人類は決まって同様の変化に併せて軍備を増強させ、戦争に走ってきた。
ここまでで私が言いたかったことは、現在の日本国民の国に対する主体性の無さは、精神的に主体を破壊されてきたのに加えて、脅威の存在から長期間目をそむけて来たことによる当然の帰結だということである。自立する必然性が存在していない。一方で、今また日本の人々がそのような脅威を感じつつあるということだ。
・現代において
冷戦時代のアメリカの庇護による安定の時代は過ぎた。北朝鮮によるテロ攻撃や核の脅威、今まで安全を保障してくれていたはずのアメリカにとっても、冷戦時代の時ほど日本を守るメリットはなくなってきてしまった。持論を併せさせて頂けば、石油供給能力の懸念と中国の台頭、アメリカの覇権主義との世界の対立などから、21世紀の世界構造は大きく変わっていくだろう→ピークオイルコミュ参照(オイ。
日本の自立を語る上で、アメリカの存在をはずすわけにはいかない。例えばこういう意見が存在する。日米安保を破棄し、在日米軍を追い出し、米ドルの下での円を脱却してこそ、真の日本の自立が成り立つ、云々。これはこれで一つの真実だろう。あとは食料とエネルギーなどの資源をちゃんと確保できれば、理想的な自立国家が誕生する。しかし、これらの意見に対して私の立場は明確だ。現在も(ある程度限定的な)将来も、日米の現体制は日本にとって非常に重要だという事である。我々に必要なのは、そういう状況を主体的に選び直すことなのではないか。それが、真に現実に即した自立ではないか。
また、近年日本の自立をうたう人々の中でよく見受けられるのが、「日本の文化や伝統と誇りを取り戻せ」的な主張である(例えば、JCの「真の自立国家シナリオ」周辺などhttp://
もう一つ。制度的な民主国家にどっぷりはまってしまうと、その国は群集心理に右往左往する国家ということになってしまう。必ずしも国民の群集心理が良い結果をもたらすとは限らない。特に混乱時には、群集心理こそ危険の種になる。そのためにも、混乱の前に、冷静に国民を導き、冷静な国家決断を下せる人物を見極められる国民にならなければならないのではないか。
故意に弱体化されたメンタリティの中で、国家としての主体性を失い、これから激動の世界に翻弄されていくのを黙ってみているよりは、危険(軍国化を望むナショナリズムや差別的民族主義の発生等)を伴うとしても、それを取り除きながらも、国民からボトムアップ的に主体性を獲得し、自らの頭で考え、自らの手で国民と祖国の運命を決するという困難な道のりへの覚悟を今決めることが、「私」たちを守り、そうした生き方が日本人の誇りや美意識に適っているのだと信じる。青山さんの言葉を借りれば、「自ら引き受けて、おのれ自身で生きる。自分でものを考え、行動する国民になる」という事である^2。
まとめると、世界の現実と未来、日本の直視しがたい歴史と現在のメンタリティの弱さを正面から見つめ、憲法改正、天皇の扱い、戦死者の扱いなどを通じて、日本人一人一人がこの国を自ら主体的に作っているという意識で、国に関与するようになったとき、日本は真の意味で自立したと言えるのではないか。
ありがとうございました。みなさんの考えるきっかけとなれれば幸いです。
主に参考にさせて頂いた書籍
1:「敗戦後論」加藤典洋 「群像」95年1月号
2:「日本国民が決断する日」青山繁晴 扶桑社 2004年
3:「日本人としてこれだけは知っておきたいこと」中西輝政
PHP
新書 2006年
特に、「ねじれ」のアイディアは1に多くを負っている。3はたまたま最近読んだ。
|
|
|
|
コメント(42)
Mizoさん、るるーさん、コメントありがとうございます。
やや自己完結的なトピック頭文となってしまったので、書き込み辛いかもしれませんが、私の問いと無関係でもよいので、「深淡生」メンバーの方々の率直な意見が伺えればと存じます。
Mizoさんがおっしゃるように、問題の幅が広すぎて発散しそうですが、議論というより様々な人の様々な思いを共有することが大切ではないでしょうか。勇気ある?書き込みを歓迎致します。
ちなみに憲法改正の是非アンケートの結果
livedoorニュース
賛成 (56.76%)
反対 (43.23%)
http://news.livedoor.com/webapp/issue/list?issue_id=140
The Commons(12/12時点)
必要 295人
不必要 271人
http://www.the-commons.jp/
反対(不必要)派も結構いるんですね。
反対と不必要とは若干違う気もしますが。
この数字、どう見るか。
ちなみに、この「ざ・こもんず」は、会員制の一風変わったシステムのブログサイトです。執筆者の顔ぶれはなかなか強力で、楽しめます。リック・タナカ氏の「南十字星通信」が私のお勧めです。
やや自己完結的なトピック頭文となってしまったので、書き込み辛いかもしれませんが、私の問いと無関係でもよいので、「深淡生」メンバーの方々の率直な意見が伺えればと存じます。
Mizoさんがおっしゃるように、問題の幅が広すぎて発散しそうですが、議論というより様々な人の様々な思いを共有することが大切ではないでしょうか。勇気ある?書き込みを歓迎致します。
ちなみに憲法改正の是非アンケートの結果
livedoorニュース
賛成 (56.76%)
反対 (43.23%)
http://news.livedoor.com/webapp/issue/list?issue_id=140
The Commons(12/12時点)
必要 295人
不必要 271人
http://www.the-commons.jp/
反対(不必要)派も結構いるんですね。
反対と不必要とは若干違う気もしますが。
この数字、どう見るか。
ちなみに、この「ざ・こもんず」は、会員制の一風変わったシステムのブログサイトです。執筆者の顔ぶれはなかなか強力で、楽しめます。リック・タナカ氏の「南十字星通信」が私のお勧めです。
1994年、日本嫌いで有名な親中家(元)クリントン大統領は、中国政府の強い要望を聞き入れる形で、それまで$1=5.72人民元であったレートを$1=8.72人民元に、大幅に切り下げた。その(元)クリントン大統領による日本の対立軸としての中国政策により、切り下げられた当時の人民元は現在2%程度の切り上げこそされたが、相変わらず低いレートのままだ。
その安い人民元を盾に、貿易上極めて優位に立ち続けている中国の経済発展が今のままのペースですすむと、五年後には倍の国力をもつだろうと分析する研究機関がある。20年後には四倍に膨れ上がるとその研究機関は試算する。つまり、五年後に今の中国と同じものがもう一つこの地球上に誕生するという事だ。
国家の自立とは、単に軍事的防衛だけを意味するものではない。
国民の生命と財産を保全することが国家の大きな命題ならば、肥大化してゆく隣国の国家戦略に見合う自国の自主的国家政策も必須だろう。
安全保障の全てをアメリカに頼り、エネルギーの安定供給も安全保障の一つと安易に考えている我が国、日本。国家の自立とは、このアメリカ依存型の安全保障の有効性の見直しから始めるべきでは無いだろうか。
おそらく日本の尖閣領有権に関する問題が、中国との小競り合いに発展した場合、日米安全保障条約はおそらく無効だろうと思う。日本の肩を持ったところで、アメリカの国益になんらリンクするものは無いからだ。
集団的自衛権を云々する前に、私たちは台湾ほどとは言わないが、自国を自力できっちりプロテクトできる体制を早急に整えるべきだと思う。
アメリカ軍の基地は要らないというなら、自前の軍隊を持つ気概があってその主張すべきだろう。自国防衛まで拒否するのなら、そのような国は国の体をなしえない。
防衛庁が防衛省に昇格するのはいいが、むしろ国防省ときっぱり本流の名を名乗ったら良いのにと私は思う。
その上で、既に動き始めているエネルギー問題にも、日本はいい加減、覚醒すべきだろうと思う。非民主国家を中心に、今なりふりかまわぬ中国の石油買いあさりが始まっている。それは、かつて米国の裏庭と呼ばれていたエリアにまで及んでいるようだ。
五年後、中国がもう一つ出来ると予想されるようなエネルギーの爆発的需要が起これば、確実に米中間には軋轢が生じるだろうと思う。冷戦時代と同じように、いつまでもアメリカが日本を守ってくれるなどという甘い夢から、そろそろ覚めるべき時期が来ているのではないかと私は思う。
その安い人民元を盾に、貿易上極めて優位に立ち続けている中国の経済発展が今のままのペースですすむと、五年後には倍の国力をもつだろうと分析する研究機関がある。20年後には四倍に膨れ上がるとその研究機関は試算する。つまり、五年後に今の中国と同じものがもう一つこの地球上に誕生するという事だ。
国家の自立とは、単に軍事的防衛だけを意味するものではない。
国民の生命と財産を保全することが国家の大きな命題ならば、肥大化してゆく隣国の国家戦略に見合う自国の自主的国家政策も必須だろう。
安全保障の全てをアメリカに頼り、エネルギーの安定供給も安全保障の一つと安易に考えている我が国、日本。国家の自立とは、このアメリカ依存型の安全保障の有効性の見直しから始めるべきでは無いだろうか。
おそらく日本の尖閣領有権に関する問題が、中国との小競り合いに発展した場合、日米安全保障条約はおそらく無効だろうと思う。日本の肩を持ったところで、アメリカの国益になんらリンクするものは無いからだ。
集団的自衛権を云々する前に、私たちは台湾ほどとは言わないが、自国を自力できっちりプロテクトできる体制を早急に整えるべきだと思う。
アメリカ軍の基地は要らないというなら、自前の軍隊を持つ気概があってその主張すべきだろう。自国防衛まで拒否するのなら、そのような国は国の体をなしえない。
防衛庁が防衛省に昇格するのはいいが、むしろ国防省ときっぱり本流の名を名乗ったら良いのにと私は思う。
その上で、既に動き始めているエネルギー問題にも、日本はいい加減、覚醒すべきだろうと思う。非民主国家を中心に、今なりふりかまわぬ中国の石油買いあさりが始まっている。それは、かつて米国の裏庭と呼ばれていたエリアにまで及んでいるようだ。
五年後、中国がもう一つ出来ると予想されるようなエネルギーの爆発的需要が起これば、確実に米中間には軋轢が生じるだろうと思う。冷戦時代と同じように、いつまでもアメリカが日本を守ってくれるなどという甘い夢から、そろそろ覚めるべき時期が来ているのではないかと私は思う。
ぬりさんの論文を大きな関心を持って読みました。
私は先日、偶然ぬりさんの問題提起にある「ねじれ」のテーマに合致するような本を読みました。
「内なる敵をのりこえて、戦う日本へ」特定失踪者問題調査会代表の荒木和博さんの最新刊です。
「歴史を繋ぐ」という章の中に、戦前は暗黒の社会だが戦後は良い社会になったとの歴史の断絶が日本人が自らの歴史を客観的に評価できなくさせている、という記述があります。
ぬりさんの世代はどうかわかりませんが、私の中にも、他国やそれに乗じて自国の中からも突きつけられる歴史の問題について、自分が受けた学校での教育やこれまで読んだ本テレビからの知識を総動員すると、その執拗さに辟易しながらも、感情的に反応し思考停止になりがちです。そうした「ねじれ」を解釈しなおすためにも、このトピには期待大です。
国家としての自立を考えるためにも、ここがしっかりしていないと難しいと思います。
軍事力を放棄した現行憲法は欺瞞でしかなく、早く改正して自衛隊を現実に即したものにしてほしいと思います。
それとセットして考えていきたいのは、交戦によって失われる命です。国防のために命を落とす事もあるでしょう、そうした方たちに対しては、国・国民からの充分な感謝の気持ち(他の表現が思いつきませんが)が向けられるべきだと思います。
過去の戦争においても、です。その点、ぬりさんとは少し考えが違うかもしれません。
決して、戦争や軍国主義礼讃とイコールで結ばれるものではないと思うのです。
ぬりさんの包容力に誘われて、思考途中のままお邪魔しました^^
私は先日、偶然ぬりさんの問題提起にある「ねじれ」のテーマに合致するような本を読みました。
「内なる敵をのりこえて、戦う日本へ」特定失踪者問題調査会代表の荒木和博さんの最新刊です。
「歴史を繋ぐ」という章の中に、戦前は暗黒の社会だが戦後は良い社会になったとの歴史の断絶が日本人が自らの歴史を客観的に評価できなくさせている、という記述があります。
ぬりさんの世代はどうかわかりませんが、私の中にも、他国やそれに乗じて自国の中からも突きつけられる歴史の問題について、自分が受けた学校での教育やこれまで読んだ本テレビからの知識を総動員すると、その執拗さに辟易しながらも、感情的に反応し思考停止になりがちです。そうした「ねじれ」を解釈しなおすためにも、このトピには期待大です。
国家としての自立を考えるためにも、ここがしっかりしていないと難しいと思います。
軍事力を放棄した現行憲法は欺瞞でしかなく、早く改正して自衛隊を現実に即したものにしてほしいと思います。
それとセットして考えていきたいのは、交戦によって失われる命です。国防のために命を落とす事もあるでしょう、そうした方たちに対しては、国・国民からの充分な感謝の気持ち(他の表現が思いつきませんが)が向けられるべきだと思います。
過去の戦争においても、です。その点、ぬりさんとは少し考えが違うかもしれません。
決して、戦争や軍国主義礼讃とイコールで結ばれるものではないと思うのです。
ぬりさんの包容力に誘われて、思考途中のままお邪魔しました^^
国の自立に関連して
私は、開戦前からイラク戦争反対の立場で、イラク戦争はアメリカによる石油目当ての戦争だとしか思っていませんし、当時から、戦争になれば泥沼化は必然だと、日本茶掲示板に投稿しましたが、
しかし、中国の核兵器や北朝鮮のミサイルおよび核開発など日本の周囲の状況を考えた場合、自前の核の傘を持たずアメリカの核の傘に頼っている以上、日本は、アメリカによるイラク戦争を支持せざるを得ない立場だったとも思っています。
もし、当時の時点で、日本に自前の核の傘が有った場合、積極的に戦争を支持する必要は無かったかも知れないことを考えると、今のイラク戦争の泥沼化(犠牲者の増大)を見る時、残念に思えます。
当時、日本の支持が無ければ、多少なりとも、それがアメリカへのブレーキとなったかも知れないからです。
私は、開戦前からイラク戦争反対の立場で、イラク戦争はアメリカによる石油目当ての戦争だとしか思っていませんし、当時から、戦争になれば泥沼化は必然だと、日本茶掲示板に投稿しましたが、
しかし、中国の核兵器や北朝鮮のミサイルおよび核開発など日本の周囲の状況を考えた場合、自前の核の傘を持たずアメリカの核の傘に頼っている以上、日本は、アメリカによるイラク戦争を支持せざるを得ない立場だったとも思っています。
もし、当時の時点で、日本に自前の核の傘が有った場合、積極的に戦争を支持する必要は無かったかも知れないことを考えると、今のイラク戦争の泥沼化(犠牲者の増大)を見る時、残念に思えます。
当時、日本の支持が無ければ、多少なりとも、それがアメリカへのブレーキとなったかも知れないからです。
佐々木先生
お久しぶりです。
なるほど。日本が核を持った上のイラク戦争不支持が国連も無視したアメリカのブレーキとなり得たかどうかは解りませんが(フランスには止められなかったし、イギリスは結局追従を選んだし)、可能性はあったと思いますし、少なくとも核保有をしていたら政治的主体性はもう少し保てたかもしれませんね。
でも、イラク戦争を防ぐためにも日本は核を持つべきだっただなんて正当化はちょっと・・・。持つとしても日本は日本の為に持つべきだと思いますよ。やはり、戦争をやると決めたアメリカが是非を問われればいいわけで、戦争を止めるのは軍事力が必然ではなくて、究極には理性だけだと思います。
なんて話をしだすと、どこぞのトピックみたいになってしまいますね。これくらいに抑えときます・・・。これも抑止力?
お久しぶりです。
なるほど。日本が核を持った上のイラク戦争不支持が国連も無視したアメリカのブレーキとなり得たかどうかは解りませんが(フランスには止められなかったし、イギリスは結局追従を選んだし)、可能性はあったと思いますし、少なくとも核保有をしていたら政治的主体性はもう少し保てたかもしれませんね。
でも、イラク戦争を防ぐためにも日本は核を持つべきだっただなんて正当化はちょっと・・・。持つとしても日本は日本の為に持つべきだと思いますよ。やはり、戦争をやると決めたアメリカが是非を問われればいいわけで、戦争を止めるのは軍事力が必然ではなくて、究極には理性だけだと思います。
なんて話をしだすと、どこぞのトピックみたいになってしまいますね。これくらいに抑えときます・・・。これも抑止力?
>13
ですよね。そうだとは思っていましたが他の方に誤解されたらやだなと思いまして。失礼しました。
>14
ちょうど最近ぱらぱらと・・・。例のトピックの影響ですねw。
政治と軍事は不可分ではありますが、軍事を下位手段として捉えるかどうかなどの考え方は、時代や国によって様々であったと思います。例えば、軍事力を政治とはっきり区別して、政治解決が失敗した後はじめて武力行使がはじまり、武力行使の目的は「勝利」であり、政治解決は「平和」だとする二分的な考え方は、ケネディ政権以前のアメリカの伝統的な戦争観です。
おそらく、今のネオコンと呼ばれる人たちの源流が、武力行使を外交手段の一つとして捉える(ネオ・クラウゼヴィッツ主義)方向に変えていった。
彼の「戦略論」は近代戦術の古典ですので、思考の土台としては重要だとは思います。レーニンや80年代のアメリカはかなりクラウゼヴィッツ好きでしたし、現在の中国も「政治と軍事の継続性」という点ではそうとも言われています。
ただ、クラウゼヴィッツが生きた時代(1780年7月1日or6月1日-1831年11月16日)は、国家総力戦という近代戦争が始まった時代で、「戦略論」は主にそのようなケースにおいての考察です。現代のように、国民不在の戦争ではありません。また、彼は当然核兵器のような大量破壊兵器の存在は知りませんし、ましてや不安による均衡(核抑止)などという状況は全く想定していません。当然のことです。
軍事力を外交手段として捉えるということは、軍事力の脱人格化、楽観的肯定に繋がりがちです。クラウゼヴィッツの時代とは違い、比べ物にならない程過剰な破壊能力が存在する現代において、軍事力の脱人格化による大量殺戮に対する倫理観の欠如は、現代にこの考え方を適用する事の危険な側面のひとつでもあると思います。
もっとも、クラウゼヴィッツはその「戦略論」の中の特定のケースにおいて、「政治と軍事の継続」の考え方を主張していて、それが戦争の本質だとは言っていませんし、私は戦略史に興味があるわけではないので、彼の真意がどうだったか、正しいか間違っているか、現在に適用できるかどうか、などはどうでもよいです。ただ、本質的な思考の出来る凄い方だったんだなと思っています。
クラウゼヴィッツの是非はともかく、数多ある戦略論のうちどの考え方を採用するのかは、その時代の政府であり国民なのだと思っています。戦略に正解などありませんから。
我々は、何を選択することになるのでしょうね。
ですよね。そうだとは思っていましたが他の方に誤解されたらやだなと思いまして。失礼しました。
>14
ちょうど最近ぱらぱらと・・・。例のトピックの影響ですねw。
政治と軍事は不可分ではありますが、軍事を下位手段として捉えるかどうかなどの考え方は、時代や国によって様々であったと思います。例えば、軍事力を政治とはっきり区別して、政治解決が失敗した後はじめて武力行使がはじまり、武力行使の目的は「勝利」であり、政治解決は「平和」だとする二分的な考え方は、ケネディ政権以前のアメリカの伝統的な戦争観です。
おそらく、今のネオコンと呼ばれる人たちの源流が、武力行使を外交手段の一つとして捉える(ネオ・クラウゼヴィッツ主義)方向に変えていった。
彼の「戦略論」は近代戦術の古典ですので、思考の土台としては重要だとは思います。レーニンや80年代のアメリカはかなりクラウゼヴィッツ好きでしたし、現在の中国も「政治と軍事の継続性」という点ではそうとも言われています。
ただ、クラウゼヴィッツが生きた時代(1780年7月1日or6月1日-1831年11月16日)は、国家総力戦という近代戦争が始まった時代で、「戦略論」は主にそのようなケースにおいての考察です。現代のように、国民不在の戦争ではありません。また、彼は当然核兵器のような大量破壊兵器の存在は知りませんし、ましてや不安による均衡(核抑止)などという状況は全く想定していません。当然のことです。
軍事力を外交手段として捉えるということは、軍事力の脱人格化、楽観的肯定に繋がりがちです。クラウゼヴィッツの時代とは違い、比べ物にならない程過剰な破壊能力が存在する現代において、軍事力の脱人格化による大量殺戮に対する倫理観の欠如は、現代にこの考え方を適用する事の危険な側面のひとつでもあると思います。
もっとも、クラウゼヴィッツはその「戦略論」の中の特定のケースにおいて、「政治と軍事の継続」の考え方を主張していて、それが戦争の本質だとは言っていませんし、私は戦略史に興味があるわけではないので、彼の真意がどうだったか、正しいか間違っているか、現在に適用できるかどうか、などはどうでもよいです。ただ、本質的な思考の出来る凄い方だったんだなと思っています。
クラウゼヴィッツの是非はともかく、数多ある戦略論のうちどの考え方を採用するのかは、その時代の政府であり国民なのだと思っています。戦略に正解などありませんから。
我々は、何を選択することになるのでしょうね。
>我々は、何を選択することになるのでしょうね。
反日よありがとう。
あなたたちのおかげで、私立ちはやっと半分だけ正常なナショナリズムに目覚めることが出来ました。完全覚醒まで、あと半分です。
というのが、不愉快な面々に対する本音でしょうか。
問題を何処に置くかで選択するものも違ってきますが、私はアメリカを再び選択する、自立する民主国家を選択するものであってほしいと思います。
中国の破綻を予測する論調もありますから、中国の10%/yearの成長がこのまま5年も継続する訳はないかなという予感もします。
非道な政治体制をとるところに不思議と埋蔵されている石油を、倫理も正義も無視し狡猾な方法で買い漁る輩には、国際非難が経済制裁という形で必ずや下ると思います。
>私の危機意識の根拠とがっちりばっちり一致してますw。
当然ですよ、啓蒙されましたからwww
わが国は、国連神話からも目覚める必要がありますね。
反日よありがとう。
あなたたちのおかげで、私立ちはやっと半分だけ正常なナショナリズムに目覚めることが出来ました。完全覚醒まで、あと半分です。
というのが、不愉快な面々に対する本音でしょうか。
問題を何処に置くかで選択するものも違ってきますが、私はアメリカを再び選択する、自立する民主国家を選択するものであってほしいと思います。
中国の破綻を予測する論調もありますから、中国の10%/yearの成長がこのまま5年も継続する訳はないかなという予感もします。
非道な政治体制をとるところに不思議と埋蔵されている石油を、倫理も正義も無視し狡猾な方法で買い漁る輩には、国際非難が経済制裁という形で必ずや下ると思います。
>私の危機意識の根拠とがっちりばっちり一致してますw。
当然ですよ、啓蒙されましたからwww
わが国は、国連神話からも目覚める必要がありますね。
こーちゃんさん
お久しぶりです。こーちゃんさんに、「感服した」だなんていわれてしまっては、ついうれしくなってしまいます。
戦前を否定しては、国家の自立は無いだろうとの見識は、ストレートには私の思いも同意します。ただ、逆にストレートに肯定することもまた、少し違うのかなとも思っています。現に、負けたわけですから、100%正しかった負けとは誰もいえないのではないでしょうか。その辺りをすなおに事実として受け止めた方が良いのではないかというのが、私の主張です。肯定か否定かでは決められないものを受け入れるという価値観が必要な気がしています。
るるーさん
中国経済が、このまま順調路線を貫けない可能性は十分あると思います。もし、成長が終わりを告げるとしても、今度はその終わり方も重要で、単に民主化が進むことになったとしても、反日教育を根っからうけている中国国民の民主政権は、やはり反日色むき出しで、今の中共よりもタチが悪くなるかもしれないという予測もされています。結局どうころんでもだめなのか・・・。わかりませんが。
啓蒙したなんて、とんでもないです。
国連の存在はメリットもあると思いますが、現実的な機能に対して、真摯に受け止めなければならないと思います。
お久しぶりです。こーちゃんさんに、「感服した」だなんていわれてしまっては、ついうれしくなってしまいます。
戦前を否定しては、国家の自立は無いだろうとの見識は、ストレートには私の思いも同意します。ただ、逆にストレートに肯定することもまた、少し違うのかなとも思っています。現に、負けたわけですから、100%正しかった負けとは誰もいえないのではないでしょうか。その辺りをすなおに事実として受け止めた方が良いのではないかというのが、私の主張です。肯定か否定かでは決められないものを受け入れるという価値観が必要な気がしています。
るるーさん
中国経済が、このまま順調路線を貫けない可能性は十分あると思います。もし、成長が終わりを告げるとしても、今度はその終わり方も重要で、単に民主化が進むことになったとしても、反日教育を根っからうけている中国国民の民主政権は、やはり反日色むき出しで、今の中共よりもタチが悪くなるかもしれないという予測もされています。結局どうころんでもだめなのか・・・。わかりませんが。
啓蒙したなんて、とんでもないです。
国連の存在はメリットもあると思いますが、現実的な機能に対して、真摯に受け止めなければならないと思います。
こんばんわ。
負けた戦さに「反省」は必要でしょうね。
(今度は上手くやるぞ!…と)
ただ負けたからといって「否定」したら続かないと思います。
実戦争に限らず戦いは続く訳ですから…。
戦争に100%正しい・間違いはあり得えないと思います。
これは素直に受け止めるとかの問題ではなく、もっと冷厳に検証されるべきものでしょう。
自立していない国家が、もし自立を目指すという力技を得るとしたら、「薄っぺらい論理」こそが必要かもしれません。
あまり複雑に考えてしまうと堂々巡りが始まってしまい、「思索の森」から抜け出す事が出来ず、立ち上がる為の筋肉が衰えてしまうかもしれません。
肉体(脳も含む)が衰えてしまい、薄っぺらい思索しか出来なくなった初老の戯言と笑って下さい。
負けた戦さに「反省」は必要でしょうね。
(今度は上手くやるぞ!…と)
ただ負けたからといって「否定」したら続かないと思います。
実戦争に限らず戦いは続く訳ですから…。
戦争に100%正しい・間違いはあり得えないと思います。
これは素直に受け止めるとかの問題ではなく、もっと冷厳に検証されるべきものでしょう。
自立していない国家が、もし自立を目指すという力技を得るとしたら、「薄っぺらい論理」こそが必要かもしれません。
あまり複雑に考えてしまうと堂々巡りが始まってしまい、「思索の森」から抜け出す事が出来ず、立ち上がる為の筋肉が衰えてしまうかもしれません。
肉体(脳も含む)が衰えてしまい、薄っぺらい思索しか出来なくなった初老の戯言と笑って下さい。
最近はもっぱら読み手側に回っています。
すいません(笑)
テーマと考える範囲が大きいので何書いていいのかよくわかりませんが、基本思ってることを書きます。
暴論ですが、1部直接民主制を導入してみる。今のところ憲法改正に国民投票が必要ですが、衆議院と参議院で意見が分かれたときや重要法案に国民投票を導入してみてはどうなんだろうかと思っています。
国民に国の未来に対する責任を持たせればと思っています。
今の日本人に欠けているのは当事者意識の欠如ではないか。政治に興味がないのは間接民主制にあるのではないかと思っています。
もちろん導入しても、失敗するでしょう。マスコミの世論誘導があるかもしれない。国民一人ひとりがいろんなことを考えなければいけないし。おそらくいろんなことで道を誤るかもしれません。しかし、失敗し続けた結果、そう遠くない未来において自立した日本が新しい日本人によって作られるのではないかと思っています。
もしそのまま日本人が間違い続ければ、それは日本人に力がなかったということだと思います。
何をもって間違いかというのは難しいところですが。
なかなか変わらないこの国で、日本国民を変革させるにはこのくらいやらなきゃいけないのかなと思います。
まあ、クーデターとかはあんまり好きではないですし(笑)
無理を承知で書いてみました。
あんまりまとまってないし、空想に近いですけどね。
すいません(笑)
テーマと考える範囲が大きいので何書いていいのかよくわかりませんが、基本思ってることを書きます。
暴論ですが、1部直接民主制を導入してみる。今のところ憲法改正に国民投票が必要ですが、衆議院と参議院で意見が分かれたときや重要法案に国民投票を導入してみてはどうなんだろうかと思っています。
国民に国の未来に対する責任を持たせればと思っています。
今の日本人に欠けているのは当事者意識の欠如ではないか。政治に興味がないのは間接民主制にあるのではないかと思っています。
もちろん導入しても、失敗するでしょう。マスコミの世論誘導があるかもしれない。国民一人ひとりがいろんなことを考えなければいけないし。おそらくいろんなことで道を誤るかもしれません。しかし、失敗し続けた結果、そう遠くない未来において自立した日本が新しい日本人によって作られるのではないかと思っています。
もしそのまま日本人が間違い続ければ、それは日本人に力がなかったということだと思います。
何をもって間違いかというのは難しいところですが。
なかなか変わらないこの国で、日本国民を変革させるにはこのくらいやらなきゃいけないのかなと思います。
まあ、クーデターとかはあんまり好きではないですし(笑)
無理を承知で書いてみました。
あんまりまとまってないし、空想に近いですけどね。
期待通り、十人十色の反応が出てきていてとてもうれしいです。マグさんのおっしゃる通り、テーマが大きいので、議論も結論を出すこともこの場においては不可能だと思う方が普通ですよね。こうして、色んな方のそれぞれの思いをたくさん伺うことが出来れば、このトピックの意味もあるかと思います。
こーちゃんさん
>素直に受け止めるとかの問題ではなく、もっと冷厳に検証されるべきものでしょう。
>自立していない国家が、もし自立を目指すという力技を得るとしたら、「薄っぺらい論理」こそが必要かもしれません。
あるがままを受け止めたいという態度は、私個人の人生観でもあるので、一般に広くそれが必要なのかどうかという事は自信がないです。こーちゃんさんのおっしゃる通りなのかもしれません。
ルンルリーさん
コメントありがとうございます。私も昭和天皇を責めることは出来ないと思っています。苦しくも実に誠実な生き方を全うされたのだと思っていますし、そう思っている日本人も多いのではないでしょうか。それが大岡の「おいたわしい」という言葉にも表れている気がします。だからこそ、「心からの敬愛に立ち、責任を追及する信奉者」を抑圧してしまった社会に問題を投げかけたいなと。
KABUさん(の旦那)
私は国家論を表芸としていないからこそ、勝手な事が言えたんだと思います。自分の専門となると、どうしてももっと慎重にならざるを得ませんよね。それでもコメントしてくださって感謝です。そしてナイス画像。
>責任を明確に取らないというのも、一つの(明確な)責任の取り方ではないでしょうか。
そういうのもありかなー、というか良いか悪いか抜きにしてそれこそ日本的?ルンルリーさんへのコメントでも書きましたが、責任を取るべきだというのが私の主張ではなく、責任をとるべき人がとっていない(という責任の取り方をしてる?)ということを、もっと多くの人が認識した方がよいのではないかという提言なわけです。
佐々木先生
では私は、
刃に心と書いて「忍」と書く。正義ある力とは、裏付けのある謙虚な忍ぶ姿勢である。(今思いつき)
戈(ほこ)が止むと書いて「武」と書く。居合の達人伯耆守(ほうきのかみ)が理想とした武の姿、平和への願い。(私は伯耆流やってました)
燕堂 -tsubamedow-さん
はじめまして。食料自給率は一言しか書いてなかったはずですが、そこに食いついて来ましたか!!確かに重要ですね。生産を増やすこともですが、廃棄率が5割ぐらいあるみたいなので、もっと食材を大切にしたいですね。外食産業の功罪でしょうか。実際現在の人口で自給はどれほど可能なんでしょうね。
マグさん
ご無沙汰しています。空想なのかもしれませんが、気持ちはすごくよく分かります。やはり国に対する責任感の欠如というか。それを変えるためのシステム作りを考えねばならないと思う気持ちは同じ気がします。どうすれば、現実的にうまくいくんだろう。
こーちゃんさん
>素直に受け止めるとかの問題ではなく、もっと冷厳に検証されるべきものでしょう。
>自立していない国家が、もし自立を目指すという力技を得るとしたら、「薄っぺらい論理」こそが必要かもしれません。
あるがままを受け止めたいという態度は、私個人の人生観でもあるので、一般に広くそれが必要なのかどうかという事は自信がないです。こーちゃんさんのおっしゃる通りなのかもしれません。
ルンルリーさん
コメントありがとうございます。私も昭和天皇を責めることは出来ないと思っています。苦しくも実に誠実な生き方を全うされたのだと思っていますし、そう思っている日本人も多いのではないでしょうか。それが大岡の「おいたわしい」という言葉にも表れている気がします。だからこそ、「心からの敬愛に立ち、責任を追及する信奉者」を抑圧してしまった社会に問題を投げかけたいなと。
KABUさん(の旦那)
私は国家論を表芸としていないからこそ、勝手な事が言えたんだと思います。自分の専門となると、どうしてももっと慎重にならざるを得ませんよね。それでもコメントしてくださって感謝です。そしてナイス画像。
>責任を明確に取らないというのも、一つの(明確な)責任の取り方ではないでしょうか。
そういうのもありかなー、というか良いか悪いか抜きにしてそれこそ日本的?ルンルリーさんへのコメントでも書きましたが、責任を取るべきだというのが私の主張ではなく、責任をとるべき人がとっていない(という責任の取り方をしてる?)ということを、もっと多くの人が認識した方がよいのではないかという提言なわけです。
佐々木先生
では私は、
刃に心と書いて「忍」と書く。正義ある力とは、裏付けのある謙虚な忍ぶ姿勢である。(今思いつき)
戈(ほこ)が止むと書いて「武」と書く。居合の達人伯耆守(ほうきのかみ)が理想とした武の姿、平和への願い。(私は伯耆流やってました)
燕堂 -tsubamedow-さん
はじめまして。食料自給率は一言しか書いてなかったはずですが、そこに食いついて来ましたか!!確かに重要ですね。生産を増やすこともですが、廃棄率が5割ぐらいあるみたいなので、もっと食材を大切にしたいですね。外食産業の功罪でしょうか。実際現在の人口で自給はどれほど可能なんでしょうね。
マグさん
ご無沙汰しています。空想なのかもしれませんが、気持ちはすごくよく分かります。やはり国に対する責任感の欠如というか。それを変えるためのシステム作りを考えねばならないと思う気持ちは同じ気がします。どうすれば、現実的にうまくいくんだろう。
ぬりさん、おはようございます。このトピが立ってから何度も巻頭論文を読み直しながら考えて参りました。ただそれだけをお伝えしたくて今朝、綴っております。
「日本という国家が自立するには」日本を構成している一人一人の国民が問題意識を持ち「自律」する事が何よりも大前提となるように思えます。そうした上で、目覚めた状態で考えてゆかないと軸が定まらず焦点がぼやけてしまいそうです。
巨大なテーマなので私自身、纏まったものは何も提示できませんが(恐らく、一生提示などできないような気がしてます)自覚して考え続ける姿勢をキープすることも肝要かなと、そのように考えます。
「思考停止」或は「思考放棄」ではなく、日常を過ごすその時々に折りに触れ意識し続けて行ければこの概容がおぼろげながら見えてくるような気がします。「傍観者」ではなく「当事者」になることからスタートになるのかもしれません。
■戦死者の弔いについて
この点ですが私はやはりまず「感謝ありき」かと捉えます。
戦争を肯定するつもりは全くありませんが、本人の意志などお構いなく強制的に戦地に送り出されて赴任地においては死を賭しても全力で戦って散って行った「普通の日本人」の方の心情を慮る時、自然と沸く思いなのではないでしょうか。「礼賛」とか「崇拝」ではありません。
「日本という国家が自立するには」日本を構成している一人一人の国民が問題意識を持ち「自律」する事が何よりも大前提となるように思えます。そうした上で、目覚めた状態で考えてゆかないと軸が定まらず焦点がぼやけてしまいそうです。
巨大なテーマなので私自身、纏まったものは何も提示できませんが(恐らく、一生提示などできないような気がしてます)自覚して考え続ける姿勢をキープすることも肝要かなと、そのように考えます。
「思考停止」或は「思考放棄」ではなく、日常を過ごすその時々に折りに触れ意識し続けて行ければこの概容がおぼろげながら見えてくるような気がします。「傍観者」ではなく「当事者」になることからスタートになるのかもしれません。
■戦死者の弔いについて
この点ですが私はやはりまず「感謝ありき」かと捉えます。
戦争を肯定するつもりは全くありませんが、本人の意志などお構いなく強制的に戦地に送り出されて赴任地においては死を賭しても全力で戦って散って行った「普通の日本人」の方の心情を慮る時、自然と沸く思いなのではないでしょうか。「礼賛」とか「崇拝」ではありません。
エルゼさん。こんにちは。何度も読んでくださったそうで、恐縮です。ありがとうございます。
本当に巨大なテーマで、私なんぞが短期間にまとめた文が、答えたるはずもなく、今でも解らないことが多いです。しかし、3週間ほどの間の、このテーマを意識しながらの生活は、とてもよい経験になりました。るるーさんの機転、このコミュの存在、青山さんに感謝したい気持ちでいっぱいです。
戦死者の弔いについてですが、私の巻頭文ではただ「受け入れる」としか書いてなかったですね。ここは最も悔いの残る点の一つです。ぎいさんとのやり取りでもあった通り、「敬意」・「哀悼」・「感謝」のせめてどれか一つを入れておきたかったです。書いていた時は、入れているつもりになっていました。大幅圧縮をかけたのでその時に消してしまったのかな。言い訳ですが・・・。
エルゼさんの心情に、とても共感いたします。コメントありがとうございました。
本当に巨大なテーマで、私なんぞが短期間にまとめた文が、答えたるはずもなく、今でも解らないことが多いです。しかし、3週間ほどの間の、このテーマを意識しながらの生活は、とてもよい経験になりました。るるーさんの機転、このコミュの存在、青山さんに感謝したい気持ちでいっぱいです。
戦死者の弔いについてですが、私の巻頭文ではただ「受け入れる」としか書いてなかったですね。ここは最も悔いの残る点の一つです。ぎいさんとのやり取りでもあった通り、「敬意」・「哀悼」・「感謝」のせめてどれか一つを入れておきたかったです。書いていた時は、入れているつもりになっていました。大幅圧縮をかけたのでその時に消してしまったのかな。言い訳ですが・・・。
エルゼさんの心情に、とても共感いたします。コメントありがとうございました。
国家の自立は、この青山繁晴『深淡生』コミュニティの主題とも言える本質的なテーマです。お気軽に話題に参加していただき、共に考える更なる実践の場となりますよう。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
近日立ち上がるめどが立っている分割トピ
?日本という国家が自立するには【大戦の意味から考える国家の自立 編】
開戦が意図したもの・当時の国際情勢・日本の当時の立場、など
?日本という国家が自立するには【要としての象徴天皇 編】
天皇制全般
?日本という国家が自立するには【民主国家としての対アメリカ 編】
日米安全保障・トランスフォーメイション・真の同盟国とは・米中の覇権、など
?日本という国家が自立するには【民主国家としての文化伝統 編】
美しい国・伝統・固有の文化・ナショナルアイデンティティー、など
?日本という国家が自立するには【国家とは何か 日本とは何か編】
?日本という国家が自立するには【自立とは何か 編】
?日本が自立した国家にならなければならないかという未来トピ
(???を統一トピとして一本化の予定)
?日本という国家が自立するには【食料・エネルギー 編】
?日本という国家が自立するには【情報管理・防諜体制・J−CIA 編】
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
トピ主が確定していない、分割トピック候補。
?日本という国家が自立するには【憲法成立「渡され方」 編】
憲法成立の背景・その後61年の憲法のありよう、など
?日本という国家が自立するには【憲法第九条 編】
九条関連全般。自衛権・専守防衛・先制攻撃・国連軍、など。国防全般
?日本という国家が自立するには【憲法第六五条 編】
責任の所在。内閣であるべきか、首相であるべきか、など。
?日本という国家が自立するには【天皇と戦争責任 編】
戦犯の概念・責任の所在・東京裁判・ヤルタ会議、など
?日本という国家が自立するには【戦死者の弔い 編】
硫黄島をはじめとする激戦地・靖国・慰霊全般
その他(エネルギー問題から考察する国家の自立)等、未提起のトピックも歓迎いたします。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
近日立ち上がるめどが立っている分割トピ
?日本という国家が自立するには【大戦の意味から考える国家の自立 編】
開戦が意図したもの・当時の国際情勢・日本の当時の立場、など
?日本という国家が自立するには【要としての象徴天皇 編】
天皇制全般
?日本という国家が自立するには【民主国家としての対アメリカ 編】
日米安全保障・トランスフォーメイション・真の同盟国とは・米中の覇権、など
?日本という国家が自立するには【民主国家としての文化伝統 編】
美しい国・伝統・固有の文化・ナショナルアイデンティティー、など
?日本という国家が自立するには【国家とは何か 日本とは何か編】
?日本という国家が自立するには【自立とは何か 編】
?日本が自立した国家にならなければならないかという未来トピ
(???を統一トピとして一本化の予定)
?日本という国家が自立するには【食料・エネルギー 編】
?日本という国家が自立するには【情報管理・防諜体制・J−CIA 編】
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
トピ主が確定していない、分割トピック候補。
?日本という国家が自立するには【憲法成立「渡され方」 編】
憲法成立の背景・その後61年の憲法のありよう、など
?日本という国家が自立するには【憲法第九条 編】
九条関連全般。自衛権・専守防衛・先制攻撃・国連軍、など。国防全般
?日本という国家が自立するには【憲法第六五条 編】
責任の所在。内閣であるべきか、首相であるべきか、など。
?日本という国家が自立するには【天皇と戦争責任 編】
戦犯の概念・責任の所在・東京裁判・ヤルタ会議、など
?日本という国家が自立するには【戦死者の弔い 編】
硫黄島をはじめとする激戦地・靖国・慰霊全般
その他(エネルギー問題から考察する国家の自立)等、未提起のトピックも歓迎いたします。
続々と、派生?トピックが立ってきましたね。私も幾つか担当するつもりです。
ただ、ここに少し書き残したことがあったので、書かせてください。本来ならば、まだ出ていない【戦死者の弔い 編】に書くべき事項なのかもしれませんが(自分がトピ主になれという突っ込みはなしで・・・)、意図したいことは別にあります。このメイントピックのトピ頭や、【民主国家としての文化伝統 編】でも、偏狭なナショナリズムの台頭にはかなり心配をしている私ですが、私をそこに引っ掛けている一つのくだりがあるので、とりあえずここで紹介させていただきます。追悼問題に対する問題提起というわけではなく、ナショナリズムの問題の一例としてです。
「国家が『国のために』死んだ戦死者を『追悼』しようとするとき、その国家が軍事力をもち、戦争や武力行使の可能性を予想する国家であるかぎり、そこにはつねに『尊い犠牲』、『感謝と敬意』のレトリックが作動し、『追悼』は『顕彰』になっていかざるを得ないのである。(中略)軍事力をもち、戦争や武力行使を行う可能性のある国家は、必ず戦没者を顕彰する儀礼装置をもち、それによって戦死の悲哀を名誉に換え、国家を新たな戦争や武力行使に動員していく。」
「靖国問題」P.205(ちくま新書 2005年 高橋哲哉)
高橋氏は、私が引用した加藤氏の「敗戦後論」の代表的な批評家です。この指摘が正しいのか間違っているのかは置いておいたとしても、この懸念事態は成立するような気がします。かといって、追悼施設や慰霊儀式の廃絶が解決策とも思えません。
ここでは、「正しさ」は問題ではない、というのが私の思いです。これ以上踏み込むと、必要以上に難しくなりそうなので、これくらいにしておきます。自分の表現能力・発信能力の限界を知りつつも、少しでも意図をご理解頂ければと思います。何かを伝えるというのは本当に難しいですね。
ただ、ここに少し書き残したことがあったので、書かせてください。本来ならば、まだ出ていない【戦死者の弔い 編】に書くべき事項なのかもしれませんが(自分がトピ主になれという突っ込みはなしで・・・)、意図したいことは別にあります。このメイントピックのトピ頭や、【民主国家としての文化伝統 編】でも、偏狭なナショナリズムの台頭にはかなり心配をしている私ですが、私をそこに引っ掛けている一つのくだりがあるので、とりあえずここで紹介させていただきます。追悼問題に対する問題提起というわけではなく、ナショナリズムの問題の一例としてです。
「国家が『国のために』死んだ戦死者を『追悼』しようとするとき、その国家が軍事力をもち、戦争や武力行使の可能性を予想する国家であるかぎり、そこにはつねに『尊い犠牲』、『感謝と敬意』のレトリックが作動し、『追悼』は『顕彰』になっていかざるを得ないのである。(中略)軍事力をもち、戦争や武力行使を行う可能性のある国家は、必ず戦没者を顕彰する儀礼装置をもち、それによって戦死の悲哀を名誉に換え、国家を新たな戦争や武力行使に動員していく。」
「靖国問題」P.205(ちくま新書 2005年 高橋哲哉)
高橋氏は、私が引用した加藤氏の「敗戦後論」の代表的な批評家です。この指摘が正しいのか間違っているのかは置いておいたとしても、この懸念事態は成立するような気がします。かといって、追悼施設や慰霊儀式の廃絶が解決策とも思えません。
ここでは、「正しさ」は問題ではない、というのが私の思いです。これ以上踏み込むと、必要以上に難しくなりそうなので、これくらいにしておきます。自分の表現能力・発信能力の限界を知りつつも、少しでも意図をご理解頂ければと思います。何かを伝えるというのは本当に難しいですね。
かなりお久しぶりです。
ただのぼやきなので自分のトピックに書くことにしました。
大学の友人と話していて。
彼いわく
世の中経済も文化もボーダーレスで、国家なんてものはあってないようなものだ。国家という幻想は無くなると政治家の仕事がなくなってしまうから、あたかもあるかのように政治家とマスコミが結託して必死になって吹聴しているにすぎない。
国が教科書制定に介入するのはおかしい。道徳に歴史上の美談を入れると、背後の陰の部分がカットされる。これは権力による歴史の捏造だ。
って。
似たような事を言っている人が世の中にたくさんいる事は知っていても10年来の友人に言われると、いささかショックでした。何が僕と違うのだろう。同じような道を辿ってきたのに。
彼とは実は昨年夏に、靖国の件で朝までやりあった事があったので、同じ事になりたくなくて、今回は適当に流しました。
昨夜の朝生で行われた視聴者アンケートで憲法改正反対が増えて、過半数を超えてました。理由の1番は9条。放送では護憲派はかなりやられていた気がしますが、なぜ反対が増える?
私はうどん食べたり友達と電話しながら眺めてましたが、話が枝葉末節揚げ足取りで、ああいえばこういう。〇祐がたくさん集まったらきっとあんなかんじ(笑)。
筋が通ってないとか、話が矛盾してるとか、かなりどうでもいいし。テレビなんだからもっと庶民におりた方がいいかも。
何故考えなければいけないのか、どのような国にしていきたいのか。
国民的議論というけれど、政治家がこれじゃなんか思いやられます。喧嘩だけ増えて疲れるだけになったりして。この番組はいつもこうだからこれはこれでいいのかもしれないけれど。
「もう少し慎重に」という主張はよく意味がわからない。単なる思考停止申告?
単なるぼやきでした。失礼。
ただのぼやきなので自分のトピックに書くことにしました。
大学の友人と話していて。
彼いわく
世の中経済も文化もボーダーレスで、国家なんてものはあってないようなものだ。国家という幻想は無くなると政治家の仕事がなくなってしまうから、あたかもあるかのように政治家とマスコミが結託して必死になって吹聴しているにすぎない。
国が教科書制定に介入するのはおかしい。道徳に歴史上の美談を入れると、背後の陰の部分がカットされる。これは権力による歴史の捏造だ。
って。
似たような事を言っている人が世の中にたくさんいる事は知っていても10年来の友人に言われると、いささかショックでした。何が僕と違うのだろう。同じような道を辿ってきたのに。
彼とは実は昨年夏に、靖国の件で朝までやりあった事があったので、同じ事になりたくなくて、今回は適当に流しました。
昨夜の朝生で行われた視聴者アンケートで憲法改正反対が増えて、過半数を超えてました。理由の1番は9条。放送では護憲派はかなりやられていた気がしますが、なぜ反対が増える?
私はうどん食べたり友達と電話しながら眺めてましたが、話が枝葉末節揚げ足取りで、ああいえばこういう。〇祐がたくさん集まったらきっとあんなかんじ(笑)。
筋が通ってないとか、話が矛盾してるとか、かなりどうでもいいし。テレビなんだからもっと庶民におりた方がいいかも。
何故考えなければいけないのか、どのような国にしていきたいのか。
国民的議論というけれど、政治家がこれじゃなんか思いやられます。喧嘩だけ増えて疲れるだけになったりして。この番組はいつもこうだからこれはこれでいいのかもしれないけれど。
「もう少し慎重に」という主張はよく意味がわからない。単なる思考停止申告?
単なるぼやきでした。失礼。
>「もう少し慎重に」
私はこの言葉は非常に便利な慣用句だと思っています。
当たり障りなく番組やディベートを締めくくる呪文の言葉とも言えるでしょうか。
このような便利な慣用句は他にもあって、例えばそれは「地球より重たい一つの命」「何の罪も無い普通の人が」のようなもので、それを言えば思考をせずとも共通のイマジネーションが完結するといった物のように思われます。
>どのような国にしていきたいのか。
わたしは、自尊自立した国家の国民になりたい。
海外で国民が困っていたら、漏らさず助けてくれる国の国民になりたい。清潔を好み、国固有の風土を愛し、薫り高い文化を楽しむ心を持つ、情け深い国民でありたい。
しかしぬりさんが友人に感じていらっしゃる脱力感に似た感覚を、私も私の友人感じることがあります。というか正直に書けば、歌舞伎を共に見て共に堪能し感動もし、いい気分で流れた銀座のバーで、ひとしきりその手の噛み合わない話しを持ちました。
またその翌日には別の人と国立博物館常設展と靖国神社の遊就館に行き、共に日本文化を良き物として分かち合い、深く共感をシェアしたにもかかわらず、彼らは日本という国が融解してもかまわないという。
彼らは私に「君にとってそんなに大切な国の概念とは何なのか」と、同じ様なことを同じような口調で問いかけます。私にとっての祖国とは『固有の領土・固有の文化・固有の言語』の何物でもありません。たった今堪能し共に酔いしれたはずの日本は、国家の容そのものなのに、なぜ国家を否定するのか、私には彼らのダブルスタンダードがどうしても理解できません。
しかし、彼らの中では整合性のあるロジックのようで、何処までいってもパラレルです。
私もぼやきました。
が、国土を失った民、もしくは統治権を失ってもそこに居続けるしかない民族の不幸を見聞きすれば、真っ当な国家観を己の頭の中にイメージすることは、無駄なことではないと私には思えるのです。
自国防衛を他国に丸投げしたような状態で、国家の自立はありえないと思うのですが、そんな自尊自立の概念は要らないと彼らは言います。冷戦構造によって保たれていた均衡がもたらした平和が、これからも続くと思っていないにもかかわらずです。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持する」この概念をいつまで・どこまで信じ続ける事ができるか、その差なのかもしれません。
私はこの言葉は非常に便利な慣用句だと思っています。
当たり障りなく番組やディベートを締めくくる呪文の言葉とも言えるでしょうか。
このような便利な慣用句は他にもあって、例えばそれは「地球より重たい一つの命」「何の罪も無い普通の人が」のようなもので、それを言えば思考をせずとも共通のイマジネーションが完結するといった物のように思われます。
>どのような国にしていきたいのか。
わたしは、自尊自立した国家の国民になりたい。
海外で国民が困っていたら、漏らさず助けてくれる国の国民になりたい。清潔を好み、国固有の風土を愛し、薫り高い文化を楽しむ心を持つ、情け深い国民でありたい。
しかしぬりさんが友人に感じていらっしゃる脱力感に似た感覚を、私も私の友人感じることがあります。というか正直に書けば、歌舞伎を共に見て共に堪能し感動もし、いい気分で流れた銀座のバーで、ひとしきりその手の噛み合わない話しを持ちました。
またその翌日には別の人と国立博物館常設展と靖国神社の遊就館に行き、共に日本文化を良き物として分かち合い、深く共感をシェアしたにもかかわらず、彼らは日本という国が融解してもかまわないという。
彼らは私に「君にとってそんなに大切な国の概念とは何なのか」と、同じ様なことを同じような口調で問いかけます。私にとっての祖国とは『固有の領土・固有の文化・固有の言語』の何物でもありません。たった今堪能し共に酔いしれたはずの日本は、国家の容そのものなのに、なぜ国家を否定するのか、私には彼らのダブルスタンダードがどうしても理解できません。
しかし、彼らの中では整合性のあるロジックのようで、何処までいってもパラレルです。
私もぼやきました。
が、国土を失った民、もしくは統治権を失ってもそこに居続けるしかない民族の不幸を見聞きすれば、真っ当な国家観を己の頭の中にイメージすることは、無駄なことではないと私には思えるのです。
自国防衛を他国に丸投げしたような状態で、国家の自立はありえないと思うのですが、そんな自尊自立の概念は要らないと彼らは言います。冷戦構造によって保たれていた均衡がもたらした平和が、これからも続くと思っていないにもかかわらずです。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持する」この概念をいつまで・どこまで信じ続ける事ができるか、その差なのかもしれません。
マー坊さん
自分のコミュでいつも石油石油と言っているのでここは敢えてエサと。ただ、それだけでなくて、敢えてエサと書いたのは、一般庶民が真にブチ切れるのは、食べ物の問題の方がクリティカルかなとも思ったからです。おそらく石油が引き金になるでしょうが。
現在世界で生産されている食糧の全カロリー(エネルギー)のうち、本質的にはおよそ半分が石油と天然ガス由来とも言えるそうです。もっとも、食にはもっと莫大なエネルギーが浪費(輸送・加工等)されています。それを合わせても、石油などの全エネルギー消費量の高々1割か2割に過ぎず(アメリカの場合)、例え石油が減っても他にまわす分を減らせば、この食糧生産量は原理的(エネルギー収支的)にはしばらくは維持出来ます。
民主国家に於いて、国民の食事に不具合が大きく出始めた場合の大衆心理の変化を私は恐れています。
日本は石油戦略で遅れをとっていますからね…。
食については、もう少しちゃんとした話をいつか食糧トピックの方でやりたいです。
自分のコミュでいつも石油石油と言っているのでここは敢えてエサと。ただ、それだけでなくて、敢えてエサと書いたのは、一般庶民が真にブチ切れるのは、食べ物の問題の方がクリティカルかなとも思ったからです。おそらく石油が引き金になるでしょうが。
現在世界で生産されている食糧の全カロリー(エネルギー)のうち、本質的にはおよそ半分が石油と天然ガス由来とも言えるそうです。もっとも、食にはもっと莫大なエネルギーが浪費(輸送・加工等)されています。それを合わせても、石油などの全エネルギー消費量の高々1割か2割に過ぎず(アメリカの場合)、例え石油が減っても他にまわす分を減らせば、この食糧生産量は原理的(エネルギー収支的)にはしばらくは維持出来ます。
民主国家に於いて、国民の食事に不具合が大きく出始めた場合の大衆心理の変化を私は恐れています。
日本は石油戦略で遅れをとっていますからね…。
食については、もう少しちゃんとした話をいつか食糧トピックの方でやりたいです。
国籍法改正案の危機を報じた『週刊新潮』(12月18日号)のグラビアページに、以下の記事があります。
『一宿一命の恩』
言うまでもなく、「一宿一飯の恩」をもじったタイトルですが、これは1942年3月、インドネシア・ジャワ島沖の海戦で撃沈された英国海軍の軍艦から投げ出された搭乗員たちが、日本軍の駆逐艦「雷(いかづち)」に救出された実話を紹介した記事です。
丸一日の漂流ののち、交戦中である日本の「雷」が近づいてくるのを見た英国海兵たちは死を覚悟しましたが、機銃掃射の代わりに彼らが見たものは、「雷」の掲げた救難活動中の国際信号旗でした。
以下、ぼやきくっくりさんの記事から引用します。
============================================================
ぼやきくっくり
『「雷」工藤艦長の武士道精神とサー・フォールの報恩』
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid573.html
甲板に引き揚げられた英海軍将兵を感激させたのは、汚物と沈没艦艇の重油で真っ黒になった英海軍将兵を、小柄な「雷」乗員達が嫌悪することなく、両脇から真水とガソリンで一人一人丁寧に洗浄する光景であった。
220名乗務の駆逐艦が敵将兵450人を救助する。通常なら反乱を恐れてここまでは救助しない、しかもこの海面は敵潜水艦の跳梁が激しかった。まさに決死の敵兵救出劇であった。
さらに「雷」は、潮流に流され四散している英海軍将兵を終日をかけて救助した。たとえ1人でも発見すると「雷」は必ず艦を停止し、総員で救助したのである。中には艦から投下された縄ばしごに自力で上がれない将兵もいたため、「雷」乗員が飛び込んで救助する光景もあった。「雷」乗員は、敵将兵に供与する艦載の被服が底をつくと、自らの分まで進んで提供した。
サー・フォールは、この光景に「自分は夢を見ているのではないか」と何度も腕をつねったと言う。それだけではない、救助活動が終了した頃、「雷」艦長(筆者注:工藤俊作海軍中佐。79年没。享年78)は英海軍士官だけを前甲板に集めた。そしてこう英語でスピーチしたのである。
「自分は英王立海軍を尊敬している。今回貴官らは勇敢に戦った。貴官たちは今日は帝国海軍のゲストである」
そして彼らに士官室の使用を許し友軍以上の処遇を行った。NHKのリポーターは、興奮を抑えながらも、なぜこのような美談が戦後の日本に伝わらなかったのか不思議でならないと発言して中継を終えた。さらに彼は、サー・フォールが、「これこそ日本武士道の実践」と発言したことをも付言していた。
============================================================
週刊新潮の記事は、元英海軍士官のサムエル・フォール氏(89)が工藤艦長と「再会」するために来日したことを、写真付きで伝えています。
彼と固い握手を交わした当時の「雷」航海長、谷川清澄氏(92)は次のように語っています。
「当たり前のことをしたのみです。彼らに戦闘力はなかった。ならば助けるのが人間です」
<書籍>
敵兵を救助せよ!―英国兵422名を救助した駆逐艦「雷」工藤艦長 (単行本)
惠 隆之介 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4794214995
『一宿一命の恩』
言うまでもなく、「一宿一飯の恩」をもじったタイトルですが、これは1942年3月、インドネシア・ジャワ島沖の海戦で撃沈された英国海軍の軍艦から投げ出された搭乗員たちが、日本軍の駆逐艦「雷(いかづち)」に救出された実話を紹介した記事です。
丸一日の漂流ののち、交戦中である日本の「雷」が近づいてくるのを見た英国海兵たちは死を覚悟しましたが、機銃掃射の代わりに彼らが見たものは、「雷」の掲げた救難活動中の国際信号旗でした。
以下、ぼやきくっくりさんの記事から引用します。
============================================================
ぼやきくっくり
『「雷」工藤艦長の武士道精神とサー・フォールの報恩』
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid573.html
甲板に引き揚げられた英海軍将兵を感激させたのは、汚物と沈没艦艇の重油で真っ黒になった英海軍将兵を、小柄な「雷」乗員達が嫌悪することなく、両脇から真水とガソリンで一人一人丁寧に洗浄する光景であった。
220名乗務の駆逐艦が敵将兵450人を救助する。通常なら反乱を恐れてここまでは救助しない、しかもこの海面は敵潜水艦の跳梁が激しかった。まさに決死の敵兵救出劇であった。
さらに「雷」は、潮流に流され四散している英海軍将兵を終日をかけて救助した。たとえ1人でも発見すると「雷」は必ず艦を停止し、総員で救助したのである。中には艦から投下された縄ばしごに自力で上がれない将兵もいたため、「雷」乗員が飛び込んで救助する光景もあった。「雷」乗員は、敵将兵に供与する艦載の被服が底をつくと、自らの分まで進んで提供した。
サー・フォールは、この光景に「自分は夢を見ているのではないか」と何度も腕をつねったと言う。それだけではない、救助活動が終了した頃、「雷」艦長(筆者注:工藤俊作海軍中佐。79年没。享年78)は英海軍士官だけを前甲板に集めた。そしてこう英語でスピーチしたのである。
「自分は英王立海軍を尊敬している。今回貴官らは勇敢に戦った。貴官たちは今日は帝国海軍のゲストである」
そして彼らに士官室の使用を許し友軍以上の処遇を行った。NHKのリポーターは、興奮を抑えながらも、なぜこのような美談が戦後の日本に伝わらなかったのか不思議でならないと発言して中継を終えた。さらに彼は、サー・フォールが、「これこそ日本武士道の実践」と発言したことをも付言していた。
============================================================
週刊新潮の記事は、元英海軍士官のサムエル・フォール氏(89)が工藤艦長と「再会」するために来日したことを、写真付きで伝えています。
彼と固い握手を交わした当時の「雷」航海長、谷川清澄氏(92)は次のように語っています。
「当たり前のことをしたのみです。彼らに戦闘力はなかった。ならば助けるのが人間です」
<書籍>
敵兵を救助せよ!―英国兵422名を救助した駆逐艦「雷」工藤艦長 (単行本)
惠 隆之介 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4794214995
「国家の自立」、「国家の自信・防衛」等々の問題を根本的に理解されていない御仁がおられます。
★民主党幹事長、「永住外国人の地方参政権」について大いに語る!★
鳩山幹事長が、「永住外国人の地方参政権」について本音を語っています。
日頃から、議論にならない議論をされる方だとは思っていましたが、ここまで、論理的思考のできない御仁であったとは…。せっかく大学では数学の工学的、社会的応用分野を学ばれたはずなのに活かされていませんね。
まぁ、わかり易い「すり替え」の見本としては、素晴らしい出来栄えとなっております。
次期政権を取ろうという野党第一党の代表は、あんなお方で、幹事長は、こんなお方です。。。
http://www.youtube.com/watch?v=1BBomcbCy_s
★民主党幹事長、「永住外国人の地方参政権」について大いに語る!★
鳩山幹事長が、「永住外国人の地方参政権」について本音を語っています。
日頃から、議論にならない議論をされる方だとは思っていましたが、ここまで、論理的思考のできない御仁であったとは…。せっかく大学では数学の工学的、社会的応用分野を学ばれたはずなのに活かされていませんね。
まぁ、わかり易い「すり替え」の見本としては、素晴らしい出来栄えとなっております。
次期政権を取ろうという野党第一党の代表は、あんなお方で、幹事長は、こんなお方です。。。
http://www.youtube.com/watch?v=1BBomcbCy_s
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|