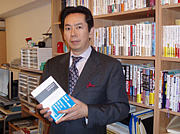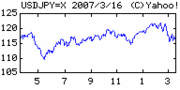гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ328件
жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ
е…Ҳзү©еҸ–еј•й–ўйҖЈгғӢгғҘгғјгӮ№гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
10/31пјҲйҮ‘пјүе…Ҳзү©еҸ–еј•еёӮжіҒгғӢгғҘгғјгӮ№
гҒ§дёӢгҒ’е№…гӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҒҹгҖӮж—ҘйҠҖгҒ®йҮ‘иһҚж”ҝзӯ–жұәе®ҡдјҡеҗҲгҒ§гҒ®ж”ҝзӯ–йҮ‘еҲ©0.20пј…еј•гҒҚдёӢгҒ’жұәе®ҡеҫҢгҒҜгҖҒеҲ©дёӢгҒ’е№…гҒҢе°ҸгҒ•гҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ„жқҗж–ҷеҮәе°ҪгҒҸгҒ—ж„ҹгҒ«гӮҲгӮӢеЈІгӮҠгҒЁйҮ‘иһҚз·©е’Ң жҜ”еҗҢ10еҶҶй«ҳпјүгҖҒ8440еҶҶпјҲеҗҢ590еҶҶе®үпјүгҖӮеЈІиІ·й«ҳгҒҜ18дёҮ0169жһҡгҖӮ10жңҲ30ж—ҘгҒ®зұіеӣҪж ӘејҸеёӮе ҙгҒҜж—Ҙ欧гҒ®еҲ©дёӢгҒ’жңҹеҫ…гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰдёҠжҳҮгҒ—гҒҹгҖӮ7вҖ•9жңҲжңҹ
- 2008е№ҙ10жңҲ31ж—Ҙ 15:56
- 698дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
ж ӘдҫЎеҲҶжһҗ(гӮөгӮӨгғҺгғјгӮігғ )гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
ж—Ҙжң¬гҒҢдҪңгӮҠгҒ гҒ—гҒҹгғҗгғ–гғ«гҒЁеҙ©еЈҠ
гғҺгғјгӮігғ гҒ®жҗәеёҜгӮөгӮӨгғҲгӮӮгӮӘгғјгғ—гғігҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ http://m.sciknow.com/ ж—Ҙжң¬гҒ®гӮјгғӯйҮ‘еҲ©ж”ҝзӯ–гҒЁйҮ‘иһҚз·©е’ҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒҹгҒ еҗҢ然 гҒ§еҖҹгӮҠгҒҹгҒҠйҮ‘гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬ гҒ®зӮәжӣҝгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгғүгғ«еҶҶгҒ®125еҶҶгҒҫгҒ§еҶҶе®үгҒҢйҖІгӮ“гҒ жҳЁе№ҙдёӯй ғгҒ«гҖҒд»–гҒ®й«ҳйҮ‘еҲ©йҖҡиІЁгӮӮеҗ«гӮҒгҒҹеҶҶе®үгҒҜгғ”гғјгӮҜгӮ’ иҝҺгҒҲгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒдё–з•Ң
- 2008е№ҙ10жңҲ25ж—Ҙ 11:27
- 116дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жӨҚиҚүдёҖз§ҖгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҢж—Ҙжң¬еЈІеӣҪпјқз–‘жғ‘гҒ®еӨ–зӮәд»Ӣе…ҘгҖҚж”ҝзӯ–гҒ®ж·ұеұӨ
ж”ҝзӯ–гӮ’еј·гҒҸдё»ејөгҒҷгӮӢгҖӮж—ҘйҠҖгҒ®и¶…йҮ‘иһҚз·©е’Ңж”ҝзӯ–гҒҜеҶҶе®үиӘҳе°Һж”ҝзӯ–гҒЁиЎЁиЈҸдёҖдҪ“гӮ’гҒӘгҒҷгҖӮгҒҷгҒ§гҒ«иЁҳиҝ°гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒпј’пјҗпјҗпјҗе№ҙгҒӢгӮүпј’пјҗпјҗпјҳе№ҙгҒ« зӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгғ–гғӯгӮ°гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҪ“иЁҳдәӢеҹ·зӯҶжҷӮзӮ№гҒ§зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгғ–гғӯгӮ°еҗҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж”№гӮҒгҒҰиЁҳијүгҒ—гҒҹгҒ„гҖӮ гҖҢе°ҸжіүдёҖ家гҖҚгӮ’жҜҚдҪ“гҒЁгҒҷгӮӢгҖҢдёҠгҒ’жҪ®жҙҫгҖҚгҒҜж—ҘйҠҖгҒ®и¶…йҮ‘иһҚз·©е’Ң
- 2008е№ҙ09жңҲ01ж—Ҙ 15:48
- 471дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жӨҚиҚүдёҖз§ҖгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҢеЈІеӣҪж”ҝзӯ–гҖҚгӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„
еҜҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе•ҸйЎҢгҒҜгҖҢеҲ©дёҠгҒ’еҸҚеҜҫгғ»йҮ‘иһҚз·©е’Ңз¶ӯжҢҒгҖҚгҒ®дё»ејөгҒ гҖӮ дёӯе·қж°ҸгҒ®иҝ‘и‘—гҖҢе®ҳеғҡеӣҪ家гҒ®еҙ©еЈҠгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢзҘһе·һгҒ®жіүгҖҚдё»е®° и«ёеӣҪгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®жүҖеҫ—йҮ‘йЎҚгҒҜеҚҠеҲҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ гҖҖгҖҢдёҠгҒ’жҪ®жҙҫгҖҚгҒҜж—Ҙжң¬йҠҖиЎҢгҒ®еҲ©дёҠгҒ’гҒ«еҸҚеҜҫгҒҷгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®и¶…дҪҺйҮ‘еҲ©гҒҢеҶҶе®үгҒ®жңҖеӨ§гҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ еҶҶе®үгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®жҷӮдҫЎи©•дҫЎгӮ’дёӢиҗҪгҒ•гҒӣгҖҒиіјиІ·
- 2008е№ҙ07жңҲ21ж—Ҙ 18:46
- 471дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 1
жӨҚиҚүдёҖз§ҖгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жіЁзӣ®гҒ•гӮҢгӮӢгғҗгғјгғҠгғігӮӯпјҰпјІпјўиӯ°й•·иӯ°дјҡиЁјиЁҖ
зҡ„гҒӘиӘҝж•ҙгӮ’е«ҢгҒЈгҒҰгҖҒйҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒжң¬ж јзҡ„гҒӘгӮӨгғігғ•гғ¬гӮ’жӢӣгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еј·еҠӣгҒӘйҮ‘иһҚеј•гҒҚз· гӮҒгҒЁжҷҜж°—гҒ®еӨ§е№…иҗҪгҒЎиҫјгҒҝгӮ’жӢӣгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ гғҗгғјгғҠгғігӮӯиӯ°й•·гҒҜ?гҒЁ гҒҜж—ҘйҠҖгҒ«и¶…з·©е’ҢгҒ®йҮ‘иһҚж”ҝзӯ–гӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒҢгҖҒи¶…з·©е’ҢгҒ®йҮ‘иһҚж”ҝзӯ–гҒҢеҶҶе®үгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еӣҪеҠӣдҪҺдёӢгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ йҒ©жӯЈгҒӘгғқгғӘгӮ·гғјгғ»гғҹгғғгӮҜгӮ№гҒҢиҖғеҜҹгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮж—Ҙжң¬
- 2008е№ҙ07жңҲ21ж—Ҙ 06:28
- 471дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
е•Ҷе“Ғе…Ҳзү©еҸ–еј•з ”з©¶дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
6/24-2
гғігғүгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮӢжҠ•иіҮгӮ„жҠ•ж©ҹиіҮйҮ‘гҒ®еӢ•гҒҚгҒҢзӣёе ҙй«ҳйЁ°гҒ®й»’幕гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®з–‘гҒ„гҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзұіеӣҪгҒ®дҪҸе®…гғҗгғ–гғ«еҙ©еЈҠгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжҖҘгғ”гғғгғҒгҒ®йҮ‘иһҚз·©е’ҢгҒҢгҖҒйҮ‘дҪҷгӮҠгғ»йҒҺеү°жөҒеӢ•жҖ§гӮ’еҶҚгҒіжӢӣгҒҚгҖҒиҶЁејөгҒ—гҒҹжҠ•ж©ҹиіҮйҮ‘гҒҢе•Ҷе“Ғзӣёе ҙгҒ«жөҒгӮҢиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁгҒҷгӮӢиҰӢж–№гҒ гҖӮгҖҖе№ҙйҮ‘ гғ«гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе•Ҷе“ҒгҒ®пј’пј”пјҗеҖҚгҒ гҖҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҖдҪҸе®…гғҗгғ–гғ«еҙ©еЈҠеҫҢгҒ®жҖҘжҝҖгҒӘйҮ‘иһҚз·©е’ҢгҒ§гҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒӘйҒҺеү°жөҒеӢ•жҖ§гҒҜгҒ•гӮүгҒ«еў—гҒ—гҖҢгӮӨгғігғ•гғ¬жҮёеҝөгҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдёӯгҒ§гҖҒж ӘгҒ«
- 2008е№ҙ06жңҲ24ж—Ҙ 17:30
- 203дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҸҫе ҙгҒ®еӨ–еӣҪзӮәжӣҝпјҒгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жң¬ж—ҘгҒ®йӣҮз”ЁзөұиЁҲгҒҜйҮҚиҰҒ
гҖҖгғүгғ«гҒҢеә•еҖӨгҒӢгӮүиІ·гҒ„жҲ»гҒ•гӮҢгӮӢеұ•й–ӢгҒҢз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғүгғ«гҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҗҶз”ұгҒҜпј“гҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ дёҖгҒӨгҒҜгҖҒзұіеӣҪж”ҝеәңгҒ®гӮөгғ–гғ—гғ©гӮӨгғ еҜҫзӯ–гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜйҮ‘иһҚз·©е’Ң гҖҒеёӮе ҙгҒ®и©ұйЎҢгҒ®дёҖгҒӨгҒ«пј‘пј’жңҲгҒ®еӨ–иІЁе»әжҠ•дҝЎзӯүгҒ®иЁӯе®ҡгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒж—Ҙжң¬гҒӢгӮүжө·еӨ–гҒёгҒ®иіҮйҮ‘жөҒеҮәгҒ«гӮҲгӮӢеҶҶе®үеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ гғңгғјгғҠгӮ№гғһгғҚгғјгҒ®дёҖйғЁгҒҜгҖҒй–“йҒ•
- 2007е№ҙ12жңҲ07ж—Ҙ 05:49
- 89дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҸҫе ҙгҒ®еӨ–еӣҪзӮәжӣҝпјҒгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
ж–°гҒҹгҒӘгғӘгӮ№гӮҜ
гҒ®дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮ·гғҠгғӘгӮӘгҒ§гҒҜгҖҒгғүгғ«е®үз’°еўғгҒ®дёӯгҒ§гҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒӘжҷҜж°—гҒҜеҘҪиӘҝгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҖҒйҮ‘иһҚз·©е’Ңзҡ„гҒӘзҠ¶жіҒгӮӮз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒжҠ•иіҮ家гҒ®гғӘгӮ№гӮҜеҠӣгҒҜе®үе®ҡгҒ—гҖҒгӮӯгғЈгғӘгғјгғҲгғ¬гғјгғүгҒ®з’°еўғгҒҢж•ҙгҒҶгҖӮгҒӨгҒҫ гӮҠгҖҒгғүгғ«гӮӮ駄зӣ®гҒ гҒҢгҖҒеҶҶгӮӮејұгҒ„зҠ¶жіҒгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮҜгғӯгӮ№еҶҶгҒҢеӨ§е№…гҒ«еҶҶе®үгҒЁгҒӘгӮӢиҰӢйҖҡгҒ—гҒ гҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮ·гғҠгғӘгӮӘгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гғүгғ«гҒҢејұгҒ„зөҗжһңгҖҒгғүгғ«
- 2007е№ҙ11жңҲ08ж—Ҙ 05:55
- 89дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
йҖҡиЁіжЎҲеҶ…еЈ«гҒҜж°‘й–“еӨ–дәӨе®ҳпјҒгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
йҖҡиЁігӮ¬гӮӨгғүпјҲйҖҡиЁіжЎҲеҶ…еЈ«пјүи©ҰйЁ“гғ»2007е№ҙеәҰе•ҸйЎҢгҒ®и§ЈиӘ¬пјҲдёҖиҲ¬еёёиӯҳпјүпјҲгҒқгҒ®пј‘пјү
гҒҰгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”ҝеәңгғ»ж—ҘйҠҖгҒҜйҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒҢеәҰгӮ’и¶…гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢгғҗгғ–гғ«зөҢжёҲгҖҚгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжҲҰеҫҢж—Ҙжң¬зөҢжёҲгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘжөҒгӮҢгҒҜгҖҒгҒңгҒІ жёҲгҖҒе•Ҹ2гҒЁе•Ҹ5гҒҜз”ЈжҘӯпјҲиҰіе…үжҘӯгғ»иҲӘз©әз”ЈжҘӯпјүгҖҒе•Ҹ3гҒЁе•Ҹ4гҒҜжҷӮдәӢзҡ„гҒӘеҮәйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮй…ҚзӮ№гҒҜгҖҒе…ЁдҪ“гҒ§ 28зӮ№гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ е•Ҹ1гҒҜгҖҢеҶҶе®үгғ»еҶҶй«ҳгҖҚгҒ®еҹә
- 2007е№ҙ09жңҲ11ж—Ҙ 22:19
- 3687дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гғҸгғӯгғјйҖҡиЁігӮўгӮ«гғҮгғҹгғјгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
йҖҡиЁігӮ¬гӮӨгғүпјҲйҖҡиЁіжЎҲеҶ…еЈ«пјүи©ҰйЁ“гғ»2007е№ҙеәҰе•ҸйЎҢгҒ®и§ЈиӘ¬пјҲдёҖиҲ¬еёёиӯҳпјүпјҲгҒқгҒ®пј‘пјү
гҒҰгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”ҝеәңгғ»ж—ҘйҠҖгҒҜйҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒҢеәҰгӮ’и¶…гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢгғҗгғ–гғ«зөҢжёҲгҖҚгҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжҲҰеҫҢж—Ҙжң¬зөҢжёҲгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘжөҒгӮҢгҒҜгҖҒгҒңгҒІ жёҲгҖҒе•Ҹ2гҒЁе•Ҹ5гҒҜз”ЈжҘӯпјҲиҰіе…үжҘӯгғ»иҲӘз©әз”ЈжҘӯпјүгҖҒе•Ҹ3гҒЁе•Ҹ4гҒҜжҷӮдәӢзҡ„гҒӘеҮәйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮй…ҚзӮ№гҒҜгҖҒе…ЁдҪ“гҒ§ 28зӮ№гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ е•Ҹ1гҒҜгҖҢеҶҶе®үгғ»еҶҶй«ҳгҖҚгҒ®еҹә
- 2007е№ҙ09жңҲ11ж—Ҙ 22:14
- 1016дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зіёзҖ¬иҢӮгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еӯӨй«ҳгҒ®гӮЁгӮігғҺгғҹгӮ№гғҲгҒҜдҪ•еҮҰпјҹпјҲ2000.01.01пјү
зЁӢеәҰгҒ®иӘҝж•ҙгҒҜиө·гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒеҖӢ дәәзҡ„гҒ«гҒҜгӮўгғЎгғӘгӮ«ж ӘгҖҢжҡҙиҗҪгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеұҖйқўгҒҜе…ҚгӮҢгӮӢгҒЁиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢе…ҲиЎҢеҲ©дёҠгҒ’гҖҚгӮ’ ж·ЎгҖ…гҒЁиЎҢгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеҲҶгҖҒгӮўгғ©гғігғ»гғүгғғгғҲгғ»гӮігғ гҒ«гҒҜйҮ‘иһҚз·©е’Ң гӮӨгғӨгғғгҒ®йғЁеҲҶгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®пјүдәҲжё¬гҒҢеӨ–гӮҢгҒҰгӮӮгҒ гӮҢгӮӮж–ҮеҸҘгҒҜиЁҖгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒд»Ҡе№ҙзӮәжӣҝгҒҢ140еҶҶгҒ®еҶҶе®үгҒ«жҢҜгӮҢгҒҹгӮүгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜж ӘдҫЎгҒҢ15000еҶҶеҸ°
- 2007е№ҙ08жңҲ05ж—Ҙ 07:30
- 12дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҸҫе ҙгҒ®еӨ–еӣҪзӮәжӣҝпјҒгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
ж–°е№ҙеәҰе…ҘгӮҠгҒ®зӣёе ҙ?
гҒҶеёӮе ҙз’°еўғгҒ®дёӯгҒ§гҖҒдёӯеӨ®йҠҖиЎҢгҒҜдёҠиЁҳгҒ®йҖҡгӮҠгҖҢйҮ‘иһҚеј•гҒҚз· гӮҒгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж”ҝзӯ–гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ еёӮе ҙгҒ§гҒҜгҖҒжҷҜж°—гҒҢиүҜеҘҪгҒ§йҮ‘иһҚз·©е’Ңзҡ„гҒӘзҠ¶жіҒгҒҢз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§пјҲйҮ‘иһҚ гҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜзө¶еҜҫйҮ‘еҲ©ж је·®гҒ§гӮӮгҖҒе°ҶжқҘзҡ„гҒӘйҮ‘еҲ©дәҲжё¬гҒ§гӮӮгҖҒдёҚеҲ©гҒӘзҠ¶жіҒгҒ«еӨүеҢ–гҒӘгҒ—гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠеҶҶе®ү
- 2007е№ҙ04жңҲ01ж—Ҙ 10:01
- 89дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гғҒгӮ§гғҖгӮјгғҹгғҠгғјгғ«гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
з¶ҡгғ»е№ҙеҸҺ300дёҮеҶҶжҷӮд»ЈгӮ’з”ҹгҒҚжҠңгҒҸзөҢжёҲеӯҰгҖҖжЈ®ж°ёеҚ“йғҺи‘—
гғһгғігӮ·гғ§гғігҒ®дҫЎж јгҒҢеҚҠйЎҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒ家иіғгҒҜеҚҠйЎҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгғҮгғ•гғ¬гҒҜгҖҒж”ҝеәңгӮ„ж—ҘйҠҖгҒҢжң¬ж°—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰйҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’гҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгғҮгғ•гғ¬гӮ’и„ұеҚҙгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ йғҠеӨ–гҖҖ家иіғгҒҢдёӢгҒҢгӮҠгҖҒз”ҹжҙ» гҒ—гҒӮгҒҶдәҢгҒӨгҒ®зҸҫиұЎгҒ®й–“гҒ«з”ҹгҒҡгӮӢжҷӮй–“гҒ®гҒҡгӮҢгҖӮ зӮәжӣҝгҖҖгҒҢдёҖеҶҶеҶҶе®үгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гғҲгғЁгӮҝгҒҜ200е„„еҶҶгҖӮгӮҪгғӢгғјгҒҜ50е„„еҶҶеҲ©зӣҠгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҖӮ йҮ‘еҲ©гҖҖгғҗгғ–гғ«еҙ©еЈҠгҒӢгӮү4е№ҙгҒҹгҒЈгҒҹ1994е№ҙгҒ®10е№ҙеӣҪ
- 2006е№ҙ07жңҲ28ж—Ҙ 22:32
- 24дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гғҒгӮ§гғҖгӮјгғҹгғҠгғјгғ«гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
зөҢжёҲгҒ®д»•зө„гҒҝпј‘пјҗпјҗгҒ®еёёиӯҳгҖҖе°ҸеЎ©гҖҖйҡҶеЈ«и‘—
дҝқжңүгҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӢ¬еҚ зҰҒжӯўжі•гҒ®иҰҸеҲ¶гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«еӮөеӢҷгҒ®иЁјеҲёеҢ–гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠйҖІгҒҫгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜжҢҒгҒЎж ӘжҜ”зҺҮгҒ®иҰҸеҲ¶гҒҜз·©е’ҢгҒ•гӮҢгӮӢж–№еҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ гғҗгғ–гғ«гҖҖйҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’ж”ҝеәңгҒҢиЎҢгҒ„гғһгғҚгғјгӮөгғ—гғ©гӮӨгӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ® гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҪұйҹҝгҒҜжҜ”ијғзҡ„ж—©гӮҒгҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒжҷҜж°—гҒҢдҪҺиҝ·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҶҶй«ҳгӮҲгӮҠеҶҶе®үгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢжӯ“иҝҺгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ гҒҫгҒЁгӮҒгҖҖ д»Ҡж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгӮ·гғ«гғҗгғјз”ЈжҘӯгҒҢзӣӣгӮ“гҒ гҖӮ гҒӘгҒң
- 2006е№ҙ07жңҲ28ж—Ҙ 04:43
- 24дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гғҒгӮ§гғҖгӮјгғҹгғҠгғјгғ«гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҒӮгҒӘгҒҹгӮ’е№ёгҒӣгҒ«гҒҷгӮӢзөҢжёҲеӯҰгҖҖгғҮгғ•гғ¬гҒЁгҒҠйҮ‘гҒЁзөҢжёҲгҒ®и©ұгҖҖжЈ®ж°ёгҖҖеҚ“йғҺи‘—
гҒ®йҠҖиЎҢгҒҢзҷәеҲёгҒ—гҒҰгӮӮе•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«йҰҷжёҜгҒ§гҒҜгҖҒзҷәеҲёйҠҖиЎҢгҒҜдёүгҒӨгҒӮгӮӢ йҮҸзҡ„йҮ‘иһҚз·©е’ҢгҖҖеҹәжң¬зҡ„гҒ«ж—ҘйҠҖгҒҜгҒҠйҮ‘гҒ®гғЎгғјгӮ«гғјгӮҶгҒҲгҒ«гҖҒгҒҠйҮ‘гҒ®дҫЎеҖӨгӮ’дёҠгҒ’гҒҹгҒҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгӮӨгғі гғ•гғ¬гӮ’е«ҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҮгғ•гғ¬дёӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҮҸзҡ„йҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’е®ҹиЎҢгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒзөҢжёҲгҒҜеҠҮзҡ„гҒ«еӣһеҫ©гҒҷгӮӢгҖӮе…¬е…ұдәӢжҘӯиІ»гҒ®жӢЎеӨ§гҒ§гҒҜгҖҒжҷҜж°—гҒҜгӮҲгҒҸгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж”ҝеәң
- 2006е№ҙ07жңҲ27ж—Ҙ 06:10
- 24дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
е°ҶжқҘгҒ«дёҚе®үгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј•пј”дәә
гҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢеӮөеҲёзӯүгӮ’еЈІеҚҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠеёӮе ҙгҒ®зҸҫйҮ‘ гӮ’еҗёеҸҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ“гҒ®жҷӮгҖҒйҮ‘еҲ©гҒҜй«ҳгӮҒгҒ«иӘҳе°ҺгҒ•гӮҢгҖҒе…¬е®ҡжӯ©еҗҲгҒҜеј•гҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ д»–ж–№гҖҒе…ҲгҒ”гӮҚиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖҒиІ·гҒ„гӮӘгғҡгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҖҒеҲҘеҗҚгҖҒйҮ‘иһҚз·©е’Ң гҒҢжҙ»зҷәгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеӣҪеҶ…йҮ‘еҲ©гҒҜдҪҺдёӢеӮҫеҗ‘гҒЁ гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ йҖҶгҒ«еҶҶе®үгҒҢйҖІиЎҢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒијёеҮәгҒҢжҙ»зҷәгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеӣҪеҶ…йҮ‘еҲ©гҒҜдёҠжҳҮеӮҫеҗ‘гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ еҫ“гҒЈгҒҰгҖҒйҒёжҠһиӮўпј’
- 2006е№ҙ06жңҲ15ж—Ҙ 01:17
- 61дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 2
гӮҝгӮҜгӮЁгғғгғҲгҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гғҲгғ¬гғігғүгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еҶҶе®үгҖҒгғүгғ«е®ү
гӮўгҒЁгҒӢдёӯеӣҪгҒ®дёӯеӨ®йҠҖиЎҢгӮӮйқҷгҒӢгҒ«еӨ–иІЁжә–еӮҷгӮ’гғүгғ«гҒӢгӮүгғҰгғјгғӯгҒ«е°‘гҒ—гҒҡгҒӨеӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеӮҫеҗ‘гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮе…ЁиҲ¬зҡ„гҒ«гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҹгғүгғ«е®үгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁдәҲжё¬гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ гҖҖд»ҠеҫҢгҒ®зӮәжӣҝзӣёе ҙгҒ®е…ҲиЎҢгҒҚгҒҜгҖҒйҮҸзҡ„йҮ‘иһҚз·©е’ҢгҒ®и§ЈйҷӨгҒҢгҒҠгҒқгӮүгҒҸжҳҘгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҖҒгҒқгҒ® еҶҶе®үгҖҒгғүгғ«е®ү
- 2006е№ҙ05жңҲ02ж—Ҙ 11:50
- 3дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
ж ӘгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј‘2жңҲ27ж—Ҙ
гҒҰгғҮгғ•гғ¬и„ұеҚҙзўәиӘҚгҒёгҖҖгҖҖ гҒ—гҒӢгӮӮгҖҒе®ҹиіӘгғһгӮӨгғҠгӮ№йҮ‘еҲ©гҒ®йҮ‘иһҚз·©е’ҢгҒ®иҝҪгҒ„йўЁгӮӮ 8411 гҒҝгҒҡгҒ»пјҰпј§ в—ҶдёҖиІ«жіЁзӣ®ж ӘгҖҖпј—,пјҗпјҗпјҗеҶҶе®үгҖҖпјҷпј”пјҺпјҷдёҮеҶҶгҖҖпјҲй«ҳеҖӨпјҷпј–пјҺпј‘дёҮеҶҶ гғ¬и„ұеҚҙ дёҚеӢ•з”Јгғ»еҗ«гҒҝ 8802 дёүиҸұең°жүҖгҖҖ в—Ҷпј‘,пј•пј—пј—еҶҶиІ·гҒ„жҺЁеҘЁдёҖиІ«жіЁзӣ®ж ӘгҖҖпј•пј•еҶҶе®үгҖҖпј’,пј“пј–пј•еҶҶ дҝЎз”ЁеҸ–зө„пјҗпјҺпј•пјҳеҖҚгҒЁеЈІгӮҠй•·гҒ§гҖҒд»Ҡеӣһ
- 2005е№ҙ12жңҲ27ж—Ҙ 21:44
- 33дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
ж ӘгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј‘пјҗжңҲпј”ж—Ҙ
иҰігҒҢеј•гҒҚйҮ‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰзү©иүІгҒ®зҹӣе…ҲгҒҢйӣ»ж©ҹгғ»йӣ»еӯҗйғЁе“Ғж ӘгҒ«дәӨжӣҝгҒ—гҒҹгҖӮи¶…йҮ‘иһҚз·©е’Ңз¶ҷз¶ҡгҒЁжҷҜж°—гғ»дјҒжҘӯеҸҺзӣҠеӣһеҫ©гҒ«еҶҶе®үгҒЁиЁҖгҒҶеҘҪз’°еўғгҒҢжҠ•иіҮ家гғһгӮӨгғігғүгӮ’жҳӮжҸҡгҒ•гҒӣгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒд»Ҡеӣһ гҒӢгӮүгҒ®иІ·еҸ–ж Әпј’е…ҶеҶҶгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒпјҷжңҲжң«пј‘е…ҶеҶҶеј·гҒ®еҗ«гҒҝзӣҠгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ в—ҺгғҸгӮӨгғҶгӮҜж ӘгҒ®жқЎд»¶гҒҜпј®пј№ж ӘдёҠжҳҮгҒЁеҶҶе®үгҒ®з¶ҷз¶ҡгҖӮпј®пј№йҖЈеӢ•
- 2005е№ҙ10жңҲ04ж—Ҙ 21:12
- 33дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
ж ӘгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј’пј—ж—Ҙ
гҒ«ж—ҘйҠҖж”ҝзӯ–委員дјҡгҒҢд»ҠеӣһгӮӮжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҖҢи¶…йҮ‘иһҚз·©е’Ңз¶ӯжҢҒгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжҳЁпј’пј–ж—ҘжҸҗдҫӣгҒ®зұіпј®пјЎпјіпјӨпјЎпјұйҖЈеӢ•пјқжҘӯзёҫж”№е–„еҹәиӘҝгҒ®еҚҠе°ҺдҪ“иЈҪйҖ жҘӯгҒӘгҒ©гғҸгӮӨгғҶгӮҜж ӘдёҠжҳҮгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒдәәж°‘е…ғеҲҮгӮҠдёҠгҒ’д»ҘеүҚгҒ®ж°ҙжә–гҒ«жҲ»гҒЈгҒҹеҶҶе®ү д»Ҡж—ҘгҒ®зӣёе ҙ гғ»зұігғҸгӮӨгғҶгӮҜж Әй«ҳгӮ„еҶҶе®үеҘҪж„ҹгҒ—гҖҒијёеҮәй–ўйҖЈж ӘгҒҢзүҪеј•гҖӮ гғ»гӮўгғүгғҶгӮ№гғҲгҖҒгғӣгғігғҖгҖҒгҒҝгҒҡгҒ»гҖҒгҒӘгҒ©дё»еҠӣж ӘдёӯеҝғгҒ«е…Ёйқўй«ҳгҖҒпј‘пј‘,пјҳпјҗпјҗеҶҶеҸ°
- 2005е№ҙ07жңҲ27ж—Ҙ 20:02
- 33дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
ж ӘгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
29ж—Ҙ
гҒӘгҒ©гҒ®дҪҺдҪҚж ӘгҒҢйҖЈж—Ҙжҙ»жіҒгӮ’е‘ҲгҒҷгҒӘгҒ©гҖҒи¶…йҮ‘иһҚз·©е’ҢгӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҒ—гҒҹгҖҺжҘӯзёҫгҒЁйҮ‘иһҚгҒ®ж··еңЁзӣёе ҙгҖҸзҡ„ж§ҳзӣёгӮ’е‘ҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»ҠеҫҢгҖҒеЈІиІ·д»ЈйҮ‘гҒҢиҶЁгӮүгӮҖгҒӢгҒ«жіЁзӣ®пјҒ гҖҗпј“гҖ‘гҖҖпј“пјҗ д»Ҡж—ҘгҒ®зӣёе ҙ гғ»еҺҹжІ№еҸҚиҗҪгҖҒпј®пј№еӨ§е№…й«ҳгҖҒеҶҶе®үгӮ’еҘҪж„ҹгҒ—гҒҰз¶ҡдјёгҖӮ гғ»жқҫдёӢгғ»гӮ·гғЈгғјгғ—гғ»жӯҰз”° ж–°й«ҳеҖӨгҒӘгҒ©йӣ»ж©ҹгғ»гғҸгӮӨгғҶгӮҜдёӯеҝғгҒ®дё»еҠӣж ӘгғӘгғјгғүгҖӮ гғ»еҘҪжқҗ
- 2005е№ҙ06жңҲ29ж—Ҙ 19:48
- 33дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘ
- ең°еҹҹ
- еҗҢе№ҙд»Ј
- и¶Је‘і
- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’
- гӮІгғјгғ
- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ
- йҹіжҘҪ
- гӮ№гғқгғјгғ„
- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі
- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә
- гҒҠ笑гҒ„
- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„
- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ
- еӯҰж Ў
- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“
- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬
- жҳ з”»
- гӮўгғјгғҲ
- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶
- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ
- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ
- ж—…иЎҢ
- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ
- еҚ гҒ„
- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ
- гҒқгҒ®д»–
еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ