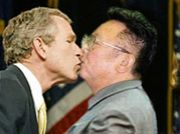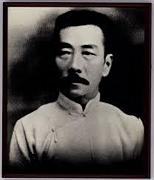гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ2013件
жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ
жқұйғ·е№іе…«йғҺгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҗжқұйғ·е…¬ең’гҖ‘еҹјзҺүзңҢйЈҜиғҪеёӮ
пј‘пј—ж—Ҙе…ғеёҘиҮӘгӮүйҷӨ幕ејҸгҒ«иҮЁеёӯгҒ•гӮҢгҒқгҒ®е®ҢжҲҗгӮ’гҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ е…¬ең’еҶ…гҒ«гҒҜж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ®йҒәзү©гӮ„еҫҢгҒ®жө·и»ҚзңҒгӮҲгӮҠдёӢиіңгҒ•гӮҢгҒҹиЁҳеҝөе“ҒгҒҢзӮ№еңЁгҒ—гҖҒеӨӘе№і
- 2017е№ҙ11жңҲ25ж—Ҙ 13:22
- 1307дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 25
зү№дәңгҒ®зҗҶдёҚе°ҪгҒ•гӮ’ж„ҡз—ҙгӮӢе ҙжүҖ
дәәеҸӮж”ҝжЁ©пјҸж„ӣеӣҪиҖ…пјҸеӨ§жқұдәңжҲҰдәүпјҸеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүпјҸиҮӘеӯҳиҮӘиЎӣпјҸгӮўгӮёгӮўи§Јж”ҫпјҸжқұжқЎиӢұж©ҹпјҸеұұжң¬дә”еҚҒе…ӯпјҸж°ёйҮҺдҝ®иә«пјҸеӨ§е·қе‘ЁжҳҺпјҸз•‘дҝҠе…ӯпјҸпјЎзҙҡжҲҰзҠҜпјҸгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢпјЎзҙҡжҲҰзҠҜпјҸж—ҘйңІжҲҰдәү
- 165дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
е·қи¶ҠзҷәвҮ’гҒ“гҒ©гӮӮгҒЁгҒҠеҮәгҒӢгҒ‘вҮ’гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҗзҙ…и‘үгҖ‘秩зҲ¶еҫЎе¶ҪзҘһзӨҫжқұйғ·е…¬ең’пј йЈҜиғҪеёӮ
гҖҗгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҖ‘ е·қи¶ҠгҒӢгӮү15еҸ·гҖҒ299еҸ·гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰдёҖжҷӮй–“зЁӢеәҰгҖӮ гҖҗиҰӢжүҖгҖ‘ жқұйғ·е№іе…«йғҺгҒ«гӮҶгҒӢгӮҠгҒ®гҒӮгӮӢзҘһзӨҫгҒ§гҒҷгҖӮ пјҲwiki жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ®ж—Ҙжң¬жө·и»ҚгҒ®жҢҮжҸ®е®ҳгҒЁгҒ—гҒҰж—Ҙжё…еҸҠгҒіж—ҘйңІжҲҰдәү
- 2017е№ҙ11жңҲ21ж—Ҙ 08:30
- 762дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫпј¶пјіжқұжўқиӢұж©ҹ
жӨңдәӢгҒ®иЁҖи‘үгҒ§гҒҜгҖҢж—Ҙжң¬гҒ®жҲҰдәүиІ¬д»»гӮ’ж—Ҙжё…гҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүгҒҫгҒ§гҒ•гҒӢгҒ®гҒјгҒЈгҒҰиӘҝгҒ№гӮӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒҶгҒЁгҖҒзҹіеҺҹиҺһзҲҫгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҖгҒҶгҖҢгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгғҡгғӘгғјгӮ’е‘јгӮ“гҒ§жқҘгҒ„гҖҒж—Ҙжң¬ гҒЁд»ҳгҒҚеҗҲгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁдҫӢеӨ–гҒӘгҒҸдҫөз•Ҙдё»зҫ©гҒ®жҒҗгӮҚгҒ—гҒ„еӣҪгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҖҚ гҒ•гӮүгҒ«зҹіеҺҹиҺһзҲҫгҒҜиЁҖгҒҶгҖҢиІҙеӣҪгӮүгӮ’еӨ§е…Ҳз”ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜдҫөз•Ҙдё»зҫ©гӮ’зҝ’гҒ„иҰҡгҒҲгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ„гӮҸгҒ°иІҙеӣҪгӮүгҒ®ејҹеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒ—ж—Ҙжё…гҖҒж—ҘйңІжҲҰдәү
- 2017е№ҙ11жңҲ18ж—Ҙ 07:29
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
дёёеұұзңһз”·гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еҸёйҰ¬еҸІиҰігҒёгҒ®з–‘е•ҸгҖҖжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҢзӘ“гҖҚгҒӢгӮү
еҜҝд№Ӣиј”гҒ•гӮ“пјҲ75пјүгҒҢгҖҢзҰҸжІўи«ӯеҗүгҒ®гӮўгӮёгӮўиӘҚиӯҳгҖҚпјҲй«ҳж–Үз ”пјүгҒӘгҒ©гҒ®и‘—дҪңгҒ§гҖҒеҸёйҰ¬еҸІиҰігӮ’жү№еҲӨгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ ж—Ҙжё…гҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүгҒЁгҖҒжҳҺжІ»гҒ®иҶЁејөдё»зҫ©гҒҜйЎ•и‘—гҒ§гҖҒеҶ…гҒ«
- 2017е№ҙ11жңҲ03ж—Ҙ 11:38
- 478дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 4
жӯҙеҸІгҒ®ж–°дәӢе®ҹ
://mixi.jp/view_bbs.pl?id=41058245&comm_id=4152294 в—Ӣж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ§ж—Ҙжң¬гҒҜжң¬еҪ“гҒ«еӢқеҲ©гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢпјҹ http
- 121дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жәҖе·һй–ӢжӢ“еӣЈгҒ®жӮІеҠҮ
6000еҜҫ8дёҮгҒ§е®ҹгҒ«50пј…гҒЁгҒ„гҒҶжҜ”зҺҮгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ жәҖе·һй–ӢжӢ“еӣЈгҒҜж—ҘйңІжҲҰдәүд»ҘеҫҢгҒ®еӨ§йҷёйҖІеҮәж”ҝзӯ–гҒ®еұ•й–ӢгҒ®дёӯгҒ§гҖҒеӣҪеҶ…гҖҒгҒЁгҒҸ
- 2017е№ҙ10жңҲ14ж—Ҙ 07:02
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
йҖЈеёҜгӮӘгғјгғ«жІ–зё„гғ»жқұеҢ—еҢ—жө·йҒ“гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј‘пјҷпј‘пјҷе№ҙпј’жңҲпјҳж—Ҙ жңқй®®йқ’е№ҙзӢ¬з«ӢеӣЈ гҖҗпј’гғ»пјҳзӢ¬з«Ӣе®ЈиЁҖжӣёгҖ‘
гҒ®ж”№йқ©гҒЁеӣҪеҠӣгҒ®е……е®ҹгӮ’йӢӯж„ҸеӣігҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ еҪ“жҷӮгғӯгӮ·гӮўгҒ®еӢўеҠӣгҒҢеҚ—дёӢгҒ—гҖҒжқұжҙӢгҒ®е№іе’ҢгҒЁйҹ“еӣҪгҒ®е®үеҜ§гӮ’и„…гҒӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒҜйҹ“еӣҪгҒЁж”»е®ҲеҗҢзӣҹгӮ’зөҗгӮ“гҒ§ж—ҘйңІжҲҰдәүгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҒҢгҖҒжқұжҙӢ
- 2017е№ҙ09жңҲ26ж—Ҙ 19:55
- 30дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
дёӯеӣҪдәәгӮ’иӘҚгӮҒгҒҹжәҖи’ҷй ҳжңүиЁҲз”»
гҒҜгғӯгӮ·гӮўеӢўеҠӣгҒ«жҠјгҒҲгӮүгӮҢгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүеҫҢгҒӢгӮүгҒҜгҖҒж—ҘйңІдёЎеӣҪгҒ®еӢўеҠӣгҒҢеҚ—жәҖгҒЁеҢ—жәҖгӮ’дәҢеҲҶгҒ—гҖҒдёӯеӣҪгҒ®жҷӮд»ЈгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжәҖе·һгҒҜж—ҘгӮҪдёЎеӣҪгҒ®еӢўеҠӣгҒЁжәҖе·һи»Қй–ҘгҒЁгҒ„гҒҶдәҢйҮҚж”Ҝй…ҚдёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҖҒжәҖе·һ ең°ж–№гӮ’й ҳжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰе®Ңе…ЁгҒ«йҒ”жҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҚ—дёӢж”ҝзӯ–гҒ®йҳ»жӯўгҖҒзҷҪдәәгҒ®жӨҚж°‘ең°ж”Ҝй…ҚгҒӢгӮүгӮўгӮёгӮўгӮ’е®ҲгӮӢгҒ®гҒҜгҒ“гӮҢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®зү№ж®ҠжЁ©зӣҠгҒЁгҒҜгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәү
- 2017е№ҙ09жңҲ23ж—Ҙ 07:16
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жәҖе·һеӣҪгҒЁгҒҜ
еӣҪгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеӨ§еӣҪгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҚ—йҖІгҒҜгҖҒдёӯеӣҪдәәгҒҢи§ЈжұәгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е•ҸйЎҢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ ж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ«еӢқеҲ©гӮ’еҸҺгӮҒгҒҹж—Ҙжң¬дәәгҒҜгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҚ—йҖІгӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒең°гҒЁ гҒ®ж°‘иЎҶгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰе®үе…ЁгҒ§еҠ©гҒ‘еҗҲгҒҶдәӢгӮ’еҝғгҒӢгӮүжңӣгӮҖгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжәҖе·һеҗҲиЎҶеӣҪгҒ®е»әеӣҪгҒҜж°‘ж„ҸгҒЁжҷӮд»ЈгҒ®жөҒгӮҢгӮ’иҰӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ ж—ҘйңІжҲҰдәүеҫҢгҒ®жәҖе·һеҸІгӮ’гҖҒж—Ҙжң¬и»ҚгҒ®гҖҢдҫөз•ҘгҖҒиҷҗж®әгҖҒз•ҘеҘӘгҖҒжҗҫеҸ–гҖҚгҒ®жӯҙ
- 2017е№ҙ09жңҲ17ж—Ҙ 06:19
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
е…җзҺүжәҗеӨӘйғҺ
ж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒйҷёи»ҚгҒ®й ӯи„ігҖӮ гҒ„гӮ„гҖҒжҳҺжІ»ж—Ҙжң¬гҒ®й ӯи„ігҖӮ еҠҹзёҫгҒ®гӮҸгӮҠгҒ«гҖҒзҡҶзҹҘгӮүгҒӘгҒ„пјҒ гҒҠжңӯ
- 1010дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жәҖе·һгҒ®еңҹең°гҒЁзҹіеҺҹиҺһзҲҫ
гҒЁгҒ„гҒҶеңҹең°гҒҢгҖҒдёӯеӣҪгҒ®й ҳеңҹгҒ гҒЁгҒ„гҒҶдё»ејөгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«жӯҙеҸІгҒ®жҚҸйҖ гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮйҖҶгҒ«гҖҢжәҖе·һгҒҜдёӯеӣҪгҒ®еӣәжңүй ҳеңҹгҒ«гҒӮгӮүгҒҡгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи«–дәүгҒҜж—ҘйңІжҲҰдәү гҒ—дёӯиҸҜж°‘еӣҪгҒ®ж”Ҝй…ҚжЁ©гҒҜгҖҒе»әеӣҪеҫҢдёҖеәҰгӮӮжәҖе·һгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ—гҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүеҫҢгҒ®жәҖе·һгҒҜгҖҒеҢ—гҒҜгғӯгӮ·гӮўгҖҒеҚ—гҒҜж—Ҙжң¬гҒ®ж”Ҝй…ҚеҢ–гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеұұзңҢжңүжңӢгҒҢеӯ«ж–ҮгҒ®еЈІеҚҙи©ұгӮ’ж–ӯгҒЈгҒҹдәӢе®ҹгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮ
- 2017е№ҙ09жңҲ10ж—Ҙ 07:06
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
еӣҪж——гҒ®йҮҚгҒҝгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жӯҙд»ЈеӨ©зҡҮпј‘пј’пј•д»ЈгҖҖгғҶгӮӯгӮ№гғҲиЎЁзӨә
еӨ©зҡҮпјҲ第122代пјү жҳҺжІ»еӨ©зҡҮгҒҜз¶ӯж–°гҒ®еӨ§еӨүйқ©гӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ«еӢқеҲ©гҖӮдё–з•ҢеҸІзҡ„гҒӘеҗҚеҗӣгҒ§гҒҷгҖӮ в—Ҹ4:17гҖҖеӨ§жӯЈеӨ©зҡҮпјҲ第123代пјү еӨ§жӯЈ
- 2017е№ҙ08жңҲ19ж—Ҙ 07:05
- 269дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 11
еӯ«еҙҺдәЁгғ»еәғеҺҹзӣӣжҳҺгғ»иүІе№іе“ІйғҺйҒ”иҰӢгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҺж—Ҙжң¬гҒҜе…«жңҲеҚҒдә”ж—ҘгӮ’зөӮжҲҰиЁҳеҝөж—ҘгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҖҢйҷҚдјҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒҚгҒігҒ—гҒ„зҸҫе®ҹгҒӢгӮүзӣ®гӮ’гҒқгӮүгҒ—гҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҖҸ
гӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁгҒ®гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҖҖгӮҪйҖЈгҒ®гӮ№гӮҝгғјгғӘгғійҰ–зӣёгҒҜгҖҒ гҖҢгҖ”гҒӢгҒӨгҒҰгҒ®ж—ҘйңІжҲҰдәүгҒҜгҖ•гӮҸгҒҢеӣҪгҒ®жӯҙеҸІгҒ®жұҡзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҸгҒҢ
- 2017е№ҙ08жңҲ16ж—Ҙ 10:24
- 59дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 1
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҒӢгӮүжәҖе·һеӣҪгҒёгҒ®жҖқгҒ„
гғӘгӮ«жҲҰдәүгҒ«гӮҲгӮҠгғ•гӮЈгғӘгғ”гғігҒ®й ҳеңҹгӮ’еҘӘгҒ„гҖҒгҒқгӮҢд»ҘеҫҢгҒҜгҖҒдёӯеӣҪеёӮе ҙйҖІеҮәгӮ’зӢҷгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ«еӢқеҲ©гҒ—гҖҒжқұгӮўгӮёгӮўгҒ®ж–°иҲҲеёқеӣҪдё»зҫ©гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰдёӯгҒ®21гҒӢжқЎ иҰҒжұӮгҒ§гҖҒеұұжқұзңҒгӮ„жәҖи’ҷгҒ®еҲ©жЁ©гӮ’зҚІеҫ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж—ҘйңІжҲҰдәүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬жӯҙеҸІгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘгӮҝгғјгғӢгғігӮ°гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮж—ҘйңІжҲҰдәү
- 2017е№ҙ07жңҲ23ж—Ҙ 06:17
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еә„еҶ…гҒ®еҝ—еЈ«гҒҹгҒЎ
гӮӮеӨ§е·қгӮӮе…ұгӮўгӮёгӮўгҒ«еј·гҒ„й–ўеҝғгӮ’еҗ‘гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзҹіеҺҹиҺһзҲҫгҒҜгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүд»ҘеүҚгҖҒд»ҷеҸ°е№је№ҙеӯҰж ЎеңЁеӯҰдёӯгҒӢгӮүгҖҒгҖҢж”ҜйӮЈе•ҸйЎҢгҒ®з ”究иҖ…гҖҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҖҢж—Ҙжң¬
- 2017е№ҙ06жңҲ12ж—Ҙ 06:03
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жқҫдёӢжқ‘еЎҫ
жқҫйҷ°е…Ҳз”ҹгҒ®гҒ“гҒ®еЎҫгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°й•·е·һи—©гҒҢз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮӢдәӢгӮӮгҖҒгҒӮгҒ®жҳҺжІ»з¶ӯж–°гӮӮгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүгӮӮгҖҒеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүгӮӮгҖҒгҒқгҒ—гҒҰд»Ҡж—ҘгҒ®зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹж—Ҙжң¬гӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ жқҫдёӢжқ‘еЎҫгҒ®еӯҳеңЁгҒҜгҖҒд»ҠгҒӘ
- 1697дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
йӯҜиҝ…гғ»дёүдёҠзҘҗдёҖгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҖдёүдёҠеӢҮд»ӢгҒ®гҒқгҒ®еҫҢгҒ®зҷәиЁҖгҒЁгӮӯгғігӮ°гғ»гӮӘгғ–гғ»гғңгғҮгӮЈгғјгӮәгҒЁгҒ®гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒқгҒ®д»–в‘Ұ
е•ҶдәәгҒҢгҒҹгӮ“гҒҫгӮҠе„ІгҒ‘гҒҹгҖӮж—ҘйңІжҲҰдәүгӮӮз„ЎзӣҠгҒӘжҲҰдәүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҒж—ҘдёӯжҲҰдәүгӮӮз„ЎзӣҠгҒӘжҲҰдәүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—еӨ§жқұдәңжҲҰдәүгҒҜиІ гҒ‘гҒҜгҒ—гҒҹгҒҢж„Ҹзҫ©ж·ұгҒ„жҲҰдәүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҒгҒҫгҒӮ
- 2017е№ҙ04жңҲ29ж—Ҙ 02:04
- 2дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
иЈҒгҒ‘гҒӘгҒ„жәҖе·һдәӢеӨүгҒ®йҰ–и¬ҖиҖ…
гҒ®жҲҰдәүиІ¬д»»гӮ’ж—Ҙжё…гҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүгҒҫгҒ§гҒ•гҒӢгҒ®гҒјгҒЈгҒҰиӘҝгҒ№гӮӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒҶгҒЁгҖҒзҹіеҺҹиҺһзҲҫгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҖгҒҶгҖҢгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгғҡгғӘгғјгӮ’е‘јгӮ“гҒ§жқҘгҒ„гҖҒж—Ҙжң¬гҒҜеҪ“жҷӮеҫіе·қйҺ–еӣҪжҷӮд»ЈгҒ§гҖҒгҒ©гҒ“ гҒЁд»ҳгҒҚеҗҲгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁдҫӢеӨ–гҒӘгҒҸдҫөз•Ҙдё»зҫ©гҒ®жҒҗгӮҚгҒ—гҒ„еӣҪгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүиІҙеӣҪгӮүгӮ’еӨ§е…Ҳз”ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜжіҘжЈ’гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҫөз•Ҙдё»зҫ©гӮ’зҝ’гҒ„иҰҡгҒҲгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒ„гӮҸгҒ°иІҙеӣҪгӮүгҒ®ејҹеӯҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӮгҒ—ж—Ҙжё…гҖҒж—ҘйңІжҲҰдәү
- 2017е№ҙ04жңҲ22ж—Ҙ 07:18
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
зҹіеҺҹиҺһзҲҫе№іе’ҢжҖқжғіз ”究дјҡгҒ®жӯҙеҸІ
ж—Ҙжң¬гҒҜж—ҘйңІжҲҰдәүд»ҘжқҘгҖҒйқһзҷҪдәәеӣҪ家гҒЁгҒ—гҒҰеёёгҒ«еҗҚиӘүгҒӮгӮӢзӢ¬з«ӢгӮ’жұӮгӮҒз¶ҡгҒ‘гҒҹгҒҢгҖҒйҒӮгҒ«гӮўгғЎгғӘгӮ«гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҖҒгӮҪйҖЈ
- 2017е№ҙ03жңҲ15ж—Ҙ 05:46
- 68дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
д»Ҡж—ҘгҒҜдҪ•гҒ®ж—Ҙпјҹж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
3жңҲ10ж—ҘгҒ®иЁҳеҝөж—Ҙ
гҒҰгӮ“жқ‘ (ж—§)йҷёи»ҚиЁҳеҝөж—Ҙ 1906(жҳҺжІ»39)е№ҙгҖң1945(жҳӯе’Ң20)е№ҙгҒ®й–“гҒ®зҘқж—ҘгҖӮ 1905(жҳҺжІ»38)е№ҙгҒ®гҒ“гҒ®ж—ҘгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүгҒ®йҷёгҒ®жұәжҲҰгғ»еҘүеӨ©
- 2017е№ҙ03жңҲ10ж—Ҙ 06:20
- 56дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
й–ўжқұгҒ®гҒҠеҜәгғ»зҘһзӨҫе·ЎгӮҠгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲ
еӢҹйӣҶзөӮдәҶж°ҙжҲёзҘһзӨҫе·ЎгӮҠ
2017е№ҙ03жңҲ04ж—Ҙ
иҢЁеҹҺзңҢ
гҒ®еҪ№гҖҒж—Ҙжё…жҲҰдәүгҖҒж—ҘйңІжҲҰдәүзӯүгҒ«гӮҲгӮӢиҢЁеҹҺзңҢеҮәиә«гҒ®жҲҰеҪ№иҖ…гҒ®еҗҲзҘҖгҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгҖҒеүөе»әеҪ“жҷӮгҒ®зӨҫж®ҝгҒ§гҒҜжүӢзӢӯгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒжҳӯе’Ңпј‘пј–е№ҙгҒ«зҸҫеңЁең°гҒ«з§»и»ўгҒ—гҖҒиҢЁеҹҺ
- 2017е№ҙ03жңҲ05ж—Ҙ 17:40
- 10дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 44
- 7
гӮ«гғҶгӮҙгғӘ
- ең°еҹҹ
- еҗҢе№ҙд»Ј
- и¶Је‘і
- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’
- гӮІгғјгғ
- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ
- йҹіжҘҪ
- гӮ№гғқгғјгғ„
- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі
- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә
- гҒҠ笑гҒ„
- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„
- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ
- еӯҰж Ў
- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“
- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬
- жҳ з”»
- гӮўгғјгғҲ
- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶
- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ
- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ
- ж—…иЎҢ
- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ
- еҚ гҒ„
- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ
- гҒқгҒ®д»–
еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ