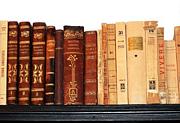гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ10件
жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ
дё–з•ҢеҸІгғ»ж—Ҙжң¬еҸІгғ»жӯҙеҸІеҘҪгҒҚгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
ж—Ҙжң¬еҸӨе…ёж–ҮеӯҰзҙ№д»ӢпјҒпјҒ
гӮү2002е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжңҖж–°гҒ®з ”究жҲҗжһңгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹжіЁйҮҲгҒЁгҖҒзҸҫд»ЈиӘһиЁігҒ®дҪөијүгҒЁгҒ„гҒҶж–№йҮқгӮ’иёҸиҘІгҒ—гҒҹ[иҰҒеҮәе…ё]гҖӮгҒ“гҒ®ж–°зүҲгҒ®ж§ӢжҲҗгӮӮгҖҒеј•гҒҚз¶ҡгҒҚгҖҒдёҠж®ө гҒ«жіЁйҮҲгҖҒдёӢж®өгҒ«зҸҫд»ЈиӘһиЁігӮ’иЁҳијүгҒ—гҖҒдёӯеӨ®гҒ«жң¬ж–ҮгҒӘгӮүгҒігҒ«гҖҒеӯҳеңЁгҒҷгӮҢгҒ°жҢҝзөөгӮ’жҢҝе…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ йҖҡеҸ· гӮҝгӮӨгғҲгғ« еҪ“и©Іе·»гҒ®ж ЎжіЁгғ»иЁіиҖ… еҮәзүҲ еӮҷиҖғ
- 04жңҲ23ж—Ҙ 05:31
- 150дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 43
йҙЁй•·жҳҺгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
зҷәеҝғйӣҶ
зҙҖдәәж ЎжіЁгҖҒж–°жҪ®зӨҫгҖҢж–°жҪ®ж—Ҙжң¬еҸӨе…ёйӣҶжҲҗгҖҚгҖҒ1976е№ҙгҖҒж–°иЈ…зүҲ2016е№ҙпјү гҖҺзҷәеҝғйӣҶгҖҖзҸҫд»ЈиӘһиЁід»ҳгҒҚгҖҸпјҲжө…иҰӢе’ҢеҪҰгғ»дјҠжқұзҺүзҫҺиЁіжіЁгҖҒи§’е·қгӮҪгғ•гӮЈгӮўж–Үеә«пјҲдёҠдёӢпјү[3 йҒ“гӮ’жұӮгӮҒгҒҹйҡ йҒҒиҖ…гҒ®иӘ¬и©ұйӣҶгҒ§гҖҺй–‘еұ…еҸӢгҖҸгҖҒгҖҺж’°йӣҶжҠ„гҖҸгҒӘгҒ©гҒ®иӘ¬и©ұйӣҶгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒгҖҺеӨӘе№іиЁҳгҖҸгӮ„гҖҺеҫ’然иҚүгҖҸгҒ«гҒҫгҒ§еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢ
- 2021е№ҙ03жңҲ03ж—Ҙ 22:10
- 1дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
ж–°ж—Ҙжң¬еҸӨе…ёж–ҮеӯҰеӨ§зі»ж„ӣиӘӯгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еҫ’然иҚү第7ж®өгҒ®дҪҗи—ӨжҳҘеӨ«иЁі
жүӢе…ғгҒ«жң¬гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒиӘҝгҒ№гӮҲгҒҶгҒҢгҒӘгҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖӮеҫ’然иҚү第7ж®өгҒ®дҪҗи—ӨжҳҘеӨ«гҒ®зҸҫд»ЈиӘһиЁігӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖӮпјҲSOSпјү еҫ’然иҚү第7ж®өгҒ®дҪҗи—ӨжҳҘеӨ«иЁі
- 2014е№ҙ08жңҲ22ж—Ҙ 00:09
- 26дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
йҖҡиЁіжЎҲеҶ…еЈ«гҒҜж°‘й–“еӨ–дәӨе®ҳпјҒгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
2014е№ҙеәҰйҖҡиЁіжЎҲеҶ…еЈ«пјҲйҖҡиЁігӮ¬гӮӨгғүпјүи©ҰйЁ“пјң第1次и©ҰйЁ“еҜҫзӯ–з·ҸгҒҫгҒЁгӮҒпјһпјҲ43пјү
еӨ–гӮ’гҒ°жү“гҒЎжҚЁгҒҰгҒҰгҖҒеӨ§дәӢгӮ’жҖҘгҒҗгҒ№гҒҚгҒӘгӮҠгҖӮдҪ•дёҮгӮ’гӮӮжҚЁгҒҰгҒҳгҒЁеҝғгҒ«еҸ–гӮҠжҢҒгҒЎгҒҰгҒҜгҖҒдёҖдәӢгӮӮжҲҗгӮӢгҒ№гҒӢгӮүгҒҡгҖӮ пјңзҸҫд»ЈиӘһиЁіпјһ гҒӮгӮӢиҖ…гҒҢгҖҒиҮӘеҲҶ гӮ’зӮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гҒЁеҝғж§ӢгҒҲгӮ’еҗүз”°е…јеҘҪгҒ®гҖҢеҫ’然иҚүгҖҚгҒ«еӯҰгҒігҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ700е№ҙгҒ®жҷӮгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰгҖҒиіўиҖ…гҒ®ж·ұгҒ„ж•ҷгҒҲгҒҢиғёгҒ«иҝ«гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гҖҒгҖҢе…ҲйҒ”пјҲгҒӣгӮ“гҒ гҒӨпјүгҒҜгҒӮ
- 2014е№ҙ08жңҲ08ж—Ҙ 08:00
- 3692дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гғҸгғӯгғјйҖҡиЁігӮўгӮ«гғҮгғҹгғјгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
2014е№ҙеәҰйҖҡиЁіжЎҲеҶ…еЈ«пјҲйҖҡиЁігӮ¬гӮӨгғүпјүи©ҰйЁ“пјң第1次и©ҰйЁ“еҜҫзӯ–з·ҸгҒҫгҒЁгӮҒпјһпјҲ43пјү
еӨ–гӮ’гҒ°жү“гҒЎжҚЁгҒҰгҒҰгҖҒеӨ§дәӢгӮ’жҖҘгҒҗгҒ№гҒҚгҒӘгӮҠгҖӮдҪ•дёҮгӮ’гӮӮжҚЁгҒҰгҒҳгҒЁеҝғгҒ«еҸ–гӮҠжҢҒгҒЎгҒҰгҒҜгҖҒдёҖдәӢгӮӮжҲҗгӮӢгҒ№гҒӢгӮүгҒҡгҖӮ пјңзҸҫд»ЈиӘһиЁіпјһ гҒӮгӮӢиҖ…гҒҢгҖҒиҮӘеҲҶ гӮ’зӮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ®йӣЈгҒ—гҒ•гҒЁеҝғж§ӢгҒҲгӮ’еҗүз”°е…јеҘҪгҒ®гҖҢеҫ’然иҚүгҖҚгҒ«еӯҰгҒігҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ700е№ҙгҒ®жҷӮгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰгҖҒиіўиҖ…гҒ®ж·ұгҒ„ж•ҷгҒҲгҒҢиғёгҒ«иҝ«гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒ•гҒ«гҖҒгҖҢе…ҲйҒ”пјҲгҒӣгӮ“гҒ гҒӨпјүгҒҜгҒӮ
- 2014е№ҙ08жңҲ08ж—Ҙ 08:00
- 1019дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гғӘгӮҫгғјгғҲеҜәеӯҗеұӢгҖҖINгҖҖSYDNEYгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲ
еӢҹйӣҶзөӮдәҶ第212еӣһгҖҖеҜәеӯҗеұӢгҖҖпј“жңҲпј–ж—ҘпјҲж°ҙжӣңж—Ҙпјүпј‘пјҷпјҡпјҗпјҗгҖңпј’пј‘пјҡпјҗпјҗ
2013е№ҙ03жңҲ06ж—Ҙ
й–ӢеӮ¬е ҙжүҖжңӘе®ҡ
е…јеҘҪгҒ®жӯ»з”ҹиҰігӮ’иЎЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ д»ҘдёӢгҖҒзҸҫд»ЈиӘһиЁігҒ§зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҖҢжӯ»гӮ’жҒҗгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз”ҹгӮ’ж…ҲгҒ—гҒҝж„ӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ гҒ„гҒҫз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢе–ңгҒігӮ’гҖҒж—ҘгҖ…жҘҪгҒ—гӮӮгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮ ж„ҡгҒӢ гӮӮд»Ҡж—ҘгҒҢдәәз”ҹжңҖеҫҢгҒ®ж—ҘгҒ гҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒ д»Ҡж—ҘгӮ„гӮӢдәҲе®ҡгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжң¬еҪ“гҒ«з§ҒгҒҢгӮ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒ“гҒЁ гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹгҖҚ гҒЁе•ҸгҒ„гҒӢгҒ‘гҒҰдёҖж—ҘгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ гҖҺеҫ’然иҚүгҖҸгҒ®дёӯгҒ«гӮӮ еҗүз”°
- 2013е№ҙ03жңҲ02ж—Ҙ 13:56
- 1дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жқұдә¬гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜгӮ№иӘӯжӣёдјҡгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲ
еӢҹйӣҶзөӮдәҶ2/13пјҲж°ҙпјүйҙЁй•·жҳҺгҖҺж–№дёҲиЁҳгҖҸ
2013е№ҙ02жңҲ13ж—Ҙ(19:30-21:00)
жқұдә¬йғҪ(еҚҠи”өй–Җ)
ж•°гҒҲгӮүгӮҢгӮӢжң¬дҪңгҒҜйқһеёёгҒ«еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„иӘһгӮҠеҸЈгҒЁгҒқгҒ®еҘҘж·ұгҒ•гҒҢйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮ зҸҫд»ЈиӘһиЁігӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“еҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒңгҒІдёҖеәҰгҒҠжүӢгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ гҒ”еҸӮ еӣіжӣё гғҶгғјгғһгҖҢгӮёгғ‘гғігӮ°жҺўиЁӘгҖҚпјҲпј‘пјү йҙЁй•·жҳҺ(и‘—)гҖҖгҖҢж–№дёҲиЁҳгҖҚ (и§’е·қгӮҪгғ•гӮЈгӮўж–Үеә«гҒ»гҒӢ) еҸёдјҡпјҡеӨ©ж°—иӘӯгҒҝ вҖ»зҸҫд»ЈиӘһиЁі
- 2013е№ҙ02жңҲ12ж—Ҙ 19:06
- 7дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 13
еҝғгӮ’жү“гҒӨгҖҒзҫҺгҒ—гҒ„ж—Ҙжң¬иӘһгҖӮгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еҫ’然гҒӘгӮӢгҒҫгҒҫгҒ«вҖҰ
гҒҶгҒ“гҒқзү©зӢӮгҒҠгҒ—гҒ‘гӮҢ еҮәе…ёпјҡ еҫ’然иҚү дҪңиҖ…пјҡ еҗүз”°е…јеҘҪпјҲе…јеҘҪжі•её«пјү зҸҫд»ЈиӘһиЁіпјҡ гҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸжҲҜгӮҢгҒ«дёҖж—ҘзЎҜгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҖҒеҝғгҒ«жө®гҒӢгӮ“гҒ дәӢгӮ’ гҒЁгӮҠ
- 2008е№ҙ08жңҲ31ж—Ҙ 01:45
- 18884дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 3
гҒҠгӮӮгҒ—гӮҚжӯҙеҸІйӨЁ-ж–°иЈҸеӨӘйғҺеұұйҖҡдҝЎгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гғһгӮ¬гӮёгғіз¬¬дәҢеҸ·пј‘пјҳпј—пјҳе№ҙпј“жңҲпј’пј•ж—Ҙжң¬гҒ§жңҖеҲқгҒ®йӣ»зҒҜгҒҢгҒЁгӮӮгӮӢ
ж–ҮеӯҰгӮ’гҒӮгӮӢж–№еҗ‘жҖ§гҒ«гҒ®гҒҝеј•гҒҚгҒҡгҒЈгҒҰгҒ„гҒ“гҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж•ҷ科жӣёгӮ„жҢҮе°ҺжӣёгҒ®жңүгӮҠгӮҲгҒҶгҒ«гӮӮз–‘е•ҸгӮ’жҠ•гҒ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҖҖеҸӨж–ҮгҒ®гҖҢж•ҷ科жӣёгҖҚгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеӨҡе°‘иӘӯгҒҝгҒҘгӮүгҒ„з®ҮжүҖгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮдёҖдәәгҒ§гӮӮеҸӨж–Үе«ҢгҒ„гӮ’з„ЎгҒҸгҒ—гҖҒжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°гҒЁгҒ„гҒҶе·ҘеӨ«гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮпјҲгҒқгӮҢгҒ§гӮӮи„ҡжіЁгӮ„зҸҫд»ЈиӘһиЁі гӮ„иЁҺгҒЎжӯ»гҒ«гҒ®гӮ·гғјгғігӮ’жҸҸгҒҸж®өгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲҶжһҗгҒӢгӮүгҖҒгҖҢвҖҰвҖҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жӯ»гҒ¬гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгғҮгӮӘгғӯгӮ®гғјгӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҖҒиӯҰжҲ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҺеҫ’然иҚүгҖҸгҒ®гҖҢе Җжұ гҒ®еғ§жӯЈгҖҚгҒ®ж®өгӮ’дҫӢгҒ«гҖҒгҖҢдҪ•гҒӢ
- 2007е№ҙ04жңҲ01ж—Ҙ 10:31
- 5дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘ
- ең°еҹҹ
- еҗҢе№ҙд»Ј
- и¶Је‘і
- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’
- гӮІгғјгғ
- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ
- йҹіжҘҪ
- гӮ№гғқгғјгғ„
- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі
- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә
- гҒҠ笑гҒ„
- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„
- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ
- еӯҰж Ў
- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“
- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬
- жҳ з”»
- гӮўгғјгғҲ
- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶
- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ
- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ
- ж—…иЎҢ
- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ
- еҚ гҒ„
- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ
- гҒқгҒ®д»–
еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ