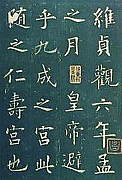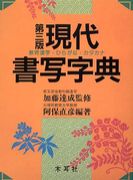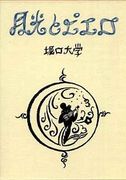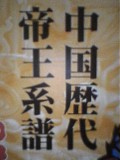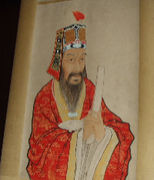гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ94件
жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ
иҮЁжӣё
е®®йҶҙжіүйҠҳпј»е”җгғ»ж¬§йҷҪи©ўпјҸжҘ·жӣёпјҪгҖҒеӯ”еӯҗе»ҹе Ӯзў‘пј»е”җгғ»иҷһдё–еҚ—пјҸжҘ·жӣёпјҪгҖҒеӯҹжі•её«зў‘пј»е”җгғ»褚йҒӮиүҜпјҸжҘ·жӣёпјҪгҖҒйӣҒеЎ”иҒ–ж•ҷеәҸпј»е”җгғ»褚йҒӮиүҜпјҸжҘ·жӣё
- 156дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жӣёеҶҷжӣёйҒ“ж•ҷиӮІ
жқҝгҖҖз”ІйӘЁж–ҮгҖҖжҘ·жӣёгҖҖиЎҢжӣёгҖҖйҡ·жӣёгҖҖиҚүжӣёгҖҖзҜҶжӣёгҖҖзҜҶеҲ»гҖҖеҲ»еӯ—гҖҖгҒӢгҒӘгҖҖдёҮи‘үд»®еҗҚгҖҖиҚүд»®еҗҚгҖҖеӨүдҪ“д»®еҗҚгҖҖд№қжҲҗе®®гҖҖеӯ”еӯҗе»ҹе Ӯзў‘гҖҖиҳӯдәӯеәҸгҖҖзҺӢзҫІд№ӢгҖҖйЎ”зңҹеҚҝгҖҖдёүеӨ§е®¶гҖҖдәҢзҺӢ
- 482дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жқұжө·йҒ“жң¬з·ҡжІҝз·ҡиҰіе…үгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
еӨ§и°·жң¬е»ҹ
(1272)е№ҙгҒ«жқұеұұеӨ§и°·гҒ®ең°(зҸҫзҹҘжҒ©йҷўеўғеҶ…ең°)гҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹиҰӘйёһ(1173гҖң1262)гҒ®е»ҹе ӮгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӨ§и°·е»ҹе ӮгҖҚгҒҢеҺҹеһӢгҒ§гҖҒе®Өз”ә
- 2014е№ҙ05жңҲ05ж—Ҙ 10:05
- 59дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 4
еҸӨеҜәе·ЎзӨјгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жё…жө„гҒ®йҒ“гҖҖгҖҖ10з•ӘгҖҖж…Ҳе°Ҡйҷў
пјҲ835пјү2жңҲ5ж—ҘгҒ«жӯ»еҺ»гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚз©әжө·гҒҜејҘеӢ’иҸ©и–©гҒ®йңҠеӨўгӮ’иҰӢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе»ҹе ӮгӮ’е»әз«ӢгҒ—иҮӘдҪңгҒ®ејҘеӢ’иҸ©и–©еғҸгҒЁжҜҚе…¬гҒ®йңҠгӮ’зҘҖгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ ејҘеӢ’
- 2014е№ҙ01жңҲ05ж—Ҙ 11:08
- 7дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жӯҙеҸІгӮ’жҘҪгҒ—гҒҸеӯҰгҒ¶дјҡ(^O^)гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
жӣёеҶҷеұұзӮҺдёҠгҒ®зңҹе®ҹ(^O^)
гҖҸгҒҢ еҶҶж•ҷеҜәпјҲжӣёеҶҷеұұгҒ«гҒӮгӮӢеҜәпјүгӮ’дҝ®зҗҶгҒ•гҒӣгҒҰгҒҫгҒҷ(^O^) зҒ«дәӢгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӣёеҶҷеұұзёҒиө·гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁ пј‘пј’пјҳпј–пјҲејҳе®үпјҷпјүе№ҙгҒ« е»ҹе Ӯгғ»дёЎиӯ·
- 2013е№ҙ10жңҲ28ж—Ҙ 22:17
- 45дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жё…ж°ҙи„©
е…үгҖҚгҖҢгҒҠгҒӢгҒӮгҒ•гӮ“гҖҚгҖҢдёүгҒӨгҒ®е°Ҹз¬ еҺҹж–°иӘҝгҖҚгҖҢжӯҢзў‘гҖҚгҖҢйҺ®йӯӮжӯҢгҖҚгҖҢиҫІж°‘гҒ®жӯҢгҖҚгҖҢе»ҹе Ӯй ҢгҖҚгҖҢеҜҢеЈ«еұұгҒ®и©©гҖҚгҖҢз„”гҒ®жӯҢгҖҚгҖҢжҜӣйҠӯгҒ®дёүгҒӨгҒ®и©©гҖҚгҖҢеӣӣгҒӨгҒ®гҒҶгҒҹвҖ•жҹіе·қ
- 14дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
еҚ—зҙҖгҒ®ж—…гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
ж…Ҳе°Ҡйҷў
гҒ®жҜҚгҒҜжүҝе’Ңпј’(835)е№ҙпј’жңҲпј•ж—ҘгҒ«жӯ»еҺ»гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚз©әжө·гҒҜејҘеӢ’иҸ©и–©гҒ®йңҠеӨўгӮ’иҰӢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе»ҹе ӮгӮ’е»әз«ӢгҒ—иҮӘдҪңгҒ®ејҘеӢ’иҸ©и–©еғҸгҒЁжҜҚе…¬гҒ®йңҠгӮ’зҘҖгҒЈгҒҹгҒЁи¬ӮгӮҸгӮҢгҖҒејҘеӢ’
- 2012е№ҙ05жңҲ05ж—Ҙ 19:07
- 76дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 6
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸ幕жң«гғ»жҳҺжІ»гҒҢеҘҪгҒҚгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
з«ңйҰ¬гҒЁж…ҺеӨӘйғҺ
е‘ЁеҜҶгҖҒе»ҹе ӮгҒ®и«–гҒ«иҖҗгӮҶгӮӢиҖ…гҒҜй•·е·һгҒ®жЎӮе°Ҹдә”йғҺгҖӮиғҶз•ҘжңүгӮҠгҖҒе…өгҒ«иҮЁгҒҝгҒҰжғ‘гҒҜгҒҡгҖҒж©ҹгӮ’иҰӢгҒҰеӢ•гҒҚгҖҒеҘҮгӮ’дјјгҒҰдәәгҒ«еӢқгҒӨиҖ…гҒҜй«ҳжқүжқұиЎҢгҖҒжҳҜгӮҢдәҰжҙӣиҘҝгҒ®дёҖеҘҮжүҚгҖӮе…¶д»–
- 2011е№ҙ12жңҲ07ж—Ҙ 20:21
- 9892дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
- 4
жҡҰгҖҒдәҢеҚҒеӣӣзҜҖж°—гӮ’е®ҡжңҹй…ҚдҝЎгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј‘пј‘жңҲпј’пјҳж—ҘгҖҢиҰӘйёһиҒ–дәәеҝҢгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ®еӨ§и°·гҒ®ең°гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«е»ҹе ӮгҒҢе»әгҒҰгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢзҸҫеңЁгҒ®зңҹе®—жң¬е»ҹпјҲжқұжң¬йЎҳеҜәпјүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж—ҘгҖҒиҰӘзҫ…иҒ–дәәеҝҢжі•иҰҒгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ гҖҖ вҖ»иҰӘйёһгҖҢж„ҡзҰҝйҲ”гҖҚгӮҲгӮҠ ж„ҡзҰҝ
- 2011е№ҙ11жңҲ25ж—Ҙ 00:31
- 728дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
дёӯеӣҪеҸІгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҺж·®еҚ—еӯҗгҖҸдәәй–“иЁ“гҖҖ24
ж—ҘдёҚж„ҸгҒ«йЈўгҒҲгҒҹиҷҺгҒ«еҮәдјҡгҒ„гҖҒд№ӢгҒ«ж®әгҒ•гӮҢгҒҰйЈҹгӮҸгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮејөжҜ…гҒҜжҒӯ敬гҒӘжҢҜгӮӢиҲһгҒ„гӮ’еҘҪгҒҝгҖҒе®®ж®ҝгғ»е»ҹе ӮгӮ’йҖҡгӮҠйҒҺгҒҺгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜеҝ…гҒҡе°Ҹиө°гӮҠгҒ«гҒӘгӮҠпјҢйҮҢй–ҖгҒҢйҖҡиЎҢгҒҷгӮӢдәәгҒ§гҖҒж··йӣ‘
- 2011е№ҙ08жңҲ02ж—Ҙ 10:11
- 1207дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жӯҙеҸІгӮ’жҘҪгҒ—гҒҸеӯҰгҒ¶дјҡ(^O^)гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҺйЎ•еҰӮгҖҸдёҠдәәгҒ®з”ҹж¶Ҝ?(^O^)
й–Җе Ӯ)гҒ®еҲҘгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹеҮҶй–Җи·Ўгғ»и„Үй–Җи·ЎгҒ®е‘јз§°гӮӮз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹ(^O^) жң¬йЎҳеҜәгҒҢеғ§дҪҚгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒ第3代гҖҺиҰҡеҰӮгҖҸдёҠдәәгҒ®жҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҒ§гҒҷ(^O^) еӨ§и°·е»ҹе Ӯ
- 2011е№ҙ01жңҲ19ж—Ҙ 09:57
- 45дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
дёҚзҹҘзҒ«йҫҚйҰ¬дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҢе…ҲжҶӮеҫҢжҘҪгҖҚзӨҫдјҡеӨүеҢ–пјҲе…ҶеҖҷпјүгӮ’гҒ©гҒҶиҰӢгӮӢгҒӢгҖҒгғӘгғјгғҖгғјгҒ®иІ¬д»»гҒҜеӨ§гҒҚгҒ„
гҒҶж”ҝ治家гҒҢжӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгҖҢеІійҷҪжҘјиЁҳгҖҚпјҲгҒҢгҒҸгӮҲгҒҶгӮҚгҒҶгҒҚпјүгҒ®ж–Үз« гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮиҢғд»Іж·№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–ҮжӣёгӮ’ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зөҗгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ гҖҢе»ҹе ӮгҒ®й«ҳгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҚігҒЎж°‘гӮ’жҶӮгҒ„гҖҒжұҹж№–
- 2011е№ҙ01жңҲ13ж—Ҙ 10:44
- 684дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
еҝғгӮ’иӮІгҒҰгӮӢиЁҖи‘үгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
гҖҢе…ҲжҶӮеҫҢжҘҪгҖҚзӨҫдјҡеӨүеҢ–пјҲе…ҶеҖҷпјүгӮ’гҒ©гҒҶиҰӢгӮӢгҒӢгҖҒгғӘгғјгғҖгғјгҒ®иІ¬д»»гҒҜеӨ§гҒҚгҒ„
гҒҶж”ҝ治家гҒҢжӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгҖҢеІійҷҪжҘјиЁҳгҖҚпјҲгҒҢгҒҸгӮҲгҒҶгӮҚгҒҶгҒҚпјүгҒ®ж–Үз« гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮиҢғд»Іж·№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–ҮжӣёгӮ’ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зөҗгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ гҖҢе»ҹе ӮгҒ®й«ҳгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҚігҒЎж°‘гӮ’жҶӮгҒ„гҖҒжұҹж№–
- 2011е№ҙ01жңҲ13ж—Ҙ 10:35
- 403дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
жҡҰгҖҒдәҢеҚҒеӣӣзҜҖж°—гӮ’е®ҡжңҹй…ҚдҝЎгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ
пј‘пј‘жңҲпј’пјҳж—ҘгҖҢиҰӘйёһиҒ–дәәеҝҢгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
йҒҺгҒҺгҒҰгҒӢгӮүдә¬йғҪгҒёжҲ»гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®й ғгҖҒгҖҢйЎ•жө„еңҹзңҹе®ҹж•ҷиЎҢиЁјж–ҮйЎһгҖҚгҒҢе®ҢжҲҗгҖӮејҳй•·пј’е№ҙпјҲпј‘пј’пј–пј’пјүпј‘пј‘жңҲпј’пјҳж—ҘгҖҒпјҷпјҗе№ҙгҒ®з”ҹж¶ҜгӮ’й–үгҒҳгҖҒдә¬йғҪгҒ®еӨ§и°·гҒ®ең°гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«е»ҹе Ӯ
- 2010е№ҙ11жңҲ25ж—Ҙ 10:45
- 728дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘ
- ең°еҹҹ
- еҗҢе№ҙд»Ј
- и¶Је‘і
- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’
- гӮІгғјгғ
- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ
- йҹіжҘҪ
- гӮ№гғқгғјгғ„
- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі
- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә
- гҒҠ笑гҒ„
- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„
- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ
- еӯҰж Ў
- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“
- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬
- жҳ з”»
- гӮўгғјгғҲ
- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶
- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ
- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ
- ж—…иЎҢ
- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ
- еҚ гҒ„
- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ
- гҒқгҒ®д»–
еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ