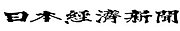今日本の政治・経済で一番の論点として昇るのは、所謂「小泉改革」の評価だと思います。
単純に「小泉改革」と言っても漠然としていますので、論点として、A規制緩和、B民営化(主に郵政)、C公共事業の削減を挙げておきたいと思います。
無論これだけでも抽象的ですので、?具体的な事例・政策、?どのような考え方で当該政策が行われたと考えるか?、?自分の考え(改革に対する賛否)を支える自分なりの考え方、を挙げていただくと議論がしやすいかと思います。?と?の違いは、?は当時の政策担当者が考えていたと思われる政策の妥当性・根拠で、?は今自分が考える?に対する根拠と考えてもらえれば分かりやすいと思います。
言いだしっぺなので、一応自分の考え方を書きますと、
A規制緩和について
?規制緩和とは、それまで業界を縛っていた供給調整的な政策を改め、所謂事業の許可制、認可制等を改め、新規参入を促進する政策です。具体的な事例としては、タクシー業者の参入制限が挙げられます。
?当時においては、極めて限られた業者間でタクシーのサービスが供給されており、謂わば既得権益化していた。ここに意欲的な新規参入業者が参入し、新しいサービスや良質なサービスを提供することにより、業界内のダイナミズムが生まれて競争が起こり、消費者の便益が増すと考えられた。
?私は、事業者間の競争により、淘汰されて失業者が発生する可能性はあると思う。しかし、それは一時的なもので、例えばA社が倒産してB氏が失業したとしても、事業に成功しているC社に雇用されれば問題ないはずである。
何故、B氏はC社に雇用されないのか。それは例えば雇用慣行(中途採用に消極的)とか、労働条件(B氏は家族持ちで借金を抱えており、C社の低賃金では働けない)の問題であったりする。
しかし、それらはいずれも規制緩和の問題点ではなく、労働法制の問題であったり、わが国経済の他の論点で扱うべき問題である。雇用慣行についてはある意味で、年功序列と言うものが新規参入を許さない会社内部の雇用慣行であるとも言えるし、労働条件は労働法制の問題である。
もし規制を緩和しなくても、長期的には業界自体が沈没していく。だとしたら、意欲的な新規参入業者が参入して業界を改革するチャンスを摘み取るべきではない。むしろ積極的に新規参入を推進し、業界内部の改革を進めるべきである。
また業績を伸ばす企業ほど内部の優秀な人材に手厚く報いるはずであり、人材を軽んずる企業からは人材が流出してその企業は淘汰されるはずである。能力が低い人々は、そのような労働生活を長期に続けることは、その人の人生について損失であり、より生産的な生活を指向するインセンティブが与えられるべきである。タクシー業界から一念発起して全く違う事業に踏み出すのも手である。そのための支援プログラムを、むしろ「競争促進政策」の一環として創り出すべきである。
とまあ、こんな感じで。分かりやすくAとか?とか書きましたが、一つの提案として受け取ってください。全く関係なく、大上段から「小泉改革とは!!」と始めて頂いても結構です。
単純に「小泉改革」と言っても漠然としていますので、論点として、A規制緩和、B民営化(主に郵政)、C公共事業の削減を挙げておきたいと思います。
無論これだけでも抽象的ですので、?具体的な事例・政策、?どのような考え方で当該政策が行われたと考えるか?、?自分の考え(改革に対する賛否)を支える自分なりの考え方、を挙げていただくと議論がしやすいかと思います。?と?の違いは、?は当時の政策担当者が考えていたと思われる政策の妥当性・根拠で、?は今自分が考える?に対する根拠と考えてもらえれば分かりやすいと思います。
言いだしっぺなので、一応自分の考え方を書きますと、
A規制緩和について
?規制緩和とは、それまで業界を縛っていた供給調整的な政策を改め、所謂事業の許可制、認可制等を改め、新規参入を促進する政策です。具体的な事例としては、タクシー業者の参入制限が挙げられます。
?当時においては、極めて限られた業者間でタクシーのサービスが供給されており、謂わば既得権益化していた。ここに意欲的な新規参入業者が参入し、新しいサービスや良質なサービスを提供することにより、業界内のダイナミズムが生まれて競争が起こり、消費者の便益が増すと考えられた。
?私は、事業者間の競争により、淘汰されて失業者が発生する可能性はあると思う。しかし、それは一時的なもので、例えばA社が倒産してB氏が失業したとしても、事業に成功しているC社に雇用されれば問題ないはずである。
何故、B氏はC社に雇用されないのか。それは例えば雇用慣行(中途採用に消極的)とか、労働条件(B氏は家族持ちで借金を抱えており、C社の低賃金では働けない)の問題であったりする。
しかし、それらはいずれも規制緩和の問題点ではなく、労働法制の問題であったり、わが国経済の他の論点で扱うべき問題である。雇用慣行についてはある意味で、年功序列と言うものが新規参入を許さない会社内部の雇用慣行であるとも言えるし、労働条件は労働法制の問題である。
もし規制を緩和しなくても、長期的には業界自体が沈没していく。だとしたら、意欲的な新規参入業者が参入して業界を改革するチャンスを摘み取るべきではない。むしろ積極的に新規参入を推進し、業界内部の改革を進めるべきである。
また業績を伸ばす企業ほど内部の優秀な人材に手厚く報いるはずであり、人材を軽んずる企業からは人材が流出してその企業は淘汰されるはずである。能力が低い人々は、そのような労働生活を長期に続けることは、その人の人生について損失であり、より生産的な生活を指向するインセンティブが与えられるべきである。タクシー業界から一念発起して全く違う事業に踏み出すのも手である。そのための支援プログラムを、むしろ「競争促進政策」の一環として創り出すべきである。
とまあ、こんな感じで。分かりやすくAとか?とか書きましたが、一つの提案として受け取ってください。全く関係なく、大上段から「小泉改革とは!!」と始めて頂いても結構です。
|
|
|
|
コメント(144)
>ぴぃすさん
ファンダメンタルズ fundamentalsつまり、経済成長の基礎的条件という意味ですが、投資、雇用、消費などの諸要因をさすのだと思います。一応私なりの考えですが。
ぴいすさんの記述では、これをどのように高めるかの方策が分かりません。ひょっとしたら私とは違うファンダメンタルズの考え方をしているのかもしれませんので、併せて教えてください。
仰られている内容は、記述にファンダメンタルズという単語が含まれているだけで、ファンダメンタルズの内容には触れていません。
>椿さん
ご指摘のニュースは経済政策そのものではないですが、一応重要なニュースですね。ただ小泉改革そのものではなく、小泉氏個人の資質に疑問を持たれているようですね。
小泉氏はもともと小選挙区制には反対だったように聞いています。小選挙区制には選挙制度としては強い政党のリーダーシップが反映されるが、逆に少数意見が無視される。大選挙区制・中選挙区制は少数意見が反映されるが、小党分立になりやすく、政局が流動的になると言われていますね。
今までの椿さんの御論旨ですと、むしろ小選挙区制のままの方が一回の選挙で多数を握れますので、増税に持ち込みやすいようにも思えます(郵政選挙がいい例ですが)。中選挙区制になるとむしろ小党分立で決め手がないという状況になりやすいので、これをもって増税を念頭にした選挙制度の改変とは必ずしも言えないと思います。
また、政府の無駄を省いて財政の構造改革を行い、財政再建の前提を作った後、最終的には増税はやむをえないと思いますよ。問題はその計算の基礎をどこに設けるかで、現状の政府の状況でそれを計算するのはおかしいとは思いますが。
ファンダメンタルズ fundamentalsつまり、経済成長の基礎的条件という意味ですが、投資、雇用、消費などの諸要因をさすのだと思います。一応私なりの考えですが。
ぴいすさんの記述では、これをどのように高めるかの方策が分かりません。ひょっとしたら私とは違うファンダメンタルズの考え方をしているのかもしれませんので、併せて教えてください。
仰られている内容は、記述にファンダメンタルズという単語が含まれているだけで、ファンダメンタルズの内容には触れていません。
>椿さん
ご指摘のニュースは経済政策そのものではないですが、一応重要なニュースですね。ただ小泉改革そのものではなく、小泉氏個人の資質に疑問を持たれているようですね。
小泉氏はもともと小選挙区制には反対だったように聞いています。小選挙区制には選挙制度としては強い政党のリーダーシップが反映されるが、逆に少数意見が無視される。大選挙区制・中選挙区制は少数意見が反映されるが、小党分立になりやすく、政局が流動的になると言われていますね。
今までの椿さんの御論旨ですと、むしろ小選挙区制のままの方が一回の選挙で多数を握れますので、増税に持ち込みやすいようにも思えます(郵政選挙がいい例ですが)。中選挙区制になるとむしろ小党分立で決め手がないという状況になりやすいので、これをもって増税を念頭にした選挙制度の改変とは必ずしも言えないと思います。
また、政府の無駄を省いて財政の構造改革を行い、財政再建の前提を作った後、最終的には増税はやむをえないと思いますよ。問題はその計算の基礎をどこに設けるかで、現状の政府の状況でそれを計算するのはおかしいとは思いますが。
>椿三十郎さんへ
> 民間が年棒制の職員が増えている状態で、公務員だけが一人当たり総労務費が闇になっているのは、どうでしょうか?公務員は税金から給料が出ているので、外交や防衛に関する国家機密とすべき問題以外は情報公開するべきだと思います。
国が十分な情報を開示していないので、椿さんが国家公務員の一人当たり総労務費を総務省に情報開示請求してはいかがでしょうか。是非、結果を教えて下さい。
私は、民間企業に勤務する経験から企業でも総労務費、平均一人当たり人件費はむずかしいと述べただけです。国がどんな数字をどんな根拠ですか大変、興味があります。
> 一般会計から特別会計など分けて、国民の代表の議員にも議論させないような予算が大半などという状態は異常です。
これは全く同感。塩爺の母屋で茶漬けをすすり、離れですきやきを食べるのはね。先日の日経新聞ではそれも小泉改革ですこしは改善されましたがまだ特別会計が大きすぎますね。
>出張費名目の闇給与が特別会計から出ているという話もあり説明義務があると思いますが。
椿さん、出張費名目の闇給与が特別会計から出ているという話が本当なら、マスコミに通報したらどうですか?本当なら社会部が張り切って報道してくれます。政府が説明義務を果たしていないのなら、総務省に情報開示請求してみてはいかがですか。
> 民間が年棒制の職員が増えている状態で、公務員だけが一人当たり総労務費が闇になっているのは、どうでしょうか?公務員は税金から給料が出ているので、外交や防衛に関する国家機密とすべき問題以外は情報公開するべきだと思います。
国が十分な情報を開示していないので、椿さんが国家公務員の一人当たり総労務費を総務省に情報開示請求してはいかがでしょうか。是非、結果を教えて下さい。
私は、民間企業に勤務する経験から企業でも総労務費、平均一人当たり人件費はむずかしいと述べただけです。国がどんな数字をどんな根拠ですか大変、興味があります。
> 一般会計から特別会計など分けて、国民の代表の議員にも議論させないような予算が大半などという状態は異常です。
これは全く同感。塩爺の母屋で茶漬けをすすり、離れですきやきを食べるのはね。先日の日経新聞ではそれも小泉改革ですこしは改善されましたがまだ特別会計が大きすぎますね。
>出張費名目の闇給与が特別会計から出ているという話もあり説明義務があると思いますが。
椿さん、出張費名目の闇給与が特別会計から出ているという話が本当なら、マスコミに通報したらどうですか?本当なら社会部が張り切って報道してくれます。政府が説明義務を果たしていないのなら、総務省に情報開示請求してみてはいかがですか。
>ぴぃすさん
ルービンやグリーンスパンは、この議論とは何も関係がありませんよ。
アメリカはファンダメンタルズが強いから云々と仰りますが、なぜアメリカはファンダメンタルズが強くて日本は弱いのでしょうか?ファンダメンタルズの意味が分からなくては議論になりません。
ファンダメンタルズという単語を繰り返し使われていますが、その意味がまったく説明されていません。説明するのに疲れたと仰いますが、全然説明になっていませんよ。
あと細かい点ですが、句読点が打たれていないので文章が読みづらく、意味が汲み取りづらいです。読んでるこちらのほうが疲れてきます。
読んでいて思うのは、単純にアメリカは基本的国力(?)のようなものが強くて、経済が発展するが、日本は基本的国力のようなものが弱いので、規制緩和しても勝てないんだ、ということが仰いたいのかなとも思います。
もしそうだとしたら「アメリカは強いから強くて、日本は弱いから弱い」と言っているようなもので、単に思考停止に陥っているだけです。アメリカの強さが何に基づくものなのかをきちんと分析して、それを日本の発展のために生かすという思考に欠けています。
それは野球の試合にどうしても勝てなくて、相手チームのことを「体が大きいから強いんだ」とか「あんなに足が速いのはズルイ」とか言っているのと、レヴェル的には違いがありません。結局自分の怠惰を糊塗するための言い訳に過ぎないですから。
ルービンやグリーンスパンは、この議論とは何も関係がありませんよ。
アメリカはファンダメンタルズが強いから云々と仰りますが、なぜアメリカはファンダメンタルズが強くて日本は弱いのでしょうか?ファンダメンタルズの意味が分からなくては議論になりません。
ファンダメンタルズという単語を繰り返し使われていますが、その意味がまったく説明されていません。説明するのに疲れたと仰いますが、全然説明になっていませんよ。
あと細かい点ですが、句読点が打たれていないので文章が読みづらく、意味が汲み取りづらいです。読んでるこちらのほうが疲れてきます。
読んでいて思うのは、単純にアメリカは基本的国力(?)のようなものが強くて、経済が発展するが、日本は基本的国力のようなものが弱いので、規制緩和しても勝てないんだ、ということが仰いたいのかなとも思います。
もしそうだとしたら「アメリカは強いから強くて、日本は弱いから弱い」と言っているようなもので、単に思考停止に陥っているだけです。アメリカの強さが何に基づくものなのかをきちんと分析して、それを日本の発展のために生かすという思考に欠けています。
それは野球の試合にどうしても勝てなくて、相手チームのことを「体が大きいから強いんだ」とか「あんなに足が速いのはズルイ」とか言っているのと、レヴェル的には違いがありません。結局自分の怠惰を糊塗するための言い訳に過ぎないですから。
ランスロさん
「日本郵政を民営化〜結局一連の主張は〜モラトリアムを与えているとしか思えません。〜その経費は税金から捻出される〜失業保険制度などを〜民営化する前も〜失業対策とは関係ないはずです。」
全ての失業が前職と同じ職種につけるとは限りません。一部の失業者が自分の畑ではない職業しか選択肢が無くなった場合どうなるのでしょうか?定職に就けずに浮浪者になる可能性が高いのではありませんか?それが経済の低迷に影響を与えているのであるならば、税金から捻出されても問題がないのではないかと思います。失業保険制度を活用している状態で失業率は何%でしょうか?1930年代頃アメリカでニューディール政策が出て経済が上向いたという事例があります。でしたら公共事業で一年間という契約で採用して、その期間営業という畑を耕しながら就職活動するシステムがあってもいいと思います。
「国営時に〜民営化しても問題ないじゃないですか?〜国の援助を受けながら〜競争原理が狂うことから、民業圧迫が問題になるんですよね?」
無理に民営化する必要がありません。民営化時は250億の黒字だったと思います。それで国の援助を受けているのでしょうか?競争原理が狂わないように透明性を図ればいいだけだと思います。
「結局のところ〜結局一時的に雇用を増やしてもしょうがない。〜持続可能な雇用を創出すべきだ。と反論しているのです。」
2007年度の厚生省の予算は約22兆ありました。一時的な雇用対策ではなく、持続可能な雇用対策になると思います。
郵政を国有化して〜結局麻生政権の特別給付金と発想は変わらないのではありませんか?〜公平性が確保されて、まだ控えめのようにさえ思えます。〜郵政は国の財産で〜利益を受けるのは雇用されるごく一部の人間だけです。」
企業収益とは何でしょうか?簡単に言うと営業収益と資産運用で成り立っています。一部の企業は資産運用だけで成り立っていると思います。ファンダメンタルズとは何でしょうか?雇用・物価・住宅・景気・個人消費・企業活動と私は思っています。特別給付金は個人消費の小売売上高・物価の消費者物価指数と生産者物価指数と貿易収支を刺激する名法案であり、ファンダメンタルズを刺激する案は間違っていません。雇用が促進し経済が高度成長すればそれでいいのではありませんか?
「日本郵政を民営化〜結局一連の主張は〜モラトリアムを与えているとしか思えません。〜その経費は税金から捻出される〜失業保険制度などを〜民営化する前も〜失業対策とは関係ないはずです。」
全ての失業が前職と同じ職種につけるとは限りません。一部の失業者が自分の畑ではない職業しか選択肢が無くなった場合どうなるのでしょうか?定職に就けずに浮浪者になる可能性が高いのではありませんか?それが経済の低迷に影響を与えているのであるならば、税金から捻出されても問題がないのではないかと思います。失業保険制度を活用している状態で失業率は何%でしょうか?1930年代頃アメリカでニューディール政策が出て経済が上向いたという事例があります。でしたら公共事業で一年間という契約で採用して、その期間営業という畑を耕しながら就職活動するシステムがあってもいいと思います。
「国営時に〜民営化しても問題ないじゃないですか?〜国の援助を受けながら〜競争原理が狂うことから、民業圧迫が問題になるんですよね?」
無理に民営化する必要がありません。民営化時は250億の黒字だったと思います。それで国の援助を受けているのでしょうか?競争原理が狂わないように透明性を図ればいいだけだと思います。
「結局のところ〜結局一時的に雇用を増やしてもしょうがない。〜持続可能な雇用を創出すべきだ。と反論しているのです。」
2007年度の厚生省の予算は約22兆ありました。一時的な雇用対策ではなく、持続可能な雇用対策になると思います。
郵政を国有化して〜結局麻生政権の特別給付金と発想は変わらないのではありませんか?〜公平性が確保されて、まだ控えめのようにさえ思えます。〜郵政は国の財産で〜利益を受けるのは雇用されるごく一部の人間だけです。」
企業収益とは何でしょうか?簡単に言うと営業収益と資産運用で成り立っています。一部の企業は資産運用だけで成り立っていると思います。ファンダメンタルズとは何でしょうか?雇用・物価・住宅・景気・個人消費・企業活動と私は思っています。特別給付金は個人消費の小売売上高・物価の消費者物価指数と生産者物価指数と貿易収支を刺激する名法案であり、ファンダメンタルズを刺激する案は間違っていません。雇用が促進し経済が高度成長すればそれでいいのではありませんか?
椿 三十郎さん
まず元自民党幹事長中川 秀直氏の政策についての提言の書き込みありがとうございす。私の率直な意見を述べさせてもらいます。
(1)天下り禁止
天下りの禁止をいくら言ったところであるのが現実だと思います。ここはいっそのこと官僚を無くし副大臣を増やしたらどうかと思います。政治家ならキャリアと少しの手当があれば問題ないと思います。
(2)国会議院削減・公務員給料削減
たしか小泉元総理が衆議員だけにして定員を500人にしたらどうかと提言していたと思います。私は法律の元での平等に反する事であり、強行採決しかなくなり十分な議論ができなくなるのでこの考えには反対です。でしたら衆参議両議院の定員数を両議院共10人減らすほうが現実的だと思います。
(3)埋蔵金ゼロ
麻生総理の75兆円の景気対策は埋蔵金から用意されたものと日本経済新聞に載っていたと思います。その政策を支持すものとに社会保障制度改革
詳しい内容がわかりませんので発言を控えさせてもらいます。
(5)景気回復(名目3%成長経済の実現)
3%では足りないと思います。実質GDPが5%以上ほしいです。麻生総理だからこそ実質GDPを5%以上にする事が出来ると思います。
まず元自民党幹事長中川 秀直氏の政策についての提言の書き込みありがとうございす。私の率直な意見を述べさせてもらいます。
(1)天下り禁止
天下りの禁止をいくら言ったところであるのが現実だと思います。ここはいっそのこと官僚を無くし副大臣を増やしたらどうかと思います。政治家ならキャリアと少しの手当があれば問題ないと思います。
(2)国会議院削減・公務員給料削減
たしか小泉元総理が衆議員だけにして定員を500人にしたらどうかと提言していたと思います。私は法律の元での平等に反する事であり、強行採決しかなくなり十分な議論ができなくなるのでこの考えには反対です。でしたら衆参議両議院の定員数を両議院共10人減らすほうが現実的だと思います。
(3)埋蔵金ゼロ
麻生総理の75兆円の景気対策は埋蔵金から用意されたものと日本経済新聞に載っていたと思います。その政策を支持すものとに社会保障制度改革
詳しい内容がわかりませんので発言を控えさせてもらいます。
(5)景気回復(名目3%成長経済の実現)
3%では足りないと思います。実質GDPが5%以上ほしいです。麻生総理だからこそ実質GDPを5%以上にする事が出来ると思います。
>株侍さん
PCが復旧しました。で、万全を期して反論を。
とりあえず、個別の論点で反論できる部分は反論して、まとめられる反論は最後にまとめて反論します。いい加減長文めんどくさいです。
>無理に民営化する必要がありません。民営化時は250億の黒字だったと思いま
>す。それで国の援助を受けているのでしょうか?競争原理が狂わないように透
>明性を図ればいいだけだと思います。
民営化する理由については何度も書いています。何度も言うようですが、人の言っていることをちゃんと理解して反論しなさい。何度も同じことを繰り返すほど優しい人は少ないですよ。あと透明化したらなぜ競争原理が狂わなくなるのですか?
>2007年度の厚生省の予算は約22兆ありました。一時的な雇用対策ではなく、持
>続可能な雇用対策になると思います。
持続可能とは予算の額とは関係ありません。国の補助に頼るのではなく、自立して経営することができるということを意味しているのです。議論の出発点からして間違っています。
それ以外の部分については、所謂「ケインズ理論」の何たるかが問題になると思います。この議論は結構核心部分ですね。
株侍さんご指摘のニューディール政策は、ケインズの理論に理論的主柱を求めて行われました。そして「何でもいいから国が財政出動して、金をばら撒けば、回りまわって経済はよくなるんだ!」という理屈が蔓延しました。麻生首相もそういう理解でしょう。しかし、そういうケインズ理解は誤っていると思います。
ケインズ自身も誤解について、一定の責任があるようです。「分かりやすく言えば、何でもいいから仕事を与えて給料を支払えば、それなりの効果があるということです。」という趣旨の発言をしているようですから。しかり「分かりやすく」言ってしかも「それなり」という一般大衆向けの発言が、誇大解釈されてしまっている点に問題があると思います。
所謂財政出動を説いたのは、彼の主著「雇用と利子の一般理論」ですが、その前著「貨幣論」では、むしろ古典派的な金融政策を主張していました。つまり財政出動は、金利が下がりすぎて金融政策が効果がなくなった(所謂流動性の罠)段階に限定された対応だったのです。財政出動によって経営者の期待売上収入を高め、それにより経営者の設備投資意欲、雇用意欲を高めるための呼び水としての財政出動です。ケインズは経営者の心理を綿密に計算して理論を立てており「金をばら撒けば云々」といった単純なものではありません。
より具体的に言うと、不況時に緊縮財政をとって不況になればなるほど財政を収縮させて負債を圧縮していたケインズの時代とは異なり、現在は散々ばら撒いてそれがまったく効果がなかったことが実証されてしまっている時代です。ケインズの時代は財政出動による経済拡大の期待度合いが大きかった、つまり財政出動の効果が高かったのに対し、今は殆ど効果がないのは実証済みです。それは為替や国際金融の問題もありますが、なによりも財政出動が結局特定の人々の利益にしか結びついていないことが分かっているからです。
また給付金についても、年金不安を抱え、しかも世界的な経済体制の変化で日本経済が対応できていないという現状があり、その状況下で金を配られても、将来不安から消費に回さないだろうから、殆ど効果がないということです。一般国民にあれだけ不評なのだから、これはもはや間違いないです。
PCが復旧しました。で、万全を期して反論を。
とりあえず、個別の論点で反論できる部分は反論して、まとめられる反論は最後にまとめて反論します。いい加減長文めんどくさいです。
>無理に民営化する必要がありません。民営化時は250億の黒字だったと思いま
>す。それで国の援助を受けているのでしょうか?競争原理が狂わないように透
>明性を図ればいいだけだと思います。
民営化する理由については何度も書いています。何度も言うようですが、人の言っていることをちゃんと理解して反論しなさい。何度も同じことを繰り返すほど優しい人は少ないですよ。あと透明化したらなぜ競争原理が狂わなくなるのですか?
>2007年度の厚生省の予算は約22兆ありました。一時的な雇用対策ではなく、持
>続可能な雇用対策になると思います。
持続可能とは予算の額とは関係ありません。国の補助に頼るのではなく、自立して経営することができるということを意味しているのです。議論の出発点からして間違っています。
それ以外の部分については、所謂「ケインズ理論」の何たるかが問題になると思います。この議論は結構核心部分ですね。
株侍さんご指摘のニューディール政策は、ケインズの理論に理論的主柱を求めて行われました。そして「何でもいいから国が財政出動して、金をばら撒けば、回りまわって経済はよくなるんだ!」という理屈が蔓延しました。麻生首相もそういう理解でしょう。しかし、そういうケインズ理解は誤っていると思います。
ケインズ自身も誤解について、一定の責任があるようです。「分かりやすく言えば、何でもいいから仕事を与えて給料を支払えば、それなりの効果があるということです。」という趣旨の発言をしているようですから。しかり「分かりやすく」言ってしかも「それなり」という一般大衆向けの発言が、誇大解釈されてしまっている点に問題があると思います。
所謂財政出動を説いたのは、彼の主著「雇用と利子の一般理論」ですが、その前著「貨幣論」では、むしろ古典派的な金融政策を主張していました。つまり財政出動は、金利が下がりすぎて金融政策が効果がなくなった(所謂流動性の罠)段階に限定された対応だったのです。財政出動によって経営者の期待売上収入を高め、それにより経営者の設備投資意欲、雇用意欲を高めるための呼び水としての財政出動です。ケインズは経営者の心理を綿密に計算して理論を立てており「金をばら撒けば云々」といった単純なものではありません。
より具体的に言うと、不況時に緊縮財政をとって不況になればなるほど財政を収縮させて負債を圧縮していたケインズの時代とは異なり、現在は散々ばら撒いてそれがまったく効果がなかったことが実証されてしまっている時代です。ケインズの時代は財政出動による経済拡大の期待度合いが大きかった、つまり財政出動の効果が高かったのに対し、今は殆ど効果がないのは実証済みです。それは為替や国際金融の問題もありますが、なによりも財政出動が結局特定の人々の利益にしか結びついていないことが分かっているからです。
また給付金についても、年金不安を抱え、しかも世界的な経済体制の変化で日本経済が対応できていないという現状があり、その状況下で金を配られても、将来不安から消費に回さないだろうから、殆ど効果がないということです。一般国民にあれだけ不評なのだから、これはもはや間違いないです。
続きです。
さらにケインズ理論にはもう一つ「乗数理論」があります。それは財政出動により支出された資金は、経済全体に波及し、最終的には莫大な経済効果となって、国庫に戻ってくるというものです。これは財政に関して、特定の業者に恩恵を与えるものだという批判について、「いや最終的に経済全体に波及し、国民全体が利益を受けるのだ」という反論であったと思います。
ケインズの時代のように、経済の規模が小さく単純であった場合はそれもありえたかもしれませんが、現代はそうではありません。経済は複雑化し、しかも人々はすでに多くの財政出動の結果(失敗)を見ています。結果それが特定業種の延命に過ぎなかったことも。
つまり「乗数」を働かせるには、より波及効果の大きい業種について、的確に財政出動をしなければならないのです。そういった意味では財政出動の質が問われています。それはもっとも経済活動が盛んな分野で、今後の発展が見込める分野です。そのほうが波及する範囲は広いですから。
オバマ政権はグリーンディールを主張していますね。日本の民主党も環境対策に財政出動することを主張してます。それは今後需要が見込まれ、発展が見込める分野に呼び水的に財政出動することが必要だという意味です。果たして環境がベストな分野かどうかは分かりませんが(有力な候補の一つではあります)、オバマ政権や民主党のほうがケインズの発想を正確に受け継いでいると思います。
「しかし、一定の効果はある」という反論があるかもしれません。資金をばら撒けばそれに応じて使う人がいるかもしれないのは当たり前です。しかし、売上の期待を高める必要があるのです。それは一定の効果を要求されるはずです。そして、より効果の高い選択肢を選択するのが合理的なのは言うまでもありません。政府部内でも「新規で有望な分野に投資を」といっている人は間違いなくいますが、それを首相が無視するのはなぜかという問題になります。特定の利益と結びついているため、新規分野に資金を回すという行動をとりたくない、だから意図的に効果の低い政策を行おうとしているとしか思えません。
「ケインズなんて知らねえ、日本の話をしているんだ」という反論(反論になってませんが)も、まあそういう意味不明のことを言う人もいそうですが、ケインズを離れても、単純に政府が金をばら撒けば経済が回復するのであれば、だれも苦労はしないはずです。明日からでも株侍さんは政府の財政出動担当者が勤まりますよ しかし、現実にそんなはずはありません。
しかし、現実にそんなはずはありません。
つまり現代の財政出動に求められているのは
?規制緩和による経済活動の自由を前提として
?有望で新規の革新的分野に投資を行い、民間の投資の呼び水となる
ことが求められているんです。それに対して「とりあえず金をばら撒いて雇用を確保すればいい」というのはケインズ理論ともニューディールとも関係なく、金を配れば何とかなるという単純な発想です。両者はまったく異なります。
さらに言うと、給付金は選挙目当てのばら撒きという部分も多分にありそうです。しかし、批判を受け、支持率が急落し、そこで引っ込めると選挙目当てだということが逆に明らかになるので、引っ込めるに引っ込められなくなったというだけに過ぎないんじゃないですかね。金で頬っぺた叩けば、自分たちに投票するだろうと言うことで、それにあっけなく引っかかっちゃう人もいるようですが。
追加で、椿さんとの間でアメリカの猟官制(スポイルズシステム)の是非が言われているようですが、現代のように国家が膨大な事務処理を担うような次代に、どういう認識で「官僚制度などいらない」と言えるのか、理解に苦しみますね。実際に組織に入って仕事をしてみれば、どれだけ膨大な事務処理か分かりそうなもんですが。
アメリカでは確かに政権交代するたびに政府の職員が交代しますが、何も教育も訓練も受けていない人が意味もなく政治的な繋がりだけで抜擢されるわけでなく、共和・民主両党とも然るべき人材リストを持っているんです、ある意味政党が官僚制度を担っているわけです。そうでなければ行政が崩壊しますよ。今の日本のように、官僚制度のうえに政党が乗っかっている訳ではないので、そのあたりは正確に認識されたほうがよいと思います。
さらにケインズ理論にはもう一つ「乗数理論」があります。それは財政出動により支出された資金は、経済全体に波及し、最終的には莫大な経済効果となって、国庫に戻ってくるというものです。これは財政に関して、特定の業者に恩恵を与えるものだという批判について、「いや最終的に経済全体に波及し、国民全体が利益を受けるのだ」という反論であったと思います。
ケインズの時代のように、経済の規模が小さく単純であった場合はそれもありえたかもしれませんが、現代はそうではありません。経済は複雑化し、しかも人々はすでに多くの財政出動の結果(失敗)を見ています。結果それが特定業種の延命に過ぎなかったことも。
つまり「乗数」を働かせるには、より波及効果の大きい業種について、的確に財政出動をしなければならないのです。そういった意味では財政出動の質が問われています。それはもっとも経済活動が盛んな分野で、今後の発展が見込める分野です。そのほうが波及する範囲は広いですから。
オバマ政権はグリーンディールを主張していますね。日本の民主党も環境対策に財政出動することを主張してます。それは今後需要が見込まれ、発展が見込める分野に呼び水的に財政出動することが必要だという意味です。果たして環境がベストな分野かどうかは分かりませんが(有力な候補の一つではあります)、オバマ政権や民主党のほうがケインズの発想を正確に受け継いでいると思います。
「しかし、一定の効果はある」という反論があるかもしれません。資金をばら撒けばそれに応じて使う人がいるかもしれないのは当たり前です。しかし、売上の期待を高める必要があるのです。それは一定の効果を要求されるはずです。そして、より効果の高い選択肢を選択するのが合理的なのは言うまでもありません。政府部内でも「新規で有望な分野に投資を」といっている人は間違いなくいますが、それを首相が無視するのはなぜかという問題になります。特定の利益と結びついているため、新規分野に資金を回すという行動をとりたくない、だから意図的に効果の低い政策を行おうとしているとしか思えません。
「ケインズなんて知らねえ、日本の話をしているんだ」という反論(反論になってませんが)も、まあそういう意味不明のことを言う人もいそうですが、ケインズを離れても、単純に政府が金をばら撒けば経済が回復するのであれば、だれも苦労はしないはずです。明日からでも株侍さんは政府の財政出動担当者が勤まりますよ
つまり現代の財政出動に求められているのは
?規制緩和による経済活動の自由を前提として
?有望で新規の革新的分野に投資を行い、民間の投資の呼び水となる
ことが求められているんです。それに対して「とりあえず金をばら撒いて雇用を確保すればいい」というのはケインズ理論ともニューディールとも関係なく、金を配れば何とかなるという単純な発想です。両者はまったく異なります。
さらに言うと、給付金は選挙目当てのばら撒きという部分も多分にありそうです。しかし、批判を受け、支持率が急落し、そこで引っ込めると選挙目当てだということが逆に明らかになるので、引っ込めるに引っ込められなくなったというだけに過ぎないんじゃないですかね。金で頬っぺた叩けば、自分たちに投票するだろうと言うことで、それにあっけなく引っかかっちゃう人もいるようですが。
追加で、椿さんとの間でアメリカの猟官制(スポイルズシステム)の是非が言われているようですが、現代のように国家が膨大な事務処理を担うような次代に、どういう認識で「官僚制度などいらない」と言えるのか、理解に苦しみますね。実際に組織に入って仕事をしてみれば、どれだけ膨大な事務処理か分かりそうなもんですが。
アメリカでは確かに政権交代するたびに政府の職員が交代しますが、何も教育も訓練も受けていない人が意味もなく政治的な繋がりだけで抜擢されるわけでなく、共和・民主両党とも然るべき人材リストを持っているんです、ある意味政党が官僚制度を担っているわけです。そうでなければ行政が崩壊しますよ。今の日本のように、官僚制度のうえに政党が乗っかっている訳ではないので、そのあたりは正確に認識されたほうがよいと思います。
まず先に訂正です。124の私の発言「雇用と利子の一般理論」→「雇用・利子及び貨幣の一般理論」です。基本的な文献なのにお恥ずかしい。
>椿 三十郎さん
別に猟官制が悪いと言っているわけではありませんよ。ただ、政治的な結び付きだけで政府高官に抜擢されるわけではない、それぞれの政党が有能な幹部人材のストックを持っているのだから、やはり専門的な教育を受けていないと高級官僚は務まりませんよ、と言っているだけで。
その観点から椿さんの論調にもやや疑問を感じる点が。
>それ以下の官僚はいままでどおり、優秀な東大法学部卒の方に頑張ってもらっ
>てせいぜい普通の国民には通訳がいないと分からない(笑)ような文言の文章
>を作っていただいたらとおもいます。課長・局長クラスに政治任用の人を増や
>すと、この人たちは若い官僚が作成した通訳が必要なような、意味不明な文章
>を分かりやすく書き直していただけるものと考えています。
この文章における「意味不明な文章」の意味が分からないのです。確かに政府答弁で「それは意味が通らないだろう」というような発言がありますが、法的な条文とかの話であれば、また話が違ってきます。
法律の条文は、その文言で紛争当事者の扮装を裁定する機能があります。そのため、あいまいさを許さない厳格な言葉遣いが要求されますが、それによりかえって一般の日常言語から乖離してしまうと言う現象が起きます。
私の深読みのしすぎかもしれませんが、自分が理解できないものは無価値である、という立場を取っているのであれば、それはかなり危険だと思います。
それは自分が理解できないものに対する恐怖に根差しており、用意に陰謀史観のようなものを受け入れてしまう下地になります。自分に理解できない状況が多発している状況で「これは○×の陰謀だ」と言われれば分かりやすいですから。ナチスのユダヤ人迫害の例が分かりやすいですね。
理解できないことや、専門性を要求されることに対する憎悪や嫉妬はいつの時代にもありますが、法律的な知識もかつての特定の人々にしか知らされない秘儀ではなくて、普通に学習すれば得られる知識ですし、高度な仕事については専門性は絶対に必要です。
政府の経費削減を抑える立場には大きく分けて2つの立場があると思います。
?政府の中の非合理的な業務・費用を圧縮しようと言う立場(つまり厳密な意味での政府の合理化)
?官僚はむかつく、いい大学を出た連中は嫌いだと言うレヴェルの官僚バッシング
?と?の区別は実際には難しいのですが、私は?の立場を取っていて、例えば裏金や、支出をプールして目的外の経費に流用する資金(所謂埋蔵金)とそれにかかわる経費はなくすべきだと言う立場です。
?の立場になると、単純に「官僚はむかつくし、俺たちの分からないことを偉そうにしゃべって不愉快だ。あんな連中は安月給でこき使ってやれ!!」と言うことになります。しかし、実際の官僚というか公務員の業務は、それなりに高度な専門性を必要とします。法律に基づいて業務をしますので、法解釈の知識は必要ですし、経済理論や所掌分野についての知識、そして上位者(政治家)に報告するときの分析や情報収集能力は当然必要でしょう。
その待遇を悪くすれば、優秀な人材は来なくなります。個人的な溜飲は下がるかもしれませんが、国家の機能は停滞し、サービスは劣化して、つけは国民に返ってきます。
私の考えは明確で、公務員・民間に限らず、高い専門性で高い生産性を有する仕事には、よい待遇で迎えるべきだと思います。当たり前ですが。
>椿 三十郎さん
別に猟官制が悪いと言っているわけではありませんよ。ただ、政治的な結び付きだけで政府高官に抜擢されるわけではない、それぞれの政党が有能な幹部人材のストックを持っているのだから、やはり専門的な教育を受けていないと高級官僚は務まりませんよ、と言っているだけで。
その観点から椿さんの論調にもやや疑問を感じる点が。
>それ以下の官僚はいままでどおり、優秀な東大法学部卒の方に頑張ってもらっ
>てせいぜい普通の国民には通訳がいないと分からない(笑)ような文言の文章
>を作っていただいたらとおもいます。課長・局長クラスに政治任用の人を増や
>すと、この人たちは若い官僚が作成した通訳が必要なような、意味不明な文章
>を分かりやすく書き直していただけるものと考えています。
この文章における「意味不明な文章」の意味が分からないのです。確かに政府答弁で「それは意味が通らないだろう」というような発言がありますが、法的な条文とかの話であれば、また話が違ってきます。
法律の条文は、その文言で紛争当事者の扮装を裁定する機能があります。そのため、あいまいさを許さない厳格な言葉遣いが要求されますが、それによりかえって一般の日常言語から乖離してしまうと言う現象が起きます。
私の深読みのしすぎかもしれませんが、自分が理解できないものは無価値である、という立場を取っているのであれば、それはかなり危険だと思います。
それは自分が理解できないものに対する恐怖に根差しており、用意に陰謀史観のようなものを受け入れてしまう下地になります。自分に理解できない状況が多発している状況で「これは○×の陰謀だ」と言われれば分かりやすいですから。ナチスのユダヤ人迫害の例が分かりやすいですね。
理解できないことや、専門性を要求されることに対する憎悪や嫉妬はいつの時代にもありますが、法律的な知識もかつての特定の人々にしか知らされない秘儀ではなくて、普通に学習すれば得られる知識ですし、高度な仕事については専門性は絶対に必要です。
政府の経費削減を抑える立場には大きく分けて2つの立場があると思います。
?政府の中の非合理的な業務・費用を圧縮しようと言う立場(つまり厳密な意味での政府の合理化)
?官僚はむかつく、いい大学を出た連中は嫌いだと言うレヴェルの官僚バッシング
?と?の区別は実際には難しいのですが、私は?の立場を取っていて、例えば裏金や、支出をプールして目的外の経費に流用する資金(所謂埋蔵金)とそれにかかわる経費はなくすべきだと言う立場です。
?の立場になると、単純に「官僚はむかつくし、俺たちの分からないことを偉そうにしゃべって不愉快だ。あんな連中は安月給でこき使ってやれ!!」と言うことになります。しかし、実際の官僚というか公務員の業務は、それなりに高度な専門性を必要とします。法律に基づいて業務をしますので、法解釈の知識は必要ですし、経済理論や所掌分野についての知識、そして上位者(政治家)に報告するときの分析や情報収集能力は当然必要でしょう。
その待遇を悪くすれば、優秀な人材は来なくなります。個人的な溜飲は下がるかもしれませんが、国家の機能は停滞し、サービスは劣化して、つけは国民に返ってきます。
私の考えは明確で、公務員・民間に限らず、高い専門性で高い生産性を有する仕事には、よい待遇で迎えるべきだと思います。当たり前ですが。
椿 三十郎さん
まず貴重なご意見ありがとうございます。
>>官僚を無くし〜高コストになっていると思います。
高級官僚が何人いて月収いくら支払われているかわかりません。しかし今までの報道を見る限り、貨幣価値の狂った人が多く無駄遣いばかりしているので、省の入れ替えではなく官僚を無くし、将来有望な政治家に任せたらどうかと思います。透明性も図れ、その分野のキャリアを積む事ができ一石二鳥な考えだと思います。天下りも無くなるのではないかと思います。
>>でしたら衆参両議院の〜政党助成金をやめて個人に活動費を支給したらどうでしょうか。
何に使ったか詳細にする事ができ、不正が起きなければ問題ないと私は思います。
>>3%では足りない〜GDPだと激しいインフレになると思います。
新しい産業ではなく日本を復興する為に、大企業の再生・中小企業の活性化を図ったらどうかと思います。大企業の再生があれば関連する中小企業もおのずと活性化するのではありませんか?日米共同で経済刺激対策をし平均株価を上昇させ企業を再生させるしかないと思います。現実そうなりそうになっています。アメリカは73兆円・日本は75兆円の経済刺激対策が行われます。
まず貴重なご意見ありがとうございます。
>>官僚を無くし〜高コストになっていると思います。
高級官僚が何人いて月収いくら支払われているかわかりません。しかし今までの報道を見る限り、貨幣価値の狂った人が多く無駄遣いばかりしているので、省の入れ替えではなく官僚を無くし、将来有望な政治家に任せたらどうかと思います。透明性も図れ、その分野のキャリアを積む事ができ一石二鳥な考えだと思います。天下りも無くなるのではないかと思います。
>>でしたら衆参両議院の〜政党助成金をやめて個人に活動費を支給したらどうでしょうか。
何に使ったか詳細にする事ができ、不正が起きなければ問題ないと私は思います。
>>3%では足りない〜GDPだと激しいインフレになると思います。
新しい産業ではなく日本を復興する為に、大企業の再生・中小企業の活性化を図ったらどうかと思います。大企業の再生があれば関連する中小企業もおのずと活性化するのではありませんか?日米共同で経済刺激対策をし平均株価を上昇させ企業を再生させるしかないと思います。現実そうなりそうになっています。アメリカは73兆円・日本は75兆円の経済刺激対策が行われます。
>椿 三十郎さん
>“100年に一度の経済危機”というのなら、まずは官僚といわれる人が塗炭の辛
>苦をなめてこそ、“ノブレス・オブリージュ”と言えるのではありませんか?
ノブレス・オブリージュ、知っていますよ。ラテン語で「高貴な立場にいる者の義務」ですよね。
しかし、そういった共同体への義務を持ち、また有能な人材ならそれにそぐう待遇をするのが筋ではありませんか?「お前らはエリートだ。そして今は非常時だ、だからひどい待遇で働け」というのはおかしいと思います。彼らの担っている業務は、企業で言うコア・コンピタンシーです。彼らがおかしくなったら全てがおかしくなりますよ。ノブレス・オブリージュとは、共同体から保護されている分、いざと言うとき共同体に奉仕する義務を負っているという意味であることを忘れてはなりません。椿さんも前のほうの文章で認められていますよね。
誤解のないように申し上げますが、私は官僚の天下りや渡りを認めているわけではありません。それは公的な監視が及ばない分野で、待遇を不当に膨らませる行為です。しっかりと公の範囲で、合理的な処遇をせよと言っているのです。
後段部分の引用は意味が分かりません。意味が不明瞭な引用は避けられたほうがいいともいます。
椿さんご指摘の新聞記事は、私も日経で読みました。しかし、読売と日経では、記事の書き方が微妙に違うと思います。
「人事局に組織移管、人事院総裁が拒否
人事院の谷公士総裁は21日、中央省庁の幹部人事を一元管理する「内閣人事局」への組織移管について「内閣人事局の機能が分からないのに、人事院の何を移管せよと言うのか。この問題がある限り、交渉に応ずるすべがない」と拒否した。近く予定される甘利明行政改革担当相との折衝に関しては「求められればいつでも出向くが、解決の出口が見えない」と指摘した。都内で記者団に語った。
これに先立ち谷氏は行革相に文書で「(組織移管なら)中央人事行政機関としての人事院は存続の余地がない。このような改革を国家公務員制度改革基本法は全く予定していない」と伝えた。
行革相は内閣人事局の中核組織として人事院の企画立案部門の移管を求めているが、事務折衝では人事院の反発が強く、調整が難航している。(02:31) 」
私はこの記事を、実務的な法解釈や行政の現場を知らない人間が「改革」を行っているという外見だけを示すため、いい加減な指示を出して人事院から拒否された記事だと解釈しました。実際内閣人事局がどういう機能を持つか分からなければ、人事院もどう対応していいか分からないのは当然だと思います。
麻生政権は改革を行う気など、実際は全くないのでしょうから、単なるパフォーマンスを行っているからこういうことになるのではないかと思います。私が前述した、現場の実務を知らない人間が適当なことをやると途端に業務が停滞する好例だとも思いますね。
>これから、改革を骨抜きにするつもりなのでしょうが。高級官僚の政治任用の
>時計の針は動き始めていますね。
高級官僚の政治任用は前述したように様々な論点をクリアしなければなりません。私が思うには、それほど本質的な議論ではないと思います。逆に財政健全化や規制緩和をおざなりにして、政治任用をして改革をやったふりというのが一番困ります。
むしろメインテーマの財政健全化・規制緩和を行い、その上でふさわしい公務員制度を議論すべきだと思います。天下りや渡りの問題は、政治任用の問題とはあまり関係がありませんよ。
>“100年に一度の経済危機”というのなら、まずは官僚といわれる人が塗炭の辛
>苦をなめてこそ、“ノブレス・オブリージュ”と言えるのではありませんか?
ノブレス・オブリージュ、知っていますよ。ラテン語で「高貴な立場にいる者の義務」ですよね。
しかし、そういった共同体への義務を持ち、また有能な人材ならそれにそぐう待遇をするのが筋ではありませんか?「お前らはエリートだ。そして今は非常時だ、だからひどい待遇で働け」というのはおかしいと思います。彼らの担っている業務は、企業で言うコア・コンピタンシーです。彼らがおかしくなったら全てがおかしくなりますよ。ノブレス・オブリージュとは、共同体から保護されている分、いざと言うとき共同体に奉仕する義務を負っているという意味であることを忘れてはなりません。椿さんも前のほうの文章で認められていますよね。
誤解のないように申し上げますが、私は官僚の天下りや渡りを認めているわけではありません。それは公的な監視が及ばない分野で、待遇を不当に膨らませる行為です。しっかりと公の範囲で、合理的な処遇をせよと言っているのです。
後段部分の引用は意味が分かりません。意味が不明瞭な引用は避けられたほうがいいともいます。
椿さんご指摘の新聞記事は、私も日経で読みました。しかし、読売と日経では、記事の書き方が微妙に違うと思います。
「人事局に組織移管、人事院総裁が拒否
人事院の谷公士総裁は21日、中央省庁の幹部人事を一元管理する「内閣人事局」への組織移管について「内閣人事局の機能が分からないのに、人事院の何を移管せよと言うのか。この問題がある限り、交渉に応ずるすべがない」と拒否した。近く予定される甘利明行政改革担当相との折衝に関しては「求められればいつでも出向くが、解決の出口が見えない」と指摘した。都内で記者団に語った。
これに先立ち谷氏は行革相に文書で「(組織移管なら)中央人事行政機関としての人事院は存続の余地がない。このような改革を国家公務員制度改革基本法は全く予定していない」と伝えた。
行革相は内閣人事局の中核組織として人事院の企画立案部門の移管を求めているが、事務折衝では人事院の反発が強く、調整が難航している。(02:31) 」
私はこの記事を、実務的な法解釈や行政の現場を知らない人間が「改革」を行っているという外見だけを示すため、いい加減な指示を出して人事院から拒否された記事だと解釈しました。実際内閣人事局がどういう機能を持つか分からなければ、人事院もどう対応していいか分からないのは当然だと思います。
麻生政権は改革を行う気など、実際は全くないのでしょうから、単なるパフォーマンスを行っているからこういうことになるのではないかと思います。私が前述した、現場の実務を知らない人間が適当なことをやると途端に業務が停滞する好例だとも思いますね。
>これから、改革を骨抜きにするつもりなのでしょうが。高級官僚の政治任用の
>時計の針は動き始めていますね。
高級官僚の政治任用は前述したように様々な論点をクリアしなければなりません。私が思うには、それほど本質的な議論ではないと思います。逆に財政健全化や規制緩和をおざなりにして、政治任用をして改革をやったふりというのが一番困ります。
むしろメインテーマの財政健全化・規制緩和を行い、その上でふさわしい公務員制度を議論すべきだと思います。天下りや渡りの問題は、政治任用の問題とはあまり関係がありませんよ。
>株侍さん
>新しい産業ではなく日本を復興する為に、大企業の再生・中小企業の活性化を
>図ったらどうかと思います。大企業の再生があれば関連する中小企業もおのず
>と活性化するのではありませんか?日米共同で経済刺激対策をし平均株価を上
>昇させ企業を再生させるしかないと思います。現実そうなりそうになっていま
>す。アメリカは73兆円・日本は75兆円の経済刺激対策が行われます。
たびたび思うのですが、貴方は肝心なところを隠蔽します。なぜ企業再生は○で新規産業は×なのですか?リスクマネーという点では両者はそれほど変わりません。むしろ多額の負債を負って債務超過になっている企業のほうが、回復にコストがかかります。マイナスからのスタートですから。
企業再生と言っても、どんな企業でも再生できるわけではありません。今後の事業見通しを立てて、市場から退出させるか、支援して再生するかの見極めをするのです。その意味では市場原理を前提にしているのです。魔法のようにどんな企業でも再生できるわけではありません。
>日米共同で経済刺激対策をし平均株価を上昇させ
そのための有効な経済対策として散々今まで議論してきたんじゃないですか?ここまでいくと呆れ果てて物も言えません。
経済対策が有効かどうかも分からないで、どうして「平均株価を上昇させ」なって言えるんですか?
総じていえることは、議論の仕方として、反論を受けて再反論できないと、論点をずらして違う反論をする、という態度が目に余りますよ。論点をずらしてずらして、通らなくなったら総論に戻り、反論されたら各論に戻る。不生産な議論の典型です。
そもそも一般社会で成立する議論の仕方をきちんと身につけるべきではありませんか?
>新しい産業ではなく日本を復興する為に、大企業の再生・中小企業の活性化を
>図ったらどうかと思います。大企業の再生があれば関連する中小企業もおのず
>と活性化するのではありませんか?日米共同で経済刺激対策をし平均株価を上
>昇させ企業を再生させるしかないと思います。現実そうなりそうになっていま
>す。アメリカは73兆円・日本は75兆円の経済刺激対策が行われます。
たびたび思うのですが、貴方は肝心なところを隠蔽します。なぜ企業再生は○で新規産業は×なのですか?リスクマネーという点では両者はそれほど変わりません。むしろ多額の負債を負って債務超過になっている企業のほうが、回復にコストがかかります。マイナスからのスタートですから。
企業再生と言っても、どんな企業でも再生できるわけではありません。今後の事業見通しを立てて、市場から退出させるか、支援して再生するかの見極めをするのです。その意味では市場原理を前提にしているのです。魔法のようにどんな企業でも再生できるわけではありません。
>日米共同で経済刺激対策をし平均株価を上昇させ
そのための有効な経済対策として散々今まで議論してきたんじゃないですか?ここまでいくと呆れ果てて物も言えません。
経済対策が有効かどうかも分からないで、どうして「平均株価を上昇させ」なって言えるんですか?
総じていえることは、議論の仕方として、反論を受けて再反論できないと、論点をずらして違う反論をする、という態度が目に余りますよ。論点をずらしてずらして、通らなくなったら総論に戻り、反論されたら各論に戻る。不生産な議論の典型です。
そもそも一般社会で成立する議論の仕方をきちんと身につけるべきではありませんか?
追記です。
成長率を巡ってインフレターゲット的な議論になっていますけど、私はインフレターゲットそれ自体に反対です。インフレは人為的に引き起こすことは容易くても、管理するのが困難で、インフレは国民経済を破壊し、産業を破壊します。
ですから経済対策により、経済が回復して道筋がついたら、然るべき時点で日銀は金利を引き上げるべきだと思います(この点では竹中平蔵氏とは意見を異にします)。お二人ともGDPの数字を挙げていらっしゃいますが、具体的な政策手法とそれに基づいた数字の議論がないと、GDPの数字だけを挙げても意味がないと思います。
あと株侍さんへの反論への追加ですが、企業再生は通常、リストラを伴います。当然従業員もリストラするわけで、それだけで雇用対策にはなりえません。新規事業の創出と企業再生がセットであるのが通常であると思います。
成長率を巡ってインフレターゲット的な議論になっていますけど、私はインフレターゲットそれ自体に反対です。インフレは人為的に引き起こすことは容易くても、管理するのが困難で、インフレは国民経済を破壊し、産業を破壊します。
ですから経済対策により、経済が回復して道筋がついたら、然るべき時点で日銀は金利を引き上げるべきだと思います(この点では竹中平蔵氏とは意見を異にします)。お二人ともGDPの数字を挙げていらっしゃいますが、具体的な政策手法とそれに基づいた数字の議論がないと、GDPの数字だけを挙げても意味がないと思います。
あと株侍さんへの反論への追加ですが、企業再生は通常、リストラを伴います。当然従業員もリストラするわけで、それだけで雇用対策にはなりえません。新規事業の創出と企業再生がセットであるのが通常であると思います。
ランスロさん
郵政民営化の件から言います。日本郵政株式会社は何度も言っていますが国の資産です。上場して株を取得したからといって、その取得にかけた金は国の資産です。例えるならば私が銀行から1000万円借りて配当金がでる銘柄を500万円分購入し、その銀行に購入した株で残りの500万円を穴埋めしてくれといっているようなものです。そんな都合のいい話が認められるわけありません。
次は新規産業の件です。新規産業を否定しているわけではありません。一番肝心な事は今ある企業の再生だと思ったから言いました。もうコメントをしないので最後に一言言います。高橋元総理の名言で「失業者が増えるたびに政治家の責任は重くなる」という発言があります。私はそういう政治家が増えてほしいです。
郵政民営化の件から言います。日本郵政株式会社は何度も言っていますが国の資産です。上場して株を取得したからといって、その取得にかけた金は国の資産です。例えるならば私が銀行から1000万円借りて配当金がでる銘柄を500万円分購入し、その銀行に購入した株で残りの500万円を穴埋めしてくれといっているようなものです。そんな都合のいい話が認められるわけありません。
次は新規産業の件です。新規産業を否定しているわけではありません。一番肝心な事は今ある企業の再生だと思ったから言いました。もうコメントをしないので最後に一言言います。高橋元総理の名言で「失業者が増えるたびに政治家の責任は重くなる」という発言があります。私はそういう政治家が増えてほしいです。
>椿 三十郎さん
>これを読んで何とも思いませんか??
意味が分かりません。何を言っているのですか?
引用された私の文章をどう読んだのか分かりませんが、ナチズムを肯定する文章とでも読まれたのでしょうか?
貴方の知らないものや異質なものへの恐怖は、ナチが異質なユダヤ人やインテリに対してもった憎悪と一脈通じるものであり、ナチズムやファシズムと一脈通じる危険なものであると指摘したのです。
ファシズムの根底にあるのは「嫉妬」である と、ピーター・ドラッカーも言っています。
日本語の能力が稚拙なのか、単に精神的に動揺しているだけなのか分かりませんが、単なるミスリーディング位なら許容できますが、次の一言は許容できません。
>アメリカやヨーロッパならあなたは袋叩きにされても誰からも同情されません
>ね。
一体貴方はどういう感覚でこんな台詞を書き込むことが出来るのですか?自分が一方的に意味を間違えて、のみならずこのようなことを平気で書き込める神経が理解できません。
考えるに、ナチズム云々の議論を貴方に直言したのは、極めて適切で的を得た指摘だったようです。
>もう、発言しません。
実に喜ばしいですね 貴方の名前は2度と見たくありませんので、絶対に書き込みをしないで欲しいです。
貴方の名前は2度と見たくありませんので、絶対に書き込みをしないで欲しいです。
>株侍さん
もう書き込まれないと言うことですけど、一応総括します。
民営化の議論については、同じ事を繰り返されていますが、政府支出が原資であっても必ずしも民営化出来ないことにはなりません(何度も言っていますが)。それは国鉄や電電公社の民営化の事例を見ても分かります。
もしどうしてもその点に拘るのであれば、何らかの形で償還する(長期で負債を返済するとか)と言う形にすれば、民営化を認めると言うことでしょうか?それでは民営化の反対の根拠として弱いですね。もっと機能的な実質的な論拠を示さないと、民営化反対論としても弱いと思いますよ。
>新規産業を否定しているわけではありません。
前の発言で「新規産業ではなく」と言われているので、否定されているのかと思っていました。
失業者が増えることは防ぐことは政治家の義務です。確かにその点では異論はありません。具体的な方策として有効な施策を打つと言うことが必要なのだと思います。
>これを読んで何とも思いませんか??
意味が分かりません。何を言っているのですか?
引用された私の文章をどう読んだのか分かりませんが、ナチズムを肯定する文章とでも読まれたのでしょうか?
貴方の知らないものや異質なものへの恐怖は、ナチが異質なユダヤ人やインテリに対してもった憎悪と一脈通じるものであり、ナチズムやファシズムと一脈通じる危険なものであると指摘したのです。
ファシズムの根底にあるのは「嫉妬」である と、ピーター・ドラッカーも言っています。
日本語の能力が稚拙なのか、単に精神的に動揺しているだけなのか分かりませんが、単なるミスリーディング位なら許容できますが、次の一言は許容できません。
>アメリカやヨーロッパならあなたは袋叩きにされても誰からも同情されません
>ね。
一体貴方はどういう感覚でこんな台詞を書き込むことが出来るのですか?自分が一方的に意味を間違えて、のみならずこのようなことを平気で書き込める神経が理解できません。
考えるに、ナチズム云々の議論を貴方に直言したのは、極めて適切で的を得た指摘だったようです。
>もう、発言しません。
実に喜ばしいですね
>株侍さん
もう書き込まれないと言うことですけど、一応総括します。
民営化の議論については、同じ事を繰り返されていますが、政府支出が原資であっても必ずしも民営化出来ないことにはなりません(何度も言っていますが)。それは国鉄や電電公社の民営化の事例を見ても分かります。
もしどうしてもその点に拘るのであれば、何らかの形で償還する(長期で負債を返済するとか)と言う形にすれば、民営化を認めると言うことでしょうか?それでは民営化の反対の根拠として弱いですね。もっと機能的な実質的な論拠を示さないと、民営化反対論としても弱いと思いますよ。
>新規産業を否定しているわけではありません。
前の発言で「新規産業ではなく」と言われているので、否定されているのかと思っていました。
失業者が増えることは防ぐことは政治家の義務です。確かにその点では異論はありません。具体的な方策として有効な施策を打つと言うことが必要なのだと思います。
>椿 三十郎さん
>官僚が書いた文章が分からない程度の人間は、ナチスのユダヤ人迫害を受け入
>れた人たちと大して変わらない程度の人間だっていう風に取れますよね。
どう読んだらそういう解釈になるんですか?意図的に読み誤っているか、最初から偏見を持って読んでいるので、解釈が歪んでいます。
私は「それは自分が理解できないものに対する恐怖に根差しており、」と言っているので、それは能力的なものではなく、感情的なものです。ユダヤ人のように自分たちに理解できない言語・習慣・発想をもった人間たちに対する恐怖や嫉妬といった感情を言っているのです。
人間誰しも能力には限界があって、全てを理解することなど出来ません。問題は自分が理解できないものに対してどう対応するかが問題で、その本質を適切に理解した上で対応するか、分からないと言うだけで拒絶するかは全く違う精神態度です。
特に貴方のいう「官僚のいう意味の分からない文章」は必ずしも意味がないものとばかりも言えません。行政や司法、国家統治の上で必要な技術に基づいたものかもしれません。しかし、それは権威に結びついた知識ですので、それは容易に「嫉妬」と結びつきます。
そしてかつてのように庶民にとって全く分からない知識でもないはずです。にも拘らず、それに言及する上でそれを理解しようともせず、単純に拒絶するばかり。それは怠惰に結びついており、しかも嫉妬から迫害・妨害しようなどもってのほかです。
実際に官僚の内部にも改革をしようという勢力はいます。そういった人々もまとめてつぶしてしまうことにもなりかねないのですよ。
そもそも、もう発言しないんじゃなかったですか?
>官僚が書いた文章が分からない程度の人間は、ナチスのユダヤ人迫害を受け入
>れた人たちと大して変わらない程度の人間だっていう風に取れますよね。
どう読んだらそういう解釈になるんですか?意図的に読み誤っているか、最初から偏見を持って読んでいるので、解釈が歪んでいます。
私は「それは自分が理解できないものに対する恐怖に根差しており、」と言っているので、それは能力的なものではなく、感情的なものです。ユダヤ人のように自分たちに理解できない言語・習慣・発想をもった人間たちに対する恐怖や嫉妬といった感情を言っているのです。
人間誰しも能力には限界があって、全てを理解することなど出来ません。問題は自分が理解できないものに対してどう対応するかが問題で、その本質を適切に理解した上で対応するか、分からないと言うだけで拒絶するかは全く違う精神態度です。
特に貴方のいう「官僚のいう意味の分からない文章」は必ずしも意味がないものとばかりも言えません。行政や司法、国家統治の上で必要な技術に基づいたものかもしれません。しかし、それは権威に結びついた知識ですので、それは容易に「嫉妬」と結びつきます。
そしてかつてのように庶民にとって全く分からない知識でもないはずです。にも拘らず、それに言及する上でそれを理解しようともせず、単純に拒絶するばかり。それは怠惰に結びついており、しかも嫉妬から迫害・妨害しようなどもってのほかです。
実際に官僚の内部にも改革をしようという勢力はいます。そういった人々もまとめてつぶしてしまうことにもなりかねないのですよ。
そもそも、もう発言しないんじゃなかったですか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
日本経済新聞 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日本経済新聞のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
困ったときには