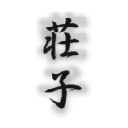━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、人におけるあぜ道
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夫道未始有封 それ道は未だ始めより封あらず。
言未始有常 言は未だ始めより常あらず。
為是而有畛也 是を為して畛(しん)あり。
請言其畛 請う、其の畛を言わん。
有左有右 左あり右あり、
有倫有義 倫あり義あり、
有分有辯 分あり辯(弁)あり、
有競有争 競あり争あり。
此之謂八徳 此れのゆくを八徳と謂う。
六合之外聖人存而不論 六合(りくごう)の外に聖人存するも論ぜず。
六合之内聖人論而不議 六合の内に聖人論ずるも議せず。
春秋経世先王之志 春秋に経世する先王の志しに、
聖人議而不辯 聖人は議するも辯(弁)ぜず。
故分也者有不分也 故に分かつは分かたざるあり。
辯也者有不辯也 辯(弁)ずるは辯(弁)ぜざるあり。
曰 何也 曰く、何ぞや。
聖人懐之 聖人はこれを懐(ふところ)にし、
衆人辯之以相示也 衆人はこれを辯(弁)じて相以って示す。
故曰 辯也者有不見也 故に曰く、「辯(弁)ずるは見ざるあり」と。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
……………………………………………………………………………………………………………
いったい、道とはもともと〔無限定で〕境界分別を持たないものであり、
言葉とはもともと一定した意味内容を持たないものである。
こういうことからして〔道を言葉によってあらわすとなると〕対立差別が生まれることになる。その対立差別について述べよう。
左があって右があり、論があって議が起こり、分類があって区別があり、競りがあって争いがあるということがそれで、これを八つの徳(──そなわち道を離れて得られたもの)と名づける。
〔そこで〕この宇宙の外のことについては聖人はその存在を否定しないが、
それについて論を立てることはしない。
また宇宙の中のことについては、聖人は論を立てても細かい議論はしない。
諸国の年代記にみえる治策や古代の王たちの記録については、聖人は議論はしても〔善し悪しの〕分別はたてない。
そもそも分類するということは分類しないものを残すことであり、
区別するということは区別しないものを残すことである。
それはどういうことか。
聖人は道をそのままわが胸に収めるのであるが、
一般の人々は道に区別を立ててそれを他人に示すのである。
そこで、区別するということは〔道について〕見えないところを残している、というものである。
……………………………………………………………………………………………………………
▽(岸陽子 訳)
……………………………………………………………………………………………………………
「道」は、本来、無限定なものである。
したがって、ことば(概念)による区分も、一時的な区分にすぎない。にもかかわらず、ことば(概念)を絶対視するからこそ、事物を差別視する観念が生ずるのである。以下、その差別観念について検討を加えよう。
まず事物は、比較対置されることによって左と右といった相対的な存在形式に「分類」される。この分類に基づいて「秩序」が立てられ、その秩序には必然的に「選択」と「競争」とを人間社会にもたらした。この「分類」と「秩序」と「選択」と「競争」こそ、人間が思考を通じて得た収穫なのである。
だからこそ聖人は、いっさいの現象をあるがままにまかせて、論じようとしない。事物の根元について、論じはするが、概念を用いて追究しようとはしない。また、古代の聖王たちの事蹟についても、事実をつまびらかにするだけで、是非を云々しようとはいないのである。
つまり、区別を立てないことが、真の区別であり、価値づけを行わないことが、真の価値づけだといえる。区別を立てず、価値づけを行わぬとはとはどういうことか。いっさいをあるがままにに受容する聖人のありかたがそれである。これに対して一般の人々は、ことばを絶対視してたがいに是非を争いあう。つまり、ことばを絶対視するのは「道」を理解していない証拠なのである。
……………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そもそも道は、未だ始めから封じざれたものとしてあることはない。
言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。
これに人の行為がともなうと、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。
どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。
左ができれば、右ができる。
倫理ができれば、義理ができる。
分割ができれば、弁舌ができる。
競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。
この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。
六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。
六合の内にて、聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。
諸国年代記にある世に伝わる古代の王の話のように、その志に対して、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。
それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。
「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。
どういうことかというと、こういうことだ。
聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。
だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、人におけるあぜ道
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夫道未始有封 それ道は未だ始めより封あらず。
言未始有常 言は未だ始めより常あらず。
為是而有畛也 是を為して畛(しん)あり。
請言其畛 請う、其の畛を言わん。
有左有右 左あり右あり、
有倫有義 倫あり義あり、
有分有辯 分あり辯(弁)あり、
有競有争 競あり争あり。
此之謂八徳 此れのゆくを八徳と謂う。
六合之外聖人存而不論 六合(りくごう)の外に聖人存するも論ぜず。
六合之内聖人論而不議 六合の内に聖人論ずるも議せず。
春秋経世先王之志 春秋に経世する先王の志しに、
聖人議而不辯 聖人は議するも辯(弁)ぜず。
故分也者有不分也 故に分かつは分かたざるあり。
辯也者有不辯也 辯(弁)ずるは辯(弁)ぜざるあり。
曰 何也 曰く、何ぞや。
聖人懐之 聖人はこれを懐(ふところ)にし、
衆人辯之以相示也 衆人はこれを辯(弁)じて相以って示す。
故曰 辯也者有不見也 故に曰く、「辯(弁)ずるは見ざるあり」と。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
……………………………………………………………………………………………………………
いったい、道とはもともと〔無限定で〕境界分別を持たないものであり、
言葉とはもともと一定した意味内容を持たないものである。
こういうことからして〔道を言葉によってあらわすとなると〕対立差別が生まれることになる。その対立差別について述べよう。
左があって右があり、論があって議が起こり、分類があって区別があり、競りがあって争いがあるということがそれで、これを八つの徳(──そなわち道を離れて得られたもの)と名づける。
〔そこで〕この宇宙の外のことについては聖人はその存在を否定しないが、
それについて論を立てることはしない。
また宇宙の中のことについては、聖人は論を立てても細かい議論はしない。
諸国の年代記にみえる治策や古代の王たちの記録については、聖人は議論はしても〔善し悪しの〕分別はたてない。
そもそも分類するということは分類しないものを残すことであり、
区別するということは区別しないものを残すことである。
それはどういうことか。
聖人は道をそのままわが胸に収めるのであるが、
一般の人々は道に区別を立ててそれを他人に示すのである。
そこで、区別するということは〔道について〕見えないところを残している、というものである。
……………………………………………………………………………………………………………
▽(岸陽子 訳)
……………………………………………………………………………………………………………
「道」は、本来、無限定なものである。
したがって、ことば(概念)による区分も、一時的な区分にすぎない。にもかかわらず、ことば(概念)を絶対視するからこそ、事物を差別視する観念が生ずるのである。以下、その差別観念について検討を加えよう。
まず事物は、比較対置されることによって左と右といった相対的な存在形式に「分類」される。この分類に基づいて「秩序」が立てられ、その秩序には必然的に「選択」と「競争」とを人間社会にもたらした。この「分類」と「秩序」と「選択」と「競争」こそ、人間が思考を通じて得た収穫なのである。
だからこそ聖人は、いっさいの現象をあるがままにまかせて、論じようとしない。事物の根元について、論じはするが、概念を用いて追究しようとはしない。また、古代の聖王たちの事蹟についても、事実をつまびらかにするだけで、是非を云々しようとはいないのである。
つまり、区別を立てないことが、真の区別であり、価値づけを行わないことが、真の価値づけだといえる。区別を立てず、価値づけを行わぬとはとはどういうことか。いっさいをあるがままにに受容する聖人のありかたがそれである。これに対して一般の人々は、ことばを絶対視してたがいに是非を争いあう。つまり、ことばを絶対視するのは「道」を理解していない証拠なのである。
……………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そもそも道は、未だ始めから封じざれたものとしてあることはない。
言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。
これに人の行為がともなうと、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。
どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。
左ができれば、右ができる。
倫理ができれば、義理ができる。
分割ができれば、弁舌ができる。
競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。
この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。
六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。
六合の内にて、聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。
諸国年代記にある世に伝わる古代の王の話のように、その志に対して、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。
それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。
「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。
どういうことかというと、こういうことだ。
聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。
だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(24)
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 夫道未始有封 ┃【それ道は未だ始めより封あらず。】
┃ 言未始有常 ┃【言は未だ始めより常あらず。】
┗━━━━━━━━━┛
そもそも道は、未だ始めから封じられたものとしてあることはない。
言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【封】の原字は「土+〔左側の字〕(△型に上部のあわさったもの)」で、
四方から△型に寄せ集めて、頂点であわせる意味をもちます。
のち、「土(二つ)+寸(て)」と書き、盛り土をした「祭壇・つか」を示します。
「あわせてとじて、中が見えないようにする」という意もあります。
*【常】は「巾(ぬの)+尚」で、もとは「裳」と同じで「長いスカート」の意。
⇒「時間が長い・いつまでも続く」「同じ姿のまま長く続く」の意となります。
◆通説では【夫道未始有封】の【封】は、「境界分別」と意訳しています。
◇【封】を意訳してしまう前に、字源に則り「手(人為)によって平らな土が△に形成され
る」(また、中が見えなくなる)といったようなイメージでとらえることが、この話の
ミソになるのではないかと思います。そのため「封じる」とそのまま訳しました。
◆通説では【言未始有常】の【常】は、「一定した意味内容」と意訳しています。
◇【常】は、「同じ姿のまま長く続く」の意と取り、「常しえ」と訳しました。
◆通説では【未始有〜】は、「〜」の単なる否定形として訳されています。
◇【未始有】は以前に説明しましたが、完全に否定形というのではなく未然形なのです。
顕在的には「無い」けれども、潜在的には「有る」と言えるかもしれないというニュア
ンスを含んでいるのです。「道」や「言」は、そのきわどい状態で「封じられたもの」
としてや「常しえのもの」としては「無い」のに(表現しきれない状態で潜在的に)
「存在している」と言っているのでしょう。
┃▼ 夫道未始有封 ┃【それ道は未だ始めより封あらず。】
┃ 言未始有常 ┃【言は未だ始めより常あらず。】
┗━━━━━━━━━┛
そもそも道は、未だ始めから封じられたものとしてあることはない。
言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【封】の原字は「土+〔左側の字〕(△型に上部のあわさったもの)」で、
四方から△型に寄せ集めて、頂点であわせる意味をもちます。
のち、「土(二つ)+寸(て)」と書き、盛り土をした「祭壇・つか」を示します。
「あわせてとじて、中が見えないようにする」という意もあります。
*【常】は「巾(ぬの)+尚」で、もとは「裳」と同じで「長いスカート」の意。
⇒「時間が長い・いつまでも続く」「同じ姿のまま長く続く」の意となります。
◆通説では【夫道未始有封】の【封】は、「境界分別」と意訳しています。
◇【封】を意訳してしまう前に、字源に則り「手(人為)によって平らな土が△に形成され
る」(また、中が見えなくなる)といったようなイメージでとらえることが、この話の
ミソになるのではないかと思います。そのため「封じる」とそのまま訳しました。
◆通説では【言未始有常】の【常】は、「一定した意味内容」と意訳しています。
◇【常】は、「同じ姿のまま長く続く」の意と取り、「常しえ」と訳しました。
◆通説では【未始有〜】は、「〜」の単なる否定形として訳されています。
◇【未始有】は以前に説明しましたが、完全に否定形というのではなく未然形なのです。
顕在的には「無い」けれども、潜在的には「有る」と言えるかもしれないというニュア
ンスを含んでいるのです。「道」や「言」は、そのきわどい状態で「封じられたもの」
としてや「常しえのもの」としては「無い」のに(表現しきれない状態で潜在的に)
「存在している」と言っているのでしょう。
●通説では、次のようになっています。
いったい、道とはもともと〔無限定で〕境界分別を持たないものであり、
言葉とはもともと一定した意味内容を持たないものである。
〇新解釈では、次のようになります。
そもそも道は、未だ始めから封じられたものとしてあることはない。
言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。
【夫道未始有封】【それ道は未だ始めより封あらず。】
〔そもそも道は、未だ始めから封じられたものとしてあることはない。〕
──「道(タオ)」…それは「首(あたま)を向けている方に進んでいくみち」です。
人が誕生したその時から、その足場は準備されていると言えるかもしれません。
一生かけて、歩むにぴったりしたところが…。
ならばと意識してその「道」を強くを求めれば求めるほど、それは「どこ?」「どのようなもの?」といった疑問が頭の中をめぐりはじめるのかもしれませんが、それは決して語られ得ないものなのです。
「タオ」に「ねばならない」「こうすべき」はないはずだと知りつつも、いつしか、思考する「言葉」で、限定する落ち着き場所を探してしまっているかもしれません。
ところが、せいぜい言えることは、「未だ始めより封じられたものとしてあることはない」という示唆に留まっています。「ここだ」とは言えない「未分化」の状態としてあるものだということをほのめかしているにすぎません。
【言未始有常】【言は未だ始めより常あらず。】
〔言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。〕
──我々は「言葉」なら時間が経過してもいつまでも同じままに保たれているものだと信じきっているかもしれませんね。ところが、「言葉」は、「未だ始めから常しえの(不変な)ものではない」と注意喚起しています。
いったい、道とはもともと〔無限定で〕境界分別を持たないものであり、
言葉とはもともと一定した意味内容を持たないものである。
〇新解釈では、次のようになります。
そもそも道は、未だ始めから封じられたものとしてあることはない。
言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。
【夫道未始有封】【それ道は未だ始めより封あらず。】
〔そもそも道は、未だ始めから封じられたものとしてあることはない。〕
──「道(タオ)」…それは「首(あたま)を向けている方に進んでいくみち」です。
人が誕生したその時から、その足場は準備されていると言えるかもしれません。
一生かけて、歩むにぴったりしたところが…。
ならばと意識してその「道」を強くを求めれば求めるほど、それは「どこ?」「どのようなもの?」といった疑問が頭の中をめぐりはじめるのかもしれませんが、それは決して語られ得ないものなのです。
「タオ」に「ねばならない」「こうすべき」はないはずだと知りつつも、いつしか、思考する「言葉」で、限定する落ち着き場所を探してしまっているかもしれません。
ところが、せいぜい言えることは、「未だ始めより封じられたものとしてあることはない」という示唆に留まっています。「ここだ」とは言えない「未分化」の状態としてあるものだということをほのめかしているにすぎません。
【言未始有常】【言は未だ始めより常あらず。】
〔言葉は、未だ始めから常しえのものとしてあることはない。〕
──我々は「言葉」なら時間が経過してもいつまでも同じままに保たれているものだと信じきっているかもしれませんね。ところが、「言葉」は、「未だ始めから常しえの(不変な)ものではない」と注意喚起しています。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 為是而有畛也 ┃【是を為して畛(しん)あり。】
┃ 請言其畛 ┃【請う、其の畛を言わん。】
┗━━━━━━━━━┛
これに人の作為が加わると、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。
どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。
……………………………………………………………………………………………………………
*【為】(爲)の原字は「手+象」で、「象を手なずけ、調教するさま」。
→「人手を加えてうまくしあげる」→「作為を加える→する」⇒「何かになる」。
◆【為是】は通説では、「これが為(ため)に」と読んで、「こういうことからして」と、
前文を軽く受け流したかたちで訳しているようです。
◇【為是】は「是を為(な)して」と読んで、「作為・人為が加わる」という意味を含んで
いると取ることが重要なポイントになってくると思います。
※「行為がともなうと」と訳していましたが、「作為が加わると」に変更しました。
*【畛】は、「田+〔右側(シン)〕(びっしりつめる)」で、
「びっしり作物を植えた田畑の間に残ったあぜ道」を意味しています。
◆通説では【畛】を、「対立差別」と意訳しています。
◇無為自然に歩む「首を向けている方に進んでいくみち」という意をもつ【道(タオ)】
に対して、「人の作為」が加わった時に必然的にできあがる【畛(シン)】(あぜみち)
とは、「みち」は「みち」でもまるで違うものだということが感じ取れます。
(日本語では、同じ「道」を用いますが、字源の奥にあるイメージの違いが重要です)
◇【請言其畛】は、【道(タオ)】については直接多くは語りえることができないが故に、
【道】との違いがわかるように「【畛(あぜみち)】について、是非語らせてほしい」
と言っているのでしょう。
┃▼ 為是而有畛也 ┃【是を為して畛(しん)あり。】
┃ 請言其畛 ┃【請う、其の畛を言わん。】
┗━━━━━━━━━┛
これに人の作為が加わると、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。
どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。
……………………………………………………………………………………………………………
*【為】(爲)の原字は「手+象」で、「象を手なずけ、調教するさま」。
→「人手を加えてうまくしあげる」→「作為を加える→する」⇒「何かになる」。
◆【為是】は通説では、「これが為(ため)に」と読んで、「こういうことからして」と、
前文を軽く受け流したかたちで訳しているようです。
◇【為是】は「是を為(な)して」と読んで、「作為・人為が加わる」という意味を含んで
いると取ることが重要なポイントになってくると思います。
※「行為がともなうと」と訳していましたが、「作為が加わると」に変更しました。
*【畛】は、「田+〔右側(シン)〕(びっしりつめる)」で、
「びっしり作物を植えた田畑の間に残ったあぜ道」を意味しています。
◆通説では【畛】を、「対立差別」と意訳しています。
◇無為自然に歩む「首を向けている方に進んでいくみち」という意をもつ【道(タオ)】
に対して、「人の作為」が加わった時に必然的にできあがる【畛(シン)】(あぜみち)
とは、「みち」は「みち」でもまるで違うものだということが感じ取れます。
(日本語では、同じ「道」を用いますが、字源の奥にあるイメージの違いが重要です)
◇【請言其畛】は、【道(タオ)】については直接多くは語りえることができないが故に、
【道】との違いがわかるように「【畛(あぜみち)】について、是非語らせてほしい」
と言っているのでしょう。
●通説では、次のようになっています。
こういうことからして〔道を言葉によってあらわすとなると〕対立差別が生まれることになる。その対立差別について述べてみよう
〇新解釈では、次のようになります。
これに人の作為が加わると、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。
どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。
【為是而有畛也】【是を為して畛(しん)あり。】
〔これに人の作為が加わると、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。〕
──「封じるもの」を作ることなく歩んでいくのが「道(タオ)」ならば、「封じるもの」を作りながら歩んでいく時にできるものが「畛(シン)」だと言えるかもしれません。「道」との大きな違いは、「封じたもの」を作ろうと人為が加わるがために、相対的にできあがるもう片方の「封じるもの」との「区別」をつけるために、当然のように「溝」といういわば境目を作る「畛(あぜ道)」ができあがる点です。
「道」を歩んでいくということは、表に見えるところと、その裏の見えないところを連続体として区別することなく、常に「一」といういうことを忘れていないのかもしれません。
それに対して「あぜ道」を進んでいくことは、「区別」をあれこれつけることによって、すべてが「一」に帰属することを忘れ、その結果として「多くのもの」に分断された意識とともにあると言うことができるかもしれません。
【請言其畛】【請う、其の畛を言わん。】
〔どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。〕
──では、実際に人における「あぜ道」とはどのようなものか、もう少し踏み込んで説明させてほしいと言っています。
こういうことからして〔道を言葉によってあらわすとなると〕対立差別が生まれることになる。その対立差別について述べてみよう
〇新解釈では、次のようになります。
これに人の作為が加わると、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。
どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。
【為是而有畛也】【是を為して畛(しん)あり。】
〔これに人の作為が加わると、「あぜ道(封じたものと溝という境)」ができあがる。〕
──「封じるもの」を作ることなく歩んでいくのが「道(タオ)」ならば、「封じるもの」を作りながら歩んでいく時にできるものが「畛(シン)」だと言えるかもしれません。「道」との大きな違いは、「封じたもの」を作ろうと人為が加わるがために、相対的にできあがるもう片方の「封じるもの」との「区別」をつけるために、当然のように「溝」といういわば境目を作る「畛(あぜ道)」ができあがる点です。
「道」を歩んでいくということは、表に見えるところと、その裏の見えないところを連続体として区別することなく、常に「一」といういうことを忘れていないのかもしれません。
それに対して「あぜ道」を進んでいくことは、「区別」をあれこれつけることによって、すべてが「一」に帰属することを忘れ、その結果として「多くのもの」に分断された意識とともにあると言うことができるかもしれません。
【請言其畛】【請う、其の畛を言わん。】
〔どうか、その「あぜ道」について言及させてほしい。〕
──では、実際に人における「あぜ道」とはどのようなものか、もう少し踏み込んで説明させてほしいと言っています。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 有左有右 有倫有義 ┃【左あり右あり、倫あり義あり、】
┗━━━━━━━━━━━━┛
左ができれば、右ができる。倫理ができれば、義理ができる。
……………………………………………………………………………………………………………
*【左】は「ひだり手+工(しごと)」で「工作物を右手に添えてささえる手」の意。
*【右】は元「みぎ手」の象形。後に「口」と合わさり「口をかばうこと」を示します。
◆【有左有右】は「左があって右があり、」としています。
◇【有】は「ある」に違いないのですが、もともと外的存在として「左右がある」という
概念ではなく、人為的概念が加わって「できる」というニュアンスだと解釈しました。
*【倫】は「人+侖」で、「きちんと並んだ人間の間がら」の意。
「侖」は「あつめ、まとめる印+冊(短冊の竹札)」の意。
(※「倫理」は、「人として行うべきすじ道」。)
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我(かどばったほこ)」で、
「きちんとしてかっこうがよい、美しいと認められるやり方」「神意にかなう」
⇒「ただしい」「よい・美しい」などの意。
(※「義理」は、「正しいとするすじ道」。)
◆通説では、【倫】は「論」、【義】は「議」と通用した字とみなして解釈をしています。
◇私はあくまでも源字に沿った解釈をしたいと思います。
一方で、内側に概念での「人として行うべきすじ道」という「倫理」ができあがると、
もう一方では、外側に行動での「正しいとするすじ道」という「義理」ができあがると
いうふうに言っているのだと解釈しました。
┃▼ 有左有右 有倫有義 ┃【左あり右あり、倫あり義あり、】
┗━━━━━━━━━━━━┛
左ができれば、右ができる。倫理ができれば、義理ができる。
……………………………………………………………………………………………………………
*【左】は「ひだり手+工(しごと)」で「工作物を右手に添えてささえる手」の意。
*【右】は元「みぎ手」の象形。後に「口」と合わさり「口をかばうこと」を示します。
◆【有左有右】は「左があって右があり、」としています。
◇【有】は「ある」に違いないのですが、もともと外的存在として「左右がある」という
概念ではなく、人為的概念が加わって「できる」というニュアンスだと解釈しました。
*【倫】は「人+侖」で、「きちんと並んだ人間の間がら」の意。
「侖」は「あつめ、まとめる印+冊(短冊の竹札)」の意。
(※「倫理」は、「人として行うべきすじ道」。)
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我(かどばったほこ)」で、
「きちんとしてかっこうがよい、美しいと認められるやり方」「神意にかなう」
⇒「ただしい」「よい・美しい」などの意。
(※「義理」は、「正しいとするすじ道」。)
◆通説では、【倫】は「論」、【義】は「議」と通用した字とみなして解釈をしています。
◇私はあくまでも源字に沿った解釈をしたいと思います。
一方で、内側に概念での「人として行うべきすじ道」という「倫理」ができあがると、
もう一方では、外側に行動での「正しいとするすじ道」という「義理」ができあがると
いうふうに言っているのだと解釈しました。
●通説では、次のようになっています。
左があって右があり、論が立って議が起こり、
〇新解釈では、次のようになります。
左ができれば、右ができる。倫理ができれば、義理ができる。
【有左有右】【左あり右あり、】
〔左ができれば、右ができる。〕
──もともと存在に「左右」の違いはありえません。ところが人間の認識という作為が介入すれば、「左」という概念で封じこめるものができあがります。それは同時に「右」という概念を作っていることに他なりません。この「左右」の境界線に「あぜ道」ができあがるのです。
人の作為が加わわった歩みによって、誰のものでもない「道」になりうるはずの「大地」は「あぜ道」ばかりになるのかもしれませんね。
【有倫有義】【倫あり義あり、】
〔倫理ができれば、義理ができる。〕
──人間の心の中の「田畑」にできる「あぜ道」も、同じような過程をたどるのかもしれません。「道」を求めて心の中で「すじ道」を立てようとすると、「こうあるべき・こうあらねばならない」という作為に満ちた概念が生まれます。それは内側では「倫理」になり、外側では「義理」になるという、この「内外」の境界線に「あぜ道」ができあがってしまうのです。
左があって右があり、論が立って議が起こり、
〇新解釈では、次のようになります。
左ができれば、右ができる。倫理ができれば、義理ができる。
【有左有右】【左あり右あり、】
〔左ができれば、右ができる。〕
──もともと存在に「左右」の違いはありえません。ところが人間の認識という作為が介入すれば、「左」という概念で封じこめるものができあがります。それは同時に「右」という概念を作っていることに他なりません。この「左右」の境界線に「あぜ道」ができあがるのです。
人の作為が加わわった歩みによって、誰のものでもない「道」になりうるはずの「大地」は「あぜ道」ばかりになるのかもしれませんね。
【有倫有義】【倫あり義あり、】
〔倫理ができれば、義理ができる。〕
──人間の心の中の「田畑」にできる「あぜ道」も、同じような過程をたどるのかもしれません。「道」を求めて心の中で「すじ道」を立てようとすると、「こうあるべき・こうあらねばならない」という作為に満ちた概念が生まれます。それは内側では「倫理」になり、外側では「義理」になるという、この「内外」の境界線に「あぜ道」ができあがってしまうのです。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 有分有辯 有競有争 ┃【分あり辯(弁)あり、競あり争あり。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
分割ができれば、弁舌ができる。
競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。
……………………………………………………………………………………………………………
*【分】は、「八印(左右にわける)+刀」で、「二つに切りわける」意。
*【辯】は「辛(刃)二つ+言」で、(【弁】は、その略字として用いたもの。)
「刃物で切り分けるように言葉を切ること」→「理屈を分けのべた議論」。
(※同じ【弁】ですが、旧字【辨】の場合、「辛(刃物)二つ+刀」で「わける」意。)
◆通説では、【分】は「分類」、【辯】は「区別」としています。
◇【分】は「二つに切り分ける」ということで、「分割」と訳しました。
【辯】がただの「区別」だけならこの字を用いず、「辨」の字を用いているでしょう。
同じ【弁】でも【辯】は「言葉を用いての区別」ということで「弁舌」と訳しました。
*【競】は「言+言+人+人」で、「二人が言い合い、勝負をやりあうこと」。
*【争】は「爪(手)+ー印+手」で、「ある物を両者が手で引っぱりあうさま」
→「反対の方向に引っぱりあう」意を含みます。
◆通説では【競】は「競りあい」、「争」は「争い」としています。
◇訳自体は通説と大差ありません。ただ字源を見ると言葉の裏に隠されているイメージが
伝わってきておもしろいですね。【競】は他人と言葉での勝負をはじめて「押し合う」
姿が、【争】は「引っぱり合う」姿が見えてきそうです。
┃▼ 有分有辯 有競有争 ┃【分あり辯(弁)あり、競あり争あり。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
分割ができれば、弁舌ができる。
競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。
……………………………………………………………………………………………………………
*【分】は、「八印(左右にわける)+刀」で、「二つに切りわける」意。
*【辯】は「辛(刃)二つ+言」で、(【弁】は、その略字として用いたもの。)
「刃物で切り分けるように言葉を切ること」→「理屈を分けのべた議論」。
(※同じ【弁】ですが、旧字【辨】の場合、「辛(刃物)二つ+刀」で「わける」意。)
◆通説では、【分】は「分類」、【辯】は「区別」としています。
◇【分】は「二つに切り分ける」ということで、「分割」と訳しました。
【辯】がただの「区別」だけならこの字を用いず、「辨」の字を用いているでしょう。
同じ【弁】でも【辯】は「言葉を用いての区別」ということで「弁舌」と訳しました。
*【競】は「言+言+人+人」で、「二人が言い合い、勝負をやりあうこと」。
*【争】は「爪(手)+ー印+手」で、「ある物を両者が手で引っぱりあうさま」
→「反対の方向に引っぱりあう」意を含みます。
◆通説では【競】は「競りあい」、「争」は「争い」としています。
◇訳自体は通説と大差ありません。ただ字源を見ると言葉の裏に隠されているイメージが
伝わってきておもしろいですね。【競】は他人と言葉での勝負をはじめて「押し合う」
姿が、【争】は「引っぱり合う」姿が見えてきそうです。
●通説では、次のようになっています。
分類があって区別があり、競(せ)りあいがあって争いがあるというのがそれで、
〇新解釈では、次のようになります。
分割ができれば、弁舌ができる。競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。
【有分有辯】【分あり辯(弁)あり、】
〔分割ができれば、弁舌ができる。〕
──「左右」や「内外(倫義)」といったような「分割」は、いつしか「自分のもの」という所有欲や支配欲をもつようになり、「他人のもの」とは一線を画することになります。するとそのことを他人に明らかにするために「弁舌」が誕生することになりますが、その「自他」を分ける境界線にも「あぜ道」ができあがるのかもしれません。
【有競有争】【競あり争あり。】
〔競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。〕
──「弁舌」は他人との関わり合いをもち、そこから善し悪しや優劣といった価値観をぶつけ合うようになりますが、「競争」という「持論の押し合いと引き合い」の境界線にも「あぜ道」ができあがってしまうことになると言っているようです。
分類があって区別があり、競(せ)りあいがあって争いがあるというのがそれで、
〇新解釈では、次のようになります。
分割ができれば、弁舌ができる。競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。
【有分有辯】【分あり辯(弁)あり、】
〔分割ができれば、弁舌ができる。〕
──「左右」や「内外(倫義)」といったような「分割」は、いつしか「自分のもの」という所有欲や支配欲をもつようになり、「他人のもの」とは一線を画することになります。するとそのことを他人に明らかにするために「弁舌」が誕生することになりますが、その「自他」を分ける境界線にも「あぜ道」ができあがるのかもしれません。
【有競有争】【競あり争あり。】
〔競(せ)り合いがおきれば、争いがおきる。〕
──「弁舌」は他人との関わり合いをもち、そこから善し悪しや優劣といった価値観をぶつけ合うようになりますが、「競争」という「持論の押し合いと引き合い」の境界線にも「あぜ道」ができあがってしまうことになると言っているようです。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 此之謂八徳 ┃【此れのゆくを八徳と謂う。】
┗━━━━━━━━┛
この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。
……………………………………………………………………………………………………………
*前にも説明しましたが、【此】は、もとは、「止(あし)+比(ならぶ)の略体」で、
「足を並べてもうまくそろわず、ちぐはぐになること」を意味しています。
⇒普通には、「近いものをさす指示語」に借用し、本義は忘れられています。
*【之】は「足の先が線から出て進みいくさま」で、「ゆく」こと。
この字も前に説明しましたが、普通、「指示代名詞」として当てられます。
また、助詞の「の」としても用いられます。
◆【此之】は、通説では「此れをこれ」と読んで、単純に「これを」と訳しています。
◇しかし、同じような意味の指示代名詞が二つ並んでいるのは不自然のように思います。
ここの【此之】は「此れのゆくを」と読んで、左右に振り分けながら順次に歩を進めて
(あぜ道を作って)いるイメージが伝わってきたために、訳上では「この動向を」とし
ました。
*【八】は「左右二つにわける」⇒両分する数え方によって、数の「8」を表します。
*【徳】の原字は【悳】「心+直」で、「本性のままの心」の意。
のちに「彳(いく)」を加え、「本性(良心)に基づく行い」を示したもの。
◆通説での【八徳】は、「八つの徳(すなわち道を離れて得られたもの)」としています。
◇確かに、八つの項目がそれ以前に述べられていますが、その前に「あぜ道」について言
及しようと言っていたことを考慮に入れるべきだと思うので、字源に沿って考えます。
【八】はもともと「左右二つにわける」意だったので「両分する」と補足しました。
◇【徳】は、「あぜ道」を作ってしまう「善いと思う行為(≒作為)に走る傾向があるも
の」と解釈して、「性向」と補足しました。
┃▼ 此之謂八徳 ┃【此れのゆくを八徳と謂う。】
┗━━━━━━━━┛
この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。
……………………………………………………………………………………………………………
*前にも説明しましたが、【此】は、もとは、「止(あし)+比(ならぶ)の略体」で、
「足を並べてもうまくそろわず、ちぐはぐになること」を意味しています。
⇒普通には、「近いものをさす指示語」に借用し、本義は忘れられています。
*【之】は「足の先が線から出て進みいくさま」で、「ゆく」こと。
この字も前に説明しましたが、普通、「指示代名詞」として当てられます。
また、助詞の「の」としても用いられます。
◆【此之】は、通説では「此れをこれ」と読んで、単純に「これを」と訳しています。
◇しかし、同じような意味の指示代名詞が二つ並んでいるのは不自然のように思います。
ここの【此之】は「此れのゆくを」と読んで、左右に振り分けながら順次に歩を進めて
(あぜ道を作って)いるイメージが伝わってきたために、訳上では「この動向を」とし
ました。
*【八】は「左右二つにわける」⇒両分する数え方によって、数の「8」を表します。
*【徳】の原字は【悳】「心+直」で、「本性のままの心」の意。
のちに「彳(いく)」を加え、「本性(良心)に基づく行い」を示したもの。
◆通説での【八徳】は、「八つの徳(すなわち道を離れて得られたもの)」としています。
◇確かに、八つの項目がそれ以前に述べられていますが、その前に「あぜ道」について言
及しようと言っていたことを考慮に入れるべきだと思うので、字源に沿って考えます。
【八】はもともと「左右二つにわける」意だったので「両分する」と補足しました。
◇【徳】は、「あぜ道」を作ってしまう「善いと思う行為(≒作為)に走る傾向があるも
の」と解釈して、「性向」と補足しました。
●通説では、次のようになっています。
これを八つの徳(──すなわち道を離れて得られたもの)と名づける。
〇新解釈では、次のようになります。
この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。
【此之謂八徳】【此れのゆくを八徳と謂う。】
〔この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。〕
──通説の「徳」を「道を離れて得られたもの」と説明しているのは、次のような他所での説明をもとにして補足したのでしょう。
『荘子』の知北遊篇に、「知」が「道」を求めて「無為謂」や「狂屈」に尋ねますが、結局何も得ることなく帰り、「黄帝」に「道」について尋ねる…という話があります。その「黄帝」の話の中に、次のような下りがあります。
「……(略)……故に曰く、道が失われてしかる後に『徳』がある。『徳』が失われてしかる後に仁がある。仁が失われてしかる後に義がある。義が失われてしかる後に礼がある。」
この下りは、下記の『老子』の第三十八章を踏まえているものかもしれません。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
上徳不徳 「上徳」は、「徳」とは意識しない。
是以有徳 これを以って、「徳」が有るのだ。
下徳不失徳 「下徳」は、「徳」だという意識を失わない。
是以無徳 これを以って、「徳」が無いのだ。
上徳無為而無以為 「上徳」は無為にして、以って何かの為ではない。
下徳為之而有以為 「下徳」はこれを為して、以って何かの為である。
……(略)……
故失道而後徳 故に、道が失われてしかる後に「徳」がある。
失徳而後仁 「徳」が失われてしかる後に仁がある。
失仁而後義 仁が失われてしかる後に義がある。
失義而後礼 義が失われてしかる後に礼がある。
……(略)……
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ここの「八徳」の「徳」は、老子の言う「下徳」に当たるものでしょう。
<一>だとしか言いようがない「道」が失われて、代わりにできる「あぜ道」のことを「八徳」と言い換えることができると言っているのでしょう。「八」という数字を使っていますが、「(八方末広がりしながら)両分する性向」という意味をもっているところがミソのようです。
これを八つの徳(──すなわち道を離れて得られたもの)と名づける。
〇新解釈では、次のようになります。
この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。
【此之謂八徳】【此れのゆくを八徳と謂う。】
〔この動向を、(人の行為による)「八徳(両分の性向)」と言おう。〕
──通説の「徳」を「道を離れて得られたもの」と説明しているのは、次のような他所での説明をもとにして補足したのでしょう。
『荘子』の知北遊篇に、「知」が「道」を求めて「無為謂」や「狂屈」に尋ねますが、結局何も得ることなく帰り、「黄帝」に「道」について尋ねる…という話があります。その「黄帝」の話の中に、次のような下りがあります。
「……(略)……故に曰く、道が失われてしかる後に『徳』がある。『徳』が失われてしかる後に仁がある。仁が失われてしかる後に義がある。義が失われてしかる後に礼がある。」
この下りは、下記の『老子』の第三十八章を踏まえているものかもしれません。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
上徳不徳 「上徳」は、「徳」とは意識しない。
是以有徳 これを以って、「徳」が有るのだ。
下徳不失徳 「下徳」は、「徳」だという意識を失わない。
是以無徳 これを以って、「徳」が無いのだ。
上徳無為而無以為 「上徳」は無為にして、以って何かの為ではない。
下徳為之而有以為 「下徳」はこれを為して、以って何かの為である。
……(略)……
故失道而後徳 故に、道が失われてしかる後に「徳」がある。
失徳而後仁 「徳」が失われてしかる後に仁がある。
失仁而後義 仁が失われてしかる後に義がある。
失義而後礼 義が失われてしかる後に礼がある。
……(略)……
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ここの「八徳」の「徳」は、老子の言う「下徳」に当たるものでしょう。
<一>だとしか言いようがない「道」が失われて、代わりにできる「あぜ道」のことを「八徳」と言い換えることができると言っているのでしょう。「八」という数字を使っていますが、「(八方末広がりしながら)両分する性向」という意味をもっているところがミソのようです。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 六合之外聖人存而不論 ┃【六合(りくごう)の外に聖人存するも論ぜず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【六合】は「東・西・南・北・上(天)・下(地)の六つの方角」「天下」「世界」の意。
(【合】は「かぶせる印+口」で「穴に蓋をぴたりとかぶせ合わせること」の意。)
*【存】は「[左上部の字(せきとめる)]+子(子孫や孤児をいたわり落ち着ける)」こと
から、「大切に留めおく」の意。
*【論】は「言+侖(集めまとめる印+冊)」で「言葉で整理して並べること」。
◆【六合之外】は、通説では「宇宙の外のことについて」と訳しています。
◇通説では、自分の立ち位置は「宇宙」から離れたところにあって、思いを馳せる思考の
範囲でものを語っているように思えます。荘子の語る「宇宙」は<一>なるものとして
存在するもので、そこに「外」があるとは思えません。【六合之外】は、「三次元の法則
に則って存在する物質的世界以外」ととらえるべきではないでしょうか。よって、ここ
ではそのことに「ついて」ではなく、そこに「おいて(にて)」と言っているのだと思い
ます。
(ここでも、人間は三次元だけの物質世界にのみ生きている存在ではないことをほのめか
しているのだと思います。)
◆通説では、【存而不論】は「その存在を否定しないが、それについて論は立てることはし
ない」と意訳しています。
◇【存】は、言葉では説明不可能な状態ながらも、英語で表現するならば、「being」のよ
うな「(ありのままに)存在すること」といったニュアンスだと思います。
そんな境地においては、一切の言葉などは介入できる状態ではなく、【不論】つまり「言
葉を並べて論じることなど一切ない」…と言っているのではないでしょうか。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 六合之内聖人論而不議 ┃【六合の内に聖人論ずるも議せず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
六合の内にて、聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【議】の「義」は「羊(形のよいひつじ)+我(かどばったほこ)」からなり、
「言+義」で「かどばって形よく折り目のある話のこと」「よしとする主張」。
◆通説では、【六合之内】は「宇宙の中のことについて」と訳しています。
◇【六合之内】とは、「三次元の法則下にある物質的世界の以内においては」ということで
しょう。
【六合之外】が「無形無限世界」」とするなら、【六合之内】は「有形有限世界」という
ことになるでしょうか。
◆通説では、【論而不議】は「論を立てても細かい議論はしない」としています。
◇【議】を「細かい議論」としていますが、ちょっとニュアンスが違うと思います。つま
り【論】と【議】の違いを「大まかな論議」と「細かい議論」としているのではなく、
【論】の主眼は自分の中で「言葉で整理して並べること」であるのに対して、【議】
の主眼は他人に対して「よしとする主張すること」という違いがあるのだと思います。
【議】を「議論」とすると「論」がかぶってしまいますが、他に適当な言葉が見つから
ないので、「議論で主張すること」と訳しました。
┃▼ 六合之外聖人存而不論 ┃【六合(りくごう)の外に聖人存するも論ぜず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【六合】は「東・西・南・北・上(天)・下(地)の六つの方角」「天下」「世界」の意。
(【合】は「かぶせる印+口」で「穴に蓋をぴたりとかぶせ合わせること」の意。)
*【存】は「[左上部の字(せきとめる)]+子(子孫や孤児をいたわり落ち着ける)」こと
から、「大切に留めおく」の意。
*【論】は「言+侖(集めまとめる印+冊)」で「言葉で整理して並べること」。
◆【六合之外】は、通説では「宇宙の外のことについて」と訳しています。
◇通説では、自分の立ち位置は「宇宙」から離れたところにあって、思いを馳せる思考の
範囲でものを語っているように思えます。荘子の語る「宇宙」は<一>なるものとして
存在するもので、そこに「外」があるとは思えません。【六合之外】は、「三次元の法則
に則って存在する物質的世界以外」ととらえるべきではないでしょうか。よって、ここ
ではそのことに「ついて」ではなく、そこに「おいて(にて)」と言っているのだと思い
ます。
(ここでも、人間は三次元だけの物質世界にのみ生きている存在ではないことをほのめか
しているのだと思います。)
◆通説では、【存而不論】は「その存在を否定しないが、それについて論は立てることはし
ない」と意訳しています。
◇【存】は、言葉では説明不可能な状態ながらも、英語で表現するならば、「being」のよ
うな「(ありのままに)存在すること」といったニュアンスだと思います。
そんな境地においては、一切の言葉などは介入できる状態ではなく、【不論】つまり「言
葉を並べて論じることなど一切ない」…と言っているのではないでしょうか。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 六合之内聖人論而不議 ┃【六合の内に聖人論ずるも議せず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
六合の内にて、聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【議】の「義」は「羊(形のよいひつじ)+我(かどばったほこ)」からなり、
「言+義」で「かどばって形よく折り目のある話のこと」「よしとする主張」。
◆通説では、【六合之内】は「宇宙の中のことについて」と訳しています。
◇【六合之内】とは、「三次元の法則下にある物質的世界の以内においては」ということで
しょう。
【六合之外】が「無形無限世界」」とするなら、【六合之内】は「有形有限世界」という
ことになるでしょうか。
◆通説では、【論而不議】は「論を立てても細かい議論はしない」としています。
◇【議】を「細かい議論」としていますが、ちょっとニュアンスが違うと思います。つま
り【論】と【議】の違いを「大まかな論議」と「細かい議論」としているのではなく、
【論】の主眼は自分の中で「言葉で整理して並べること」であるのに対して、【議】
の主眼は他人に対して「よしとする主張すること」という違いがあるのだと思います。
【議】を「議論」とすると「論」がかぶってしまいますが、他に適当な言葉が見つから
ないので、「議論で主張すること」と訳しました。
●通説では、次のようになっています。
〔そこで〕この宇宙の外のことについては聖人はその存在を否定しないが、それについて論を立てることはしない。また宇宙の中のことについては、聖人は論を立てても細かい議論はしない。
〇新解釈では、次のようになります。
六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。
六合の内にて、聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。
【六合之外聖人存而不論】【六合(りくごう)の外に聖人存するも論ぜず。】
〔六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。〕
──「六合の外」とは、「三次元空間世界の法則に支配されないそれ以外」のいっさいの境界線などなく、全てが融合している<一>なる宇宙と言えるかもしれません。わかりやすくその宇宙を「大海」と喩えるならば、聖人はそこにあっては、「一滴の雫」として確実に「存在」していると言えても、そこでは分離するものはないと言えるでしょう。
「三次元世界以外にて(あるがままに)存在する」とは、例えば、南郭子綦の身に起きた状態や、太古の人の知が至ったというこの上ない心地といった境地のありさまを示しているのではないでしょうか。聖人はある種のバイブレーションに満たされたような状態で「存在すること」はあっても、その時には言葉がまったく介入しない状態であるがために、「論じること」はありえない状態なのでしょう。
【六合之内聖人論而不議】【六合の内に聖人論ずるも議せず。】
〔六合の内にて聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。〕
──聖人と言えども一人の人間である以上は、「三次元世界の法則に支配されているそれ以内」の境界線をもった存在であるわけです。わかりやすくその状態を「泥玉」と喩えるならば、「水(being)」と「土(言葉もその一種)」とのコラボレーションによって、他人と分離できる「論理」を展開することはあっても、互いに「水」という融合できる性質をもった仲間意識をもっているならば、「議論で(他人に)主張すること」はしないと言えるでしょう。言いかえるならば、変幻自在の「水(being)」は、その律動に合わせ、認識できる「泥玉の形(論議)」をつくることはあっても、その「形(議論)」に固執することはないということになるかもしれません。「土(言葉)」は「仮宿」だということを忘れることはないからでしょう。
その表現は、例えば南郭子綦が顔成子游に対して、「我を喪っていた」と言った後に、その時の状態(being)を言葉によって展開した天籟の話のようなものかもしれませんね。
〔そこで〕この宇宙の外のことについては聖人はその存在を否定しないが、それについて論を立てることはしない。また宇宙の中のことについては、聖人は論を立てても細かい議論はしない。
〇新解釈では、次のようになります。
六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。
六合の内にて、聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。
【六合之外聖人存而不論】【六合(りくごう)の外に聖人存するも論ぜず。】
〔六合(りくごう)(上下東西南北・三次元空間)の外にて、
聖人は「(あるがままに)存在すること」があっても、「論じること」はしない。〕
──「六合の外」とは、「三次元空間世界の法則に支配されないそれ以外」のいっさいの境界線などなく、全てが融合している<一>なる宇宙と言えるかもしれません。わかりやすくその宇宙を「大海」と喩えるならば、聖人はそこにあっては、「一滴の雫」として確実に「存在」していると言えても、そこでは分離するものはないと言えるでしょう。
「三次元世界以外にて(あるがままに)存在する」とは、例えば、南郭子綦の身に起きた状態や、太古の人の知が至ったというこの上ない心地といった境地のありさまを示しているのではないでしょうか。聖人はある種のバイブレーションに満たされたような状態で「存在すること」はあっても、その時には言葉がまったく介入しない状態であるがために、「論じること」はありえない状態なのでしょう。
【六合之内聖人論而不議】【六合の内に聖人論ずるも議せず。】
〔六合の内にて聖人は「論じること」はあっても、「議論で主張をすること」はしない。〕
──聖人と言えども一人の人間である以上は、「三次元世界の法則に支配されているそれ以内」の境界線をもった存在であるわけです。わかりやすくその状態を「泥玉」と喩えるならば、「水(being)」と「土(言葉もその一種)」とのコラボレーションによって、他人と分離できる「論理」を展開することはあっても、互いに「水」という融合できる性質をもった仲間意識をもっているならば、「議論で(他人に)主張すること」はしないと言えるでしょう。言いかえるならば、変幻自在の「水(being)」は、その律動に合わせ、認識できる「泥玉の形(論議)」をつくることはあっても、その「形(議論)」に固執することはないということになるかもしれません。「土(言葉)」は「仮宿」だということを忘れることはないからでしょう。
その表現は、例えば南郭子綦が顔成子游に対して、「我を喪っていた」と言った後に、その時の状態(being)を言葉によって展開した天籟の話のようなものかもしれませんね。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 春秋経世先王之志 ┃【春秋に経世する先王の志に、】
┃ 聖人議而不辯 ┃【聖人は議するも辯(弁)ぜず。】
┗━━━━━━━━━━━┛
年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のその志において、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【春秋】は、「春と秋」「年月」「歴史書」の意。
*【経世】は、「世の中を治める」の意。
*【先王】は、「昔の聖天子(堯・舜・禹など)」「先代の王」の意。
*【志】は、「心+士(進み行く足の形が変形したもの)」で「心が目標を目ざして進み行
くこと」。
◆【春秋経世先王之志】は、通説では【志】を「シ」と読んで「記」と解釈しています。
「諸国の年代記にみえる治策」+「古代の王たちの記録」に「ついては」としています。
◇通説では【志】の意味が反映されていないようです。どのような意味で【志】と言って
いるかというと、「世の中を治める」ために必要な「心の目標」ではないでしょうか。
よって【春秋経世先王之志】は、「年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のそ
の志において」と解釈しました。
(冒頭の翻訳では「諸国年代記にある世に伝わる古代の王の話のように、その志に対し
て」としていましたが、確認作業を通して少し見直しました。)
◆【聖人議而不辯】は、通説では「聖人は議論はしても(善し悪しの)分別はつけない。」
としています。
◇【辯】は、前に説明したように、ただ「(善し悪しの)分別をつける」といったことでは
なく、「弁舌すること」つまり「分割する言葉によって弁じること」と解釈しました。
よって、聖人は「議論で主張をすること」はあっても、「分割する言葉によって弁じるこ
と」はしない…と訳しました。
┃▼ 春秋経世先王之志 ┃【春秋に経世する先王の志に、】
┃ 聖人議而不辯 ┃【聖人は議するも辯(弁)ぜず。】
┗━━━━━━━━━━━┛
年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のその志において、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。
……………………………………………………………………………………………………………
*【春秋】は、「春と秋」「年月」「歴史書」の意。
*【経世】は、「世の中を治める」の意。
*【先王】は、「昔の聖天子(堯・舜・禹など)」「先代の王」の意。
*【志】は、「心+士(進み行く足の形が変形したもの)」で「心が目標を目ざして進み行
くこと」。
◆【春秋経世先王之志】は、通説では【志】を「シ」と読んで「記」と解釈しています。
「諸国の年代記にみえる治策」+「古代の王たちの記録」に「ついては」としています。
◇通説では【志】の意味が反映されていないようです。どのような意味で【志】と言って
いるかというと、「世の中を治める」ために必要な「心の目標」ではないでしょうか。
よって【春秋経世先王之志】は、「年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のそ
の志において」と解釈しました。
(冒頭の翻訳では「諸国年代記にある世に伝わる古代の王の話のように、その志に対し
て」としていましたが、確認作業を通して少し見直しました。)
◆【聖人議而不辯】は、通説では「聖人は議論はしても(善し悪しの)分別はつけない。」
としています。
◇【辯】は、前に説明したように、ただ「(善し悪しの)分別をつける」といったことでは
なく、「弁舌すること」つまり「分割する言葉によって弁じること」と解釈しました。
よって、聖人は「議論で主張をすること」はあっても、「分割する言葉によって弁じるこ
と」はしない…と訳しました。
●通説では、次のようになっています。
諸国の年代記にみえる治策や古代の王たちの記録については、
聖人は議論はしても(善し悪しの)分別はつけない。
〇新解釈では、次のようになります。
年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のその志において、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。
【春秋経世先王之志】【春秋に経世する先王の志に、】
【聖人議而不辯】【聖人は議するも辯(弁)ぜず。】
〔年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のその志において、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。〕
──「道」を体得している聖人は、言葉が介入しない存在(being)として超然としているだけで、言葉では「何も表現しない」と言っているわけではないようですね。衆人と同じように「言葉」を使って説明し、何かを誰かに伝えようとする時には、必要に応じて「論じること」もあれば「議論で主張をすること」もあると言っているようです。けれどもそうすることによって衆人が陥るような「あぜ道」を歩むことはないようです。
同じ言葉を用いるにしても、聖人と衆人とでは、何がどのように違うのでしょうね。
どうやら、その説明をするのに、古代の聖王、堯(ぎょう)や舜(しゅん)の話の中にその秘訣が隠れているようですが、ここでは具体的に判明できません。
※一連の聖人の話は、研究者たちも「意味がはっきりしない」とか「誤入か?」と疑問を抱いていたりして、あいまいに流しているようです。ここについては、後に出てくる第8話を交えて、その時に推理しながらもう少し詳しく説明したいと思っています。
諸国の年代記にみえる治策や古代の王たちの記録については、
聖人は議論はしても(善し悪しの)分別はつけない。
〇新解釈では、次のようになります。
年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のその志において、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。
【春秋経世先王之志】【春秋に経世する先王の志に、】
【聖人議而不辯】【聖人は議するも辯(弁)ぜず。】
〔年代記にあるような、世の中を治める古代の聖王のその志において、
聖人は「議論で主張をすること」はあっても、
「分割する言葉によって弁じること」はしない。〕
──「道」を体得している聖人は、言葉が介入しない存在(being)として超然としているだけで、言葉では「何も表現しない」と言っているわけではないようですね。衆人と同じように「言葉」を使って説明し、何かを誰かに伝えようとする時には、必要に応じて「論じること」もあれば「議論で主張をすること」もあると言っているようです。けれどもそうすることによって衆人が陥るような「あぜ道」を歩むことはないようです。
同じ言葉を用いるにしても、聖人と衆人とでは、何がどのように違うのでしょうね。
どうやら、その説明をするのに、古代の聖王、堯(ぎょう)や舜(しゅん)の話の中にその秘訣が隠れているようですが、ここでは具体的に判明できません。
※一連の聖人の話は、研究者たちも「意味がはっきりしない」とか「誤入か?」と疑問を抱いていたりして、あいまいに流しているようです。ここについては、後に出てくる第8話を交えて、その時に推理しながらもう少し詳しく説明したいと思っています。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 故分也者有不分也 ┃【故に分かつは分かたざるあり。】
┃ 辯也者有不辯也 ┃【辯(弁)ずるは辯(弁)ぜざるあり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。
「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。
……………………………………………………………………………………………………………
◆【故分也者有不分也 辯也者有不辯也】の【故】は「それ」と読んで「夫」と通用する
ものとして「そもそも」と訳しています。【分】は「分類」と訳し、【辯】は「区別」と
訳し、それぞれ反対の状態(「分類しないもの」「区別しないもの」)を「残すこと」と
しています。
◇【故】を直訳すると流れが読めなくなるので、通説では「そもそも」としたのでしょう
が、「それ故」と直訳しておきますが、その説明は第8話に譲ることにします。
◇微妙なニュアンスの違いになりますが、【分】は「分類」というよりは「分割」という感
じで、【辯】は「区別」というよりは「(言葉で区別して)弁じること(弁舌)」という
感じではないかと思います。この行為は聖人といえども普通の人と同様にしていても、
聖人は一見矛盾しているような、パラドキシカルな表現に思えるかもしれない【不分】
(分割していないもの)、【不辯】(弁じてないもの)がその心の内に「共存する」とい
ったニュアンスだと思います。
┃▼ 故分也者有不分也 ┃【故に分かつは分かたざるあり。】
┃ 辯也者有不辯也 ┃【辯(弁)ずるは辯(弁)ぜざるあり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。
「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。
……………………………………………………………………………………………………………
◆【故分也者有不分也 辯也者有不辯也】の【故】は「それ」と読んで「夫」と通用する
ものとして「そもそも」と訳しています。【分】は「分類」と訳し、【辯】は「区別」と
訳し、それぞれ反対の状態(「分類しないもの」「区別しないもの」)を「残すこと」と
しています。
◇【故】を直訳すると流れが読めなくなるので、通説では「そもそも」としたのでしょう
が、「それ故」と直訳しておきますが、その説明は第8話に譲ることにします。
◇微妙なニュアンスの違いになりますが、【分】は「分類」というよりは「分割」という感
じで、【辯】は「区別」というよりは「(言葉で区別して)弁じること(弁舌)」という
感じではないかと思います。この行為は聖人といえども普通の人と同様にしていても、
聖人は一見矛盾しているような、パラドキシカルな表現に思えるかもしれない【不分】
(分割していないもの)、【不辯】(弁じてないもの)がその心の内に「共存する」とい
ったニュアンスだと思います。
●通説では、次のようになっています。
そもそも分類するということは分類しないものを残すことであり、
区別するということは区別しないものを残すことである。
〇新解釈では、次のようになります。
それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。
「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。
【故分也者有不分也】【故に分かつは分かたざるあり。】
〔それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。〕
【辯也者有不辯也】【辯(弁)ずるは辯(弁)ぜざるあり。】
〔「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。〕
──通説と新解釈の微妙な違いを図式化するならば、次のようになりそうです。
(通説↓前者に主眼点がある)
「分類」⊃「分類しないもの」/「区別」⊃「区別しないもの」
(新解釈↓前者と後者は同等かむしろ後者に主眼点がある)
「分割」⊆「分割していないもの」/「弁じること」⊆「弁じていないもの」
先にした「泥玉」の喩えで言うならば、個人という「土」に「水」が合体してできる「泥玉」は、他とは完全に「分割」された存在となってしまっていますが、(聖人は)両者の「泥玉」の中に潜む「水」を忘れずに感じており、その融合性が故に、「分割していないもの」の存在の意識をはっきりと持っていると言えるのではないでしょうか。
同様に、「言葉」に「気のようなもの」が合体してできる「弁舌」は、他とは違う意見を述べるようになってしまうこともあるでしょうが、(聖人は)その中の、「言葉」では表現しきれない「気のようなもの」を感じ取り、その親和性が故に、「弁じていないもの」の意識をはっきりと持っていると言えるのではないでしょうか。
「分割」や「弁じること」だけに終始してしまうのは、「あぜ道」を進むことでしょう。
一方、パラドキシカルな二面性をもった時、はじめて「道」を歩んでいることになるのかもしれませんね。
そもそも分類するということは分類しないものを残すことであり、
区別するということは区別しないものを残すことである。
〇新解釈では、次のようになります。
それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。
「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。
【故分也者有不分也】【故に分かつは分かたざるあり。】
〔それ故、「分割」していても、そこには「分割していないもの」があるのだ。〕
【辯也者有不辯也】【辯(弁)ずるは辯(弁)ぜざるあり。】
〔「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ。〕
──通説と新解釈の微妙な違いを図式化するならば、次のようになりそうです。
(通説↓前者に主眼点がある)
「分類」⊃「分類しないもの」/「区別」⊃「区別しないもの」
(新解釈↓前者と後者は同等かむしろ後者に主眼点がある)
「分割」⊆「分割していないもの」/「弁じること」⊆「弁じていないもの」
先にした「泥玉」の喩えで言うならば、個人という「土」に「水」が合体してできる「泥玉」は、他とは完全に「分割」された存在となってしまっていますが、(聖人は)両者の「泥玉」の中に潜む「水」を忘れずに感じており、その融合性が故に、「分割していないもの」の存在の意識をはっきりと持っていると言えるのではないでしょうか。
同様に、「言葉」に「気のようなもの」が合体してできる「弁舌」は、他とは違う意見を述べるようになってしまうこともあるでしょうが、(聖人は)その中の、「言葉」では表現しきれない「気のようなもの」を感じ取り、その親和性が故に、「弁じていないもの」の意識をはっきりと持っていると言えるのではないでしょうか。
「分割」や「弁じること」だけに終始してしまうのは、「あぜ道」を進むことでしょう。
一方、パラドキシカルな二面性をもった時、はじめて「道」を歩んでいることになるのかもしれませんね。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 曰 何也 ┃【曰く、何ぞや。】
┃ 聖人懐之 ┃【聖人はこれを懐(ふところ)にし、】
┃ 衆人辯之以相示也 ┃【衆人はこれを辯(弁)じて相以って示す。】
┗━━━━━━━━━━━┛
どういうことかというと、こういうことだ。
聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【懐】は「心+右側の字(目からたれる涙+衣)」で、
「胸中やふところに入れて囲む」「中に囲んで大切に温める気持ち」。
*【衆】は「日(太陽)+人が三人(多くの人)」で、
「太陽のもとで多くの人が集団労働をしているさま」。「多くの」「普通の」の意。
*【示】は「祭壇」を描いた象形文字。「外にあらわして見せる」「人に見せる」の意。
◆通説では【聖人懐之 衆人辯之以相示也】の【之】は両方「道」だと解釈しています。
◇【之(これ)】は前文を受けて、「二面性をもった拠り所の感覚」といったニュアンスで、
聖人の場合は、【之】(言葉で表現されることとは別の不可分ままの感覚≒二面性をもっ
たパラドキシカルな「道」)を自分の心の内部で(大切に温めるような気持ちをもっ
て)【懐】にするのに対し、普通の人の場合は、【之】(二面性をもった矛盾を生じる
「あぜ道」)を相手に対して【弁】じて(外部に見えるように)【示】すにすぎないと
言っているようです。
┃▼ 曰 何也 ┃【曰く、何ぞや。】
┃ 聖人懐之 ┃【聖人はこれを懐(ふところ)にし、】
┃ 衆人辯之以相示也 ┃【衆人はこれを辯(弁)じて相以って示す。】
┗━━━━━━━━━━━┛
どういうことかというと、こういうことだ。
聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【懐】は「心+右側の字(目からたれる涙+衣)」で、
「胸中やふところに入れて囲む」「中に囲んで大切に温める気持ち」。
*【衆】は「日(太陽)+人が三人(多くの人)」で、
「太陽のもとで多くの人が集団労働をしているさま」。「多くの」「普通の」の意。
*【示】は「祭壇」を描いた象形文字。「外にあらわして見せる」「人に見せる」の意。
◆通説では【聖人懐之 衆人辯之以相示也】の【之】は両方「道」だと解釈しています。
◇【之(これ)】は前文を受けて、「二面性をもった拠り所の感覚」といったニュアンスで、
聖人の場合は、【之】(言葉で表現されることとは別の不可分ままの感覚≒二面性をもっ
たパラドキシカルな「道」)を自分の心の内部で(大切に温めるような気持ちをもっ
て)【懐】にするのに対し、普通の人の場合は、【之】(二面性をもった矛盾を生じる
「あぜ道」)を相手に対して【弁】じて(外部に見えるように)【示】すにすぎないと
言っているようです。
●通説では、次のようになっています。
それはどういうことか。
聖人は道をそのままわが胸に収めるのであるが、
一般の人々は道に区別を立ててそれを他人に示すのである。
〇新解釈では、次のようになります。
どういうことかというと、こういうことだ。
聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。
【曰 何也】【曰く、何ぞや。】
〔どういうことかというと、こういうことだ。〕
──「分割」していても「分割してないものがある」とか、「弁じて」いても「弁じていないもの」があるという相反する二面的な表現は、パラドキシカルな感覚にも、矛盾する感覚にも思えるだけに、それはどういうことなのか、もう少し違う角度で説明しようとしているようです。
【聖人懐之】【聖人はこれを懐(ふところ)にし、】
〔聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
──聖人は表現上「分割」していたり「弁舌」していたりしても、それは表層の「仮の姿」ということを忘れずにいるため、「分割していないもの」「弁じていないもの」が同時にあるという意識を、言葉を用いることなく「懐(内部の深層部)」で大切にもち続けている者だと言っているようです。その感覚はパラドキシカルなものですが、矛盾するものではないということになるでしょう。
【衆人辯之以相示也】【衆人はこれを辯(弁)じて相以って示す。】
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。〕
──ところが、普通の人は、表現上の「分割」していたり「弁舌」していたりすることが「仮の姿」だとは思っておらず、その内容こそが重要なこととなり、相手に対して言葉で「弁じ」尽くせば「外的に見えるものになる」という気持ちでさし「示す」ことに奔走している者だと言っているようです。
それはどういうことか。
聖人は道をそのままわが胸に収めるのであるが、
一般の人々は道に区別を立ててそれを他人に示すのである。
〇新解釈では、次のようになります。
どういうことかというと、こういうことだ。
聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。
【曰 何也】【曰く、何ぞや。】
〔どういうことかというと、こういうことだ。〕
──「分割」していても「分割してないものがある」とか、「弁じて」いても「弁じていないもの」があるという相反する二面的な表現は、パラドキシカルな感覚にも、矛盾する感覚にも思えるだけに、それはどういうことなのか、もう少し違う角度で説明しようとしているようです。
【聖人懐之】【聖人はこれを懐(ふところ)にし、】
〔聖人は(表現とは別に、この不可分の感覚を)「懐(ふところ)にしている」が、
──聖人は表現上「分割」していたり「弁舌」していたりしても、それは表層の「仮の姿」ということを忘れずにいるため、「分割していないもの」「弁じていないもの」が同時にあるという意識を、言葉を用いることなく「懐(内部の深層部)」で大切にもち続けている者だと言っているようです。その感覚はパラドキシカルなものですが、矛盾するものではないということになるでしょう。
【衆人辯之以相示也】【衆人はこれを辯(弁)じて相以って示す。】
普通の人は相手に対して「弁じること」によって示そうとするにすぎないのだ。〕
──ところが、普通の人は、表現上の「分割」していたり「弁舌」していたりすることが「仮の姿」だとは思っておらず、その内容こそが重要なこととなり、相手に対して言葉で「弁じ」尽くせば「外的に見えるものになる」という気持ちでさし「示す」ことに奔走している者だと言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 故曰 辯也者有不見也 ┃【故に曰く、「辯(弁)ずるは見ざるあり」と。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。
…………………………………………………………………………………………………………
◆【辯也者有不見也】は、通説では「区別ということは〔道について〕見ないところを残
している」としています。
◇さて、ここの受け取り方が微妙です。というのも、ここの【辯(弁)】は聖人の弁か、
普通の人の弁かによって、受け取り方が違ってくるからです。ここでは、聖人が行うよ
うな本来の【辯】について語っているのだと解釈しました。つまり、前のパラドキシカ
ルな説明…「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ…と
言った説明を別の角度から補足したのだと思います。「弁じていないもの」とは矛盾を
生じかねない否定形ではなく、「懐」での感触としては確かなものとして肯定できる何
かが「ある」が、それは「見えないもの」だということになるようです。
┃▼ 故曰 辯也者有不見也 ┃【故に曰く、「辯(弁)ずるは見ざるあり」と。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。
…………………………………………………………………………………………………………
◆【辯也者有不見也】は、通説では「区別ということは〔道について〕見ないところを残
している」としています。
◇さて、ここの受け取り方が微妙です。というのも、ここの【辯(弁)】は聖人の弁か、
普通の人の弁かによって、受け取り方が違ってくるからです。ここでは、聖人が行うよ
うな本来の【辯】について語っているのだと解釈しました。つまり、前のパラドキシカ
ルな説明…「弁じること」はあっても、そこには「弁じていないもの」があるのだ…と
言った説明を別の角度から補足したのだと思います。「弁じていないもの」とは矛盾を
生じかねない否定形ではなく、「懐」での感触としては確かなものとして肯定できる何
かが「ある」が、それは「見えないもの」だということになるようです。
●通説では、次のようになっています。
そこで、区別ということは〔道について〕見ないところを残している、というのである。
〇新解釈では、次のようになります。
だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。
【故曰 辯也者有不見也】【故に曰く、「辯(弁)ずるは見ざるあり」と。】
〔だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。〕
──本来の「弁じる」ということは、「分割」をまのがれ得ない「言葉」だけがあるのではなく、常に「懐(胸中)」にて収められている「見ることができないもの(弁じ得ないもの)」があると言えるのだ…と言っているようです。
想像するに、「見えないもの」とは、「言葉」を使って思考を伴う認識とは違って、「実存の波動」とでもいうべきような「バイブレーション」を「懐」で感じることだけしかできない認識なのかもしれません。
「泥玉」の喩えで言うならば、「土(泥)」という「見える形」の中に、「見えなくなってしまっている水(の振動)」を感じながら認識することだと言えるかもしれませんね。宇宙の大海と一体となることができる「水」は相手の中にも存在していて、共振という形でいつでも融合可能になれるものなのかもしれませんが、普通の感覚では「見えないもの」としか言えないのでしょう。
そこで、区別ということは〔道について〕見ないところを残している、というのである。
〇新解釈では、次のようになります。
だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。
【故曰 辯也者有不見也】【故に曰く、「辯(弁)ずるは見ざるあり」と。】
〔だからこう言う。「(本来の)弁じることには、見えないものがある」と。〕
──本来の「弁じる」ということは、「分割」をまのがれ得ない「言葉」だけがあるのではなく、常に「懐(胸中)」にて収められている「見ることができないもの(弁じ得ないもの)」があると言えるのだ…と言っているようです。
想像するに、「見えないもの」とは、「言葉」を使って思考を伴う認識とは違って、「実存の波動」とでもいうべきような「バイブレーション」を「懐」で感じることだけしかできない認識なのかもしれません。
「泥玉」の喩えで言うならば、「土(泥)」という「見える形」の中に、「見えなくなってしまっている水(の振動)」を感じながら認識することだと言えるかもしれませんね。宇宙の大海と一体となることができる「水」は相手の中にも存在していて、共振という形でいつでも融合可能になれるものなのかもしれませんが、普通の感覚では「見えないもの」としか言えないのでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-