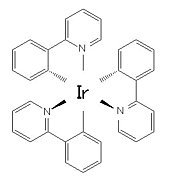たとえば、東京スカイツリーのような大きな建造物の設計に際して、風洞実験を行って耐風安定性を検証しようとします。
何分の一かの模型をつくって大きな扇風機が吸引する風にさらします。
実際のタワーが風速80m/s、90m/sの風に耐えられるかどうかを実験で検証したいとき、模型をおいた風洞では何mの風を吹かせばよいのでしょうか。
20分の1の模型であれば、風速も同じ比率で縮小して4m/sや、4.5m/sの風を吹かせば実験をしたことになるでしょうか。
これに関連して知っておかなければならないことが「相似則」です。
およそほとんどの物理量、つまり長さとか質量とか時間とかですが、すべて単位というものをもっています。
このような基本的な単位から、長さと時間を組み合わせて速度や加速度を求めるとか、そのほかにも力や運動量、応力やエネルギーといった、それぞれ基本単位の積からなる単位を持つ物理量に展開していきます。
単位とは次元と尺度からなっていますが、本質的な性質は次元です。
日常的な感覚からでも、誰もが異なる単位のものは足し合わせることが出来ないこと、それが意味のないことを知っています。
速さと長さのそれぞれの大きさを足してもなんの意味もありません。
したがって現実の物理現象を説明する計算式は、この次元の法則が守られていなければならないことがわかります。
このように、物理法則を表す計算式は必ず次元の法則を守っていることを前提として、物理現象の変数が変化したとき、他の変数をどのように変化させればいいかを考えることができます。
タワー柱に風がぶつかっている状態を想定して実験してみたい。
直径dの柱の周りを、粘性係数μ、密度ρの流体が、速度uで流れる実物に対し、模型の柱の直径D=αdとするとき、いくらの粘性係数(M=βμ)の、いくらの密度(P=γρ)の流体を、いくらの速度(U=δu)で流せば実験たり得るか、という問題として考えてみます。
この、αβγδの関係式ができればいいということになります。
この場合、dは[m]、μは[?/m・s]、ρは[?/m3]、uは[m/s]の単位を持つことからこれらの組み合わせで、次元のない無次元量となる関係をつくると、uとdとρの積がμと同じ次元を持つことになるから、u・d・ρをμで除する式をつくればこれは無次元数となります。
この式の分子分母をρで割ると、これは慣性力と粘性力の比である有名な無次元量であるレイノルズ数となります。
このような流体を考えるのであれば、α・δ=β・γの関係を満たすように決めればいいことです。
直径の縮小に応じて、適宜それに合う粘性係数や密度を持つ流体を探して、いまの式に合う速度で流せばいいのです。
20分の1の模型であるから、20分の1の流速で流せば実験たり得るという単純なものでないことがわかりました。
ここで、理学的な話ではないが、相似則は社会現象においてどのようになされているのかを少し考察してみたいと思います。
そもそもアメリカで成立する法則、たとえば経済政策や教育政策などが日本に適用できるために成立していなければならない相似性についてどう考えればいいのでしょうか。
司法制度審議会が、わが国は今後は国のかたちとして「事前調整型」から[事後調整型」に変わるのだといったといいますが、事前調整から事後調整に変わるためには、社会を成立させている多くの変数・パラメーターが、いかなる相似則に基づいて、どう変わらなければならないのか、また変わっていなければならないのかが、研究され尽くしていなければいけません。
人の世界である国のかたちを規定するパラメーターである次元数は、物理の世界よりもはるかに複雑で、無限にあります。
その何をとればただしく相似則が成り立つように出来るのでしょうか。
たとえば無常観を持たざるを得ないほどの厳しい自然災害、つまり一瞬にすべての資産を崩壊させ多大な人命を奪う大地震や、家屋も田畑もすべてを押し流す洪水などを経験する国としない国との違い。
また、長い歴史が侵略と大量虐殺に埋め尽くされていて、死に臨めば必ず誰かに恨みを残していった国と、歴史的にほとんど皆殺し的戦争もせず皆殺しにされた経験もなく、死に際して人を憎まずあきらめを抱いて赴いた国との違い。
絶対神を有する一神教的な世界と、自然に神性があると考える多神の世界との違い。
大勢が役割分担して狩りをするための作業の共同と、そのための高いコミュニケーション作法を必要とした世界と、人と違うタイミングで田植えをすれば田に水も引けず、収穫期の違う稲の作付けをすれば単独で雀たちと戦わなければならないから、他人との協調と同調を基本にせざるを得ない世界との違い。
会を成立させている数多くの変数・パラメーターの相似則も考えずに、仮説を立て実物に当てはめてしまうと、社会の実相を無視した誤った結論に導く答えしか出てきません。
仮説の適用にあたって考えるべき社会のための相似則は、必ず存在するが、どの条件の適合を仮説の制度化への前提とするかはきわめて重要だということです。
何分の一かの模型をつくって大きな扇風機が吸引する風にさらします。
実際のタワーが風速80m/s、90m/sの風に耐えられるかどうかを実験で検証したいとき、模型をおいた風洞では何mの風を吹かせばよいのでしょうか。
20分の1の模型であれば、風速も同じ比率で縮小して4m/sや、4.5m/sの風を吹かせば実験をしたことになるでしょうか。
これに関連して知っておかなければならないことが「相似則」です。
およそほとんどの物理量、つまり長さとか質量とか時間とかですが、すべて単位というものをもっています。
このような基本的な単位から、長さと時間を組み合わせて速度や加速度を求めるとか、そのほかにも力や運動量、応力やエネルギーといった、それぞれ基本単位の積からなる単位を持つ物理量に展開していきます。
単位とは次元と尺度からなっていますが、本質的な性質は次元です。
日常的な感覚からでも、誰もが異なる単位のものは足し合わせることが出来ないこと、それが意味のないことを知っています。
速さと長さのそれぞれの大きさを足してもなんの意味もありません。
したがって現実の物理現象を説明する計算式は、この次元の法則が守られていなければならないことがわかります。
このように、物理法則を表す計算式は必ず次元の法則を守っていることを前提として、物理現象の変数が変化したとき、他の変数をどのように変化させればいいかを考えることができます。
タワー柱に風がぶつかっている状態を想定して実験してみたい。
直径dの柱の周りを、粘性係数μ、密度ρの流体が、速度uで流れる実物に対し、模型の柱の直径D=αdとするとき、いくらの粘性係数(M=βμ)の、いくらの密度(P=γρ)の流体を、いくらの速度(U=δu)で流せば実験たり得るか、という問題として考えてみます。
この、αβγδの関係式ができればいいということになります。
この場合、dは[m]、μは[?/m・s]、ρは[?/m3]、uは[m/s]の単位を持つことからこれらの組み合わせで、次元のない無次元量となる関係をつくると、uとdとρの積がμと同じ次元を持つことになるから、u・d・ρをμで除する式をつくればこれは無次元数となります。
この式の分子分母をρで割ると、これは慣性力と粘性力の比である有名な無次元量であるレイノルズ数となります。
このような流体を考えるのであれば、α・δ=β・γの関係を満たすように決めればいいことです。
直径の縮小に応じて、適宜それに合う粘性係数や密度を持つ流体を探して、いまの式に合う速度で流せばいいのです。
20分の1の模型であるから、20分の1の流速で流せば実験たり得るという単純なものでないことがわかりました。
ここで、理学的な話ではないが、相似則は社会現象においてどのようになされているのかを少し考察してみたいと思います。
そもそもアメリカで成立する法則、たとえば経済政策や教育政策などが日本に適用できるために成立していなければならない相似性についてどう考えればいいのでしょうか。
司法制度審議会が、わが国は今後は国のかたちとして「事前調整型」から[事後調整型」に変わるのだといったといいますが、事前調整から事後調整に変わるためには、社会を成立させている多くの変数・パラメーターが、いかなる相似則に基づいて、どう変わらなければならないのか、また変わっていなければならないのかが、研究され尽くしていなければいけません。
人の世界である国のかたちを規定するパラメーターである次元数は、物理の世界よりもはるかに複雑で、無限にあります。
その何をとればただしく相似則が成り立つように出来るのでしょうか。
たとえば無常観を持たざるを得ないほどの厳しい自然災害、つまり一瞬にすべての資産を崩壊させ多大な人命を奪う大地震や、家屋も田畑もすべてを押し流す洪水などを経験する国としない国との違い。
また、長い歴史が侵略と大量虐殺に埋め尽くされていて、死に臨めば必ず誰かに恨みを残していった国と、歴史的にほとんど皆殺し的戦争もせず皆殺しにされた経験もなく、死に際して人を憎まずあきらめを抱いて赴いた国との違い。
絶対神を有する一神教的な世界と、自然に神性があると考える多神の世界との違い。
大勢が役割分担して狩りをするための作業の共同と、そのための高いコミュニケーション作法を必要とした世界と、人と違うタイミングで田植えをすれば田に水も引けず、収穫期の違う稲の作付けをすれば単独で雀たちと戦わなければならないから、他人との協調と同調を基本にせざるを得ない世界との違い。
会を成立させている数多くの変数・パラメーターの相似則も考えずに、仮説を立て実物に当てはめてしまうと、社会の実相を無視した誤った結論に導く答えしか出てきません。
仮説の適用にあたって考えるべき社会のための相似則は、必ず存在するが、どの条件の適合を仮説の制度化への前提とするかはきわめて重要だということです。
|
|
|
|
|
|
|
|
科学の知恵袋 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-