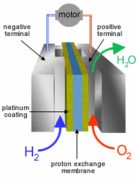燃料電池の起源は内燃機関より古く、原型は1839年のウィリアム・グローブ卿の発明まで遡る。酸素と水素がそれぞれ入った容器が希硫酸に浸されており、容器内に白金電極を挿入することで、電気を取り出せることを示した。1958年、アルカリ形燃料電池が実用化され、1968年からアポロ計画に採用。固体高分子形燃料電池は、1965年、GE(ゼネラルエレクトリック)社がナフィオン膜を用いたものを開発。ジェミニ計画に用いられ始めて実用化された。宇宙開発での実用化成功を受け、民生用燃料電池の開発も始まり、純水素の使用でコストのかかっていた宇宙開発用のアルカリ形燃料電池に代わって、燃料に多少の不純物を許容する固体酸化物形と溶融炭酸塩形の開発へと移行していった。
この頃から、地球規模で環境問題への関心が高まり、小型軽量で低温作動の固体高分子形燃料電池が、事業用だけでなく自動車や携帯用電源、家庭用電源として注目されるようになり、現在も研究が盛んに行われている。
次回は、「原理について」
この頃から、地球規模で環境問題への関心が高まり、小型軽量で低温作動の固体高分子形燃料電池が、事業用だけでなく自動車や携帯用電源、家庭用電源として注目されるようになり、現在も研究が盛んに行われている。
次回は、「原理について」
|
|
|
|
コメント(4)
PEFCの場合はナフィオンが使用されてからずいぶんたつけど、いまだに完全に代用できるものが開発されていない。もともと水酸化ナトリウム製造用の電解質膜だったのに…
技術の確立は早い時期からされていたのに、ここまでまったく普及されなかったのはコストの面が大きく関わってます。電解質膜、白金触媒、加湿器や一酸化炭素のフィルター、etc
石油をイケイケで使っていた、当時は燃料電池のようにコストが高いクリーンエネルギーは関心が低かったみたいです。
でも今は違う。世界がクリーンエネルギーを求め、燃料電池にも次代のエース的存在になってきました。
次回の原理にこうご期待
写真は実用化されたヤ○ハの二輪車
技術の確立は早い時期からされていたのに、ここまでまったく普及されなかったのはコストの面が大きく関わってます。電解質膜、白金触媒、加湿器や一酸化炭素のフィルター、etc
石油をイケイケで使っていた、当時は燃料電池のようにコストが高いクリーンエネルギーは関心が低かったみたいです。
でも今は違う。世界がクリーンエネルギーを求め、燃料電池にも次代のエース的存在になってきました。
次回の原理にこうご期待
写真は実用化されたヤ○ハの二輪車
去年まで基礎研究を行っていたとりさんともうします。
1 動作温度 について
PEFCは運転温度が60℃から80℃くらいですが、実験を行う際は定常状態を確保するためにヒーターなどでセルを暖めます。ですが、実用化されたスタックでは起動するときに徐々に電流を吸い出すためそのときの損失となるジュール熱がスタックそのものを温めていくと考えられます。なので発電時はかならず冷却が必要になります。(色々な問題が起こるため。)
2 エネファームでのガス燃焼について
これは、メタンガスから水素へ改質する際に700℃近くの高温状態が必要なためです。
なので水素が生成され、硫黄分などの不純物が除去されたあとはセルスタック温度近くまで冷却されるはずです。(でないと高分子膜がダメになるはず。)
常温で高効率な燃料電池はおそらくPEFCとなるのではないかな?と思います。
出先で携帯電話からの入力のためおおざっぱな回答になってしまい、もうしわけございません。
(間違いがあったら訂正お願いします。)
1 動作温度 について
PEFCは運転温度が60℃から80℃くらいですが、実験を行う際は定常状態を確保するためにヒーターなどでセルを暖めます。ですが、実用化されたスタックでは起動するときに徐々に電流を吸い出すためそのときの損失となるジュール熱がスタックそのものを温めていくと考えられます。なので発電時はかならず冷却が必要になります。(色々な問題が起こるため。)
2 エネファームでのガス燃焼について
これは、メタンガスから水素へ改質する際に700℃近くの高温状態が必要なためです。
なので水素が生成され、硫黄分などの不純物が除去されたあとはセルスタック温度近くまで冷却されるはずです。(でないと高分子膜がダメになるはず。)
常温で高効率な燃料電池はおそらくPEFCとなるのではないかな?と思います。
出先で携帯電話からの入力のためおおざっぱな回答になってしまい、もうしわけございません。
(間違いがあったら訂正お願いします。)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
固体高分子形燃料電池(PEFC) 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-