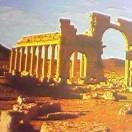今回から1年ぶりにユング路線に戻りましたので、ちょっと講義を聴いてのメモを書きました。
聴きながらのメモなので、理解が間違っているところしゃ主観もありますので、ご了承ください。
「ユング研 赤の書についての講義 表現するとはどういうことか」
2月16日は、白田さんによるユングの赤の書についてでした。
とっても楽しみにしていたので、真剣に聞きましたよ。(いつも真剣ですが)
さて今回白田さんが、ユングの赤の書を通してテーマとしてことは、「表現するということは、いったい何なのだろう」ということです。
赤の書は、ユングが心の不安定な時期で、時代も激動であった時期に書き始めて約16年間書き綴ったユングの私的日記です。(1914年から1930年)
この私的という意味は、もともと霊的に敏感なユングが、多分この激動の時代と不安定なユングの心がシンクロし合い、そこから人類共通の何かが夢として表現されてきたのだろうと推測されるが、そういった彼個人の内的な出来事を文書に、絵画に表現していった日記であるということです。
http://
日記の書式は、初期の第一の書は、18ページで、文字で書かれていて、形式的にも整っていて、最初から赤の書を出版するつもりで書いたのではないかと白田さんは考えているそうです。
しかし書に表現していくということは、自分の夢との対話ですから、どんどん深くなっていくのでしょうし、表現も洗練されていく。その結果、当初の形式からはどんどんはずれ、絵画になっていくわけです。
実際第2の書は、180ページがほとんど絵画でしかも、どんどん形式が進化・変化していっています。ちなみに第三の書は本にはならかったそうです。
日記では、「今の精神とは違う精神が私に「せよ」と語りかけてくる。それを私は書いている」といった風な大げさな言い回しになっていて、ユング自信もあまりそれが好きでないそうです。そしてしだいに文字が減っていき、最初の一ページぶち抜きの絵がギルガメッシュだそうです。ギルガメッシュは冥界への案内人という意味があるんでしょう。
ストーリーを追っていくと、
巨人(ギルガメッシュ)が現れる
→ 巨人が死にかかる
→ 巨大な力を得る
→ 呪文と絵が延々と続く
→ 神が出てくる
→ 神がどこかにいっていしまい地獄めぐりが始まる
→ 曼荼羅イメージが出てきてどんどん変化する(自分の中の神をコントロールできないジレンマを曼荼羅を書いて沈める)
→ 太陽を蛇が食べようとする
→ 蛇から賢者の石にかわる(賢者の石の裏側は邪悪)
→ ・・・
という感じだったかな。誤解やもれているものがたくさんあるかもしれませんが、こんな感じです。
ところがユングは、これを書くのを突然中断します。原因は、ヴィルヘルムに錬金術の事を教えてもらい、さらに曼荼羅の存在を知ったためだそうで、自分が描いていたものが曼荼羅と同じであることを知ります。
ユングに何がおきたかというと、赤の書は、ユングの内面の探索であり、それを絵画という手法で表現して来たわけですが、錬金術がそれと同じ研究を外面の世界でやっていたということを知ったわけです。そのため、赤の書の役割を終え、連金術の研究に切り換わったということだそうです。
中断は、1902〜1928年は空白で、再度晩年の1959年に少し書いているすです。(ユングが亡くなったのは1961年85歳)
さて、白田さんの今回のテーマは、「表現とは何だろう」でした。
私たちは、表現することで、世界の関係性を変えていくのだ、というのが結論です。われわれの行為によって、世界は変わっていくと。
つまり外面の世界でわれわれは科学や工学を発展させ、世界を作り変えていってますが、それは内面でも同じだということを言いたいわけです。
行為は、外面だけでなく、内面も含む。
たとえば親鸞の念仏を例に挙げてますが、念仏を唱える時点で、世界の関係性が代わっていく、世界が変わっていく。つまりこれがユングのいう布置(個人の心(内面)における問題のありようと、ちょうど対応するように、外的世界の事物や事象が、ある特定の配置を持って現れてくる)という概念に同じだというわけです。
われわれは夢と対話したり、内面から湧き上がるものを芸術として表現することで、外面だけに限らず内面においえても世界の関係性を変えている、再構築していっているというわけです。
ポストモダン的にいうと間主観性というものが、我々の考え方や思考、言語を規制している構造なわけですが、この間主観性の構造が白田さんが言っている世界の関係性なわけで、我々は表現するという行為を通して、まさにそういった側面からも世界を変えていっているよ。だから表現するということは、芸術はとっても大切なんだよというのが彼の主張だったと思います。
ちなみに白田さん自身も前期のテーマである「芸術のことば」に自分は強く影響されたと。それで今回は、レジュメを作らずに、表現していくというスタイルに挑戦してみました。ということでした。
聴きながらのメモなので、理解が間違っているところしゃ主観もありますので、ご了承ください。
「ユング研 赤の書についての講義 表現するとはどういうことか」
2月16日は、白田さんによるユングの赤の書についてでした。
とっても楽しみにしていたので、真剣に聞きましたよ。(いつも真剣ですが)
さて今回白田さんが、ユングの赤の書を通してテーマとしてことは、「表現するということは、いったい何なのだろう」ということです。
赤の書は、ユングが心の不安定な時期で、時代も激動であった時期に書き始めて約16年間書き綴ったユングの私的日記です。(1914年から1930年)
この私的という意味は、もともと霊的に敏感なユングが、多分この激動の時代と不安定なユングの心がシンクロし合い、そこから人類共通の何かが夢として表現されてきたのだろうと推測されるが、そういった彼個人の内的な出来事を文書に、絵画に表現していった日記であるということです。
http://
日記の書式は、初期の第一の書は、18ページで、文字で書かれていて、形式的にも整っていて、最初から赤の書を出版するつもりで書いたのではないかと白田さんは考えているそうです。
しかし書に表現していくということは、自分の夢との対話ですから、どんどん深くなっていくのでしょうし、表現も洗練されていく。その結果、当初の形式からはどんどんはずれ、絵画になっていくわけです。
実際第2の書は、180ページがほとんど絵画でしかも、どんどん形式が進化・変化していっています。ちなみに第三の書は本にはならかったそうです。
日記では、「今の精神とは違う精神が私に「せよ」と語りかけてくる。それを私は書いている」といった風な大げさな言い回しになっていて、ユング自信もあまりそれが好きでないそうです。そしてしだいに文字が減っていき、最初の一ページぶち抜きの絵がギルガメッシュだそうです。ギルガメッシュは冥界への案内人という意味があるんでしょう。
ストーリーを追っていくと、
巨人(ギルガメッシュ)が現れる
→ 巨人が死にかかる
→ 巨大な力を得る
→ 呪文と絵が延々と続く
→ 神が出てくる
→ 神がどこかにいっていしまい地獄めぐりが始まる
→ 曼荼羅イメージが出てきてどんどん変化する(自分の中の神をコントロールできないジレンマを曼荼羅を書いて沈める)
→ 太陽を蛇が食べようとする
→ 蛇から賢者の石にかわる(賢者の石の裏側は邪悪)
→ ・・・
という感じだったかな。誤解やもれているものがたくさんあるかもしれませんが、こんな感じです。
ところがユングは、これを書くのを突然中断します。原因は、ヴィルヘルムに錬金術の事を教えてもらい、さらに曼荼羅の存在を知ったためだそうで、自分が描いていたものが曼荼羅と同じであることを知ります。
ユングに何がおきたかというと、赤の書は、ユングの内面の探索であり、それを絵画という手法で表現して来たわけですが、錬金術がそれと同じ研究を外面の世界でやっていたということを知ったわけです。そのため、赤の書の役割を終え、連金術の研究に切り換わったということだそうです。
中断は、1902〜1928年は空白で、再度晩年の1959年に少し書いているすです。(ユングが亡くなったのは1961年85歳)
さて、白田さんの今回のテーマは、「表現とは何だろう」でした。
私たちは、表現することで、世界の関係性を変えていくのだ、というのが結論です。われわれの行為によって、世界は変わっていくと。
つまり外面の世界でわれわれは科学や工学を発展させ、世界を作り変えていってますが、それは内面でも同じだということを言いたいわけです。
行為は、外面だけでなく、内面も含む。
たとえば親鸞の念仏を例に挙げてますが、念仏を唱える時点で、世界の関係性が代わっていく、世界が変わっていく。つまりこれがユングのいう布置(個人の心(内面)における問題のありようと、ちょうど対応するように、外的世界の事物や事象が、ある特定の配置を持って現れてくる)という概念に同じだというわけです。
われわれは夢と対話したり、内面から湧き上がるものを芸術として表現することで、外面だけに限らず内面においえても世界の関係性を変えている、再構築していっているというわけです。
ポストモダン的にいうと間主観性というものが、我々の考え方や思考、言語を規制している構造なわけですが、この間主観性の構造が白田さんが言っている世界の関係性なわけで、我々は表現するという行為を通して、まさにそういった側面からも世界を変えていっているよ。だから表現するということは、芸術はとっても大切なんだよというのが彼の主張だったと思います。
ちなみに白田さん自身も前期のテーマである「芸術のことば」に自分は強く影響されたと。それで今回は、レジュメを作らずに、表現していくというスタイルに挑戦してみました。ということでした。
|
|
|
|
コメント(9)
清志朗さんの日記に書かせていただいたコメントを、こちらにものせさせていただきます
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
清志朗さん、ご講義の内容を伝えてくださって、ありがとうございます。
どんなご講義だったのか、ずっと気になっていたのですよ。
「表現する」ことによって世界を変えていく、というのは、個人の生活の中でもありうることだと思いました。
何も言わなかったりしなかったりする緘黙や不登校、引きこもりでさえも、当人にとっては、「表現」であり、そのアンバランスさが次なる発展の契機となることもあると思います。その発展を手助けするのに、ユング心理学が貢献できるといいですよね。
また、ユングは、書く(描く)ことによって、気が狂うことから免れたのだとも思います。
私には、太陽を蛇が食べようとするイメージが、「無意識」が「意識」を呑み込もうとするイメージのように思えて仕方ありません。
そしておそらくは、「無意識」の奔流に呑み込まれず、「意識」の優位を保つためには、「書く(描く)」ことが不可欠だったのでしょう・・・。そうした無意識と意識の格闘の過程を描いたものが『赤の書』なのだと思います。
「芸術」をはじめとする「表現すること」は、まさに「心理活動の賜物」と言ってもいいですよね
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
清志朗さん、ご講義の内容を伝えてくださって、ありがとうございます。
どんなご講義だったのか、ずっと気になっていたのですよ。
「表現する」ことによって世界を変えていく、というのは、個人の生活の中でもありうることだと思いました。
何も言わなかったりしなかったりする緘黙や不登校、引きこもりでさえも、当人にとっては、「表現」であり、そのアンバランスさが次なる発展の契機となることもあると思います。その発展を手助けするのに、ユング心理学が貢献できるといいですよね。
また、ユングは、書く(描く)ことによって、気が狂うことから免れたのだとも思います。
私には、太陽を蛇が食べようとするイメージが、「無意識」が「意識」を呑み込もうとするイメージのように思えて仕方ありません。
そしておそらくは、「無意識」の奔流に呑み込まれず、「意識」の優位を保つためには、「書く(描く)」ことが不可欠だったのでしょう・・・。そうした無意識と意識の格闘の過程を描いたものが『赤の書』なのだと思います。
「芸術」をはじめとする「表現すること」は、まさに「心理活動の賜物」と言ってもいいですよね
わぁ・・・、夜叉に「意識」が呑み込まれたらどうなるんでしょう・・・。この世で社会的に生き抜いていくためには、(たとえば鉦の音や太鼓の音を鳴らして)この世のルール(意識)をきちんと目覚めさせておかなければなりませんよね。
ところで、錬金術にも、緑のライオンが太陽を食べる絵がありますよ。
フォン・フランツによると、ライオンは死から復活するための仲介者――意識と無意識の間に起こる律動的な変化や太陽と生命の神秘に関係しているもの――の象徴なのだそうです。
国や地域を変えても、似たようなイメージが、人々の心に浮かび上がり、人々の心を強くとらえるのを知ると、やはりユングの言うように「集合的無意識(普遍的無意識)」なるものの存在を仮定したくなりますよね
ところで、錬金術にも、緑のライオンが太陽を食べる絵がありますよ。
フォン・フランツによると、ライオンは死から復活するための仲介者――意識と無意識の間に起こる律動的な変化や太陽と生命の神秘に関係しているもの――の象徴なのだそうです。
国や地域を変えても、似たようなイメージが、人々の心に浮かび上がり、人々の心を強くとらえるのを知ると、やはりユングの言うように「集合的無意識(普遍的無意識)」なるものの存在を仮定したくなりますよね
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-