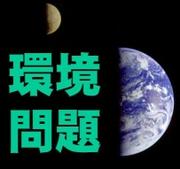|
|
|
|
コメント(37)
英国のキュー王立植物園、ロンドン自然史博物館、それに自然保護団体の国際自然保護連合(IUCN)の科学者が発表したところによると、世界にある38万種の植物のうち、5分の1が絶滅の危機に瀕しており、最大の原因が人間の活動にあるという。
報告によると、植物にとって一番の脅威は農地への転用で、絶滅危惧種の33%が直接的な影響を受けている。
その他の脅威としては、開発、森林伐採、それに家畜のための土地利用などが挙げられた。
また、最も打撃を受けている場所はブラジルの熱帯雨林のような熱帯林だいう。
キュー植物園の責任者スティーブン・ホッパー氏は、
「何もせずに植物の種が失われていくのを見ているわけにはいかない。植物は地球上のすべての生物の基盤となっており、きれいな空気、食物、それに燃料を提供する。すべての動物は植物に頼っており、われわれ人間もそうだ」
と語った。
科学者らは、IUCNの絶滅危惧種リストに追加予定の植物リスト作成のために行った5年間にわたる調査データを利用した。
世界の植物が直面する脅威について世界的な分析が行われたのは今回が初めてのため、科学者らは今回の結果が自然保護活動の進ちょくを計る基準になることを望んでいる。
この報告は、10月半ばに名古屋で開かれる生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に先だって発表された。
この会議で各国は世界の動植物保護に向けた新たな目標を設定することになっている。
参照
ロイター通信 2010年9月30日
http://jp.reuters.com/article/jpnewEnv/idJPjiji2010093000321
報告によると、植物にとって一番の脅威は農地への転用で、絶滅危惧種の33%が直接的な影響を受けている。
その他の脅威としては、開発、森林伐採、それに家畜のための土地利用などが挙げられた。
また、最も打撃を受けている場所はブラジルの熱帯雨林のような熱帯林だいう。
キュー植物園の責任者スティーブン・ホッパー氏は、
「何もせずに植物の種が失われていくのを見ているわけにはいかない。植物は地球上のすべての生物の基盤となっており、きれいな空気、食物、それに燃料を提供する。すべての動物は植物に頼っており、われわれ人間もそうだ」
と語った。
科学者らは、IUCNの絶滅危惧種リストに追加予定の植物リスト作成のために行った5年間にわたる調査データを利用した。
世界の植物が直面する脅威について世界的な分析が行われたのは今回が初めてのため、科学者らは今回の結果が自然保護活動の進ちょくを計る基準になることを望んでいる。
この報告は、10月半ばに名古屋で開かれる生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に先だって発表された。
この会議で各国は世界の動植物保護に向けた新たな目標を設定することになっている。
参照
ロイター通信 2010年9月30日
http://jp.reuters.com/article/jpnewEnv/idJPjiji2010093000321
【COP16京都議定書扱い焦点に メキシコで閣僚準備会合】
メキシコ・カンクンで開かれる気候変動枠組み条約第16回締約国会議(COP16)を前に、メキシコ市で閣僚級の準備会合が開かれ、先進国の温室効果ガス削減目標を定めた京都議定書の枠組みを、2013年以降も続けるよう求める意見が発展途上国などから相次いだ。
これに対し、日本やカナダ、ロシアは、「先進国のみが義務を負う枠組みの延長は認められない」と反対姿勢を表明。
締約国会議で議論の焦点になりそうだ。
会合には約50カ国が参加し、議定書に定めのない13年以降の枠組みや途上国支援について意見交換。
交渉が進まないため13年以降に削減目標の「空白期間」が生じる恐れがあることから、暫定的に議定書の削減目標を延長するのを検討するよう求める声が途上国から出て、欧州連合(EU)も同調した。
日本やカナダ、ロシアは、「議定書の枠組みは世界の排出量の27%しかカバーされておらず不十分」と反対。
議定書を未批准の米国は静観の構えだった。
参照
神戸新聞 2010年11月6日
http://www.kobe-np.co.jp/knews/0003587115.shtml
メキシコ・カンクンで開かれる気候変動枠組み条約第16回締約国会議(COP16)を前に、メキシコ市で閣僚級の準備会合が開かれ、先進国の温室効果ガス削減目標を定めた京都議定書の枠組みを、2013年以降も続けるよう求める意見が発展途上国などから相次いだ。
これに対し、日本やカナダ、ロシアは、「先進国のみが義務を負う枠組みの延長は認められない」と反対姿勢を表明。
締約国会議で議論の焦点になりそうだ。
会合には約50カ国が参加し、議定書に定めのない13年以降の枠組みや途上国支援について意見交換。
交渉が進まないため13年以降に削減目標の「空白期間」が生じる恐れがあることから、暫定的に議定書の削減目標を延長するのを検討するよう求める声が途上国から出て、欧州連合(EU)も同調した。
日本やカナダ、ロシアは、「議定書の枠組みは世界の排出量の27%しかカバーされておらず不十分」と反対。
議定書を未批准の米国は静観の構えだった。
参照
神戸新聞 2010年11月6日
http://www.kobe-np.co.jp/knews/0003587115.shtml
■中東の水不足深刻化 国際協力体制を シンクタンク提言■
水不足が深刻化している中東地域の各国は協力して対応に乗り出す必要があるとの報告書を、インドのシンクタンク「戦略展望グループ」がまとめ、公表した。
スイス、スウェーデン両政府の要請に基づいてまとめられたこの報告書によると、ヨルダン川やヤルムク川などの主要河川の水量は過去50年で大幅に減っている。
また、ユーフラテス川が干ばつで干上がる場合があることも予測され、死海は2050年には小さな湖になってしまうという。
これらの河川の下流に位置するイスラエルやヨルダン、パレスチナ自治区ではそれぞれ5億〜7億立方メートルの上水が不足している。
一方、上流に位置するトルコは、1980年代にイスラエルやペルシャ湾沿岸諸国への上水パイプライン建設を計画して失敗に終わった経緯があるものの、「平和に向けた影響力を」行使できる立場にあるとしている。
また報告書は、イスラエルの持つ海水淡水化や排水再利用などの技術の効果は限定的だろうと指摘し、「イスラエルも2020年以降には、国外からの水の調達や、水資源確保のための域内協力をする必要が出てくるだろう」とした。
スイスのミシュリン・カルミレイ外相は、トルコ、イラク、シリア、レバノン、ヨルダン、パレスチナ自治区、イスラエルが緊密に協力して水資源の管理を行うよう呼びかけた。
スイスは、トルコ、イラク、ヨルダン、シリアが既に始めている取り組みを拡大する形での水資源管理の協力体制の実現に向け、上記7か国・地域の政府に働きかけている。
参照
AFP 2011年2月22日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2786742/6851129
水不足が深刻化している中東地域の各国は協力して対応に乗り出す必要があるとの報告書を、インドのシンクタンク「戦略展望グループ」がまとめ、公表した。
スイス、スウェーデン両政府の要請に基づいてまとめられたこの報告書によると、ヨルダン川やヤルムク川などの主要河川の水量は過去50年で大幅に減っている。
また、ユーフラテス川が干ばつで干上がる場合があることも予測され、死海は2050年には小さな湖になってしまうという。
これらの河川の下流に位置するイスラエルやヨルダン、パレスチナ自治区ではそれぞれ5億〜7億立方メートルの上水が不足している。
一方、上流に位置するトルコは、1980年代にイスラエルやペルシャ湾沿岸諸国への上水パイプライン建設を計画して失敗に終わった経緯があるものの、「平和に向けた影響力を」行使できる立場にあるとしている。
また報告書は、イスラエルの持つ海水淡水化や排水再利用などの技術の効果は限定的だろうと指摘し、「イスラエルも2020年以降には、国外からの水の調達や、水資源確保のための域内協力をする必要が出てくるだろう」とした。
スイスのミシュリン・カルミレイ外相は、トルコ、イラク、シリア、レバノン、ヨルダン、パレスチナ自治区、イスラエルが緊密に協力して水資源の管理を行うよう呼びかけた。
スイスは、トルコ、イラク、ヨルダン、シリアが既に始めている取り組みを拡大する形での水資源管理の協力体制の実現に向け、上記7か国・地域の政府に働きかけている。
参照
AFP 2011年2月22日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2786742/6851129
■温室ガス削減 新枠組みで「罰則なし」求める■
京都議定書に続く2013年以降の温室効果ガス削減の新枠組みを巡り、環境省は、今年末に南アフリカで開かれる気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)に向け、新枠組みでは削減目標を達成できなかった場合の罰則を設けないように求める方針を固めた。
仙台市で開かれたCOPの全国説明会で、同省の南川秀樹次官が「目標を守ることは必要だが、少しでも超えると重い罰が加わるのがいいかは検討が必要だ」と述べた。
京都議定書では、各国が約束期間(08〜12年)内に削減目標を達成できなかった場合、超過した排出量の1.3倍を次の約束期間の削減義務に上乗せする罰則規定がある。
この規定は、各国が確実にガスを削減する動機付けになり、各国間の公平性を担保する役割も果たしていた。
参照
読売新聞 2011年2月22日
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20110222-OYT1T01003.htm
京都議定書に続く2013年以降の温室効果ガス削減の新枠組みを巡り、環境省は、今年末に南アフリカで開かれる気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)に向け、新枠組みでは削減目標を達成できなかった場合の罰則を設けないように求める方針を固めた。
仙台市で開かれたCOPの全国説明会で、同省の南川秀樹次官が「目標を守ることは必要だが、少しでも超えると重い罰が加わるのがいいかは検討が必要だ」と述べた。
京都議定書では、各国が約束期間(08〜12年)内に削減目標を達成できなかった場合、超過した排出量の1.3倍を次の約束期間の削減義務に上乗せする罰則規定がある。
この規定は、各国が確実にガスを削減する動機付けになり、各国間の公平性を担保する役割も果たしていた。
参照
読売新聞 2011年2月22日
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20110222-OYT1T01003.htm
■気候変動などで世界のサンゴ礁の75%以上が危機に■
米政府の海洋監視機関や非政府組織(NGO)の環境保護団体は、「危機にさらされるサンゴ礁・改訂版」と題する報告書を公表し、世界的な海水温の上昇、二酸化炭素(CO2)の排出量増加、それに魚の乱獲など現場水域の諸要因によって、世界のサンゴ礁の警戒レベルが危険領域に入ったと警告した。
サンゴ礁は魚のすみかとなり、観光客を引き付け、海の生物多様性を保護している。
しかし、報告書によると、今や世界のサンゴ礁の75%以上が危険にさらされているという。
1998年に公表された前回の報告書「危機にさらされるサンゴ礁」では、約60%のサンゴ礁が人間の活動によって脅かされているとしていた。
改訂版の発表にあたり米海洋大気局(NOAA)のルブチェンコ長官は、「前回報告を出して以降、警戒レベルは懸念される水準から切迫した水準に上がった」と話した。
サンゴ礁に依存した環境下で、食料ないし収入を得ているのは世界で5億人以上。
報告書はサンゴ礁が年間300億ドル(約2兆5000億円)の恩恵をもたらしていると推計している。
報告書によれば、気候変動を加速させるCO2の排出が海水の酸性化の原因にもなっており、海水の酸性化はサンゴ礁の形成を妨げている。
また海面温度の上昇はサンゴの悲惨な白化(サンゴと共生している藻類の放出によりサンゴが白く見える現象)をもたらしているという。
サンゴが危険にさらされる現場水域での要因には、魚の乱獲、爆発物や毒物を利用した破壊的な漁獲手法、農薬の流出による汚染、沿岸地域の乱開発、サンゴ礁水域でいかりや鎖を引きずる船舶、環境を無視した観光などが挙げられる。
報告書はこれらの脅威が緩和しなければ、2030年までに90%以上、50年までにすべてのサンゴ礁が危険にさらされると警告。
サンゴ礁が劣化したり喪失された場合に経済的に被害を受けやすい国として27ヵ国を挙げ、中でもコモロ、フィジー、グレナダ、ハイチ、インドネシア、キリバス、フィリピン、タンザニア、バヌアツの9ヵ国が最も脆弱だと述べた。
参照
ロイター通信 2011年2月24日
http://jp.reuters.com/article/jpnewEnv/idJPjiji2011022400400
米政府の海洋監視機関や非政府組織(NGO)の環境保護団体は、「危機にさらされるサンゴ礁・改訂版」と題する報告書を公表し、世界的な海水温の上昇、二酸化炭素(CO2)の排出量増加、それに魚の乱獲など現場水域の諸要因によって、世界のサンゴ礁の警戒レベルが危険領域に入ったと警告した。
サンゴ礁は魚のすみかとなり、観光客を引き付け、海の生物多様性を保護している。
しかし、報告書によると、今や世界のサンゴ礁の75%以上が危険にさらされているという。
1998年に公表された前回の報告書「危機にさらされるサンゴ礁」では、約60%のサンゴ礁が人間の活動によって脅かされているとしていた。
改訂版の発表にあたり米海洋大気局(NOAA)のルブチェンコ長官は、「前回報告を出して以降、警戒レベルは懸念される水準から切迫した水準に上がった」と話した。
サンゴ礁に依存した環境下で、食料ないし収入を得ているのは世界で5億人以上。
報告書はサンゴ礁が年間300億ドル(約2兆5000億円)の恩恵をもたらしていると推計している。
報告書によれば、気候変動を加速させるCO2の排出が海水の酸性化の原因にもなっており、海水の酸性化はサンゴ礁の形成を妨げている。
また海面温度の上昇はサンゴの悲惨な白化(サンゴと共生している藻類の放出によりサンゴが白く見える現象)をもたらしているという。
サンゴが危険にさらされる現場水域での要因には、魚の乱獲、爆発物や毒物を利用した破壊的な漁獲手法、農薬の流出による汚染、沿岸地域の乱開発、サンゴ礁水域でいかりや鎖を引きずる船舶、環境を無視した観光などが挙げられる。
報告書はこれらの脅威が緩和しなければ、2030年までに90%以上、50年までにすべてのサンゴ礁が危険にさらされると警告。
サンゴ礁が劣化したり喪失された場合に経済的に被害を受けやすい国として27ヵ国を挙げ、中でもコモロ、フィジー、グレナダ、ハイチ、インドネシア、キリバス、フィリピン、タンザニア、バヌアツの9ヵ国が最も脆弱だと述べた。
参照
ロイター通信 2011年2月24日
http://jp.reuters.com/article/jpnewEnv/idJPjiji2011022400400
■温暖化対策のもう1つのカギ「ブラックカーボン」■
バイオマス(生物資源)燃料の燃焼で排出されるススの粒子や乗り物の排気ガスなどを削減すると、気候変動の進行を鈍化させ、健康面でも多くの恩恵をもたらすという報告書を、国連(UN)が発表した。
これによると、2030年までにこれらの汚染源を除去できれば、今世紀半ばまでに1度と推定されている気温の上昇幅のうち0.5度分を圧縮できるという。
また、主要な呼吸器疾患の原因となっているススの粒子がなくなれば、ほぼ即座に健康面に良い影響がでるという。
報告書は、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の専門家らが執筆。
1992年の環境開発会議(地球サミット、リオサミット)から来年で20年になるのを記念して、ケニアの首都ナイロビで開かれていた。
世界の環境ガバナンスについて協議する会合に集まった世界各国の環境担当相に提出された。
全32ページのこの報告書は、主要な2つの汚染源に触れている。
1つは、木材やバイオマスを燃焼することにより発生するススのような粒子「ブラックカーボン」。
もう1つは、乗り物などの排気ガスと太陽光との化学反応で発生する「地上オゾン」だ。
滞留するブラックカーボンは太陽光を吸収して熱を蓄え、モンスーンなどの気象パターンを変えてしまう可能性もある。
報告書は、化石燃料燃焼による二酸化炭素の排出削減が急務であることには変わりないものの、ブラックカーボンと地上オゾンの削減は温暖化対策として効果的だと提言した。
参照
AFP 2011年2月28日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788037/6887364
バイオマス(生物資源)燃料の燃焼で排出されるススの粒子や乗り物の排気ガスなどを削減すると、気候変動の進行を鈍化させ、健康面でも多くの恩恵をもたらすという報告書を、国連(UN)が発表した。
これによると、2030年までにこれらの汚染源を除去できれば、今世紀半ばまでに1度と推定されている気温の上昇幅のうち0.5度分を圧縮できるという。
また、主要な呼吸器疾患の原因となっているススの粒子がなくなれば、ほぼ即座に健康面に良い影響がでるという。
報告書は、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の専門家らが執筆。
1992年の環境開発会議(地球サミット、リオサミット)から来年で20年になるのを記念して、ケニアの首都ナイロビで開かれていた。
世界の環境ガバナンスについて協議する会合に集まった世界各国の環境担当相に提出された。
全32ページのこの報告書は、主要な2つの汚染源に触れている。
1つは、木材やバイオマスを燃焼することにより発生するススのような粒子「ブラックカーボン」。
もう1つは、乗り物などの排気ガスと太陽光との化学反応で発生する「地上オゾン」だ。
滞留するブラックカーボンは太陽光を吸収して熱を蓄え、モンスーンなどの気象パターンを変えてしまう可能性もある。
報告書は、化石燃料燃焼による二酸化炭素の排出削減が急務であることには変わりないものの、ブラックカーボンと地上オゾンの削減は温暖化対策として効果的だと提言した。
参照
AFP 2011年2月28日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788037/6887364
■国民参加型の気候変動調査 使うのはシャボン玉■
英気象庁は、国民参加型の気候変動測定キャンペーンを開始した。
使うのはシャボン玉と鏡。
空を見上げるだけでもよい。
同庁が国民に呼びかけている方法はいずれも簡単だ。
シャボン玉を飛ばして風速を測る、鏡の助けを借りて雲が流れる方向を確認する、など。
飛行機雲を観測して、その時の気温、湿度を記録したり、温度計無しで感じる体感温度を記録するタスクもある。
飛行機から排出された水分が冷気と混ざって結晶化するのが飛行機雲だ。
これは地表熱の放散を妨げ、地球温暖化の一因にもなる。
コンピューターは気温と湿度を基に飛行機雲の発生場所を予測できるが、実際に確認する方法は空を見上げること以外にない。
同庁の気象学者は、「これらの指標は、当方の標準的な観測網を駆使しただけでは分析も測定も極めて困難。そのため、今回の試みには、既存の観測データを補完する新たなデータを集めて(気候変動の手掛かりを)もう少し得ようという狙いがある」と説明した。
参照
AFP 2011年3月3日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788578/6906240
英気象庁は、国民参加型の気候変動測定キャンペーンを開始した。
使うのはシャボン玉と鏡。
空を見上げるだけでもよい。
同庁が国民に呼びかけている方法はいずれも簡単だ。
シャボン玉を飛ばして風速を測る、鏡の助けを借りて雲が流れる方向を確認する、など。
飛行機雲を観測して、その時の気温、湿度を記録したり、温度計無しで感じる体感温度を記録するタスクもある。
飛行機から排出された水分が冷気と混ざって結晶化するのが飛行機雲だ。
これは地表熱の放散を妨げ、地球温暖化の一因にもなる。
コンピューターは気温と湿度を基に飛行機雲の発生場所を予測できるが、実際に確認する方法は空を見上げること以外にない。
同庁の気象学者は、「これらの指標は、当方の標準的な観測網を駆使しただけでは分析も測定も極めて困難。そのため、今回の試みには、既存の観測データを補完する新たなデータを集めて(気候変動の手掛かりを)もう少し得ようという狙いがある」と説明した。
参照
AFP 2011年3月3日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788578/6906240
■干ばつ被害の小麦生産地帯に恵みの雨■
長引く干ばつで小麦生産への被害が懸念されていた中国北部で、恵みとなる降雨と降雪が確認された。
中国農業省は、これらの地域で広域にわたって降雨および降雪があり、同地域における干ばつは大幅に緩和されたと発表した。
農業省によると、2011年2月末から40ミリに達する降雨や降雪があり、小麦栽培への影響が懸念される面積は1か月前の770万ヘクタールから250万ヘクタールまで大幅に減少した。
中国北部では、冬季が小麦栽培の時期にあたるが、1か月以上におよぶ干ばつで小麦生産に被害が出れば、世界最大の小麦生産国かつ消費国である中国が、国際市場で大量の小麦を買い付けることが予想され、小麦価格高騰の恐れが出ていた。
干ばつ対策として、中国政府は130億元(約1600億円)をつぎ込んで、被災地域に緊急用井戸、灌漑施設などを建設すると発表している。
しかし、農業省は、長引いた干ばつの後で豊作を確保するためには、さらに数週間の降雨が必要だと慎重な姿勢をみせている。
参照
AFP 2011年3月3日
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/disaster/2788443/6888415
長引く干ばつで小麦生産への被害が懸念されていた中国北部で、恵みとなる降雨と降雪が確認された。
中国農業省は、これらの地域で広域にわたって降雨および降雪があり、同地域における干ばつは大幅に緩和されたと発表した。
農業省によると、2011年2月末から40ミリに達する降雨や降雪があり、小麦栽培への影響が懸念される面積は1か月前の770万ヘクタールから250万ヘクタールまで大幅に減少した。
中国北部では、冬季が小麦栽培の時期にあたるが、1か月以上におよぶ干ばつで小麦生産に被害が出れば、世界最大の小麦生産国かつ消費国である中国が、国際市場で大量の小麦を買い付けることが予想され、小麦価格高騰の恐れが出ていた。
干ばつ対策として、中国政府は130億元(約1600億円)をつぎ込んで、被災地域に緊急用井戸、灌漑施設などを建設すると発表している。
しかし、農業省は、長引いた干ばつの後で豊作を確保するためには、さらに数週間の降雨が必要だと慎重な姿勢をみせている。
参照
AFP 2011年3月3日
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/disaster/2788443/6888415
■乱立する条約 環境保護活動の妨げに■
環境への関心の高まりを受け、過去20年間にできた環境関連の条約は500を超えるとみられている。
しかし、なかには無駄で、かえって環境保護の妨げになっている条約も多いと、各国の環境相らが参加してケニアのナイロビで開かれた国連(UN)の会合で多くの専門家が指摘した。
世界の環境ガバナンスについて協議されたこの会議では、世界的な環境保護体制の見直しが必要との認識で一致した。
条約が乱立する現状についてある外交官は「航空機にパイロットがいない状態」と表現した。
国連環境計画(UNEP)の規模や影響力は、世界貿易機関(WTO)や世界保健機関(WHO)に比べてかなり見劣りする。
UNEPの2010年度の予算はわずか8300万ドル(約68億円)にすぎず、続々と登場する環境関連の条約への影響力はほとんどない。
■乱立する条約 「条約間格差」も
環境関連の条約は500以上存在するとみられるが、UNEPのアヒム・シュタイナー事務局長は、正確な数は誰も把握していないのではないかと言う。
その多くはブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議(地球サミット)」が開催された1992年に以降に結ばれたものだ。
条約ごとに事務局が設立されているが、事務局間の連携はほとんどない。
現在では無数の法体系が分厚い網のように複雑にはりめぐらされ、専門家でさえ理解するのが難しい状態になっているという。
1992年から2007年の間に18の国際条約のもとに540回の会議が行われ、5000以上の決定が下された。
こうした状況に開発途上国からは、対応しきれないとの声が上がり始めている。
ナイロビでの環境会合に参加した専門家の1人は、「化学製品に関する規制1つをとっても、主な条約だけで3つある。この3条約を統合するのではなく、単に共通の枠組みの中に位置づけるという合意に達するだけで5年もかかった」とため息をついた。
ばらばらに存在する各条約は決して対等ではない。
たとえば1992年に採択された「国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」には、1000億ドル(約8兆2000億円)の資金がたやすく集まった。しかし、その2年後に採択された「砂漠化対処条約(UNCCD)」は資金集めに苦戦を強いられた。
ある外交関係者は、「貧しい国の条約だから誰も気にかけない」と言う。
■「世界環境機関」設立を推す独仏 米中露印などは消極的
ナイロビでの環境会合では総論で一致したが、ばらばらな制度を調和させるための協議は何年も前から行き詰まったままだ。
欧州連合(EU)を後ろ盾に持つフランスとドイツは、改めて「世界環境機関」の設立に向けてロビー活動を行っている。
フランスのナタリー・コシュスコモリゼ エコロジー担当相は、「UNEPを強化して、地球規模で機能する機関にしたい」と語る。
一方、米国や中国、ロシア、インドなどは、政治的・経済的な思惑から現在のところこの問題について積極的な発言はしていない。
ナイロビでの会合は、2012年6月にリオデジャネイロで開催予定の地球サミットでの合意も視野に入れ、各国がこの問題を持ち帰って検討することを呼びかけて閉幕した。
参照
AFP 2011年3月2日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788431/6865630
環境への関心の高まりを受け、過去20年間にできた環境関連の条約は500を超えるとみられている。
しかし、なかには無駄で、かえって環境保護の妨げになっている条約も多いと、各国の環境相らが参加してケニアのナイロビで開かれた国連(UN)の会合で多くの専門家が指摘した。
世界の環境ガバナンスについて協議されたこの会議では、世界的な環境保護体制の見直しが必要との認識で一致した。
条約が乱立する現状についてある外交官は「航空機にパイロットがいない状態」と表現した。
国連環境計画(UNEP)の規模や影響力は、世界貿易機関(WTO)や世界保健機関(WHO)に比べてかなり見劣りする。
UNEPの2010年度の予算はわずか8300万ドル(約68億円)にすぎず、続々と登場する環境関連の条約への影響力はほとんどない。
■乱立する条約 「条約間格差」も
環境関連の条約は500以上存在するとみられるが、UNEPのアヒム・シュタイナー事務局長は、正確な数は誰も把握していないのではないかと言う。
その多くはブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議(地球サミット)」が開催された1992年に以降に結ばれたものだ。
条約ごとに事務局が設立されているが、事務局間の連携はほとんどない。
現在では無数の法体系が分厚い網のように複雑にはりめぐらされ、専門家でさえ理解するのが難しい状態になっているという。
1992年から2007年の間に18の国際条約のもとに540回の会議が行われ、5000以上の決定が下された。
こうした状況に開発途上国からは、対応しきれないとの声が上がり始めている。
ナイロビでの環境会合に参加した専門家の1人は、「化学製品に関する規制1つをとっても、主な条約だけで3つある。この3条約を統合するのではなく、単に共通の枠組みの中に位置づけるという合意に達するだけで5年もかかった」とため息をついた。
ばらばらに存在する各条約は決して対等ではない。
たとえば1992年に採択された「国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」には、1000億ドル(約8兆2000億円)の資金がたやすく集まった。しかし、その2年後に採択された「砂漠化対処条約(UNCCD)」は資金集めに苦戦を強いられた。
ある外交関係者は、「貧しい国の条約だから誰も気にかけない」と言う。
■「世界環境機関」設立を推す独仏 米中露印などは消極的
ナイロビでの環境会合では総論で一致したが、ばらばらな制度を調和させるための協議は何年も前から行き詰まったままだ。
欧州連合(EU)を後ろ盾に持つフランスとドイツは、改めて「世界環境機関」の設立に向けてロビー活動を行っている。
フランスのナタリー・コシュスコモリゼ エコロジー担当相は、「UNEPを強化して、地球規模で機能する機関にしたい」と語る。
一方、米国や中国、ロシア、インドなどは、政治的・経済的な思惑から現在のところこの問題について積極的な発言はしていない。
ナイロビでの会合は、2012年6月にリオデジャネイロで開催予定の地球サミットでの合意も視野に入れ、各国がこの問題を持ち帰って検討することを呼びかけて閉幕した。
参照
AFP 2011年3月2日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788431/6865630
■大気汚染で寿命が2年縮む■
欧州の主要都市で大気汚染に歯止めをかければ、年間1万9000人の命を救うことができ、地元住民の平均寿命も約2年伸びる、との調査結果が発表された。
医療費も315億ユーロ(約3兆6000億円)削減され、職場を長期欠勤する人も減るという。
欧州連合(EU)の資金援助で行われた約3年間にわたる調査計画「Aphekom」では、計約3900万人が居住する域内12か国25都市を対象に、大気汚染を引き起こす微小粒子状物質の量を調べた。
世界保健機関(WHO)が推奨する量は1立方メートル当たり10マイクログラム(μg)以下だが、この基準をクリアした年はスウェーデン・ストックホルムだけだった。
最も多かったのはルーマニア・ブカレストの38.2μgで、ハンガリー・ブダペスト(33.7μg)、スペイン・バルセロナ(27μg)と続いた。
その他の主要都市では、イタリア・ローマが21.4μg、パリは16.4μg、ロンドンは13.1μgだった。
排気ガスなどに含まれる微小粒子状物質は、肺の奥に入ると呼吸器疾患や心疾患を引き起こす恐れがある。
10都市を対象とした「Aphekom」の別の調査では、小児喘息の15〜30%が、交通量の多い道路の近く住んでいることに起因している可能性があるとの試算結果が出ている。
参照
AFP 2011年3月4日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788705/6910784
欧州の主要都市で大気汚染に歯止めをかければ、年間1万9000人の命を救うことができ、地元住民の平均寿命も約2年伸びる、との調査結果が発表された。
医療費も315億ユーロ(約3兆6000億円)削減され、職場を長期欠勤する人も減るという。
欧州連合(EU)の資金援助で行われた約3年間にわたる調査計画「Aphekom」では、計約3900万人が居住する域内12か国25都市を対象に、大気汚染を引き起こす微小粒子状物質の量を調べた。
世界保健機関(WHO)が推奨する量は1立方メートル当たり10マイクログラム(μg)以下だが、この基準をクリアした年はスウェーデン・ストックホルムだけだった。
最も多かったのはルーマニア・ブカレストの38.2μgで、ハンガリー・ブダペスト(33.7μg)、スペイン・バルセロナ(27μg)と続いた。
その他の主要都市では、イタリア・ローマが21.4μg、パリは16.4μg、ロンドンは13.1μgだった。
排気ガスなどに含まれる微小粒子状物質は、肺の奥に入ると呼吸器疾患や心疾患を引き起こす恐れがある。
10都市を対象とした「Aphekom」の別の調査では、小児喘息の15〜30%が、交通量の多い道路の近く住んでいることに起因している可能性があるとの試算結果が出ている。
参照
AFP 2011年3月4日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2788705/6910784
■ CO2の排出量 ■
日本のCO2の排出量は13億6000万?とも言われいる様ですが。
都市ごみ焼却量約5350万トン、その内プラ関係約1000万トン、含水率の高い生ごみ類の焼却の助燃に多量の石油と灰の溶融には多くの電力も使われているが、資料には出てこない。
又下水道等の汚泥は約1億8000万トンこれも、脱水焼却されている。これも助燃の石油は膨大であろう。しかも焼却により、発生する1酸化2窒素の温暖化ガスの効果はCO2の310倍の効果があるといわれている。どの程度出ているものか。知りたい所である。
ちなみにメタンガスの温暖化ガスのこうかはCO2の21倍といわれている。少し判れば、基本の排出量の数字まで疑問に思える処である。
公にすると問題も多いのでしょう。
日本のCO2の排出量は13億6000万?とも言われいる様ですが。
都市ごみ焼却量約5350万トン、その内プラ関係約1000万トン、含水率の高い生ごみ類の焼却の助燃に多量の石油と灰の溶融には多くの電力も使われているが、資料には出てこない。
又下水道等の汚泥は約1億8000万トンこれも、脱水焼却されている。これも助燃の石油は膨大であろう。しかも焼却により、発生する1酸化2窒素の温暖化ガスの効果はCO2の310倍の効果があるといわれている。どの程度出ているものか。知りたい所である。
ちなみにメタンガスの温暖化ガスのこうかはCO2の21倍といわれている。少し判れば、基本の排出量の数字まで疑問に思える処である。
公にすると問題も多いのでしょう。
■北極のオゾン層 過去最大の減少■
世界気象機関(WMO)は、北極のオゾン層の破壊規模が過去最大を記録したと発表した。
非常に寒い天候と大気中の有害物質が原因だという。
北極のオゾン層は、冬の始まりから3月末までの間に40%減少した。
冬の間の減少幅としては、これまでで最も大きかったときでもおよそ30%だったという。
「地球上の生物を有害な量の紫外線から守るオゾン層はこの春、過去例を見ないレベルにまで減少した。原因はオゾン層を破壊する物質が大気中にあることと、今冬の成層圏が非常に寒かったことにある」と、WMOは声明を発表した。
オゾン層の少ない領域は3月末から移動し、グリーンランドやスカンジナビア半島上空に到達する。
今後数週間、これらの地域では通常よりも高いレベルの紫外線放射に注意する必要がある。
WMOは、「今後数週間で正午の太陽高度が上がるにつれて、オゾン層の減少の影響を受ける地域では、通常よりも高い紫外線放射を受けることになる。それら地域では国が発表する紫外線予報に注意する必要がある」と、注意を促した。
オゾン層を破壊するのは、冷蔵庫や一部プラスチック製品、一部エアゾールスプレーなどに含まれる化学物質のフロンガス。
大半のフロンガスは1987年のモントリオール議定書で、段階的な廃止が求められているものの、大気中に長期間とどまり続ける。
議定書の成果として、極地以外の地域のオゾン層は、2030〜2040年には1980年代以前のレベルにまで戻るとみられている。
また、南極のオゾン層は2045〜2060年ごろ、北極のオゾン層はそれより10〜20年早く回復するとみられている。
参照
AFP 2011年4月6日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2794329/7050597
世界気象機関(WMO)は、北極のオゾン層の破壊規模が過去最大を記録したと発表した。
非常に寒い天候と大気中の有害物質が原因だという。
北極のオゾン層は、冬の始まりから3月末までの間に40%減少した。
冬の間の減少幅としては、これまでで最も大きかったときでもおよそ30%だったという。
「地球上の生物を有害な量の紫外線から守るオゾン層はこの春、過去例を見ないレベルにまで減少した。原因はオゾン層を破壊する物質が大気中にあることと、今冬の成層圏が非常に寒かったことにある」と、WMOは声明を発表した。
オゾン層の少ない領域は3月末から移動し、グリーンランドやスカンジナビア半島上空に到達する。
今後数週間、これらの地域では通常よりも高いレベルの紫外線放射に注意する必要がある。
WMOは、「今後数週間で正午の太陽高度が上がるにつれて、オゾン層の減少の影響を受ける地域では、通常よりも高い紫外線放射を受けることになる。それら地域では国が発表する紫外線予報に注意する必要がある」と、注意を促した。
オゾン層を破壊するのは、冷蔵庫や一部プラスチック製品、一部エアゾールスプレーなどに含まれる化学物質のフロンガス。
大半のフロンガスは1987年のモントリオール議定書で、段階的な廃止が求められているものの、大気中に長期間とどまり続ける。
議定書の成果として、極地以外の地域のオゾン層は、2030〜2040年には1980年代以前のレベルにまで戻るとみられている。
また、南極のオゾン層は2045〜2060年ごろ、北極のオゾン層はそれより10〜20年早く回復するとみられている。
参照
AFP 2011年4月6日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2794329/7050597
■南半球の豪雨はオゾンホールが原因■
米コロンビア大学の研究チームは、過去50年間のオゾン層と気象データを分析した結果、南極上空のオゾン層が気候変動の重要な要因となって、南半球で降雨を増加させていたとする論文を米科学誌「サイエンス」に発表した。
極域でのオゾン層破壊と赤道付近にまでいたる地域の気候変動を関連付けた研究は初めて。
研究チームは、世界各国の気候変動政策において、北極での氷床溶解や温室効果ガスの問題と同様に、オゾン層の問題も考慮する必要があると訴えている。
オゾンホールの存在が明らかになったのは1980年代。
フロンガスの多用が原因だったことから、1989年にはクロロフルオロカーボン(CFC)など、オゾン層を破壊するおそれのある物質を規制するモントリオール議定書が発効。
196か国が締約した。
オゾンホールは2050年ごろまでに消失するとみられているが、コロンビア大の研究者たちは、オゾンホールの問題が解決したわけではないと警告する。
コロンビア大の研究チームは、カナダの中層大気モデルと米国立大気研究センターによる地域大気モデルを参照した。
4つの実験で海氷、地表温度、降水量、オゾンホールに関するデータを比較分析した結果、オーストラリア東部、インド洋南西部、南太平洋収束帯で夏季にみられる豪雨には、オゾンホールが関連していることが分かった。
研究チームの1人、ロレンゾ・ポルバーニ氏は、「我々の研究はオゾンホールの影響が広範囲に及ぶことを示した。気候システムにおいて、オゾンホールは大きな役割を果たしている」と話す。
今後も研究チームは、各地で大規模洪水や地滑りなどの被害をもたらしている「異常な降水現象」について調べる計画だという。
参照
AFP 2011年4月22日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2796609/7119382
米コロンビア大学の研究チームは、過去50年間のオゾン層と気象データを分析した結果、南極上空のオゾン層が気候変動の重要な要因となって、南半球で降雨を増加させていたとする論文を米科学誌「サイエンス」に発表した。
極域でのオゾン層破壊と赤道付近にまでいたる地域の気候変動を関連付けた研究は初めて。
研究チームは、世界各国の気候変動政策において、北極での氷床溶解や温室効果ガスの問題と同様に、オゾン層の問題も考慮する必要があると訴えている。
オゾンホールの存在が明らかになったのは1980年代。
フロンガスの多用が原因だったことから、1989年にはクロロフルオロカーボン(CFC)など、オゾン層を破壊するおそれのある物質を規制するモントリオール議定書が発効。
196か国が締約した。
オゾンホールは2050年ごろまでに消失するとみられているが、コロンビア大の研究者たちは、オゾンホールの問題が解決したわけではないと警告する。
コロンビア大の研究チームは、カナダの中層大気モデルと米国立大気研究センターによる地域大気モデルを参照した。
4つの実験で海氷、地表温度、降水量、オゾンホールに関するデータを比較分析した結果、オーストラリア東部、インド洋南西部、南太平洋収束帯で夏季にみられる豪雨には、オゾンホールが関連していることが分かった。
研究チームの1人、ロレンゾ・ポルバーニ氏は、「我々の研究はオゾンホールの影響が広範囲に及ぶことを示した。気候システムにおいて、オゾンホールは大きな役割を果たしている」と話す。
今後も研究チームは、各地で大規模洪水や地滑りなどの被害をもたらしている「異常な降水現象」について調べる計画だという。
参照
AFP 2011年4月22日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2796609/7119382
■1世紀以内に海面が最大1メートル上昇■
地球温暖化により1世紀以内に海面が最大1メートル上昇し、現在では「100年に1回」規模の沿岸部の洪水がもっと頻繁に起こるようになると指摘する研究結果を、オーストラリア政府の気候変動委員会が発表した。
報告をまとめたウィル・ステフェン氏は、「世界の海面は2100年には、1990年のレベルから0.5〜1メートル上昇するだろう」と述べた。
「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」では、2007年に海面上昇は0.8メートル以下と予測しているが、同発表ではもっと高い値になる場合もあるとされていたため、今回の研究結果と矛盾することはないと同氏は述べている。
それから5年が経つ今回の報告は最新の気候科学に基づいた上、オーストラリア連邦科学産業研究機構および気象庁の専門家らの査読も受けている。
ステフェン氏は「巨大な氷床の変化についても、以前よりも明らかになっている。
特にグリーンランドの氷塊の容積が減っていること、その減少のペースに拍車がかかっていることもだ。したがって(海面上昇の予測の)上限を引き上げる必要がある」と説明した。
報告書によると、0.5メートルの海面上昇でもその影響は驚異的に大きい。
海面が0.5メートル上昇した場合、オーストラリアを例にとればシドニーやメルボルンといった沿岸部の大都市圏で浸水被害が発生するような事態が増えるおそれがある。
「100年に1度」規模の大災害が毎年起こるような可能性もあり、「最悪でも2020年までに、温暖化ガスの排出量のグラフを増加から減少に転じさせることが不可欠」だと同氏は警告した。
またステフェン氏は、オーストラリアで近年、森林火災や干ばつ、サイクロンの発生などが増加していることについても、気温上昇の影響が考えられると指摘した。
オーストラリアで猛暑を記録した日は過去50年間で2倍以上増えており、熱波や森林火災の起きやすい環境になっている。
参照
AFP 2011年5月26日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2802457/7263212
地球温暖化により1世紀以内に海面が最大1メートル上昇し、現在では「100年に1回」規模の沿岸部の洪水がもっと頻繁に起こるようになると指摘する研究結果を、オーストラリア政府の気候変動委員会が発表した。
報告をまとめたウィル・ステフェン氏は、「世界の海面は2100年には、1990年のレベルから0.5〜1メートル上昇するだろう」と述べた。
「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」では、2007年に海面上昇は0.8メートル以下と予測しているが、同発表ではもっと高い値になる場合もあるとされていたため、今回の研究結果と矛盾することはないと同氏は述べている。
それから5年が経つ今回の報告は最新の気候科学に基づいた上、オーストラリア連邦科学産業研究機構および気象庁の専門家らの査読も受けている。
ステフェン氏は「巨大な氷床の変化についても、以前よりも明らかになっている。
特にグリーンランドの氷塊の容積が減っていること、その減少のペースに拍車がかかっていることもだ。したがって(海面上昇の予測の)上限を引き上げる必要がある」と説明した。
報告書によると、0.5メートルの海面上昇でもその影響は驚異的に大きい。
海面が0.5メートル上昇した場合、オーストラリアを例にとればシドニーやメルボルンといった沿岸部の大都市圏で浸水被害が発生するような事態が増えるおそれがある。
「100年に1度」規模の大災害が毎年起こるような可能性もあり、「最悪でも2020年までに、温暖化ガスの排出量のグラフを増加から減少に転じさせることが不可欠」だと同氏は警告した。
またステフェン氏は、オーストラリアで近年、森林火災や干ばつ、サイクロンの発生などが増加していることについても、気温上昇の影響が考えられると指摘した。
オーストラリアで猛暑を記録した日は過去50年間で2倍以上増えており、熱波や森林火災の起きやすい環境になっている。
参照
AFP 2011年5月26日
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2802457/7263212
■環境危機時計 「極めて不安」9時1分■
人類が存続していくのに地球環境がどの程度危機的な状況にあるかを示す指標「環境危機時計」の2011年の時刻は9時1分を指した。
3年連続で針が戻り、2010年と比べた戻り幅は1992年の調査開始以来最大の18分となった。
旭硝子財団は、省エネや再生可能エネルギー政策、森林保全の取り組みが世界各国で進められつつあることが一因と分析している。
同財団が実施した、各国政府や環境問題に関わる有識者へのアンケート結果を基にした。
2011年は77カ国計1000人(回収率14%)から回答を得た。
地域別では、日本8時46分(マイナス23分)、北米9時35分(マイナス38分)などである。
時刻は、0時1分〜3時が「ほとんど不安がない」、3時1分〜6時が「少し不安」、6時1分〜9時が「かなり不安」、9時1分〜12時が「極めて不安」を示す。
参照
毎日新聞 2011年9月8日
http://mainichi.jp/select/science/archive/news/2011/09/08/20110908ddm041040178000c.html
人類が存続していくのに地球環境がどの程度危機的な状況にあるかを示す指標「環境危機時計」の2011年の時刻は9時1分を指した。
3年連続で針が戻り、2010年と比べた戻り幅は1992年の調査開始以来最大の18分となった。
旭硝子財団は、省エネや再生可能エネルギー政策、森林保全の取り組みが世界各国で進められつつあることが一因と分析している。
同財団が実施した、各国政府や環境問題に関わる有識者へのアンケート結果を基にした。
2011年は77カ国計1000人(回収率14%)から回答を得た。
地域別では、日本8時46分(マイナス23分)、北米9時35分(マイナス38分)などである。
時刻は、0時1分〜3時が「ほとんど不安がない」、3時1分〜6時が「少し不安」、6時1分〜9時が「かなり不安」、9時1分〜12時が「極めて不安」を示す。
参照
毎日新聞 2011年9月8日
http://mainichi.jp/select/science/archive/news/2011/09/08/20110908ddm041040178000c.html
■干ばつ 2012年以降も続く恐れ アメリカ■
アメリカのネブラスカ大学の付属機関、干ばつ軽減センター(NDMC)の気候学者マーク・スボボダ氏は、アメリカの南部を襲っている記録的な干ばつは長期化し、2012年以降も続く可能性があるとの見方を明らかにした。
同氏は、「米干ばつ監視」と呼ばれる州、連邦の気候学者の団体の週報で、南東部、特にジョージア、アラバマ州東部で悪化していると述べた。
先に米大西洋岸をかすめて北上したハリケーン「アイリーン」も干ばつ地帯にはわずかな雨量しかもたらさなかった。
最も被害が大きいのはテキサス州で、2011年は19世紀末に観測が始まって以来最悪の年になると予想されている。
最も厳しい干ばつ状況である「異常」と、それに次ぐ「極度」の二つのレベルに入る地域は、同州の95%となり、全州の94%からさらに拡大した。
同州の当局は干ばつ被害は50億ドルを超えていると見ている。
オクラホマ州も被害が大きく、「干ばつ監視」によると、「異常」「極度」のレベルは85%にまで広がり、カンザス州では3分の1近くがこのレベルだ。
小麦農家は、耕地の水分不足で秋の作付けを危ぶんでいるという。
参照
時事通信社 2011年9月2日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011090200240r
アメリカのネブラスカ大学の付属機関、干ばつ軽減センター(NDMC)の気候学者マーク・スボボダ氏は、アメリカの南部を襲っている記録的な干ばつは長期化し、2012年以降も続く可能性があるとの見方を明らかにした。
同氏は、「米干ばつ監視」と呼ばれる州、連邦の気候学者の団体の週報で、南東部、特にジョージア、アラバマ州東部で悪化していると述べた。
先に米大西洋岸をかすめて北上したハリケーン「アイリーン」も干ばつ地帯にはわずかな雨量しかもたらさなかった。
最も被害が大きいのはテキサス州で、2011年は19世紀末に観測が始まって以来最悪の年になると予想されている。
最も厳しい干ばつ状況である「異常」と、それに次ぐ「極度」の二つのレベルに入る地域は、同州の95%となり、全州の94%からさらに拡大した。
同州の当局は干ばつ被害は50億ドルを超えていると見ている。
オクラホマ州も被害が大きく、「干ばつ監視」によると、「異常」「極度」のレベルは85%にまで広がり、カンザス州では3分の1近くがこのレベルだ。
小麦農家は、耕地の水分不足で秋の作付けを危ぶんでいるという。
参照
時事通信社 2011年9月2日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011090200240r
■CO2削減はアメリカ経済に打撃 テキサス州知事■
アメリカ大統領選に名乗りを上げている共和党のペリー・テキサス州知事は、ニューハンプシャー州アトキンソンでの集会で、気候変動が人間の行為によって引き起こされたとする見方に改めて疑問を呈した。
同氏は、二酸化炭素(CO2)排出量の削減は米経済を「荒廃」させる恐れがあるとしている。
ペリー氏は、「科学は地球温暖化が人間の行為で起きたとは結論付けていない、とする見解を私は引き続き支持する」と言明した。
テキサスは、石油と天然ガスの資源に恵まれた州だが、現在は歴史的な干ばつで山火事・野火の頻発と異常高温に悩まされている。
共和党の候補者指名争いに参加している人たちの中で、気候変動の主たる原因は人間の行為だと考えているのはハンツマン前ユタ州知事だけだ。
全米科学アカデミー(NAS)が2010年に1372人の気候科学者を対象にした調査では、97%以上が変動の主因は人間にあると答えた。
しかし、同年にピュー研究センターが行った調査ではこうした考えを支持する米国民は3分の1程度にすぎなかった。
2006年の調査では50%が支持していた。
参照
時事通信社 2011年10月3日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011100300156r
アメリカ大統領選に名乗りを上げている共和党のペリー・テキサス州知事は、ニューハンプシャー州アトキンソンでの集会で、気候変動が人間の行為によって引き起こされたとする見方に改めて疑問を呈した。
同氏は、二酸化炭素(CO2)排出量の削減は米経済を「荒廃」させる恐れがあるとしている。
ペリー氏は、「科学は地球温暖化が人間の行為で起きたとは結論付けていない、とする見解を私は引き続き支持する」と言明した。
テキサスは、石油と天然ガスの資源に恵まれた州だが、現在は歴史的な干ばつで山火事・野火の頻発と異常高温に悩まされている。
共和党の候補者指名争いに参加している人たちの中で、気候変動の主たる原因は人間の行為だと考えているのはハンツマン前ユタ州知事だけだ。
全米科学アカデミー(NAS)が2010年に1372人の気候科学者を対象にした調査では、97%以上が変動の主因は人間にあると答えた。
しかし、同年にピュー研究センターが行った調査ではこうした考えを支持する米国民は3分の1程度にすぎなかった。
2006年の調査では50%が支持していた。
参照
時事通信社 2011年10月3日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011100300156r
■資源減少と気候変動 人類の健康の最大の脅威に■
ロンドンで開かれた世界の気候と健康に関連する会合に参加した専門家らは、食料、水、森林といった地球の天然資源が驚くほどのスピードで減少しており、その結果、飢餓、社会的争乱、それに種の絶滅といった事態を引き起こしていると警告した。
専門家らは、食料の収量の変化によって空腹状態が広がると栄養失調につながり、水不足は衛生状態の悪化を招くと述べた。
また、環境汚染によって免疫システムが弱くなるほか、水や土地をめぐる争いを理由とした居住地移転や社会的無秩序が感染症を拡散させるとも指摘した。
オーストラリア国立大学の教授(公衆衛生学)は、2050年までにはサハラ砂漠以南のアフリカだけで死者数がさらに7000万人増える恐れがあると語った。
気候変動によって蚊の活動範囲が広がってマラリアなどの病気の感染率が上がり、2025年から2050年にかけてジンバブエなどの国が影響を受けるとみられている。
さらに、地球温暖化によって洪水が増え、病気を運ぶ水がこれまで到達しなかった場所にまでやって来るため、中国では新たに2100万人が住血吸虫症にかかる危険にさらされる恐れがあるという。
教授は、「健康被害は、巻き添えを食うといった単に付随的なものではない。むしろ中心的なもので、気候変動によるその他全ての影響がもたらすデニュマン(最終的な結末)を形作るだろう」と警告した。
参照
時事通信社 2011年10月18日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011101800290r
ロンドンで開かれた世界の気候と健康に関連する会合に参加した専門家らは、食料、水、森林といった地球の天然資源が驚くほどのスピードで減少しており、その結果、飢餓、社会的争乱、それに種の絶滅といった事態を引き起こしていると警告した。
専門家らは、食料の収量の変化によって空腹状態が広がると栄養失調につながり、水不足は衛生状態の悪化を招くと述べた。
また、環境汚染によって免疫システムが弱くなるほか、水や土地をめぐる争いを理由とした居住地移転や社会的無秩序が感染症を拡散させるとも指摘した。
オーストラリア国立大学の教授(公衆衛生学)は、2050年までにはサハラ砂漠以南のアフリカだけで死者数がさらに7000万人増える恐れがあると語った。
気候変動によって蚊の活動範囲が広がってマラリアなどの病気の感染率が上がり、2025年から2050年にかけてジンバブエなどの国が影響を受けるとみられている。
さらに、地球温暖化によって洪水が増え、病気を運ぶ水がこれまで到達しなかった場所にまでやって来るため、中国では新たに2100万人が住血吸虫症にかかる危険にさらされる恐れがあるという。
教授は、「健康被害は、巻き添えを食うといった単に付随的なものではない。むしろ中心的なもので、気候変動によるその他全ての影響がもたらすデニュマン(最終的な結末)を形作るだろう」と警告した。
参照
時事通信社 2011年10月18日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011101800290r
■小島しょ国連合 気候変動で条約締結求める■
気候変動から最も影響を受けやすいとされる小さな島国の連合組織「小島しょ国連合(AOSIS)」は、先進諸国が新たな気候変動に関する条約の締結を、京都議定書の期限が切れる2012年から何年も遅らそうとしていると痛烈に批判した。
42の加盟国からなるAOSISは、日本やロシアといった国々が新たな国際取り決めの締結を2018年または2020年に延期させようと「無謀で無責任な」行動に出ていると指摘した。
AOSISの議長国グレナダの環境相は、「世界各国政府が目標を厳しく設定した取り決めで合意できなければ、カリブ海、太平洋、アフリカなどの世界中の小島しょ国は気候変動の結果、厳しい干ばつ、海面上昇、より強力なハリケーンに一層さらされることになるだろう」と指摘した。
AOSISは、先進国と開発途上国の多くもまた、2012年末までに合意したいと考えていると指摘し、ダーバン(南アフリカ)での国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)においては各国がこの期限の順守で同意するよう求めた。
COP17では、190を超える国の代表が、気候変動交渉を再開する。
しかし、温室効果ガス排出量削減を求める拘束力のある条約合意の可能性は低く、それには数年かかるとみられている。
先進国と途上国の溝が深いからだ。
途上国は京都議定書の延長を求めているが、ロシア、日本、カナダなどは、同議定書がそもそも一部主要国のみに温室効果ガスの削減義務を課したものだと指摘、すべての大口ガス排出国が含まれない限り、その延長には応じないとしている。
参照
時事通信社 2011年11月4日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011110400268r
気候変動から最も影響を受けやすいとされる小さな島国の連合組織「小島しょ国連合(AOSIS)」は、先進諸国が新たな気候変動に関する条約の締結を、京都議定書の期限が切れる2012年から何年も遅らそうとしていると痛烈に批判した。
42の加盟国からなるAOSISは、日本やロシアといった国々が新たな国際取り決めの締結を2018年または2020年に延期させようと「無謀で無責任な」行動に出ていると指摘した。
AOSISの議長国グレナダの環境相は、「世界各国政府が目標を厳しく設定した取り決めで合意できなければ、カリブ海、太平洋、アフリカなどの世界中の小島しょ国は気候変動の結果、厳しい干ばつ、海面上昇、より強力なハリケーンに一層さらされることになるだろう」と指摘した。
AOSISは、先進国と開発途上国の多くもまた、2012年末までに合意したいと考えていると指摘し、ダーバン(南アフリカ)での国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)においては各国がこの期限の順守で同意するよう求めた。
COP17では、190を超える国の代表が、気候変動交渉を再開する。
しかし、温室効果ガス排出量削減を求める拘束力のある条約合意の可能性は低く、それには数年かかるとみられている。
先進国と途上国の溝が深いからだ。
途上国は京都議定書の延長を求めているが、ロシア、日本、カナダなどは、同議定書がそもそも一部主要国のみに温室効果ガスの削減義務を課したものだと指摘、すべての大口ガス排出国が含まれない限り、その延長には応じないとしている。
参照
時事通信社 2011年11月4日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011110400268r
■欧州債務危機 気候変動対策費不足も■
イギリスの会計・コンサルティング大手アーンスト・アンド・ヤング(E&Y)は、ユーロ圏の債務危機がさらに悪化すると、世界各国の拠出する気候変動対策資金が当初の予定よりも少なくなり、2015年までに調達ギャップが450億ドルに拡大する恐れがあるとのリポートを発表した。
緊縮財政により、政府が変動対策投資水準を維持することが難しくなるからだという。
E&Yは、現在の緊縮財政水準であっても、主要10カ国(ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、日本、米国、オーストラリア、南アフリカ共和国、韓国)による再生可能燃料、クリーン技術、汚染削減策、各種補助金への拠出額は合計で225億ドル不足しそうだとしている。
国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)で京都議定書の後継となる合意達成の可能性は低い。
また、気候変動に最も脆弱な国々の支援に各国が拠出約束している年間1000億ドルの資金が予定通り集まらない懸念も出てきている。
E&Yは、ユーロ圏の債務危機が深刻化して新たな銀行危機に陥れば、ドイツが最大の資金調達ギャップに直面し、その絶対額は83億ドルに達するだろうと予想。
スペイン、日本、米国は60億ドル以上、英国とフランスは50億ドル以上のギャップになろうと述べた。
また、現在の緊縮策の下では、ギャップは2015年までにスペイン、英国、フランスが最悪になるだろうという。
参照
時事通信社 2011年11月18日
http://www.jiji.com/jc/rt
イギリスの会計・コンサルティング大手アーンスト・アンド・ヤング(E&Y)は、ユーロ圏の債務危機がさらに悪化すると、世界各国の拠出する気候変動対策資金が当初の予定よりも少なくなり、2015年までに調達ギャップが450億ドルに拡大する恐れがあるとのリポートを発表した。
緊縮財政により、政府が変動対策投資水準を維持することが難しくなるからだという。
E&Yは、現在の緊縮財政水準であっても、主要10カ国(ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、日本、米国、オーストラリア、南アフリカ共和国、韓国)による再生可能燃料、クリーン技術、汚染削減策、各種補助金への拠出額は合計で225億ドル不足しそうだとしている。
国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)で京都議定書の後継となる合意達成の可能性は低い。
また、気候変動に最も脆弱な国々の支援に各国が拠出約束している年間1000億ドルの資金が予定通り集まらない懸念も出てきている。
E&Yは、ユーロ圏の債務危機が深刻化して新たな銀行危機に陥れば、ドイツが最大の資金調達ギャップに直面し、その絶対額は83億ドルに達するだろうと予想。
スペイン、日本、米国は60億ドル以上、英国とフランスは50億ドル以上のギャップになろうと述べた。
また、現在の緊縮策の下では、ギャップは2015年までにスペイン、英国、フランスが最悪になるだろうという。
参照
時事通信社 2011年11月18日
http://www.jiji.com/jc/rt
■政治ではなく科学に基づく気候変動交渉を■
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の議長は、気候変動交渉について、異常気象による脅威の増大に焦点を当てる必要があると述べ、各国が政治的な小競り合いから離れる必要があると指摘した。
政治的な小競り合いは、温室効果ガス排出に関するより厳しい条約締結への取り組みを阻害しているという。
世界約200カ国の交渉担当者が南アフリカ共和国のダーバンに集まり、2週間にわたって国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)が開かれる。
会議で全ての主要排出国を拘束する合意に向けて大きく前進すると期待する人々は、非常に少ない。
同議長率いるIPCCは、政策立案者向けにリポートを公表した。
リポートは、熱波の襲来が増えるのはほぼ確実で、より激しい雨、より多くの洪水、より強力なサイクロンや土砂崩れ、より厳しい干ばつが今世紀に地球上の各地を襲う可能性が高いと指摘するものだった。
また、同議長は今回の会議について、「残念ながら、現状は全体的に、これらの現実に関する視点が抜け落ちている」と述べた。
参照
時事通信社 2011年11月24日
http://www.jiji.com/jc/rt
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の議長は、気候変動交渉について、異常気象による脅威の増大に焦点を当てる必要があると述べ、各国が政治的な小競り合いから離れる必要があると指摘した。
政治的な小競り合いは、温室効果ガス排出に関するより厳しい条約締結への取り組みを阻害しているという。
世界約200カ国の交渉担当者が南アフリカ共和国のダーバンに集まり、2週間にわたって国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議(COP17)が開かれる。
会議で全ての主要排出国を拘束する合意に向けて大きく前進すると期待する人々は、非常に少ない。
同議長率いるIPCCは、政策立案者向けにリポートを公表した。
リポートは、熱波の襲来が増えるのはほぼ確実で、より激しい雨、より多くの洪水、より強力なサイクロンや土砂崩れ、より厳しい干ばつが今世紀に地球上の各地を襲う可能性が高いと指摘するものだった。
また、同議長は今回の会議について、「残念ながら、現状は全体的に、これらの現実に関する視点が抜け落ちている」と述べた。
参照
時事通信社 2011年11月24日
http://www.jiji.com/jc/rt
■中国やブラジルなど新興国も気候変動基金に貢献を■
アメリカの気候変動担当特使は、当地で開催された主要経済国フォーラム(MEF)終了後、貧困国が気候変動に立ち向かうのを支援するために年間1000億ドルを拠出する「グリーン気候基金(GCF)」について、一部の開発途上国も拠出をすべきだと述べた。
MEFは、日米欧の先進国のほか、中国、インド、ブラジルなどの新興国など排出量の多い17カ国・地域が参加した。
同特使は、先進国がGCFに資金拠出するとみられるが、開発の進んだ一部新興国からの寄付を受け入れるための扉も大きく開かれていると語った。
また、メキシコのカルデロン大統領が数年前に最初にGCFの概念を提唱した際、同大統領は先進国と開発途上国を含む全ての国々がGCFに貢献することを思い描いていたと付け加えた。
世界で最も豊かな国の1つであるノルウェーと、最も貧しい国の1つであるバングラデシュは手を組み、ブラジルや中国などの国々にGCFへの貢献を求めた。
ノルウェーの気候変動交渉担当者は、新興国が「明日にでも資金を準備する」と予想する人もいないし、それを迫る人もいないが、新興国が近いうちに拠出約束を検討し始めることへの期待感が存在すると語っている。
主要新興国への拠出期待の動きは、気候変動交渉上の変化を表しているほか、交渉における中国とブラジルの経済的な立場が強まっていることを反映している。
中国とブラジルはかつては開発途上国とされ、京都議定書に基づく排出量削減の義務を負っていない。
参照
時事通信社 2011年11月21日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011112100315r
アメリカの気候変動担当特使は、当地で開催された主要経済国フォーラム(MEF)終了後、貧困国が気候変動に立ち向かうのを支援するために年間1000億ドルを拠出する「グリーン気候基金(GCF)」について、一部の開発途上国も拠出をすべきだと述べた。
MEFは、日米欧の先進国のほか、中国、インド、ブラジルなどの新興国など排出量の多い17カ国・地域が参加した。
同特使は、先進国がGCFに資金拠出するとみられるが、開発の進んだ一部新興国からの寄付を受け入れるための扉も大きく開かれていると語った。
また、メキシコのカルデロン大統領が数年前に最初にGCFの概念を提唱した際、同大統領は先進国と開発途上国を含む全ての国々がGCFに貢献することを思い描いていたと付け加えた。
世界で最も豊かな国の1つであるノルウェーと、最も貧しい国の1つであるバングラデシュは手を組み、ブラジルや中国などの国々にGCFへの貢献を求めた。
ノルウェーの気候変動交渉担当者は、新興国が「明日にでも資金を準備する」と予想する人もいないし、それを迫る人もいないが、新興国が近いうちに拠出約束を検討し始めることへの期待感が存在すると語っている。
主要新興国への拠出期待の動きは、気候変動交渉上の変化を表しているほか、交渉における中国とブラジルの経済的な立場が強まっていることを反映している。
中国とブラジルはかつては開発途上国とされ、京都議定書に基づく排出量削減の義務を負っていない。
参照
時事通信社 2011年11月21日
http://www.jiji.com/jc/rt?k=2011112100315r
■アフリカ南部の降雨パターンが変化 食料生産に脅威■
アフリカ南部の降雨パターンが気候変動の影響で不規則になっており、同地域の人々の主食で現金収入源でもある農作物の長期的な生産が脅かされている。
南アフリカ共和国、ザンビア、それにマラウィといった国々では近年、主食のメイズ(トウモロコシ)が豊作だった。
これにより、しばしば飢餓に襲われたことで知られる同地域の食料安全保障が向上した。しかし農家は、何百年もの間、夏の雨季のタイミングを予想できていたが、今は予想が次第に難しくなっていると述べている。
マラウィの2010〜2011年度のトウモロコシ収穫量は380万トンになり、前年度の350万トンを超えるとみられ、収穫を増やす潜在性もある。
しかし、2011〜2012年度の収穫は危機に直面するとの見方が強まっている。
10月に始まった作付けの最初の重要な段階に干ばつに見舞われている公算が大きいためだ。
専門家は、天候パターンが変化しているため、とりわけアフリカ南部のリンポポ川流域の雨水に依存する農業の見通しが暗いと指摘している。
リンポポ川はボツワナ、南ア、モザンビーク、それにジンバブエにまたがる地域を流れる。
アフリカ最大のトウモロコシ生産国である南アでは、2010〜2011年度の収穫の際、異常な降雨で農場へのアクセスが困難になり、打撃を受けた。
ザンビアでは、予想以上に早い降雨の結果、当初310万トンの豊作とみられていたトウモロコシが100万トン近く失われたという。
参照
時事通信社 2011年11月25日
http://www.jiji.com/jc/rt
アフリカ南部の降雨パターンが気候変動の影響で不規則になっており、同地域の人々の主食で現金収入源でもある農作物の長期的な生産が脅かされている。
南アフリカ共和国、ザンビア、それにマラウィといった国々では近年、主食のメイズ(トウモロコシ)が豊作だった。
これにより、しばしば飢餓に襲われたことで知られる同地域の食料安全保障が向上した。しかし農家は、何百年もの間、夏の雨季のタイミングを予想できていたが、今は予想が次第に難しくなっていると述べている。
マラウィの2010〜2011年度のトウモロコシ収穫量は380万トンになり、前年度の350万トンを超えるとみられ、収穫を増やす潜在性もある。
しかし、2011〜2012年度の収穫は危機に直面するとの見方が強まっている。
10月に始まった作付けの最初の重要な段階に干ばつに見舞われている公算が大きいためだ。
専門家は、天候パターンが変化しているため、とりわけアフリカ南部のリンポポ川流域の雨水に依存する農業の見通しが暗いと指摘している。
リンポポ川はボツワナ、南ア、モザンビーク、それにジンバブエにまたがる地域を流れる。
アフリカ最大のトウモロコシ生産国である南アでは、2010〜2011年度の収穫の際、異常な降雨で農場へのアクセスが困難になり、打撃を受けた。
ザンビアでは、予想以上に早い降雨の結果、当初310万トンの豊作とみられていたトウモロコシが100万トン近く失われたという。
参照
時事通信社 2011年11月25日
http://www.jiji.com/jc/rt
戦争は最大の環境破壊、今、安倍、自公政権が成立させようとしている
法案を阻止させなければなりません。
下記はらせてください。
ーーーー
<以下、転送>
(以下転送・転載・拡散大歓迎)
皆さまへ(重複申し訳ありません。拡散歓迎です)
FoE Japanの満田です。
連日、各地で、また国会前で、安保法案に反対し、民主主義を守るための行動が
くりひろげられています。
こんなにも多くの人たちが立ち上がったことは希望です。
さて、環境・平和・人権にかかわる市民団体で、安保法案に反対する共同声明を
出そうとしています。
この際、いままで安保法案に対してあまり声をあげてこなかった団体も含め、い
ろいろなところから反対の声があがっていることを見せていきたいと思います。
http://www.foejapan.org/infomation/news/150716.html
今朝までに、100の団体からご賛同のご連絡をいただきました。ありがとうございました。
個人賛同も受け付けることといたしました。
できれば、団体賛同、個人賛同、両方お願いします!
団体賛同フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/5ca8639b81236
個人賛同フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/0bcfea9281379
※賛同の締め切りは、7月27日(月)です。
※共同声明の発表は、7月28日(火)13時〜14時に、参議院議員会館(B103)に
て行う予定です。また詳細はご連絡します。
呼びかけ団体:ラムサール・ネットワーク日本、ピースボート、グリーンピース
・ジャパン、環境市民、ジュゴン保護キャンペーンセンター、FoE Japan
連絡先:満田夏花(みつた・かんな) FoE Japan(エフオーイージャパン)
kanna.mitsuta@nifty.com 携帯:090-6142-1807
花輪伸一 ラムサール・ネットワーク日本
Hanawashinichi2@mbn.nifty.com 携帯:090-2452-8555
-----
明日、大阪で学生さん(SEALs)が主催するデモがあります。
官邸前でがんばってくれてる人たちに負けないように大阪でも
社会人もおばあちゃん、おじいちゃんも一緒に平和で戦争を
しない国でいられるようアクションを!
SEALDs KANSAI(自由と民主主義のための関西学生緊急行動)とSADL(民主主義と生活を守る有志)
7/19(日)16:30-
【「戦争法案」に反対する関西デモ】
@大阪 うつぼ公園集合 御堂筋南下
https://www.facebook.com/events/1444782769163881/
http://sealdskansai.strikingly.com/
---
安倍特高のヒゲの隊長https://www.youtube.com/watch?v=0YzSHNlSs9g
さっきの安倍特高のヒゲの隊長にあかりちゃんが反論。きいてみて!
あかりちゃんの反論が普通の人の反応だとおもうんだけど・・・
【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた https://youtu.be/L9WjGyo9AU8
法案を阻止させなければなりません。
下記はらせてください。
ーーーー
<以下、転送>
(以下転送・転載・拡散大歓迎)
皆さまへ(重複申し訳ありません。拡散歓迎です)
FoE Japanの満田です。
連日、各地で、また国会前で、安保法案に反対し、民主主義を守るための行動が
くりひろげられています。
こんなにも多くの人たちが立ち上がったことは希望です。
さて、環境・平和・人権にかかわる市民団体で、安保法案に反対する共同声明を
出そうとしています。
この際、いままで安保法案に対してあまり声をあげてこなかった団体も含め、い
ろいろなところから反対の声があがっていることを見せていきたいと思います。
http://www.foejapan.org/infomation/news/150716.html
今朝までに、100の団体からご賛同のご連絡をいただきました。ありがとうございました。
個人賛同も受け付けることといたしました。
できれば、団体賛同、個人賛同、両方お願いします!
団体賛同フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/5ca8639b81236
個人賛同フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/0bcfea9281379
※賛同の締め切りは、7月27日(月)です。
※共同声明の発表は、7月28日(火)13時〜14時に、参議院議員会館(B103)に
て行う予定です。また詳細はご連絡します。
呼びかけ団体:ラムサール・ネットワーク日本、ピースボート、グリーンピース
・ジャパン、環境市民、ジュゴン保護キャンペーンセンター、FoE Japan
連絡先:満田夏花(みつた・かんな) FoE Japan(エフオーイージャパン)
kanna.mitsuta@nifty.com 携帯:090-6142-1807
花輪伸一 ラムサール・ネットワーク日本
Hanawashinichi2@mbn.nifty.com 携帯:090-2452-8555
-----
明日、大阪で学生さん(SEALs)が主催するデモがあります。
官邸前でがんばってくれてる人たちに負けないように大阪でも
社会人もおばあちゃん、おじいちゃんも一緒に平和で戦争を
しない国でいられるようアクションを!
SEALDs KANSAI(自由と民主主義のための関西学生緊急行動)とSADL(民主主義と生活を守る有志)
7/19(日)16:30-
【「戦争法案」に反対する関西デモ】
@大阪 うつぼ公園集合 御堂筋南下
https://www.facebook.com/events/1444782769163881/
http://sealdskansai.strikingly.com/
---
安倍特高のヒゲの隊長https://www.youtube.com/watch?v=0YzSHNlSs9g
さっきの安倍特高のヒゲの隊長にあかりちゃんが反論。きいてみて!
あかりちゃんの反論が普通の人の反応だとおもうんだけど・・・
【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた https://youtu.be/L9WjGyo9AU8
■太平洋ゴミベルト
「太平洋ゴミベルト」(ゴミベルト)は、サンフランシスコとハワイのほぼ中間にある北太平洋の領域である。この領域では、海流が収束し、主にいろいろな種類のプラスチックゴミが集積している。ゴミベルトは、北太平洋循環流によって形成される。 循環流は、コリオリの効果によって起こる海流の循環システムである。
ゴミベルトのプラスチックゴミのほとんどは、陸起源のゴミで、従来のプラスチックは生分解しないし、現在のバイオプラスチックも海洋環境で生分解しないため、長い漂流期間に耐えてそこに漂着した。全ての種類のプラスチックは、海洋環境では光分解するだけなので、プラスチックは、さらに細かい破片に破壊される、そして/または、 時間がたつにつれてUV光にさらされて色を変えるだけである。
「ゴミベルト」と聞くと、海の真ん中に浮いているプラスチックの島を思い浮かべる人が多いかもしれないが、この「ゴミベルト」は、分解のさまざまな段階にあるプラスチックが水柱の上層に浮遊している、プラスチックのシチューでおおわれた広大な領域という説明のほうが的確だろう。アルガリタ海洋研究財団の研究とスクリップス海洋研究所のシープレックス調査によると、ゴミベルトの中やその周辺で、遠海魚がプラスチックを食べていることが実証されている。
ゴミベルトに集積したゴミは、時間とともに循環流によってゴミベルトの外に押し流される。この例が、ハワイ諸島の北東に面する海岸に漂着するゴミである。そこに漂着するプラスチックゴミは膨大な量になることもある。多量のプラスチックが胃から発見されたコアホウドリの死骸の写真によって、プラスチックが死に至る原因になることが実証され、この写真を見た多くの人たちが、プラスチックごみを減らす努力をするように動機付けられた。
個人や団体がゴミベルトを除去することを議論しているが、あまり現実的ではない。「ゴーストネット」(訳注:海に廃棄された網。そのまま放置されれば海洋生物を巻き込んで殺してしまう)や放置された漁具を回収する有効なプロジェクトはいくつかある。しかし、プラスチックのほとんどが非常に小さい断片なので除去作業を実行すれば、海洋生物にも影響を与えてしまい、除去作業から得られる肯定的な面を打ち消してしまうだろう。
この問題を解決するために一番よい方法は、ゴミベルトの原因となるプラスチックゴミを出さないようにして、問題を根本から解決することである。
出典
http://www.beachapedia.org/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E3%82%B4%E3%83%9F%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88
「太平洋ゴミベルト」(ゴミベルト)は、サンフランシスコとハワイのほぼ中間にある北太平洋の領域である。この領域では、海流が収束し、主にいろいろな種類のプラスチックゴミが集積している。ゴミベルトは、北太平洋循環流によって形成される。 循環流は、コリオリの効果によって起こる海流の循環システムである。
ゴミベルトのプラスチックゴミのほとんどは、陸起源のゴミで、従来のプラスチックは生分解しないし、現在のバイオプラスチックも海洋環境で生分解しないため、長い漂流期間に耐えてそこに漂着した。全ての種類のプラスチックは、海洋環境では光分解するだけなので、プラスチックは、さらに細かい破片に破壊される、そして/または、 時間がたつにつれてUV光にさらされて色を変えるだけである。
「ゴミベルト」と聞くと、海の真ん中に浮いているプラスチックの島を思い浮かべる人が多いかもしれないが、この「ゴミベルト」は、分解のさまざまな段階にあるプラスチックが水柱の上層に浮遊している、プラスチックのシチューでおおわれた広大な領域という説明のほうが的確だろう。アルガリタ海洋研究財団の研究とスクリップス海洋研究所のシープレックス調査によると、ゴミベルトの中やその周辺で、遠海魚がプラスチックを食べていることが実証されている。
ゴミベルトに集積したゴミは、時間とともに循環流によってゴミベルトの外に押し流される。この例が、ハワイ諸島の北東に面する海岸に漂着するゴミである。そこに漂着するプラスチックゴミは膨大な量になることもある。多量のプラスチックが胃から発見されたコアホウドリの死骸の写真によって、プラスチックが死に至る原因になることが実証され、この写真を見た多くの人たちが、プラスチックごみを減らす努力をするように動機付けられた。
個人や団体がゴミベルトを除去することを議論しているが、あまり現実的ではない。「ゴーストネット」(訳注:海に廃棄された網。そのまま放置されれば海洋生物を巻き込んで殺してしまう)や放置された漁具を回収する有効なプロジェクトはいくつかある。しかし、プラスチックのほとんどが非常に小さい断片なので除去作業を実行すれば、海洋生物にも影響を与えてしまい、除去作業から得られる肯定的な面を打ち消してしまうだろう。
この問題を解決するために一番よい方法は、ゴミベルトの原因となるプラスチックゴミを出さないようにして、問題を根本から解決することである。
出典
http://www.beachapedia.org/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E3%82%B4%E3%83%9F%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88
アルシオン・プレヤデスビデオニュースNo.63-2017:
イルカ・クジラ大量死 音波の海、海底ソナー、石油採掘探査を止めろ!
マイクロプラスチック海洋汚染、放射能汚染
サイバー攻撃、マクロン不正選挙、ブラジル、
トランスヒューマニズム、
国際社会の危機的状況
UFOの目撃
UFO異星人機密情報とJFKマリリンモンロー暗殺
各場面キャプチャ
http://cqclabojapan.doorblog.jp/archives/51421577.html
マリリン・モンローの死因に新説「宇宙人情報を公表しようとしたため」
http://www.epochtimes.jp/2017/05/27524.html
米国映画界の大スター、マリリン・モンローの死因は今でも謎に包まれている。
あるドキュメンタリー映画で、モンローの死亡に宇宙人が関わっていたとの推測が浮上している。
米FOXニュースが5月23日、このほど公開された新作ドキュメンタリー映画「Unacknowledged(未確認)」で、モンローは宇宙人の存在を示す証拠を公表しようとしたために殺されたとする説が浮上したと報じた。
イルカ・クジラ大量死 音波の海、海底ソナー、石油採掘探査を止めろ!
マイクロプラスチック海洋汚染、放射能汚染
サイバー攻撃、マクロン不正選挙、ブラジル、
トランスヒューマニズム、
国際社会の危機的状況
UFOの目撃
UFO異星人機密情報とJFKマリリンモンロー暗殺
各場面キャプチャ
http://cqclabojapan.doorblog.jp/archives/51421577.html
マリリン・モンローの死因に新説「宇宙人情報を公表しようとしたため」
http://www.epochtimes.jp/2017/05/27524.html
米国映画界の大スター、マリリン・モンローの死因は今でも謎に包まれている。
あるドキュメンタリー映画で、モンローの死亡に宇宙人が関わっていたとの推測が浮上している。
米FOXニュースが5月23日、このほど公開された新作ドキュメンタリー映画「Unacknowledged(未確認)」で、モンローは宇宙人の存在を示す証拠を公表しようとしたために殺されたとする説が浮上したと報じた。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
環境問題を考える 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-